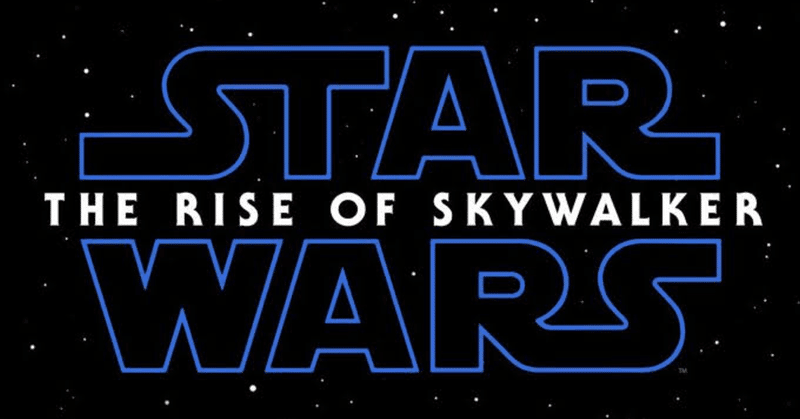
「スカイウォーカーの夜明け」に備えて-暗黙の物語のスクラップ&ビルド
「遠い昔、遥か彼方の銀河系で...」
1977年の第一作公開から四十余年。スターウォーズサーガの最終章、『STAR WARS/スカイウォーカーの夜明け』の公開日(2019/12/20) が迫ってきた。

予習、ではないけれど、前作『STAR WARS/最後のジェダイ』(2017) を観た後に記した文章を再掲し、新作公開に備えることにする。
---------------
映画『七人の侍』を初めて観たのは、高校生の頃だった。静かに、けどメチャメチャ驚いたのを覚えている。

「マジか!スゲーーー!」的な分かりやすい驚きじゃない。気づくとボッコリ脳天に穴開けられてた的な、達人にスッパリ斬られてたのに数秒気づかなかった的な、静かで深い不思議な感触の驚きだった。
うまく言えない。
映画の見所の一つは激しくも目まぐるしい泥っどろの合戦シーン。野武士集団を相手に、農民たちと助っ人侍たちが展開する戦闘シーンは一瞬たりとも目が離せないし、息つく間もない。
合戦が終わり、観ているこっちもようやく息をつく。「フー.... 」
そしてラスト。
「今度もまた負け戦だったな。勝ったのはあの百姓たちじゃ、儂たちではない」
かの有名な島田官兵衛の名台詞が流れるあたりで、件の驚きが突然訪れる。
ん?、、、戦死した侍は○○と○○と、、、生き残った侍は○○と○○と、、、えっ!?
メインキャラと思しき侍がことごとく死に、生き残っていたのは勝手にサブキャラと見なしてた侍ばかりだった。ことごとく見事に予想を裏切られる結末。
そうだ。誰がどうなるかなんて時の運。作戦が成功するかどうかだって時の運。分からないのが当たり前。
歴史とは、膨大な失敗と試行錯誤の繰り返しなのだ。
英雄が瞬殺され、雑魚キャラがしぶとく生き延びることだってありがち。というかそっちの確率の方がむしろ高い。
英雄的行為というのはギャンブルだ。無謀な作戦であっても信念に準じて先頭を切り、皆を鼓舞すべく不確実な地獄に自ら何度でも突っ込んでく人のことを英雄と呼ぶ。
一寸先は闇。それが現実。
そんな残酷な世界を生き延びるべく僕らは安定の物語にすがるのだ。これ狙ってやってんのか。セカイのクロサワ畏るべし。
「物語」の機能についてはポイントが三つある。
一つ、僕らの脳には暗黙裡にある種の「物語の型」が刷り込まれている。人はその型に沿った物語を期待し、期待通りの展開に安心を得る。
二つ、その型を見事にスルリと外されると強烈な驚きと違和感が同時に瞬時に湧き起こる。少し遅れて快感がジワリと入り混じる。そして溜息と共にえも言われぬ解放感が一気に広がる。
三つ、型を外されたり壊されたりすることに強烈に不安や不快、場合によっては怒りを感じる人は結構多い。 そして、その大半はオトナであり、さらにそのまた大半はオトコだったりする。
安心と停滞。型がもたらす表裏の作用。
不安と創造。型の破壊がもたらす表裏の作用。
そのバランス匙加減はなかなかに難しい。

昨日見た『STAR WARS/最後のジェダイ』は、そのあたりの匙加減がイイ感じな作品だった。
物語の展開、概念、敵味方の関係性。従来のSTAR WARSの型がことごとく、しかもサラリと覆されていく。
極めつけは、生ける伝説ルーク・スカイウォーカーの口から発せられるこの台詞。
"Amazing!Every word of what you just said was wrong!"
たった一言で、従来の枠組が粉微塵に打ち砕かれる。
カッケー!(゚∀゚)
新たなコンセプト新たな秩序が真っさらなまま次世代に託される希望に満ちたラストシーン。
カッケー!(゚∀゚)
「創造的破壊」という言葉がしっくりハマる、爽快な新時代のお伽噺でした。
リアリティがどうこうとか話の辻褄がどうこうとかキャストがどうこうとか、賛否両論はあるけれど、無邪気に子どもじみてることにこそ意味があるお伽噺に、そんなクレームはナンセンスだと思います。
次作はJJエイブラハム再降臨すると訊く。
楽しみ... (´ー`)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
