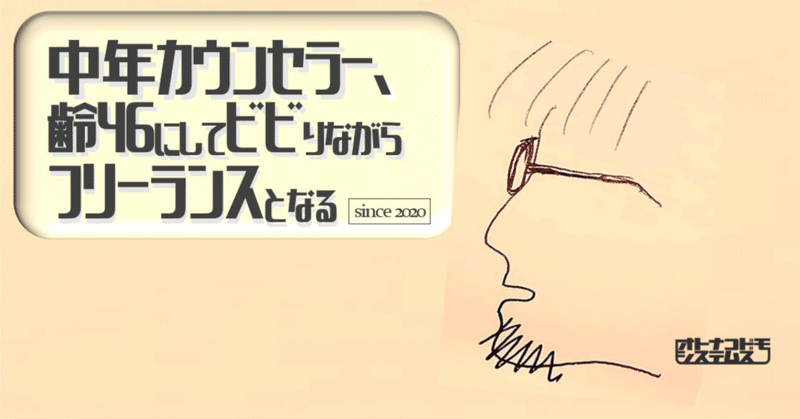
「聞き書き」をはじめたーつれづれ起承転結(3)
「聞き書き」という取り組みを知ったのは今年の二月のことだ。
いつもお世話になりっぱなしのSocial Book Cafeハチドリ舎で行われた、『がんフーフー日記』の作家&ライター・清水浩司さん、消化器外科医&うんコメンテーター・矢野雷太さんのお二人によるイベントで、初めて耳にした。
「聞き書き」とはインタビューの一形式なのだが、インタビュアーは仮説や予断を控え、話し手の話したいことをそのまま話してもらい、そのまま聞き、そのまま書きとめ、話された言葉を話し手が今まさに目の前で話しているかのような文章としてまとめていくものだ。
イベントでは、小田豊ニさんの『「聞き書き」をはじめよう』(木星舎,2012)が参考図書として紹介されていた。
思いや感情は、流れていく。言葉にしなければ伝わらないことも多い。相手が身近な人であればあるほど、大切な人であればあるほど、伝える機会をつくるのは難しかったりする。伝えたいことが自分にとって大切であればあるほど、正確に言葉にするのも難しかったりする。
有名人の大きな声は、どこかに残る。けれど、無名の人々の声は、それがどれほど価値あるものであっても、聞いて残そうと意図しなければ、誰にも伝わらないまま流れていくことが多い。
そんな大切な言葉の橋渡しをお手伝いするのが「聞き書き」という取り組みだ。
清水さんと矢野さんは、この「聞き書き」という手法を用いて、例えば認知症早期の方、例えばがん末期患者の方などにインタビューを行うことで、自身の人生の振り返り、現在の思い、大切な人へのメッセージなどを"生の言葉"として聞きとり、書き残すという活動を広めようとしている。
医師である矢野さんは、この取り組みをACP(アドバンスドケアプランニング)の手法の一つとして活用することも考えている。ACPとは、各自が将来の変化ー例えば、自ら意思表示ができない深刻な事故や病気に陥った場合ーに備えて、自分がどんな医療・ケアを受けたいのか、何を優先したいのかを、家族・近しい人・専門家を交えて話し合い、希望する医療のカタチを周りと共有しておくための取り組みだ。
2019年に厚生労働省が「人生会議」というネーミングで普及を図ろうと作成したポスターが炎上したことを記憶しておられる方もいるかもしれない。
炎上した理由も分からないではないけれど、とっても大事な取り組みであるのもまた確かだ。やっておかないと、状況によっては、本人も家族も治療・ケアスタッフも、みな悩み苦しむことになりかねない。
そんなこんなで、僕はこの「聞き書き」にめちゃくちゃ興味を持った。自分もやってみたいと思った。カウンセラーとして身につけてきたノウハウを、話し手のみなさんから大切な言葉をひきだすことに役立てることができるのではないかと思った。
僕は早速、清水さんや矢野さんのチームに入れてもらった。聞き書きを進め、広めていくチームだ。
そして、この6月から終末期のがん患者様への「聞き書き」を始めた。
自身の人生の振り返り、病と治療への思い、大切な人に残したいメッセージなど、ご本人が話したいと思われることを聞き、書き、文章に残す。
まだ1ケースしかやってないけど、めちゃくちゃ難しく、めちゃくちゃやりがいのある仕事だと感じている。
めちゃくちゃ疲れるけど、慣れてはいけない仕事だと思っている。
頑張る。
やっぱり起承転結になってない気がする。ムズいな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
