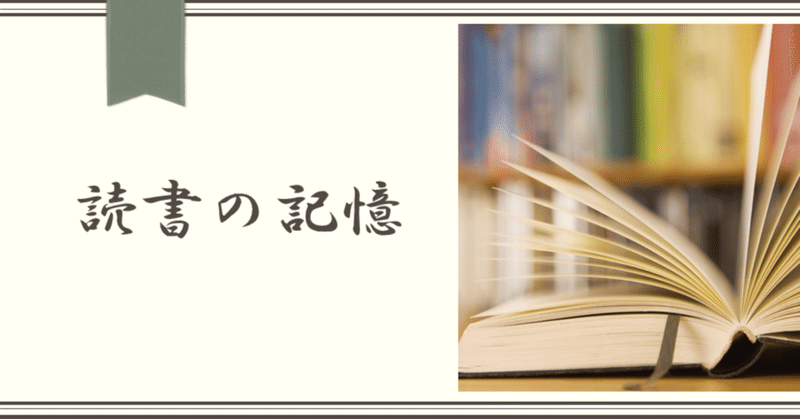
2022年4月
読んだ本の数:8冊
■狂うひと :「死の棘」の妻・島尾ミホ/梯 久美子(新潮文庫)
読了日:04月02日

三月に読んだ『死の棘』。あれは『小説』だけれど、ではその小説がどのように生まれたのか、登場人物の実際は?に迫る評伝。
感想むずかしい。
まずは、文学の研究ってこうするのかという発見あり。そして、人間のおそろしさ。いや、作家のおそろしさか?それとも、この人たち個人のおそろしさだろうか、に慄く。劇場型人生。神話を生きるひとたち。舞台上の人間が信じていることに、観客である周囲の人間や読者が巻き込まれていく様。
作家ごとに通奏低音ともいうべきテーマがあるだろうが、それは、作家が見つけたものともいえるし、束縛されているものにもみえる。苦しくないのか。苦しそうだ。それでも書くことを止められない人間が作家になるのか。
一連の『死の棘』ものが発表されていた当時の、世間一般読者の反応が知りたい。一大センセーションを巻き起こして、猫も杓子も読んだのだろうか。それとも、とはいえ文学愛好家がショックを受けた程度ですよなのか。ご存知の方がいたら教えてください。
本論にはあまり関係ないことだけれど、白木屋火災ズロース事件を疑いない真実として紹介している箇所に「おや…」と。わたしは、これは後から生み出された都市伝説説をとる派の者。
■いのちの話 (中学生までに読んでおきたい日本文学 2)/松田哲夫編(あすなろ書房)
読了日:04月03日

『死の棘』を読んだので、同作者、島尾敏雄の『島の果て』を再読。どうやら初読の時点でこの話に感銘を受けていたようだ。今はまた別の世界が見えて凄絶。
■[白川静の絵本]死者の書/白川静、金子都美絵(平凡社)
読了日:04月10日

漢文学者・東洋学者の白川静の著作からインスピレーションを受けた画家による絵本。特に『死』をテーマにした一冊。
こんなにも死に連なる漢字があるということは。人々が、どうにか死をあらわし理解しようとした証なのかもしれない。白川静のことばは経文のように難解で、いきなりかじりついてかみ砕けるものではなさそうだ。でも、不思議に音楽的。わからなくても追っていたいリズムがある。そう思えるのは、絵本に再編されて、視覚イメージでことばを補強できるからこそ。
うまい試みだとおもう。
■幻覚剤は役に立つのか/ マイケル・ポーラン、宮崎真紀(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)
読了日:04月12日

タイトルを見て即決した本。幻覚剤の(西洋科学による)発見と研究のこれまでとこれから、で?実際どうなの幻覚剤は?に山のようなインタビューと著者の実体験によって迫る。
読みきるまでにずいぶん時間がかかってしまい理解も小間切れ。とにかく最終章(幻覚剤の作用や幻覚剤療法についての最新の研究の内容)がとても興味深く希望に満ちた内容だったので、清々しい気持ちで読み終えた。自己判定では、自分は幻覚剤が「効く」タイプの人間だろうと思う。
以下へえ!となったり、連想ゲームのはじまったキーワードなどを。
・セットとセッティング:映画『ラスト・サマー』のダニーのバッドトリップを思い浮かべた。彼女のような人こそ、正しく「幻覚剤が役に立つ」人かもしれないのだけど。
・トリップの実態は、結局やってみなきゃわからないのだ。著者が筆を尽くして書いている体験記も「ふーん」となるのがもどかしい。筆を尽くしつつもとても言葉では無理、としきりに述べているところだし、そういうものなんだろう。
・『トード』が特別なのは、紹介されているなかではこれだけが動物由来だからかな?と素人考え。
・幻覚剤の歴史と医療と医学と政治と経済:幻覚剤がタブーになったのも、また復権しつつあるのもどちらもこれらの相互作用。そして、医学的にはOKでも儲けを出せる仕組みを構築できないと医療としては成り立たなかろうという意味の一文。まあそうなんだよなあと唸った。医学と医療と金の問題は、これに限ったことじゃないけどもさ。SSRIが引き合いにだされてて、良くも悪くもものすごくインパクトのある(あった)薬なんだよなあと思った。
・訳者あとがきに重要な単語を取り違えている箇所があったので、これは手持ち以降の版でなおるといいな。重箱の隅をつつくように気になる……
■図説快楽植物大全/リチャード・エヴァンズ・シュルテス他(東洋書林)
読了日:04月12日

『幻覚剤は役に立つのか』の副読本として再読。
■森の生活〈下〉ウォールデン/H.D ソロー、飯田実 (岩波文庫)
読了日:04月29日

真理にたどり着きたかった人の、思索と生活の記録。とでも言ったらいいのだろうか。
『森の生活』というタイトルが持つ印象から、わたしは、なにかこの作品に描かれているのとは異なる謙虚さを期待していたのだと思う。つまり著者に対して「もっと謙虚におなりよ」と、読書中に度々思ったわけだが、解説にある人となり・来歴には好感をもち……。直接会えたらどんな人だったのだろうか。
ウォールデン湖の色について言及した箇所。おや、ずいぶん妙なことを言っているぞこれは……と少し調べてみたところ、本書の出版はレイリー散乱もラマン効果も発表される前なのだった。いろんな人がいろんなレベルで仮説を立てたり、なんとなくこういうことかなあとふんわり世界を眺めているうちに、いろいろなことが解き明かされてきたんだろうねえ。こういうことに行き当たるのも、古典を読むおもしろさだよね~。
■マイホーム大全 2022 (晋遊舎 100%ムックシリーズ)
読了日:04月29日
そろそろタイムリミットとかいうしな~と思いさらっと。
自分には買うことのメリットがあんまりない。一括で買えるわけでなし、ずっとここにいるかどうかは更に相当怪しいから。
■氷の城/タリアイ・ヴェーソス(国書刊行会)
読了日:04月30日

出版社の宣伝ツイートにて一目ぼれ。
あらすじも概略も書きすぎてしまう気がするので書かない。これから読むなら、まずは真っ新な状態で触れてほしい。
圧倒的な寒さ、というよりも冷たさ。そして乾燥。さらさらした文章。淡々としていてあまり多くは語られないが、文字になっている以上の情報(情報というと情緒がなさ過ぎるのだけれど、いま、いい言葉が思い浮かばない)を受け取った。『tellingではなくてshowing』とはなるほど言い得て妙だ。読み手を限定しない、こども時代に読んでもおとなになってから読んでもいい本だ。すうすうと身に馴染む文章。原語で読んでいるわけではない。それはそうだが、翻訳を信じている。一目ぼれは勘違いではなかった。
