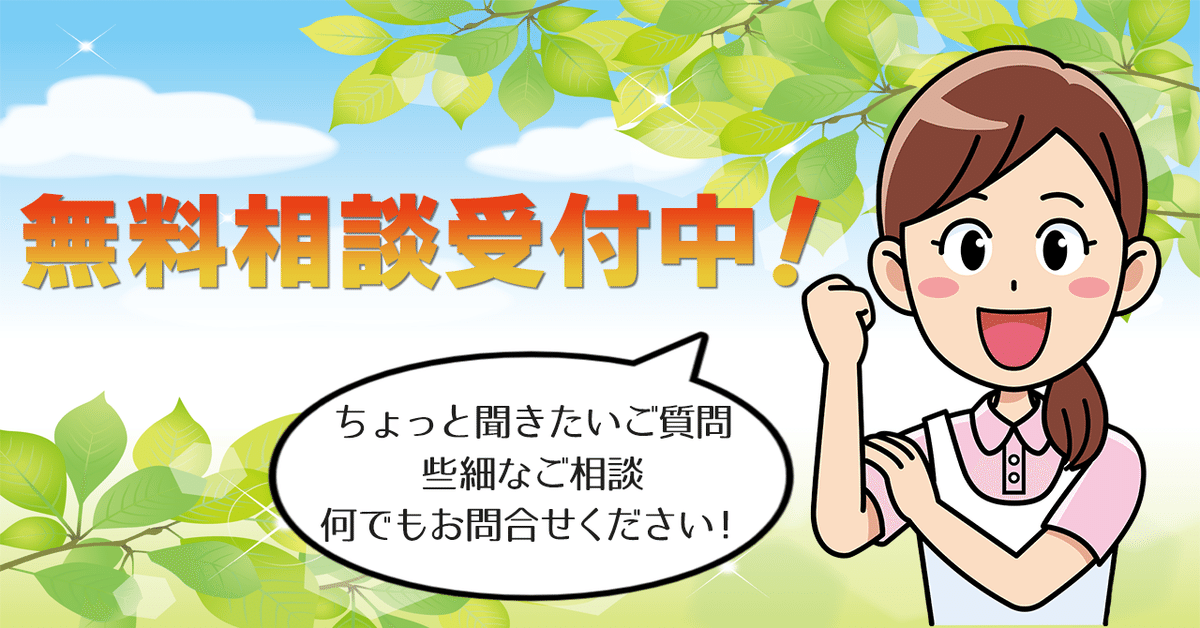「物忘れが増えてきた時にできる、家族の対応」
介護に従事していると、「どうすればいいかわからないから教えて!」
と、よく相談を受けることがあります。
「最近母の物忘れが多く、発言がちんぷんかんぷんな時があるので、思い切って病院へ行ってみました。
認知症ではないと診断されたけれど、そんな母に対して今後どのように対応していけばいいのかわからなくて。」
物忘れは誰にでもある事ですが、それが目立つようになってきたりした時に家族の対応はどうするか、まずは物忘れについて説明していきましょう。
「物忘れについて知っておく」~自信を無くしてしまう前に~
物忘れには大きく分けて、
「老化による物忘れ」と「認知症による物忘れ」
この二つがあります。ではどのような違いがあるのでしょうか。
「老化による物忘れ」はほとんど進行しません。環境の変化にもさほど影響がなく、適応することができます。
「認知症による物忘れ」は、その種類にもよりますが、進行してしまいます。さらに、環境にも左右されやすく、著しく進行してしまう恐れがあります。適応することや、新しい事を覚える事も難しくなります。
まずはこの二つの基本的な違いを理解して頂いた上で、日常生活によくみられる場面を通して、
「望ましい対応」と「家族として出来る事」を、
紹介していきましょう。
「物忘れは誰にでもある事」~日常的な物忘れ~
日常生活の中での「物忘れ」と言えば、
・「買い物に来たけど、何を買おうとしていたか忘れた」
・「鍵や眼鏡をどこに置いてしまったか忘れた」
・「美味しかったけど、何を食べたか忘れた」
などが、よく聞く話です。
これらの場合、日常生活にほとんど支障はありません。
しかし、当人は少なからずとも、不安な気持ちになっていると思います。
この場合、「望ましい対応」としては、
「否定的な事はせず、肯定する事」が大切です。
なぜならば、たとえ忘れてしまっていても、当人は忘れない様に頑張っているからなんです。

確かに物忘れは誰にでもあります。
しかし一度や二度ならともかく、何度も忘れている事が増えていくと、
「なぜ忘れるの?」「何度言わせるの?」
と、家族ならつい、口にしてしまいますよね。
また、言い方も強くなってしまい、言葉だけでなく、否定的な態度をとってしまうことで、口論になる事もあります。
「老化による物忘れ」の場合は、本人が自覚している場合が多く、つい口にした、何気ない言葉が、当人を傷つけてしまっていると考えると、望ましい対応とは言えません。
ではこれが毎日のように続いてしまうと、どのような事になるでしょう。
当人は「忘れてしまう、失敗してしまう」という思考が先立ってしまい、自発的な行動が徐々に失われ、気持ちもふさぎ込んでしまいます。
また、そのストレスが認知症を発症するきっかけにもなってしまいます。
そうならないためにも、たとえ忘れてしまった時でも、
・「いいよいいよ、気にしないで」
・「私もよく忘れるから、大丈夫だよ」
・「心配しなくていいよ」
など、肯定的な態度で、当人が安心できる言葉かけをすることが大切です。

「日常的な物忘れを減らす!」~家族として出来る事~
■日記やメモをつける癖を今からでもつけ始める事。
■物の置き場所や日付けをわかりやすく掲示する事
■役割分担を決め、忘れにくい環境や習慣を作る事
をお勧めします。
これらは全て、当人に「安心感」を感じてもらうためのものです。
忘れようと思って、忘れているわけではありません。家族のみんなが協力することで、一人では難しくても、「もっと頑張ろう!」という、前向きな気持ちになってもらえる事が重要です。
「物忘れでは済まない」~お薬の飲み忘れ~
高齢者の方は定期的に病院に通院することが多いと思います。
受診後にはお薬が処方され、高齢者の多くの方が何かしらのお薬を飲んでいるのではないでしょうか。
ここでよく耳にする場面があります。「お薬の飲み忘れ」です。
もの忘れが増えると、当然、お薬の飲み忘れ等も出てきます。
これは健康状態にも関わってきますので、忘れると、
日常生活に支障が出てきてしまいます。

この場合の「望ましい対応」とは、
「確実に飲めるように工夫をする事」が大切です。
一言でお薬と言っても、飲み薬や貼り薬、塗り薬、点眼薬など、様々な種類があります。
形状も違えば、頻度も違い、これを間違わず、毎日飲み続けるには、やはり工夫が必要でしょう。
飲み忘れはもちろん注意しないといけませんが、飲んだか飲んでないかを忘れてしまう事が一番危険なんです。
2度も3度も同じ薬を飲んでしまうと、これは生命の危険が伴ってきます。
例えば血圧や血糖を下げるお薬を飲んだにも関わらず、また飲んでしまうと、血圧や血糖が下がり過ぎてしまい、意識がなくなってしまうこともあります。
たかがお薬の飲み忘れと思わず、「決められた量」を「決められた時間」に飲むという事は、とても重要なことなんです。
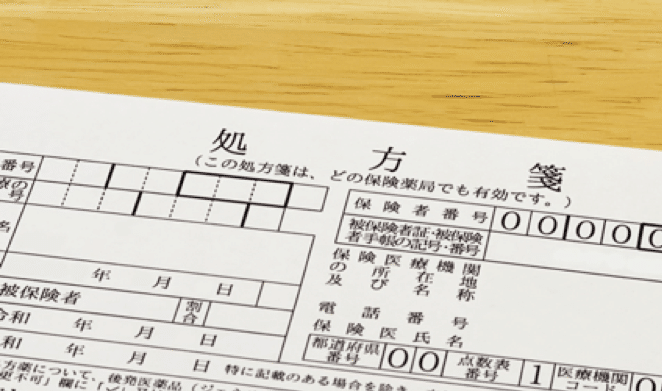
「お薬の飲み忘れを防ぐ!」~医者や薬局にも相談する~
■お薬カレンダーを設置する
■処方の際に、薬局で一包化してもらう
■食事の準備と一緒に、薬のセットを共に行う。
がお勧めです。
お薬カレンダーは薬局等でも売っており、一か月用や、一週間用、朝・昼・晩に分かれているものなど、用途に合わせて購入する事ができます。
薬局では一包化(複数種類の薬を、飲むタイミングごとに一つの袋にまとめる)してもらったり、かかりつけ医には服薬のタイミングを一回にしてもらうなどの相談もすることができます。
そして、できるだけお薬のセットは当人でやってもらい、習慣化できるよう、お声掛けから始めればいいのではないでしょうか。
「家族ができる、最も重要なこと」~できない事よりも、できる事に目を向ける~

物忘れが多くなると出来ない事も増えていきます。
しかし、出来る事もまだまだたくさんあるはずです。
そこに目を向けましょう。
できなくなったからといって、代わりにやってしまうと、ますます出来ないことが増えていってしまいます。
出来ないことであっても、まずは共に行い、意識付けすることが大切です。
それが自信となり、習慣化していく事ができます。
もちろん否定的な対応はせず、根気強く応援してあげてください。
「忘れたり間違っていても、共に行い、支える」
これは家族にしかできない、同じ時間を過ごせる大切な行動ではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?