
『春いちばん』再読 ➁
キリスト者で生協や農民組合の創始者、なおかつ100万部を超えるベストセラー『死線を越えて』の著者である賀川豊彦(1888-1960)は、戦前戦後を代表する著名人の一人である。
その妻の生涯を描いたのが『春いちばん 賀川豊彦の妻ハルのはるかな旅路』(玉岡かおる、家の光協会、2022年)だが、夫のキャラクターが濃すぎて、主人公の影は薄い。
ハルは賀川と同年生まれで、尋常高等小学校を卒業後は、女中奉公を経て女工となった。成人後に洗礼を受け、賀川と結婚した。
当ブログの前回に私は、二人は<典型的な ” 夫唱婦随 ” カップル>と表現したが、けっして誇張ではない。『春いちばん』には、夫に従順な妻の姿が、これでもかと言わんばかりに描かれている。( )内は角岡の註である。
<ハルは賀川の邪魔にならぬよう、それでいて彼の助けとなるよう働いて過ごした>
<「どこにだって逃げません。だって豊(彦)さんのいるところが私の居場所ですから」>
<ハルの座標軸は常に賀川だ。彼の提唱することがすべてこの世の真理だった>
<一心同体? そうありたいが、賀川とハルでは器が違いすぎ、それでも一つと言うなら賀川が九割九分で、ハルは残りのたった一分の存在だ>
<賀川の考えは広大だ。だから自分は従い、支えるのみだ>
<常に賀川の言うままに従ったハル。どんな状況でも涙をこらえてついていったハル。そんなハルの標である賀川を傷つけるなら、絶対に許せない>
賀川は、文字通り ” 主人 ” である。実際にそうだったようだが、そのままストレートに登場人物に言わせたり、地の文章で書くのはどうだろうか。賀川が九割九分で、ハルは残りの一分というのは、あんまりである。これでは主人公が形無しではないか。
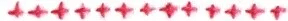
ハルが絶対神のごとく信奉し、仕えた賀川の女性観は、現在から見ると古色蒼然としている。彼が執筆した『女性賛美と母性崇拝』(東京慶文堂書店、1937年、『賀川豊彦全集 第7巻』所収、キリスト新聞社、1963年)は、タイトル通り女性を賛美しつつ、その社会的役割について次のように述べている。
<なほ婦人は民族に対する重大な責任がある。男は個人主義的であるのに対して女は常に団体的である。団体的と云ふのは子供を連れ、夫に仕へ、ホームを持つことである。夫がその餌をさがす間、婦人は家に在つて、子供を育て、父母に、夫に仕へる使命を持つて居る。女が男のやうになれば、婦人として存在の必要はない。人間としての女は人間にならなければならないと云つて、子供は家に放つて置いて、華美な洋服で身体を装飾して、何々運動とか何々会と、子供にもやさしい言葉の一つもかけてやらず、家を外に「私急がしいわ」と云つて男のやうになりたいと考へる人は男になれば可い>
男は仕事、女は家庭という、典型的な性別役割分業を推進したのが賀川であった。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)を例にとり、日本女性の特質を次のようにも述べている。
<最初米国婦人と結婚したが、その女に棄てられて今度は黒人の女と結婚し、又妻君に遁げられて後に日本の女と結婚した。一番気持のよかつたのは日本の女である。日本の女は犠牲的精神に富んで居る、日本の女程犠牲的な女はないと彼は言つている>
女性に犠牲的精神を求めるのが、キリスト者で社会運動家の賀川だった。女性の社会進出と家庭の両立は、いつの世も問題とされる。その条件となる託児所について、賀川は喝破する。
<託児所も必要だが、本当を言ふと赤ン坊を持つお母さん達がもつと理想的に遣るならばそれは不要になる。託児所や乳児院に赤ン坊を託する文明は、実は間違つた文明で、母は育てなければならないものであるのに、其赤ン坊を放つて置いて労働するのは何う見ても正しい事とは言はれない>
子供は母親が育てるものという信念は、揺るがない。もはや信仰の域に達している。
ちなみにこの『女性賛美と母性崇拝』は、女性以外についても、饒舌に述べている。
<黒人種はどうも脳髄が大きいのである。けれども黒人種がそれほどの発明をしていない>
<酔つぱらつて生んだ子供は低能になる>
<不幸にしてお産が重いとか、白痴、低能、発狂、変質などの子が生れるとする。今日の医者も患者もモルヒネを平気で使ふから、生れ乍らにしてかういふ子供が出来ないとも限らない。かうして家庭に暗い影がさす>
賀川の社会的弱者に対する差別的な視線は、徹底している。
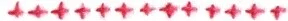
賀川の妻であったハルは、まさに夫と ” 一心同体 ” だった。1928年に発表した「家庭と宗教」という論考で、彼女は次のように記している(『賀川ハル史料集 第二巻』所収、三原容子編、緑蔭書房、2009年)。
<妻たる者よ、主に従ふごとく己の夫に従へ、夫は妻の為たればなり、と聖書にある如く、よく夫に従ふ、選沢に於て間違なく一たん夫と定めたれば従順でなければならぬ>
聖句を引いてまで、夫に従うことを説いている。キリスト教における男尊女卑もまた、問題である。
ハルは賀川の妻であるとともに、牧師の妻でもあった。つまり、信者の世話役を担った。その役割を『春いちばん』の著者玉岡は、 ” 女中 ” という言葉で表現している。
同書では二人の結婚後、夫婦が住む神戸・新川の住民を集めた披露宴で、賀川にこう語らせている。
「病気や急用で手がいる時は遠慮なく言ってください。このお嫁さんはおたくの女中になって働きます」
玉岡は賀川の女中発言を受けて、ハルの心境を次のように記している。
<我慢強さ、根気良さ。女中時代に誰からも認められたハルの長所が、ここでは何より活きる。自分は神の僕、女中なのだ。それをどうしていやがることがあろう>
女中発言を聞いた賀川の義母が、ハルに声をかける。
「さっそくだけど、足を揉んでくれる?」
「お義母さん、この人は女中ではなく‥‥」
賀川の忠告をさえぎり、ハルが答える。
「先生、大丈夫。揉ませていただきます」
当初は伝道師と被伝道者の関係であったことから、ハルは賀川を終生「先生」と呼んでいた。義母に寄り添うハルを見た新川の人々は、<文句を言わずよく動くハルに目を見張った>。
夫や父母に従順な妻の姿が、肯定的に描かれている。この作品を誰が喜んで読むのだろうか。
今では使われなくなった ” 女中 ” という言葉が、この作品では全編を通して、何度も出てくる。
<社会の小使いを自負する夫と、その女中を自認する妻と>
<ハルはあくまでも賀川の女中であればよかった>
<賀川に従順な女中であって何が悪い。言われるがままに金をやりくりする大蔵省であって何がいけないのだ。賀川はハルを必要としている、そしてハルがいなければ賀川は回らないことは誰もが知っていた>
雇い主は、女中が必要だ。女中がいなければ困る。ハルは雇用された女中ではないが、主従関係という意味で、両者は似ていなくもない。男性優位社会を前提にした共依存を肯定的に描くのは、時代にそぐわない。
半世紀以上前に亡くなった賀川豊彦について、あれこれ批判するのは控えたいと私はこれまで何度も書いてきた。妻のハルについても同じである。問題は、それをどう描くかである。
玉岡はこの作品の中で、ナツというもう一人のハルを設定し、作中で自由に本音を語らせている。たとえば賀川が新川の人々に「このお嫁さんがおたくの女中になって働きます」と発言した際に、「先生、ひどいこと言うよね」と読者に語りかけている。現在から見ると差別的にとらえられかねない賀川の発言を、ナツが中和している。
ところがそのすぐあとに、<自分は神の僕、女中なのだ。それをどうしていやがることがあろう>と続けている。<神の僕>とは言うが、実際は夫や住民の女中ではないか。
ナツをもっと有効に登場させることができなかったのだろうか。

『春いちばん』には ” 女中 ” とともに ” 母 ” という言葉も頻出する。賀川が自伝的小説『死線を越えて』(正確にはその続編の『太陽を射るもの』)で、ハルを母のように表現したからである。以下、引用する。文中の ” 新見 ” は賀川、 ” 喜恵子 ” はハルである。
<新見としては、喜恵子に愛せられて居ることを、此上なき幸福と感じ始めた。それは母の愛のやうに温かいものであつたからである>
賀川はハルに対して母性を感じていた。だからであろう、玉岡がハルを描く際には、やたらと ” 母 ” が出てくる。
<疲れを癒やす一杯の茶を差し出す時のハルは、賀川にとっての ” 母 ” だった。彼が好むことやりたいことは、どんなことでも打ち消すことなく受け止めたい>
母は、どんなことでも受け止める存在なのだろうか。
賀川は『死線を越えて』の中で、ハルの容貌について<更けてみえる>と何度も書いている。『死線』の刊行で、賀川には莫大な印税が入った。なにせ100万部を超える、大ベストセラーである。『春いちばん』の中で、もう一人のハルであるナツがつぶやく。
<――なんちょねえ。これだけのお金が入るなら、豊さんがハルのことを ” お岩さんみたいだ ” と書いたとしても辛抱するよねえ。
そうなのだ。ここでもまたハルは許す人であり、彼の母にはならねばならなかった>
どうやら玉岡は、母=許す人、と考えているようだ。これもまた、性別役割分業の一種であろう。たとえ容貌を悪く書かれても、母であれば印税がたんまり入ることで許せるのだろうか?
幼児教育施設を設立する際のハルの心中を、玉岡はこうつづっている。
<わたしは世の中の ” 母 ” になろう。――母は家族のために働くものだ。どれだけ疲れようとも萎えようとも、家族の幸せのために身を捧げる>
家族のために働くのは、母だけではあるまい。また、家族の幸せのためとはいえ、母を疲れさせ、萎えさてはならない。
<二児の母となり、ハルは女性として充実をきわめる時期を迎える>
<三児の母となり、賀川の妻として、ハルはやっと心の自立を果たした気がした>
いずれも育児は母親の役割、喜びと言わんばかりの記述である。男も子育てに参加することが当たり前とされる現在において、このような表現は時代に逆行する。
育児によって親も成長することはあるとは思うが、結婚や育児が幸せの条件であるかのような書き方に、私は違和感をおぼえる。

史実や歴史を変えることはできない。いや、変えてはならない。しかし、現在から考えて好ましくないそれを表現する際、何の注釈もなしにそのまま記述するのは不用心すぎる。
前にも書いたが、フェミニズムの旗手で社会学者の上野千鶴子が、この本の帯に推薦文を書いている。
<後から来た女は前に歩いた女を見いだし、生きかえらせ、出会い直す。力づよい評伝文学だ>
旧習、陋習まで生き返らせてはならない。<2023・10・31>
『春いちばん再読』①
https://note.com/kadooka/n/na3d494ff23d6
あなたのサポートによって愛犬ももじろうのおやつがグレードアップします。よろしくお願いします。
