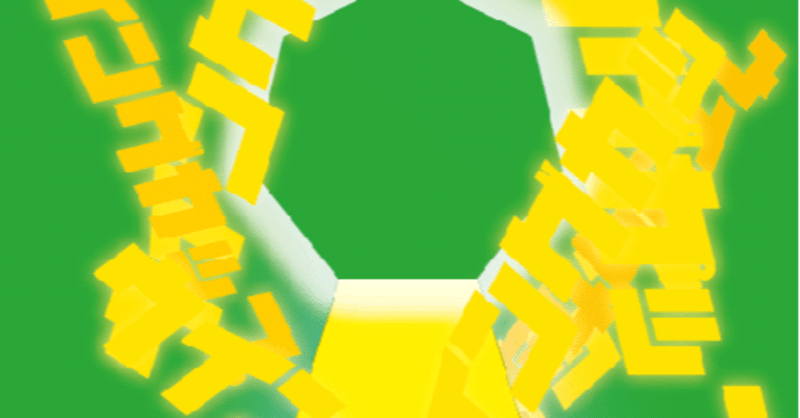
WINGCUP2021総評
■ にほひ「かえりたい」
江藤淳は「成熟と喪失」の中で戦後の家族像について「息子にとって、父は母に恥じられるみじめな父になり、母はその父に仕えるほか生きる道のないことで、いらだつ母になる」と記したが、この作品は見事に、みじめな父と恐らくいらだちの末に母が家を去ってしまったあとの、ある家族の時間を描いている。劇中で妹が語るように、この家族はどうしようもない男どもの家である。ネットパトロールに忙しいヒキニートの弟と、(さほど詳細にはは語られないものの)母が家庭を捨てた主な原因なのだろう、酒を飲んでは暴力を行使しているらしい廃業した元弁当屋の父親は、常にそりが合わない。その間で妹は、母親を直接的に知らないにも関わらず、母親の代わりの役目を背負わされ人生を浪費しているように見え、常態化しているのであろう父に対する妹のつねりも、まるで子どもとしての父を懲らしめる母親のようである。本作に登場する家族はそれぞれに反発し傷つけあっていると一見感じさせながらそれはポーズでしかなく、その傷つけ合いの中にどこか生ぬるさがあり、それはあくまで家族のなかで互いの存在を確認し、家族を維持するための微温的なコミュニケーションの一種でしかないように感じさせるものがあり、もはやこの世にいない母も、不在の中心としてこの家を支配しているという点でそれの共犯者ですらある。そして、そんな底なし沼のようなぼろぼろの家族という制度(=偏狭で過疎化が進んでいるのであろう地方都市)の中からいち早く抜け出した姉は母の死をきっかけに帰還するが、母の家出とともに崩壊していった自身の家族を具体的にどうするのか何もしないのか、結局最後まで何もできず決めかねて傍観しているだけのように見える。
(しかし、あのすでに亡くなっていると思しき姉の幼馴染の登場が、姉にそしてこの家族劇に何をもたらしているのか、今一つ曖昧だったようにも思う。)
誰もが皆家族の崩壊について、自立した個人として理性的に対話し対処することが出来ず、皆気づけばぼろぼろの家族という制度――機能不全の古き家父長制――を延命させることになし崩し的に躍起になってしまっている滑稽さとイヤ~な感じは大変リアルで見事だ。そして、納骨の前日に母の骨壺を破壊し――文字通り母を完全に崩壊/解放させようとする弟だけがもしかしたら家族の中で唯一、バイトの面接に行くことで家族の磁場から解放され、救われるのかもしれない。しかし一方の姉妹の方はといえば、姉は結婚がしたいのでもう仕送りができない、と父に告げる。それが本当だとしたら、姉は家族の修復を断念し新しく自分の家族を外でつくりなおすことにしたのだろうか。しかし裏を返せば、姉は新たな家族をつくることでしか家族から解放されなかったということであり、家族という制度に縛られていることに変わりはない(もちろん全く違う、新しい形で家族をつくりなおす可能性はゼロではないかもしれないが)。一方最後に情けなく「いっしょにごはんを食べたかっただけ」、という父に対し、そもそも母を知らないにも関わらず、「しっかり立って、お父さん」と励ます妹は、妹兼母としてよりいっそう家に縛られ続けるだろう。
ところで、この作品で描かれているぼろぼろの家族という制度および古き家父長制と、特にそこから逃れきれない姉妹について、作者はどのようにとらえているのだろうか、と思った。肯定なのか否定なのか、どちらでもないのかあるいは…良くも悪くも踏み込まないスケッチであり、それが本作の独特な魅力、浮遊感にもつながっているのだが、そこに留まっているが故の曖昧さが、現在形の「家族劇」としての作品のポテンシャルを削いでしまっているようにも感じられたのです。
■ 劇団ぱぶろば「CHU-WOMAU」
大変舌足らずだが展開の予想ができない不思議な感触の作品である。オムニバスコント風味の作品かと思いきや、一筋縄ではいかないフックが仕込まれているというか。宇宙(火星)および宇宙人と人類の遭遇を作品の主題として、全9章は大変緩やかにつながっているようにも見え、2章と8章は同じ場の同一時間軸で、一部同じ登場人物が出てくる4章はもしかしたらその前日譚なのかもしれず、6章はそれの後日談なのかもしれないし、また、研究者たちが火星へのロケット打ち上げの準備を進める中、火星人が現れる→ロケットは打ち上げられたが撃ち落されたらしいことがわかる3章~6章は同じ時間軸と感じられる。
その中でも、火星に行く女子学生たちを描いた2章と8章が印象に残る。高校の卒業旅行として火星に行く少女3人と宗教団体の少女が火星行の宇宙船で出会う。その宗教の教義は宇宙人に自身をいけにえとして捧げることで、宇宙人のように肉体を捨てた魂だけの存在へと進化することのようである。少女3人が退屈しのぎに人生ゲームを始める(!)中、宗教団体の少女は、この宇宙船内にすでに宇宙人がいるというお告げを受け取る。続いて少女3人が人生ゲームの続きをしているところから始まる8章で、この作品はオムニバスコント仕立ての基調を突如かなぐり捨て、不穏さに満ちはじめる。一人の少女は火星にきた理由について、一つは高校卒業の記念であり、もう一つは人間の可能性を観たかった、しかし人間の進化はここにはないことが分かった、そして自分は結果的にあの宗教団体の少女と同じようなことを言っている、と語る。そしてもう一人の少女は突如、自分は実は宇宙人であり、自分は火星に帰還するためにこのロケットに乗っていることを告白する。そこに宗教団体の少女が現れ、二人とともに人生ゲームに興じはじめるが、(2章終わりのお告げより)この宇宙船内にいる宇宙人を探しているらしい彼女は、宇宙人を特定するため、そして宇宙人に自身を殺させ「お引上げ」してもらうために二人に銃を向け、一人の少女を銃殺し、宇宙人であるという少女に銃で自身を銃殺するよう求めるが、宇宙人の少女は銃を使わず突然宗教団体の少女を絞殺する。そこで火星からの迎え?が現れるが、宇宙人の少女は自分のこめかみに銃口を向け、そこで物語はほぼ断ち切られる。
オムニバスとはいえ唐突な鬱展開ではあるが、特に8章に満ちている不穏さや出口のなさからは人類や人生、科学技術や宗教に対する失望、諦観、厭世観が垣間見え、それは作品全体を覆っている気分としてあり、8章の展開はそれが一気に噴き出しただけだともいえる。
地球人や地球に見切りをつけ宇宙で(もはや似たようなものである)科学・宗教に人類の新たな可能性を求めてはみたものの、そんなものはなくそのどちらにも失望し、宇宙人に出会ったところでそこにあるのは殺す殺されるの関係しかない。宗教団体の少女にとって人生とは死の間際に振り返ったところでいかに退屈だったかを思い知る程度のものでしかない。自分の人生と世界について、まるで人生ゲームでも見ているように俯瞰してしまう漠然とした退屈さと失望の「気分」をこの作品はとらえようとしているのかもしれず、それはこの数年間の世界を過ごした実感の一つとして決して間違ってはいないと思う。というわけでささやかですが私から個人賞を、旗揚げおめでとうございます。
■ ヨルノサンポ団「イロトリドリのシロクロ」
同居する二人の女性、教師と劇中には登場しないCAの妻、母子家庭の母とその息子、第一子出産間近らしい妻とその夫という4組の家族が団地を舞台に交錯する(本当に団地の一室を舞台に交錯するときもある)群像劇である。同居する二人の女性のうち一人は普通のOLのようだが、もう一人は親と縁が切れ実質養われている状態で、奇天烈な小説を執筆しネット上にアップし続けている。彼女には次回作として自身が住んでいる団地を舞台にした作品の構想があり、前述の妻が出産間近らしい夫婦について、その夫がエイリアンのような顔だから、という理由で実は夫はエイリアンであるという設定を考えている。OLの方と不倫関係にあるらしい(昔は宇宙飛行士になりたかった)教師は、自分の生徒が飛び降り自殺未遂を図ったらしく対応に追われ、生徒の家を訪れる。しかしその生徒は記憶障害があるらしく飛び降りた記憶がない。怪しげな水を出してくるあたりスピリチュアルの気があるその母は、近頃ネットで人体に悪影響を及ぼす、人間関係に崩壊をもたらす、などと話題になっている団地近くの火葬場から出る煙が息子の飛び降りの原因ではないかと言い出し、教師を巻き込んで火葬場反対の署名運動を始めようとする…
このように団地に住む登場人物たちは私たちと同じく、皆それぞれに何らかの問題を抱えている。火葬場から出る煙はネットの噂通り人体に悪影響を及ぼすのものなのかは実際のところわからないのだが、結果的にそれは登場人物たちの抱える問題や行動により影響を与える、または与えているように見えてしまうだろう。その意味ではあの煙はネットで広がる噂やデマ、フェイクニュースそのもので、劇中の台詞にもあるように、火葬場の煙は「世の中は思っているほど美しくない」という現実を暴く装置として機能しているといえる(あるいはダイレクトに煙草の煙)。
台詞にもあるように、火葬場の煙が暴いた「思っているほど美しくない世界」と、そして思っているほど美しくない私たち自身と私たちはどう付き合うのか、あるいは過剰に美化されていく・ノイズが排除されていく世界とどう付き合うのかということがこの作品では問われ、登場人物たちは応答していく。母子家庭の息子は清浄さを嫌ったのか「もっと空気の汚い場所を探す旅にでる」といい空を飛びこの地を去り、エイリアン(に似た夫)の妻はお腹にいるのかもしれない子供について、「生まれたくないと言っているのでこの中でいさせてあげようと思う」という。一方小説家の女はこの中でただ一人、「煙が無くならないでほしい」・「私たちがきれいじゃないことを教えてくれている気がする」と火葬場の煙を肯定する。物語の終盤、彼女は同居人のOLに好意を告白し一度は拒絶されるものの、結局は煙を出す煙突を見に二人で外に繰り出す。OLの女は不倫相手の教師と同じく、自分も昔は宇宙飛行士になりたかったことを告白する。二人はここではないどこかに行くのではなく、とりあえずはここで 「思っているほど美しくない世界」 と付き合っていく、ノイズを排除せずに付き合っていくことを選択したことが暗示されるエンディングには静かに心動かされるものがある(とはいえ、個人的にはあの夫婦にも救いが欲しかった。夫が火葬場で働いていることが判明するからこそ)。優秀賞おめでとうございます。
■ 餓鬼の断食「対岸は、火事。」
明確なストーリーラインなどはなく、就職を控えたり控えなかったりする年代の男女6人が、餃子パーティーのために借しアパートに集まって過ごす中でのとりとめのない会話の時間をリアルタイムに切り取った、チャラめのリアリティ番組仕立ての約70分といえば事足りてしまうのだが、魅力的な登場人物たちがいちいち煌めくような台詞を使って自身の心情をきっちり無理なく吐露できる実は手堅い構造の脚本と、関西弁現代口語演劇かくあるべしとでもいいたくなるナチュラルかつハイスピードなタイム感・高情報量での発話・会話をものにしている俳優陣の練度に単純に舌を巻く。
社会学部から文学部に編入し最近はデカルトの方法序説を読んでおりつけている香水はジバンシィ、挽いたコーヒーはそのまろやかさにおいて高評価であるらしいノボルがダンサーのナオと付き合っているなれそめは、キャリアの割には大きい舞台が続きそのことで悪い噂がたち精神的に限界を迎えたナオの傍に少しでもいたいからだったという。看護師の学校に通っているらしいカオリは長年習っていたバイオリンを先生との不適切な関係がバレたことで辞めてしまったことに今でも深く傷ついている。普段はかつての文豪を主に愛読しているようだが最近はノルウェイの森を読んでいるらしくでもさくらももこしか勝たん! と語るものの太宰に深く傾倒しているらしいシュンは天王寺でギターの弾き語りをやっている。漫才や音楽で生きていきたいとはいうものの6人の中では一番クールで知的な突っ込み役ポジションのアイカはエリート女子高の偏差値的な意味ではなくその空気に疲弊しドロップアウトした過去がある。優男のセイヤはかつてカオリと付き合っていたようでしかしながらナオにも手を出したことがあるらしく、そのことがきっかけで起こるノボルとシュンの喧嘩が、唯一のわかりやすく劇的なシーンかもしれない。
必ずしもデカルトやマルクスという固有名詞が出てくるからというわけではなく、この作品の登場人物たちは皆頭がよく、とても自分たちのことをわかっている人たちだと感じられる(でなければ、あんなに自分のことを客観視して話せるわけがない)。マーク・フィッシャーいうところの再帰的無能感――「彼らは今の事態は良くないとわかっているが、それ以上に、この事態に対してなす術がないということを了解し」、そしてそれを気持ちポジティブに内面化しており、それはウクライナ戦争のみならず(戦争反対デモへの淡白な反応!)自分たちの行動にも向けられているように感じられる。「稚拙な論理は往々にして暴力に着地せざるを得ない、70年代で証明されてるやん」とアイカは言うものの、私たちは変わらずノボルとシュンのように殴り合いをし、その暴力の光景は「三月の5日間」におけるイラク空爆よろしく本作にうっすらと影を落としているウクライナ戦争と重なるだろう。人類は伝染病も戦争も災害も克服したと思っていたが、全くそうではなかったというやつで、恐らく彼らのことだからそんなことも承知のはずなのだ…かつての千葉雅也は『小説、苦手なんです。というか、人間と人間のあいだにトラブルが起きることによって、行為が連鎖していくというのがアホらしくてしょうがない。だって、人と人のあいだにトラブルがおきるって、バカだってことでしょ。(略)魂のステージが低いという前提で書いているから、全ての小説は愚かなんですよ』と誇張的に語った(ちなみにその後、氏はその考えについてある面では変わり、ある面では変わっていないと述べ、実際に小説家としても精力的に活動している)。一方彼らは高等遊民のように文学や音楽やアートに勤しみ恋愛のトラブルも享受する。「恋愛して喧嘩するんならせんかったらええやん」とわかっていながら恋愛する。人間の愚かで時に愛おしい営み、あるいは理性と情動のせめぎあいが劇場の外と劇場の内で今まさに同時に起こっている様を私たちは観ることになる。そして「文学はなんかおかしいから」というあまりに本質的な理由で社会学部から文学部に編入したノボルの態度を、私は今こそ肯定しなければならないと思った。この社会は虚偽であり(社会唯名論)、文学=人生の存在だけに賭けるということ、文学=人生を尽きなく享受することこそが最も善く生きることだということ。小泉義之のことばを借りれば、『若者が先達の営為を知ろうが知るまいが、それでも、若者は、いかなる人文知や思想史研究よりも文学が大切なものであることを銘記しておくべきで』あり、『学問も政治も、人生に寄生するものにすぎない。学問も政治も人生の前に跪くべき』で、『文学は、人生を書くことができる。文学だけが、人生そのものになりうる』ということ。
作品はウクライナ戦争反対デモ見物を兼ねた散歩に6人が繰り出していくところで終わる。彼らは決してデモに混ざることはなく、デモをつまみに酒でも飲んでいるに違いないしそうあってほしい。容易ではないが社会ではなく人生を享受しつくすことこそが、この2、3年の世界への最も優雅で美しいデモンストレーションであることを、この作品は身をもって示している。最優秀賞おめでとうございます。
■ 演劇強制収容所 旦煙草吸「そっか」
なるほど、パッケージとしては(あまり詳しいとは言えないのですが)アニメや2.5次元っぽさや地下アイドル感も加えた、エログロアングラ演劇だグランギニョルだ! と思った。「1963年、もはや戦後ではない」という大仰な言い回しとともに始まるのは、リリス計画という計画が秘密裏に進行しているらしい戦後のある女学校を舞台にした、そこに通う女学生たちや教師たちによる群像劇なのだけど、このおどろおどろしさ一転突破なアングラ感について、個人的にはこれをネタでやっているのか、メタでやっているわけではなさそうだし、じゃあベタ(本気)でやっているのか? などと考えていた。どう考えてもネタでやっていると感じ、声には出さなかったけど爆笑しながら見たところもあり、大変混乱していて非常に楽しく観たのは確かです(やはり今の世界に向き合おうとしたら、このように正しく混乱したものをつくるのも一つの誠実な態度なのかもしれないと思うのです)。
本作の大きな核として進行するリリス計画のリリスについて調べてみると、リリスはアダムと対等に扱われることを要求してアダムと口論となり、アダムのもとを去ったという経緯のためか、Wikipediaによれば女性解放運動の象徴の一つにもなっているらしく、劇中のリリス計画とは「イブの血が流れている現在の女性をイブの呪縛から解き放ち、本来の女性の姿にし少女を少女のまま母体にする」というものらしい。非常に興味深く、フェミニズム的な文脈でアングラ演劇を再構築するのか!? と思いきやどうやらそういうわけでもないようで、アングラ演劇的なものを構成する要素の一つにすぎないというか。他にも過激な性的シーンや緊縛、ハーフ差別、今後日本は戦前回帰し多様性などは無意味になる、など様々なトピックやタブーに接触しそうな刺激的な台詞やショッキングなビジュアルは頻出するものの、全てが構成要素の範疇内ではあり、懐かしのアングラ演劇的なフォーマットというか趣味性の中に良くも悪くも納まっている印象。そこでふと見てみたパンフレットのごあいさつには、「時代錯誤も甚だしい社会問題ミーハー祭です」と書かれておりとても納得し、たしかにこの、過激な描写や社会問題を様々な歴史的文脈や政治性を抜きにしごたまぜにして、アングラ演劇的な作品を構成するあくまで一要素としてミーハー精神でピックしてフラットに配置されている、パッチワーク感こそが興味深い「今」であるし、作り手もそれに自覚的なのであればその意図は十全に達成されている。ただピックした諸問題について、今の劇世界の強烈な個性――アングラフォーマットはそのままに、ミーハー精神からもう少し踏み込んで扱ってみることで、今を生きる人が今こういった作品を上演する意義や意味が、より強く迫ってくるものになるかもしれません。あるいはもっともっと社会問題ミーハー祭りを極めきることで、新たな展開が見えてくるという可能性もあるとは思います。とにかく、劇世界の強烈な個性は素晴らしく、確固とした独自の美学があることも十分に了解できるので、より高い完成度を目指して活動を続けていただけることを期待しています。
後記のようなもの
今年久々に、というかほぼ初めてか?演劇のコンペで審査される側になったのですが(第12回せんがわ劇場演劇コンクール)、審査される側のキツさを改めて思い知りまして、審査する側としての自らを思わず省みたのでした。上演後の一般審査員の皆さんとのアフターディスカッション、そして専門審査員の皆さんの講評会での真摯な佇まいに、演劇作品の上演すら厳しい判断を迫られる時代だからこそ、一つ一つの作品に真摯に接していくことの大切さを改めて学びました。WINGCUPもそうありたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
