
都立高校入試国語大問5「古文」対策②
今回は都立入試国語の「古文」対策について書いていく。
では以下、平成31年都立入試問題。


[問2]の問題文を読むと、
「大岡さんの発言の中で引用されている紀貫之と西行の桜の歌の特徴について説明したものとして最も適切なのは、次のうちではどれか」
と書かれているので、
紀貫之と西行の桜の歌の特徴
について本文からその根拠を探していこう。
では、本文を確認すると、(2)以降の文から
「たとえば紀貫之の歌で、山寺にもうでて、一夜泊まった歌がありまして、
宿りして春の山辺に寝たる夜は
夢のうちにも花ぞ散りける
あれは、夢の中で桜が豪華に散っている感じが非常によく出ているんですけれど、西行になると、「夢中落花」などという題で有名な、
春風の花を散らすと見る夢は
覚めても胸の騒ぐなりけり
あれなんかは、ちょっと桜の見方が変わっていますね。
それと、西行は、何を対象に詠んでも、自分のことになる。桜が咲くのが苦しいなんてね。」
と書かれているので、単純に
紀貫之=客観的な文章(見たことを書いている。)
西行=主観的な文章(自分の心情を入れて書いている。)
また本文に以上の歌の現代語訳があるのでそれぞれ確認していこう。
紀貫之の歌
宿りして春の山辺に寝たる夜は
夢のうちにも花ぞ散りける
「旅先で宿をとって春の山辺に寝た夜は、夢の中にまで昼間に見た桜の花が散っていたことよ。」
⇒桜の美しさの印象を書いている。(客観的)
西行の歌
春風の花を散らすと見る夢は
覚めても胸の騒ぐなりけり
「 春風が桜の花を吹き散らす夢は、目が覚めてもなおその美しさに私の胸はかき乱されることよ。」
⇒桜の美しさに目覚めてからも、感動し心を動かされたことを書いている。(主観的)
とそれぞれ矢印で書いた2つの
客観的な美しさか主観的な美しさ
というポイントを確認して選択肢を選んでいこう。
そうすると、
ア「紀貫之の歌は桜の花が夢の中で舞う繊細な美しさを描いているが、西行の歌は桜の花が夢の中で散る悲しみを独自の視点で描いている。」×
イ「紀貫之の歌からは作者のゆったりとした人柄が伝わってくるが、西行の歌からは桜より自分が大切だという利己的な人柄が伝わってくる。」×
ウ「紀貫之の歌は桜が華やかに舞い散る様子を表現しているが、西行の歌は桜の美しさに加えて美しさに心乱される心情をも表現している。」○
エ「紀貫之の歌には満開の桜を愛する心情が巧みに表現されているが、 西行の歌には貫之よりも強い愛情が素直な言葉で表現されている。」×
となるので、答えはウとなる。
このようにポイントを取り出し、
その軸から選択肢を選ぶ
ということを行っていけば古文も確実に正答することができる。
好き勝手に読むのではなく、しっかり軸を持って読解するようにしていこう。
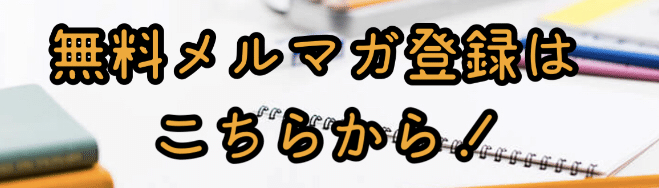
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
