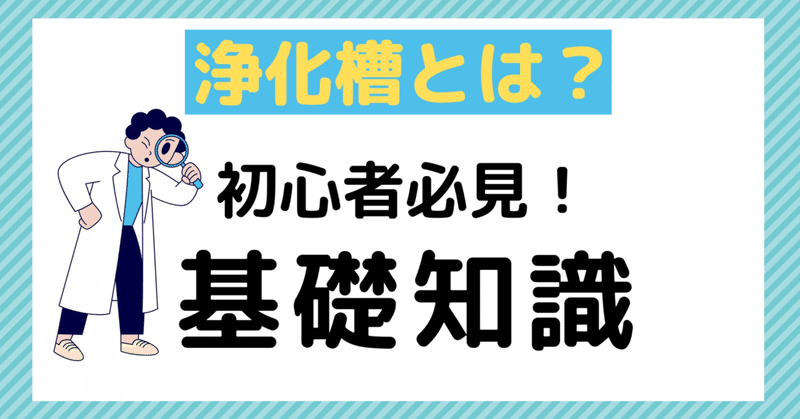
浄化槽の【基礎知識】毎日使う浄化槽を網羅的に解説!
浄化槽の知識を身に付け未来の地球、未来の子供のために、より良い環境を目指していきましょう!

本記事では、現在浄化槽を使用している方、これから浄化槽を使用される方に浄化槽の基礎知識を分かりやすく網羅的に解説しています。
この記事を見て分かること
浄化槽って何?
浄化槽維持管理とは?
浄化槽清掃とは?
浄化槽ブロワーとは?
浄化槽の法定検査とは?
浄化槽とは?一般家庭に設置している汚水処理装置

■ 浄化槽とは家庭版の汚水処理場
■ 合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の2種類ある
■ 点検、清掃、法定検査が必要
■ 定期的な検査をおこなうことで環境が守られている
浄化槽とは、下水道がまだ整備されていない場所や、この先も下水道が通る予定がない地域に多くあり、一家に一基設置されている「一般家庭版の汚水処理装置」のことです。
浄化槽とは一般家庭版と言いましたが、下水が通っていない地域では病院や学校なども合併浄化槽で汚水を処理しています。
生活排水を未処理で放流してしまうと川や海の生物、環境に悪影響が出てしまうので環境を守るためには必須の設備と言えます。
浄化槽と聞くと馴染みがなく、汲み取り式トイレ(ボットン便所)や臭いものと思う方がいます。ですが、「浄化槽と汲み取り式トイレは全くの別物」です。
浄化槽と汲み取り式トイレの同じところはどちらも「バキュームカー(衛生車)で汲み取り、浄化槽引き抜き清掃作業」をおこなうことです。
浄化槽は全国の普及率が10パーセントほどで認知度がまだまだ低いんです。
お客様で私の家は汲み取り式トイレと思っていたのに浄化槽だったんだ、なんてこともありました。
都会では下水道が普及していて、浄化槽も汲み取り式トイレもほとんど無くなっていますが、地方にはまだまだ多く「バキュームカーも現役」で活躍しています。
都会でも外仕事の現場やイベント等の仮設トイレがあるので、バキュームカーは必須で、これから先も無くなることはありません。
清掃作業をおこなう際に、バキュームカーに備わっている燃焼式脱臭器が燃焼しながらニオイを取り除いています。その際に煙が発生します。
発生した煙が皆さんの頭に思い浮かぶ、おならのようなニオイです。
ニオイを消すためにニオイが出るの?と思われるかも知れませんが、あるとなしでは大違いなんです。
昔と現在で比べるとバキュームカーから出るニオイもかなり軽減されています。それでもやはりニオイはありますけどね。笑
余談ですが、「浄化槽や下水道を使用しているとニオイが出る」ことはあります。
流しているモノがモノだからです。
よく下水道はニオイが出ないと仰る方がいますが、下水道だからニオイが全く出ない、浄化槽だからニオイが出るということではありません。
ただ、浄化槽の場合マンホールが数枚あるため、しっかり閉まっていない場合や劣化などによる原因で、ニオイが出る可能性が高いことは間違いなく多いと考えられます。
合併処理浄化槽の処理能力

一般家庭の浄化槽には「2種類」あります。
合併処理浄化槽と単独処理浄化槽があります。
合併処理浄化槽は、家庭で使用した「全ての生活排水」を処理することができます。
どの程度キレイに処理できるかというと、「BODという汚れの指標」では、人は「1日約40g」ほどの汚れを流出しているといわれています。
し尿(13g)
洗濯、お風呂(9g)
台所、洗面台(18g)
合併処理浄化槽の処理能力は「BOD除去率90%以上」となっているので「40gの場合4gまで減らす」ことが可能です。
単独処理浄化槽の処理能力

一方の、単独処理浄化槽は「トイレのみ」浄化槽に繋がっています。
単独処理浄化槽はトイレのみなので、洗濯、お風呂、台所、洗面台は「未処理」で側溝や河川に放流されている状態です。
さらに、単独処理浄化槽の処理能力は「BOD除去率が65%以上とそこまで高くない」ため、上記と同じ使用状況で計算すると次のようになります。
し尿(約5g)
洗濯、お風呂(9g)
台所、洗面台(18g)
1日に人が流出する汚れの指標は約40gなので、単独処理浄化槽の場合、「32gが未処理で放流されている状態」です。
約80%が未処理で側溝や河川に放流されているため、環境によくない状態です。
単独処理浄化槽は昔の浄化槽
■ 現在、単独処理浄化槽は設置できない
■ 合併浄化槽への切り替えが推奨されている
■ 補助金もある
単独処理浄化槽は浄化処理能力に期待できないため、「平成13年4月1日から設置が禁止」されています。
新設工事をおこなう際は「合併処理浄化槽の設置が義務付けられるように」なりました。
現在、全ての地域で単独処理浄化槽を使用している方へ、合併処理浄化槽、もしくは下水道に切り替えることを推奨しています。
ただ、当然費用が掛かるので簡単に切り替え工事がおこなえていないというのが現状です。
切り替える際には補助金も出ているので、「住んでいる地域+浄化槽補助金」で検索してみてください。
一番小さな5人槽で地域によっても異なりますが、約30万円ほどの補助金がおります。
維持管理とは?保守点検、清掃、法定検査の3点

浄化槽を所有する方が必要な義務
■ 保守点検
■ 浄化槽清掃
■ 法定検査
浄化槽維持管理とは「保守点検、浄化槽清掃、法定検査」この3点セットです。
浄化槽保守点検をおこなう際は「浄化槽管理士という国家資格」が必要になります。
▼浄化槽を「所有する方には3つの義務」があります。
下の動画ではそれらを簡単にわかりやすく解説しています。
なぜ、保守点検が必要かというと、浄化槽自体メンテナンスが必要な仕組みになっているからです。
維持管理をおこなっていない浄化槽はただの汚物を溜めているタンク状態となり、環境にとってものすごく悪影響を及ぼしてしまいます。
保守点検の内容
■ 消毒剤補充
■ 槽内の漏水、装置確認
浄化槽漏水、修理の詳細記事はこちら
■ 水質チェック
■ 害虫駆除
浄化槽に潜む害虫の駆除、対処方法の詳細記事はこちら
国家資格を持つ浄化槽管理士が浄化槽の型にあった適正な点検をし、水質の向上、日々のメンテナンスをしています。
浄化槽維持管理の記事はこちら
定期的なメンテナンスをおこなうことで、異常事態を早期発見することができます。
人間の体と同じく早期発見をすることで、掛かる費用も最小限で抑えることが可能です。
普段、維持管理をしていなくて困った際に管理業者を呼び、気付いた時には手遅れになっている浄化槽をたくさん見てきました。
これらは浄化槽維持管理をしていると必ず早期発見できています。
どんなモノでもほったらかしにしていると「ホコリを被ったり、汚れてサビが付いたり」しますよね。
浄化槽は基本的に毎日使用するものなので、定期的な管理をしていないと消毒剤が無くなったり機械が故障したりと次々に問題が発生します。
浄化槽が詰まったり、大腸菌が滅菌処理されず環境によくない水が流出してしまいます。
点検、清掃、検査は環境のため

点検や清掃の際に異常がある場合、お伝えするとお客様にこのようなことを言われることがあります。
お客様「点検も、清掃もしているのになんで異常が起きるの?」
気持ちはわかります。
これは、他のことに例えるとわかりやすいと思うので例文を2つ用意しました。
例1. 車で例えると、車検を受けた次の日になのになぜか調子が悪い、なにかしらの問題が起きたという方もいると思います。
車検時は問題がなくても次の日に問題が起きるということもあります。
例2. あなたは毎日病院に通っていたとします。
病院に通っているからといって病気やケガをしないわけではないですよね?
ですが、病院に通っていると早期発見することができます。
浄化槽も同じで定期的な点検、清掃、法定検査を受けていても異常が発生することはあります。
一方で、定期的な維持管理をおこなうことで早期発見することができます。
人間の体と同じく早期発見をすることで、掛かる費用も最小限で抑えることが可能です。
基本的に異常無しという結果が多く、点検や検査を受ける意味あるの?と思われがちですが異常無し状態が一番良く、異常無しを目指してわたしたちも日々管理をおこなっています。
ホタルや川魚が減っている?

昔は家の前でホタルや川魚が見れていたのに、現在は全く見れなくなったという方もいると思います。
ホタルや川魚はキレイな水がある場所を好むので、浄化槽維持管理を受けていない方だけの影響とはいいませんが、確実に環境に影響しています。
下の動画では維持管理の大切さ動画で解説しています。
多少の閲覧注意があるので苦手な方はそのまま読み進めてください。
保守点検の回数は地域によって異なる
保守点検回数は浄化槽法第十条で決められており「1年に3回以上」とされています。
合併処理浄化槽の場合、1年に3回の点検回数だと異常が発生した時の対処が遅れたり、消毒剤が不足してしまうことが頻繁に起こります。
なので、年に4回以上のことが多く、推奨もされています。
保守点検回数は年に3回以上は必要です。
最低3回以上であれば回数に決まりはなく、年に6回や、毎月点検を実施している地域もあります。
上記の場合、かかる費用は1回分が安くなっています。「大型浄化槽になると、毎日点検」が必要な現場も多くあります。
浄化槽清掃とは?槽内の汚れを引抜く作業

浄化槽法で清掃回数が決まっており、「原則1年に1回以上の清掃」をおこないます。
浄化槽の型式によって清掃頻度が異なりことがあり、単独処理浄化槽の全ばっき型に関しては容量が小さいため「6ヵ月(半年)に1回以上の清掃が必要」となっています。
清掃しないと起こる問題
■ ニオイ、汚れが外に流出
■ 槽内の装置が故障する
■ 早期発見が遅れる
浄化槽清掃をしないとニオイがでます。
臭い物に蓋をする、と言ったことわざがありますがまさにその通りで、例えその時はニオイが出ていなかったとしても一時しのぎにしかなりません。
浄化槽の型式には清掃時期を目安にできる堆積汚泥というものがあります。
底部に沈んだ汚泥量、スカムを測定し、型式に合った堆積汚泥量があるのでその基準値を超えていた場合は清掃時期と判断する目安になります。
汚れが溜まったら清掃を実施しましょう。
下の動画では堆積汚泥について解説しています。
浄化槽に汚泥が溜まるとガスが発生する
下の動画では実際にガス抜き作業をおこなっています。
汚泥が溜まるとメタンなどのガスが溜まります。
点検時にガス抜き作業をおこないますが、完璧にガスを抜くことは不可能です。
保守点検や清掃をおこなっていない場合、溜まったガスがろ材を上に押し上げ槽内が壊れる原因になります。
清掃を実施していない場合、汚泥の重みに「ろ材を止めているネットが耐えれなくなり」抜け落ちます。抜け落ち故障すると浄化槽の処理性能に支障をきたします。
定期的な清掃をおこなうことで上記のことが起きる確率を減らすことが出来ます。
浄化槽の修理をするとなると、その修理代は軽く10万円を超えてしまいます。。。。
浄化槽清掃は槽内を確認するため

浄化槽清掃をすることで点検では見えなかった状態を目視で確認することができます。
早期発見や異常があった場合、これ以上酷くならないような対策を提案したりすることもできます。
※例外として使用頻度が少なく、そこまで汚れが溜まっていない場合は「2年に1度の清掃」など、臨機応変に対応してくれる地元業者も多いと思います。
逆に、使用頻度が多く汚れが多い場合は、1年に1回の清掃では正常な浄化機能が保てないため「1年に1回以上」の清掃をおこなわないといけません。
浄化槽の清掃は基本的に1年に1回ですが、汚れに応じて清掃回数を増やしましょう!
浄化槽清掃には知識、技術が必要!
浄化槽には1槽、2槽、ばっ気槽と別々の役割がある部屋があります。
浄化槽の1槽目には沈殿分離槽といって「固形物と液体」に分離する槽があります。
底部には水より重い汚泥や食べカスが溜まります。
上部には底部で出たガスや水より軽いゴミ、油が溜まっていきます。
底部には「底部汚泥」、上部には「スカム」と呼ばれる固まりを溜めています。
浄化槽を使用していると汚れが溜まりスカムもどんどん大きくなっていきます。下の動画ではスカムを解説しています。
汚れの溜まる目安がおよそ一年

底部汚泥やスカムの汚れが溜まる目安がおよそ1年ということです。
汚泥が外に流出することを防ぐために清掃をおこないます。
最近の合併処理浄化槽はとてもコンパクトになっているので、1年持たないこともよくあります。
浄化槽とはいえ、使用量のキャパを越えてしまうと、処理が追いつかなくなることは皆さんなんとなく想像できるかと思います。
なので、環境のためには、汚れの量に合わせて清掃回数を増やしていくことをおすすめします。
清掃をする際に使用する車が「バキュームカー(衛生車)」です。
バキュームカー乗っていると、初心者の方によく言われることがあります。
初心者さん「ホースを突っ込むと吸引できるんでしょ?簡単そうだね。」
わたし「実際はそれほど単純ではありません。」
下の動画では実際に私が清掃をしています。よろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。
国家資格が無くてもバキュームカーの操作は可能ですが、浄化槽清掃技術者という国家資格があるほど、「浄化槽を清掃するには知識、技術が必要」です。
当然、初心者の方とベテランの方では清掃の仕上がりもかなり違ってきます。
良い管理業者の特徴、選び方

良い会社の特徴
■ 対応が早い
■ 愛想が良い
■ 人が変わらず安定している
浄化槽管理会社はたくさんあり契約金額もさまざまです。
安ければ安いといいと思っているお客様が多いと思いますが、全然そんなことはありません。
対応が遅い、愛想が悪いというのは、仕事がうまく捌けていない会社に多くあります。
仕事が捌けていない=仕事が雑になりがちです。
しっかり連携が取れている会社には余裕があり対応も愛想もとても良いです。
点検や清掃のたびにコロコロ人が変わる会社はよくありません。この話はどこの会社でもそうですよね。
良い会社というのは人が辞めていきません。
相場や口コミを調べて、良い業者と契約しましょう。あなたの大事な資産を託すことなので。
浄化槽維持管理費用相場
清掃費用の相場ですが、地域や人槽の大きさによって変わるので目安としては、1番小さな浄化槽の5人槽で「20000円ほど」です。
保守点検と清掃料金を合わせて年間約4万円ほどになります。
4万円を365日で割ると1日あたり109円です。こちらに法定検査料、ブロワーの電気代もかかります。
ブロワーとは?微生物や配管に空気を送る心臓の役割

微生物、配管に空気を送り循環している
微生物処理している
大きくわけて2種類の微生物がいる
ブロワーが故障するとニオイの原因になる
ブロワーが壊れると水質が悪くなる
どのように汚水をキレイに浄化処理しているかというと、「微生物によって有機物(汚れ)を分解」しキレイに処理をしています。
簡単に説明すると微生物が汚れを食べて処理しています。
大きくなった微生物は、水より重くなることで底部に沈み、汚泥返送配管によって最初に流入する1槽に汚泥が溜まっていく仕組みです。

微生物には「空気を必要とする微生物と、空気を必要としない微生物」の2種類がいます。
空気を必要とする微生物を「好気性微生物」空気を必要としない微生物を「嫌気性微生物」といいます。
空気を好む微生物に、酸素を送る機械がブロワーとなります。
ブロワーが故障し空気が送られなくなると、「好気性微生物が死滅」し、うまく浄化処理できなくなります。
水質が悪くなりニオイの出る原因になってしまいます。
また、ブロワーが止まると配管(散気管)の吹き出し口や管内に汚れが詰まり、正常に空気が吹かなくなります。
下の動画で解説しています。
嫌気性微生物は、1槽目と2槽目で有機物を主に「二酸化炭素、メタン」などに(汚れ)を分解しています。
好気性微生物は主に有機物を「窒素ガス」などに分解しています。
法定検査とは、管理が適正にできているか?浄化槽は正常かを第三者目線で検査する機関

法定検査の件でお客様から1番多い質問は、7条検査と11条検査ってなに?という質問です。
■ 7条検査とは、浄化槽を設置後3ヶ月経った日から5ヵ月間のあいだに検査するもので、「使用開始時の1回のみの検査」となります。
浄化槽が適正に設置されているか、水の流れは問題ないかなど検査しています。
■ 11条検査とは、「毎年1年に1回検査をする」こと。
浄化槽が適正に機能しているか、管理業者は点検、清掃を適正に実施しているかなどを検査します。
ほとんどの方が7条検査は受け終わっていると思うので以下の3つを覚えていれば大丈夫です。
1年に3回以上の保守点検、1年に1回以上の浄化槽清掃、1年に1回の都道府県の法定検査があると覚えていて下さい。
浄化槽維持管理は集団生活する上でのルール
Q なぜ民間業者に維持管理をしてもらっているのに、法定検査を受けないといけないの?
A 管理者(これを見ているあなた)は浄化槽維持管理では、上記の維持管理とは?で申し上げているように、「保守点検、清掃、法定検査」この3点セットになっているからです。
とはいえ、皆さんの気持ちも分かります。私自身、自分で保守点検、清掃をすることは可能ですが、法定検査は受けています。
車で例えると自分で整備ができるからといって、車検に掛かる費用を支払わなくてもいいとはなりません。
それと同様に必要だからあるわけで支払うだけ無駄なんて決して思わないで下さい。
法定検査なんて受けなくていいよと仰っている方は自分自身のことしか考えていません。
お客様「法定検査は2重取りだ!受ける意味あるの?」
お客様からすると、2重取りなんじゃないの?受ける意味あるの?と思う方もいると思いますが、お客様が依頼している民間業者がしっかり仕事をしています!といった太鼓判を押してもらっている証明にもなるので、信用できる業者ということなります。
仕事なんだから当たり前でしょ?と思われる方もいると思いますが、テキトーな業者はどの職業にも存在しています。
そのような業者が仮に一つでもあると環境にすごく悪影響ですよね。
民間管理業者とは別の法定検査センターという機関があることで、お互いの機関が気を緩めることなくしっかりとした業務を実施し、環境を守っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
