
ブルアカ苗字考その③ ~珍しい苗字~ (300世帯以下、100世帯以上)
いよいよ本企画の大立ち回り、珍しい苗字の域に突入する。とはいえこれでもブルアカの中ではよくいる方なのだ。
また再三伝えた通りここからはネット上からサルベージした苗字の実在証拠と共にお送りする。方法については冒頭の記事を参照頂きたい。
加えて100%の信憑性があるわけではないことと、どうしてもストリートビューの仕様上画質が著しく悪くなってしまう画像があることをご容赦願う。
美甘
約300世帯・1,100人
読み:みかも、みあま、みかん

少女の名前のようなかわいらしくてスウィーティーな苗字だが、岡山県真庭市などで見られる。発祥も同地で、美甘郷という地名があったようだ。
また戦国時代には田井城を拠点として同地付近を美甘氏が支配したと言われる。
この苗字の他の読み方に「みかん」(鳥取県などに存在)というものがあるが、果物のミカンを表すと思われる苗字も「樒柑」「樒柑山」などいくつか存在し、いずれも希少だ。

羽川
約260世帯・900人
読み:はがわ、はねかわなど

秋田県などに見られる苗字。由来は秋田県秋田市の地名「下浜羽川」から。また同地名は「はねかわ」と読むが、苗字では「はがわ」読みが圧倒的に多い。
羽川というと『化物語』の羽川翼を思い出すユーザーも多いかもしれないが、同作品に登場する苗字は「阿良々木」「戦場ヶ原」「八九寺」「忍野」など非実在のものも多い。阿良々木は実は冒頭で紹介した須﨑氏のサイトには記載があるのだが、有名な幽霊苗字として知られている。「戦場ヶ原」「忍野」も著名な名勝があるため実在しそうではあるが、今のところ確認はできていない。何でもは知らないわよ。苗字のことだけ。

下倉
約220世帯・800人
読み:しもくら、したくら

長野県、三重県、山梨県などに多い。字面通り下(ここで言う下とは標高の低い土地のこと)に倉があったか、もしくは「倉」が「崖」を意味するため下に崖があったことが由来であるとされる。ちなみに「崖」のつく苗字は僅か4種ほどしかない。
個人的に下倉といえばニトロプラスのライター・下倉バイオを思い出すが、彼の名の由来は下倉楽器の経営する下倉バイオリンからであり、同社の社長も下倉姓である。

黒見
約200世帯・700人
読み:くろみ

鳥取県境港市・米子市などに多い苗字。同地付近にあった黒見村が発祥とされる。あまり情報がない。
境港市の先々代市長に黒見哲夫という人物がいたが、彼は同市出身者の代表格である水木しげるを称え、「水木しげるロード」を設置した。これを機に地域活性化が図られ、「妖怪の町」として境港市は一躍有名となったのだ。

浦和
約190世帯・800人
読み:うらわ

埼玉県に非常に有名な地名があるが、苗字としてはそこまで数がない。同地を由来として埼玉県にも多いが、三重県にも多い。こちらは現在の南伊勢町に位置する古和浦湾から取られ、平家の落人が名乗ったそうだ。
そして浦和で苗字といえば、19世紀の宇和島にいた浦和盛三郎という人物を是非取り上げたい。彼は宇和島を中心に由良半島の漁業勃興に貢献した偉人なのだが、同時にその地の住民に職業にまつわる苗字を授けたとされ、作物に由来する「大根」、魚に由来する「浜地」などの名字を生んだという。
ちなみに当記事は極めて健全であり、下ネタもなく透明感を保ち続ける所存である。

鰐渕
約180世帯・800人
読み:わにぶち、わにふち

新潟県・福井県に多い。類似となる鰐淵の異形とされる。また奈良時代の豪族に和邇(和珥)氏がおりそれに通じるとも。
古事記には海の怪物として「和邇」という表記があり、これはワニそのものではなくワニザメを意味するのではないかという説がある。これに関してワニに皮を剥がされたウサギを助けるオオクニヌシの逸話もあるので、興味があれば各々調べてみるとよい。
またアカリは食の怪物である。
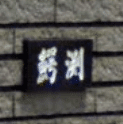

表札で敢えてそうしているというケースもある。
風巻
約180世帯・770人
読み:かざまき、かぜまき

あまり出番のないキャラだが、フルネームが判明しているらしいので一応掲載する。
新潟県中魚沼郡津南町にダントツで多く、少ない世帯数ながら同町ではトップ30に入る苗字。「風が激しく吹き荒れること」を意味する風巻(しまき)という古語があるため、これに端を発した地形由来の苗字と思われる。「雪風巻」は冬の季語。
また新潟県上越市には風巻神社という神社もある。同地はその名の通り風を祀っているため、ライダーが多く訪れるそうだ。

天童
約140世帯・500人
読み:てんどう

ユウカに次ぐ新たな月曜日の使者としてログインを果たしたアリスの苗字・天童は、秋田県湯沢市などに存在。発祥は山形県天童市とのことだが、同地にはほとんどいないようだ。
またこの苗字を聞いて天童よしみを思い浮かべるユーザーも多いだろうが、これは芸名であり本名は吉田芳美。ルポライターの竹中労なる人物が「『天』から授かった『童』(わら/わらべ)」という意味合いで名付けたそうで、天童市すら関係がない。
︙
︙
︙
天童……仏教の守護神や天人などが子供の姿になって人間界に現れたもの。
ストーリーを見ていると、何か深い意味のある苗字な気がしてならない。
その他にもアリストテレスにかこつけて「天動説」からとか、その言動を踏まえて「任天堂」から来ている説など、苗字にもかなりの含みがある生徒と言える。

棗
約130世帯・570人
読み:なつめ

福井県に多く分布しており、発祥も現在の福井県福井市石新保町にあった同地名からと言われている。また、「夏目」の異形とも考えられる。
ちなみに本来読まないにも関わらず「棘」と書いて「なつめ」と読む苗字も数世帯ほど存在しており、苗字の不可思議さを伺わせる。「朿」とは「草木の先端の尖った形」を意味する象形文字のようだ。
棗という苗字のキャラでは『リトルバスターズ!』の棗兄妹を思い出すユーザーも多いだろう。
なおイロハの中の人である福圓美里の苗字「福圓」は非常に珍しい苗字である。「圓」は「円」の旧字体であり、兵庫県伊丹市などにある福円寺の寺号由来という説が濃厚だ。
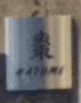
宇沢(宇澤)
約130世帯・570人
読み:うざわ、うさわ

山形県、千葉県、大阪府などまばらに見られる。「宇」とは「宇宙」のように広大な規模を表す意味もあるが、ここでは恐らく家を覆う庇のこと(特に伽藍を覆う庇のことを「堂宇」などと呼ぶ)。そこに地形の沢が合わさったものと考えられる。
またストリートビューで漁ってみれば分かるのだが、電話帳が「宇沢」であるのに対し表札では「宇澤」と旧字体表記であるものが多い。この場合は後者が恐らく正しい戸籍であり、新字体で掲載されることはよくあるのだ。
なんとなく「ウザい」から来ていそうな苗字ではあるが、山口県にはそのまま「有財」と書いて「うざい」と読む苗字も存在する。加えて仏教由来では「有財餓鬼」(うざいがき)という四字熟語もあり、そのなんとも現代的な語感から『トリビアの泉』で紹介されたこともある。


浅黄
約120世帯・510人
読み:あさぎ、あさおなど

山形県に集中する。
発祥は現在の京都府福知山市三和町で、かつてここに浅木山城なる城があり、そこの城主が現在の山形県西村山郡河北町に関わりを持ったとされる。
いつ頃「木」から「黄」に転じたかは不明だが、単純に「浅木」からの異形とも考えられるだろう。
「浅黄色」とは文字通り薄い黄色のことを指す一方で、「浅葱色」と同一視されることもある。よく「新選組の羽織の色」とも言われるこの色は薄い藍色がベースであり黄色とは全く関係がない。よって後者を指す場合の「浅黄」は単に当て字なそうだが、それにしても紛らわしいとは思わなかったのだろうか?

伊草
約100世帯・530人
読み:いぐさ

埼玉県や神奈川県などの関東一円に多い苗字。現在の埼玉県比企郡にあった伊草郷が由来とされる。
ハルカの趣味が雑草栽培ということで、畳の原料に使われるイグサともかけているのではないかとも考えられる。イグサは漢字では「藺」と書くのだが、この字にまつわる苗字の話をひとつ。
鹿児島県に集中する「藺牟田(いむた)」という苗字がある。同県の薩摩川内市発祥の苗字で200世帯ほどいるのだが、どうも「藺」という字に馴染みがないためか、2000年頃の電話帳ではこれが十数件ほど「蘭」と誤登録されてしまい、「蘭牟田」という形で登録されてしまっていたことがある。
結果として「蘭牟田」は実体のない苗字として独り歩きしてしまった。
このようなケースの他にも電話帳では芸名や店名などを住所として登録しているため、実際には存在しないはずの苗字があたかも実在するようにネット上で語られることがある。先程「羽川」の項目でも触れたが、このような苗字を「幽霊苗字」という。よって希少苗字を探る際、我々はまず実態を掴むことから始めなければならない。
このことについては後々の記事でも触れるであろう。


さて、ここまでで段々と耳慣れない苗字も増えて来ただろうが、驚くべきことにまだ半分も経過していない。相対的に有名人の数も減ってくるのでそれに託けた話もできず、そろそろ書けるネタも減ってくる気がするが今後に期待して頂けると幸いだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
