
"選択の自由"はどうやったら手に入るのか。
今から3年前、2018年に株式会社TOMAPを立ち上げ、"すべての人に選択の自由を"というミッションを掲げました。
TOMAPを立ち上げると同時にプログラミングスクールZeroPlusも立ち上げたのですが、今思い返すとこのミッションへの解像度は全然低かったように思います。
「教育を通して選択肢を与えられたらいいな〜」となんとなく思っていた僕が、改めて最近考えた"選択の自由"という言葉の定義についてお話しします。ただ、これからも僕は成長するので、また3年後は別のことを想っているかもしれません。
この記事は僕の周りにいる人々へのメッセージでもあり、3年後の自分に向けたログポースでもあります。
そもそもなぜこのミッションを創ったのか。
ミッションの言葉を作ったのは僕ですが、これは創業メンバーの共通した想いでもありました。
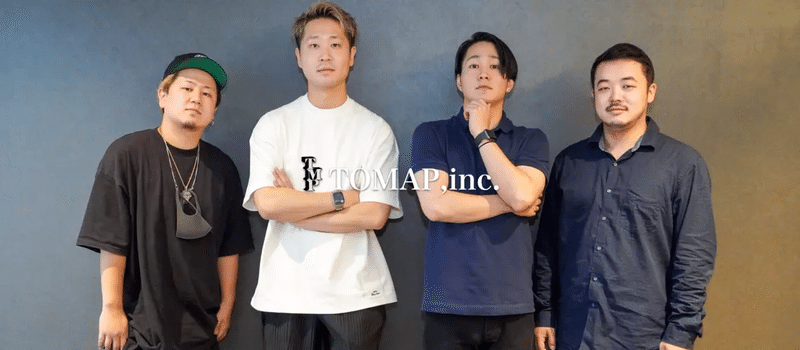
僕はそもそも日本で高校で挫折し、留年し、退学し。その時点で選択肢はすべて潰えたものと思っていました。実際に留年&退学を高校の段階でかましてみるとわかりますが、親先生友達から「もうまともな就職もできないし、人生終わったよ。」って言われるんです。情報源が周りの人しかない高校生の僕は「あ、そうなんだ。」って思ってました。絶望というよりは虚無ですかね。
でもそこから親が勧めてくれて海外に行かせてもらい、なんやかんや大学も行き、大学生の頃に今の会社を立ち上げています。やっぱり転換期は海外でまったく異なる価値観に触れたことです。「みんな家買うための貯金とかしてんの?」って純粋だった僕が聞いた時、みんなに笑われました。「家買う金あるなら大○麻買うぜ!」って。褒められたことではないかもしれませんが、僕の小さな世界はそこで崩れました。いい高校に入り、いい大学に進学し、いい企業に入ってお金をもらい、家や車を買って家族を持つ。それが成功であり正解。そんな価値観を押し付けられてきた一方で、世界にはそんなアホがたくさんいる。肩の力が抜けました。「あ、別に価値観があるところにいればいいんだ。」衝撃でした。
その価値観は今でも僕のルーツとなり、ZeroPlusを大きくする原動力となっています。
そんな背景を持った僕と、状況は違えど同じように選択肢を持っていなかったけど道を切り拓いた人たち。創業メンバーで語り合い、代表の想いを聞き、僕から自然と「すべての人に選択の自由を」この言葉が出てきました。
"選択の自由"の公式を発見しました。
発見しました。とか言ってるけど割と早い段階で気づいてはいました。でも改めて言葉にした時、自分の中での納得度が200%になったので語ります。
選択の自由=選択肢の数×主体性
こう書くとそれっぽいですね。解説します。
まず、そもそもの選択肢がなければ高校の時の僕と同じように、目の前の壁を見上げるしかありません。大前提、選択肢の数はいくつか持つ必要があります。選択肢については、「自分ができること」の幅が大きな要因となります。僕たちがやっているプログラミング教育も、テクニカルスキルを身につけることで、選択できる職種を増やします。これは簡単な話です。
問題は主体性。「自分の考えや判断をもとに行動する性質」と辞書にはあります。
いくら目の前に選択肢があったとしても、「選ぶ」という行為をしないと意味がありませんよね。ましてや人の命令や指示に従って選んだ道に"自由"はあるでしょうか。
選択肢を増やし、自分の考えや判断に基づいて選んでいく。これこそが選択の自由と僕は考えています。
プログラミングだろうがなんだろうが、教育事業をやっている以上。僕はスキルだけでなく、"主体性"も育めるような本質的な教育を届けていきます。約束します。
"主体性"ないかも...という人へ。
よく「日本人は主体性に欠ける」と言われます。実際に自分の行動に紐づいている自分の考えや判断に自信を持てない人もいるのではないでしょうか。
大丈夫です。ただの経験不足です。「自分の考えや判断」というのは、繰り返すことによってだんだん固まってきます。
目の前に女の子が2人いたとして、どっちと付き合うか。ただし相手の顔や性格などは何もわからず、"女性"という性別だけがわかっている。
判断のしようがないですよね。よくわからない例でした。
自信を持てないみなさんはこの状態です。だから情報を得て、それを理解し、自分の意見を持つ。これを繰り返していくことでしか、思考力や判断力は身につきません。
じゃあ今どうしたらいいの!?って思った人。今は自分の欲望に問いかけてみましょう。自分に対して「君はどうしたいの?」って常に問いかけてあげてください。欲望というエネルギーを使って進み、たくさんの成功や失敗を繰り返すことで"主体性"は育まれていきます。
もう疲れたのでこの辺で終わりますが、この記事を読んで少しでも共感してくれたら嬉しいです。あと最後に言い訳すると、これを書いている今はZeroPlusの卒業生の人と「30分で記事書くわ」って約束して時間ギリギリなので駆け足です。以上。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
