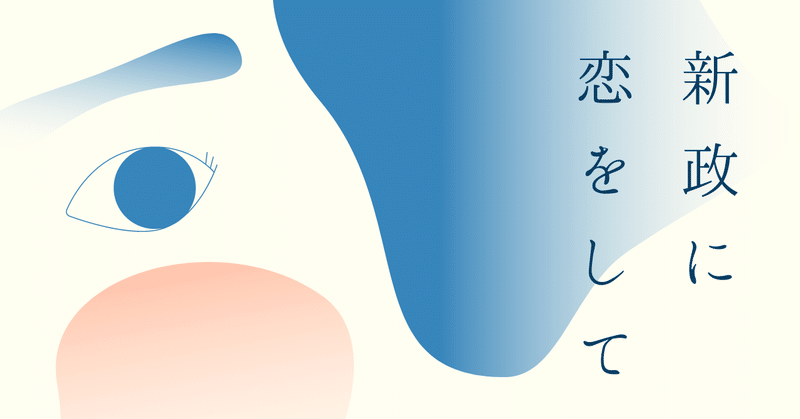
新政に恋をして
第一章「新政との出逢い」
僕が新政と出逢ったのは、ちょうど君に出逢った冬の頃だったと思う。その年の秋、ちょうど僕が26歳になる誕生日。札幌で僕が好きなアーティストのライブがあった。そして、君と出逢った。
君は可愛らしいお洋服に身を包み、もうすぐ冬になるというのに、半袖と短いスカート、軽いジャケットを羽織って、旭川から札幌のライブに来ていた。
ライブの後の高揚感もあり、知り合って直ぐにご飯に行った。その時はライブの余韻に浸っていた。すぐに連絡を取り合う仲になり、何回かデートを重ね、クリスマスを過ぎた寒空の夜、僕らは抱き合った。好きなバンドのヴォーカルの誕生日だった。
君は旭川の大学に通っていて、近くには有名な酒屋があった。僕が日本酒好きだったこともあり、ふたりでよく通ったよね。その時ふと目についたのが『新政』だった。僕の地元が東北だったこともあり、秋田のお酒ということで目を引いた。しかも当時、東大出身の新代の若手酒造経営者として多くの雑誌で紹介されていたのが、現8代目蔵元社長「佐藤祐輔」さんだった。
第二章「合言葉としての新政」
気がつけば、君に会いに旭川に来て、君の大学の近くの酒屋で新政を買って帰るのが月に一度の楽しみになっていた。No.6(R-type, S-type, X-type)、Colors(エクリュ、ラピス、ヴィリジアン、コスモス)、亜麻猫……全てが魅力的だった。新政を開栓する時はいつも君がいて、場所は君と初めて出逢った居酒屋だった。その居酒屋は日本酒の未開封提供に拘っており、未開封品に限り持ち込みが許されていた。封切りの日本酒がどれだけ美味しいか、そこで身をもって味わった。純米吟醸や純米大吟醸では、きちんと脱気処理をしないとものの2, 3時間で味が落ちる。特に新政の封切りは格別であった。周りが吟醸香で満たされる。新政を手にその居酒屋を訪れるのは至福の喜びだった。「新政」は、君との合言葉になっていたかもしれない。
君は覚えているかい? 君と付き合って2年目のクリスマス、滅多に手に入らない新政の秋桜(中取り)と天鷲絨(中取り)を手に、小樽のホテルに泊まった。露天風呂の一等客室。新政を味わうのにまさに適した部屋だった。フレンチのフルコースを堪能し、君と部屋でゆっくり新政を楽しんだ。クリスマスカラーの新政に心が弾んだ。あの夜は最高の時間が流れていた。
第三章「突然の別れ」
すあんなにも楽しくふたりの時間が流れていたのに、君はどうして僕の前から姿を消してしまったのだ? 君がいなくなってから、僕は借金に溺れ、ろくに新政も買えなくなっていた。自殺未遂もした。でも死ねなかった。もう旭川に通うこともなくなっていた。毎日昼に起きてボーッと一日を過ごし、ゲームをするか寝るかの生活。失業保険で生活費を賄い、もうかれこれ1年が経とうとしていた。
そんなある日、ある一通の封書が僕の元に届いた。差出人は書かれていなかったが、僕には分かった。君の字だと。心の底から待ち望んでいた、君の言葉だと。
「元気にしていますか? 純をひとりにしてごめんね。でももう耐えられなかったの。ごめんね」
その手紙で彼女は何度も謝っていた。僕を残しひとり死んでしまったこと。
あの時の彼女は仕事を初めて1年目で、心身ともに疲弊していた。なんとかしたいと思ってはいて寄り添ってはいたが、ある日突然、彼女は自らの意思で命を絶ったのだった。
僕はすぐさま荷物をまとめて、お昼過ぎの旭川行きの特急に乗り込んだ。旭川駅前から医大行きのバスに乗る。医大の手前で降りて、彼女の下宿先に顔を出す。彼女の部屋はまだそのままあった。下宿先のおばさんも中々片付けられないのだという。
僕は久しぶりに彼女とよく行った酒屋も覗いてみることにした。相変わらず多くの人で賑わい、人の出入りが絶えなかった。新政もあった。だが、買う気にはならなかった。
旭川に長居はせず、夕方の特急で札幌に帰ることにした。仕事、探そうかな。
第四章「新たな門出」
旭川に行ったことで、僕の中でひとつの踏ん切りがつき、彼女のことは胸の内にしまいながら、ちゃんと前を向いて歩こうと思った。彼女の分まで、僕が生きようと。
そして、僕は就労支援の仕事についた。障がい者と一緒に作業をし、社会的な自立をサポートする仕事だ。社会的に生きづらさを抱えた人達が、少しでも毎日を楽しく充実して送れるように。そのサポートがしたいと思った。
新しい仕事を始めて1ヶ月が経とうとしているある日の休日、僕の元に小包が届いた。差出人の名前を見て、僕は涙が止まらなくなった。紛れもない、君の名前だった。中身を開けてみると、僕が見たこともないラベルの新政が入っていた。
「わたしのイラストがラベルになったんだよ! 凄いでしょ! 褒めて褒めて」
僕はぎゅっと胸に新政のボトルを抱き抱えた。
こんな嬉しいサプライズがあるかよ。
その日、僕はその新政を彼女と通った居酒屋に持ち込むことにした。居酒屋のアニキも泣いてくれた。笑ってくれた。「良かったな」と肩を叩いてくれた。サプライズが好きだった君が僕に残してくれた大きな贈り物。新政は、僕のアイデンティティになった。
彼女の命日には、必ずいつもの居酒屋で新政を持ち込んで飲むことにしている。
やっぱり、封切りの新政は格別だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
