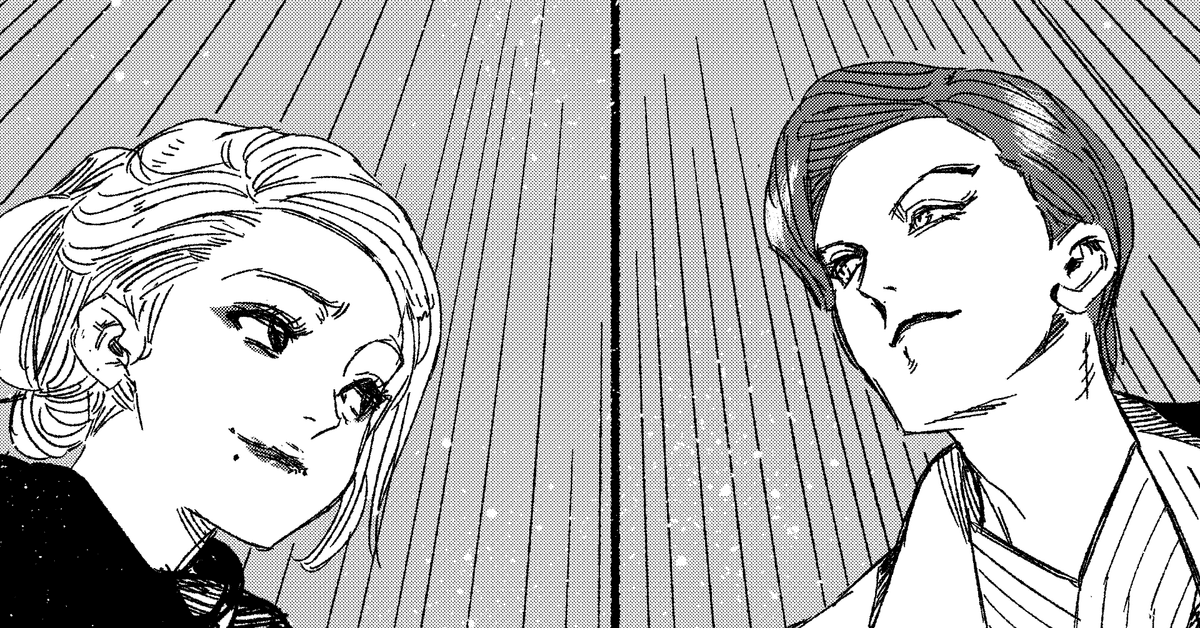
十和田シン ジャックジャンヌ1周年記念小説【ハッピー・アニバーサリー 後編】
ジャックジャンヌ1周年を記念したアニバーサリー小説、後編!! オニキス、ロードナイト、クォーツの3クラス、とまどい、衝突しながらも公演へ向けて進んでいく。ふだんは交わらないメンバーたちの姿はファン必見です!!
十和田シン
ノベライズ作家、シナリオライター。別名義である十和田眞の名前で『恋愛台風』を執筆、小説デビュー。『NARUTO』『東京喰種』シリーズの小説を担当、ADV『ジャックジャンヌ』シナリオを石田スイ氏と執筆。また、奥十の名前で漫画家として活動する。コミックス『マツ係長は女オタ』発売中。
【7】
ユニヴェールという場所は三百六十五日全てが記憶に残っていくのかもしれない。
「……」
クォーツの稽古場で、希佐は台本を見つめていた。
町名決定に無関心な議長。それに、強い違和感がある。
「おっつかれい、立花くん! ご機嫌いかがかな」
「あっ……根地先輩」
「どうだい、議長のご様子は」
希佐は台本を閉じる。
「自分なりにイメージしてたんですけど……うまく掴めなくて。昨日の出来事を見て、一層わからなくなりました」
根地はうんうんと頷く。
「織巻くんが時折見せる火の玉剛球ストレートの威力たるや。それを言われちゃおしめぇよってな! フミや組長たちが発言しづらい中、よく言ったもんだよ」
「発言しづらい?」
根地が大袈裟に両手を広げる。
「だって! このメンツが方針決めちゃったら、納得感すごすぎてみんな従っちゃうでしょ? 例えばおフミさんに『お前ら、玉阪を祝う気持ちがねーぞ』なんて言われたら『はいそうですね僕が悪かったですごめんなさいわっかりましたぁ!』じゃない」
それこそ、発言した瞬間に解決しそうな威力がある。
「でもそれって、ユニヴェールの『自主性』からかけ離れちゃうと思うのよねぇ。強い人に依存して、考える機会が奪われるというかさ。だから、織巻くんみたいに……言葉は悪いけど、良くも悪くも舐めてかかれる人が言った方が、自分の気持ちを無視することなくその現実と向き合える気がするのよ。『俺もそう思う』『僕はそう思わない』って感じでさ。まぁ、僕は織巻くんのこと舐めないけどね。美味しくなさそうだし!」
「思考が活性化しやすい、ってことですか?」
「僕のジョークも聞いて? でもまぁ、そういうことよ。しっかり賛も否も出る。んで、否定肯定どんと来いなぶん、まだまだ一つにまとまる力はない。やっぱそう簡単な問題じゃないからね。人が沢山集まる場所になるとなおさらよ」
三クラスが玉阪の日を祝うために一致団結する、その目標はまだ遠いのか。
「なにか……できないんでしょうか」
希佐は台本を見つめる。今回、希佐はなにかにつけて蚊帳の外だ。議長と想いは重ならないのに、議長と同じように、みんなの輪から隔絶された存在になっている。それがもどかしい。自分もこの舞台のためにできることがないのだろうか。
「否定肯定の渦の中、立花くんのように思ってる人は他にもいるだろうね。たとえば……海堂」
「海堂先輩が?」
「ん。発言しづらい立場とはいえ、それこそ海堂は今回織巻くんがいる開組のリーダー。そこから出た意見を無下にはできない。海堂は僕より遥かにずっとしっかりしてるからね!」
そして、ニッと笑う。
「行ってみる? 開。玉阪には行ったんでしょ」
「え、いいんですか?」
「よいさぁ。夏公演とは真逆だね! あのときはオニキスとロードナイトの組長に引っ張り回されてたけど、今回は自ら足を向ける! ……それがきっと、役の『透明感』に繋がると思うよ」
――透明感。
配役発表のとき、根地から言われた言葉だ。
「行きたいです、開に」
根地がにっこり笑った。
「いってらっしゃいな」
希佐は根地に進められるまま、オニキスへと向かう。
「……あれ、海堂先輩?」
稽古場の前、遠くから見てもわかる凜とした佇まい。
「来たか、立花! 根地から話は聞いたぞ!」
「すみません、今日はよろしくお願いします!」
「ああ!」
そのまま、稽古場の中に入るつもりだったのだが、海堂が、「それでは行こう」と足を踏み出した方角は稽古場とは真逆。
「えっ、あの、海堂先輩?」
稽古場を振り返りながら尋ねるが、彼の歩みは止まらない。どんどん学外へと進んでいく。
「開を見たいのだろう?」
頷く希佐に海堂は自身の胸を叩いた。
「だったら俺を信じて着いてくると良い!」
海堂の力強い言葉には有無を言わせぬ迫力がある。
(そういえば……)
タイプは違うが、フミにもこういう所がある。どんな状況でも彼が一言発するだけで全てストンと入り込んで、納得してしまうことが。
(だからこそ、発言することに慎重になるのかな……)
敏感で聡いこの人たちは、浮き上がる問題の形も、正しい解決法もわかっていながら、黙っていなければいけないことが多いのだろうか。
それは――息苦しくないのだろうか。
「立花!」
「あ、は、はい!」
気づけば階段を下り、校門前に辿り着いていた。
「……えっ」
待機していたのは、いかにも高そうな黒塗りの車。
素早く運転手が現れ、ドアを開く。
「あ、あの……?」
これは一体。
「では行こう!」
説明不充分で混乱しているが、信じろと言われたのだ。希佐は意を決して車に乗り込んだ。
「……見えるか、あそこが多嘉良川だ!」
坂を下り、町を抜け、車で数十分ほど走ったところで、視界の先に川が見えてきた。
「えっ、多嘉良川って、リンが魚を釣って食べた……?」
「そうだ! 大伊達山を水源とし、玉阪と開を隔てる川でもある!」
川のこちらが玉阪で、渡った先が開。
希佐はようやく、自分が『開の町』に向かっていることを知る。
根地はもともとそのつもりで、でも悪戯心も含めて希佐を送り出していたのだろう。
車が多嘉良川に架かる橋を渡る。
「多嘉良川は砂金がとれたことでも有名だ」
「えっ、砂金!? あ……もしかして多嘉良川って、宝の川という意味ですか?」
「聡いな。他にも色々意味があるそうだが、一番はそれだ。さぁ、開に入ったぞ」
川を越えると、町の景色が急激に変わっていく。
「都市だ……」
古い歴史を感じさせる玉阪にはないビルの数々が開という町にはあった。
「よし、ここで降りよう」
車が止まったのはビジネス街の中心にある近代的な駅のターミナル。
そこには大きく「玉阪市駅」と書かれている。
そういえば、ワークショップでアキカが、「玉阪市駅」についても話していた。
「玉阪市の政治機能は全て『開』に揃っていると、モナ・スタースクールでモナさんたちから教えてもらったことがありました」
「そう! 向こうに市役所! すぐ近くに警察署! 公園向こうには裁判所や大学病院、他には博物館や美術館、水族館といった文化施設もある!」
「海が近いんですか?」
「開のすぐ隣が絢浜市だからな!」
少し前、夏合宿で宿泊した海堂グループ所有の『ヴィルチッタ絢浜』がある絢浜市だ。
「開にはビジネス街もある! うちの関連会社も入っているぞ!」
希佐にとっては海堂はオニキスの組長だが、彼には海堂グループの御曹司という側面もある。いや、本来はそれが正面なのだろうか。
「開は玉阪と見た目から全然違うんですね」
「玉阪は歴史的景観の保全に注力しているからな! その分、開が都市機能の発展を請け負っている部分がある」
だからこんなに都会なのか。
希佐は背後にある駅を改めてみる。一点、気になることがあった。
「駅の名前……『開』ではないんですね。あ……!」
それが、玉阪と名前を争い負けた結果なのだろうか。
しかし海堂はすぐ否定する。
「ここは開だが、かつての武士の町『開』はもうひとつ向こう側だ。では行こう!」
「えっ、あ、はい」
海堂は車ではなく徒歩で、線路沿いの通りを進んだ。
「あれ……」
すると急に、景色がひらける。
「あっ」
四方をビルに囲まれた高台に、立派な城が建っているのが見えた。
「あれが、開の城だ」
城が近づくにつれ、街並みも徐々に変わってくる。
曲がりくねった道、長い石積みの塀、漆喰の蔵、美しい寺院、そして古い武家屋敷。
これが、開。武士の町。
「ああ、ここだ」
海堂が立ち止まったのはそんな町の一角。青々とした大きなもみじの木がある武家屋敷だった。一般公開されているようだ。
入り口には、住所が書かれた細長い町名板がある。
『玉阪市開』と記されている。
海堂はそれをしっかり見てから中に入った。
「これ……資料館になっているんですね」
いくつもの部屋が連なるこの家には、開の武士にまつわる資料が多く置かれている。
当然のように彼らが仕えた藩主の名も。
「この……江戸中期の開松原(ひらきまつばら)という人が、比女彦に玉阪の土地を与えた人物だ」
「……! この人が……」
『玉阪町』の説明で聞いてはいたが、こうやって開の町で見る彼の名は重みが違う。
「相当なやり手だったそうでな。彼の時代、開は大いに栄えたらしい。玉阪座も松原公の功績の一つだからな。だが……時代は移り変わる」
奥に進むと、着物姿と洋服姿の男が入り交じったモノクロ写真が展示されていた。
「これは開の武士たちだ。正式には士族か。俺たちが演じている人たちも、ここにいる」
「えっ!」
希佐は驚いて写真を見る。
「真ん中にいるのが新田氏……俺が演じている人だ。こっちは初花氏で加斎。これが楢柴(ならしば)氏……カイ。ちなみに、織巻が演じている人物……彼だけ下の名前だな。琳(りん)氏はこの写真に写っていない。写真を撮る日に寝坊したそうだ」
「えっ!」
「この家の主が手記にそう書き残している」
大事な日に寝坊、どこかで聞いたことがある話だ。
根地もその話を知っていて、わざと重ねたのだろうか。
希佐は改めて写真を見る。
生身の人間、実在の人物。
(私たちは……過去に起きた現実を演じているんだ……)
考えてみると、史実を元にした舞台は初めてだ。
それが、ずしりと肩に乗る。
「俺には開関係の知り合いがいる」
「えっ……」
「この町に縁がある人だ。その人のことを思うと、どうしても凜々しく、雄々しく、演じたくなった。今もそうだ。玉阪と同じように、開も人々に愛されている場所だからな」
ただ、と海堂は言う。
「その気持ちだけではだめだと気づかされた。あの赤髪にな」
スズのことだ。
「自分の気持ちにウソをついたり、顔を背けたりはしない。ただ、同じように玉阪を祝う気持ちを持たなければいけない。その上で、開組の演出について色々と考えたかった。だから今日、ここにきた」
「そうだったんですね……。あの、ご一緒してもよかったんでしょうか? 同じ舞台とはいえ私が演じる役は開とは関係のない立場なのに……」
開を想う大事な時間に、自分がいては邪魔なのではないだろうか。
「……」
海堂はもう一度、古い写真を見る。
「立花」
「はい?」
「知っているか? お前が演じている議長もまた、開の武士だ」
「……。えっ!」
驚いて海堂を見上げる。
「彼も新田と同じように開出身の政治家で、士族。そんな彼が町名検討議会で議長を任されたんだ」
驚きに胸が打ち鳴る。
「すみません、私、全く知りませんでした……」
「知らないことを正直に知らないと言えるのは良いことだ。そもそも根地も、歴史をなぞってはいるが、歴史色を強くしたかったわけではないだろう。根地が追っているのはあくまで歌劇としての面白さ。根地のそういう舞台感覚がねじれを生むこともあるのだが……今、その話はいい」
海堂がゆっくりと縁側に向かう。
「立花、議長はな……玉阪側から多額の賄賂を受けとっていたんだ」
「えっ……!!」
体が大きく跳ねた。感情の見えない無関心な男に、突然混ざった錆色。
(まさか、その結果が玉阪市……!?)
開の人間でありながら、開の人間を裏切ったのか。
動揺に、汗が滲む。
「いや待て!」
「えっ」
しかし、海堂が急に制止してくる。
「立花。実際は、議長が開と繋がり、玉阪側の人間たちを陥れる計画を練っていたんだ」
「えっ!?」
さっきと真逆じゃないか。
議長像に墨がぶちまけられる。
もはや輪郭さえわからない。
ところが、そんな希佐を見て、海堂が「ははははは!」と大きく笑った。
「か、海堂先輩……?」
「いや、すまない! 悪いことをした。立花、この二つは当時実際に立った噂なんだ」
「えっ、じゃあ、嘘、ということですか? それとも、本当?」
「さぁ、それはどうだろうな」
海堂は含みを持たせる。
希佐はハッとし、背筋を伸ばした。
ここは、ユニヴェール。
「調べてみます」
自主性が重んじられる場所。それはきっと、人が成長するうえで、大事なことだから。
議長がわからないと思っていた。だけどそれは、自分がもっと深く彼を知ろうとしなかっただけ。
海堂が深く頷く。
「……ん?」
そこで海堂の携帯が鳴った。
「……菅知か。よし、立花。そろそろ帰るとしよう!」
この場でも、自主性が彼らを突き動かしていた。
「……さてさて、どうしましょうかネェ、玉阪の日」
海堂不在のオニキス稽古場。開組の生徒たちは、オニキス、クォーツが入り交じり、顔をつき合わせ、話し合っていた。
「……正直、今回の舞台、気が乗らない部分があった。あまりにも玉阪優位に描かれていないか?」
登一が複雑な表情を浮かべる。オニキス生もそれに同調する。
「玉阪が名を勝ち取る話だ。優位に描かれるのも当然だろう」
だが、鳳はスパンと言い放つ。
「オニキスは自分たちの感情を優先しすぎている。舞台以上にな」
鳳のもの言いに、登一の眉間のしわが深くなった。
「それを言うならクォーツのジャックは消極的すぎないか? 大事なところで後ろに引いている印象がある。舞台から遠のいているように見える」
鳳が「違う」と否定する。
「前に出過ぎることで舞台が壊れることだってある。繰り返すが、これは玉阪が名前を勝ちとる物語だ。なのにオニキスは前に出すぎている。もっと俯瞰的に舞台を見るべきだ。玉阪を立てるべきだ」
登一が「うっ」と言葉に詰まった。
今度はダンテが「ン~、でも」と発言する。
「それじゃあ開と玉阪の対立軸が崩れませんかネェ? 対等であってこそ引き立つ関係だと思いますヨ。立てられなければ負けるのであれば、それは玉阪側の問題じゃないデスか?」
「いや、それは……」
「そもそもあちらには、麗しの花たちが揃っているんですヨ? 高科先輩が立てられなければ負けるとでも?」
ダンテは言葉巧みだ。
「そんなことは言っていない!」
「ですよネ。じゃあもう一度考えてみてください。開が前に出ず、この舞台が成り立つのかどうか」
今度は鳳が押され始める。
そこで、スズがすっくと立ち上がった。
「おい、ダンテ! 言い負かすことだけ考えてんだろ! 祝う気持ち感じねーぞ!」
スズの指摘に加斎が吹き出す。
「はい、アウト。玉阪祝いたい警察来たよ、ダンテ」
「ア~、スズはとっても厳しいネ~」
「でもさ、織巻。ダンテの言ってること、俺は間違ってると思わないよ。だってさ……」
そんな白熱する議論を、少し離れた場所で見ている人物がいた。
カイと菅知だ。
二人は自分たちの発言の重さを考慮したうえで距離をとっている。無言のままずっと。
それは、答えが出るまで続くのだろうとカイは思っていた。
「……睦実先輩」
そんな中、菅知が口を開いた。
「ん、ああ?」
「今回の合同公演、どう思ってます?」
「今回の? 俺は……」
すぐに答えられなかった。今となっては、『合同公演』という言葉が指し示す範囲は広い。
一言でこう、と言うのが難しいほどに。
「……俺は、ずっと思ってるんですよ」
だが、菅知はそうではないらしい。
「海堂さんと高科先輩が組むと聞いて、そこは俺の場所やぞって」
「……!」
最初も最初、始まりの場所。
「今回の舞台決まったときから、ずっと思ってるんです。合同って時点で、二人が組むのは想像できましたからね」
カイの意識はスタート地点に戻される。合同公演が決まったあの日。
そして、配役発表があった瞬間。
「確かに華のある二人が組めば見栄えはええですよ。でも……海堂さんを一番輝かせることができるのは俺や。高科先輩相手でも負けん。俺や、俺やぞって」
一見、感情の起伏が乏しいクールな彼だが、その胸には、熱い闘志を秘めている。
(フミと、海堂……)
彼らがこうやって組むのは、実は初めてではない。
立花継希と組んでいたときも、立花継希がいなくなった頃も、そしてカイというパートナーがいる今も、76期が集まれば、フミはいつも海堂と組む。
海堂は、大きく変化するフミをものともせず、王者の風格でフミの隣に立っていた。
彼はフミを楽しんでいたし、フミもそうだったのではないかと思う。
そんな二人を見て、カイはずっと思っていた。
――似合う、と。
過去を思い出すと、無力が近づく。
(いや、ダメだ)
カイはふつふつとこみ上げそうになった感情を抑える。
学んだから。夏公演で。
器でしかない自分が、器にもなれる自分に変わった。
そこになんの差がと思う人もいるのだろう。
選べるようになったのだ。
自らの意志で、望んで器ができるようになったのだ。
カイのために器になってくれた希佐のおかげで。
だから、過去の自分の弱さで、今の変えてもらった自分を傷つけたくない。
そのためには――“正直”が必要なのかもしれない。
「……今回の舞台については、祝いたいと思っている。織巻と一緒だ。ただ……」
カイは自嘲の笑みを浮かべた。
「少し悩んでいた。パートナーのこともだし、あとは、クォーツのジャックであるということ」
カイはぽつりぽつりと話しだす。それが菅知への礼儀のような気もしていた。
「クォーツのジャックは、ジャンヌの器として動くことが多い。極めてユニヴェール的だ」
そう、ユニヴェールにおいてジャンヌは華。その華を生かすために動くのがジャック。それが通例。
ジャックを主役に立てるオニキスは、むしろ特殊なのだ。
ただ、その特殊さに照らされると、自分たちの形を知ってしまう。
「華としての魅せ方を熟知しているジャックたちと並んで、レベル差のようなものを感じた。クラス色が違うと言えばそれまでだが……オニキスのジャックは、強い」
そしてカイは思ったのだ。
自分に華のあるジャックを育成できるのか、と。
いや。
自分に、織巻寿々を育てられるのかと。
その透明性が故に、なにものにでも美しく染まる希佐とは真逆。
スズは決して染まらない織巻寿々という名の原色。
オニキス生相手にどんなに拙くても決して劣ることなく張り合うスズを見て、その想いを一層強くした。
クォーツのジャックエースが、華のある人間であれば――立花継希のような人であれば、スズはもっと成長できたのではないかと。
今のクラスの形が、器という立場の自分が、彼の成長を阻害しているのではないかと。
「……睦実先輩」
そこで、菅知が口を開く。
「でもあなたは夏公演で銀をとったやないですか」
「……!」
個人賞のことだ。
カイにとっては、多くの助けによって手に入れた結果。花が咲いた瞬間。
しかし、オニキス――菅知にとってはどうだ。
つねにフミを追い、銀をとり続けていた海堂の陥落。
もしかすると、海堂以上に、菅知がその事実を重く受けとめているのかもしれない。
海堂の器として、彼を輝かせることに心血を注ぎ続けている彼だからこそ。
彼が器として海堂の隣に立っている時間は、カイがフミの隣に立っている時間よりも、長いのだ。
「俺、もう一個思ってることがあるんです」
こんなときでも彼はペースを崩さない。
「睦実先輩の言葉って、本当に睦実先輩の言葉でしょうか」
「どういう……ことだ?」
「睦実先輩の言葉、根地先輩を感じることがあります」
「……!」
思いがけない言葉だった。
だが胸を刺された気持ちにもなった。
心当たりが、ある。
菅知は脇にはさんでいた台本をパラパラとめくる。
「睦実先輩は、根地先輩が脚本に込めた意味を読み解き、かみ砕き、わかりやすくして、俺らに伝える代弁者のように見えることがあるんです。そこに、睦実先輩の意志はあるんでしょうか?」
「俺の……」
「海堂さんは、そこに引っかかってるんですよ。だから頷かない」
でも、と菅知は言う。
「睦実先輩の『声』なら聞くはずです」
菅知の声は優しかった。
菅知が台本を閉じ、目を細める。
「この舞台、海堂さんの本当の隣は、高科先輩やなくて睦実先輩なんじゃないんですか?」
「菅知……」
「見せてくれませんかね、睦実先輩の“銀”を。祝わないかんのですから、『玉阪の日』を」
これがオニキスのアルジャンヌだ。
器としての自分を誇り、ぶれることなく戦い続けるアルジャンヌ。
「……。菅知」
「はい」
「海堂を呼んでもらえないか?」
菅知が口角を上げる。
「そろそろ戻ってくるんやないですかね。少し前に連絡入れときました」
菅知がそう言うのとほぼ同時だった。
「戻ったぞ!」
海堂がオニキスに帰還した。
「さぁ、どうなっている!」
確認のため、菅知に問う。そこでカイが一歩前に出た。
「……どうしたカイ」
なにか感じたのか、海堂がカイに向き直る。
「舞台について、提案をしたい」
「……ほう。聞こう」
海堂とカイの対面に、討論していた開の生徒たちが慌ててそちらを見る。
「カイさん……」
「……」
スズと、鳳もだ。
そうだ、自信を持たなくてはとカイは思う。
自分のためにも、後輩のためにも、クォーツのためにも。
「お前を華、俺を器として動きたい」
カイが最初にやって海堂に否定された案だ。
「それは、なぜ?」
「最もふさわしいからだ。もう一度ためさせてくれ」
「……」
カイが真っ直ぐ海堂を見る。海堂は頷いた。
「……みんな、準備してくれ!」
生徒たちが一斉に立ち上がった。
「『……このまま名を奪われるというのか』」
海堂演じる新田が歯がみする。
比女彦ら、玉阪座の役者らの働きにより、もはや「玉阪」は新時代の代名詞となっていた。
「『新田……お前はじゅうぶんやったよ、だから、少し休んでくれ』」
やつれ追い詰められる新田を、カイ演じるナラシバが諫めようとする。
「『……いや、だめだ! 比女彦に会ってくる』」
「『開の政治家が自ら比女彦を尋ねるというのか……! お前がそんなことする必要などない、もういい、時代が悪かったんだ、時代が……!』」
「『俺は諦めない! 開のためならなんでもする……なんでもだ!』」
衝突する二人。
それを見ながら、多くの生徒が頷いた。
武士としての強さを持つが故の哀しさは全て海堂の新田に、時代に翻弄されながらも受け入れようとする弱さ故の強さはナラシバに。
華として立つのは海堂だが、器のカイの存在感もたしかにある。
あとに続く展開なども考えれば、この関係性は非常に効果的でもあった。
なにより、凹凸が重なり合うような二人の関係が美しかった。
「……最初に伝えたいことがある」
芝居を終え、カイが改めて海堂を見る。
「この台本が、コクトが、俺に『器』になれと言っているのは確かだ。だが……俺自身もそう思っていた。今回の舞台、海堂の器として動きたいと」
「!」
海堂が驚き目を開く。
「俺はコクトの舞台が好きで……コクトの作ろうとしているものを一緒に見たい、一緒に作りたいという気持ちがある。だから、コクトの言葉をそのまま借りて語ってしまうところがあった。だが、これは俺の意志なんだ。俺自身が納得しているからこそ、こうやって動いているんだ」
カイは「覚えているか、海堂」と、問う。
「同期の訪問公演、ジャックエースとして前に出るお前の後ろで、俺は名もない背景だった。だが、コクトがクォーツに来て、俺がジャックエースに選ばれ、器になって……今こうやって、舞台の上、お前と並び、語らうことができる。それは、俺にとってこのうえなく幸福なことなんだ。だからこそ、自分の力を生かしたい。器として研鑽してきたこの力を使いたい」
「……」
「正直、お前相手だと、華をやるより器をやる方が難しい。お前には、いつもパーフェクトをたたき出すパートナーがいるからな。そいつとの戦いでもある」
菅知がわずかに顔を上げ、そしてまた戻した。
「だから海堂、認めてくれないか。お前が華で、俺が器だ」
恐らく。
海堂と同じ舞台で演じられるのはこれが最後だ。
――76期生。
きっとフミと司の胸にも、同じ思いがある。
根地は――わからないが、それでも。
この舞台は、76期生にとってこれから迎える惜別の一つ。
自分たちは、卒業を控えた三年生なのだから。
「……」
海堂がスッと腕を組む。
答えは早かった。
「わかった!」
海堂の胸に感傷はなく、きっと誰よりも未来を見ている。
「優れたものを評価せずに繁栄はない! 今回は、お前が懸命に鍛えてきた器の力、感じさせてもらうぞ!」
海堂がカイの方へ手をさし出した。
「……ああ!」
その手を、しっかりと握る。
その瞬間、オニキス生も、クォーツ生も、全員、胸をなで下ろした。
「……だがいつかは華になれ」
「!!」
その声は、カイにだけ届く声量。
「お前にはその力がある」
固く握りしめられた手が、未練なく離れていった。
「なぁ、鳳!」
スズが誇らしげな顔でカイを見る。
「やっぱカイさんはすげーよな!」
鳳はふんっとそっぽを向いた。
これだからスズのことが嫌いなんだと何度でも思う。
このユニヴェールにおいて、鳳が一番仲がいいのは、この織巻寿々なのではないかと錯覚しそうになるから。
「お前のことは気に食わんが同感だ」
スズがニカッと笑う。
「おっしゃあ! はいはいはいはいはい!」
スズが大きく手を伸ばした。
「どうした、赤髪!」
「この勢いでもっかいダンスやりたいッス!」
「ははははは! よし、舞台の頭から、一気に通すぞ! 玉阪の誕生日を祝うためにな!」
【8】
蝉の鳴き声が、ピタリとやんだ。
「希佐ちゃ~ん!」
海堂と一緒に『開』に触れた翌日、午後。
玉阪座駅の改札口から、中学時代からの友人、茜あおが姿を見せた。
両手にはいかにも重そうなトートバッグを持っている。
「あお! こんなに用意してくれたの!?」
希佐がかけより、彼女の手からバッグをとった。
「資料になりそうな物、片っ端から持って来たよぉ!」
「わぁ、ごめんね! えっと、とりあえず喫茶店入ろうか!」
「うん!」
駅から歩いてすぐ、比女彦通りにある喫茶店。
「ほら、見て希佐ちゃん。これが『玉阪町の命名について』。こっちは『明治の大合併』。あとこれが『名前を失った開』……」
テーブルの上には分厚い歴史書が開かれていく。
海堂と別れたあと、希佐は玉阪について、そして自分が演じる議長について、調べることにした。
だが、こういった歴史を探る場合、どうやって進めていけばいいのか、いまいちわからない。だからあおに相談したのだ。
あおはそれこそのんびりおっとりしているが、ユニヴェール歌劇学校の舞台が見たいという夢を胸に、玉阪市の隣、絢浜市にある聖アガタ女子学院に合格した才女である。
入学してからというもの、いつも試験勉強で苦しんでいるが彼女は勉強ができるのだ。
あおは話を聞くなり、「あおも、手伝うよ!」と言ってくれた。
「私も記念式典見に行きたいけど、玉阪市に住んでないと応募できないんだよ~。残念だな~って思ってたから、こういう形で関われて嬉しい! 希佐ちゃんの役に立てるのはもっともっと嬉しい!」
「あお……本当にありがとう」
「えへへ。あ、そうだ、それでね、玉阪市の歴史……本によってビミョ~に内容が違うんだ」
希佐はあおが持って来てくれた本を読む。
「本当だ……。こっちは玉阪の役者の動きが多いね。こっちは開……」
「こういうのって書いた人の考えが色濃く出てたりするんだよ。だからなるべく色んな資料を集めて、考え方が偏らないようにしたほうがいいの」
あおはさらりと言っているが、それは本当に大事なことかもしれない。誰にだって確かな言い分があるのだから、どちらか一方に肩入れしたら、もう一方が見えなくなる。それこそ玉阪と開のように。
「それでね、この辺の資料を読んでもらったうえで希佐ちゃんに見せたいものがあるの」
「見せたいもの? わかった。じゃあ、まずは読むね」
「うん」
希佐が本を読み始めると、あおは黙ってそれを見守る。
そういえば中学のときも、こうやって二人、静かに時間を過ごすことがあった。
(……私が大変だったとき……あおはずっと側にいてくれたもんな……)
希佐の手を黙ってぎゅっと握ってくれたことだって。
そのときのことを思い出すと涙腺が緩むから、希佐は誤魔化すように息を吐いて、資料に集中する。
海堂が言っていたように、議長に対する様々な噂話も載っていて、それなのに実際はどうだったのかは書かれていない。
(この人は一体どういう人だったんだろう……)
調べれば調べるほど、わからなくなっていく。
あおが用意してくれた資料を全部読んでも、結局それは同じだった。
「ふー……」
成果が上げられなかった脱力感。
しかし、そこであおがバッグの中からファイルを取り出す。
「え、これって……」
見れば文献のコピー。
「持ち出し禁止の本だったからコピーしたんだ!」
「そうなの!? そんなにすごい本なんだ」
「うん。これね」
コピーの文面を、あおがなぞる。
「命名騒動のとき、議長をしていた人が書いた記録なんだよ」
「えっ!?」
喫茶店の中、思わず叫んで立ち上がった。みんなの視線が自分に向いて、希佐は慌てて腰を落とす。
「議長さんのご子孫がとりまとめたものみたい。おかげで文章もなんとか読めるよ。昔すぎるとあおもよくわからないから」
あおが「えーっとね」と読み始める。
「『町の命名に関して私が議長に指名された。私はここから、一切の交友を断つ。透明性を保つために』」
「え……」
最初から衝撃的だった。
(透明性……)
あおの言葉は続く。
「『玉阪の役者から面会の申し出。断る』『町で開の武士に会ったため、引き返す。しばらく町は歩かない』『玉阪の鶏笠焼きも、季節のいちじくも食べれず』『将棋の誘い。断る』」
あおから語られる彼は、人との交流を徹底的に避け、閉じこもっていた。町の名に関する自身の見解は一つもない。
「議長に選ばれてからずっと、こんな感じなんだ。ほらこれも。『今日は一人、将棋を指す。昨日もそうだし、明日もそうだろう』……」
いつもなら、正面に人がいるのだ。きっと開の仲間たちが。
あおは更に先を読む。
「『庭のもみじ』」
「え……」
その言葉に覚えがある。
「『庭のもみじ、未だ青く。早く町が赤く美しく色づけば良い』……」
風景が、思い浮かんでくる。
突然、予感がした。
「あお、議長さんは町の名前が決まったあとはなにか言ってる?」
「なにも。なんにも。今日はうどんを食べたとか、仲間が家に来たとか、仲間と昔撮った写真を見て、そのうちの一人が寝坊して映っていないことを笑い合ったとか……」
「……!!」
希佐は思わず口を押さえた。
脳裏に海堂の言葉が蘇る。
――琳氏はこの写真に写っていない。写真を撮る日に寝坊したそうだ。
――この家の主が手記にそう書き残している。
海堂に連れて行ってもらった、開の武家屋敷。そこには大きなもみじの木。
「あの家……、議長の家だったんだ……!」
開の歴史で埋められた場所。写真に写った仲間たち。
それが議長の屋敷。
だったら議長も開を愛しているに決まっている。
でも議長に選出された彼は、玉阪はもちろん、仲間との交流も避け、誰とも関わらず、名が決まるその日まで待った。
それはなぜなのか。
「……」
あおと別れ、玉阪坂を上りながら希佐は町を眺める。
そこかしこから歴史情緒が漂う町。
坂の上からだと、遠く川の向こう、開の町の姿も見える。
少し前まで、あの場所も玉阪市だと知らなかった。
――もみじ、未だ青く。早く町が赤く美しく色づけば良い。
「……」
どんな想いで、そう綴ったのだろう。
「……立花?」
ユニヴェールが近くなったところで、前方を歩く人を見つけた。
向こうもこちらに気づいて振り返る。一期上の先輩、白田だ。
「白田先輩、お疲れ様です」
「ああ。……なに、またあちこち動き回ってるの?」
「自分が演じる議長について色々調べていました」
白田ははぁ、と呆れのため息。
「忙しいなお前も。で? それを踏まえてまた玉阪や開の稽古を見にくるの?」
希佐は苦笑する。
「いえ、自分の稽古に専念しようと思います」
白田が意外、とでもいうように希佐を見た。
「みんなのことが気になって、あっちにこっちに動いていたんですけど……私の役は議長なんです。玉阪でも、開でもない、中立な立場の人。だったらきちんと腰を据えて役と向き合うべきだってようやく気がつきました」
人の感情が激しく交差し火花が飛ぶ場所は、希佐の心を激しくかき乱す。なにかしなければと掻き立てられる。
だけど、人との関わりを避け、自身の役割に専念した議長のことを思い、改めた。
「適した人が、適した場所で、適した力を発揮する……」
今回の配役だってそう。
「私に求められているのは人と交ざり合うことじゃない。中立で……透明」
激しくぶつかる時勢の流れ、その真ん中、飲まれることなく自分の足で立つ標識。
「みんななら、きっと大丈夫。絶対に、良い舞台になる」
希佐は信じる。みんなのことを。
「すみません、長々と。それじゃあ、お疲れ様でした」
希佐は白田に頭を下げるとクォーツの稽古場に向かって走っていった。
「……」
一人になった白田は、駆けていった希佐の背中に、ユニヴェール劇場の真ん中で臆することなく手を挙げていたスズを重ねる。
「これが同期なんだから、世長も鳳も大変だな」
希佐とスズに、今度は御法川と菅知を重ねる。
「…………」
自分の姿は、一体なにに重なるのか。
「あー……もう」
白田ははーっと大きくため息をつく。
「……仕方ないな!」
白田は歩き出した。
校門から続く大嫌いな地獄の階段をのぼり、その勢いのままユニヴェール校舎を横切って、クォーツ寮も通り過ぎて。
「おい!」
やってきたのはロードナイト寮。
「……えっ、美ツ騎様!? 美ツ騎様だ!」
稀は驚き声を上げ、他のロードナイト生もあっという間に集まってきた。
騒ぎを聞きつけ、御法川もやってくる。
「えっ、白田? どうしたんだ」
御法川の手には台本が握られていた。顔色はすこぶる悪い。
「『玉阪町』のことでなにか確認か?」
「どうしたんだ、はお前だ御法川。あとお前たちもだロードナイト生。いつになったら真面目にダンスに取り組むんだ」
ロードナイト生が「あわっ」と胸を押さえた。
加斎やオニキス生に言われたときのような反発をしないのは、白田のジャンヌとしての素質や、トレゾールとしての実績からくる尊敬の念ががあるからだろう。
「でも、どうしても歌が気になって……」
稀が指先をすり合わせながら勢いなく言う。
「言い訳するな」
「ご、ごめんなさい!」
だからこうやって白田に叱られても、即座に謝罪する。
「えーっと、だ、ダンスの稽古するか!」
しょんぼりしているロードナイト生たちを見て、御法川がわざと明るく言った。
(『適した人が、適した場所で、適した力を発揮する』……)
そういうのは嫌いだ。
嫌いだが。
「御法川、お前は黙ってろ」
「えっ」
「僕がこいつらの歌を見る」
その場にいたロードナイト生が一斉に場がどよめいた。
「え、歌? ダンスじゃなくて、歌って言ったよね!?」
真っ先に稀が叫ぶ。
「言った言った! てことはぁ、美ツ騎先輩が私たちに、歌のレッスン~~~!??」
ユキも驚き声をあげる。
天変地異の前触れかとロードナイト生たちが慌てふためく。
そんな中でも一番驚いているのは御法川かもしれない。
「おい、白田、どういうことだ?」
困惑顔の御法川を白田は睨みつける。
「お前は自分のことに集中しろ」
「えっ」
「フミさんの隣が片手間でできるか」
言い切った。
うちのアルジャンヌを舐めるなよと。
それに、御法川がぐっと唇を引き結ぶ。
多分そんなこと、御法川自身が一番よくわかっている。
でも、だけど、放棄できない責任が彼にはあるのだ。
――だから。
「ロードナイトがダンスの稽古に集中できないのは、歌に自信がないからだ。僕が一気に歌う力を底上げする!」
それまで騒いでいたロードナイト生が息を飲んだ。
白田の目が本気だったから。
「だからお前は、浮いた時間を全部自分に投資しろ、御法川。それから、フミさん相手に真っ向から勝負するな、機転を利かせて、活路を見いだせ。僕は知ってるぞ、御法川。お前は頭が悪くない」
「白田……」
「じゃあ、稽古するから集まれ。希望者だけで良い。やる気のない人間の面倒見るほど僕は優しくない」
白田がロードナイト生に睨みを利かせる。
「いや絶対参加するー!!」
だが、即座に稀が大きく手を伸ばした。
「美ツ騎様から直々に歌の指導なんてレア中のレアイベントじゃん!」
嬉しくて仕方ないという表情だ。
隣にいたユキとエーコも同じ。
「美ツ騎様の歌も間近で聴けるしぃ! まじまじのハッピーセットぉ!!」
「……ん!」
ロードナイト生たちが手を合わせて喜び合っている。
波はあるが、ロードナイト生はみんな歌が好きなのだ。
「……あらあら」
少し離れた場所から、司がその光景を見る。
「ふふ、いいじゃない」
【9】
ここはいつも、わずらいものを避けるように清浄なお香の香りで包まれている。
「……では、アンバーは凱旋公演をやらないと?」
演劇講師でクォーツ担任、江西録朗がたゆる香りの先にいる人物に問いかけた。
「ああ。田中右がそういうご気分じゃないそうで」
当代玉阪比女彦、中座秋吏は「まぁ、そんな気がしてたけどなぁ」と笑う。
「海外公演は成功したと聞いていますが」
それを祝して執り行われることになったのが凱旋公演なのだ。
「周囲の評価がよろしくても、当人が納得できなきゃそれまでだ。田中右が動かなきゃ、アンバーは誰一人動かねぇ」
アンバー。
天才・田中右宙為の王国。
「箍子先生はなんと?」
それはアンバーの担任、箍子数弥のこと。
「『田中右くんに任せます』だとさ。実際のところは、穏やかじゃないだろうけど。でもまぁ、なんでも利用するんじゃねぇの。老獪な人だからなぁ、あの人は」
ひょうひょうと言ってはいるがそれこそ根深い問題である。
「それより江西、あれはどうなってんだ」
「『玉阪の日』ですか?」
「ちょうど、玉阪座の方から話がきてさ。出席どうされますか、だとよ。そりゃあ参加しますわな」
名の元となった玉阪座の代表として、この式典に参加するのだ。
「順調、という話は耳にしません」
「ははは! 三クラス合同って案にはビックリしたもんだが、一筋縄ではいかねぇか」
中座はどこか楽しそうだ。
「やれるだろ、あいつらなら」
子を慈しむ親の声で、中座は明言する。
世間から隔絶されたようにも見えるこの香が焚かれた部屋の中からでも、彼は生徒たちの姿を見ている。
「……あいつはどうだい?」
潜められた名はすぐにわかった。
「変わらず」
「結構だ。他の生徒と同じように気にかけてやってくれ」
「はい」
校長室を退室し、職員室に戻ると、ちょうどオニキスの担任、長山山門と、ロードナイトの担任、丹頂ミドリが二人話していた。
「ほう、ではオニキスの心に火が灯ったと?」
喜ばしいね~♪ と丹頂が歌う。
「ええ! 俺の心も熱く燃えてきました!」
感情をそのまま体に乗せて、山門が踊る。
言語ではなくパッションで語る二人。
江西は邪魔にならないように、気配を消してそっと自分の席に座る。
「録朗! 秋吏のところかい?」
しかし丹頂が目ざとく気がついた。
「ああ、はい。わかりますか」
「香るよ、沈香だ。父親の倫(おさむ)とは趣味が違うね!」
校長室で焚かれていたお香だろう。
目ではなく鼻が利いたようだ。
「アンバーのことで、色々と」
「ああ、数弥が言っていた。私としてはアンバーの海を越えた舞台、見たいものだが……まずは『玉阪の日』だ! 録朗、どうやら開が進んだらしいぞ」
「開が?」
「熱い羽ばたきがおきているようだ。その風が別の誰かの羽根になり得るかもしれない」
丹頂の背中に背負う羽根が揺れる。
「これは心躍りますね……! よし、俺も自らの足で、空を舞い踊ろうじゃありませんか!」
「そうだ山門! 君は飛べる!」
この二人なら本当に飛べるかもしれない。もう飛んでいるのかもしれない。
そんなことを思いながら歌い踊る二人を見ていると、突然、職員室の扉が開いた。
「先生方、よろしいでしょうかッ!」
現れたのはロードナイトのジャックエース、御法川だ。
「どうした我らが薔薇騎士!!」
丹頂が軽やかに右手を差しのばす。
「俺が高科先輩の隣で遜色なく立てる手段をご教授頂きたいです!」
それは江西たち教師陣にとって、刺激的な言葉だった。
どれだけ大変なことか、わかっているからだ。
「もうどんな手段でも良いんで! なんでもやるんで! 俺の器の限り! でも壊れない範囲で!」
ここで全てを棒に振るつもりはない。その冷静さがかえって良い。
「わかったよ、基絃!」
真っ先に声を上げたのは丹頂だった。ロードナイトの担任。なにか糸口があるのだろう。
「録朗に任せよう!」
違った。
Uターンなんて生やさしいものではなく、Iターンの角度で話が江西に投げられる。
ただ、最も適しているだろう。今の御法川に必要なのは、話をしっかり聞いてくれる大人だ。
「今、高科の隣に並んで、どう感じている?」
「俺の存在が邪魔です。一番彦のせいで、比女彦の華が陰ります」
そんな現実を認識するなんて辛いだろうに、その苦しさを踏み越えてでも前に進もうとしている。だから江西はゆっくり対話する。
「具体的に、どういうとき、強く感じる?」
酷な質問だが、御法川はこんなことでは折れないという信頼だ。
「セリフを言っているときに強く感じます。しゃべればしゃべるほど、舞台の温度が下がるんです。ただ、これに関しては……」
そこで御法川が言い淀んだ。
「素直に言って良い」
江西は先を促す。
「……脚本を見たときから感じていました。一番彦は口が過ぎるのではないか、と」
丹頂が「なるほど」と背中の羽根を一本引き抜いて、自身の髪に挿した。まるで髪飾りだ。なぜ、今突然そういうことをしたのかわからない。ただ、丹頂はそういう人だと全員わかっているので疑問も感じない。
「録朗、確か『玉阪町』時代の比女彦は『玉阪志木年』だったね。彼の時代の一番彦は、実際比女彦に対して口うるさいところがあったと聞く。周囲からうとまれることもあったと」
御法川が「えっ! じゃあ……」と考えてもいなかった可能性に気づく。
「温度が下がる方がリアルということさ!! すごいじゃないか、基絃! 忠実に再現できているよ!」
「なるほど、そうだったんですね、よかった……じゃなくて! 実際そうでも舞台の上じゃ、見てくれる人、シラケちゃいますよ、絶対に!」
御法川の意見はもっともだ。根地はたまに、こういうことをしでかすなと江西は思う。
「こんな空気になるくらいなら、しゃべらない方がマシだって、思うくらいなんですから! ……あっ!!」
そこで御法川がハッと目を見開いた。
見つけたようだ。
「しゃべんなきゃいいんだ!!」
ここにロードナイト生がいたら「なに言ってんの!?」と彼をバカにしただろう。
しかし、江西は思った。
悪くない、と。
「根地に話してみるといい。舞台をよくするためなら、あいつはなんでもする。急なセリフ変更だってな。それに……お前ならその『芝居』ができるよ」
「……! ありがとうございます!」
御法川が丁寧に頭を下げる。
「では、失礼しました!」
彼はそのまま、職員室を飛び出していった。
「青春の足音が響き渡っている……玉阪組も大きく変わりそうですね、丹頂先生!」
「ああ!」
きっと、うまくいく。
がんばれよ、と江西は小さく呟いた。
御法川に、そしてこの舞台に参加している生徒たちに。
「では慶びの歌を高らかに歌おうじゃないか!」
「俺はその歌に乗せて踊りましょう!!」
「録朗、さぁ、君も一緒に!」
ついでに自分にも、がんばれと言い聞かせた。
夜も更けて、山から風が下りてくる。
ざわざわ、ざわざわ、ざわざわと。
「チッ」
その中に、悪態の舌打ち。
「くそ……、くそ……!」
ガン、ガンとカカトで道を蹴る。
「いつも思ってるんですけど」
問いかけながらも他人事。
「そうやって物に当たって、痛くないんですか? もしかして、痛いのがお好きなんですか?」
にっこりと目が歪な弧を描く。
「んなわけねーだろ! ……クソがっ」
ギリと歯がみするのはアンバーのジャンヌ、紙屋写。
「ああ、怖い、怖ぁい」
意識的か、無意識か、ウツリを平然と煽るのは同じくアンバーのジャンヌ、百無客人。ウツリが露骨にチッと舌を打って百無を睨む。
「……なんでだ。海外公演は成功したのに、誰もがアンバーを、宙為さんを賛辞したのに……どうして、宙為さんは……!」
アンバーの神様は全てを疎み、姿を隠してしまわれた。
「それだけ高みを目指しているということですよ」
「お前が宙為さんを語るなっ!」
ウツリが噛みつきそうな勢いで詰め寄る。百無の瞳、真っ暗闇がウツリを覆う。
「紙屋くん、百無くん」
諫めるのは多くの年輪が刻まれた、アンバーの担任、箍子数弥だった。彼は腕を後ろに組んだまま、こちらに歩みよってくる。
「ふんっ」
いったん休戦。なにせ欲しい情報がある。
「宙為さんは、なにか……?」
「特には」
捨てきれない希望を、一瞬で踏み潰された。
「……くそ」
田中右宙為のために自身の血肉を捧げるように尽くしても、貰えるのは冷たい一瞥だけ。
それでも、見て貰えるだけ幸せなのかもしれない。
「宙為さん……」
ぐっと拳を握るウツリを、興味なさそうに百無が見ている。
「さて……」
箍子は数刻前のことを思い出した。
大伊達山に一人入ろうとする田中右との会話。
――『玉阪の日』?
箍子は「ええ」と答えた。そこで根地が見られるとも。
――下らない日だ。
でも、根地くんが出ますよ、と繰り返す。
三クラス合同で出るそうですともつけ加えた。それには興味がないだろう。
――……。
田中右はじっと黙り、そして、去って行った。
(案外、もしかしたら……)
箍子は口ひげをさする。
「とにかく、準備はしておいてください。田中右くんのために」
彼の名を出せば、二人の顔も変わった。
山から風が下りてくる。
【10】
「いや~、全く驚いた!」
ロードナイト二年、一ノ前衣音は、その場にいる全員に聞こえるよう、「驚いた、ああ、驚いた!」と繰り返す。
「昨日、あの美ツ騎がロードナイトに歌の指導をしたと言うんだ! 天ぷらとチョコレートがひっくり返る事件だよ! それにしてもなんという不覚……! なにせこの一ノ前衣音、うっかり不参加なんだ! 僕がいたら、白田美ツ騎のサポートができたのに! いや逆に? 白田美ツ騎が僕のサポートをしてくれたかもしれないのに! もちろん参加できなかった理由はある! 大事な理由だ。君……おにぎりを知っているかい? そう、お米のおにぎりだ! 実はね。このたび新しく、比女彦通りに『七輪おにぎり』なる店ができたんだ! 七輪の上で自らおにぎりを焼ける店だよ! しかもね、おにぎりだけではなく、オカズのお魚や、デザートのお餅まで焼くことができるんだよ! 真夏に七輪であぶられて、僕も焼き白玉みたいになっちゃったけどね! ああ~、ちょっと待ってくれ! 白玉の白と白田の白は一緒じゃないかぁッ!!」
「えーっ!! 御法川先輩、セリフ一個だけになってる~!!」
ロードナイトの稽古場。玉阪組の芝居を通し終えたところで稀が声をあげた。
セリフ数で言えばフミの次に多かった御法川が、劇中、たった一言しかしゃべらなくなっている。
「御法川くんからセリフ削除依頼を受けまして! 大胆にカットしてみましたよぉ!」
その結果を見るために、今日は根地も玉阪側に参加していた。
「さてどうだい、君たちのジャックエースは!」
根地がロードナイト生に問う。
「超邪魔だったのに邪魔じゃなくなりました!!」
「ミノリン先輩らしからぬ渋さがあってぇ、ハマってるぅ!」
「……ん!」
好き勝手言われているが、総じて好評だ。
それに、セリフがなくなったからといって、一番彦の存在が消えたわけではない。むしろ逆。
比女彦の少し後ろ、寡黙につき従う一番彦は華のある比女彦の相棒としてしっくりきていた。
「ん、いいと思うぜ、御法川」
「! ありがとうございます!」
フミに褒められ、御法川がお礼を言ったあと、ぐっと拳を握った。そして、ロードナイト生を見る。
「いやそれにしても、歌もすごいな。一日でこんなに変わるか?」
御法川が言うように、白田の指導によってロードナイト生の歌声は一層良くなっていた。
「歌、クォーツ的な流れが入ってるんだよ。根地さんが作ってるから。それを歌い上げるコツを教えれば、あとは早かった」
「あ~、なるほど! いやでも、白田、人に教える才能あるんじゃ」
「別に。今回はたまたま、僕が向いてただけ」
そう、適していただけ。
白田はチラリと司を見る。
根地の曲を初見で一気に完成まで持っていき、稽古を重ねれば重ねるほど、てっぺんを更新していく司の姿を。
そんな司が歌だけに専念できるトレゾールではなく、アルジャンヌに転じた哀しさを。
トレゾールとして歌う姿を間近で見たからこそ、司が今背負っているアルジャンヌという役目に複雑な想いが芽生える。
適していたから。
今のロードナイトで、その役割を担うことに。
適していたから。
それが運命になったのか。
「……!」
視線に気づいたのか、司がにっこりと笑った。
司はクラス生を鼓舞し、先頭を駆けるオニキスの海堂とは違う。
どんなときでも優雅に、絢爛、でもときに燃えさかるような美しさを放つロードナイトの華。
その華は、自身の周りを飛びかう蝶を楽しげに眺めているようにも見える。
白田はトレゾールだからこそ、その才を惜しいと思ってしまうが、司はもしかしたらユニヴェールでの運命に対する悲壮感はなく、今できることをただ楽しんでいるだけなのかもしれない。
全て想像だ。結局、司のことはわからないのだから。
忍成司こそがロードナイトだということしか、わからない。
「じゃあ次はフミがみんなにダンス教えてあげてよ」
司がフミにねだるように言った。
「……ちょっと、止めてくださいよ、忍成先輩」
白田がさすがにそれを制する。
「だって、あとはダンスができればいいわけでしょ? ねぇコクト」
「さようでございますよ薔薇姫!」
「ね、ね、だからお願いフミ! 美ツ騎だってやってくれたんだから!」
司がお祈りするように手を重ねる。
「まぁ、ボチボチ俺も働かねーとな。でも、歌とは違って時間かかるぞ。クラス内でもかなり個人差あるから」
フミがロードナイト生をぐるりと見回す。
「レベルに分けて稽古したほうがいいかもなぁ。んで、その中に踊れる生徒をリーダーとして入れて……」
フミは御法川やエーコといった踊れる生徒の名前をあげる。
「あとクロも」
「……なんですって? 聞いてないわ!」
「今言った。人手不足」
「酷い! 私はあなたの心の隙間を埋める都合の良い女でしかないのね……!?」
「あともうちょっと踊れるヤツがいたらいいんだけど……」
「やだもっとラリーして!」
フミがうーんと首をひねったそのときだった。
「邪魔するぞッ!」
勢いよく稽古場の扉を開け、入ってきた人がいる。
いや、人たち、だ。
「お疲れーッス!」
「……なんだ、コクトもいたのか」
海堂らオニキス勢と、クォーツのジャックたちだ。
「あらどうしたのよ」
司の言葉に、海堂が代表して前に出る。
「開の稽古は完了した!」
ロードナイトが一気にザワついた。
「えっ、もう終わったの!?」
「た、確かにぃ、先行ってはいたけどぉ!」
稀が戸惑い、ユキが慌てる。
玉阪はようやくこれからというときだったのに。
「ちょっともう海堂! そんなこと言ったらこっちの士気が下がるでしょ!」
司が正面切って海堂に不満をぶつける。
「こっちはやっとダンスを頑張ろうって盛り上がってきたところなの! ほんっと空気が読めない男ね!!」
「そうか、だったらちょうど良かった!」
海堂がうん、と頷く。司が「はぁ!?」とかんしゃくを起こす。
「……ツカサ、俺たちはダンスの手伝いにきたんだ」
ぶつかりやすい海堂と司の間に、カイが入った。
「それに、稽古が完了したというのは、『自分たちだけでできることが終わった』だけだ。ここからは、玉阪側と合わせて調整していきたい。だから、ここに来た」
カイの誠実な説明に、ロードナイト生の気持ちがいったん落ち着く。御法川も「良かったじゃないですか!」と声を上げた。
「ちょうど人手が足りてなかったんですから! 教えてもらいましょうよ!」
御法川の言葉を受け、菅知がスッと前に出る。
「ああ、お前のダンスも見たんで、御法川。あと、白田」
「えっ」
「………」
教える側にいた御法川の立場が突如逆転する。そして少し前まで歌を教える側だった白田もその回転に巻き込まれた。ロードナイト生に比べればそれなりに踊れているので大丈夫だろうと油断していた。菅知は意外と白田に容赦ない。白田は現実逃避でスッと目を閉じた。
「えーっと、あ、世長!」
スズに呼ばれ、世長はそちらに駆けていく。なかなか人の輪に入れず、特に集団になると一人で沈黙しがちな世長にとって、こういうときのスズの存在はいつもありがたかった。
「すごいね、開組。あんなに大変そうだったのに、しっかりできあがったんだ」
「急に『ドーン!』ときて、そのまま『おらぁ!!』って進んで、勢いよく『バーン!』ってなった」
「そ、そっか……?」
なにかをきっかけに、ことがうまく転じたのだろうと想像する。
「世長はダンスどんな感じ? あと他のクォーツ生たちも」
スズが散らばっていたクォーツ生たちも手招きする。
「踊れはするけど、開と並んでとなるとまだまだ厳しいよ。かなり歌に集中してたから……他のクォーツ生も似たような感じじゃないかな……」
「うわー、玉阪組の歌、すごそうだな……! でもまずはダンスか! 鳳、みんなのダンス、手伝うぞ!」
「お前ごときが僕に指示を出すな! お前にだけは絶対に言われたくない!」
スズに言われて、鳳が吠える。
「鳳、すまないな。よろしく頼む」
「承知しました!!」
カイに言われて秒で意見を変える。
「織巻、鳳、俺たちも手伝う!」
「おっ、ありがとな、長山!」
「じゃあ僕はロードナイトのお花さんに……」
「ダンテ! お前もこっちだ!」
「ああ~」
玉阪と開が混ざっていく。
「忍成、教えるよ」
「ええ~、加斎ぃ? 恩売られてるみたいでヤだ~!」
「早いところ歌の稽古に入りたいからスパルタでいくよ」
「やだぁああああァァァァアアアアアッッ!!!!」
クラスの垣根もなく、ユニヴェール生として交ざり合っていく。
「いや~、いいねぇ」
その光景を見ながら根地がうんうん、と頷き、背を向けた。
「おーっと。どこ行くんだ、クロ?」
そんな根地の肩に、フミの腕がガッと回る。
「あらやだフミさん! これだけ心強い光景が広がっているんだから、僕はみんなに想いを託して……」
「オニキスが手伝ってくれんなら、もっと上目指せると思うんだよなぁ?」
「なに、やな予感。やめて、それ以上言わないで!」
そこにカイも加わる。
「コクト。たまにはみんなと汗水たらして踊るといい」
「ちょっと、カイ! フミと一緒になって僕をはさまないでくれる! 屈強! 屈強なんだよ君らは! てゆーか町人はAもBもCもDも踊らないんですけどっ!?」
両隣の高身長はびくともしない。
「ああ、根地! どうしたんだ、捕まった宇宙人みたいな格好をして!」
そこで海堂が駆け寄ってきた。
「助けて海堂! このままじゃ月に返されちゃう! 月に強制送還されちゃう!」
「いや、ここでフミが納得するまで踊ってもらうだけだ」
「それが一番しんどい!」
根地が反抗的に座りこむ。
「ところで根地! 舞台について質問いいか!」
海堂は意に介さず話を進めた。
「はいどうぞ」
根地がシャンと立ち上がる。
「御法川のセリフを大胆に削ったそうだな! だったらその分、俺に新しいセリフをくれないか!」
「なにそのシステム」
そう言いながらメガネを持ち上げる根地の目は好奇心で輝いている。
「新田として、開の武士として、言いたいことがあるんだ!」
「ほぉ? その心は?」
海堂は自分の胸を押さえる。
「多くの人々を仲間につけた玉阪側が名を勝ち取る……それは史実だが、別の見方もあるのではないかと思うようになった。今こうやってクラスが協力し合う姿を見てその気持ちは一層強くなっている!」
根地がメモ帳を取り出した。
「海堂。開の武士はなんて言いたがってる?」
「それは――」
「………」
ぺらり、と台本をめくる。じっと見つめて、ぺらり、ぺらり。
クォーツの稽古場に、希佐一人。
いつも賑やかなこの場所に、ページをめくる音だけが響く。
その音は少し開けた窓から吹き抜ける風に飛ばされてしまいそうなくらい軽い。
でも、ここに記された言葉の数々は、どこまでも広くて深い。
じっと見つめ、目を閉じる。そして思い描く。
この言葉が生み出す世界を。
希佐は立ち上がった。
「……始まる」
舞台が。
『玉阪町』が、ここに。
――初めまして、ごきげんよう!
突然だけど、ちょっと良い?
あなたの町のお名前、なんですか?
へぇ、へぇ、なるほど、そいつはいい!
とっても素敵な名前じゃない!
もちろん、君がつけた名前だろ?
え、違う? じゃあ誰が?
こんな素敵な君が住む町に、こんなに素敵な名前をつけたんだい――?
時は明治二十二年。
大伊達山を正面に広がる二つの町は大きく揺れていた。
「まったく、こんなことあり得ない!」
その町の一つ、開出身の起業家、初花は苛立ちを隠さない。彼の付き人たちも同意するように深く頷く。
「そもそも、こんな会合が開かれていること自体が屈辱だ! 即刻決議し、解散すべき!」
初花が木製の机を激しく叩くと、その隣にいた長身の男が諫める。
「わざわざ開まで来てくれるんだ……、そう、荒立てるな……」
場を取り持つように言うのはこちらも開出身の警官、ナラシバだ。いかにも屈強そうな体格をしていながら、人の顔色をうかがっている小心者。彼の部下警官だって、呆れてため息をついている。
だから初花はナラシバの言葉に取り合わない。
「そもそもなんだ、あいつらは! 約束の時間はもうすぐだぞ! 遅刻するつもりか!」
そこで上座に座っていた男が「初花」と呼んだ。それには初花もびくりと反応する。
「まだ時間ではない」
威風堂々とした佇まい。一目でただ者ではないとわかるその男は、開の武士筆頭であり、政治家でもある新田だった。
彼は余裕の表情で、懐中時計を確認している。
「そうだそうだ。怒っても腹が減るだけだ」
ナラシバの弟分であるリンが呑気にそんなことを言った。
初花が「仕事を持たずの足手まといが」と吐き捨てる。
開は本来武士の町。かつては藩主に仕えていたが、明治はそんな彼らの人生を無情にくるりとひっくり返した。大政奉還だ。
武士たちは主をなくし、職も消え、慣れない商売や農業、北の開墾に転じた者もいる。
リンのように当てもなく暮らす人間も少なくなかった。
この足並み揃わぬ中で聞かされたのが、町の合併話だ。
相手は江戸に開の殿様が土地を与えた役者たち。
かつて与えた者に、奪われようとしているのだ。
「……来たな」
新田が懐中時計をパチンと閉じる。緊張が走った。
「失礼致します」
「……!」
真っ先に入ってきた人物に全員息を飲む。
傾国の美女といった雰囲気漂うその人は、玉阪座の二番比女。
その後ろから白磁の人形のような美しさを持つ三番比女。
さらに五番、六番、七番比女と続く。
初花の付き人が「ここは竜宮城か?」と思わずこぼした。
あまりにも美しいのだ。
だが、既に圧倒されているというのに、“頂点”が最後に姿を見せた。
「お待たせして申し訳ありません」
怖気が走るほどの美しさ。
「玉阪を代表してやって参りました。玉阪比女彦と申します」
玉阪座の当代、女役である比女を演じる玉阪比女彦。
最愛の兄を亡くし打ちひしがれながらも舞台に立ち、玉阪座の内政を自らの手で大きく変え、今までにない試みを次々と打って出る才人でもある。
比女彦の凄みはこの場を圧倒していた。
ただ一人、新田は悠然と組んだ指をほどくことなく、もっと言えば比女彦を見ることもなく笑みを浮かべている。
比女彦の側に着いていた男が、新田の正面の椅子を引いた。こちらも眉目秀麗。聞くところによると、彦役の頂点で比女彦の相手役、一番彦らしい。
比女彦は彼が引いた椅子に腰掛ける。他の役者たちも席に着く。
そこで、ようやく、会合の議長が姿を見せた。
「それでは始めます」
議長が淡々と、開始の合図をする。

「議題は名を、玉阪とするか、開とするか。双方で決めてください。」
議長がそう言ったところで、新田が机を蹴り飛ばした。
「……当然開だよ」
突如、音楽が流れ出す。
そう、これは――ユニヴェール歌劇。
「わぁ……!」
玉阪市が所有する文化施設内、大ホール。客席にはいっぱいの玉阪市民。
照明が一気に舞台を照らした。袖で待機していた全生徒が登場し、玉阪と開に分かれて踊り出す。
「すごい……!」
ユニヴェール生のダンスに、『玉阪の日記念式典』参列者たちが歓声を上げる。
そう、ユニヴェールだ。
クォーツ、オニキス、ロードナイトの囲いはない。
「すごい……ユニヴェールの歌劇……!」
観客は群舞の迫力に飲まれ息を飲む。
「町の名は開!」
「町の名は玉阪!」
玉阪と開は激しく主張を繰り返す。いつまでも止まらない、いつまでも終わらない。もしかすると、永遠に?
カーン、と突如、無情な鐘の音が響いた。
激しく踊っていた玉阪と開が、ピタリと止まる。
そして一言。
「着席してください」
双方の様子を極めて無関心に見ていた議長がそう促す。玉阪と開は一斉に着席した。
その滑稽さに、観客たちがどっと笑う。
「決まらなかったので、今日はお終い、また次回」
つれない議長がそう言い放ち、さっさと退席する。残された玉阪と開の人々はお互いにらみ合って、そして真逆の方向に出て行った。
観客たちは、拍手でそれを見送った。
「ダンス……すごく良かったです!!」
舞台袖、希佐は感情を抑えられなかった。
双方の主張が激しくぶつかるダンスが、玉阪と開の歴史と、譲れぬ想いを鮮烈に灼きつけていったから。
希佐にも、そしてなによりこの場に訪れた『玉阪の日』参列者にも、強く、強く。
彼らはもう、この歌劇に引き込まれている。
海堂がフッと笑った。
「当然だ! なにせ俺たちは、あのユニヴェール歌劇学校の生徒だからな!」
海堂の言葉は、どこまでも高く誇らしげだった。
「あー良かったぁ……!!」
一方、稀たちロードナイト勢はダンスが終わってホッと胸をなで下ろす。
「忍成」
「げっ、加斎!」
「ロードナイトすごく良かったよ」
「え」
加斎がさらりと褒めて、サッと通り過ぎていった。
「……え、なに!? 今のなに!? 今、加斎が褒めた!?」
「……ん」
戸惑う稀に、エーコが加斎の背中を見ながら頷く。ユキが「やばぁい!!」と騒いだ。
「やだもうぉ、加斎ってばぁ~! 絶対モテるぅ~! ミノリン先輩の百倍モテるぅ~! マジマジで罪~!」
飛び火に御法川が「おい!」とつっこむ。
「カイ、開組はちょっと暴走してるくらいがよろしそうだから、その辺頼むよ! 鳳くんもね!」
舞台の、劇場の温度を、その肌で正確に測った根地が鋭く指示を出す。
「ああ」
「はい!」
任せろ、任せてくださいと言うようにカイと鳳が頷く。
「……スー」
口を大きく開閉し、顔をほぐしていたスズにフミがスッと近づいた。
「どうよ、俺らの玉阪の日、祝いっぷりは」
スズはよくほぐした顔でニッと笑う。
「最高ッスね!」
舞台はまだ続く。
「ああああああああ~~~~~~!」
舞台の真ん中、クルクル木の葉のように舞うのは町人、根地だ。
Aかもしれないし、Bかもしれないし、Cの可能性もDの可能性もある。
「こんなに性格の違う二つの町が一つになるなんて、そもそも無理な話じゃないかしら!」
頬に手を置き、困り顔。四十そこらの女性だろうか。
「……でも国がそう言ってるんだ。開にするしかないだろう」
急に声が低くなった。口調も威圧的な彼は開の町人かもしれない。
「なにをおっしゃる! 開の町は、殿様がいなくなってから活気を失い、寂れる一方じゃないですか! かつては武士と呼ばれた人たちも今では職を失い、まるで野良猫、そして野良犬! そんな街の名前はつけられません!」
若い女性の訴えに、男が「ええい、うるさい!」と睨みを利かせる。
しかし、女性は負けない。
「そうやって脅せば言うことを聞くと思っているなら大間違いよ! 今は明治、これから玉阪という名前と一緒にこの町は広く大きくなっていくんだから!」
「……ほんっと器用だな、根地さんは」
袖で白田がぼやく。
一人で町人ABCD。ときにはE、Fと時勢を語る人々を演じている。
すごすぎて呆れてしまう。
「観客の皆さんも楽しそうですね」
白田の隣で同じように舞台の上の根地を見ながら世長が言う。
一人で何役も演じている姿は、物珍しいし、面白い。
ここで息が抜けるから、また物語に集中できる。
「……根地さんがいなくなったら、どうなっちゃうんだか」
「え?」
「いや、別に」
脚本演出、ジャックにジャンヌ、そして組長。
クラスにおいて根地が受け持つ役割はあまりに大きい。
言ってしまえば、フミだって、ただアルジャンヌだけをやっているわけじゃないし、カイだってそう。
それが、白田の心を重くする。
今回、他クラスとの稽古で、他クラスの同期たちがどうやって先輩や後輩たちに関わっているのか、リアルに感じることができた。
自分は、遅れているのだと見せつけられた。
そんなこと、経験しなくたってわかっていたのに、実際目の当たりにすると、あまりにも大きい。
「おい、着物の襟、崩しすぎ! もっとキレイに合わせろ! あと帯もアレンジしすぎだ!」
御法川がロードナイト生に声をかけている。過保護にも見えるが、御法川は常にクラス生を意識して、動いている。
菅知だってそうだ。他クラスの白田に当たり前のようにダンスの指導をつけたのは、クラスでの積み重ねがあるからこそ。
なにか行動すれば他人は勿論、自分さえ「珍しい」と思う白田とは違うのだ。
「よくあそこまで後輩の面倒見られるな」
御法川の姿を見ながらぽつりと呟く。
「本当にすごいですよね」
世長も静かに同意した。
「でも、白田先輩も、77期生の先輩の中で、一番僕たちの指導をしてくださってますよね」
「……え?」
言われた言葉の意味が本当にわからなかった。世長も「えっ」と戸惑い、「あの、その……」と自分が発した言葉の不備を模索する。
でも、結局その言葉以上のものは見つからなかったのだろう。
「二年の先輩の中で、白田先輩が一番、僕たち一年の面倒を見てくださっていると思います。歌は勿論、なんというか、クォーツ生としてのありかたとか……」
「……」
どんな人間に対しても適度な距離感でそっと寄り添える希佐や、誰に対してもゼロ距離で真正面にいるスズではなく、世長にそんなことを言われるなんて。
「そうは、思わないけど」
なんとなく否定してしまったのは、まだ受けとめる勇気がないからか。
でも、この言葉は、忘れないような気がする。
「……世長、お前はもうちょっと着物の襟を緩めた方がいいぞ。窮屈に見える」
「えっ、あ、はい!」
ぽーん。
桜色の鞠が投げ出されて跳ねた。
ぽーん、ぽーん、ころころろ。
「……やめて! 返して!」
町の少女が鞠を追いかけ、抱きしめる。
「どうしてこんなことをするの……。え、玉阪の人間だから……?」
舞台はパッと暗くなった。
今度は「なぜなんです!」と声が響いて明かりがつく。
そこに、困窮した男の姿。
「金は貸せない……!? 俺が、開の人間だから……?」
また、明かりが消える。
次は玉阪、次は開、また玉阪、そして開。
町の名騒動をきっかけに関係が急激に悪化していく玉阪と開。
町は黒く濁っていく。
「……比女彦、用心しなさい」
玉阪座。二番比女が忠告する。
「開の武士どもがお前の命を狙ってる」
「ハッ。熱狂的なご贔屓ができてしまったな」
「比女彦さん」
軽口をきいた比女彦を、三番比女が咎める。
「そうですよ、兄さんになにかあったら私たち、嫌だわ」
五番比女がそう言って、同意するように他の役者たちもうんと頷く。
「お一人の命ではありませんよ、兄さま」
七番比女の言葉に、「それはもう、今回に限らずずっとそうだろう?」と比女彦が笑う。
「大丈夫、肝に銘じておくよ。さ、今日はこれで終いだ」
役者たちは全員不安そうだが、比女彦が立ち上がれば、みんな仕方なく立ち上がる。
「……ん?」
そこに、雷鳴が響いた。
「……こいつは雨が降るな」
ざぁざぁざぁ。
雷鳴から程なく、雨は勢いよく降り始める。
「このままでは名を玉阪にとられる!」
新田の邸宅で、初花が叫んだ。
「何百年も続いてきたこの開の名が……! 命を懸け、守り繋げてきた開の町が、俺たちの代で……! あんな役者どもに土地なんか与えるべきじゃなかったんだっ!」
「……初花。それは開公の判断だ」
新田がそれはダメだと鋭く注意する。
「ですが! それこそ、このまま名を奪われれば開公に申し訳が立たない!」
どん、と机を打つ初花の目はギラついていた。
「もし、開の名が玉阪の下に着くくらいなら……玉阪比女彦の命、奪ってやる!」
それにはナラシバが慌てた。
「おい、止めろ! 俺は警官だぞ。聞かなかったことにしてやる、だからもう二度と言うな。ただでさえ治安が悪くなって大変なんだ、この命名騒動のせいで」
「だからなんだ、この腰抜けが! ああ、そうだ、今すぐにでも比女彦を殺してやる……。 開の殿のご恩に報いず裏切る仇者をな! そうすれば、あいつと一緒に玉阪の名もなくなるだろう……!!」
「やめろ、やめてくれ初花! おいお前たち、初花を休ませてやれ!」
尋常ではない雰囲気に、初花の付き人が彼の体を支え、退室していった。ナラシバがはーっと息を吐く。もうこんな話は終わりにしたいと言うように。
「初花の言いたいことはわかる」
だが、終わるはずがないのだ。
「おい、新田! やめろ、お前まで。滅多なことは言うな」
「恐ろしきは玉阪比女彦だ。あいつなら政界に行ったとしても確実にのし上がれただろう。恐ろしいほど頭が切れる。それに人たらしだ。完全に世論を手に入れた」
いつだって強気だった新田が両手で顔を覆う。
「開公に面目がたたない」
「新田……」
「……このまま名を奪われるというのか」
「新田……お前は充分やったよ、だから、少し休んでくれ」
「……いや、だめだ! 比女彦に会ってくる」
新田が席から立ち上がる。
「開の政治家が自ら比女彦を尋ねるというのか……! お前がそんなことする必要などない、もういい、時代が悪かったんだ、時代が……!」
「俺は諦めない! 開のためならなんでもする……なんでもだ!」
今にも邸を飛び出しそうな新田をナラシバが止める。
「新田、落ち着け新田。奥方、新田を奥の部屋に!」
新田の妻が即座に姿を見せ、そっと彼の背に手に添えて、奥へと消えていく。
これ以上、話し合いなんかできるはずがない。
「……大変なことになったね、ナラシバさん」
雨の中。傘をさして開のぬかるむ道を歩く。後ろには弟分のリン。
「……殺されてしまうかもしれないね、比女彦は」
ぽつりとリンが言った。
「馬鹿なことを言うな」
「でも、町の名は、玉阪になる。これは間違いないだろ?」
「……」
リンが傘をくるりと回す。
「今殺されなくても、いずれ死ぬ。名前を奪われてしまった開の人間の誰かに。血に濡れた町になるよ、『玉阪町』は」
雨脚は弱まることもない。
「それにしても、参ったもんだね、開の連中は。目がぎらついてやがる」
比女彦は傘を肩に自身の邸宅へと向かう。少し後ろに一番彦。
「この辺で開のヤツらを見かけたら報告するようにと方々に言ってはいるが」
玉阪座には不審な人物が近づけないように見張りもつけている。
七番比女も言っていた。自分一人の命ではないのだ。
「名を生み繋げるというのは大変なことよ」
それは、玉阪比女彦という歴史を通して知っている。嫌というほど。
そこで、パシャ、と水の音が聞こえた。
降る雨の音ではない。
踏まれ上がった水の音だ。
「……ん? ……!! あんた……」
雨の中、男が一人傘も差さず立っている。
――ナラシバだった。
「………」
警官の制服、腰には――軍刀。
「警官は便利だ。不審じゃない」
ばしゃ、と水たまりを踏む。
「町の人は比女彦さんを守ってくださいねと話しかけてくるし、見張りも見回りですと言えば容易く通してくれた」
雨でぬかるんだ土にぐちゃりとブーツの足跡がつく。
「お前さん……」
雨に濡れ、張りついた髪の隙間からギラついた目が比女彦を見る。
「町は玉阪となるでしょう。あなたがいようが、いまいが関係なく。だったらせめて……」
雷鳴が響いた。
「誰かがお前を殺める前に、俺がお前を殺してやるッッッ!!」
ナラシバが軍刀を抜いた。
その切っ先はナラシバの目のように異様に輝いていた。
そこで、今までずっと背後に控えていた一番彦が、傘を閉じ、前に出る。
比女彦を守るように。
「おい!」
こちらは丸腰。敵うはずがない。
しかし一番彦は、この場面にそぐわないほど優雅にゆったりと、比女彦を振り返った。
「……稽古の時間だ。お行きなさい」
彼は小さく微笑んで、比女彦の体をトン、と押す。
優しく、穏やかなのに、どこまでも強い。
「だめだ……っ!」
比女彦は必死で彼の袖を掴もうとした。
そんな一番彦の後ろ。
ナラシバが土を蹴り、一気に迫ってくる――
「これが……武士の誇りだッッ!!!」
そして血が舞った。
「……!!」
流れた血は比女彦のものではなかった。
「……!? リン!!」
開の士族、リン。
ナラシバが駆けるよりも速くリンが駆け、振り上げられた軍刀の前に飛び出したのだ。
「……ってぇ……!」
「リン、どうして!」
リンの右腕から血が流れる。
「医者呼んでこい!」
叫んだのは、比女彦だった。
「っ!?」
ナラシバが驚いて比女彦を見る。
「早く! すぐに!」
比女彦は一番彦に向かって叫んでいた。
「おい、兄さん、大丈夫かい!」
比女彦は自分の着物を脱いでリンの腕を止血する。
「なぜ……」
呆然とするナラシバを比女彦は「『なぜ』じゃねぇよ!」と怒鳴りつけた。
「人は死んだら戻らねぇ! 屋敷に運ぶ、お前さんが背負うんだ、早くしろ! この兄さんを助けたくねぇのか!」
リンは腕を押さえ呻いている。
ナラシバはグッと息を飲み、リンを背負うと、先導する比女彦のあとに続いて走り出した。
「ナラシバ、リン!」
それから数刻。比女彦からの連絡を受けた新田が比女彦の邸に駆け込む。
「新田……すまない……すまない……」
ナラシバががくりと肩を落とした。
「リンは……!?」
「寝てるよ」
「……!」
ナラシバの代わりに答えた比女彦に、新田はハッと彼を見る。
「医者に診せて、傷は縫合してもらった。ちっと熱は出てるけど……強いもんだよ」
そう、か……」
比女彦に案内され、新田は眠るリンの前に座る。
人の気配に気づいたのか、リンが呻いて目を開き、新田を見上げた。
「ああ、新田さん……。すみません、こんな時間に」
「いや、いい。……どうしてこんなことに?」
リンがヘッと鼻で笑う。
「ああ見えて、ナラシバさんの開への想いは人一倍強い。開の仲間が苦しむ姿を見て、玉阪への憎しみが堪えられなくなったのさ」
新田がぐっと拳を握った。気づけず、追い詰めた自身のふがいなさ。
自分がやれば良かった。
そんなことさえ思ってしまう。目の前に、ヤツはいる。
ただもうひとつ、聞かなければいけないことがある。
「……リン、お前はどうして」
――比女彦を助けた?
新田は暗に尋ねた。
「そりゃあ……」
リンが目を閉じる。
「開への想いが強いからですよ」
「なに?」
ナラシバの説明と同じ理由じゃないか。
「だってこんなことで開の名を残してどうするんですか。十年先も百年先も、この町の名が生きる限り、血に濡れた開の名が残ってしまうんですよ」
「!」
「ナラシバさんは俺にとっちゃいい兄貴分だ。開の仲間だってそう。だから十年先の、百年先の、顔も知らないどうでもいい誰かにバカにされたくなかったのさ。だから斬られたんだ。そうすりゃみんな、目を覚ますだろうって。いつもバカにされてるけど、俺の命はみんなにとって軽くはないってわかってるからさ」
「リン……」
「それにさ」
リンがへらっと笑う。
「俺ぁ玉阪の舞台が好きなんだ」
新田も、そして顔を伏せて黙って聞いていた比女彦もハッとリンを見る。
「昔、みんなで見に行ったじゃないですか。玉阪の舞台。新田さんのおごりでさ。ああ、楽しかったなぁ、あの舞台」
リンが目を開き、新田を見る。
「また行きましょうよ。新田さんのおごりでさ。開の仲間、全員で。きっと楽しいさ、あのときと一緒でさ」
そう言って、リンはまた眠りに就いた。
「……」
「……新田さんよ。今回の件、私は人に言うつもりはない。そいつに命を助けてもらったからね」
「……」
「あとはまぁ……」
比女彦はリンを、そしてナラシバを見る。
「また見に来てくれよ私らの舞台」
「……!」
「大丈夫、今度は私がおごってやるよ。特等席だ。みんなで一緒に見に来ておくれ。絶対にお前さんたちを楽しませるよ」
それを聞いて、なぜかナラシバがうっと背を丸め、泣き出した。
「うっ……く……う、う……」
仲間たちと共に、玉阪座で見た舞台を思い出したのだろうか。
新田が「そうだな」と小さく頷いた。
数日をおいて、新田はリンを引き取り開の町に連れ帰った。
そこには開の仲間が集まり、みな、沈痛な表情を浮かべている。
彼らには全て話した。
「俺が……俺があんなことを言ったから……」
「違うんだ、初花……! 俺のせいだ……!」
初花の言葉を、ナラシバが強く否定する。
新田は着物の袖に手を入れ、じっと黙り込んでいる。
「もうやめてくれよ。俺は生きてるし比女彦も黙っててくれるんだ。もういいじゃないか」
「良くない! 良くないんだよ、良くないんだ……」
初花がリンの動かない右腕を見る。
「みんな」
そこで新田が立ち上がった。
「玉阪座の舞台を見に行った日のこと、覚えているか?」
すぐに返事は返ってこなかった。しかし、初花が「覚えていますよ」と絞り出す。
「新田さんのおごりで見に行った」
「そうだ。だから忘れてもらっちゃ困る」
「でも、あんな舞台……」
「初花。正直に言ってくれないか」
新田が初花の言葉を阻む。いや――『嘘』を阻んだ。
初花は額に手を置き、堅く目を閉じる。
「……楽しかったですよ、日頃の鬱憤なんか全部吹き飛んじまうくらい。武士の憂いを忘れちまうくらい」
「みんなは?」
その場にいた者たちは、みな、やはりためらいはしたが、初花と同じように「楽しかった」と答えた。
新田はその言葉を聞き、また椅子に座り直す。
「みんなに話したいことがある」
その真剣な面持ちに、全員の背筋が伸びた。
「俺は……」
空は一転、青空だ。
「比女彦さん本当に行くのですか」
三番比女が伏し目がちに問うてくる。
「ああ、行くさ」
「絶対に危ないよ、兄さん」
「兄さま、開は信用なりません」
例の件は秘密にしていても、起きてしまったことは自然と感じとられてしまうものだ。
「本当に言っても聞かない男だね、お前は。いつか痛い目を見るよ」
二番比女は冷たく言いながらも比女彦の側から離れない。
一番彦もだ。
「さて、今日はどうなるか」
比女彦たちは多嘉良川にかかる橋を渡り、会合の場に入る。
「……」
今日は珍しく早めに来たのだが、開の代表者たちは既に集まっていた。
ただ、いつも荒立っていた開の代表者たちが今、風のない湖畔のように静かだ。
その空気の異質さに、五番比女や六番比女が思わず身を引く。
「待たせて悪かったね」
だが、比女彦はいつも通り、自分の席に着く。他の役者たちも怖々と席に着いた。
そこで議長が現れ、真ん中に座る。
「それでは始めます」
いつもいつでもこの合図。
「町の名を、玉阪とするか、開とするか」
いつもは開側があれこれ意見を言ってくるのだが、今日はすっと新田だけが手を挙げた。
議長は静かに新田を見る。
「……新田さん」
「はい」
新田が立ち上がる。そして、言った。
「町の名は……『玉阪』です」
比女彦たちが驚き彼を見上げる。
逆に開の者たちは、新田の言葉を噛むように俯いた。
議長だけが変わらず、正面を向いている。
「……新田さん、それはいけねぇよ」
比女彦は思わず制止した。ナラシバの罪を償うための代償にして欲しくないからだ。
「先日、うちのナラシバが多大なるご迷惑をおかけした。彼は比女彦の命を狙おうとした」
しかし新田が自らそれを玉阪側に暴露する。
役者たちは察してはいたのだろうが、実際に開側の口から聞き、いきり立った。
「貴様、よくも……!」
敵意を燃やす三番比女を比女彦は制す。
「……本当に、申し訳ありませんでした!」
そこで、ナラシバが立ち上がり、深く頭を下げた。
プライドの高い開の人間が頭を下げたことに、役者たちは固まった。
新田は更に、事の詳細を役者たちに語る。
リンの話を聞けば、役者たちの口も自然と閉じていた。
「謝罪の意味を込めて、名を譲るのかい」
話が終わったところで比女彦は新田に問う。
「まさか、違う」
新田ははっきり否定した。比女彦は「だったらなぜ」と問う。
「ここにいる仲間たちと玉阪座の舞台を見に行ったことがある」
唐突な思い出語り。しかも敵対していた玉阪座の。
全員がそれに耳を傾ける。
議長も。
――希佐も。
(ここはもう……新しく書き加えられたセリフ……)
本当は、それこそもっとあっさり、町の名前は『玉阪』に決まっていた。
しかし、海堂が開の武士として言いたいことがあると進言し、その言葉を踏まえて、フミやカイ、そして司が意見を出し合って。
全部抱きしめるように、根地が言葉を織り上げた。
だから希佐は耳を傾ける。議長として。
誰とも交わらず、でも、最前席に座る者として。
「舞台を見ている間、ずっと楽しかった。舞台を見終わったあとも、楽しかった。月日が経っても振り返り、また行きたいなと語り合った。そうなんだ、あの日の舞台を想うたび、俺たちの心に明かりが灯る」
新田が自分の胸を押さえる。
「今回リンがナラシバを止め、比女彦を庇ったのも、その想いがあったからだ。俺は思った。初代玉阪比女彦に土地を与えた開の殿も、同じような思いがあったのではないかと。比女彦の舞台に胸の明かりが灯り、消えることなく照らし続けていたのではないかと」
「!」
玉阪の役者たちが目を見開く。
「無論、他にも様々な意図があっただろう。そもそもこの論が間違っている可能性がある。俺ごときに開の殿のお気持ちを察せられるはずがないのだから。だが、やはり思うのだ。わざわざ宿場町近くに土地をやり、支援し、自由を与え続けたのは、ご自身の胸に消えぬ明かりが灯っていたからではないかと。そしてその明かりを、他の誰かに、多くの人に与えたかったからではないかと。心豊かな開の殿が、喜びを分かち合いたくて」
役者たちはいつのまにか俯いていた。スン、と鼻を鳴らす者もいた。
新田の言葉に熱が籠もっていく。
「なにより、俺が思ったのだ。激しく変わる時勢、不安定な世の中で、玉阪の舞台は人の心を明るく支える。そしてその明かりが、俺たちの仲間に、俺たちの子に、孫に、もっと先、俺たちの血を引き継ぐ子孫たちに灯ればいいと。刀も血も哀しみの涙もなく、舞台を楽しめる世の中であって欲しいと」
比女彦が思わず「新田さん……」と名前を呼ぶ。
「そのために、我々開は陰から支えよう。舞台の町、『玉阪町』の一員として」
新田の言葉に呼応して、初花が「同じく」と立ち上がった。ナラシバが、リンが「同じく」と立ち上がる。その場にいた開の代表たちが全員立ち上がり、「同じく」と。
「……新田さん」
比女彦が立ち上がる。役者たちも全員立ち上がった。それは、比女彦と同じ気持ちだということ。
比女彦がスッと手を伸ばす。
新田がその手をじっと見つめ、手を伸ばす。
二人は手を、堅く握り合った。
――ああ。この瞬間を、待っていた。
「……町の名は」
議長がカンと鐘を打つ。
「満場一致で『玉阪町』!」
その瞬間、議長の声が初めて高揚した。
(ああ、そうだ)
――希佐は思った。
(きっとこの感情だ)
そして、思いがけないことが起きた。
「良かった……!」
観客席から、聞こえたのだ。
「良かった……良かった……おめでとう……!!」
町の誕生を喜び、祝福する声が。
高まる感情を抑えきれず、打ち鳴らされる拍手の音が。
それはどんどん大きく膨れ上がっていく。
(ああ、そうか)
希佐は理解した。
――透明。
どちらの色にも染まらず、常に公正だった議長。
その議長が下した判断をみんな信じた。
議長が認めた答えなのだから、そこに間違いはないのだと。
玉阪と開が導き出した答えは、なにものにも代えがたいほど素晴らしいものなのだと。
この町は、全ての人に祝福された名前なのだと、みんな素直に、真っ直ぐ、喜んでいるのだ。
愛する玉阪の町。
(良かった)
この一瞬のために、希佐は議長を演じていた。
(良かった……)
そして、役目を果たした。
希佐は未練なく立ち上がり、一人退席していく。
「では、町の名を祝して歌おうじゃないか!」
背中で彼らの声を聞きながら。
(……あ)
客席に、モナとアキカの姿を見つけた。
モナは顔をくしゃくしゃにして泣いていた。
嬉しそうで嬉しそうで幸せそうで。
(良かった……)
かつて、玉阪と開が思い描いた遠い未来。
それが今、ここにあるのだ。
誕生日、おめでとう。
「……どうでしたか、田中右くん」
美しい近代的な建築物。記念式典が行われている大ホールを田中右宙為はあとにする。
目尻のしわを深くして微笑む箍子の問いかけに田中右は答えず通り過ぎた。
やれやれ、と言葉には出さず、息をつく。
「……凱旋公演、やります」
急に、田中右が言った。
「……やらないと言っていた凱旋公演を……ですか?」
箍子は驚きを胸に収めたまま、しっかり確認する。
「見せてもらいましたので」
田中右は振り返らない。
「俺も見せましょう」
そうして彼は去って行った。箍子はふふ、と微笑む。
「紙屋くんと百無くんに連絡しなくては」
夕暮れの山に、秋の匂い。
「……キュイ?」
草を踏む足音に耳を立て、白イタチが顔を上げた。
「キュイ! キュイキュイキュイ!」
駆けた先に、一人の少女。
「ああ、オナカ! 元気だった?」
「キュイ!」
希佐はしゃがんで、オナカと目を合わせる。
「今日はね、『玉阪の日』だったんだ。玉阪の誕生日を祝ったんだよ」
「キュイ~?」
「みんなで舞台に立ったんだ。すごく……すごくよかった」
「キュイ~! キュイキュイ!」
「ふふ」
はしゃぐオナカに希佐は微笑む。
「オナカにも、見せてあげたいなぁ……あ」
ふと見上げた先、夕日に照らされ赤く色づく木があった。
「もみじだ」
まだ青いはずのもみじが、茜に染まっている。
「……」
希佐はもみじ越しに、町を見た。
近くはユニヴェール、玉阪座、比女彦通り、そして遠く開の町々まで。
「……誕生日、おめでとう」
もう何年も続く町。
でも、希佐にとっては今年が初めて祝う誕生日。
「おめでとう」
そして希佐は祈るのだ。
来年も、そして再来年も。
今と変わらずこの場所で、仲間たちと一緒に誕生日を祝えるようにと。
「おめでとう……おめでとう」
希佐は静かに目を閉じる。
遠い未来を思い浮かべて。
――ありがとう。
どこからか遠く、そんな声が聞こえたような気がした。
(了)
