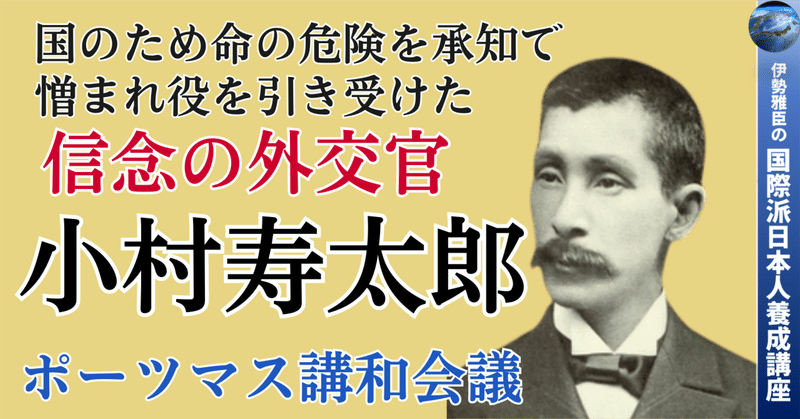
JOG(365) ポーツマス講和会議
国民の怒りを買うことを覚悟して、小村寿太郎は日露講和会議に向かった。
過去号閲覧: https://note.com/jog_jp/n/ndeec0de23251
無料メール受信: https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=172776
■1.「帰国するときは、人気は全く逆でしょうね。」■
明治38(1905)年7月8日、東京は曇天で蒸し暑かった。外相・小村寿太郎は桂太郎首相とともに、外務省から馬車で新橋駅に向かっていた。駅に近づくにつれて沿道の人の数は増していった。駅前に着くと、人々の間から万歳の声が起こり、国旗や旭日旗が大きく振られた。小村一行が馬車を降りると、歓声はさらに高まった。小村は低い声で桂に言った。「帰国するときは、人気は全く逆でしょうね。」桂は、黙って答えなかった。
小村は日本政府の全権代表として、これからロシアとの講和会議に臨むために、アメリカに出発する所だった。1月の旅順攻略、3月の奉天会戦、そして5月の日本海海戦と、帝国陸海軍は連戦連勝を続けていたため、国内世論は多額の賠償と領土割譲を期待していた。東京帝国大学の7人の教授が、最低限度の講和条件として償金30億円、樺太、カムチャッカ沿海州すべての割譲を求め、それが容れられない場合は戦争継続を、という決議書を政府に提出し、新聞はこれåを強く支持した。
しかし、ロシア側は満洲の兵力を急速に増強しつつあり、当然、講和会議でも強い態度に出るはずで、国民が期待するような講和条件を呑むべくもなかった。
全権として、これほど損な役回りはなかったが、小村は桂首相の指名をすぐに受諾した。開戦時にはロシアとの交渉に見切りをつけて主戦論を支持した手前、国民の怒りを買うことを覚悟の上で、責任をとろうとしたのである。送別会の席上では、元老・井上馨は「君は実に気の毒な境遇に立った。今まで得た名誉も地位も、すべて失うかも知れない」と涙ぐんだ。
小村全権一行は、横浜からアメリカに向かう客船「ミネソタ号」に乗り込んだ。波止場で幾重にもなって大歓声で見送る人々を見ながら、随員の一人は「あの万歳が帰国の時に馬鹿野郎の罵声ぐらいですめばいい方でしょう。おそらく短銃で射たれるか、爆裂弾を投げつけられるにちがいありません」と暗い顔をして言うと、小村はつぶやいた。「かれらの中には、戦場にいる夫や兄弟、子供が今にも帰してもらえるのだと喜んでいる者もいるはずだ。」
■2.ロシア全権との引き合わせ■
一行は7月19日にシアトルに上陸し、シアトル市民から盛んな歓迎を受けた後、鉄道でニューヨークに向かった。7月25日、ニューヨークに到着し、8月5日には仲介役のルーズベルト大統領の専用艦メイ・フラワー号に招待され、ロシア側使節と引き合わされた。
ロシア側全権は元大蔵大臣セルゲイ・ユリエウィッチ・ウィッテ。ロシア随一の政治力をもつ人物として名高かった。身長180センチをはるかに超える体格で、150センチにも満たない痩せた小村が並んで座ると子供のように見えた。
しかし、小村は平然とした顔つきで、ルーズベルト大統領の質問にも適切に答え、ロシア側に畏敬の念を与えた。ウィッテの方は努めて尊大に振る舞おうとしていたが、敗戦国の卑屈感が表情に表れ、目は落ち着きを失っていた。
■3.誠実さが外交の基本方針■
8月10日、講和会議がポーツマス市の海軍工廠で始まった。同市はニューヨークの北方4百キロの海岸沿いにある閑静な避暑地で、警備も容易なことから会議場に選ばれたのだった。
小村は会議の冒頭で、議事内容を外部には漏らさないとの同意をウィッテから取り付けた上で、日本側の講和条件をすべて提示した。小村が長い外交官生活を通じて基本方針としていたのは、歴史の浅い日本の外交は、手練手管では所詮、欧米の外交には対抗できないので、愚直に誠実さを貫くことだった。
講和条件は、桂内閣が小村の出発前にとりまとめたもので、「韓国からのロシア権益の撤去」「日露両軍の満洲からの撤兵」「ロシアの領有する旅順・大連などの租借権譲渡」を絶対譲れない3条件とし、それ以外の「賠償」「樺太割譲」などは「比較的必要条件」や「付加条件」としていた。戦争原因であったロシアの満洲・朝鮮への侵略さえ排除できれば、なんとか講和に持ち込みたい、というのが日本政府の本音で、領土や賠償金要求は小村の手腕に任されていた。
翌日の朝刊各紙には、日本側の提示した講和条件が一字一句の誤りなく報じられていた。ウィッテは日本側の要求を公表することで、その条件が過酷であることを内外に印象づけようとしたのである。しかし、事前に「樺太割譲」「25億円、ないし30億円の賠償」を日本が要求するだろうという推測が流れていたので、各国の新聞は賠償金額も明示しない日本案をかえって穏当なものと受けとめた。ウィッテの策略は逆効果だった。
■4.会議決裂も辞さず■
交渉は日本側の提案に沿って行われ、絶対譲れない3条件としていた「韓国からのロシア権益の撤去」「日露両軍の満洲からの撤兵」「ロシアの領有する旅順・大連などの租借権譲渡」については、字句上のやりとりはあったものの、おおむね日本側通りに妥結した。
8月15日、第4回目の会議で「樺太割譲」が取りあげられると、交渉は山場を迎えた。実は講和会議の直前、7月31日に日本は樺太全島を占領していた。わずかなロシア守備隊はいたが、その抵抗は微弱だった。これは小村が以前から強く主張していた作戦であった。満洲からロシア軍を駆逐しても、戦争が終結すれば清国に返還しなければならない。樺太ならロシア領として割譲を要求できるし、現実に日本が占領していれば、交渉の有力なカードとなる。
樺太割譲の要求に、ウィッテは「断じて同意しない」と言った。領土割譲は、大敗して戦争を継続する余力も尽きた国がすることで、ロシアはそのような状態とは全く違う、という理由だった。
小村は、1809年に間宮林蔵がそれまで半島だと思われていた樺太が島であることを発見し、大陸との間の海峡が「間宮海峡」と名付けられた事実を指摘して[a]、「あらゆる記録から見て、樺太を最初に領有したのは日本であり、日本が千島・樺太交換条約で樺太を譲ったのは、ロシアの圧力に屈したものであり、それはロシアの侵略行為であった、と指摘した。
小村は語調は鋭く、ウィッテの顔を見つめながら主張した。ウィッテの顔からは血の気がひいていた。小村が「あくまでも樺太割譲を要求する」と主張すると、ウィッテは「到底、日本の要求には応じられない。これ以上、会議を続けても意味はない」と会議の決裂をほのめかした。講和が決裂すれば、日本の満洲派遣軍は大幅に増強されつつあるロシア軍と新たな戦闘を強いられ、兵力も軍費も尽きた日本の存立は危うくなる。
しかし事情はロシア側も同じだ、と小村は思った。陸軍大佐・明石元二郎の働きで、ロシア国内の革命の動きは激化しつつあり[b]、これ以上戦争が長引けば、内乱が勃発する恐れもあった。小村は、自分の方から口を開くべきでない、会議決裂も辞さずというゆるぎない姿勢を貫くべきだ、と考えた。
しばしの静寂の後、ウィッテが折れて「会議を決裂させることは、私の本意ではない。この問題を後回しにして、他の条件の討議に移ってはどうか」と提案し、小村も同意した。
■5.決裂の危機■
しかし、もう一つの難題である償金支払いも、ウィッテは「このような要求を受け容れるなら、むしろ戦争を継続した方がいい」と突っぱねた。
ウィッテは次回18日の会議が終わり次第、講和成立を諦めてニューヨークに引き揚げることを記者会見でほのめかした。ロシア皇帝がウィッテに会議をただちに中止して帰国せよ、との指令を出した、という情報もしきりに流された。小村もポーツマスを引き揚げる準備を整えた。新聞には、会議は決裂の危機にある、と大きく報じられた。
18日の会談の冒頭、小村は樺太割譲と償金支払いに応ずるなら、ロシア海軍力制限など残る条件は撤回すると提案した。ウィッテは驚き、そして全権代表のみの秘密会談を申し入れた。
秘密会談では、ウィッテはロシア本国での強硬論の高まりに自分自身も苦しい立場にあると述べ、償金支払いは絶対に無理だが、樺太の南半分の割譲なら可能性がある、と提案した。小村は、「ロシア側が一歩譲るなら、我々も一歩を譲らぬでもない」として、すでに占領している樺太の北半分を返還するなら、相当の代償を支払って貰わねばならぬ、と応じた。ウィッテは「それも一理ある」と述べて、互いにこの案を本国に伝えて、指示を仰ぐこととした。
■6.「一握りの土地も一ルーブルの金も日本に与えてはならない」■
日本本国からは、小村の適切な努力で妥協の道が開かれたことは「帝国政府に於いて最も満足する所なり」と全面的な賛成の意向を打電してきた。
また、仲介役としてこの妥協案を聞いたルーズベルト大統領も、すでに占領している樺太の北半分を返還する以上は、代償金を支払うのは当然だとして、この案を全面的に支持する旨の親電をロシア皇帝に送った。
しかしルーズベルト大統領からの親電を受け取った皇帝は、電報用紙の端に鉛筆で「一握りの土地も一ルーブルの金も日本に与えてはならない」と書いて、ラムスドルフ外相に渡した。さらに追い打ちをかけるように、ウィッテに談判を打ち切るように指示した。そしてルーズベルト大統領には、妥協案をすべて拒否し、「自ら先頭に立って満洲に出陣する」と答えた。ルーズベルトは「ロシアには匙を投げた」と憤った。
8月26日の会議では、ウィッテは苦渋の色を浮かべて、ロシア政府の全面的拒絶を伝えた。小村は落ち着いた声で、「貴方達が平和のために尽力したことを、私も十分に知っている」と慰めた上で、もう一度だけ最後の会議を提案した。
■7.領土・償金要求放棄の決断■
各新聞は一様に、日本が樺太北部返還という譲歩を示したのに、それすら拒否しているロシアを激しく批判した。このまま談判が決裂すれば、世界の世論はロシアを非難し、嘲笑するだろう、とまで述べた。
日本では、決裂不可避との小村からの報告を受けて、元老、閣僚が対策を協議した。満洲のロシア軍は着々と増強が進み、今や日本軍の3倍にも達していた。一方、日本の軍費は底をつき、このままでは弾薬も糧食も底をついて、全軍が大陸の原野に立ち往生してしまうことが予想された。
結局、講和を成立させるには、樺太も償金も大譲歩をするしかない、との結論に達した。国内の新聞は、ロシアの強硬姿勢を突き崩せぬ政府に激しい非難を寄せている。そこにこのような譲歩をすれば、国内に大騒乱が起こることは明らかだった。また対外的にも、これではどちらが戦争の勝者か、分からなくなってしまう。
しかし亡国の危機を避けるには、それらに構っている余裕はなかった。元老、閣僚全員一致で要求放棄を決議し、明治天皇に報告すると、天皇はそれを期待したようで、即座に裁可を与えられた。 樺太も償金も放棄して、講和に応ぜよ、という暗号電文が小村のもとに届いたのが28日午後1時だった。暗号を翻訳した書記官は、突如、号泣し始めた。日本はロシアに屈服し、小村の努力も水疱に帰したのである。電報を読んだ小村は「まず代償金の撤回を声明して反応を伺い、それでもウィッテが少しの心の動きも見せない場合は、樺太全島を無条件で返還する方法をとる」と、冷静な口調で言った。
■8.講和成立■
しかし、その夜、新たな電報が飛び込んできた。イギリスの駐露大使からの情報として、ロシア皇帝が「償金支払い要求など断じて受けいれぬが、樺太はロシアが領有してからわずか30年ほどであるし、南半分を日本に譲る気持ちがないではない」と語ったという。世界各国のロシア非難の論調が圧力となったのだろう。
翌29日、最後の会議で、ウィッテはロシア側の回答を文書で提出した。イギリスからの情報通り、金銭支払いは拒否するが、樺太の南半分の譲渡に同意する、というものだった。ウィッテは小村の表情を不安そうに伺った。
小村の方も、日本側の覚え書きを差し出した。それには「日本の償金支払い要求は正当な理由があるが、一つは人道と文明のため、一つは日露両国の真の利益を考えて、その要求を撤回する」と書かれていた。ウィッテは顔を紅潮させて喜びをあらわにした。
翌朝の新聞は、講和成立の記事で埋め尽くされ、ウィッテの外交手腕と日本の寛大さが賞賛された。ルーズベルト大統領の親友として、ニューヨークで対日世論工作にあたっていた金子堅太郎の次の声明が大きく掲載された。
日本政府が戦勝国として当然の理由をもつ償金支払い要求を潔く撤回したのは、日本人が金銭よりはむしろ人道を重んじ、文明を尊び、世界の平和を愛する人種であるからにほかならない。私事であれ国事であれ、われら日本人は金銭よりも名誉を重んじる。
■9.出迎え■
9月1日、日本国内の新聞各紙は、日露講和条約の成立を大きく報ずると共に、「この屈辱」「あえて閣臣元老の責任を問う」などとロシアに屈した軟弱外交を責め立てた。5日には日比谷公園広場で講和反対の国民大会が開かれ、3万人もの参加者が暴徒と化して、市内の2百以上もの派出所が焼き払われた。小村の家族の住む外相官邸も放火され、群衆が門の内部にまで入り込んだが、近衛師団が駆けつけて排除した。
小村は会議後、高熱を出して、ニューヨークのホテルで療養していたが、なんとか小康状態を取り戻し、10月17日、横浜港に到着。そのまま特別仕立ての汽車に乗って、午後4時に新橋駅に着いた。一般の乗客は遠ざけられ、プラットフォームには着剣した兵が整列していた。
桂首相や山本海相が迎えに出て、小村の両側に立ち、その腕を抱えてプラットフォームの出口に進んだ。小村に爆弾か銃弾が浴びせられた折りには、共に斃れることを覚悟していたのである。
(文責・伊勢雅臣)
■リンク■
a.JOG(302) 間宮林蔵の樺太探検 ロシア艦来襲時の敗走者との汚名をそそぐべく、林蔵は命をかけた樺太探検に乗り出した。
b.JOG(176) 明石元二郎~帝政ロシアからの解放者 レーニンは「日本の明石大佐には、感謝状を出したいほどだ」と言った。
■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)
→アドレスをクリックすると、本の紹介画面に飛びます
1. 吉村昭、「ポーツマスの旗」★★★、新潮文庫、S58
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ おたより _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■「ポーツマス講和会議」について
Yuzoさんより
最後の小村外相を、桂首相などが、抱きかかえるように車に乗せた場面が、とくに印象に残っています。「けしからん」といって憤り、何も知らない勇ましい連中による、彼への狙撃を、3人が身をもって防いだというのは、感激と感動を覚えずにおられません。
ついでに、うろ覚えのことですが、桂首相や他約2名が、やはり日露戦争の戦費調達に四苦八苦して、米・英からの援助に頼むほかないと考えていたときのことを思い出しました。このとき、確か、高橋是清さんを、新橋かどこかの料亭に招いて、「是非、君に、この大任をお願いしたい」と懇々と説得されたようです。
しかし、「こんな大役、とても果たせない」と再三辞退されてしまった後、どうにか諒解を得たときに、「これで、日本は救われる」といって、皆抱き合って、感激の余り涙を流して喜び合ったという場面です。
やはり、こういう至誠の人たち、豊かな感激・感動の精神をもった人たちがいたおかげで、あれほどの勃興も、真の日本の発展も成されたのかなと思いました。今後の日本も、こういう人たちがたくさん輩出して、政治から企業から真に立派になってほしいと思います。
hiroshiさんより
貴メルマガを読んで、明治人の死生観の一部分を感じ、本当にそのつめの垢でも煎じて飲みたいと思うときが度々あります。今回のメルマガを読んでもそう思いました。特に最後の部分『桂首相や山本海相が迎えに出て、小村の両側に立ち、その腕を抱えてプラットフォームの出口に進んだ。小村に爆弾か銃弾が浴びせられた折りには、共に斃れることを覚悟していたのである。』を読んだとき、涙が出てパソコンの前で泣いてしまいました。
なんて凄い人達だろう!自分の死を冷静に考え、死以上のものに自分を委ねる、真剣に冷徹に国の現実と将来を思う、その姿勢には本当に頭が下がります。
Kazyさんより
今号を拝読致しまして、当時の外交官の外交手腕に改めて感銘を受けました。自らの名誉も地位も、そして場合によっては、命をも、かなぐり捨てる覚悟で、国家の長い未来を見据えた外交交渉を信念を貫き通して行う姿勢は、我が国のみならず、世界の外交官の鑑とも言える偉業であったと思います。
翻って、今日の、看板だけは「外務省」ですが、実状は「外媚省」とでも言いたくなるような体たらくを見るにつけ、この差は一体どこから来たのかと疑問に思うことしきりです。
「公のために私を滅することも厭わない」精神、明治維新から日清・日露の戦役に至る動乱の時代ゆえに備わった感性、動乱の時代を生き抜いた類稀な人生経験、など、考えるときりが無いですが、結局のところ、「自らの立場と使命を厳しく真剣に自覚し、周囲の情勢を冷静かつ的確に捉え、皆のために良かれと自ら信ずる道を貫く」その姿勢ではないかと思います。そして、現在の官僚や政治家と呼ばれる人たちの大多数に最も不足しているように思えます。
我が国の幸いなところは、産業界には、そのような精神を持ち、また、実践している方々が、町工場から大企業まで多くいて、そのような方々が生産・経済活動の中核にいることではないかと思いました。
■ 編集長・伊勢雅臣より
公にために尽くした人々は同時代の同胞のためのみならず、我々子孫にも貴重な精神的財産を残してくれています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
