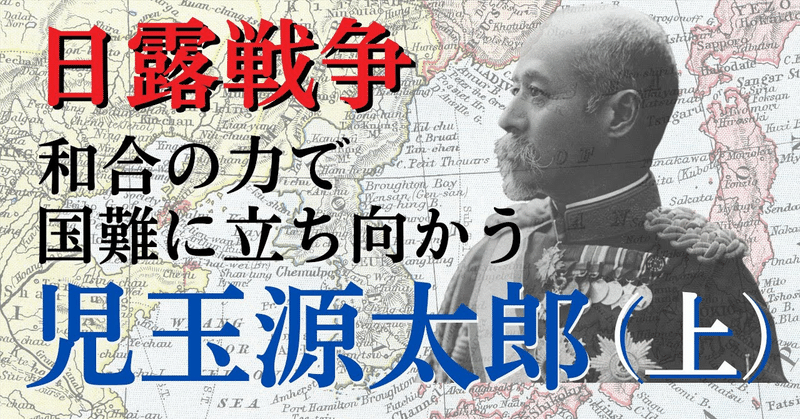
JOG(385) 救国の軍師・児玉源太郎(上)
児玉源太郎は自ら2階級下の参謀次長となって、この国難に向かっていった。
過去号閲覧: https://note.com/jog_jp/n/ndeec0de23251
無料メール受信: https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=172776
■1.フロックコートから軍服へ■
明治36(1903)年10月12日朝、参謀本部に突如、内相兼台湾総督の児玉源太郎が現れた。いつもはフロックコート姿なのに、今日は軍服に黄金色の参謀肩章を右胸に吊っている。
児玉は参謀たちの中に田中義一少佐を見つけると、両手で軍服の両袖をつかんで、奴凧(やっこだこ)のように両手を広げ、「おい、田中、これでよかろう」と言った。田中は体を震わせながら「はい、まことに結構であります」と答えた。
前参謀次長・田村怡与造が肺炎で急死したのが10月1日。ロシアとの戦争が避けられない状況の中で、日本陸軍は作戦計画・指導の中心を失って、重大事態に陥っていた。ロシア相手の国運を賭けた戦争となれば、その指導者は作戦計画における知謀だけでなく、国家内外の大局にも通じ、全軍にゆるぎない信頼を受ける人物でなければならない。それには児玉源太郎しかいない、というのが、政府・陸軍を通じて、衆目の一致した所であった。
しかし問題は、すでに内相・台湾総督である児玉を参謀次長に据えれば、今日で言えば副首相を2階級下の防衛次官に降格するようなものである。首相の桂ですら、児玉に直接、言い出せないでいた。業を煮やした若手参謀の田中義一少佐が、児玉の家にやってきて「軍人のくせに、フロック・コートを着て、重大な軍事的機会を忘れちょる閣下がおります」と当てつけたのである。[a]
児玉自身も、この亡国の危機には自分が出るしかないと思っていたのであろう。ついに首相官邸に出向いて、自ら参謀次長になると申し出た。児玉がフロックコートを軍服に着替えて、参謀本部に現れたのは、その2日後のことであった。
総務部長の井口省吾少将は感激して、この日の日記に「もって天のいまだわが国を棄てざるを知る」と書いた。乃木希典は児玉の志に感動して漢詩を作り、「報国尽忠ノ人」と呼んだ。
■2.「どんな無理をしても、戦費調達をやりましょう」■
翌13日、児玉は財界大御所とも言うべき渋沢栄一を訪ねた。ロシアと戦うのに必要な膨大な戦費を何とか調達せねばならない。渋沢は「ロシアと戦うだけの金など、日本中の銀行の金庫からかき集めても足りない」と突っぱねていた。[b]
児玉は渋沢につぐ財界の有力者である日本郵船社長の近藤廉平に会い、満洲の様子を見てきてほしい、としつこく頼んだ。近藤が行ってみて、「満洲の大平原はロシア軍の大部隊に覆われている」と報告すると、渋沢は顔色を変えた。
参謀次長として現れた児玉に、渋沢は勝つ見込みがあるか、と尋ねた。
__________
勝つまではゆきません。総力をあげ、なんとか優勢に持ち込み、外交によって戦を終わらせてもらう、というところです。作戦の妙を得、将士が死力を尽くせば、いまなら、なんとかやれる。日本はここで、国運を賭して戦う以外に道はない。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
こう答えながら、児玉の両眼に涙がどっとあふれ出た。渋沢も涙を流した。
__________
児玉さん、わたしも一兵卒として働きます。どんな無理をしても、戦費調達をやりましょう。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■3.「陸海対等で仲よくやろうじゃないですか」■
2日おいて15日、今度は児玉は海軍大臣の山本権兵衛(ごんべえ)を訪ねた。山本は「韓国などは、ロシアにとられても構わない。日本は固有の領土を防衛すればよい」と広言していた。
児玉は一人で海軍大臣室に入り、自分が参謀次長になったいきさつ、渋沢が開戦を覚悟してくれた事などを語った。山本はひざを乗り出さんばかりに耳を傾け、児玉が「もしやると決まりましたら、陸海対等で仲よくやろうじゃないですか」と言うと、山本は、我が意を得たりという表情で「やりましょう」と力強く答えた。
児玉は陸海軍の「共同和合」が対ロシア戦の急務だと考えていた。満洲に陸軍の軍勢を送るにも、兵器・食料を運ぶにも、海軍の協力が不可欠である。しかし従来からの「陸主海従」の慣習に海軍が不満を持ち、両者の協力は円滑ではなかった。そこで児玉は「陸海対等で」と持ちかけたのである。
児玉の私心のない腹を割った話に、山本もこの際、私情を棄てて最善を尽くさねばならない、と思った。翌日の部長会では「つまらない意地は棄てる。要は、帝国の危急を救い、終局の大功を収めることにある。みなもこの点をとくと承知してもらいたい」と一同に語った。 同時に、児玉と会った翌々日17日に、常備艦隊(後の連合艦隊主力)司令長官を、日高壮之丞(そうのじょう)中将から、東郷平八郎中将に変えた。日高は山本の子供の頃からの友人だったが、自負心が強すぎて土壇場で大本営の言うことを聞かない恐れがある、と考えたのである。この私情を殺した人事が、後に日本海海戦の勝利として結実する。
■4.「ロシアにたいする政戦略を完全に一致させていただきたい」■
10月19日、児玉は伊藤博文を訪ねた。伊藤は田村・前参謀次長から「わが軍備はまだ充実していない」と聞いて、開戦をためらっていた。児玉は、現在なら勝てないことはないが、このままロシアの軍備増強を許せば、ますます不利になる、と説いた。
__________
今後、わたしは、(自分の上長であり、陸軍の最高責任者である)山県元帥に報告する情報のすべてを、かならず伊藤侯にも報告させます。伊藤・山県両侯が一体となって元老会議を指導し、ロシアにたいする政戦略を完全に一致させていただきたいのです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
山県と仲の良くない伊藤は、あれこれと口を出したが、児玉はときには大声で反論し、ときには懇切に説明した。ついに伊藤は顔色を和らげ、「君は政戦略の両面を見て、大局からわたしを補佐してくれるただひとりの人物じゃ」と言い、児玉の進言に同意した。
こうしてわずか10日ほどのうちに、児玉は陸海軍、政財界の総意をまとめあげ、一致協力してロシアの侵略に立ち向かう体制を作り上げてしまった。
「勝敗のカギは人にある。日露両国の最高指導者をめぐる人の和の総合力が、勝敗を決定する」というのが、児玉の考えだった。
■5.皇帝とベゾラフゾフ一派の私心■
児玉の私心のない働きによって、いち早く「人の和の総合力」を築き上げた日本に対して、ロシアはどうであったか。
ロシア皇帝の寵臣ベゾラフゾフは満洲と朝鮮の国境をなす鴨緑江(おうりょっこう)で植民地経営を行う鴨緑江木材株式会社を経営していた。この年の5月には、ロシア軍は鴨緑江河口の朝鮮側にある竜岩浦(りゅうがんぽ)に侵入し、宿営地を作り始めた。軍と会社が一体となって、極東侵略を進めていたのである。
ロシア陸将のクロパトキンは、ウィッテ蔵相・ラムスドルフ外相の同意を得て、この会社が日本との衝突の原因になりかねない事から、その利権を外国商社に転売すべき、と上申した。
しかしベゾラフゾフ一派は、皇帝に「日本軍などは問題にならない。兵力を増強すれば、ロシアが満洲、朝鮮を、イギリスのインドのようにすることは、すこしも困難でない」と報告した。この会社から多額の機密費を受け取っている皇帝は、これに賛成して、クロパトキンらの上申を退けた。
ベゾラフゾフが皇帝を取り込み、慎重派の中心者ウィッテを失脚させると、クロパトキンもただちに陸相を辞任した。ベゾラフゾフはさらに自派のアレクセーエフを極東総督とするよう皇帝に進言して、受け入れられた。
アレクセーエフは、「満洲・韓国の境界に中立地帯を」と要求する日本側の外交文書を皇帝に送る際に、次のような意見を添えた。
__________
日本は兵も少なく、財政も貧困である。・・・だから日本は戦争には訴えない。ロシアは強硬な態度を取り続けるべきである。日本はかならずロシアの言うとおりになるであろう。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
もっともウィッテやクロパトキンは慎重派ではあったが、和平派であったというわけではない。彼らはまずシベリア鉄道を完成させ、それによって極東でのロシア軍を充実させるまでは日本と事を構えるべきではない、と考えていたのである。この路線でロシア政府内がまとまっていたら、数年のうちに満洲・朝鮮はずるずるとロシアの勢力下となり、日本は「ロシアの言う通りになる」属国に転落していたであろう。
経済力、軍事力に勝るロシアが、唯一日本に劣っていた点があるとすれば、自らの野心から強硬に満洲・朝鮮での利権拡大を狙うベゾラフゾフ一派によって「人の和の総合力」がかき乱されていた、という点であろう。
■6.「コダマがいるかぎり、日本陸軍がロシア陸軍に勝つ」■
児玉は対露開戦で国内の政戦略を一本化する傍ら、次長室に1ヶ月ほど泊まり込んで、対露作戦を練った。12月30日に行われた初の日本陸海軍合同作戦会議では、次のような作戦協定が結ばれた。
__________
陸軍は鴨緑江以南の朝鮮半島を、いちはやく占領する。機を見て鴨緑江以北の南満洲に進出し、積極的にロシア軍を撃破する作戦を取ることもある。
海軍は開戦劈頭(へきとう)、旅順のロシア主力艦隊にたいして、駆逐隊による夜襲を行い、甚大な損害を与える。陸軍はそれを成功させるために、京城に急派する部隊の朝鮮上陸行動を、海軍の統制に従わせる。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ドイツ陸軍から派遣されて陸軍大学校の戦術教師をしていた恩師メッケルの「敵の機先を制し、兵力を集中して戦え」という言葉を、陸海軍の緊密な連携のもとに実践する作戦だった。
明治37(1904)年2月8日夜、日本の駆逐艦10隻が旅順港口外に停泊中のロシア太平洋艦隊を魚雷攻撃して、日露戦争が始まった。ドイツに帰っていたメッケルは、戦争の予想を聞きに来た新聞記者たちに対してこう言った。
__________
日本が勝つ。日本にはゲネラル(将軍)・コダマがいる。コダマがいるかぎり、日本陸軍がロシア陸軍に勝つ。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■7.北進続ける日本陸軍■
黒木為楨(ためもと)大将率いる第一軍主力は、2月16日から仁川に上陸し、朝鮮半島を北進した。4月30日には、鴨緑江が黄海に注ぐ河口近くに設けられたロシア軍陣地に12センチ砲20門の砲弾を数時間も叩き込み、その後に鴨緑江を渡って、要地・九連城を占領した。ロシア側の兵力2万に対し、日本側は4万、砲火器も日本軍が優勢だった。兵力を集中して、緒戦から圧倒するという児玉の作戦通りの戦いであった。
勇猛果敢で世界に名高いロシアのコザック軍を日本軍が打ち破り、九連城を占領したとの報告を受けた児玉は男泣きに泣いた。ここで負ければ日本陸軍の前途はなく、ひいては日本の前途もない、と思っていたのである。九連城を落とした第一軍は、勢いに乗って、戦う毎に勝ち、北進を続けた。
同時に、第二軍は遼東半島のくびれた部分にある金州・南山要塞に襲いかかった。ここを占領して、その先端部にある旅順要塞を満洲から分断して無力化してしまおう、という戦略である。ロシア軍の要塞は強固で、4千名以上もの死傷者を出したが、海軍の砲艦隊の援護射撃を受けて、占領に成功した。目的を達した第二軍は満洲の遼陽を目指した。
■8.陸海軍の「共同和合」の綻び■
しかし、旅順港については、海軍は自ら攻めるので、陸軍は関与しないで欲しい、と主張していた。海軍の手柄にしたい、という私心であろう。児玉が腐心していた陸海軍の「共同和合」が綻びを見せた。そこから日露戦争における最大の危機が広がっていく。 海軍は廃船を旅順港口に沈めて、太平洋艦隊を閉じこめるという作戦を3回も試みたが、要塞からの猛攻に阻まれ、いずれも失敗した。軍神・広瀬少佐の戦死は、この2回目である。[c]
海軍は音をあげて、陸軍に陸から旅順要塞を攻略してくれ、と頼みこんだ。児玉はすでにこの事態を想定して、乃木希典率いる第三軍を編成していた。
■9.日本の命運がかかった旅順攻略■
しかし、旅順はセメント20万樽で固めた大要塞であり、野砲の砲弾ぐらいではびくともしない堅牢さを誇っていた。大砲は陸正面に向かっているものだけでも488門、機関銃も数百挺備えられていた。
海軍は、旅順港内のロシア艦隊を砲撃するために、港内を見下ろせる203高地をすみやかに占領して欲しい、と要請したが、第三軍の伊地知・参謀長は陸軍には陸軍の方針がある、と突っぱねた。そして8月19日から5万7百余人の勢力で正面からの総攻撃を敢行したが、死傷者じつに1万5千8百人という惨憺たる結果に終わった。
8月30日には第1、2、4軍13万が遼陽において22万のロシア軍と激突した。黒木大将率いる3万人が夜、太子河を渡って、奇襲を敢行するなど思い切った戦術をとり、不意をつかれたロシア軍を奉天に退却せしめた。
一方、乃木の第三軍は11月に入っても旅順を攻め落とせないでいた。すでにバルチック艦隊はロシア本国を出港し、来年の1月頃には日本近海に現れる。迎え撃つ連合艦隊としては艦船の修理・整備のために、12月10日までに旅順港に潜む太平洋艦隊を撃滅しておく必要があった。
また、ロシア陸軍も奉天で着々と増強しつつあった。早く第三軍が旅順を攻略して駆けつけないと、次の会戦での日本軍の勝ち目はなかった。乃木の第三軍がいつ旅順要塞を攻略できるのか、日本の命運はこの一点にかかってきたのである。
(文責・伊勢雅臣)
■リンク■
a. JOG(108) 台湾につくした日本人列伝 これらの人々はある種の同胞感を抱いて、心血を注い で台湾の民生向上と発展のために尽くした。
b. JOG(279) 日本型資本主義の父、渋沢栄一 経済と道徳は一致させなければならない、そう信ずる渋沢によって、明治日本の産業近代化が進められた。
c. JOG(228)広瀬武夫を敬愛したロシアの人々 ペテルブルグの人々に深い敬愛の念を与えて、海軍大尉・広瀬武夫は帰っていった。
■参考■
(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)
→アドレスをクリックすると、本の紹介画面に飛びます。
1. 生出寿『謀将 児玉源太郎』★★★、徳間文庫H4
2. 古川薫『天辺の椅子: 日露戦争と児玉源太郎』★★、文春文庫、H8
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ おたより _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■「救国の軍師・児玉源太郎(上)」について hiroさんより
日露戦争に国家の存亡がかかっていた事が本当に実感出来た。また、児玉が私利私欲を捨てて国家の首脳達を説得して回った事で、国家が一丸となっていった経緯など、まるで坂本龍馬のような働きをしていると感じた。今の政治家の目に余る腐敗堕落ぶりを児玉源太郎さんに一喝して貰いたい。
■ 編集長・伊勢雅臣より 一国が興るのも、滅びるのも、「人」ですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
