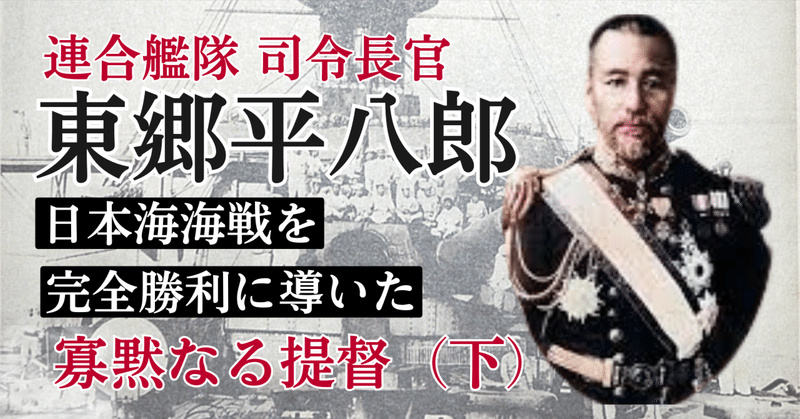
JOG(400) 東郷平八郎 ~ 寡黙なる提督 (下)
日本海海戦に向かう東郷提督の静かなる闘志
【お詫びと訂正】
動画中(12分17秒あたり)、第26代セオドア・ルーズベルト大統領の画像を掲載すべきところ、誤って第32代フランクリン・ルーズベルト大統領の画像を掲載してしまいました。正しくは以下の画像になります。お詫びして訂正いたします。

過去号閲覧: https://note.com/jog_jp/n/ndeec0de23251
無料メール受信:https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=172776
■1.敵を待つ■
明治38(1905)年5月22日、2隻のロシア軍艦が九州南端の沖を北北西に向けて進んでいるのを発見したとの報告が、連合艦隊旗艦・三笠にもたらされた。幕僚の中には「敵艦隊は津軽海峡か宗谷海峡に向かうのでしょう。その作戦と思われます」と会議で主張する者もいた。
東郷は「陽動作戦である。たいして気にとめぬがよい」と静かな口調で言った。またウラジオストックの敵艦2隻が出撃したなどとの報告が届いたが、東郷はこれも敵の牽制作戦とみて動かなかった。
バルチック艦隊が対馬海峡を通過するとすれば、その速度から推定して、25日あたりには姿を現すはずであった。ところがいっこうに敵は姿を見せない。
実はバルチック艦隊は艦隊速度を落として、水雷艇の攻撃を避ける練習をしたりしていたのだったが、そんな事は知るよしもなく、東郷と連合艦隊はひたすらに敵を待った。
■2.「本日天気晴朗なれども波高し」■
5月27日午前4時45分、五島列島の近海から「敵の艦隊発見」の無電が届いた。バルチック艦隊は東北東に針路をとり、対馬東水道に向けて進行中であった。ただちに大本営向けに最初の報告文が打電された。
__________
敵艦見ゆとの報に接し、連合艦隊は直ちに出動。之を撃滅せんとす。本日天気晴朗なれども波高し。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
艦隊はウラジオストックまで追跡するのに必要な石炭を甲板に積んでいたが、東郷の指示で海中に投げ捨てた。その後、乗組員は石炭投棄で汚れた体を洗い清め、清潔な下着と軍服に着替えた。負傷した時に、黴菌に冒される恐れを少なくするためである。また砲弾発射の煙から目を守るための硼(ほう)酸水と、鼓膜を守るための耳栓が配られた。まるで戦国武将が静かに戦支度を整えているかのようである。
これに対して、バルチック艦隊の各艦は、ウラジオストックにたどり着くのに必要な量の3倍以上の石炭を甲板上にまで積み込んでいた。このために運動速度の低下を来たし、さらに日本艦隊の命中弾を受けた際に激しい火災に見舞われることになった。また日本艦隊が待ち受けていると予想される対馬海峡に進入した際にも、なお平時における密集縦隊のままであって、戦闘隊形をとっていなかった。バルチック艦隊の戦闘意思はいささか散漫だった。
午後1時37分、北東に進むバルチック艦隊の姿が見えた。1時55分、東郷は旗艦・三笠のマストにZ旗を掲げさせた。
__________
皇国の興廃此の一戦に在り各員一層奮励努力せよ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
この時、東郷は最上艦橋に立ち、右手には大きな双眼鏡を持って胸のあたりに置き、左手は長剣の柄を握りしめ、静かに敵を睨みつけていた。この敵を撃滅しなければ祖国の明日はない。東郷の静かな、しかし断固たる戦闘意思が連合艦隊の一人一人に伝わった。
■3.敵前回頭■
このままでは西に向かう連合艦隊は北東に進むバルチック艦隊と、すれ違ってしまう。その際に撃ち合っても、撃ち漏らした敵には、その後で反転しても追いつけない。
連合艦隊が敵の前面を横切った所で、幕僚の一人が怒鳴るように言った。「(敵の旗艦)スウォーロフは(距離)8千。どちらの側で戦をなさるのですか」 その時、東郷の右手がさっと左方に半円を描いた。東郷と顔を見合わせて頷いた加藤参謀長の甲高い声が響いた。「艦長、取舵一杯に」伊地知・三笠艦長が「え、取舵になさるのですか」と聞くと、参謀長が「左様、取り舵だ」
三笠は艦首を左に急転し、180度反転して、今度は敵の先頭を左から横切ろうとした。これを見たあるロシア将校は「自分の眼を信ずることができなかった」と手記に書いている。回頭点では砲撃の静止目標となるからである。
この時とばかり、ロシア艦隊は先頭の三笠に射撃を集中した。数分の間に300発以上の砲弾が三笠の周辺に降りそそいだが、一発も当たらなかった。東郷はこれまでの海戦で、ロシア側の射撃能力では8千メートルの距離からでは命中しないことを知っていたのである。
三笠が回頭を終え、敵の進路を塞ぐ位置についた。ロシア艦隊との距離は6千4百メートルにまで縮まっていた。「撃ち方始め!」の号令がかかり、右舷の諸砲がいっせいに火をふいた。
■4.戦闘■
旗艦スワロフの状況が次のようにロシア側に記録されている。__________
スワロフはもっとも優勢な戦艦六隻の標的となった。その砲弾はまるで烈しい霰(あられ)のように落下した。砲弾は榴弾で、これが炸裂すると、何千というこまかな破片になって飛び散り、物凄く大きな火焔と、息も詰まるような黒色か淡黄色の煙の渦巻がパッとひろがったかと思うと、可燃物という可燃物は総なめで、鉄板に塗ったペンキさえ、みるみる燃えてしまった。・・・
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ロシア艦隊の砲弾は、装甲部を貫いて一定の深さまで到達しなければ炸裂しなかったが、連合艦隊の使用した砲弾は強力な下瀬火薬を充填してあり、当たりさえすれば瞬間的に火災を起こして、敵艦の戦闘能力を奪ってしまうのである。
__________
こんどは司令塔ののぞき孔で敵弾が炸裂した。・・・司令塔内にいた人々の一部は即死し、残りは全部が負傷した。提督も負傷した。飛んできた弾片で、頭を割られたのだ。舵輪も被害をまぬがれなかった。操縦する者のないスワロフは、盲人みたいにぐっと横にそれて、戦列をはなれてしまった。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
こうしてバルチック艦隊の艦船は次々に集中砲火を浴び、同様の運命をたどった。隊形は乱れ、各艦はバラバラに潰走を始めた。それをさらに連合艦隊の駆逐艦、水雷艇が肉薄して魚雷攻撃をか、次々と沈めていった。沈没した艦船から海上に脱出した多くのロシア将兵は、日本の艦船がボートで救助した。
昼間の戦いを終えて、東郷が最上艦橋を離れるとき、立っていた足あとだけがくっきりと激浪の飛沫にぬれずに残っていた。
■5.「とても人間業とは思えません」■
負傷したロジェストウェンスキー中将から、艦隊指揮権を任されたネボガトフ少将は、翌日、わずかに残った数隻の艦船とともに、降伏信号を掲げた。ネボガトフとその幕僚は旗艦・三笠の将官室で降伏協定を結び、ともに杯をあげて戦闘の終了を祝しあった。一段落したあと、ネボガトフは東郷にこう聞いた。
__________
貴官は、どうして、わが艦隊が宗谷とか津軽海峡を選ばずに、朝鮮海峡を通ると判断されたのですか? とても人間業とは思えません。教えてください、その判断の根拠を!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ロシア側は、日本艦隊の全勢力が対馬海峡の一点に集中しているとは、まったく想像もしていなかったのである。東郷は、口許に苦笑を浮かべてこう答えただけであった。
__________
そう信じたまでです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
なおも首をかしげているネボガトフに、東郷はこう言った。
__________
よくもはるばる1万5千海里を航破してここまで来られましたな。その勇気と技倆には、敬服のほかはありません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
結局、バルチック艦隊の38隻のうち、撃沈19隻、捕獲5隻。マニラや上海に逃げ込んで、武装解除されたもの6隻。遠く本国に逃げ帰ったもの1隻。目的地たるウラジオストックに逃げ込めたのは3隻だけだった。バルチック艦隊は東郷が約束した通り「撃滅」された。世界海戦史上に残る大勝利であった。
■6.「敗れたからといって、恥ずる必要はないと思います」■
重傷を負ったロジェストウェンスキー中将を乗せた駆逐艦ベドウイも白旗を掲げて降伏した。中将は汽船で佐世保の海軍病院に運ばれて、手当を受けた。
6月3日夕刻、東郷は花束を持って、海軍病院に見舞いに出かけた。ロジェストウェンスキーは、頭に包帯を巻き、血の気のなくなった顔に微笑を浮かべて、半身を起こして東郷を迎えた。東郷はベッドに近づき、その手を握ってこう言った。
__________
勝敗は軍人を志した者にはつねにつきまとって離れないものです。敗れたからといって、恥ずる必要はないと思います。要は本分をつくしたか否かにかかっています。貴官は有史以来、前例のない1万数千海里に及ぶ航海を大艦隊をひきつれて遠征してこられました。しかも今日の海戦で貴艦隊の将兵は、実によく勇戦され、感心しております。
貴官が重傷を負ってまで敢然として大任を尽くされたのに、小官は心から敬意を表します。当病院は俘虜収容所ではありません。諸事不自由でしょうが、どうか、自重自愛されて、一日も早く速やかに快癒されるよう祈ります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ロジェストウェンスキーは感激して、もう一度、東郷に握手を求め、うつむき加減に涙をこらえながら言った。
__________
名誉の高い貴官の鄭重な訪問に接したのを光栄に思います。貴官の温情は、小官をして負傷の苦痛を忘れさせたほどです。感極まって、言葉も出ないくらいであります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
両眼に涙をため、ふかくうなだれたロジェストウェンスキーは、神への感謝を込めて、十字を切った。
■7.「武人として、この上もない幸せ」■
明治38(1905)年12月20日、連合艦隊の戦時編制が解かれ、その解散式で東郷は解散の辞を読み上げた。原文は秋山参謀の起草になる格調高い漢文調であるが、その一部を現代文に要約してみよう。
__________
過去1年半、風波と戦い、寒暑を冒し、しばしば強敵とまみえて生死の間に出入りしたことは、容易な業ではなかったが、考えてみると、これまた、長期の一大演習であって、これに参加し、多くを学ぶことができたのは、武人として、この上もない幸せであった。・・・
翻って、西洋史を見るに、19世紀の初め、ナイル及びトラファルガー等の海戦に勝ちたる英国海軍は祖国を泰山の安きに置きたるのみならず、それ以後の後進は、よくその武力を保有し世運の進歩に後れなかったので、今に至る迄永くその国益を擁護し、国権を伸張するを得た。・・・
我ら戦後の軍人は深くこれらの事例に鑑(かんが)み、今までの練磨に加うるに戦役の実体験を以ってし、更に将来の進歩を図りて時勢の発展に遅れないよう期すべきである。・・・
神明はただ平素の鍛練に努め、戦はずして既に勝てる者に勝利の栄冠を授くると同時に、一勝に満足して治平に安ずる者よりただちにこれを奪う。
古人曰く勝って兜の緒を締めよ・・・と
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
英国海軍を例に挙げているのは、英国に留学して、その海軍に学んだ東郷の若き日の思いからであろう。その英国海軍のように、厳しい平時の訓練と絶えざる技術の進歩によって、護国の大任を果たすことが、軍人としての使命であり、また幸福でもあった。
■8.ルーズベルト大統領の注目■
米国ルーズベルト大統領は、この辞を読んで、次のような書簡を海軍長官あてに送った。
__________
アドミラル東郷は古今の偉大な海の闘将の一人に仲間入りした。戦いが終わり、彼が指揮した連合艦隊が解散されるに当たって、東郷の行った訓示は、わが海軍省の一般命令にもこれを挿入すべきであると、余をして考えさせたほど、注目すべきものであった。海上であれ、陸上であれ、強い軍人を作る根本、すなわち強い陸海軍を作る根本はいえずれの国においても皆同じである。[2,p382]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ルーズベルト大統領の命令で、米海軍内で日本海軍の研究が始まった。当時下級士官であったチェスター・ニミッツは、その研究を通じて、最高指揮官としての模範を東郷に見いだし、その神髄を学び取っていた。ニミッツは、昭和9(1934)年、東郷の国葬の時にも、米国アジア艦隊司令長官の乗り込む旗艦オーガスタの艦長として、来日した。
後にニミッツは米・大平洋艦隊司令長官となって、日本海軍を撃破し、昭和20(1945)年9月2日、アメリカ合衆国の全権の一人としてミズーリ艦上で日本降伏受託書に署名した。
■9.『三笠と私』■
ニミッツは、横須賀に係留されていた戦艦・三笠が戦争中は真鍮や銅の付属品を軍需資材として持ち去られ、戦後はダンスホールに使われているのを知り、『文藝春秋』昭和33年2月号に『三笠と私』と題する一文を発表した。
__________
この有名な軍艦がダンスホールに使用されたとは嘆かわしい・・・
どういう処置をとれと差出がましいことはいえないが、日本国民と政府が全世界の海軍々人に賞賛されている東郷提督の思い出をながらえるため、適切な方法を講ずることを希望する・・・
この一文が原稿料に価するならば、その全額を東郷元帥記念保存基金に私の名で寄付させてほしい・・・[a]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これを機に日本人の間にも三笠保存の動きが急速に盛りあがった。ニミッツの意を受けた米海軍は横須賀にあった廃艦一隻を日本に贈与し、スクラップにして得られた約3千万円を三笠の復元に充てさせた。ニミッツのお陰で「記念艦三笠」は復元され、今も当時の勇姿を見せている。
艦内には当時の遺品、記念品が多数展示されているが、その一つに東郷を中心として海軍幹部たちが並んだ写真があった。まるで青年のように気概に溢れた凛々しい表情に、筆者はしばし見入った事を記憶している。
(文責:伊勢雅臣)
■リンク■
a.JOG(236) 日本海海戦 世界海戦史上にのこる大勝利は、明治日本の近代化努力の到達点だった。
b. 名越二荒之助、「記念艦三笠とニミッツ提督」
■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)
1.下村寅太郎、『東郷平八郎』★★★、講談社学術文庫、S56
2. 真木洋三、『東平八郎 下』、★★★、文春文庫、S63
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ おたより _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/■
前号「東郷平八郎 ~ 寡黙なる提督 (下)」について
「省三」さんより
400号発刊おめでとうございます!
最近貴誌をしりまして、愛読させていただいております。ほぼ8年間に亘って、継続して発行することは、並大抵の努力ではなかったかと存じます。1000号発行に向かってさらに頑張ってください。一読者として大いに楽しみにしております。
また、本日の記事は、胸が熱くなるような気持ちで読ませていただきました。簡潔に、そして淡々とした筆調でありながら、読者の気持ちを熱くさせる筆力には大変感じ入りました。おそらく、編集長の東郷提督に対する尊敬の念がそうさせたのでしょう。
ありがとうございました。ますますのご活躍を期待しております
「84歳の元海軍士官」さんより
貴メールを、かねがね高く評価しているものです。今回の記事、抜群で、血湧き、肉踊ります。あれこれ批判をしないで、素直に、国の大事に身命をかけた大先輩の偉業を偲ぶべきでしょう。良い記事です。有難う御座います。
「けんいち」さんより
東郷大将は偉人であったと思いますが、当時の日本人に勇敢で責任感の強い人が多かった事も忘れてはならないと思います。太平洋戦争終結時の総理大臣鈴木貫太郎は日本海海戦の時、水雷戦隊の士官として海戦の始まる直前に駆逐艦を率いて大胆にもバルチック艦隊の鼻先を横切り、ロシア艦隊に機雷敷設を疑わせ艦列を混乱させました。彼は日清戦争でも敵軍港内に夜間、水雷艇隊の先頭をきって突入し弾雨の中で停泊中の戦艦を雷撃し世界最強の英国海軍を驚かせ、鬼貫太郎と呼ばれます。またその際発射管の故障で水雷発射に失敗した下士官は、責任を感じて寄港後に自刃しています。
しかし米海軍研究家アルフレッド・マハン提督が賞賛しつつも警告した言葉、負け戦から戦訓は得られるが、勝ち戦から戦訓は得がたい、と言った通り、東郷大将は後々まで大艦巨砲主義に固執して日本海軍の近代化を遅らせます。
また日本海海戦後の東京の園遊会で東郷司令官に感激の対面をした米海軍のチェスター・ニミッツ士官候補生は、いつの日か東郷の弟子達と戦って勝つのだという念願を胸に抱き、40年後米国太平洋艦隊司令官として見事にそれを果たします。
しかし、ニミッツと東郷の弟子達が、相手艦隊をを見ずに繰り広げた日米空母同士の太平洋を舞台とした海空戦は、世界史に唯一の記録として語り継がれるでしょう。それはNYハドソン川に浮かぶ記念空母イントレピッドの展示でも見る事ができます。
■ 編集長・伊勢雅臣より「84歳の元海軍士官」さんからも、激励の言葉をいただき、恐縮しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
