
NanoVNA プリアンプ編 2
1200Mhzプリアンプの 入力整合状態 S11を
NanoVNAで見てみよう
no+eは後から修正できるので、このシリーズ1
も追加加筆しています 見てみて下さい
NanoVNA使い方 プリアンプ編
なので プリアンプの作り方や調整方法では
なく NanoVNAでの測定方法になります。
S11は OPEN/SHORT/LOAD の校正キットを
使って校正面にてキャリブレーション取ります
よって測定物のコネクタ形状によってキットが
変わるのですがNanoVNAに付属してくるのは
SMAPの物だけです。NP, NR, SMAP, SMARの
物を中古でも見かけたらゲットしておくと
良いのですが、通常キットだけでNanoVNAが
数台購入できる金額の事が多いです。
今回は付属してきた物とNPで校正した物なので
差分も見られると良いかな?
いずれ、変換コネクタ入るのが大半のケース
変換分の電気長を補正して校正面を動かすよう
ですが、NanoVNAが手の届く価格で入手できる
時代、厳格な事を置いといてやってみましょう
PORT1のSMARコネクタに付属の校正キットで
キャリブレーションを取ってみます
事前に見る範囲、今回は1200Mhz~1400Mhz
を決めてから実行します。 S21も同じです
後から見る範囲を変えた場合は都度CALします
信頼できるケーブルの先で校正しても大丈夫
準備できたら測定物を接続します。
出力は必ず 50Ωで終端するか、ケーブルで
PORT2につないで測定します
事前に8753で取っておいた物がこちら


調整ポイントが少し違いますね

調整ポイントがズレる
8753は入力POWERが変更できるので上げると
同じように調整ポイントがズレてます。
FETへの入力が高いレベルで調整している為
入力レベルによって変化してるようです

調整時はSWRではなくLogMagにした方がピーク
を取りやすいですが、逆に言えば狭帯域化している
のが良く見えてますね
SWR表示でも左右がアンバランスになってます
LogMagで見た反射は-40dBなので1/10000以下
気持ち良く合ってますが調整の仕方が悪い見本かも

マキ電機のプリアンプ S11 SWR表示
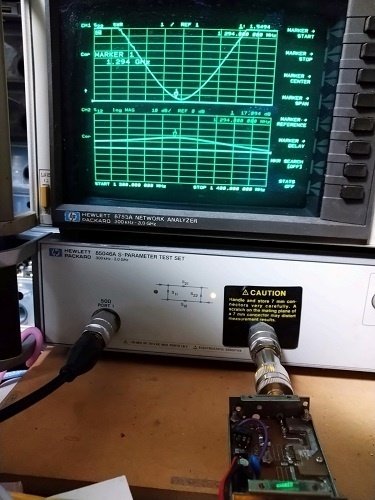
ほぼ同じように見えます
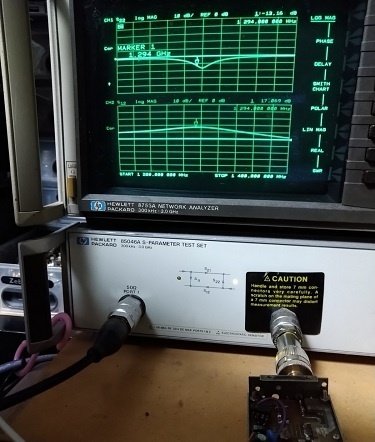
ブロードです
調整がズレていたので修正しました。20年近く前の
製作物 くり抜きケースと違い板金だと基板の歪み
とかで変化しやすくなるのは仕方ないか~

ゲイン低いですが、この位ブロードであれば
色々な要因があっても安心できます
2つの1200Mhzプリアンプを例に 入力整合
をNanoVNAで見ながら8753との比較を中心に
見てきましたが、ほぼ同じように使えます。
POWERが変更できなかったり、少々仕様と
違うのは気になりますが、コスパは最高!
それで、チャント使える機材!
8753は40年近く前の機材。老朽化でメンテ
できなければ それでオシマイ
NanoVNA アンテナアナライザではなくて
ベクトル・ネットワーク・アナライザです
今回はここまで
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
