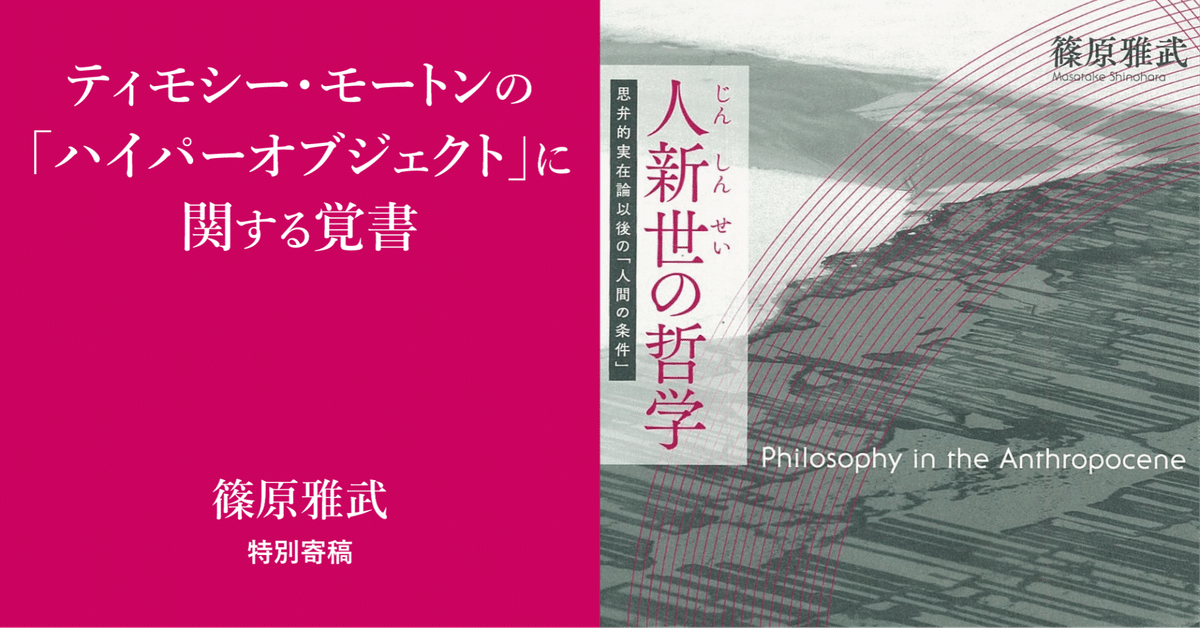
【篠原雅武・特別寄稿】ティモシー・モートンの「ハイパーオブジェクト」に関する覚書――追記(2021/11/18、12/8追記)
2021年11月16日、Wired web版(英語版)に、ティモシー・モートンの「世界の終わり」に関する記事が公開された。そこでは彼の代表作『ハイパーオブジェクト』についても論じられている。その成り立ちに関して、驚くべき記述がある。すなわち、2008年に、モートンは、奇妙な実存的気分にとらえられたのだが、そのことで、広大であり、人間にとって根本的に奇妙で理解するのがむずかしい現象にふさわしい言葉を定めることができるようになった。モートンは、2012年にそれを書くべく椅子に座ったが、わずか15日で『ハイパーオブジェクト』という著作が溢れ出てきた、と[注1] 。ここで重要なのは、モートンが気分(feeling)から文章を書いている、ということである。そうであるならば、モートンが考えていることをこちらが受けとめ解釈するには、ただ字面だけではなく、その文章に先立つところに生じる気分を感じるところまで達することが求められる。それは、自分の内面を深く掘り下げ、モートンの気分と同じ気分を自分のなかに発見することでもある。
モートンが『ハイパーオブジェクト』で展開した「世界の終わり」についての考察は、私にも思い出深いものである。2016年8月にヒューストンを訪問したときに何かと話したのも、まさにこのテーマだった。そのときの対話は、『現代思想の転換2017』(篠原編、人文書院、2017年)に収録されている。このときに考えたことをベースにして、私は『「人間以後」の哲学』(講談社、2020年)で、次のようなことを論じた。
「これにかんしてティモシー・モートンは、哲学的な観点からの考察を試み、確定的な背景ないしは場所としての世界の終わりを意味するものと考えていく。彼自身述べているように、これは世界そのものが存在するのをやめ、消えてしまうことを意味しない。むしろ、安定的なものとして保持されていた人間世界の確定状態そのものが揺らぎ、地球的事物の世界との境界が曖昧になり、定まらなさ、脆さが前景化していくことを意味している 。世界の脆さが前景化するとき、安住し、安楽に居直ることのできていた確定的な世界から、私たちは追いやられていくことになるだろう。だが、じつは世界は、本当はずっと不確定で脆かったのかもしれない。この現実を、まずは認め、受け入れていくことが求められている」[注2]。
ここで私が書いた文章について説明したい。第一に、この文章は、モートン自身が明確に書いていることを、そのまま述べたものではない。実を言うと、これはモートンが『ハイパーオブジェクト』のp. 99-100で述べたことに関する一定の解釈で、そのかぎりでは、著者の読解から導き出される一定の創作物である。p. 99-100のどこかでモートンが実際に書いていることを事実としてそのまま書いたのではない。まず私はこれまで『複数性のエコロジー』(以文社、2016年)や『人新世の哲学』(人文書院、2018年)などでモートンにかかわる考察をしてきたが、『「人間以後」の哲学』では、「人間以後」という学術的な問題設定を行うためにも不可欠な視角・観点を定めるためのものとしてモートンにおける「世界の終わり」の考察を行った。つまり、そのような関心からモートンが『ハイパーオブジェクト』で述べていることを読解し、さらにモートンの他の著作や論文をも参照し、『自然なきエコロジー』(篠原雅武訳、以文社、2018年)から『Humankind』(翻訳が岩波書店より2022年に刊行予定)でに至るまで持続して問うてきた主題である「場所」論の分析との関連させるなかで、モートンの「世界の終わり」に関する議論を読み解くことを試みた。
つまり上記の私の文章は、モートンが『ハイパーオブジェクト』で書いたことを読めば自ずと出てくる見解ではない。実を言うと、私が2016年8月にモートンを相手に行ったインタヴューでも、モートンは、モートンが提示する「世界の終わり」に関する議論はさまざまに誤読されていると述べている。つまり、モートンが書いていることには自由な解釈の余地があり、だから私の解釈以外の解釈もありうる、ということである。モートンが言うには、代表的な誤読として、世界そのものの消滅や破滅といった破局的事態を述べたものという解釈(マーク・フィッシャーの「未来の消滅」の議論)や、あるいは、人間世界と自然世界の境界の消滅と一致といった解釈(ラトゥールのANTとの関連で行われる解釈)があるが、それとは違うことを、2013年の『ハイパーオブジェクト』では述べたつもりだと言っていた。そして、私が『「人間以後」の哲学』で提示した解釈は、このときの会話に裏付けられている。
ところで、モートンが私に語った「世界の崩壊」についての考察は、2017年の『Hunankind』で展開されている。
「エコロジカルな目覚めのおかげで、あなたはあなたの世界を誤作動していて壊れているものとして経験するが、それは、私たちが自分たちの世界として考えていて、しばしば徹底的に人間中心主義的にスケール化され規範化された背景から、ありとあらゆるたぐいの事物がはみ出すかぎりにおいてである。融解する多冬極氷から、あらゆるたぐいの予期しえぬ事物が現れつつある。それは、メタンガスや冷戦期の基地といったものだが、ただ深いところに埋め込まれた事物だけでなく、私たちの無意識の心の奥深くに埋め込まれた思考と想定も現れつつある」[注3]。
「だが、この誤作動をつうじて、人は何か深いことに気づきつつある。(円滑で完全な)世界そのものという観念も壊れている。それを元へと戻すことなどできないが、なぜなら、そこで事物がはみ出すといったことなどなく円滑に作動しただ起こるという概念そのものが、人間中心主義的な尺度でできたものだからだ。諸々の世界は、そのようではない。これは、私たちが世界についての考え方を変えてしまったことを意味している。世界はまさにこのボロボロで穴だらけのパッチワークキルトで、その始まりと終わりは、定まった地平で画されていない。そこで、空間的で時間的な地平は、等しなみに穴だらけで、ぼやけている 」[注3]。
ここにもあるように、世界の崩壊、誤作動は、世界の消滅や滅亡ではなくて人間中心主義的にスケール化された「背景」(background)から多くの事物が逃れていくということが述べられていて、その過程で、通常成り立っていた世界についての考えも失効すると述べられている。
ただ、私が書くときに依拠した『ハイパーオブジェクト』では、世界の終わりに関して、ここまで明確には述べられていない。ゆえに、私も「人間以後の哲学」の該当箇所の引用文献に『Humankind』を入れておくべきだったし、参照注としてモートンとの2016年8月の会話に言及しておくべきであった。つまり、上記の私の文章は、『ハイパーオブジェクト』と『Humankind』を踏まえていることに加え、モートンとの会話から得た示唆を踏まえたうえでの解釈であり、見解である。
また、モートンの『ハイパーオブジェクト』では、背景と前景の区別の崩壊について論じられているし、崩壊において現れてくる「世界」の実相が脆くて美的な領域として描かれているが、それでも「崩壊前に保たれていた世界に安住できていた状態が終わる」とまではじつは書かれていない。ゆえに、「安住し、安楽に居直ることのできていた確定的な世界から、私たちは追いやられていく」という一文は、モートンの文章を読むだけではでてこない見解で、そのかぎりでは、私なりの議論の展開であり、創作物である。モートンは、どちらかといえば、背景と前景の区別の崩壊において出会ってしまう世界の不気味さや、あるいは、世界が穴だらけであるということに関心をむけているが、以前の世界に安らうことのできていた状態から人が追いやられるという「難民的状況」については明確に述べていない。これは、私がこれまで行ってきたアーレントの『全体主義の起源』や藤田省三の「「安楽」への全体主義」(初出『思想の科学』(1985年)、『全体主義の時代経験』(みすず書房)所収)の読解を踏まえた考察であり、また、『人間以後の哲学』で論じたフレッド・モーテンの議論と重ねて読む中で導きだした解釈である。
そして、私のこの文章が私独自の解釈であるのがなぜかといえば、『「人間以後」の哲学』で私は、「世界」に関わる他の論者の議論(メイヤスー、マルクス・ガブリエル、ヴィヴェイロス・デ・カストロ、ディペッシュ・チャクラバルティなど)との比較のなかで、モートンの議論の独自性を示そうとするなかで提示した解釈だからである。人間世界の崩壊や、人間から離れたところにあるものとしての世界(planet earth)をめぐる考察は、近年のエコロジカルクライシスのなかで盛んに提示されているが、それらと関連させ、のみならずそれらとの違いを明確にしつつモートンの議論を解釈すると、先の私の解釈になる。もちろん、これが本当に正しいかは、私にもわからない。ただ少なくとも、私は『ハイパーオブジェクト』には書かれていない解釈の秘訣をモートン本人から聞いた上で誤読せぬよう慎重に考えながら解釈した。今にして思えば、それはもしかしたら、モートンと私がそのとき感じた一種の気分から出てきた言葉であり、考察だったのかもしれない。
注1 Laura Hudson, “At the End of the World, It’s Hyperobjects All the Way Down,” https://www.wired.com/story/timothy-morton-hyperobjects-all-the-way-down/
注2 篠原雅武『「人間以後」の哲学』講談社、2020年、42-43頁。
注3 Timothy Morton, Humankind, London: Verso, 2016, p. 92.
- - - - -
追伸(2021年12月8日)
この間、二度ほど、人文書院のnoteに文章を書いたのだが、その背景には、次のことがある。それは、森田氏の著書『計算する生命』『僕たちはどう生きるか』でティモシー・モートンが論じられているのにもかかわらず、日本語で出された主要な先行研究である拙書(『複数性のエコロジー』『人新世の哲学』『「人間以後」の哲学』)に関する参照注もなければ私の名前の記載も一切ないことにどことなく居心地の悪いものを感じて彼にメールを送った、ということがある。なお、最初の記事ではあたかも私は森田氏とは面識のないかのように書いたが、実はそういうわけではない。
それはともかく、森田氏とのやりとりは、学術書での文献の引用や参照におけるルールにかかわる普遍的な問題と関係があるのではないかと思うようになった。そのあたりのルールをしっかりシェアするというのは大学生がレポートを書く上でも重要なことだと思うし、また、大学院生や大学の研究員や大学教員などが論文を書いたり書籍を書いたりする上でも重要なことだろう。人文書院でも最近『ゆるレポ』という著作が出ていたので、これとの関連で、私が経験し、考えたことを、シェア可能な情報として公表することにも意味がないわけではないと思うようになった。
まず私は森田氏に、次のようなメールを送った。
「まず、この二冊の著書は、私にはどことなくよそよそしいものに感じられた。書かれている内容としては、ティモシー・モートンを論じていたり、ecological awareness(私はエコロジカルな目覚めと訳していますが)を論じたりと、どことなく関心を同じくしているだろうが、そのスタイルというか、著書そのものが放つ存在感の水準では、私の存在をどことなく遠ざけるもののように感じた。」
末尾の文献一覧に一つも私の著作が記されていないことがそれを明示している。別にそのテーマを論じる際は絶対言及せねばならないとまではいわないが、それでも、森田氏がそのテーマにたどり着くにあたって何を参照し、何にヒントを得たかを文中のどこかで記載するのは、著者の最低限のマナーではないかと考える。
先行研究の引用の仕方、先行研究を踏まえたうえで自説の展開をするなど、文章の作法といったことも、査読論文や博士論文を書く中で学ぶことになる。「研究者」と名乗るのであれば、そういったこともわりと大切なことだと考える。
これに対する森田氏からのメールでは、『人新世の哲学』を読み、これがきっかけで、モートンの著作を知ったこと、モートンとの出会いのきっかけは間違いなく篠原氏の著作であったということを認める記述があった。また、2019年の夏に『複数性のエコロジー』を読むなどして、篠原氏の仕事が大きな意味を持っていたことは間違いない、とのこと。
それでも私は、研究会などクローズドな場で起きた出来事とは違い、出版物として形になってしまっていて、多くの人の目にすでに触れてしまっている問題でもあると考え、質問状をつくり、送付した。その概要は、おおよそ次のとおり。
1 拙著を何らかのかたちで読解し、参照し、自分の著書内に反映させたということを森田氏ご自身でも認めているということなので、拙著の存在を知らず、独自でモートンの著作群を知ったというわけではないことはわかった。であれば、自説を展開する際、私の著作を参照したことを明記し、それが何から導き出されたか、何を参照したかを書籍中で明記するのは当然のことと思う。それにもかかわらずそれができていない特段の理由があるのだとしたらそれを詳しく教えていただきたい。
2 もしも今後『計算する生命』を重版することや文庫化することがあるとしたら、この辺りに関して、どのように読者に説明するつもりであるか。
これに対し、森田氏から返信があった。概要は次のとおり。
「モートンの出版物に関しては、英語で読めるテキストは原文で読んでいる。ハイパーオブジェクトは、自分でほぼ全体を訳してみながら、繰り返し精読をしている。『計算する生命』におけるモートンの読解では、篠原氏の著書を参照した箇所はない。モートンの著書を語る篠原氏の言葉は、極めてクリアなモートン自身の言葉に比べると、自分の頭には入ってこないということがあり、モートンのテキストを読解する上で、篠原氏の著書から直接影響を受けたという自覚がない。また、モートンのことを知る経緯まで含めて本文内で書くことは、必ずしも必須ではない。様々なものに触発され影響を受けながら思考は編まれていくもので、そのすべての「きっかけ」を列挙することは原理的に不可能。」
拙著を読んだことがモートンを知る「きっかけ」だったということを言いながら、それに言及する必要はない、ということらしい。読んだことはあっても影響を受けたという自覚がないから先行研究として言及する必要はないらしい。先行研究を参照するということの意味が森田氏にはわかっていないのだろうか。さらにいうと、モートンを私の著作から知ったのであれば、それはモートンを知る重要な「きっかけ」であって、そこに触れようとせず、沈黙することには、何かいわく言い難い「意図」が働いていたのではないかと勘繰らずにはいられない。
ただ、さらにもう一つ、気になることがあったので、森田氏に問い合わせた。それは次のようなことである。
『僕たちはどう生きるか』(集英社、2021年)で、次のような文章が出てくる。
「前景と背景、図と地を切り分けて考える発想そのものの機能不全。ティモシー・モートンはこれを、「世界の終わり」と呼ぶ(注13)。それは、終末論的で破局的な、人類や地球そのものの終わりではなく、内と外、図と地を切り分け、自分だけが安全に引きこもれる場としての「世界(world)」があると考えること自体の有効性の終わりなのだ。」(28頁)
この記述に関して気になるのは、次の二つである。
1 森田氏の文章には、引用注として注13と明記され、モートンの著作『ハイパーオブジェクト』が挙げられていながら、肝心のページ数が明記されていない。これだと、モートンの著作のどこの箇所でモートンがこのようなことを述べているのかがわからない。これはモートンが書いたことの引用なのか、それとも、森田氏の解釈なのか、はっきりしない。
2 さらに、この箇所は、拙著『人間以後の哲学』の次の箇所とよく似ている。
「これにかんしてティモシー・モートンは、哲学的な観点からの考察を試み、確定的な背景ないしは場所としての世界の終わりを意味するものと考えていく。彼自身述べているように、これは世界そのものが存在するのをやめ、消えてしまうことを意味しない。むしろ、安定的なものとして保持されていた人間世界の確定状態そのものが揺らぎ、地球的事物の世界との境界が曖昧になり、定まらなさ、脆さが前景化していくことを意味している 。世界の脆さが前景化するとき、安住し、安楽に居直ることのできていた確定的な世界から、私たちは追いやられていくことになるだろう。だが、じつは世界は、本当はずっと不確定で脆かったのかもしれない。この現実を、まずは認め、受け入れていくことが求められている。」(42-43頁)
この箇所に関して問い合わせたところ、これはモートンの著作を読めばクリアに論じられていることである、とのことであった。だから篠原氏の著作を参考にした覚えはない、とのこと。
拙著の箇所が、「モートンの著作を読めばクリアに論じられている」のではないことに関しては、noteのなかで論じたので繰り返さない。ゆえに、モートンの著作を何らかの関心に基づいて読まないかぎりあのような見解は出てこない。これに対し、モートンのどこをどのようにして読解して導き出したかということに関しては、森田氏の著作では十分な説明が行われていないので、森田氏の説明には、疑問がなくもない。この点に関して、もっと追求しようと考えたが、このままやり取りを続けても平行線に終わると私は判断し、やりとりを打ち切った。
ただ、一言だけ言っておきたかったことがある。先行研究の著作から何らかの影響をうけ、似たような文章を書き、それを自分の著作として発表しつつも、その先行研究の存在に関しては沈黙するという状態があるというのは、それを書いた当人には、あまりいい気がしない。繰り返しになるが、私の著書の存在を知らず独自にモートンのことを知りそれで本を書いたというのであれば別に問題ないのだが、森田氏自身みとめるように、そういうわけではなさそうだからだ。
ただ、やり取りを続ける中で私は、森田氏のなかでの引用のルールはかなり独特なもののようにも思われた。森田氏が引用なるものをどう考えているのか、正直私にはわからないが、それでも、長年論文や著書を書く中で、私が守ってきたルールとはどうやら異なることだけは確かなようだ。そのあたり、もしかしたら、誰からも学んでいないのではないか。
私自身、引用ルールを、次のように設定している。ちなみに、私自身は、戸田山和久氏の『論文の教室 レポートから卒論まで』(NHKブックス)から多くを学んだ。
1 自分に先行する著書や論文で、一読したものについては、それが自分の論述と何らかの関係を持つのであれば、かならず言及する。自分の見解と合わない場合であっても、批判するか、不十分な箇所を明記するか、自分の見解と合わないのはなぜかを論じる。そのことで、自分の議論がどういうものか、そのテーマ全体のなかで位置づけることができる。あるいは、これまでの解釈・読解の流れがどのようなものであるかをまずは示し、それに対して自分が何をいうかを明確にする。もちろん、ハイデッガーやデリダやマルクスなど、膨大な研究蓄積がある対象に関してすべての先行研究を明示するのは無理で、そこで取捨選択が行われるのは仕方ない。ただ、取捨選択する場合にも、自分が何を論じているか、何を問題にしているかを明確にするということが前提になる。
2 あまり知られていない対象(モートンさんも、世界的には著名でも、日本ではあまり知られていないし、論じられていない)であればなおさらそこには気をつける必要がある。実際、森田氏も、岡潔について書かれたもの(『数学する身体』)では、高瀬正仁氏の著作などを文献リストに入れている。著者が影響を受けたかとか好きか嫌いかといったことは読者にはあまり重要でなく、学術的な領域内での見取り図などをしっかり示しそこで自分の議論の独自性が何かを明示されているかどうかが重要である。
森田氏とのやり取りを経る中で、私は、学術・出版の世界での最低限度のルールというか、公共性といったことに関して、あらためて考えるようになった。森田氏の文章には、私の著書への言及が一切ない。引用注も参照注もでてこない。仮に参照したのであれば「先行研究」の一つとして注に入れるか本文中で言及するのが学術上のルールだろう。先行研究の到達点を明らかにし、自己の見解との相違を明らかにするためにも、先行研究の引用については引用注を付けることが要求される。その観点から言うと、重大な問題ではないか。森田氏の著作は日記のような本であり、学術的なものではないと判断することもできるが、それでも他の箇所では、学術的な文献が参照される場合には、それらが参考文献・先行研究として挙げられている。そのかぎりでは、森田氏は学術的な文献を参照する際は引用注・参照注を付しているので、引用のルールを知らないわけではなさそうである。それに対し、私の著書が出てこない。これは不自然ではないか。参考文献を書籍内に明記するのは、その文献が自分の好みに合うからではない。嫌いであり、同意できない文献であっても、それとの違いを明記する(なにゆえに同意できないか、その根拠を示し、そのうえで自分の見解を示す)というのが、学術研究成果の発表の基本である。
- - - - -
篠原雅武(しのはら・まさたけ)
1975年生まれ。京都大学総合人間学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。哲学・環境人文学。現在、京都大学大学院総合生存学館(思修館)特定准教授。単著書に『公共空間の政治理論』(人文書院、2007年)、『空間のために』(以文社、2011年)、『全‐生活論』(以文社、2012年)、『生きられたニュータウン』(青土社、2015年)、『複数性のエコロジー』(以文社、2016年)、『人新世の哲学』(人文書院、2018年)、『「人間以後」の哲学』(講談社選書メチエ、2020年)。主な翻訳書として『社会の新たな哲学』(マヌエル・デランダ著、人文書院、2015年)、『自然なきエコロジー』(ティモシー・モートン著、以文社、2018年)。現在『人類(Humankind)』(ティモーシー・モートン、岩波書店、2022年)の翻訳刊行が予定されている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
