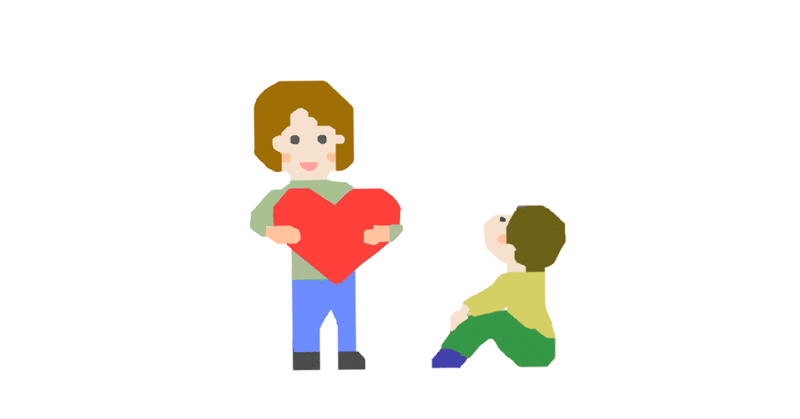
ともだちとコミュニケーション論
今日ははっきり言って、自分の生き方を一切脚色も何もしないで話します。だから自惚れていると言われても結構。厨二病こじらせたやつだと言って結構。でも何も嘘はない。
国分功一郎という哲学者をご存知だろうか。現在存命の哲学者の代表格と言っていいほど有名な学者である。代表的な著作は「暇と退屈の倫理学」。高校生ならピンと来るだろう。東京書籍(シェア率はトップレベル)の現代文の教科書において同名により抜粋が教材として掲載されている。個人的な話をすると現代文教材として好きな教材の3本の指に入る(残りは鈴木孝夫の「相手依存の自己規定」(閉された言語・日本語の世界の一説)、ドナルド・キーンの「かなえられた願いー日本人になること」の2つである)。
その中でもタイムリーな話を扱っているのが、「暇と退屈の倫理学」である。人間社会においての余暇時間についての批評が、テーマとなっている。なお出典となった同名書籍も現在読み進めている最中だ。その中で次のような一節がある。私は好きな評論の中でも特にこの一節が好きだ。引用させていただく。
人はパンがなければ生きていけない。しかし、パンだけで生きるべきでもない。私たちはパンだけではなく、バラももとめよう。生きることはバラで飾らなければならない。
読んだことのない人のために、前後の文脈を説明しておくと、吉本隆明とウィリアム・モリス(20世紀イギリスの社会主義者)による解釈を紹介しながらイエス・キリストの考えを紹介し、バラ=余暇の過ごし方についての考えを述べていく、というような文脈である。
欲求階層説に見た人間関係
ではここまで壮大なはじめはここまでにして、どうしてこの一節を引用したのか。人間関係は「パン」なのか「バラ」なのか問題を取り上げたいからである。これを極めて理論的に説明するため、マズローの欲求階層説を取り上げる。

なお欲求階層説は倫理の授業で出てくる非常に眠いあれだ。「パン」と「バラ」の線引きはどこからだろうか。明らかに成長欲求は「バラ」であるだろう。達成されずとも人間は生きて行くことができる。では欠乏欲求について分析していきたい。まず、承認欲求・所属と愛の欲求は達成されずとも生きて行くことができるので「バラ」、生理的欲求は生命維持を目標とするため「パン」だろう。
安全の欲求もよほど運が良くない限り、安全が確保されない場合長く生きることはできないため、今回は「パン」に入れることにしたい。
ひとまず欲求階層説のピラミッドの分類はできた。では今日はこの課題を解決することから始めたい、「ともだち」はどこに分類されるのか問題である。はっきり言って突っ込んで考えなかったら、「所属と愛の欲求」に分類されるだろう。しかしこのマズローの欲求階層説には一つだけ欠点があると言う事を提案したい。「西洋的価値観」に偏っているという現実だ。これを提唱したのは日本人ではない。ではここで「東洋的価値観」と「西洋的価値観」の定義をしておく。私が考えるに、西洋的価値観とは人間関係が非常にドライでかつ人工的なものを美しいと考える(他人にあまり干渉しない・作られたものが美しいなど)。東洋的価値観とはその逆、人間関係が非常にウェットでかつ自然なものを美しいと考える(他人に干渉する・自然を生かしたものが美しいなど)。
今日はとことん現代文の教科書を引用することが好きだということに気づいたが、はっきり言って例としてはわかりやすいので、これをあえて取り上げる。これらは山崎正和「水の東西」、鈴木孝夫「相手依存の自己規定」に取り上げられている。
この価値観の違いをもとにして話を戻す。「ともだち」はどの欲求問題か、である。東洋的価値観に立って考えた時、日本人の人間関係はウェットなものである。どういうことかというと、他人との関係を切っても切り離せないというものだからだ。
そのような人間関係が、先進国病と呼ばれる、日本に自殺者が多くなる事を手伝っているように感じる。ここについて今日は突っ込むのを控えておく。
このような価値観を持つ東洋人(特に日本人)において、人間関係や友人関係というのは所属と愛の階層のような関係ではないということだ。生理的欲求階層、すなわち生死に直結するような関係の構築をするわけである。
人間とコミュニケーションの関係
生きることは話すこと。コミュニケーションをし続けること。こう感じたことがある。3年前の自宅待機が数ヶ月続いた時期に感じたことだ。この自宅待機について今更何か批判をするつもりはない。
人生において会話が大切である、そう感じた。こうエネルギーが有り余っているような感覚といえばいいだろうか、どうにかしてこの感情を共有したいと感じたことがあった。周りの友人らも同じ感情を抱いていたという事を後から知った時、自分だけではないと強く感じた。これが人間なのだという強い確証を得たような感覚を得た。
会話だけではない。映画「彼女が好きなものは」の中で、カップルがセックスに失敗するというシーンがあった。なんだろう。「俺ら何やっちゃってるんだろう」というような空気ではない、気まずい空気が流れていくというシーンがあった。その時に確信を得た。物語のようないわゆる作り話は、表面的なコミュニケーションを超えた、核心的なコミュニケーションを強調することができる。というより強調することにこそ意味がある。誇張することにこそ意味がある。
反対に強調されないだけで、少なからず表面的なコミュニケーションの深層には核心的なコミュニケーションがある。そしてその核心に触れることこそが以心伝心である。伝わらないことがあるから喧嘩がある。だから人間は面白い生物である。
そうして人間は誰かにわかって欲しくて叫ぶ。誰かにわかって欲しくて表現する。誰かにわかって欲しくて呼吸する。
ともだちとコミュニケーション
人間という生物のコミュニケーションについて深く、血を通わせながら考察してきた。最後に人間はなぜともだちを求めて、なぜともだちとコミュニケーションをとろうとし続けるのか。この課題を考える。
なぜ人間は100%感情や知覚をコピーすることができないのに、伝えようとするのか、シェアしようとするのか。
学級目標に「楽しいことはみんなで共有して喜び、悲しいことはみんなで共有して悲しもう」的な事をあげられることがある。私は完全に今も理解し切っているわけではない。しかし次のようなメリットがあると感じている。
精神的な問題は時間が解決することもある。歌詞とかでも度々この考え方は取り上げられる。その時間潰しにコミュニケーションは役立つことがあるだろう。そのコミュニケーションをするためには友達を必要とする。自らを防衛するために用意をする意味合いで友達を求めるのかもしれない。
話し相手に友達がなることがある。人間関係の深層にも損得勘定は働いていると考えたことがある。話を聞いていると、友達が気が楽になっていくだろう、そんな自己満足を求めて話を聞いているのかもしれない。それで相手が悲しんでいるのかもしれないが、そんなことは知ったことない。
反感を買うかもしれないが、あえてはっきり言わしてもらう。私は馬鹿な人間だから、そんな理論的なことも考えず、困っている人を助けたくなる。自己犠牲を平気でして誰かを助けたくなる。それが自分の長所なのかもしれない。
それでこそ「ともだち」なんだと思う。ここに「友達」と「ともだち」の違いが生じるのだと思う。自分より他の人の方が大切だと本気で思っている、大馬鹿者が人間関係を考えてみた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
