
モダクラ論争を繰り返す前に考えておきたいこと【スト6】
書いてる人:CラシードとMエドのWマスター
両スタイルの使用者でかつ、上級者とも初級者とも決して言えない、どっちつかずな立場
格ゲーは90年代にゲーセンと家庭用でカジュアルに遊んでいたが、対戦ゲームとして打ち込めたのはストVのシーズン5が始まる頃(2021年2月)に復帰してから
現在のデバイスはメカニカルキーボード(87キー)を用いた疑似レバーレス。キーボード設定の布教記事も書いている
性格的に、対戦や練習だけでなくデータ収集を頑張るタイプ。ストV時代から現在にかけて複数のプレイコミュニティ内で交流を得ている
結論から先に
1.今のスト6にモダンは“絶対”必要
2.モダンに調整は“現状は”必要
3.現状のモダンに不満やヘイトを感じる人がいるのは自由
4.ヘイトがあってもモダンプレイヤーがモダンを使わない理由にはならない
1はトッププレイヤーなど、特にコミュニティを支えている人たちの意見も含めた結論だと言える。
格ゲーにおいて、プレイヤー人口や流行を絶対の正義とするなら、「モダンがなければ遊ばなかったプレイヤー」「配信をしなかった配信者」「開かれなかった大会」といったスケールの大きさからして不可欠と言えることになり、ここのコンセンサスが取れないと話が始まらない。
逆に言えば、「モダンを存続させるかぎり、スト6や格ゲー文化そのものは必ず衰退する! 絶対に有害!」くらいの極論で対抗しなければモダン不要論を説くことはできない、ということだと思う。イヤ、自分ならそこまで言うぞと言う覚悟のある人は、いるだろうか?
2は、そうした不要論や「モダン有害論」があったとして、スト6から削除するよりも修正と調整で解決することを考えたらいい、という話になってくる。
そして、格ゲーで特定のシステムを「調整しなくてもいい」と言い切ることは、「共通システムやキャラの調整も一切しなくていい」と言ってしまうことと変わらないのだ。
モダン/クラシックも、ゲームバランスを構成する要素の一部でしかない。「モダンを調整しなくていい」と言うのなら、「ラッシュ関係の入力問題(※1)や本田の頭突き・百貫も調整しなくていい」と言うのと同然なのだと覚えておきたい。
(※1 ちなみに発売直後のスト6には「パリィボタンを使ったキャンセルドライブラッシュ」が存在しなかったが、特に初心者帯での入力の困難さが疑問視されたことで、柔軟にアップデートが行われた経緯がある。また、ラッシュの時間停止中にコマンド入力が乱れることによるストレスはプレイヤーから常に訴えられ続けており、今も残される不満点のひとつに挙げられる)
不満や、開発の意図しなかった不備があるなら調整が検討されるのは当たり前だし、開発側もプレイ環境の反応を見なければ検討すらできないのだから、プレイヤーが不満やストレスを訴えることは別に悪くはないのだ。
そして以上のことから言える3と4も、やはり必要なコンセンサスであると思いたい。
モダンは共通システムであり、キャラ性能でもある
モダンは「操作タイプ」と呼ばれることから、あたかもデバイス選択と同レベルの、入り口から違う遊び方をしていると思われることが多い。
なのでFPSにおける、キーマウ・パッド論争(エイムアシスト問題)と並べられることもあるようだ。

元動画: 【 #大バかたチ 】第213回 かずのこ杯を振り返りつつスト6!#スト6
だが、スト6にも「ゲームパッド」、「アケコン(レバー)」、「レバーレス」、「キーボード(&マウス)」とで異なる入力規定が存在し、どれが優位とも言いにくい、細かな実践値の差が生じている。
その上でクラシックとモダンのタイプに別れるのだが、スト6における操作タイプというのはデバイスの差というより「キャラ性能の差を生むシステム」である、と自分は考えている。
ヒントはスタイル選択の歴史のなかに
つまり、クラシックとモダンの違いはデバイス差に例えるよりも、従来の格ゲーで数多く採用されていた「モード選択システム」や「差分キャラ選択システム」に近いのだと個人的には思う。
例えばKOF97~98に存在していた「アドヴァンスド/エキストラ」というモード選択システムは、新/旧(KOF96と95以前)の操作感をプレイヤーに選ばせたという点で、モダン(=現代的)/クラシック(=伝統的)とよく似たネーミングになっていた。

一方、カプコンのゲームとしては『X-MEN』シリーズ、ストZEROシリーズ、『ヴァンパイア』シリーズなどでオートモードを選べる「プレイモード」の概念が先行していた。だが、そちらは明確に初心者用を意識したシステム(俗に言う「補助輪」のような、いずれ卒業することを前提とした機能)だったので、通常モードと両立するようには考えられていなかっただろう。
そのため、むしろZERO3(1998年7月~)の「イズム選択」や、

カプエスシリーズ(2000年8月~)の「グルーヴ選択」こそが、KOF97~98におけるモード選択の延長として捉えられるはずだ。

まさしく、カプエス2におけるSグルーヴはエキストラモードを、Nグルーヴはアドヴァンスドモードをベースに設計されていた事実もある。
それらがモダン/クラシックに近いと言えるのは、「モダンが初心者救済というより、クラシックがおじ救済」と呼ばれていることにも似ている。基本的には「自分の慣れ親んだ、得意なスタイルを選んでください」という、既プレイ勢の遊びやすさを想定したシステムだったからだ。
KOFの「アドヴァンスド」「エキストラ」はその点ではスト6よりも遥かに過激なネーミングだった。なんせ、意訳してしまえば「進化系」と「おまけ」である。初期KOFを再現したエキストラは、確かに初期作の感覚そのままで操作しやすかったものの、「できればKOF96以降の新たなスタンダードに慣れて移行してほしい」というメッセージを開発側から感じられたものだ。
実際、エキストラモードはあまり対戦上の優位を発揮しなかったはず(攻略で変化するにせよ)だが、スタイル選択による優位差というのは、開発の意図に関わらず、多かれ少なかれ発生することとなる。
特に、修正パッチを当てることのできないゲーセン時代にその格差を後から埋めることは不可能なので、「得意だったスタイル」を選択することが必ずしも幸福な結果に繋がるわけではなかった。いくら愛着があっても、弱くて勝てなければ使ってられないし、より強いスタイルが発覚すれば、それがプレイ環境を支配する。
カプエス2を例に取るなら、それがKグルーヴへのヘイトとして現れていたのだろう。
【マゴ】カプエス2のぶっ壊れシステムについて語るマゴさん「Kグルの存在があのゲーム辞めさせた人多いんじゃないかな…」
総キャラ数を倍に増やした神システム
また、SNKでは『サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣』(1995年11月~)で実装された「剣客/剣豪/剣聖」のレベル選択がオートモードのシステムを模していたが、斬紅郎無双剣(斬サム)以降のサムスピや『月華の剣士』シリーズ(1997年12月~)で注目すべきは、「修羅/羅刹」や「力/技」などの差分キャラを生み出せる、剣質(対極選択)の発明にあっただろう。

差分キャラといえば、アクションゲームの古典である『マリオブラザーズ』と『スーパーマリオブラザーズ』にかけて、「マリオの2Pカラーであるルイージ」に性能差が付けられていったように、ストシリーズにおける「リュウに対するケン」も2Pカラー的な存在だったのが、独自のキャラ性能で差別化されて現在に至っている。
それらはコンパチブルキャラクター、コンパチとも呼ばれるが、斬サムで生まれた「羅刹ナコルル」も、初代サムスピから2Pカラーに差分グラフィックが用意されていたこと(紫ナコルル)に端を発していた。

容量や作業量の負担をかけずに、実質的なキャラ数を増やすことのできるコンパチのアイディアは、ケンや豪鬼のように「別人のキャラクター」を独立させるケースもあれば、同名キャラに技や性能の差分を作る方向にも発展していった。
技の差分としてなら、スト3ではスーパーコンボが、スト4ではウルトラコンボが選択式になっていたし、スト5のシーズン3以降はVシステムの選択(特に「Vトリガー」は4のウルコン選択を継承していた面が強い)によって個性を変えることができた。それらの持ち技選択も、コンパチの発想が形を変えたシステムだった。
ただ、いずれもスタイル選択と同じく攻略を詰めていくと、「明確な優位差」が周知されるようになる。プレイヤーが得意な個性を出すというよりは、全ての選択肢に「ほぼ正解」が導き出されてしまって、結局は決まった組み合わせだけが環境で生き残ることになりやすい。
こうした歴史の上で、スト3〜5まで採用されていた技選択の要素が、スト6で撤廃されている事実に注目すべきだろう。
つまり、スト5のVシステムではVスキルI・IIとVトリガーI・IIを組み合わせた2×2でキャラの差分を作っていた。その掛け合わせをなくしたということは、モダンによる×2の掛け合わせこそがキャラの幅を補うと考えられているということだ。
相手がモダンタイプかクラシックタイプかで戦術は絶対に変えたほうがいい。各タイプの強い所を見るんでなくモダンならでは、クラシックならではの弱点を突くべき。
ストリートファイター6の総キャラ数は実は36キャラというわけです!
「同キャラの操作スタイルの違い」という評価で終わらせずに、「キャラ数を2倍に増やすシステム」と解釈した発言を行っていたのは、自分が知るトッププレイヤーのなかではカワノ選手のこのpostでしか見た覚えがない(見逃していたら申し訳ありません)。
これはもっと、多くのプレイヤーがコミュニティに向けて発信していたほうがいい解釈だと思う。
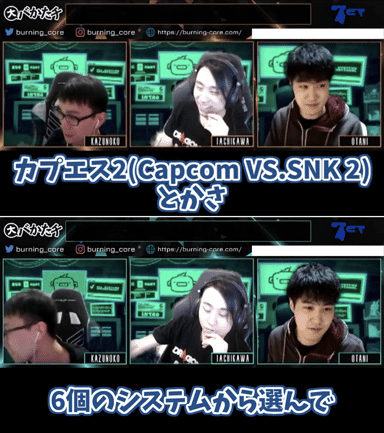
元動画: 【 #大バかたチ 】第213回 かずのこ杯を振り返りつつスト6!#スト6
ちなみに最近だと、カプエス2のグルーヴを例え話にしたかずのこ選手(※図の左)もいて、格ゲー歴の長いプレイヤーにとっては飛躍した発想ではないことも分かる(カワノ選手はスト5以降のプレイヤーなので、比較材料がないのは仕方ないとして)。
低ランク帯と高ランク帯で変わるヘイトと調整内容
結論の2(モダンに調整は"現状は"必要)に戻ると、そこで考えたほうがいい調整内容は、以下の項目に整理できると思う。
a. 初中級者帯の問題解消
b. 上級者帯の問題解消
c. モダン/クラシック格差の解消
d. モダン内のキャラ格差の解消
モダンに対する不満は、上級者と初級者とでヘイトの向かう先が異なるという点に注意が必要だ。
初級者をコーチする立場にあるトッププレイヤーたちの認識でも、「初級者帯から中級者帯に上がるまではモダンを使ったほうが絶対強い(強くなるのが早い)」とみなされている。
そのため、「a. 初中級者帯の問題解消」で想定される不満は、「モダンの不合理な強さ」に比重が置かれやすいだろう。
低ランクというのが、具体的にどこまでのランクを指すのかは意見が別れるとして、正直なところ「一定の強さにぶつかるまでモダン有利」という現状の性質そのものは変わらなくてもいいとは思う。
「クラシックは大器晩成型のプレイヤーか、カベを越えられなくなったモダンプレイヤーが選ぶスタイル」と割り切ることは、ゲーム性のひとつとして仕方のない面もあるのではないだろうか(ただ、これは「程度の問題」がある話として後述する)。
それでは、モダン対策が進んでプレイヤーの実力差がむき出しになってゆく「b. 上級者帯の問題解消」となると、モダンヘイトは主に「つまらなさ」の形を取るようになっていく。
格ゲーというのは、強さとは無関係の「つまらなさ」でキャラへのヘイトが形成される傾向も強く、モダンヘイトもそうしたキャラヘイトと同じだと思って議論したほうがいいのだろう。
「別ゲーをやらされる感覚」というつまらなさ
勝ち負けと関係のない、つまり公平であったりむしろ有利とも言える対戦内容において何が不満を生むかというと、「別のゲームをやらされるストレス」にあると考えられる。
対戦ゲームにおける「つまらなさ」の言語化は難しく、例えばマゴ選手、どぐら選手らからは「自分より簡単なことをされて困らされるのがムカつく理由」「自分のほうが難しいことやってるのにっていうバカにされた気になる」などと、難易度差をその理由として聞くことが多い。そうした見解も、自分のやっている(やりたい)ゲームと相手のやっている(相手にやらされる)ゲームに差がありすぎる、という説明に代えられるだろう。
以下は極端な思考実験だが、例えば「どこからでも崩せる始動技を当てると、画面がテトリスのような落ちゲーに変化して落ちゲーで勝った側が大ダメージを与えられる」というコンセプトのキャラがいたとする。おそらく、使用プレイヤー以外の100%が「クソキャラ」と認定するだろう。「令和にいていいキャラじゃない」と例外なく口を揃えるはずだ。
最終的に、始動技の当てやすさとリスクリターンにバランスが取れていて、「互いに落ちゲーの練習をちゃんとやり込むことで五分に持ち込める」という神調整だとしても、「格ゲーでそんな練習したくない、格ゲーの面白さじゃない」「そもそも自キャラを動かせる時間を奪われることが面白いわけない」という感覚がコミュニティの総意となればそれはクソ技でありクソキャラだという評価が決まっていく。ここまでは同意が得られやすいと思う。
そして、この「別ゲーをやらされる感覚」というのは、飽くまで「程度の問題」であるはずだ。旧作でもザンギエフやダルシムが嫌われやすい傾向がありつつも存在し続けていたが、その別ゲー感が「ギリギリ許されるかどうか」というラインの問題だった(※2)と思う。
(※2 ちなみにスト5の終盤でザンギは弱キャラ、ダルシムが強キャラという評価で落ち着いていたため、好き嫌いとキャラの強さが大して相関しなかったことも解る)
そしてスト6のシーズン1においては、(超の付く上級者帯まで行けば弱い扱いを受ける)エドモンド本田が明確にザンギやダルシム以上に問題視されている。ついには「許されない」というレベルの見解で固まってきたのも、このラインを超えるかどうかで判断されているのだろう。
その本田も、シーズン2を控えた大型バランス調整において、「初級者には(実は上級者でも)対策困難かつ簡単な技を弱体化し、上級者帯においても使い甲斐のありそうな技を強化する」という、各方面からの不満の少ないだろう調整点が示唆されている。
これらのケースから学べるのは、モダンの「不合理な強さ」や「つまらなさ」も、程度問題で解消しうる点をいくらか含むだろうということだ。
先述した、「クラシックは大器晩成型のプレイヤーが選ぶもの」の真逆が、モダンの特性だと言える。
本田が「ライン超え」扱いされた結果、丸く収まりそうな調整を受けるのだとしたら。もちろん、モダンにも似た調整(初級者帯での強さを抑えつつ、上級者帯での弱さを補う形での)が実施されることは自然にありうる。
ただし、開発の意図や理想はわからない
ただ、次の「c. モダン・クラシック格差の解消」に進もうとすると、これまでとは全く別の視点も考慮しなければならない。
「そもそもカプコンは同じ強さにしたいのか、格差を作りたいのか?」という開発の方針に関して、我々は憶測することしかできないからだ。
「競技シーンにおける結果」だけを見て「開発の想定通り」と仮定するなら、カプコンは明確にモダンをクラシックより強くしようとしていない。
その事実からの想像だが、開発は「クラシックを一掃してモダンが席巻するゲームを作ること」をあまり望んでいない。クラシックしか選びたくない人はクラシックを、モダンでしか始められない・続けられないという人はモダンを使えばよいという共存共栄を何より望んでいるように見える。
開発スタッフのなかにも“古のプレイヤー”がいて、彼らからは「クラシックなんて呼び方は嫌!」なんて声がありましたし。
別の客観的な推測として、スト6の開発チームには、クラシックのテストプレイヤーのほうが充実しているように思える。
そうでもなければ、βテスト時点から「全キャラ中で唯一、4F技のないモダンジェイミー」が発覚して製品発売後1ヶ月で修正されるなんてことはまず起きないはずだろう。
そのジェイミーほどではないにせよ、「モダンの作り込み不足」に多くのモダンプレイヤーは不満を抱えている。
モダンの伝道師とも呼べるハイタニ氏が代表となって「足りないところ」を発信してくれているが、コミュニティ的にはまだまだ関心度の低い話題だと言えるだろう。
だからもう、全部ひっくるめて「どっちが強いか、対戦して決めたら」ってなりまして。
この「(モダンとクラシックは)どっちが強いか、対戦して決めたら」というディレクターの発言も、開発側が「モダンとクラシックのゲームバランスが本当にいいのかはっきり解っていない」、「環境に問わせるしかない」という意味だという気がしている。
「テストプレイヤー同士で対戦させた結果、決まりました」とも言い切っていないし、もしテストプレイで白黒を付けていたとしたら、単純に「クラシックが勝つように作りました」と言っていることになるわけだが、飽くまで「どちらにも利点はあり、不利な点も含めて好きな方を使っていい」と、曖昧にはぐらかした発言がその後に続いている。
中山D:どの操作にも利点はあります。モダンはコマンド操作がない分、必殺技を強度で打ち分けできなかったり、通常技が少なかったりしますし。そこも含めて、好きな方を使っていいよって思ってます。論争もあるなとは考えていましたが、そこは織り込み済みです。
モダンの強さを完全に計算できるほど作り込めていないからこそ、プロから「慎重に強くされてない」と分析されるような、臆病さや控え目とも取れる調整が行われているのではないだろうか。
その慎重さを抑えて「ガチに平等」なバランスを攻めようした場合、Kグルーヴの如く「うっかり」プレイ環境を壊してしまいかねないポテンシャルもモダンは抱えている。
特にプロゲーマーはプロ選手である以上、モダンが有利だという結論が出れば、勝つためにモダンへと移行していくはずだし、そう断言している選手もいる。現状そうなっていないのは、元々カプコンにはクラシックを駆逐する意図や確信がなかったということだろう。
だとすれば、「カジュアルでも競技シーンでも、モダンとクラシックが半々になる環境」が開発側の理想なのだろうと、好意的に考えることもできる。
ただ、「慎重にクラシックを超えないように調整した」モダンのままで構わないとするのか、「半々の共存」を目指して微調整を繰り返していくのか、という運営方針については、残念ながら想像することしかできない。
実は難しいアシスト入力
少し別の話題を提供すると、クラシック経験者がモダンをやり込もうとすると口を揃えて言うのが「アシストボタンを使った入力はクラシックよりも難しい、全然簡単じゃない」という意見だ。
実際、格ゲーマーは「ボタンをタイミングよく押す」という操作には慣れていても、「タイミングよく押しっぱなしにして離す」というホールド操作に慣れていない人が多いと思う。
スト5にもボタンホールドを利用した「ホールド必殺技」が一部のキャラに実装されていたが、やはり押しっぱなしてから離すという操作が苦手で、避ける一因になっていたのではないだろうか。
当然、筆者もモダンを始めた頃はかなり戸惑っていたが、アシストボタンが「モーションを伴わない方向入力」と同じなんだと気付いてイメージを変えてから、迷わなくなった。
自分はレバーレスと変わらないキーボードで操作しているから尚更だが、「タイミングよく押して離す」を小刻みに挟みながら入力するという意味では、下入力の役割と、アシスト入力の役割は同じだと結論したからだ。
イメージとしては、「上下左右や奥行きでもない、見えない方向に“押す”操作がアシスト」とみなし、攻撃ボタンではなく方向ボタンに近い意識(具体的には、ジャンプボタンと同じ右手の親指)で押すことで、脳の混乱をクリアできるようになった。
ちょっと言っていることがよく解らない話もしたかもしれないが、「みんなが思ってるほどモダンは簡単なわけではないよ」という意見も入れておかないとモダン派にとって不公平だし、念の為、ってことで。
ワンボタン入力から再燃したモダクラ論争
モダクラの格差を単純化すると、細かくは以下の利点・不利点でバランス調整が行われている。
利点
ワンボタン必殺技のマニュアルに対する相対的「速さ」
コンボテクを不要にするアシストコンボ(一部に自動目押しや自動ヒット確認が付く)
立ち回りで方向入力を無視したアシスト攻撃を出せる(屈ガードしながら立中Pを置けるなど)
DP、DI、投げ専用ボタンが用意されているので意図しない動作が暴発しにくい
不利点
ワンボタンの「速さ」に見合ったダメージ補正(※SAの最低保証は対象外)
ワンボタンとアシストコンボの利点に見合った「実用的な通常技、一部のマニュアル必殺技、一部の必殺技の強度の封印」
特殊なアシスト入力の難しさ
攻撃ボタンの同時押しがDPとDIに対応していないので、一部の複合入力が不可能
(ゲームシステム外のデメリット)上級者向けの攻略が集まりにくく、クラシックの応用を超えにくい
まず「d. モダン内のキャラ格差の解消」の話を先にしてしまうと、「アシストコンボ」と「封印技」の内容が優遇されているかどうかで、モダンキャラには大きな格差が生じている。
「モダン適性」という用語でプレイヤーたちが会話している時点で、モダン内に不公平があると認識されていることも解るだろう。
「キャラ調整はちゃんとしてほしい」という声は格ゲーの常として大きいわけだが、「モダンをクラシックと同じくらい重視して開発している」のなら、モダン内の格差も納得感の高い調整が求められていくはずだろう(もちろん、「アシコンがゴミな代わりに封印技が痛くない」とか、その逆でバランスを取ることもできるため、不遇なアシコンや不遇な封印技を全て救わなくてもいいのだが)。
さて、その上で「c. モダン/クラシック格差の解消」に戻ると、モダンは「ワンボタンの優位性」がまず突出した上で、主に封印技の痛さによって釣り合いを持たせた構造になっている。
筆者としては、「ワンボタンの理不尽な優位性とつまらなさ」は理解できるという立場だし、ワンボタンが発揮する「相手の行動に対する抑制力の高さ」は、先述した「別ゲーを強制されることのつまらなさ」という基準に当てはめた場合でも、ラインを超えているという判断が優勢とされても不思議じゃないと認識している。
ただ、ワンボタン無敵技、ワンボタン弾抜け、ワンボタン差し替えしなどに対するヘイトは、感情的なものなので極端な要望に変わりやすい。
極端なものの代表が「ワンボタン入力時の無敵を削除すればいい」なのだが、ゲームデザイン的に「入力が違うだけで、出る技は同じ」がスト6における操作タイプのコンセプトだろうと思う。開発陣はそれを美しいと考えない可能性が高いと思われ、80%のダメージ補正は必殺技の挙動そのものには手を加えない、そのなかでのギリギリの調整だったのではなかろうか。
さらに言えば、モダンの利点を完全に奪っていくと、「モダンを使う意味がない」と、本格的にプレイヤーから見捨てられる結末が想像できる。
あと意見が多いけどワンボタン無敵系統が削除された場合間違いなく俺はモダン辞めるね
そうなるとモダンは完全に格ゲーの入り口用のシステムになると思う。
そのため穏健的な意見では、「ワンボタンでSAを出せてもいいが、発生の速さをマニュアルに近付ける」というものが多い。
それもプロ選手の配信などを見ていれば長く言われ続けている提案のひとつであって、珍しい意見ではなかったと思う。それがSNS上では珍しかったのか、今月の始めに謎にバズって、大きく紛糾していた。
そういや配信コメントで出たスト6調整案で「モダンのSAはボタン10フレ押しっぱなしで発動する」はかなりいい調整じゃね?途中で発動やめれるし、ボタン押しっぱだからいい感じに他の操作の足枷になるし。10フレはクソ早だし。
んで主力技をもうちょい使えるようにする。これ皆幸せルートないすかね?
これが「いくら決着が付いたと思っても、モダクラ論争に終わりはない」とコミュニティに実感させた一件でもあった。改めて多くのプレイヤーが、この記事の最初に並べた「結論」について考え直す切っ掛けにもなったのだと思う。
ワンボタンSAを「遅く」するアイディアでバランスは解決するか?
ワンボタンSAを「遅く」する方法には、入力成立後の発生が数F遅れるディレイ方式や、逆に数Fの押しっぱで入力が成立するホールド方式などが主に提案されている。
この「数F」を微調整することで、速度による優位性も管理しやすい(※3)わけだが、入力方式としてはイレギュラーすぎる。「スト6らしい操作感」から外れていることによる違和感や、意図しない不具合も懸念されやすい。
(※3 例えば16Fだとマニュアルの平均入力速度と比べて殆ど優位がないし、4Fなら「まだ強い」と呼べる塩梅になると想像できる)
レバーレスvsアケコンvsパッド、真空波動拳[↓↘→↓↘→+P]の入力が一番速いのは誰だ!? コマンド速度王決定戦!!【まちゃぼー・キチパ】
そのため個人的には、ほぼ「ないだろう」と思うアイディアたちだ。
面白そうな代案として思い付くのは、SAの入力を「方向+強+SP」の(「強+SP」同時押しボタンを利用した、実質2ボタンの)従来方式から、「アシスト未入力→アシスト→アシスト離し→アシスト+方向+SP」という、前後ステップや天昇脚コマンド(N→下→N→下+攻撃ボタン)のようなワンアクションを加えつつ、実質3ボタンの同時押しとすることだ。
アシストを前ステのように連打することは通常、想定されない操作なのでOD必殺技からの誤発動も起きにくいだろうし、天昇脚コマンドと違って「入力成立前は好きな方向を押してていい」ので難しくもない。簡単操作がウリのモダンの良さも維持しやすいと思う。
そして、咄嗟の脊髄反射でSAを返すことはできなくなる。クラシックプレイヤーが真空コマンドをぐるぐるして「入力を作る」必要があるのと同様、ある程度の読みを加えなければ反応しにくくなるはずだ。
それでも、「ガードしながら待てる」「カクカクしないので入力を作っていてもバレにくい」などの点では強いままなのだが、ガードを兼ねる点では「真空竜巻コマンドのSA」を少し超えるくらいの利点かもしれない。
また、直感的にも「通常必殺技の入力の×2だからスーパーアーツ」という納得感を得やすい真空コマンドに対し、「OD必殺技(アシスト+方向+SP)の×2(アシ×2+方向+SP)だから真空コマンドに対応している」というイメージは初心者にこそ伝わりやすいのではないだろうか。
「現状の評価」と「調整の要望」は別、という結論
クラシックとモダンを両方使うプレイヤーとして思うのは、ワンボタンSAをほんのちょっと遅く、本当の咄嗟には出せないようにする調整は全然許容できる範囲にあり、それでも利点と言えば利点と思えるだろうということだ。
同時に、アシコンと封印技のテコ入れがその代わりに貰えるなら歓迎するだろうし、何よりプレイ環境に溜まっているヘイトが「ほんのちょっと遅く」したぶんだけ緩和され、みんなの納得感が増すのであれば、コミュニティ全体にとってプラスなことだろうと思う。
改めて最初の結論を振り返るなら、
1.今のスト6にモダンは“絶対”必要
2.モダンに調整は“現状は”必要
3.現状のモダンに不満やヘイトを感じる人がいるのは自由
4.ヘイトがあってもモダンプレイヤーがモダンを使わない理由にはならない
「現状への評価」と、「調整への期待や要望」は切り離せると思ってほしい。
現状は認めることにしたとしても、「改善できることなら、もっと良くなってほしい」という理想は、みんなで信じていいことのはずだから。
自動実況機能を使ったアイディア
最後におまけとして。自分がモダンと対戦してガックリする時というのは、「追い詰めた相手がモダンだとは気付かずに油断してSAカウンターされた」というシチュエーションが多い。
「ワンボタンSAはクソ」「モダンおもんな」と憤慨する人の多くも、この「気付かなかったおかげで逆転負けを食らった」経験が多いのではなかろうか。
そんな時、自分はモダンそのものではなくUIへ不満を向けるようにしている。試合開始前からモダンとクラシックの区別がイヤでも付くようにデザインされていれば、油断しようもないからだ。
「必要な情報が意識外になりやすい」という見落としの問題は、プレイヤーが努力する以前に、デザインで解決すべき問題でもある。
ところで、アール氏らの自動実況機能で「プレイヤー1」と「プレイヤー2」の選手紹介をするくだりに「プレイヤー1、モダンを選択!」などと丁寧に呼んでもらうのはどうだろうか。
というか、イベントで実際に出演している人たちの実況解説を聞いてみれば、選手の操作タイプという重大な情報に言及しないことはほぼありえない。むしろ、実況機能がそれを考慮していないのは不自然なくらいだろう。
ホンモノの格ゲーイベントを感じさせる、自然な実況解説を聞きたい(※4)という意味でも、互いの操作タイプを開幕から実況してもらえるのは嬉しいテコ入れ要素だと思う。
(※4 ちなみにバトルセッティングから音声ボリューム0、字幕ONにする設定もあるので、音声がジャマだと思うなら字幕で「読む」こともできる)
(※この記事は下記のはてなブログのエントリから転載しています)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
