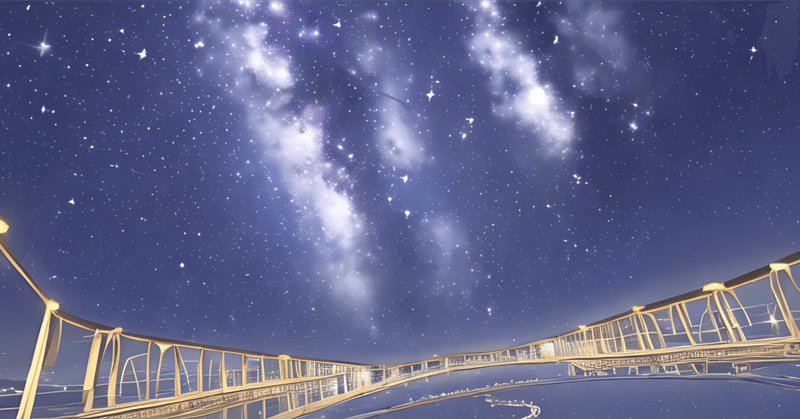
第11話 木暮雅人
「世界は平和だ、少なくとも飢えることはない。間違った生き方さえしていなければ。」
そう言ったのは確か父だった気がする。私達の家はそれなりに収入があって、資産らしい資産のない家庭ではあったが、留学までさせてくれた。それは私が一人っ子だったからからかもしれない。
余裕があったとは言えないが少なくとも貧しくはなかったような気がする。
百歳近くまで死ぬことはない。遺伝子疾患やなんらかの病気持ちであっても、適切な治療さえ受ければ、だれもが長生きできる。 国籍さえちゃんと持っていれば、この国の国籍を持っているかぎり、社会福祉は手厚い保護を与えてくれる、少しばかりの不自由と義務さえ差し出していれば。
私はこの街に戻ってきた日のことを思い出していた。
「FUKっていう名前のイカれた空港があるから日本は好きだね、とてもクールだ」と言って笑っていたミュージシャン。
2035年36年と続けて起こった大きな地震。昔流行ったマンガにちなんで関東地獄地震と呼ぶものもいた。正式名称は関東令和大震災と東海令和大震災。死者行方不明者の数は合わせて800万人を越え、火災により関東平野の三割の住宅が消失した。とはいえ、バイオレンスジャックもスラムキングも、それからアイラ武藤も現れることはなかった。無秩序な無法地帯になることもなく、それなりに秩序立てられた復興計画にのっとり再開発が進められた。けれども、新たな投資を呼び込むほどの国力も魅力も日本には残っていなかった。 政治的な中心地はそれでも東京に残っていたが、多くの企業は東京から消えていった。日本の経済的な中心地となったのが九州にある福岡市だった。 早いものであれからもう十年以上が過ぎている。あの日飛行機の窓から見た福岡の夜景の華やかさは昨日のように思い出すことができる。
窮屈な飛行機の椅子の横にある小さな窓から見えた地上の街の光。
地震から三年後。福岡市は日本の文化・商業における情報発信の中心地となっていた。
一方そのっころアメリカ合衆国では「ネオフェデラリストの陰謀」という陰謀論が幅を効かせるようになっていて、赤と青に分かれて二分されていた。ほとんど内戦状態といっていいような常態で、国のあちこちでテロが日常化していた。
そんなアメリカの生活に嫌気がかしていたのだ。
FUKOKAが日本の中心になってもう随分になる。
2048年にアメリカから帰って来たときには到着したのは福岡空港だった。そのころから線状降水帯雨による大雨が普通になっていて、何日も続くホースでばら撒くような大粒の雨が街を水浸しにしていた。今日はその合間の晴れの日だったが、気温は38℃、強烈な暑さは地球温暖化がどうしようもなく進んでいることを実感させた。七月から九月までの平均気温は32℃だった。北九州市でも暑い夜がしばらく続くのだろう。
台風も、個数が増えた。この10年間は、毎年40個以上の台風が発生している。
毎年の酷い暴風と土砂降りの雨の日。自分が子供の頃もいい加減暑かったが、大人になった2020年頃からはどんどん暑くなってきて、6月の中頃から9月の末まで、最高気温が40度を超えることも珍しくなくなっていた。
この時期、夜であっても気温は35度を超えることが普通で、ほとんどの人間は夜の街を出歩かなくなっていた。
夜の街は、かつての賑わいを失い、静寂が支配していた。街路灯が照らすのは、空っぽの店舗と閉じたシャッターだけで、昼間の喧噪はどこへ行ったのか。 街には確かに人が住んでいる。しかし、彼らは昼間の強烈な日差しと夜の蒸し暑さから逃れるため、自宅に籠もることが多くなっていた。
私がアメリカにいた頃、日本の友人から聞いた話では、エアコンを使わない家庭はほとんどなくなっていたが、電気代の高騰により、豊かな家庭は涼しい室内で快適に過ごし、一方で経済的に苦しむ家庭は暑さとの戦いに明け暮れていた。
そして、日本に戻ってきて私が見たのは、二極化する社会の姿だった。高層ビルの上層階には、ガラス越しに見える豪華なリビングルームと、夜景を楽しむ人々の姿。地上には、日陰を求めて行き場をなくした人々が、ビルの谷間のエレベーターのない低い建物にひっそりとたむろしていた。
街角のコンビニエンスストアの前では、涼を求めて店内に入ろうとする人々が列を作っていた。店の外では、氷水に浸かったペットボトルが、昼間なら太陽の光に輝いている。しかし、その光景の裏には、経済的な余裕がないために必要最低限の冷たい水さえ買えない人々の姿があった。
ビルの屋上から見下ろせば、一見して繁栄している都市の景色が広がる。しかし、その輝きの中には、見えない亀裂が走っていた。豊かな者とそうでない者の間には、目に見えない壁が築かれていた。
福岡の夜は、昔よりも静かになっていた。昔は夏の夜、子供たちの笑い声が響いていたものだが、今はそれも聞こえない。暑さが人々の活動を制限し、夏の夜の賑わいも失われてしまった。
私は、自宅のベランダで夜風を感じながら、かつての日本を思い出していた。子供の頃は、隣の家との間には狭い路地しかなかったが、今ではその路地も日中は灼熱の空間となり、夜になっても熱がこもっている。
私の家族は幸運な方だった。私たちは、まだ夏の暑さから逃れるための方法を持っている。しかし、窓の外を見れば、そうでない人々が多いのがわかる。彼らは夜、路地や公園で涼を求め、日中は日陰で身を寄せ合っている。
かつて私が住んでいたアメリカでも、社会の格差は深刻だった。しかし、日本に戻ってきてみると、ここでも同じような状況が広がっている。それは、見える形での貧富の差ではなく、生活の質という形で顕在化している。
福岡の新しい区分けは、都市の二面性を際立たせていた。 NWFUK(北西福岡)とSEFUK(南東福岡)という、ある意味で下品な響きを持つ名称がついた。都市のこの部分には、独特の文化が生まれ、それぞれが異なる世界を形成していた。NWFUKは、比較的落ち着いた地域として知られ、SEFUKは、裕福な層が集まる商業地域として発展していた。
しかし、このような単純な東西の分け方は、実際には福岡の複雑さを表現するには不十分だった。都市は単なる地理的な位置によって定義されるものではなく、そこに住む人々のコミュニティ、収入、教育水準、そして文化によって形成される。私がこの街に戻ってきてから10年以上が経ち、その間に見た変化は、単なる地名の変更以上のものだった。
福岡は今や、日本の経済と文化の中心地となっていた。東京の代わりにこの都市が、新たな日本の顔となっている。アメリカにいた頃、私は決して世界がこのように変わるとは思っていなかった。しかし、大切なことは常に自分の内側にある。それを誰かに奪われることはないが、失うことへの恐れは常にあった。
木暮雅人は、人は長生きするために生きているわけではないと考えていた。 確かに、長生きはできる時代になった。しかし、真に重要なのは、その長い人生をどのように過ごすかだ。 そしてこの変わりゆく福岡で、それぞれの人々が異なる生き方をしているのが、街の多様性を物語っている。
2058年6月21日
「今日は夏至ですね。一年で一番昼の時間が長い日です。時刻は22時、現在の最高気温は35.7℃と暑い夜となっています。」 ライブハウス『あんぷらぐど』でボーカルの男がおしゃべりをする。曲と曲の間、ハイハットの上下する音、スネアドラムとバスドラムのコンビネーションのリズムに合わせながら客たちに話しかける。フロアの客は「そんなことよりも次の曲を」と急かす。
ここは音楽を体で感じるための場所だ。 頭で聞くのではない、体で聞くということだ。五体そのものが感じる振動やリズムは、VRの共有体験では正確に再現することはできない。巨大なスピーカーから発せられる振動(爆音といっていい)音圧は実際のライブハウスだけで感じることができる。もちろん、全感覚没入型のVRシステム(NEUROSENSE-VR (Neurological Sensory Enhancement System for Virtual Reality)やIMMERSIO-VR (Immersive Multisensory Experience System for Virtual Reality))を利用すれば、完全没入感によって身体的な刺激も同期することができたが、一般市民に手が出せる価格ではなかった。
音楽というよりはむしろ肉体に刻まれる振動といったほうがいい音に身を任せていると気分が高揚する。人間が肉体で物事を捉えるということの証拠にもなると思う。
音楽は耳で聞くだけのものじゃない。リズムに合わせて、空気の振動に合わせて心臓の鼓動が同期していくような感覚になっていく、音楽と肉体がシンクロするのは、たしかに心地よかった。
巨大な音の振動は原初的な本能や欲求を満たしていくような気がした。
「嫌いじゃない、何よりも実感がある。」木暮はアナログでローテクなロックミュージックは、原始的な欲望を掻き立てるこの場所が嫌いではなかった。
ライブの楽しみ方は、多分この100年、変わっていない。
モッシュ、ダイブ、コールアンドレスポンス、シンガロング、自分が10代のころとほとんど変わっていない。100平米にも満たない小さなフロアは、50人も入ればもういっぱいいっぱいだ。誰かとぶつかることなくすれ違うことはできなかった。
自分が渡米する前、二十代前半のころは、ライブハウスは下火になっていて、イベントの回数も全国的に少なくなっていた。動画配信サイトやSNSで直接ファンと交えることができるようになったバンドやアーティスト達は、それなりのフォロアーを得ることで、一足飛びにホールライブを行うようになっていた。キャパシティー(観客数)が300人未満の小さな箱で行うのは、素人に毛が生えたような地元のバンドばかりだ。観客同士が顔見知りばかりでとても狭いコミュニティーがそこにはあった。自分が通っていたころも、ライブハウスへ行けば、誰か知り合いか、知り合いの知り合いばかりという状況がいつものことになっていた。
久々に行ったライブハウスは、そのときとは少しばかり状況が変わっていた。
まず、変わったのは、自分の年齢だ。もう十代二十代のころのような激しいノリは流石に無理だった。老体に鞭打つという言葉がぴったりだ。
それから、自分の知り合いはおろか同年代のものは一人もいなかった。考えてみれば自分も来年には還暦を迎える。座席のないライブハウスにとっては、想定外の客としてこの場にいるという、その場違いな感じを強く感じていた。
ライブハウスマーカス、過去三回あった、パンデミックによる行動制限を乗り越え、来年75周年を迎える、古くからある場所だ。ここにいるものは皆スタイルもいいし、誰もが魅力的に人体改造をしている。 天使のような均整のとれた人間ばかりだ。それは少し残念な気もする。みな綺麗だが似たり寄ったりで個性なんてないに等しい。どこかで見たような目、眉毛、口元、鼻筋、まるで大量生産された規格モノのドールのような顔ばかりだ。 男か女なのかは関係無い、ほとんどはどちらでもOKのバイセクシャルだ。 俺はナチュラルな女としか寝ないが、最近は見かけることが少ない。 ここにも、それらしいのが20人ぐらいいるが、せいぜい本物の女は三人か四人だろうと思う。 19時を少しすぎたころ、依頼人が現れた。 それが依頼人であることは一目見てすぐ分かった。 正直、少しばかり驚いた。 どんな人間が現れるかと思っていたら、アバターそのままの姿をした子供だった。 昨日の映像そのまま、着ている服まで同じ。 違うのはSIDの生体埋め込みチップがこめかみのところに二つ。アモルファスの輝きが濡れているように見える。 バリバリのサードしかも∑世代(2030年代生まれ)だ。 彼らを子供と思ってはいけない、独立した一個の人間として相手しなければならない。 保護という名のもとの年齢を利用した逆差別を訴えた彼らは、全てのネットを利用する権利を大人から奪還した。年齢による保護条例のあれやこれやは彼らが成人を迎える頃に廃止された。 そう、「子供は間違った判断をする」っていうのは、旧世紀の大人たちが自分のプライドを維持するために持っていた幻想にすぎなかった。成年と未成年の間で様々な契約を行うときに、誤った判断をして契約を間違うという割合は変わらなかったというエビデンスが明白になった。 大人と子供という区別はなくなっていた。成人だろうが未成年だろうが、騙される人間は騙されるし、騙されない人間は騙されない。アシスタントAIによるリアルタイムの警告や注意の表示はその差をなくしていたのだ。 ネットを使いこなせるようになり、ある程度のIR(インフォメーションリテラシー)を持っていれば、誰もがその権利を行使することができた・・・。 そう、子供だからといって馬鹿にはできない、彼らの頭の中にはありとあらゆる法律知識や、判例、情報があるのだ。 法を知る者が勝つのはいつの時代にも共通していた。 子供はモノを知らないという大義名分はもはや存在しなかった。 過去において大人たちが何十年もかけて得てきた知識や経験を子供たちは、半年もかからないうちに習得してしまう。 ネット上に有害と呼ばれる情報は数多く存在していたが、彼らはそれを使いこなすことが生まれながらにできるようなものだった、彼らは別の意味で現実とネットの区別がついている。 というより、ネットワークがより現実に近づいている。彼らにとって、ネットの人格と実際の人格を使い分けるのは、面倒で手間のかかるだけのことでしかないのだ。しいて言うなら子供を産む力、生殖機能があるかないかが大人と子供を分ける基準になった。 年齢ではなく、初潮を迎えたか、精通を迎えたかで大人と子供に区別される。
ただ区別されるだけで、大人と子供は同等の権利と義務を負っていた。20世紀末期に主張された「子供の権利条約」は子供達自身の手によってかなり拡大解釈された。 今の子供たちのほとんどは、生まれてすぐにSIMを植え付けられる、それが親(保護者)あるいは社会の義務だった。
おかしな話だし矛盾もある。SIDは14歳以上になるまでその施術を制限されるが、SIMは、生まれてすぐの装着が義務付けられている。 それが、「ネットに繋がる権利保障」 彼らは物心ついたときには当たり前のように、ネットを使いこなしている。
この子もきっとそうなんだろうな。見た目に惑われちゃだめだ、子供扱いしたらとんでもないことになる。
「あなたがグレッグ?」女の子が質問する。まだあどけない12かそこらの外見には合わない意外なほど落ち着いた声だった。彼女の瞳には年齢にそぐわない知性が宿っているように見える。 「通称だけどね、本名は木暮雅人だ。」 「はじめまして、依頼人の、ティファ・新宮寺です。約束分の振り込みは済ませてあるわ、確認してもらった?」 アバターと違って感じいい声だ。人工音声ではないように聞こえるがどうだろう。 「ああ、さっき待ってる間に済ませたよ、こいつでね。」 そう言って俺は、グラスタイプのSIDを彼女に見せた。 「そうよかったわ、じゃ早速、本題にはいっていいかしら?」 大人びた表情で彼女は話す。 瞳だけを見ていると、十分に成熟した大人のそれに近い印象を受ける。 「どうぞ」 「それじゃその前に、SIDの共感モードを開放してもらえるかしら?」 「すまない、俺の頭の中にはSIDは入ってないんだよ。外付けのやつでよければ別にかまわないが、どうしてだい?」 「本物のアンプラグドなんだ、初めて会った」と少女は笑い、少し驚くと同時に、珍しいものを見るような目付きになる。
「言葉じゃ伝わりにくいことってあるでしょう?」 「なるほどね」 俺はそういってグラスSIDを掛けた。起動するまでの時間がいつもより長く感じられる。 ログインが完了すると同時に彼女は無表情になって話し始めた。 「探して欲しいのはある男の子。」
「彼が生きているかどうかは、関係ないわ、あなたは見つけさえすればいいの、報酬は20万ユーロ、少ないかしら?」 今度はオフで彼女の声がした。 俺はSIDを外して話した。 「20万 ?そらまた豪儀だな、なんでそんな金が払えるんだい?」 「クリエイター・・・・」 そこまで言いかけて彼女の視線が遠くを見つめる。
彼女の視線の先にはメッセージが表示されていることが見て取れる。脳内の視覚情報野に直接表示される情報に注意を向けている人間のその表情だ。
「なにかメッセージが届いたのか?」聞こうとした瞬間彼女は言葉を遮るように言った。 「ま、いいわ、これ以上話すのはやめておきましょう。 連絡はここまで送ってくれればいいわ、定期連絡は結構です。何か変化があったときだけでいい。とりあえず必要経費として1万ユーロ」 そう言って彼女は紙に書いたアドレスを手渡すと逃げるようにビートハウスを出ていった。
それが2週間前の出来事だった。
100年くらい前、ネットのない時代に失われた情報を探すというのは、ほとんど不可能なことだったように感じられる。今日では、ネットワークの力により、あらゆる情報が保存され、手の届くところにある。それはまるで、広大な海に落ちた指輪を七つの海を探し回るようなものだった。
だが、だからこそ、隠された情報、公開されていない情報はネットの海まではながれてこない。ネットワークの外側に目を向けることがより必要になっていた。独立系のネットワーカーたち、彼らはインディーネットの影の住人だ。閉じられた小規模なネットワーク、ほとんどが会員制で、非公開サーバーで運営されている。数百人以下の小さなコミュニティで、彼らが扱うのは常に100パーセント違法な情報だ。殺人映像、幼児虐待、営利誘拐といった、狂気じみた、サイコパスのようなデータがここでは通貨となる。
この暗黒街のネットワークを渡り歩く者たちは、知識の裏路地を知り尽くしている。彼らとの取引は危険を伴うが、時にはそれが唯一の選択肢となる。この情報の迷宮を探索することは、戦いであり、その先には予測不可能な結果が待ち受けている。
情報は分断化され、それぞれの情報の海はつながることはなかった。いくつもの限られたネットワーク、限られた人間だけが接続することのできる、無数の情報の断片だけが漂っているのが電脳空間だ。
ネットの繋がりのなかでは、俺はグレッグという名前で動いていた。
本名は木暮雅人、コグレから連想しただけの単純なハンドルネームで、十代のころからずっと使っていたものだ。匿名SNSでの名前をそのまま使い続けてもう30年以上。今どきはハンドルネームを使う人は少数派になっていた。今はハンドルネームと本名を使い分ける意味やメリットはほとんど無くなっている。 俺はHMP(ハンプ)で情報家をやってる。 昔なら探偵って言う職業が一番しっくり来る表現かもしれない、探し屋なんて言われ方もする。主に情報ファイルの検索や探索をやってる。 依頼された事項に関するファイルをネットやオフラインで見つけ出し読みやすいようにまとめてクライアントに送る専門家だ。(いつの時代も専門家ってのが必要だ。) HMPって言うのはハーフマネーピープルの略だ。 マネーピープル(MP)、全世界人口の約35パーセントがマネーピープルと呼ばれるオフライン労働者達だった。実際の流通や実務には人の手が必要で、彼らは自分が行動する褒賞として金銭を要求した。彼らは消費し所有することに魅力を感じていた。そして、ネットで無料提供するだけの資源(資質や技能)を持っていなかったし持つ必要もそれほど感じていなかった。 そして彼らのほとんどはNWPだった。 MPのほとんどの人間は犯罪者か、ネット恐怖症の人々だ。(あるいはネットワークを使ったことがない者たち)ネットの情報と現実の区別がつかずに、実際に犯罪や殺人を犯した人間やNWP(ネットワークパラノイア)と呼ばれる精神病にかかった人間たち。彼らは自分自身の経験や記憶と、ネットワークにある記憶の区別がつかなくなっている。アイデンティティーが崩壊して自己消滅をおこしてしまった、あるいは起こしつつある人間だ。 典型的なタイプは「自分は本当は違う人間だ」と思いこんでる。もっとも彼らが異常なのかどうかは誰にもわからない。もしかしたら彼らのほうが正常なのかもしれないってことだ。だが、ひとつだけ確かに言えることがある、とにかく彼らは、自分でそういう生き方を選択したのだ。 HMPは両方にまたがる生き方を選択した人間達。そのほとんどはセカンド(セカンドミレニアムエイジ・1000~1999年生まれの人間を指す造語)の世代だ。2000年以降に生まれた人間でHMPのような生き方をしているものはあまりいない。言ってみれば前世紀の遺物、時代に取り残され得た人間たち。
俺は金も稼ぐし、情報も売る。 今の世の中では、ほとんどの情報は無料で手に入れることができるけれど、本当に必要な情報は有料で取り扱われている。まぁ、ほとんどの有料情報はクソみたいなもので、クソみたいな情報はほとんどの場合、たった一人にしか価値がない。 その情報が貴重だとか重要だとかそういう価値基準はない。 その情報を欲しがる人間が少なければ少ないほど情報は高価になっていく。 人間はクソにしか金を払わないってことなのかもしれない。 それでもクソしか欲しがらない人間は案外いるし、クソの大好きな人間は思っているよりもずっと多いだろう。
2058年6月8日午前3時26分
俺はいつものようにメッセージのフィルタリングを始めた。 俺のSIDは薄っぺらなグラス(メガネ)タイプで、頭にかぶせる6世代くらい前のモデルだ。けれどもそれで十分間に合ってる。 今はSIDを使ってるほとんどの人間が生体侵襲型を使ってる。 けれども俺には脳に直接機械を植え付けることに抵抗があった。ナノマシンが頭脳の表面に侵襲するイメージは食い物にカビが生えている様子を連想させた。 どうしても生理的に、受け付けることが出来なかった。 SIDグラスの起動まで約20秒。 頭の中で、「Welcome SIDCOM」と起動音が鳴り響く。
コネクト:メッセージ受信:::接続中 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、326通のメッセージが届いています。 そのうち312通は、識別コード99999:ジャンクメールです。 削除しますか?
「削除」と俺は声で答える。
「コネクト:削除します。」人工的な機械音声が返す。
DM(ダイレクトメール)は認められているものの、SIDCOMのサービスとして、やり取りされるメッセージのうち、ジャンクメッセージ、いわゆるダイレクトメールには必ず識別コードをくっつけないといけない決まりになってる。ない場合はIDを即座に抹消され以後2年間ネットに接続できなくなるからだ。とは言っても実際はIDは裏で金銭取引されているから、ほとんど意味はないのだけれども。 少なくとも個人識別が可能なので、SIDを使ったアクセスはできない。(もっともキータッチ式の端末からはアクセスできる)この時代、生体SIDを利用している人間の脳には一つ一つIPアドレスが振られているということになる。
コネクト:>>>件名を表示します。 1『あなたにお知らせがあります』 2『あなたをリッチにさせるいくつかの方法。』 3『満足していますか?』 4『宗教ではありません』 5『メールアドレスが消えてしまいました。』 6『私の秘密を見てください』 7『私の秘密を見てください。』 8『お久しぶりです。』 9『件名なし』 10『ディアムより、』 11『12月22日の件』 12『驚いた!』 13『25684XXX』 14『件名なし』 15『件名なし』 1から9まで、それから14と15は削除、 残りはダウンロード
「『ディアムより』を開いて」と音声コマンドを唱える。
目の前にディアムが現れる、なにか獲物を狙う光を秘めているような青い瞳をしているし、身長だって7フィート近くあるように見える。スマートで贅肉の無い若若しい青年だが、実物のあいつは40近くになる脂ぎったふとっちょだ。 メッセージで送られてくる映像は、100%AIで画像処理されていて現実とは程遠い。皆が自分好みのエフェクトを掛けまくって 前世紀のネットの習慣にならって「アバター」呼ばれてる。 『払いはキャッシュでいい?』 映像のディアムがさわやかな笑顔で話す。 すぐ返信:『馬鹿言ってんじゃないよ、デジタルトークンに決まってるだろう。すぐ振り込め』
「コネクト:メール返信を終了しました。」
13番のメールは仕事の依頼だ。 ページにあるコード、25684XXXは、ファイルの捜索依頼だ。 レベルがXXX ってことは相当違法性が高いのかもしれない。 「ダウンロード、メール13を」
「コネクト:メッセージを表示します」
59歳、来年は還暦だ。
自分が生まれた頃の還暦、そして自分が20だった頃の還暦は、その年令からくるイメージは随分違った。
そして2058年の今、還暦というのは、まだまだ若い。
女性の場合、還暦過ぎて出産するものも少なくなかった。
孫よりも若い、叔父や叔母も珍しくはなかった。
SIDを装着していない自分は、同世代の他の人間よりは老けて見える。
見えるだけではなく実際老けていると言っていい。
実際タイムマシンに乗ってきた、20世紀の人間が、この時代の還暦の年齢を推定すれば、ほとんどが、30代前半くらいと答えるだろう。
そして俺がいくつか尋ねれば、彼らは四十四か五ぐらいと言われるに違いない。
つまり俺は同世代のものよりも一〇歳以上老けて見えるっていうことだな(心外だけれども)アンプラグドの平均寿命はプラグドよりも10年以上短いという統計がある。
ファミリアのおせっかいは、食生活、生活習慣に事細かに口出ししてくるそうだ。
身体に良い食べ物、運動を行うアドバイスやレコメンドなんかを、それはもう嫌っていうほど送り込んでくるらしい。
俺はそういうのは間になってます。好きなように食べ、好きなように飲み、好きなように生きる。ファミリアの言いなりになる人生なんてまっぴらごめんだ。
ただし、アンプラグドにできる仕事っていうのは、限られている。
単純作業はもちろん、まともな職に着くことはほぼできない。
フリーランスの探偵家業は、プラグドではない者でもやることができる稀有の職業だと言える。警察官などチームで動く場合SIDは必須だが基本単独行動が主な探偵のような業務であれば、なくてもなんとかなるものだった。
いざというときの通信手段、コミュニケーション方法が共有できないというのは、そいつがチームで仕事をすることができないことの証明にしか過ぎない。
生態侵襲型でないSIDを利用するけれども、それでまあ十分な気がする。
サングラスの形をしたARメガネタイプのデバイスでSIDCOMのネットワークにアクセスする。音声による検索結果は、AIアシスタント、つまりファミリアの手にかかれば、それほど違いがない。
もちろんスピードが段違いに遅い。音声入力の場合は、声にしてプロトコルを伝える必要がある。つまりはひと手間が多いのだ。
「現在の日本におけるSIDCOMネットの利用者の総数を調べて」と実際に言葉にしてAR域に表示されたファミリアに質問する。
一方SID利用者は言葉(プロトコル)に落とし込む必要がない。
脳内で「日本のSIDCOMネットの利用者の総数は・・・」と言いかけた瞬間に、その答えが頭の中に思い浮かぶ。ネットの情報を検索していると意識することなく、ずっと前から、その答えを知っているかのように知識が肉付けされていくのだ。
プラグドたちは知らない。SIDを持たない少数派の人間たちが、どんな人生を歩んでいるのか。
そしてSIDを持たないアンプラグドたち、それを使ったことのない彼らは、その自分自身が選択した人生が正しいと知る方法も間違っていると判断する知識も持っていなかった。
新しい技術が生まれ普及したとしても頑なにそれを使わず変わろうとしない人間は以前から存在していた。アーミッシュや、ハッターライト、モナスティックな衣服をまとった宗教団体。テクノロジー回避を推奨する個人や小規模なグループ、宗教団体だけではないが、それを選択しない生活をしている者、情報のアクセスを制限している者は少なからずいた。
それは信仰とも言える。
彼らは同じような主張を持っている。口にするのは似たような言葉。
「プラグドは電子の奴隷だ、ただ搾取されているだけだ。自分自身で選んだ生活が正しいと知る方法も、間違っていると判断するための知識ももっていない。」と。
アンプラグドであるということは、ただ搾取されているだけなのかもしれない。自分だってそう思ったことは何度もある、今だってそう思っている。アンプラグドたちに、安価は疑似SIDを与えて、そして、アンダーグラウンドなSIDアプリの中にはLSDのような効果、中毒性のあるものもある。
通称『ガム』
形状はチューインガムと全く同じで、タブレット錠にしか見えない。口に放り込んで何度か噛むだけで接種できる。味はペパーミントのものが多い。そこはお菓子のガムと一緒だ。
違うのは、噛んだあと数秒後に、ナノマシンが構内の粘膜を通じて、脳に吸収される。SIDを施術したものにとってはとんでもない快楽をもたらす。もちろん、違法品だし、ネットで手を入れることはできない、実際の売人と”街のどこかで実際に会って”手に入れるほかはない。そしてその支払は現金のみだ。支払い履歴がネット上に残る電子的な決済方法は、その手の商売に利用されることはなかった。(この時代、現金は違法な取引でしか利用されないと言っても過言ではない。使われる紙幣は米ドル札がほとんどで日本の円もそれなりにつかえる。)
ソケットと呼ばれる生体侵襲型BMIもある。正式な名称はSIM。
「Society-Integrated Module」(社会統合モジュール)と呼ばれるそのデバイスはSIDCOMからライセンスの提供を受けた企業の製品でSIDと違い、頭蓋骨に穴を開けて、ソケットと呼ばれるデバイスを直接後頭部に接続する。手術自体は一時間ほどで終わる。
価格は200ドル程度、だいたい月給の半分くらいで手に入れることができる、貧乏人のためのSIDとも言われる。その名の通り、社会生活に統合されるためのデバイスで、昔の言い方で言えば、人体に直接接続されるマイナンバーカードみたいなものだ。外部からの入力もできるが、その時に利用されるものもガムと呼ばれる板状の記憶デバイスで、それを差し込み口に入れることで、アプリケーションのインストールをしたり、記憶の移転や伝達などを行うことができる。
「それって不便じゃない?いいかげんアンプラグドやめたら」
ディアムはいつもそう言っていた。冷ややかではあるけれど、大人をからかう子供のような目をしていたことを思い出す。
彼女は最新のSIDをその頭脳に持っていて、そして、いろいろなOSを組み合わせた、グレーゾーンのOSを使いこなして、電脳世界を自由に行き来していた。
彼女にとってこの現実の世界は、不自由な場所でしかないのかもしれない。ファミリアと一体化した彼女のアバターは、電脳空間を自由に移動している。たぶん、彼女に取って肉体はあまり意味を持たない。言葉を交わすのは電脳空間の中だけだ。お互いのアバターを介してセックスも何度か楽しんだ。
どんな出会い方だったのかは覚えていない。チャットルームだったのか、ワールドだったか、どこのSNSのサービスで知り合ったのか曖昧な記憶しかない。
きっと一番最初はたわいのない会話、挨拶程度のやりとりから始まったのだと思う。何度かメッセージのやりとりもしただろう。その頻度は少なかったように思う。それでもいつの間にか親しみを覚え、お互いの名前を呼び合っていた。
俺は彼女をディアムと呼び、彼女は俺のことをグレッグと読んだ。本名やどこに住んでいるのか、本当のところ、おれは彼女のことをなにも知らない。それでも電脳空間での出来事やネット上だけの関係性がちょうどいい距離で二人を絆げていたように思える。
世界は完全に二分されているといってもいい。
アクセス先は同じネットだしプロトコルも共通化されているけれども、ディアムのリアルな世界と俺の感じている世界は交わることはなかった。
けっして交わらないと言い切ることはできなかったけれど、まったく同じ時をともにしながら俺たちがが生きている世界は全く違った。
SIMは誰でも使用できるし、ナンバーさえあれば、日本国籍を持っていれば自分の肉体・頭脳を無料で利用できる電子端末にすることができる。
世界のほとんどの国家でも利用されている。人間全てに番号が割り振られていることは、幸せなことなのか、自由を失うということなのかは、よくわからない。
SIMやSIDを利用しないことによる不便さは途轍もなく大きかった。
「自分が自分であることを証明できない」
この一言に集約されている。
SIDCOMのネットワークに自分のナンバーを登録してさえいれば、必要十分な福利厚生を得ることができた。
大事なのは、生命の保護だ。
どんな生き方を選ぶことが、正解なのかは人それぞれだとしか言えない。
SIDのみを利用するものSIDとSIMのどちらも利用するもの、SIMだけを利用するもの、そしてそのどちらも利用しないもの。 実際、SID、SIM、どちらも利用していない、っていうのは、この世に存在しないっていうことと同じだ。見えない、存在しない人間だからこそ、そういう人間にしかできない仕事というのは、この世の中にはある。それが探偵やあるいスパイや諜報員という秘匿性の高い職業。なにかミスをしたとき、その正体を知られるリスクを極限まで小さくしたいとき、アンプラグドである意味が最大限活かせる。
俺は思い出す。
いつだったかディアムと交わしたバカバカしい会話の内容を。どうだったろうか、あのときは確かディアムとはVR空間の何処かでの会話だった気がする。
こんな感じで会話は始まった。
「私はSIDCOMのアカウントをもってないの。」とディアム。
「でも、君は実際アクセスしているじゃないか、この空間で会話しているっていうことはアカウントを持ってるっていうことだろう?」と俺は言う。SIMデバイスだとSIDCOMの能力・機能の一割も利用できないっていう話も聞く。だからといってディアムが嘘をついているようにも思えなかった。うん、たぶんそれは本当なのだろう。
SIDデバイスを利用するにはSIDCOMのアカウントを持っていることが必須だ。そもそもアカウントを持っていなかったら、サービスに接続することができない。けれど彼女はアカウントを持っていないという、どういうことなんだろうか?
「アカウントなんてなくても、この空間にいることははできるのよ」とディアムは続けて言う。
「この電脳空間の中にいるいろいろなAIやBOT、人格があるように見えるプログラムたちは当然アカウントを持っていない。それはわかる?」
「そりゃそうだろう、ゲームに出てくるキャラは全部がBOTだろう?単なるプログラムやアルゴリズムにしか過ぎない。ネットワーク上のプログラムなんだからネットに繋がっていないときはないし、実際に肉体を持っているわけでもない。」
「BOTの殆どはアクセスしなくてもコマンドを与えることができるの。」
「そもそも存在ってなんなんだよ」
頭脳が直接ネットに接続される、自分と他者との境目が曖昧になる。
脈絡のない会話がランダムに再生されるように流れている。
「・・・だけれども、そういうことは生理的に無理な気がする。自分の脳みそが外に向けて開放されている、思っていることや考えていることが、どこかの誰かに筒抜けになってるって言うことだろう。」
「街の大通りを真っ裸で歌いながら踊っているみたいなもんだ。自分の性癖を大きな声で叫びながら」
「俺はおっぱいが大好き、」だの「尻にむしゃぶりつくのがたまらない」だの変態なことをわめきながら闊歩するような変態じみた行為ができるとは、どうしても思えなかった。
「いや、そういうことじゃないよ、自分のプライベートや秘密については、きちんと隠すことだってできる」とディアムは言って続ける。
「ただ、自分のことを何もかも、隠し事がないように振る舞ったり行為したり、行動したりするほうが、長い目で見ると結局のところ最適解だってこと。」
「あぁ、そう。なんでも隠さないで正直にするのが一番正しい戦略だっていうのは、わかるよ。正直者が一番ってこと」
「そうよ」そういって彼女は微笑む。
「たしかに正直が一番なんだろうさ、けれども自分の嫌な部分もおかしな部分もさらけ出す、って言うのがどうもね。どんなことであれ、いずれは表に出てくるし、隠し事はできなくなるのだから。」
「言いたくないことを無理して表現したり、看板に書いて掲げるような行為っていうのは、どんなもんだろうね、。え」
「あなたが、そういう感覚を持つのも分からなく無いわ」
彼女は、そういって意地悪く笑うのだった。
「あなたの生きてきた時代、生まれた年、私がまだ生まれる前の世の中世界の価値観に照らし合わせれば、わたしたちが今言ってる内容は、みょうちきりんで矛盾だらけだっていうこともわかる。
大事なのは、なんとかして、その世界の矛盾を受け入れるのかっていうことなんでしょう?」
俺は流れ溢れていくディアムとの会話を反芻しながら、静かな部屋の中で考えを巡らせている。SIMやSIDのようなデバイスは、俺たちの生活を根底から変えてしまった。しかし、それによって得られたものと失われたもののバランスは、いつも微妙なものだった。
ディアムとの会話が途切れることなく再生される。思い出すというのとは違う手順で記憶が想起される。これは思い出しているわけではない、もしかしたらちょっとしたプログラムのエラーなのかもしれない。
彼女は、自分の真実を隠さないことが、電脳世界で生きる上での賢明な選択だと言っていた。しかし、僕にはそれがとても恐ろしいことのように思えた。自分のすべてを晒すことは、自分のアイデンティティを世界に露呈することに他ならない。
自分が今思っていることが、本当に自分が思っていることなのか自信がない。SIDが見せてる幻影なのかもしれない。そもそも本当に俺自身の記憶なのかどうかもあやしいのだ。
俺は窓の外を見ながらぼんやりと考える。この世界は、電子的な身体拡張を受け入れた人々と、そうでない人々とで分断されていた。SIDやSIMを持たない人々は、社会から取り残され、見えない存在になってしまう。それは、ディアムが言うように、電脳世界での生き方が唯一の生き方であるかのように思えた。
過去の映像が浮かぶ。
スマートフォンが鳴り、画面にはディアムからのメッセージが表示されていた。「今日はどう?また電脳空間で会わない?」彼女のメッセージはいつも俺を少しばかり緊張させた。彼女は、俺ににとって特別な存在だった。そう特別な存在だ。だが、彼女との関係は、電脳空間の中だけのものだった。現実世界での彼女の姿を僕は知らない。それが、この関係の不思議なところでもあったし、自然なことでもあった。
メッセージに返信するためにスマートフォンを手に取る。しかし、ふと思いとどまり、画面を見つめる。この電脳世界での関係が、自分たちにとって本当に大切なものなのか、それともただの逃避なのか、その答えはいつも曖昧だった。
「いいよ、会おう」と僕は返信した。そして、その日の夜、二人は再び電脳空間で会い、お互いのアバターを介して新たな会話を交わすのだった。
俺たちの関係は、現実と電脳世界の間の狭間で揺れ動いていた。しかし、そのどちらかを選ぶことは、まるで不可能なように思えた。二人はは、この新しい世界のルールに従いながら、自分たちの居場所を模索し続けていたのだ。
SIMERにとって、この世の中は妄想にあふれているのかもしれない。
生き方も価値観もぜんぜん違う、組み合わさることも交わることもない。
だれもわからないのかなそんなことは。
この都市で売り買いされるガムはどんな性能なのか、同じ人間に二束分のチェックを入れてもらうということが。
長い雨が街を包み込み、闇がますます深くなった。主人公は街角のカフェでガムの製造者、ジョンソンと会う約束をしていた。ジョンソンはこの街で最も不可解な存在の一つで、そのガムは半分都市伝説のように語り継がれている。不安と興奮が入り混じった気持ちで、主人公は待ち続けた。
ジョンソンがカフェに姿を現すと、彼はいつものように無愛想な表情で挨拶を交わし、すぐに本題に入った。
「君が探しているもの、それは「ターゲット」と呼ばれている。」
主人公は興味津々で聞いた。
「ターゲット?それは一体何なんだ?」
ジョンソンは深呼吸をし、慎重に語り始めた。
「ターゲットは、失われたもの、見つけるべきもの、そして闇の中で生きる者たちが必要とするものだ。それは、記憶のかけら、秘密の断片、そして未知の力を持つかけらなんだ。」
主人公はその説明を聞きながら、自分が抱えている仕事の依頼を思い出した。エリック・マルティネス・サントスを探し出す、という依頼だ。ジョンソンが言う「ターゲット」は、まさにそれにぴったりの言葉のように思えた。
「では、どうやってそれを見つけるんだ?」
主人公は尋ねた。
ジョンソンは微笑みながら答えた。
「それにはガムが必要だ。」
主人公は興味津々で聞き進んだ。
「ガム?あのガムのことか?」
ジョンソンは頷いた。
「そう、あのガムだ。それを使えば、ターゲットの痕跡を見つけることができる。ただし、ガムの効果は強力すぎて、使いすぎると依存症になる危険がある。」
主人公は考え込んだ。ガムを使えばターゲットを見つけられるかもしれないが、その代償は高い。依存症になってしまえば、自分のプライバシーも秘密も失ってしまうかもしれない。
「それなら、どうすればいい?」
主人公は再び尋ねた。
ジョンソンは重要な情報を伝える前に、まずは契約を結びたいと言った。それは彼の信念であり、仕事のルールでもあった。
「契約を結んで、ガムを手に入れたら、その使い方を教えてやる。ただし、その代償も受け入れなければならない。」
主人公は悩むことなく、頷いた。彼はエリック・マルティネス・サントスを見つけることが使命だと感じていた。そして、そのためにはどんな代償でも受け入れる覚悟があった。
ジョンソンは紙に契約書を書き始め、主人公はその内容を読みながら、運命の道を進む決断を下した。闇の中で生きる者たちが求めるもの、それはターゲットの痕跡をたどるための鍵だった。
そのディアムが死んだ、という知らせを聞いた。
警察が踏み込んだときには、脳が焼かれたようになっていて、記憶を読み込むこともできなかったそうだ。
デスログ(死ぬ寸前にアップロードされたはずの彼女の記憶メモリ、デスログと呼ばれる死亡する直前の24から60時間程度の記憶)も記憶されていなかった。
消去されていたようだと警察は言葉を濁していた。
本体なら、どのような者であっても死ぬ前の約36時間分の記憶映像、その脳が、目が見たもの耳が聞いたものは、すべてログとしてクラウド、ネットワーク空間に蓄積されているはずだった。
「それが消えていた?」
捜査官は答えた
「消えていた、というよりも、まるで最初からなかったかのように、改ざんされている」
「どうして改ざんされているって言うことがわかる」
「基本的にデスログは暗号化され、その改竄は不可能だ、事実上、無理。」
「消すこともできないはずだ。」
「消された痕跡すらのこっていない」
「つまり、どういうことだ」
「彼女、ディアムの存在そのものがなかったことにされている」
「ここにある死体はどう説明する?」
「というか、ここにあるこの死体がディアムかどうかは、誰も証明できない。」
「ファミリアを持っているなら、そいつはSIDのユーザーだし、自分のアバターを使ってコミュニケーションをしているなら、それはSIMのユーザーだ。それは間違いない。どちらにしてもログは必ず残る」
「どこのサーバーにもディアムがいたという痕跡がのこっていない?」
「そうだ、あんたの通信ログにのこされている、そのディアムという女(?)の識別コード、個別アドレスにはなにも残っていない。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
