
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録〈前編〉
まえがき・註
「AIで紡ぐ」という触れ込みですが、本文は全て人間が執筆しています。各章各節について、AI(GPT-4)に都度感想を求めながら書き進め、また画像生成AI(DALL-E3およびMicrosoft Copilot)により各シーンに適切な挿絵画像を生成しました。物語の発案、構成、および執筆は全て人間によるものですが、画像生成と監修を含めた総体的な作業についてAIとの協業の側面があるため、表記の通りのタイトルとしました。
なお、30万字以上の保存ができなかったため、前後編に分けております。
第1章
第1節『神秘の扉』
「やった!」
喉の奥を突いてついて飛び出しそうになる歓喜の声を押し殺して、その若いウォーロックはあたりを見回した。あぶないあぶない。ここは禁忌とされる裏路地の法具屋『アーカム』の店先。こんなところにいるところを治安維持部隊にでも見つかろうものならたちまち捕り物騒ぎになる。実際のところ、ここは権力の犬どもが手柄を上げようとうろうろしているアカデミーの目と鼻の先なのだ。

コイル巻きの暗号と呼ばれる複雑な迷路暗号を解き、この街の通りという通りを様々な仕方で歩いてやっとたどりつくことができたのだ。ここで下手を打つわけにはいかない。彼女は息を切らしながらも、最高潮に達するその胸の高まりを必死に飲み込もうとしていた。手の震えを懸命に抑えながら、ドアノブへと手を伸ばす。見たことのない古い錬金金属でできたそのノブは、彼女の興奮とは裏腹に季節外れの冷たさをたたえていた。

すっと一息ついて、彼女は一気にドアを引いた。その刹那、外の世界とは違う埃と黴にまみれた咳を誘う乾いた匂いが彼女の嗅覚を捉えた。制服の袖口で口元を覆い、彼女は薄暗い店内へと足を進める。店内にこれといった明かりはなく、入り口から一本、埃っぽい道が奥へと続いていた。その両側には見たこともない魔術具や魔法具であろうものが乱雑に積み上げられている。そこらのものにぶつからなうよう身体をよじらせながら先へ進むと、一層奥深いところにぼんやりと明かりがともっており、カウンターのようなものの奥にはっきりとはとらえられない人影のようなものが見えた。

その場所に向かって、恐る恐る足を進める。数ある裏路地の魔法具店の中でも一級と言われるこの店に今いることは、彼女のとめどない好奇心を大いに満たしていた。店主はいったいどんな人物か、今自分はどんな禁忌に触れているのか、その精神はこれから次々と明らかになるのであろう事柄に思いを巡らせることでいっぱいであった。少しずつ、奥のカウンターが近づいてくる。
「いらっしゃい。」
店主と思しき者の声が聞こえる。店主?ウォーロックの脳裏に不自然な違和感が走った。幼すぎる。ここは政府とアカデミーの第一級指名手配を受ける名うての裏法具屋だ。子どもの声などするはずがない。奥のカウンターに目をやるが、明かりに乏しいその一帯はうすぼんやりで、人影の詳細までは直ちには分からなかった。更に奥へと足を進めた。
「いらっしゃい。」
再びその声がして、あたりがぱっと明るくなった。その時の光景は今後長らく忘れられないものとなるであろう。目の前に現れたのは齢十にも満たぬ、あどけない少女であった。ブロンドのドレッドヘアで、透きとおるエメラルド色に輝く瞳をもつその少女は静かに語った。

「私はアッキーナ。アッキーナ・スプリンクル。この店の店主です。今日はどのような御用ですか?」
アッキーナ!?政府とアカデミーの双方が血眼になって探す第一級指名手配犯の、あのアッキーナ・スプリンクルがこの少女だというのか?ウォーロックの動揺をよそに、奥からもう一人の声がした。
「これ、アッキーナ。あまりお客様を驚かせてはいけませんよ。」

そう言って姿を現したのは、フードとヴェールでしっかりと顔を隠した聡明な口調の女性であった。
「まあ、いらっしゃい。今日はまた随分とお若いお客様ね。驚いたでしょう?でも、この子がこの店の店主というのは本当です。それで、今日は何をお探しでいらしたのかしら?」
「えっと…。」
ウォーロックは言い淀んだが、居住まいを正して、話し始めた。
「私は、ずっとここに来たかったのです。外の世界では決して見ることのできない数々の神秘的な品々を集めているというこの店に。コイル巻きの暗号のことを知ったときは、胸躍るような心地でした。これでアーカムに行けるのだと。そして、街の通りという通りをその暗号が示すであろう手順で、歩いて、歩いて、そして…。」
その胸の高鳴りは最高潮に達していた。興奮に押されて、自分が何を話しているのかわからぬままに言葉を矢継ぎ早に紡いでいた。
「あらあら、お若いのにあの暗号を解かれるなんて。あなたはとても優秀なのね。」
フードの女性は目元に笑みをたたえながらやさしくその言葉を遮った。
「お疲れになったでしょう?お茶でもいかがですか?」
一瞬のためらいの後、ウォーロックは頷いて答えた。
「アッキーナ、お茶を入れてちょうだい。」
「はい、マダム。」
少女はそう答えるとカウンターの奥に消えていった。かびた古書が放っているのか、神秘の香りがあたりに充満している。自分を取り囲んでいるその未知の品々が一体どのようなものであるのか、どうしてこうも禁忌とされる物品がここにはあふれているのか、そんなことに思いを巡らせながら、若いウォーロックはあわただしくあたりを見回していた。
「まぁまぁ、時間はゆっくりあるのですから、落ち着いてお掛けなさいな。」
マダムと呼ばれたその女性が椅子を差し伸べてくれる。彼女はそこにゆっくりと腰を下ろした。
「それで、何か、お探しのモノがあるのかしら?」
「いえ、ただ、とにかくここに来たかったのです。あらゆる秘術が揃うと言われるこの場所に。今、ここにいることがまだ信じられません。」
そんなとりとめもない言葉を交わしていると、カウンターの奥の扉が開いて、少女が3人分のお茶をのせた大きなお盆を両手いっぱいに抱えて出てきた。
「お待たせしました。マダム。べランドリウムのお茶しかありませんでしたが、それでよろしかったですか?」
少女がたどたどしく語る。べランドリウム?聞いたこともない銘柄である。お茶であるのかどうかすらウォーロックには判らなかったが、瑠璃色の深い色味と芳醇な薬香を称えるその液体は、何とも興味をそそるものであった。

「それでかまわないわ、アッキーナ。あなたも一緒にいただきましょう。」
少女は小さく頷いて、ウォーロックが座っているそばに置かれた小さな樽に飛び乗った。
「さぁ、召し上がれ。」
女性の促しに小さく目礼をして、カップに手をかける。口元までそれを運ぶと香りがふっと強くなった。嗅いだことのあるようなないような不思議な感覚だが、魔法学の講義で扱った東洋という地域の乾燥薬の匂いに似ているかもしれない。ウォーロックはカップを静かに口元に運ぶ。その瑠璃色の液体は、なんとも甘酸っぱい、柑橘類のような味わいに、生姜のような独特の辛みがあった。
「こほこほ。」
隣で、少女が小さく咳をしている。
「あら、アッキーナにべランドリウムはちょっと刺激が強すぎたかしら?」
「いえ、大丈夫です、マダム。」
「美味しいです。」
ウォーロックは静かに言った。
「これはどのような飲み物なのですか?べランドリウムという名前は聞いたことがないのですが…。」
「そうね、外の世界では知られていない、もう忘れられた古いお茶よ。葉もこの店に残っているぶんだけしか、きっと残っていないわね。」
「そんな貴重なものを頂いてよかったのですか?」
「ええ、久しぶりのお客様ですもの。もてなすのが私たちの務めですわ。」
そう言うと、彼女は静かにカップを傾ける。
「せっかくおいでになられたのですもの。お茶が一段落したら、店内をご覧になりません?」
「ぜひ!」
その瞳に宿る好奇の輝きを一層大きくして、鈴の転がるような声でウォーロックは答えた。女性はソーサーにカップを置くと静かに立ち上がり、手招きしてウォーロックを誘った。彼女はその導きに吸い込まれるようにしてその後についていった。カウンターの奥には更に店が広がっており、初めて目にする、何に使うのかもわからない魔術具や魔法具が所狭しとひしめいていた。
「これがね…。」
知性をにじませるその声が商品を説明していく。
生きたまま冥府の門を通過することができるが、うっかりすると自分が幽霊になってしまうかもしれないローブ、強い魔力に応じて敵をひとりでに打ち倒してくれるが、それを使う者を永遠の眠りに閉じ込めるという魔法の剣、天使への信仰を断ち切り、寿命を代償として捧げることで妖精王の力を授かることのできる着衣、健康と引き換えに膨大な魔力を一度に得ることのできる劇薬…、それからどれほどの時間がたったであろう。ウォーロックは神秘の品々について歌うように語るその女性の声に心奪われ、時が過ぎるのを忘れてしまっていた。その店のあらゆる品々が若い好奇心を捉えて離さなかった。全てが魔法の糸、スペル・バインで編まれたという、目に見えないローブをウォーロックが思わず身に付けようとしたとき、小さなアッキーナが慌ててそれを止めた姿はなんともほほえましいものであった。後から聞いたところでは、そのローブを一度身に付けると、永遠にこの世から姿が消えてしまうのだというではないか!
ひとしきり店内を見て回った後、三人は再びカウンターのある場所に戻ってきた。ウォーロックと女性は椅子に腰かけ、アッキーナはいそいそと奥の台所らしきところに向かって姿を消す。
まるで白昼夢を見ているかのように神秘の中で陶酔していたウォーロックは、かちゃりとカップをソーサーに置く音で我に返った。
「おかわりをどうぞ。」
アッキーナが、べランドリウムのお茶を運んできてくれたのだ。カップからは湯気が揺蕩っている。
「ありがとう、アッキーナ。あなたもそこに座ってクラッカーでもお食べなさいな。」
女性の優しい声の響きに、ごそごそとクラッカーの箱をつつく音が続く…。そして、サクサクという心地よい音が店内を包んでいった。
「せっかくここにいらしたのですから、一つ頼まれてくれないかしら?」
女性がウォーロックに語りかける。
「なんでしょう?私でお役に立てることなどあるのでしょうか?」
「実はね、最近この店に泥棒が入ったの。やってくるだけでも大変なこのお店に泥棒なんておかしいことだけれど、でも本当のことなのです。その実、犯人は常連さんなのよ。盗まれたのは『アッキーナの瞳』という、あの子の瞳と同じ色の法石が載った指輪。それは生命の神秘と霊性の安定を司るガブリエルの加護を受けた法石なのだけれど、って、アカデミーで魔法を学ぶあなたには今更いうまでもないわね。」
目元を少し緩めて女性が続ける。
「彼、あぁ、泥棒のことね。彼は、裏取引でその指輪を売りさばくつもりらしいの。でも、実はその指輪はちょっとわけありで、できれば取り返したいのです。でも、アッキーナはここを離れることはできないし、私はこの店とのかかわりを公にはできません。それになにより、このお店の性質上、警察に届け出るなんてできない相談ですから。」
女性は更に目を細めた。
「それでね、あなたにお願いしたいの。アッキーナの瞳を探して取り返してきてくれないかしら?」
「でも…、私はその男性のことを知りませんから、探しようがありません。」
「それは大丈夫。アッキーナの瞳は、ガブリエルの加護にある法石だから、それが取引されるのは、生命と霊性の安定に関する物品がやり取りされる闇市のはずよ。それがいつ、どこで開催されるかさえ突き止めることができれば、その取引の場に、彼はきっと現れるわ。ほら、最近アカデミーをにぎわしている看護学部の制服の横流しがあるでしょう?それが取引されるのと同じ闇市よ。なにかの手掛かりにならないかしら?」
ウォーロックの瞳に、俄かに若々しい好奇の色が満ち満ちてくる。
「はい!私にやりおおせるかどうかわかりませんが、看護学部の制服の横流しは学内でもちょっとした問題になっていますから、調べればきっとわかると思います。私も今年初等部の後期課程に進んで、ちょっとした護身はできるようになりました。きっとお役に立てるようにやってみます!」
その声は意気に彩られ、上ずっていた。
「じゃあ、お願いね。もし困ったことがあったらいつでもここを訪ねていらっしゃい。私はいつもここにいるわけではないけれど、アッキーナに言いつけてくれれば、連絡は直ぐに取れるわ。」
女性は立ち上がり、奥に向かって進み始めた。
「よろしくお願いね、かわいい魔女さん。」
そういうと、カウンターの奥の暗闇へ、その姿は溶けていった。
「帰り道は分かりますか?」
アッキーナが問う。
「コイルを逆順にたどればいいのよね?」
「そうです。それではお気をつけて。」
そういうとアッキーナは樽から立ち上がり、クラッカーの欠片をぽろぽろとこぼしながらウォーロックの手を引いて出口へと案内してくれた。来た時と同じひんやりしたドアノブに手を伸ばす。静かにドアを押し開け、アッキーナに手を振ると、彼女もまたモミジのような小さな手を振って返した。店を出た時、明日から訪れるであろう新しい生活の変化に、ウォーロックはその胸の高鳴りを抑えることができないでいた。
「これで、つまらないアカデミー生活ともおさらばよ!」
そう言って、彼女は来たときとはに暗号の道順をたどり、アカデミーの宿舎へと帰路についた。
陽が大きく傾き、魔法の街の石畳を赤く照らし出している。その赤さは、ウォーロックの心のうちに燃える好奇の色と重なるようでもあった。
「明日は早いわ。」
そう言うと、彼女はアカデミーの門の中へと消えていった。
第2節『看護学部の制服はおいくらで』
どこの世界にも好事家というのはいるものだ。そんなことをぼんやり考えながらネクロマンサーはベッドに身を横たえて、夜が白むのを待っていた。
最近、私の所属するアカデミーの看護学部ではおかしなことが流行っている。女学徒が自分の制服を闇市に密売するというのだ。若い女性の美しさを示すシンボリックな物品というのものは、一部の好事家やいわゆる変態と呼ばれる人々には大枚をはたいても惜しくはないということがあるらしいが、そうした感覚は全然わからない。ただ、周りの看護学部の同級生たちは、しきりに小遣い稼ぎに勤しんでいる。なんでも最近では、値段を吊り上げるために着装者の魔術記録を添付する「お顔付」なるものが人気を博しているそうで、お顔を美しく記録するために魔術記録に様々な細工をして盛るのが流行りなのだという。事程左様に、教室からは制服が次々と消え、汚損を理由とした再支給の申請が後を絶たない。アカデミーの事務方は頭を抱えているそうだ。
まあでも、私にはそんなことは関係ない。

私は、本科を死霊科に置き、看護科を掛け持ちするネクロマンサーにすぎない。地味な私の制服など欲しがる者は、余程の物好きでもいないだろう。なにより、その闇市とやらがどこで開催されているのか、そんなことは知らないのだ。それより、二科の掛け持ちで忙しい日々をどう前向きに紡いでいくかの方が遥かに大切で、よそ見をしている暇などなかった。
寝返りを打つと、壁に掛けた制服が目に入る。こんなものが、とんでもない値段で売れるこの社会はどうかしているわ。もしかして、私の制服も皆のようにお顔を盛ったりすれば売れたりするのかしら、そんなことを思いめぐらせているうちに、薄明りの窓の外から小鳥の早朝のさえずりが聞こえ始めた。朝だわ。
彼女はゆっくりとベッドから起き上がり、やかんを火にかけた。小さなテーブルにつき、パンとハムを用意する。コーヒーも入れよう。やかんが沸騰を告げる。ひととおり朝食の用意を済ませ、乾いたパンと塩辛いハムをコーヒーで喉に運んだ。陽が少しづつ高くなる。
用意を済ませ、寮の自室を施錠する。今日は看護学部の回復術式の実習の日だ。いつもなら赤と黒の禍々しい死霊科の制服を着て出かけるところだが、今日は一部で「桃衣」として人気を博しているらしい看護学部の制服に身を包んでいる。明け方の思索ともつかないものふけりのくだりを反芻しながら、彼女は看護学部棟の方へ歩みを進めていった。
寮から看護学部等までは少し距離がある。小高く丘になったところ、そこには食堂などがあり、昼間には多くの学徒で賑わいを見せる、その場所の脇を通り抜けて丘を下りつつ、大教室棟の方へ向かう。そこには暗黒魔導士科と魔術師科の教室が軒を連ねている。彼女たちは華々しいが、暗黒魔導士科の学徒たちは少し能天気であけすけだし、魔術師科の学徒たちは純血魔導士科の優秀な学徒たちに負けまいと目を血走らせて勉学に励んでいる。そのがつがつとした向学心は正直あまり得意ではない。
そんなことを考えながら丘のくだりに差し掛かったころ、ちょうど暗黒魔導士科の教室への入り口があるあたりだ。そこから私を呼び止める声が聞こえた。
「ねぇ、ねぇってば!聞こえてるんでしょ。」
振り返ると同じ年頃のウォーロックの子が私を呼んでいる。気づかぬふりでとも思ったが、こちらが気づいたのを察したのか、ずんずんと近づいてくる。
「ちょっと、聞こえてるなら返事くらいしてよ!」
「え、はい。あの、ごめんなさい。」
「ねぇ、死霊科の4年生で看護科と掛け持ちしているネクロマンサーって、あなたのことでしょ?教えてくれない?その制服ってどこで売ってるの?」
「あの、何のことですか?」
「だから、その制服を売っている場所を教えて欲しいのよ。」
「これは看護学部の支給品ですから、買うことはできないかと…。」
「そんなことを聞いているんじゃないわ。だから…」
「あの、これが欲しいのですか?」
「あなたの着古しなんて興味ないわよ。そうじゃなくて、この制服が取引される闇市のことを知りたいの。」
合点がいった。しかし、このウォーロックはなぜそんなことを聞くのだろう。
「あの…、看護学部の制服が最近不正に取引されていることは私も知っていますが、残念ながら私は制服を、あの…、まだ売ったことがないので、闇市の詳しいことは知らないんです。」
「ふーん。あなたみたいな美人の制服なら絶対高く売れてるはずだと思ったんだけど、眼鏡違いだったかな?」
よくわからないことを言う。しかも、勝手に眼鏡違いとは失礼きわまる人だ。これ以上関わっても仕方ない。そう思ってその場を離れようとするが、声はまだ続く。
「ねぇ、お願いがあるの。私に手を貸してくれない。事情があってその制服が取引される闇市の開催日時と場所を突き止めたいのよ。」
ますますわからない。しかも、こちらのことはお構いなしだ。
「実はね。私、あるものを探しているの。どうやらそれはガブリエルの加護を受けたものらしくて、看護学部の制服が取引される闇市で売りさばかれる可能性が高いらしいのよ。それで、闇市のことを調べてるの。」
それが、私と何の関係があるのか?
「それで、秀才で美人と噂の掛け持ちネクロマンサーのあなたを探していたわけよ。」
「あの、残念ですが。私ではお役に立てません。別の看護学部の方に当たってください。」
「そうはいかないわ。手伝ってもらうには一通りの護身ができる人じゃないと困るもの。」
手伝う?なぜ私が手伝うことになっているのか?それに護身とはどういうことだ?
「相手はね、泥棒なの。それに闇市なんかに踏み込んでいくわけだから、攻撃術式の一つもできる人と一緒じゃないとね、なにかと困るのよ。回復術式や治療術式しかできない看護学部の人を連れて行ったって、足手まといになるだけでしょ?」
ウォーロックは思うままにしゃべる人が多いとは聞いていたがこうまでとは思わなかった。
「それでね、あなたを探してたの。死霊科との掛け持ち生って思ったより少なくてね。4年生ではあなただけでしょ?ねぇ、私に力を貸してくれない?あなた、攻撃術式や召喚術式は使えるのでしょ?」
「はい。それはもちろんできますが…。」
「なら、決まりよ!」
何が決まったのだろう。遠くで予冷の鐘が鳴るのが聞こえる。
「いけない!授業が始まるわ。今日遅刻すると補習なのよ。もう行くわね。お昼に丘の横の泉のほとりで待ってるわ。絶対来てよ。いいわね!」
そう言い残しながら嵐が去るようにそのウォーロックは駆けていった。何だったのだろう。とりあう筋合いもないが、私にもそんなことを考えている余裕はない。急がなければ遅刻してしまう。看護学部棟へと足を早めた。
* * *
思いがけない嵐に遭遇したが何とか間に合った。教室に入ると、中が騒然としている。どうやら、また制服の密売がアカデミーの事務方に露見したらしい。教卓には随分と不機嫌な事務方教員がいる。
「全員席につけ!」
その不機嫌が声の形を得た。
「またしてもアカデミーからの支給品である看護学部の制服を闇市に売りさばいた不届きものがいる。君たちはいったい制服を何だと考えているの
だ?」

「お金の種です。」
そんな小声が聞こえた気がした。
「とにかく、今後は制服の支給は汚損品との交換を前提とする!」
「えー!」という抗議の声が上がる。
「これからは汚損品との交換でなければ新しい制服の支給はしない。いいか!制服を売りさばく不届きものは今後は下着で講義を受けてもらうからそのつもりでいたまえ。パンツェ・ロッティ教授の点数を稼ぐにはまたとない機会となるだろう!」
そう言うと教員は席をけって教室を出て行った。教室内が一気に騒然となる。
「どうしよう、今月の寮賃、制服売って捻出しようと思ったのに、困ったことになったわ…。」そんな声が聞こえる。耳をそばだててみると更に色々と聞こえてきた。
「心配ないわ。お顔付の制服ほどいい稼ぎにはならないけど、看護学部の物品なら大抵何でもお金になるんだから!よかったら、今度一緒に闇市に行かない。帽子でも手袋でも何でも売れるわよ!近々だしね。」
その口調から察するに彼女は闇市の常連のようだ。確かにきれいな顔立ちをしている。彼女のお顔付であればさぞ高く売れるのだろう。そういえば、彼女のお顔付の制服が史上最高値を更新したとか何とかいう話を以前に聞いたことがあるような気もする。

闇市は文字通り禁忌の場所である。治安維持警察に見つかればもれなく逮捕・補導だ。アカデミーの学徒とて例外ではない。普通の神経ならそんなところに出入りする気にはならないわけだが、やはりお金の魅力はそれだけ大きいということなのだろう。私は、これまでそうした場所には関心すら寄せてこなかった。ところが、今朝方から俄かにしてそうした黒い誘惑が私の周りをしきりにうろつく。どうしたのだろう?いずれにしても、そのような場所に出入りして、悪銭を稼ぐなどとは世も末だと思うが、しかし、先ほどのウォーロックが喜びそうな話ではある。私の耳は自然とその話に聞き入っていた。
「ねぇ、知ってる?今度の闇市には人為のロードクロサイトが出品されるらしいのよ!あの石、回復術式の力の引き出しに抜群の効果があるらしいから、今度の試験に使えるかもね!」
人為のロードクロサイト!?聞かなくていいことを聞いてしまった…。人為のロードクロサイトとは、つい最近、錬金術と魔法による人為的な錬成が成功した法石で、生命と霊の領域に極めて強い効力を持つとされているものだ。それがあれば、アンデッドの制御を非常によくすることができるという。私は今、メダリオンを使ったアンデッド錬成の儀式について学んでいるが、メダリオンにその法石を使えば、非常に強力なアンデッドを生成できるらしい。また、ロッドにその石を据えてゴーストを召喚すれば、とても特徴的な魂魄を召喚できるという。
私はゴーストの召喚が好きだ。あの独特のシルエットは何とも愛らしい。とくにあのぷりっとしたおしりがたまらない。スケルトンなんて、ガリガリでなんのかわいげもないが、ゴーストのあのぷりぷりしたおしりを眺めているだけでネクロマンサー冥利に尽きると言ってもいいかもしれない。それは言いすぎか…。いずれしにしても、人為のロードクロサイトを据えたロッドがあれば、召喚するゴーストの姿形をかなり思い通りにできると聞く。俄然興味が沸いてきてしまった。
「あの…。」
自分でも驚くことに私は思わずその女学徒に声をかけていた。
「その闇市は、…どこで開かれるのですか?」
「驚いた!あなたみたいな優等生が闇市に興味があるの?」女学徒は目を丸くする。そんなに意外か…。
「いえ、あの、どういうところで看護学部の品物が売れるのか少し関心があって…。」
「ふーん。いいわよ。教えてあげる。確かに闇市では何でも売れるけど、制服ほどいいお金になるものはなかなかないわよ。下着でも売ればべつだけど。」
彼女はいたずらっぽく笑った。まさか下着を売ったことがあるのか?
「でも、ただで教えるって訳にはいかないわね。」
その口元が意地悪く歪む。
面倒なことを言う…。
「あの、どうすればいいですか?」
「あなたもアーカムのことは知ってるでしょ?そこで売っている『恋のしずく』と交換ってのはどう?」
アーカム…、禁断の法具屋。聞いたことはあるが、そこに至るためには知る者だけが知る特別な暗号を解かなければならないとされる秘密の店だ。そういえば先月魔法雑誌で特集されていたが、そんな所への生き方なんかわかる訳がない。関わるのではななかったかもしれない…。若干の後悔にさいなまれながらも二の句を継ぐ。
「もし、それを持ってくれば、闇市のことを教えてもらえるのですか…?」
「ええ、『恋のしずく』さえあれば、あの泥棒猫に取られた彼を取り戻せるもの。ちょっとした荒治療だけどこの際仕方がないわ。」
そういう彼女の瞳は色濃い光を放っていた。
「そうですか…。探してみますね…。」
「ええ、もし手に入ったら、交換条件よ!」
そういうと彼女は踵を返し、その取り巻きたちと闇市では何が高く売れるかという話に花を咲かせている。聞こえてくるところでは、彼女たちはお金のためには本当に下着を売るらしい。どこのブランドのものが高く売れるとか、お顔の魔術記録をどう盛ればいいか等、その話は尽きることがない。どうやらロコット・アフューム製の物品が闇市では人気だそうだ。確かに、あそこのブランドの服飾はかわいい。私のような地味な女にでも欲しいと思わせるものがある。
本鈴が鳴って、教科担当の教授が入ってきた。授業が始まる。講義は昼まで2コマ、みっちりと続いた。
* * *
午前の講義終了を告げる鐘がなった。さて、どうするか?彼女は丘の横の泉のほとりで待つと言っていた。そして今、私には、断片的にではあるが闇市に関する情報がある。なによりその闇市には人為のロードクロサイトが出品されるというのだ。いつもの私なら、こうした危険からは身を遠ざけて、安全第一の判断をする。ただ今回ばかりは?思案しながらも私は丘を登って、泉の方へと向かっていた。
「やあ!」
今朝以来の声が聞こえてくる。彼女だ。
「やっぱり来てくれたんだね!」
まだ決めたわけではないが…。
「で、どう?手を貸してくれる気になったから来てくれたんだよね?」
その疑いを知らぬ目が期待に満ちた輝きを増す。
「あの、とりあえず、闇市のことがちょっとだけわかりました。」
「そうなの!どんなこと!?」
「私の看護科のクラスに、どうやら闇市の常連と思しき人がいるんです。」
「で、で?」
「その彼女に闇市のことを訪ねたところ、交換条件を持ち掛けられまして…。」
「うんうん。」
「闇市開催の日時と場所の情報と引き換えに、アーカムで売られている『恋のしずく』を持ってきてほしいと、そう言うんです。でも、あなたも知っての通りアーカムはとても有名なお店ですが、そこに行く方法がわからなくて….。」
「なあんだ!そんなことなら問題なしよ!」
ウォーロックは大きな目を一層見開く。どういうことだ?
「ここだけの話だけどね。」
彼女はもったいぶって言葉を続ける。
「本当は秘密にしておくべきなんだろうけど、私とあなたはこれから運命共同体だから話しておいてもいいかもね。」
運命共同体!?何のことか?
「実はね、私の探し物というのはアーカムからの依頼なのよ。」
驚いた。この子はアーカムに行ったことがあるというのか?
「この間ね、私、ついにアーカムに至る道を見つけたの。あのコイル巻きの暗号を解いたわけね。」
なんということだ!ただのお調子者かと思ったが、あの暗号を解いたというからには、魔法使いとしての力は本物なのだろう。興味が沸く。
「それで、アーカムを訪ねたんだけどね。そこで出会った人に、最近アーカムで起こった窃盗事件について相談されたの。その時盗まれた法石を私に取り返してきて欲しいってね。それで、その法石が、ガブリエル関係の物品がやり取りされる闇市、つまり看護学部の制服が売られるその場所で売却される可能性が高いということらしのよ。それで貴方に声をかけたわけ。」
なるほど。
「ということは、あなたは再びアーカムに行くことができるのですか?」
「もちろん!再びでも三度でも、何度だって行けるわ!」
「それなら、『恋のしずく』を手に入れることもできる訳ですね。」
「もちろんよ。」
彼女は水筒の代わりにしているのであろう薬瓶の水を一気に飲み干すと、大きく息をついてこう続けた。
「これで話は決まりね。早速アーカムに行きましょう!今日の放課後、いいわね!」
相変わらず他人の都合を一切気にしない人である。しかし、人為のロードクロサイトのこともある。お金はかかりそうだけどいざとなれば、何か売ってでもお金は作れる。でも、私の下着なんて売れるのかしら?おかしな考えが頭をよぎる。禁忌の場所に近づくというのは正直気乗りしないが、見返りは悪くない。
「それでは、放課後ゲート前で…。」
気が付けば私の方から場所を指定していた。腹をくくるべきか?
「でも、裏取引の場に踏み込むなんて危険ではありませんか?」
「大丈夫よ!」彼女の顔は自信に満ちている。
「私、こう見えても閃光と雷の領域は得意なのよ。まだ4年だけど、『雷:Lightning』の術式が使えるわ!」
すごいことだ。人となりはともかく、魔法使いとしての力量は確かに違いない。
「あなただって、『魂魄召喚:Summon Ghost(s)』くらいはできるのでしょ?いざとなればあなたのゴーストをけしかけて、私たちはスタコラよ!」
「ええ、まぁ、魂魄召喚は使えますが…。でも一度にそんなにたくさん召喚できるわけではありません…。」
「大丈夫よ。あなたが優秀であることはいろんなところから聞いているもの。あなたと私の二人ならきっと何とかなるわ!」
何だろう、この様子だと作戦も何もなしにその場に踏み込むつもりなのだろうか?それともアーカムに応援でもいるのか?複雑な感情が脳裏をよぎる。しかし面白そうでもあるのは確かだ。なにより、人為のロードクロサイトが手に入る機会を得られるというのが大きい。あの法石はまだ錬成されたばかりで市場には出回っていないのだ。
「わかりました。では、放課後、ゲート前でお会いしましょう。アーカムまでの道案内をお願いします。」
「いいわ。よろしくね!」
「はい、こちらこそ。」
とうとう話がまとまってしまった。午後の講義をどのように過ごしたのかよく覚えていない。どうしたのだろう、私も禁忌の狂気に取りつかれたのだろうか?放課後を告げる鐘が鳴り響く。とにかくゲートに急がなければ。
第3節『再訪』
講義が終わった。
汗が首筋を流れ落ちる。既に夕刻に差し掛かるが、夏の日は高く、これからまだ何事か成そうというには十分な時間が残されていた。夜まではまだ長い。ゲートの柱に背をあずけて、誰かを待つ若いウォーロックはしきりに看護学部の方を見やっていた。昼間の約束は果たされるのか、ほんの少しの心細さとともにそこに佇んでいた。

彼女は昨日からのことを思い出していた。コイル巻きの暗号と呼ばれる迷路に気づいたのはつい先月のことだった。この魔法の街の地図を広げて全体を俯瞰すると、ところどころに電磁コイルを巻いたかのような一連の流れが現れるのだ。それを見出した時の興奮といえばなかった。そのコイル状の通りの連鎖にはいくつかのパターンがあるが、なかなかその全容はつかめなかった。分からないならば試すしかない。若いウォーロックは持ち前の好奇心と行動力に身を任せ、全てのパターンを総当たりで試してみることにした。その道を左巻きにたどるべきか、右巻きにたどるべきか、最初はそれすらわからなかったが、あるとき、とある一連の通りを右巻き辿るとクリーパー橋のところでうまくくるりと線が回らなくなることに偶然気づくことができた。それできっと左巻きが正解なのだろうと思い定め、それから毎日、候補となる通りをひとつひとつ変えながら、ひたすら左回りにその街を彷徨った。思えば、コイル巻きの暗号というのもずいぶん怪しい情報だった。週間魔法誌の特集にたまたまアーカムのことが載っていた。記事は面白おかしくそこにたどり着くための秘密について書き連ねており、その中に「コイル巻きの暗号」という言葉があっただけだ。コイル状に通りを巡っていけばアーカムにたどり着けるかもしれないというのは、彼女の思い付きでしかなかった。そもそもその雑誌記事は、本気でアーカムを取り上げるでもないただの娯楽記事にすぎなかった。
しかし、昨日、彼女はついにその道筋を見つけたのだ。その突飛な思い付きは当たっていた。アーカムへは、特定の通りを特定の順序で踏破することでたどり着けた。ポイントとなる通りは5つで、クリーパー橋の西の切れ目から、マーチン通り、アカデミー前、リック通りを経てクリーパー橋の下の高架下を通りぬけ、最後に南大通りを南下する。すると本来は別の店があるはずの南大通りとアカデミー前の交差点にアーカムが現れる!肝心なのは、クリーパー橋を渡るのではなく、その高架下を行くことであった。この通りに進んでいくと、クリーパー橋の高架をくぐるあたりから周囲が霧に覆われてくる。南大通りを南下するに従ってその霧は次第に濃くなり、アカデミー前との交差点に差し掛かるころには、周囲数メートルしか見えないほどにその霧は濃さを増していって、そのただなかにアーカムはあった。アーカムといえば、違法店の中でも、政府とアカデミーから第一級の指名手配を受けている特別の存在だ。だから、それがアカデミー前と南大通りの交差点に位置しているというのはあまりにも意外だった。木を隠すには森の中ということか。いずれにしても濃霧の中に『アーカム』の看板を見つけた時の感動は生涯忘れることはできないだろう。クリーパー橋の南の切れ目から、通りの頭文字を繋ぐと、マーチン通り:Martin Street、アカデミー前:Academy Avenue、リック通り:Rick Street、クリーパー橋の高架下:under the Creeper Bridge、南大通り:South Avenueで、M.A.R.C.S.となる。このマークスというのは、魔法社会に住む者なら誰でも知っている古いおとぎ話に出てくることばで、「魔法のお印」というような意味だ。偶然の一致かどうかはわからないが、そのお印の位置にアーカムは確かにあった。街全体には他にもコイル状に通りが巡っている個所はいくつかあるが、その頭文字が有意な意味を持つのはこの組み合わせしかなかった。
* * *
そんなことを思い出していると、看護学部棟のほうからこちらに小走りで向かってくる人影が見えた。彼女だ!黒髪のネクロマンサーは、昼休憩の約束を反故にはしなかった。これで冒険が始まる。若いウォーロックの心は、興奮と好奇に満たされていった。
「遅れてごめんなさい。」
「いいのよ。看護学部棟からここまでは遠いもの。そんなに待ってもないし。それより随分走ったみたいね。大丈夫?」
「ええ、大丈夫です。回復術式の実習が長引いてしまって。それから、制服転売についての注意と指導が講義後にもあったりしたものですから…。」
「そうだったの。それにしてもその制服、そんなに良く売れるのね。ウォーロック・コースのこの黒いのも売れないかしら?まぁ、色気の違いってやつかしらね。」
ウォーロックは苦笑いを浮かべる。
「さあ、行きましょう!といっても結局はここに戻ってくるんだけどね。」
「どういうことですか?」
「アーカムはここからすぐのところにあるのよ。昨日と同じならね。でも、随分遠回りをするわ。結構時間がかかるからすぐに行きましょう!まず、クリーパー橋の西端までいかないと。」
「そんなに遠くまで行くのですか?目的地はこの近くなのに?」
「そうなのよ。そこが出発点。クリーパー橋の西を行き切って、マーチン通りから始まるわ。そこから特定の道順でここまで戻ってくるの。面白いわよ。」ウォーロックはころころと笑った。
「さぁ、出発!」
「はい。」
二人は歩みを進める。道すがら、二人は色々な話をした。お互いの名前、専攻科、それを選んだ理由、将来の夢にはじまり、好きな魔法具のブランドから好みの異性の特徴まで、話に花が咲いた。面白かったのは、最初よそよそしい感じのしたネクロマンサーの少女が、思いのほか少女趣味で、ぬいぐるみやマスコットなどの外観のかわいらしいものをとてつもなく愛好しているという話であった。特に召喚したゴーストのおしりをめでるのが好きで、いかにかわいらしい姿のゴーストを召喚できるかに多くの情熱を傾け、アカデミーでの研究に没頭しているというくだりは、アカデミーで習う魔術や魔法学など退屈だとしか感じていないウォーロックにとってはとても新鮮に感じられた。その時のネクロマンサーの語り口はとても流暢で、朝方の遠慮がちに話す姿とは実に対照的であった。ネクロマンサーの方もまた、ウォーロックのする、屈託なく気の置けない話し方に幾分かは慣れたかのようであった。途中で休憩することも考えたが、二人とも興味の方が勝ったようで、そのまままっすぐにマークスを辿って行った。
昨日と同じように、クリーパー橋の高架下を抜け、南大通りに差し掛かったあたりから、天候の良さとは不釣り合いな濃い霧があたりを覆い始めた。南大通りからアカデミー前通りに戻るころには、あたりはすっかり真っ白で、照り付けていたはずの太陽は、霧のヴェールの外でぼんやりとした輪郭をだらしなくゆらしていた。霧は夏の暑さを強調し、ふたりとも汗がやまない。アカデミー前の交差点は、石畳が整備され清潔な場所のはずであるが、あたりの空気には不思議と土や草の香りが入り混じって、その場所のもつ特別な時代性を醸し出していた。やがて『アーカム』の看板が二人の前に姿を現す。
* * *
「ここよ。」
声を弾ませてウォーロックはネクロマンサーに言った。
「ええ、驚きました。本当にこんなところにアーカムがあったのですね。」
ネクロマンサーの美しく黒い瞳もまた好奇の光で輝いて見えた。
「さぁ、行きましょ。さらに驚くことがあるわよ。」
ウォーロックはいたずらっぽく笑うと、昨日と同じ見慣れぬ錬金金属のドアノブに手をかけた。そのときと同じ冷たさがてのひらに伝わる。
「あれ?」
「どうしたのですか?」
「開かないわ。」
「でも、ドアには『商い中』とありますよ。」
「そうよね。でも開かないの。昨日は簡単に開いたのに…。」
必死にドアを引っ張るウォーロック。その手に力がこもる。
「もしかして、押すんじゃないんですか?」
「え?でも昨日は引いて開けたのよ。」
「代わってみてください。」
そういうとネクロマンサーはドアノブに手をかけ、ドアを押して見せた。 ゆっくりとドアが開く。
「ほら。」
ウォーロックは狐につままれたような顔でただ目を白黒していた。
「さぁ、いきましょう。」
ネクロマンサーに促されてふたりは店内へと足を進める。店内の様子は見た目には昨日と変わらない。細い通路の両脇にはありとあらゆる魔術具や魔法具が乱雑に積み重なっており、その多くは埃をかぶっていた。でも何かが違う。ウォーロックにはそう感じられた。香りだ!昨日この店に入った時には、埃と黴の入り混じった独特の咳を誘う匂いが鼻についたが、今日はハーブのような芳醇な香りが店内を満たしている。
「素敵な香りですね。」
「そうね。昨日はこんな感じじゃなかったんだけど…。」
言い淀みながらも共に奥へと進んでいく。狭い通路を抜けると例のカウンターが見えてきた。だがその様子もまた違っている。昨日は誰がそこにいるのか直ちには分からないほどのうすぼんやりとした明かりだったが、今日は瀟洒な飲食店の入り口のように、明るい光に照らされている。奥から、聞き覚えのあるようなないような声が聞こえてきた。
「いらっしゃい。」
本当なら、そこには見知ったあの幼い少女が姿を現すはずだった。少なくともウォーロックはそれを期待していたし、それと違うことが起こるとは考えてもみなかった。ところが、実際に目の前に姿を現したのは、ブロンドのボブカットでエメラルドの瞳をたたえた少年だった。

全体的な容貌だけは昨日の少女に似ていないわけではない。美しいブロンド、透きとおるエメラルドの瞳。白い肌。それは同じだ。でもそれ以外が全く違っている。背丈は二人と同じかそれより高いくらいで、樽の上で脚をぶらぶらクラッカーをかじっていたあの幼子の面影はない。声も心なしか太く感じる。どうみても男の子だ!
「やあ、あなたでしたか。昨日ぶりですね。いらっしゃい。」
明らかな驚きと動揺の表情を浮かべているウォーロックを見てネクロマンサーが小声で声をかける。
「どうかなさったのですか?こちらが店主の方で?」
「え、え、その、そうね。そう…なのかしら…。」
言葉にならない。ネクロマンサーはその顔をじっと見入っている。
「おかしな人ですね。昨日会ったばかりじゃないですか?もうお忘れで?僕ですよ。アッキーナです。アッキーナ・スプリンクル。」
それを聞いてますます頭が混乱する。
「アッキーナですって!?でも、昨日は確か…。」
「あはは。面白い人だ。昨日も今日も僕は僕ですよ。神秘の魔法具屋『アーカム』へようこそ。再訪を歓迎します。今日もべランドリウムでいいですか?」
「え、ええ。そうね。お願いするわ。でも…。」
いましがた確かにアッキーナと名乗った少年はいそいそと、カウンター奥の台所らしきところに消えていった。
「どうしたのですか?様子が変ですよ?大丈夫ですか?」
ネクロマンサーが心配そうに彼女の顔を覗き込む。
「アッキーナさんって、もしかしてアカデミーと政府から第一級指名手配されているあの彼ですか?手配の魔術記録とは全然違いますけど…。」
彼?彼…!?。確かに先ほどアッキーナと名乗った人物はちょうど二人と同じ年恰好の少年であった。
「そ、そうね。それはそう。でもね。私の頭がおかしくなったのかもしれないんだけど…。彼、そう彼ね。彼は私の知っているアッキーナとは違うのよ。」
ネクロマンサーは意味が分からないという風に眉をひそめた。
「昨日確かに私はアッキーナに会ったの。でもね、それは年端もいかない女の子だったのよ。確かにそう、あれは女の子だったわ。」
ネクロマンサーはますますわからないという顔をする。
「でも、先ほどの方がアッキーナさんですよね?彼は昨日もあなたが来たと言ってましたよ。昨日は別人とお会いになられたのではないのですか?」
「いえ、ちがうわ。確かに私は昨日ここにきて、そしてアッキーナに会った。それしか確かなことは言えないんだけど。でも、それだけは確かだわ…。私は昨日、ここでアッキーナ・スプリンクルに会ったのよ。」
「でも、それは彼とは違う少女だった、と。」
「そうなの。私は夢でもみているのかしら。アッキーナは昨日そこの樽でクラッカーをかじっていたわ。ほら見てよ、まだクラッカーの欠片が散らばってるでしょ?」
ウォーロックが指さした先の樽の下には、確かにクラッカーの屑が散らかっている。誰かがそこでつい最近クラッカーを食べていたのは間違いないようだ。今朝方の強引で押しの強い自信満々の姿とは対照的に、あからさまに動揺を見せるウォーロックの姿がさほど新鮮だったのか、ネクロマンサーは思わず噴き出した。
「笑うことないじゃない!?」
「いえ、ごめんなさい。でも闇市に泥棒を捕まえに行って法石を取り返そうと息巻いていたあなたが、あの男の子ひとりに手玉に取られていて、大丈夫なのかなって。」そう言いながらネクロマンサーは笑いを堪えている。
「な!?でも、こっちが全然知らないのに昨日会ったなんて言われたらびっくりするのは当然よ。だって…。」
ウォーロックがいよいよ取り乱しているところに件の少年が再び姿を現した。昨日は両手いっぱいに抱えていたのと同じお盆を片手に載せて悠々とカウンターまで運んでくる。そこに昨日と同じ独特の色と香りのべランドリウムのお茶がしつらわれていた。
「どうぞ。」
少年はふたりの前にお茶を供し、席を進めてすすめて自分もカウンターの向こうに腰かけた。今日は樽ではなく椅子に。
「どうしました?冷めないうちにどうぞ。」
「あ、あの。今日はあの方はいらっしゃらないの?」
ウォーロックは混乱と動揺の中で、声を絞った。
「あぁ、マダムですね。彼女がここにいることはめったにありません。昨日のあなたはラッキーでしたよ。ここで彼女に会えるなんて。それで、法石の行方は分かりましたか?」
それを聞いてウォーロックは俄かに我にかえった。
「ええ、もちろん。そのことで来たのよ。でも、ごめんなさいね。私がおかしいのかもしれないけれど、あなたは私が昨日会ったアッキーナではないわ。そして今日はマダムもいない。彼女から託された大切な話を、確信の持てない相手に話すことはできないわ。はっきり聞くわね。あなたは誰なの?」
少年は何か得心したような表情浮かべたあとで、口を開いた。
「あなたの驚きは分かりますよ。確かに昨日あなたが会ったのは今の僕ではありません。でも間違いなく、昨日あなたが会ったのも、僕もアッキーナ・スプリンクルです。訳あって事情は話せません。また、昨日のに会わせろ言われても今すぐはできないんです。でも、僕はアッキーナで、昨日あなたが会ったあの子です。今は男ですが。もしなんならマダムと連絡しましょうか?彼女の言葉なら信じられるでしょう?」
返事に一瞬窮する。
「いえ、いいわ。ここにはあなたしかいなくて、あなたはマダムと法石のことを知っている。そして私のことも昨日のことも。それは嘘とは思えないわ。だからひとつだけ。私は昨日あなたに助けられたことがあるの。それが何だかわかる?」
「スペル・バインの透明ローブのことでしょ?いやぁ、あの時は肝が冷えましたよ。説明も聞かないでいきなり着ようとするんですから。あれを着てしまったらこの世界から姿が消えてしまうんですよ。」
本当にそれは一大事だったという、そんな表情と声色で少年は話した。
「そう、その通りよ。分かったわ。目の前の事実は信じられないけど、あなたという人とあなたの言葉を信じることにするわ。」
「わかってくれてありがとうございます。本当は説明すべきだと思うんですが。ちょっといろいろ複雑なんです。実は、さっき少しだけ嘘をつきました。本当は、昨日の姿に今ここでなることはできるんですよ。でも、それをやってみせたら、それこそあなたはびっくりでひっくり返ってしまうでしょ?だから今日のところはこの辺で勘弁してください。」
申し訳なさそうな、いたずらっぽそうな表情を浮かべてアッキーナは続ける。
「で、法石の方はどうなりました?」
「闇市の開催場所と日時を知っている人物と接触できたわ。でも交換条件をもちかけられたの。このお店に『恋のしずく』という品物があるでしょ?それと引き換えに情報を教えてくれるそうよ。」
「そうですか…。」少年の表情が俄かに曇った。
「あなたたちはアレがどんなものかご存じで?」
「惚れ薬でしょ。若い子たちの間では割と有名よ。」
「それは、市販のやつですよね。ここのは…。困ったな。今日はマダムもいないし…。」
「どういうこと?それがあれば、法石の場所がわかるのよ?ためらうようなことじゃないじゃない?」
「うーん…。」少年の返事は重い。
「あれは惚れ薬なんかじゃあないんですよ。巷に出回っているのは、『恋のしずく』の模造品で、まあ、要するにまやかしなんですが、本物のアレは飲んだ後に見た相手の虜になってしまうという代物なんです。」
「やっぱり惚れ薬じゃない!」ウォーロックはいらだつ。
その横ではネクロマンサーがべランドリウムのカップを静かに傾けていた。
「その、虜になるというのが問題なんですよ。それは文字通り虜になるわけで、飲まされた相手は金輪際、自分とその相手のことしか認識できなくなるんです。」
「どういうこと?」
「まったくそのままの意味でして、この世界に二人きりの人間のことしかわからなくなるんです。飲まされた相手の世界にはもはや自分と相手しかいません。周りにどれだけ人がいようともうそれを永遠に認識することはできなくなるんです。」
「それって…。」
ネクロマンサーもさすがに驚きを隠せなかったようだ。カップを傾けたままその黒い瞳をこちらに向けている。
「そんな危ないもの渡せるわけないじゃない!」
ウォーロックは怒りを隠さなかった。
「だから、困ってるんです。法石の在りかを知るには今のところそのなんとかさんの協力を得る必要がある訳ですよね?ところがそのためにはその何とかさんのかわいそうな想い人を犠牲にしなければならない。そういうのはなかなか困るんですよ…。」
「その通りね…。」
場にしばし沈黙が訪れた。
「あの…。」ネクロマンサーがその静寂を破る。
「それなら、模造品を彼女に渡してはどうですか?どのみち本物のことは当の本人も知らないでしょうから、誰も傷つけないならそれが一番に思うのですが…。」
「でも、それは彼女を騙すことにならない?」年並みの正義感をのぞかせるウォーロック。
「確かにそうですが、アッキーナさんのお話を聞いてしまった以上、そのお薬を彼女に渡すことができないのは確かです。この際、嘘も方便ということにはなりませんか?」
「いえ、それはできないわ。他人を騙すというのは気が進まないもの。そうねぇ、少なくとも嘘ではない解決策がないものかしら?」
そう言うウォーロックに向かって少年が手を打った。
「こうしましょう!」
二人の瞳が少年に注がれる。あたりをべランドリウムの柔らかい香りが包んでいる。
「このべランドリウムのお茶は、かつて『恋人たちのお茶』というニックネームがついていたんですよ。なに、初めての逢引のときにこれを飲むとその恋が成就するというありきたりなものなのですが、幸いにして外の社会にはもうこのお茶はありません。だから、このお茶のいわれをちょっと誇張して、その何とかさんに差し上げることにしましょう!そうすれば少なくとも嘘にははならずにすみますよ。」
「いいわね。」
「はい。」
ウォーロックとネクロマンサーは顔を見合わせた。
「それじゃあ決まりですね。お茶を包んできますよ。それらしくね。」
そういうとまた少年はいそいそとカウンターの奥に消えていった。その後ろ姿には確かにきのうのよちよちとしたアッキーナの面影が微かにあるようにも感じる。そんなことを考えながらウォーロックはその後ろ姿を見送っていた。
「いい案があってよかったですね。こうした古い『いわれ』って意外に効果があったりするものですから、もしかしたら彼女の復縁も本当に適うかもしれませんね。」
「そうね。確かにそうよ。とにかく、あんな危険なものを渡すことはできないもの。嘘もだめだし。」
そんなことを話していると、クラッカーをくわえ、手に小さな薬瓶を持った少年が姿を現した。
「お待たせしました。葉っぱのまま包もうかと思ったのですが、腐るものではないので、薬瓶につめてそれっぽくしてみましたよ。その何とかさんには、想い人と二人でお茶をするときに、その飲み物は何でもいいので、このべランドリウムのお茶を数滴それに加えるように伝えてください。サイン入りの添え書きにもその旨を書いておきました。これで体裁は整うでしょう。あとはこの古い言い伝えが嘘ではないことを祈るだけですね、っと。」
そういうと、少年は薬瓶を添え書きとともに小箱にしまって包みをし、ウォーロックに渡した。

「頼りにしてますよ。」
「ええ、任せておいて。」
「お帰りは分かりますね?」
「コイルを逆順でしょ?」
「はい。」
* * *
こうして、ウォーロックとネクロマンサーの二人はアーカムを後にした。マークスを逆順にたどるにはおよそ1時間かかる。ふたりが再びアカデミー前に帰り着いたころには、西の空が赤く燃え、アカデミーの学舎を美しく彩っていた。
「じゃあ、これをあなたに預けるわ。きっと、お願いね。」
「はい、明日彼女にこれを渡して闇市について教えてもらってきます。」
「それにしても、真面目で優等生のあなたが、私のこんな道楽に付き合ってくれるとは、正直思っていなかったわ。ゲートで待ってるとき、本当はふられた気分だったのよ。」
「それはごめんなさい。あの、そういえば、私とあなたは確か運命共同体なのでしたね?だから話しますけど、私にも欲しいものができたんです。」
「欲しいもの?」
「はい、なんでも今度の闇市には人為のロードクロサイトが出品されるそうなんです。私はそれが欲しくて。」

「まぁ、あなたって意外と現金なのね!」
「現実的と言ってください。」笑いながらネクロマンサーは続ける。
「さっき、アーカムに行く途中でゴーストのことを話したでしょ?人為のロードクロサイトがあれば、召喚するゴーストの姿をかなり自由にデザインできるようになるんです。それはあくまで幽霊ですが、女の子を男の子にしたり。」
「アッキーナのことね。」
「はい。彼を信用して大丈夫なのですか?」
「そうね…。正直、自信はないわ。でもあの透明ローブのことは、あの場所にいなければわからないはずよ。それを語る、えっと、彼ね、彼の言葉に嘘はないように思えたわ。だから信じることにしたの。」
「そうなんですね。人為のロードクロサイトが手に入ったら、私の手でアッキーナさんを女の子にかえてみましょう!」
「まぁ、それって、アッキーナを幽霊にするってこと!?」
「うふふ、そうなってしまいますね。もちろん今のは冗談ですが、私にも私の目的ができました。だからあなたのお手伝いをすることに決めたんです。」
「そう、ありがとう。心強いわ。」
「こちらこそ。」
「じゃあ、明日よろしくね。」
「わかりました。お昼にまた今日と同じ場所で会いましょう。」
「ええ。」
そうして二人はそれぞれの寮へと向かって歩き始めた。太陽が西の地平線でゆらゆらと揺れている。生暖かい夏の風がさっと通りを吹き抜ける。それは、まるで退屈な日常を掃き飛ばすようでもあった。星がちらちらと輝き始め、静かに夜の帳がおりてくる。
第4節『闇に消える桃衣』
「お待たせしました。」
聞きなれた声を聞いて安堵する。
今、夜の10時15分を回ったところだ。合流は無事に出来た。すべてはこれからはじまる。
深夜11時から、ここポンド・ザック街の一角で、大天使ガブリエルにまつわるさまざまの品物をやり取りするという闇市が開催される。アーカムで手に入れた恋の秘薬と引き換えにその情報を得たのは、今から4日前のことだった。黒髪のネクロマンサーは、この闇市の常連らしいケイティという名の少女から、見事にその情報を引き出すことに成功した。恋の秘薬を手に入れたケイティの機嫌は上々で、この闇市のどこで何が扱われているかまで、その知る限りを懇切丁寧に教えてくれたという。必要な情報はいま私たちの手中にあらかた揃っていた。真夏の夜の、むっとした暑さと湿気があたりを取り巻いている。
声の主の姿を見て、ウォーロックは少し驚いた。
「まぁ、あなたそのままの格好で来たの?それって例の看護学部の制服でしょ?」
「ええ、着替える時間がなくて。どうやらアカデミーでも今日のこの闇市については把握しているようで、講義の後にそれはそれは随分と長いお説教と警告があったんです。本当は一度寮に帰って、ネクロマンサーの制服に着替えてから来るつもりだったのですが、ここまでの移動のことを考えると、その時間がありませんでした。」
「そんなに遅くまでお説教とは、ずいぶんね。」
「はい。木曜の看護科は準夜間講義ですから、終わるの自体が午後8時です。そこからあのお説教が始まって、私たちが解放されたときには、時計はもう9時に差し掛かっていました。アカデミーからここまで歩いて1時間少々かかりますから、着替えていたのでは間に合わない目算が高かったのです。それで、そのまままっすぐここに来ました。」
「なるほどね。でも耐性の方は大丈夫なの?」
そう言われたネクロマンサーは改めてウォーロックの装束を見た。彼女が身に付けているのは、ブラウスとコルセット、そして丈の短いプリーツスカートから成る、術士の制服と呼ばれるいわゆるアカデミーの制服だが、特にコルセットはいくつかの防御呪印を配置することで、物理的と魔法的の両方の耐性を高めた特別のものを身に付けていた。ブラウスとスカートにも工夫があるようだ。確かに、これから闇市で窃盗犯に接触しようというのだ。せめて死霊科の制服にだけは着替えて来るべきだったかもしれない。ネクロマンサーの脳裏に後悔の念がめぐったが、今更いってみても仕方がない。
「ずいぶん、耐性に配慮した構成ですね。私ももっと考えるべきでした…。」
「私たちの学年だとまだローブは着られないから、せめて制服だけでもと思ってね。」そういってウォーロックはコルセットを強調して見せた。

「もうすぐ10時40分か。そろそろね。会場の方に移動しましょう。」
ポンド・ザック街は普段から人通りの多い繁華街で、メインストリートの周辺は様々な商店や飲食店、趣味の店などが所狭しとひしめいて賑わっている。しかし、それとは反対方向の、何本か通りを奥に入り込んだあたりからポンド・ザック川にかかる小さな橋に向かう方角にかけては、蜘蛛の巣状に古い通りが入り組む迷路のような構造になっており、ケイティの話ではその橋にほど近い、特にたくさんの小さな裏路地が複雑に入り組む辺りが今日の闇市の会場なのだということだった。
正直、こんな深夜に女二人でそんな場所に出向くというのはぞっとする話だ。好奇心よりも不安と恐怖が勝る。まして、これから接触しようというのは、あの有名な神秘の法具屋『アーカム』から法石の指輪をまんまと盗み出したという名うての盗人なのだ。ふたりの顔に緊張と心配の色がにじむ。
狭い裏路地を幾重にも重ねていくうちに、あたりはどんどん光を失っていく。また、先ほどまで気味悪いほどに静かだったその場所に、にわかに人影が現れ動き出すのが感じられた。ひそひそとした声と物音がしきりに聞こえてくる。どうやら少しずつ、その闇市とやらが胎動を始めたようだ。
ケイティから、制服を売るならここだと教えられた場所にとりあえずやってきた。
「10時55分。少しずつだけど取引はすでに始まっているようね。」
緊張に震える声でウォーロックが語る。
「そうですね。急に人影が多くなりました。会話する声も目立ちます。始まったのは間違いないみたいです。」ネクロマンサーも周囲の気配に気づいていた。これから件の男を探し出さなければならないが、アーカムの店主、アッキーナの瞳と同じ色の法石の指輪を持つ男という以外に手掛かりはない。じっとしていても、その男と邂逅できる可能性は低いだろう。ウォーロックが一つの提案をした。
「闇市は午前1時までよね。ふたりでずっといっしょでは効率が悪いから、まずは別々にそれらしい男を探しましょう。それで、12時にまたここで落ちあって情報交換よ。」
その提案は、合理的なものに思えた。なにより人知れず「自分の目的」を探す時間的猶予もできたわけだ。ネクロマンサーの内心は踊る。
「それがいいですね。そうしましょう。万一の時はポンド・ザック橋を抜けるところまで逃げて、そこで落ち合うということで。」
「わかったわ。そうしましょう。じゃあひとまず12時にここで。」
「はい。」
そういってふたりは別れた。11時を回って、ますますその闇市の舞台はひそやかな活況に包まれてくる。ところどころに人だかりができ、競売のようなことが行われている。声を出すのは具合が悪いのであろう、誰もがなにやら手を頭上に高く挙げて、指を折ったり曲げたり、見たこともない仕方で値段らしきものを伝えている。ときどき、静かな歓声があがる。売買が成立したのだろう。
狭く入り組んだ裏路地をあちこちに行ったり来たりするが、一向にそれらしい男の姿は見えない。というよりも怪しさで言えば、どれもこれもがそれらしくて仕方がない。酒の匂いを振りまきながら千鳥足で通りを蛇行する老人、人目をさけるようにこそこそと裏路地のより深いところへ消えていく男、袋小路に座り込んで、客を待っているらしい商人、どれがその盗人なのか見当をつけることも難しかった。
そうこうしているうちに、早くも約束の12時が近づいてくる。この街では、深夜12時の少し前から、自警団が夜回りと火の用心の鐘(といっても騒がしいものではないが)を鳴らす。その音が遠くから聞こえてきた。ひとまず戻ろう。ウォーロックはさきほどと同じところ、看護学部の制服を売るならここ、の場所に踵を返した。
* * *
見知った姿が見える。
「どうだった?」
「だめです。人が多すぎて…。それらしい人物は見つけられませんでした。」
「同じくよ。」
「これからどうしますか?」
「そうね、やみくもに歩き回っても駄目だということはわかったわ。困ったわね。いざという時のためにも、これからはできればふたり一緒にいたいし。」
「同感です。」
そんな相談をしているときだった。
「もし。」
聞きなれない声が背後から聞こえた。
「あのう、それ。そちらのお嬢さんが着てらっしゃるのは、アカデミーの看護学部の制服でございますよね?」
慇懃無礼な言い回しが不快に耳に絡みついてくる。ネクロマンサーは脅えて身構えた。
「だったらなんだというのかしら?」ウォーロックは強気に応じた。
その声の主は一見初老の紳士風であったが、その口元は少し下卑ていて、いかにも好事家といういやらしい表情にも見えた。

「いえね。へへ。お恥ずかしい話ですが、今日の私めの目的は、そちらのお嬢さんのお召し物なのでして。」
ぞっとする話である。こんな初老の男が、女学徒が今まさに身に付けている制服をよこせというのだ。ふたりは背中に何とも言えない気味悪さを感じた。早くこの場から立ち去りたいというのが、共通の思いだった。
「あなた、自分の言ってることがわかってるの?ここでこの子をひんむこうってわけ?どうかしてるわ。」
そう息巻くウォーロックの後ろで、ネクロマンサーは片手で胸元をキュッと握り込み、身体を小さく固くしている。心なしか震えているようだ。
「これはこれはお手厳しい。何もただでと言っているわけではございませんじゃあないですか。なにせここはガブリエルの闇市ですから。そうですね。とてもかわいらしいお嬢さんのお顔を直に拝見できましたから。へへ。お顔付でなければこれくらいですが。」
そういって、甲を向けた左手の指を二本立てながら、
「生のお顔付ということで、これくらいでどうでしょうや?」
男はその二本指を三本指に変えて見せた。
その刹那、ふたりはおもわず息をのんだ。
あった!!
男が示す三本目の、老いぼれたその薬指に、『アッキーナの瞳』に違いない美しい指輪が輝いている。ここで逃すわけにはいかない。邪険にすることもできなくなった。
「そ、そうね。悪くないわね。」
それがいくらを指すのか、ウォーロックには見当もつかなかったが、とにかく興味はあるというそぶりを見せなければと思わせぶりに返して見せた。
「で、ございましょう?これでも十分破格だと思うところに、これですから。へへ。悪くはない話でございましょうや?」
男はその指を二本にしたり三本にしたりしながらにやにやとふたりの顔を覗き込んでくる。生理的嫌悪を必死に抑えて、彼女は続けた。
「それでも安いくらいだわ?あなた、この子が何者か知っているの?」
「いえ、特段存じあげませんが。でもまぁ、お美しい方であることだけはこの目に映ってございまして。」いちいち気味が悪くて仕方がない。
「この子は綺麗なだけじゃなくて、4年でただ一人、死霊科と看護科を掛け持ちする秀才中の秀才よ。だから、この子の制服をここで引きはがそうというならそれ相応のものをもらわなきゃね。」
後ろでネクロマンサーがもうやめてくれという泣きそうな顔で、胸元を握っているのとは反対の手でウォーロックのスカートの裾にしがみついていた。
「ほぅほぅ。それはそれはなんとも素晴らしいお話で。で、お嬢さん方はこの老いぼれの何を欲しいとおっしゃるのかな?」
くいついた!!
「そうね。見たところ、あなた、ずいぶんと分不相応な指輪を身に付けてるじゃない?それと交換というのはどうかしら?」思い切って本題に切り込んでみた。
「おやおや、この指輪に目を付けるとはお目が高い。しかしですな。これは、お嬢さんたちもご存じでしょう。行きたくても行けない神秘の法具屋『アーカム』から手に入れた極上の逸品でして。私めと致しましてもおいそれと差し出すわけにはまいりませんので。」
まあそうだろう。
「『アーカム』から手に入れたが聞いてあきれるわ。それはあなたが盗ったものでしょう?ネタは割れているのよ。さっさと返してちょうだい!」
「おやおや、盗んだとは心外な。盗んだというならそれは『アーカム』の方でございまして。へへ。これはもともと正真正銘私めのものでございますから。」
どういうことだろう?しかし今はそんなことを問答している暇はない。
「まあ、それはどうでもいいことよ。いい。あなたはこの子の着ている制服が欲しい。そして私たちはあなたの指にあるその指輪が欲しい。需給は一致していると思うけど?」
「へへ、これは一本取られましたな。なんとも賢いお嬢さんで。よござんしょう。あなたの提案で手打ちと致しましょうじゃあありませんか?」
慇懃無礼なその物言いがとにかく耳について仕方がないが、上手く話しはまとまった。困ったのはネクロマンサーの方である。ウォーロックの背に小さく身体を隠しながら顔を小さくふるふると横に振っている。
「なによ。腹をくくりなさいよ!これで一件落着なのよ。制服くらいなんとでもなるじゃない。いざとなれば、死霊科の制服で看護科の講義に出ればいいだけだわ。」ウォーロックはそう小声で言い放ったが、ネクロマンサーはいよいよその黒い瞳をうるわせ始めた。
「なによ?」
「あ、あの、だって…、だって私いま…。」とうとう泣き出しそうである。
「ああ、そういえば、それもそうね。」何やら思いついたようにウォーロックが男に告げた。
「もう一つ、欲しいものがあるわ。」
「こりゃあ何とも欲深いお嬢さんで。なんですね?」
「今あなたが着ている、その薄汚いコートよ。いくらなんでもここでこの子をひんむいたままにしておくつもりじゃないんでしょ?」
「へへ、そりゃあどうも。気が付かないことで。失礼致しやした。よござんしょう。この指輪とコートを差し上げますから、私めにはそのお嬢さんの、肌のぬくもりが冷めないうちのやつをひとつおねがいしたいんで、へへへ。」
気持ち悪さに我慢も限界だが、ここは耐えるしかない。
「まずは指輪よ。着替えるには場所を移さなないといけないわ。だからまずは指輪を渡してちょうだい。」
「よござんす。」
そういうとその老紳士は静かに指輪を抜き取り始めた。
その時である。壊れた蓄音機のように乱れた響きが彼らの耳に届いた。
「おい。その指輪をこちらに渡せ!」
* * *
ふりかえるとそこには真っ黒な魔帽とローブを目深にかぶり、顔を隠した気味の悪い風体の男が立っていた。

「もう一度言う、その指輪をこちらに渡せ。」
「なによ、横取りするつもり?残念だけどあなたに渡すつもりはさらさらないわ。さっさと消えなさい。」
その刹那だった。その魔法使いの手から炎がほとばしる。『火の玉:Fire Ball』の術式だ!
あぶない!その熱球がウォーロックの額をかすめた。髪の毛の焼ける嫌な臭いが鼻を刺す。
「なによ!?問答無用ってわけ?」
男はなおも手を緩める気配がない。
「お嬢さん方、こりゃあ危のうございます。とにかくまずはひと気のないところまで参りましょうや。」老紳士が言う。
「そうね。さあ!」しがみつくネクロマンサーを促す。
「どっちに向かうの?」
「そうですねぇ。ここは人通りが多くていけません。そうざんす。ポンド・ザック橋へ向かいましょう。この時間のあそこらへんは殆ど閑古鳥です。」
「わかったわ。」
そういうと三人は一斉に走り出した。
黒づくめの男は走るというよりは転がるような姿でその後を追ってくる。
「何よあいつ、なんであんなに気味が悪いのよ!?」
ふらふらよたよたとよろめきながらも、しかしその男は三人の後を追ってくる。すぐに追いつかれるというのではないが、背後から襲ってくる火の玉がやっかいだ。その騒動に気づいて周りも騒然とし始めた。野次馬ができては非常にまずい。厄介ごとはごめんだ!
「急ぎましょう!」ネクロマンサーにも力が戻る。
火の玉を巧みにかいくぐりながら、できるだけひと気の少ない真っ暗な通りをいくつか抜け出て、ようやくポンド・ザック橋を見据えられる小道に出た。ひと気の方はすっかりついえたようだ。あとは、とにかくあいつを何とかしなければ!
「あの…」
「なによ、こんな時に」
「『雷:Lightning』の術式はどうしたんですか!?」
「っつ!」
「ここまでくればもう魔法を使っても大丈夫なはずです。あの男ひとりなら、『雷:Lightning』で退けられるでしょうに!どうして使わないんですか!?」
「お嬢さんはそのお歳で『雷:Lightning』の術式がお使いになられるんで?」
老紳士も魔法には詳しいようだ。
簡単に言ってくれるわね。ウォーロックはバツが悪そうに言う。
「使えるには使えるけど…。」
息を切らしながらウォーロックは続けた。
「私の『雷:Lightning』は、威力は超一級だけど、命中精度は三流以下なのよ!」
「なんですかそれ!?私たちの力じゃ、『雷:Lightning』が使えるのはせいぜい1回ですよね?どうするつもりなんです?あなたを当てにしてたのに!」
「わかってるわよ。だから何とか…」
そういうウォーロックの頭上を火の玉が再びかすめる。
「何とか狭いところに追い込めないかを考えてるわけ!使えるのは一回こっきり、外したらそれまで、魔力枯渇よ!」
「それじゃ、まるであなたがお荷物じゃあないですか!?」
「わかってるわよ!」
以前に、護身のできない看護学部生では足手まといになると言ったのを憶えられていた。その唇は呪文を詠唱しようと微かに動き出すが、思いがどうにも定まらない。機会は一度しかないのだ。こんなところで万一にも魔力枯渇を起こしてしまえば、それこそ一貫の終わり。美女の姿焼きの盛り合わせ、変態添えのできあがりである。冗談じゃない!
「それじゃあですね…。」
老紳士が割って入ってきた。老練というべきか、彼の足腰は年齢不相応に強健で、ふたりについてくるというより巧みにふたりを誘導するかのごとく、道筋を的確に選びながら橋に向かっていく。
月は厚い雲の中にその顔を隠しており、辺りは漆黒の闇に覆われていて、ろくに周囲の様子を確認することもできない。足元が走りやすい石畳なのがせめてもの救いだ。橋がますます近づいてくる。それは欄干の低い石造りの古いもので、人がなんとかすれ違うことができるくらいの道幅しかないものであった。長さはそれほど長くないが、狭さという点ではうってつけである。
「あの橋の真ん中に追い込みましょうや!」
たしかに、あの橋の上であればまず外すことはない。
「でも、そのためには挟み撃ちにする必要があるわよ!どうやって!?」
「それなら、任せてください。」ネクロマンサーがきっぱり言い放った。
「さっきから気になっていたのですが、あの男、私たちを追っているというより、いちいち動くものに反応しているようなところがあるんです。だから、こうすればきっと!」
『現世に漂う哀れな霊の残滓よ。我と契約せよ。我が呼び声に応えるならばその彷徨える魂に仮初の影を与えん!魂魄召喚:Summon of Ghost(s)!』
制服のポケットから小ぶりのワンドを取り出してそう詠唱すると、ネクロマンサーはたちまちのうちに自分たちにそっくりな背格好の霊を三体同時に召喚して見せた。4年生にして同時に三つ、しかも霊の姿形を適切巧みに造形している。すごい!ウォーロックは息をのんだ。老紳士も感心しているようだ。
案の定、黒づくめの輩はその影の方に気を取られたようである。相変わらず歩くともこけるともつかないしぐさで今度はその影を追い始めた。
「今でござんす。」
そういうと、老紳士はふたりの魔法使いのからだを路地横の防火井戸の陰に押し込んだ。黒づくめはそれに気づくこともなく、橋に向かう霊の影の方を追っていく。しめた!三人はその背後をとることに成功したのだ!
やがて橋のなかほどまで差し掛かれば、霊の影と後を追う三人で、あれを狭い橋の真ん中にくぎ付けにできる!
井戸の横をそれが通り過ぎた後、しばしの間隔をとって気取られぬように三人はその後を追い始めた。相変わらず壊れた操り人形のような奇妙な動きを連続させながら、その男のような生き物は一心不乱にその前を行く霊の影を追っていく。それが繰り出す火の玉の明かりだけが頼りというほどにあたりはどんどん暗くなっていった。
いよいよ、霊の影がその狭い石橋に差し掛かる。それを追って蠢く黒い生き物。橋の中ほどで、霊の影はぴたりと止まった。
「追い詰め、め、た、たぞ。」冷たく壊れた声が響く。その手に火の玉を宿しながら、それは霊の影との距離を詰めた。

「ゆ、指輪を、指輪をわ、わたせ、せ、せ、せ…。」それはいよいよ人間離れした様子を呈し始めた。
「今です!」
ネクロマンサーの合図に続いて詠唱の声がこだました。
『天候を司るものよ。わが手に閃光をともせ。雲を呼び集めよ。雷光をもってわが敵を打ち払わん!雷:Lightning!』

一瞬、昼光のまぶしさがあたりの造形物の詳細をありありと照らし出す。ウォーロックの手から鋭い雷がほとばしり、それは正確にその黒づくめの身体の中央を貫いた!雷が大木を引き裂く音の後、狭い石畳の橋の真ん中あたりで、その生き物の身体は激しく燃え上がった。炎に包まれながら、いよいよ壊れたゼンマイ仕掛けの機械のような、およそ人間のもがきとは明らかに異なるしぐさを紡いで、それはよろよろと欄干にもたれかかり、そのまま下の川の中に燃え落ちていった。不思議だったのは、そのローブの材質の所以だろうか、炎の色が普通の色とは違って、薄気味の悪い白味がかかったピンクとも紫ともつかない色を発していたことである。その最期は焼け崩れて闇に消える桃衣のようであった。
* * *
「おみごとでござんす!お嬢さん方、お見かけ以上でやすね。」
老紳士がふたりに賛辞を贈った。
「ええ、まあね。それにしてもあなたすごいじゃない!どうやってあんな召喚ができたの?姿形を私たちに似せた上で同時に三体なんて、びっくりだわ!」
「これを使ったんですよ!」そう言ってネクロマンサーはふたりにひとふりのワンドを見せた。

「これってもしかして。」
「はい、手に入ったんです、人為のロードクロサイト!初めて使うから、うまくできるか分かりませんでしたが、噂通りの法石です。私たちを助けてくれました。」
「へぇ~、ずいぶんと値が張りそうだけど、どうやって手に入れたの?」
「内緒です。」そういってネクロマンサーは小さく舌を出した。
「ふーん、あなたって、お金持ちなのね。」
この子、こんな表情もするんだ。ウォーロックにとってそれはとても新鮮だった。つい先日知り合ったばかりの、彼女のそんな新しい一面を垣間見られて、素直にうれしかった。ネクロマンサーがなぜそうまで顔を真っ赤にしているのかはわからなかったが…。
「それじゃあ…」老紳士が口をはさんだ。
「よござんすでしょうか?我々の取引を再開しようじゃあありやせんか?」
「そうね。丁度いい具合にあそこに姿を隠せるくらいの木戸があるわ。私たちはそこでこの子を着かえさせるから、先に指輪とコートを渡してちょうだい。」
「よござんす。」そう言うと老紳士はその指から『アッキーナの瞳』を外してウォーロックに渡した。
「私めの方もお忘れなく。楽しみにしてやすんで。」その顔が助平そうに笑った。
「わかってるわよ。さぁ、行きましょ。」ウォーロックが促すとネクロマンサーは首を振った。
「大丈夫です。一人でできますから。」
そう言うと男からコートを受け取って、彼女は木戸の裏に身を隠した。するすると着衣をとく乾いた音が聞こえる。男はその音がたまらないというふうに聞き入っている。どうにも気持ちのいいものではない。
そのとき、ふと手元に視線を移すと、ウォーロックは『アッキーナの瞳』の中に何かの像を見た気がした。なんだろう?そこには天使のような姿をしたウォーロック自身らしき姿と、プラチナブロンドの美しい長髪に透きとおる空色の瞳をたたえた者の姿が一瞬映し出されたが、それはたちまちに解像度を失って霧消した。しかしウォーロックは、さしてそれを気にもしなかった。
ほどなくして、コートをしっかりと着込み、両手に看護学部の制服を抱えたネクロマンサーが木戸の裏から姿を現した。
「どうぞ。」そっとそれを男の前に差し出した。
老紳士はこれぞ至福というような、ぞっとする表情を浮かべて、両手でうやうやしくそれを受け取った。心なしかその息遣いは荒い。
「ありがとうございやす。それじゃあ、私めはこれで。今夜は実にいい取引ができやした。その上、素晴らしいショーまでお目にかけて頂いて、大満足でさぁ。」そういうと踵を返し、その狭い橋を渡って夜の帳の中にそのいやらしい姿を消していった。心なしか、黒づくめが川に焼け落ちたあたりで、歩みをわずかに遅めたような気もしたが、そんなことはもはやどうでもよい。あの貴婦人からの依頼を見事にやりおおしたのだ!ウォーロックの心は、興奮と満足で満たされていた。ネクロマンサーもその小さな体に合わない大ぶりのコートの中で、笑顔を浮かべている。
「さぁ、私たちも帰りましょう。」
「そうですね。」
「こんな時間だし、いろいろ気を付けないとね。」
「はい。」
そんな言葉を交わしながら、ふたりもまた漆黒の闇の中に溶けていった。
夏の夜空を満点の星々が彩っている。月あかりがない分、星々の輝きは増しているように見えた。様々の星座が、漆黒のキャンバスを縦横無尽に彩っている。川面からは流水の香りが漂う。星座群の瞬きは、ふたりの初陣を祝福しているかのようでもあった。真夏の夜が更けていく。
* * *
後日アーカムを訪れたふたりから『アッキーナの瞳』は無事に返還された。そのとき偶然に居合わせていた例の貴婦人は、少女アッキーナとともに大いにふたりを歓待しては、たくさんの古い魔法のお菓子をお土産に持たせたりした。
彼女たちが店を去った後、アーカムを急な静けさが襲う。
少女は奥の戸棚でなにかごそごそとやっている。
「やっぱり、狙ってきたわね。」
「はい。ガブリエルと聞くと見境いないようです。」
「困ったことになりそうだわ…。」
ふぅ、と一息つくと、貴婦人はそっとささやいた。
「とにかくも、ご苦労だったわね、アッキーナ。」
「いえ。」少女はその小さな頭をふるふると横に振る。
「でも、それを着るのは、女の子の時だけにしなさいね。」
「はい。」
そういうと、アッキーナは何かをしまった戸棚の扉を、その小さな手で静かに閉めた。アーカムに神秘の静けさが戻っていく。
第2章
第1節『赤い瞳の苦労人』
「ったくよぅ!ふざけんな!」
そういうと、少女はその年齢の割に随分と年季の入った『輻輳の手指』を乱暴にロッカーにぶちつけた。
「おもしろくねぇ。」
「あら、今日も朝から口が悪いわね。」
「うっせぇよ。」
「また、例の銀髪女?」
「そうだよ。ったく、おんなじ6年なのにどうしてこうも違うんだ!?ちくしょうめ。」
「だってさ、あちらはご貴族様の天才ご令嬢だもの。自称たたき上げのへっぽこウィザードとは格が違うのよ。」
「わーってるよ。でも悔しいじゃねぇか。なんでいつもこうなるんだよ!リズ、あんただってそう思うだろ?」
リズと呼ばれた少女は、また始まったというような顔をして言う。
「だってさ、相手はあんたがひょろひょろした火の玉をなんとかかんとかひとつ作り出す間に、10も20も氷塊を繰り出してくるんだから。どう逆立ちしたって勝てるわけないじゃない?」
「そりゃそうだけどよ。同い年だぜ?才能ってのはそんなに大事なのかよ。それがなきゃ駄目ってんなら、努力なんて意味ねぇじゃねぇか…。」その語気が少し威勢を失う。
「だから、才能っていうんじゃない?」リズはいたずらっぽくそういった。
「そうだけどよ…。ったく、やってらんねぇよ。」
若き金髪のウィザードはすっかり消沈してしまった。
「そんなに悲観することないんじゃない?」リズは慰めるように言った。
「ウィザード科の中じゃ、あんただって名うてなんだし。なんせ、前期課程の段階で『輻輳の手指』の着装を許されたのはあんただけなんだから。その努力は十分実ってると言えるんじゃない?」
「つまんねぇ…。」
そう言ってうなだれると、ベンチから立ち上がって制服に着替え始めた。
ウィザードは魔法を使える術士である。だから魔術師と呼ばれる訳だ。しかし、生まれながらにして魔法の素質に恵まれているウォーロックや、代々の遺伝によって破格の素質を最初から受け継いでいるソーサラーに比べれば、その生来の素養は比べようもなく乏しい。だから、魔法の模擬戦や競技大会では、いつも臍を噛まされる。特に、年若く、まだその努力が十分に結実しない初等科の時期においてはなおさら彼女たちとの素養の差は際立ち、人知れず劣等感に苛まれることが多い。
その実、随分な悪態をついていたこの少女は、今年のウィザード科では、飛びぬけた能力を発揮していた。生まれもった魔法的素養はほとんど皆無だったが、アカデミーはその努力と成果を十分に評価していた。初等科の前期課程では、普通ウィザードには『保護の手袋』と呼ばれる魔力暴発から手指を守る基礎的な装具の着用しか許されないが、彼女はその時点で既に『輻輳の手指』と呼ばれる、魔法力の強化に資する手袋の着用を許されていた。それは、その努力と成果がその年齢にして並々ならぬことを示す証でもあった。

彼女たちは今、来月開催される『全学魔法模擬戦大会』に向けた練習に励んでいた。それは各学年ごとのウォーロック、ウィザード、ソーサラー、ネクロマンサーがクラスごとにチームを組んで、魔法の模擬戦を繰り広げるというもので、異国で言うところの体育祭に相当する、全学を挙げた一大イベントだ。普段の勉学と教練の成果を遺憾なく発揮できるその場に、自分の将来と可能性をかける学徒は多い。事実その大会には各種職能ギルドのスカウトが多く観戦に来ており、その目に留まった者はギルドから職の斡旋を直々に受けることができる。また特に優秀な者は、アカデミー固有の自警団である『アカデミー治安維持部隊』へのスカウトを受けることすらある。それは、経済的に条件がよいというのみならず、学内における一種のステータスであり、一部の者にとっては、若く未熟な自尊心を満たすための重要な事柄であった。
そこに向けた朝練習の後に、先ほどのやりとりは繰り広げられていた。この時期、その大会に代表選手として出場する学徒たちは、午前講義の前と、午後講義の後に、懸命に練習に励み、美しい汗を流す。彼女もまたその中の一人であった。
着替えを終えると、その若きウィザードは憮然とした表情で、ひょいと学生かばんをひっかけ、更衣室を出ようとした。
「ちょっとまった。」呼び止める声がする。
「あぁ?」
「今朝の努力賞よ。あげるわ。」
リズが水薬の瓶を差し出した。
「お、『怪物栄養』じゃねえか?いいのかよ?」
「あなたは私たちの希望だもの。これからも頑張ってもらわなきゃね。それを飲んで、そのしょげた顔をなおしてちょうだいな。」
リズは屈託ない笑顔をウィザードに向けた。
『怪物栄養』というのは、今若者たちに人気の、いうなればエナジードリンクである。それなりに値の張る品で、そんなものをポンとよこしてくれるリズは随分と気前が良い。その気遣いがやさぐれをほぐしてくれる。

「なんだよ…。」少女少し気恥しい表情をのぞかせた。
「サンキュな。」
そう言ってその若きウィザードは更衣室を後にした。
晩夏の太陽が朝からギラギラと照り付けている。もうすぐ9月に入るが、まだまだ残暑どころか酷暑である。厳しい練習は激しく彼女たちの体力と魔力を奪うが、それはまた、優れた魔法使いとなるために必要な、重要な教練のひとつでもあった。太陽はますますその高度を上げていく。遠くで予鈴が鳴り響いていた。午前の講義が始まる。
朝の練習に臨んでいた魔法使いたちは次々と更衣室を後にし、各々が所属する教室棟へと足早に歩みを進めていった。今日も一日が始まる。
* * *
教室についたころには、若きウィザードはもうへとへとであった。リズからもらった『怪物栄養』は、喉の渇きを満たすには十分であったが、その触れ込み通り怪物となるには少々物足りないものであった。
午前講義の開始を告げる本鈴が教室内に鳴り響く。本来ならここからが学業の本番であるが、極度の疲労と眠気が彼女を襲った。持ち前の真面目さで必死に目をこするが、その美しい茜色の瞳の中では銀の砂が耐えようもなく舞っていた。
「寝るわけにはいかねぇ。」ウィザードは必死に耐えている。
「今日の魔法要素理論の講義には、あのくそ銀髪に一泡付加すヒントが絶対ある筈なんだ。ちゃんと聞いておかないとまた今朝の二の舞になる。」彼女は、唇をかみしめ太ももに爪を立てる。しかし疲労感と眠気は容赦なくその小さな体を襲ってきた。
気が付くと午前講義の1コマ目が終わっていた。
「やっちまった…。」深い反省がウィザードの胸を締め付ける。
こういうと、彼女の努力なるものが所詮まやかしに聞こえるかもしれないだろう。しかし、それは無理からぬことでもあるのだ。全学魔法模擬戦大会においては、その代表選手に選抜されるだけで随分とハードルが高い。そのためには過酷なトレーニングと魔法力の強化が求められる。彼女たちはそれを朝晩欠かさずずっとやっているのだ。今朝方のように、ソーサラー科の手練れにコテンパンにされることも少なくない。年若いウィザードにとって、基本術式の『火の玉:Fire Ball』を行使するのは精神的にも肉体的にもまだまだ負担が大きい。それに対して、ソーサラーが得意とする『氷礫:Ice Balls』の術式はその威力と効果に不相応に、初等術式に属しており、その優れた遺伝的魔法力の優位を活かしてソーサラーは余裕綽々でその術式から存分に力を引き出して襲い掛かってくる。リズの、勝てるはずがないというのは現実的に正鵠を射ていた。実際のところ、初等術式にろくな対抗手段をもたないウィザードが同じ学年のソーサラーとある程度渡り合えるだけでも大したものなのである。それは、才能というものの生来の優位性を嫌というほどに思い知らせるものであった。担当教授が不覚にも居眠りをしてしまったウィザードを叱責して起こさないのは、そうした彼女たちの悲哀と現実をよく知っているからである。
「まだ、2限がある。1限目のやつは今晩やりなおしだ!」
そう言って居住まいを正すと、リズのくれた『怪物栄養』の残りを一気に飲み干した。もう銀の砂は舞わない。二限目の彼女は魔法書と黒板にかぶりつくようにして、聞こえてくる教授の言葉を一言たりとも漏らすまいという勢いでノートに書きなぐっていった。その並外れた集中力は時間の流れをも歪めるのか、2限目の修了を告げる鐘はあっというまにそこに鳴り響いた。
「よし!」2限目は満足だった。
「火の玉だけがウィザードじゃねぇんだよ。あいつをとっちめるには、別の工夫がいる。あのうっとうしい氷の玉の生成をさせる時間を与えないことがきっと鍵になる筈なんだ。そのための術式がきっとどこかにある。」そうつぶやいて、席を立つとウィザードは食堂の方へ駆けて行った。
ウィザード科の教室棟から食堂に向かう小高い丘を駆け抜ける途中で見たくない顔に遭遇した。くそ銀髪の舎弟野郎だ。くそ銀髪も嫌いだが、あいつには実力がある。その一方でこの舎弟野郎はくそ銀髪の威を笠に着て、ウィザード科を見下しているだけのどうにもいけ好かない最低野郎だ。

「今朝もお嬢にコテンパンにされたらしいじゃない?」
「だからなんだよ?」
「あんたら劣等種が、お嬢に挑むなんて、むりむりかたつむりだってまだわからないの?」余裕をかます嫌な物言いだ。バカにしやがって。
「うっせえな。なんならここで相手になってやろうか!?」
「馬鹿言わないでよ。私はこう見えて理想家の平和主義者なのよ。ウィザードなんか相手にしたって、ロッドが痛むだけだわ。お断りよ。」
むかつく野郎だ。初等部の癖に生意気にロッドなんか使いやがって。
「てめぇがすげえんじゃなくて、親が金持ちなだけだろうが!」
「そうよ。私のお父様は魔法省の高官だもの。だからさっきも言ったじゃない?私たち純血魔導士と、あんたら劣等種じゃ所詮釣り合わないのよ。正直、あんたがお嬢に食い下がってくるの、私たちのチームにとっちゃ迷惑なのよね?わかんないかしら?お嬢と私たちは、今年、ソーサラーギルドのスカウトを本気で狙ってるのよ。初等科の段階でスカウトを受ければ、ソーサラー科全体の大きな名誉なの。そのために私たちにはしなきゃならないことが山ほどあるってわけ。あんたに付き合ってる暇は正直全然ないのよ。だから、これ以上お嬢に絡むのはやめてくれる?」
高圧的でいちいち鼻につく物言いだ。
「それはあたしの勝手だろうが!。今に見てろよ。今年の大会では、このあたしがあんたの大好きなそのくそお嬢に泣きべそかかしてやるからな!」
「負け惜しみを。まあいいわ。これ以上は時間の無駄だし、さっさと行ってちょうだい。」
「あたしに、くそ銀髪にかかわるなというなら、てめぇこそリズをいじるのをやめやがれ。」
この女は今の調子でリズのことを見下して罵倒してくる。いわゆるいじめだ。こいつの取り巻きも一緒になってやりやがる。今のところ暴力や過激な行動には出ないが、そのやり方は陰険で汚い。リズはあんな感じだから気にする様子をみせないが、正直胸糞が悪い。そう思いながら、ウィザードは食堂に駆けていった。
「ふん、劣等種が。」舎弟野郎と呼ばれた少女は吐き捨てるようにその背後を見送った。
昼の太陽は相変わらずぎらぎらとアカデミーの敷地全体に照り付けている。その酷暑は若いウィザードの小さな自尊心を徹底的に焼き尽くすかのようであった。
「くだらねぇ。」
ひとことだけ呟いて、ウィザードは食堂の中に消えていった。束の間の休息である。また午後からは講義が始まり、その後には過酷な教練が待っている。憔悴している暇はない。とにかくやるしかないのだ。彼女は自分に強く言い聞かせていた。
太陽がほんのわずかに西に傾く。
* * *
午前2コマ目に続いて、午後の講義は充実していた。引き続き魔法要素学の講義だったが、なにも自分の主たる加護大天使に属する要素だけをバカ真面目にやることだけが能じゃないことがわかった。
ウィザードを加護するのは火と光のエレメント(要素)を司る大天使長ミカエルだが、それは極めて厳格な天使で、努力を重ねて十分に力が実るまであえて庇護者に強力な力を与えない厳粛さをもっている。それ故に、基本術式の『火の玉:Fire Ball』でさえ、ソーサラーの初等術式である格下の『氷礫:Ice Balls』の術式に性能的には及ばないのだ。これはミカエルが課す一種の試練でもあった。
その上を修得しようと思えば、中等術式の『砲弾火球:Flaming Cannon Balls』になる。これが使えればいう事なしだが、初等科の学徒がそれを身に付けるのにはかなりの無理がある。修得の為に学ぶべきエレメントの領域が広く、仮に魔法の素養に恵まれていたとしても、講学上の理論的知識がそれに追いつかないのだ。ミカエルというのはこのように少々厳格過ぎてやっかいな側面をもっている。だからウィザード科では中退者が耐えない。みんな嫌気が差すわけだ。
しかし、諦めていたのでは、あのくそ銀髪にほえ面かかすことはできない。何としても別の方法を模索する必要がある。それで気づいたのが、専攻大天使のエレメント以外の領域まで勉学の幅を広げることであった。ソーサラーと同じウリエルを選択したのでは、相対するミカエルの力が弱まってしまい、結局はこっちが不利になる。天才相手に同じ土俵で遣り合うなんて無茶が過ぎる。だから、それ以外の選択が必要だ。ガブリエルは強い力を寛容に与えてくれる慈悲の大天使として知られているが、回復・治療と召喚に特化したその特性はベクトルが違いすぎて応用の仕方が分からない。それなら、時間と空間、閃光と雷を司るラファエルはどうか?時間と空間はウォーロックでも中等部に入ってからだから、初等部のウィザードは門前払いだが、閃光と雷なら火と光とは相性がいい。
「これだ!」ウィザードはうっかり講義中に声を挙げそうになったのを必死に飲み込んだ。でもやれる。ラファエルの領域には天候に関するものもあるから、上手くやればあのむかつくくそ銀髪を炎の雨でちりちりにしてやることだってできるかもしれない。自慢の銀髪をそんなにされたら大べそ必至だ。そんなことを考えながら講義に没頭していった。
魔法要素学は嫌う学生が多い退屈な理論講義だが、野望に燃えるウィザードにとっては、それはまさに宝の山に見えていた。
そんな具合で、午後の講義はあっという間に2コマとも終わった。実に得るものの多い講義だった。満足の表情を携えてウィザードはいそいそと教室を後にした。今日の日程はまだ終わらない。今度は大会に向けた準備をチームのメンバーとしなければならない。
午後講義後の自主教練というのは、異国で言うところの部活動のようなものであるが、それは肉体的、魔法的教練だけに限ったものではない。朝の教練では、身体が元気なうちに肉体と魔法を鍛えるが、午後には魔法学理論を仲間と一緒に深めることに費やされることも多い。その日の午後教練もそれが予定されていた。
午後教練のための教室に移動すると、もうリズたちの姿があった。
「やあ、午前中はお疲れだったね。あれじゃあ怪物にはなれなかったかな?」そう言ってリズが笑う。
「1コマ目は不覚をとったけど、2コマ目はあんたのおかげでばっちりだったぜ!」そう言って席に着くとリズが隣に腰を下ろした。
「また、夜中にひとりでせっせと復習するつもりなんでしょ?」
そういうと、リズは午前中1コマ目のノートの写しを差し出してきた。
「なんだよ?」
「まあまあ。今朝も言ったけど、あんたは私たちの大切な希望だからね。その希望をサポートするのも私たちの務めってわけよ。」
そう言うと、リズはウィザードが不覚にも眠ってしまっていた間に進められた講義の内容を丁寧に教えてくれた。それでウィザードは、夜更かしから解放されるのである。
「どう、だいじょうぶ?」
一通りの説明を終えたリズがウィザードに問う。
「ああ、ありがとな。本当に助かったよ。」
「どういたしまして。」
リズが解説を始めてくれてから、かれこれ1時間半が過ぎていた。陽が大きく傾き、オレンジ色の光線が教室に幾本も走っている。
「どうよ、今日はこれくらいで。あんたにとっては休むのも大切な仕事よ。」
リズは優しい。こうした配慮はなかなかできるものではない。こいつは看護科向きなんじゃないか?ウィザードはそんなことを考えた。
「そうだな。たまには少しばかり早く帰るか?」
「そうしましょ。」
そういうと、ふたりは他のメンバーに別れを告げて、教室を先に出た。
「ごめんね、お先に。」
周りも、ウィザードの人並みならぬ努力は承知である。咎める者は誰もいない。
「また明日ね。明日こそ、あの銀髪女の鼻っ柱をへし折ってよね!」そんな声も聞こえる。
「ああ、任しとけ!」
ふたりが教室棟を抜けて寮棟に向かう道に出た時には、太陽は一層傾き、ふたりの前に長い影を落していた。
「あんまり無理は駄目よ。」そう語り掛けるリズに、
「リズたちが、みんながいるからね。大丈夫さ。」そう返して石畳を歩いていく。

ふたりの影は西日を受けて一層長くなる。角を曲がって寮棟にたどり着いた。
「じゃあ、私はこっちだから。」
リズはそう言って自室のある方向に向きを変える。
「ああ、また明日な。」
そういってふたりは別れた。
晩夏の暑さはこの時間になっても一向に衰えることを知らないようだ。あたりは蒸しかえり、石畳には陽炎が立っている。まだまだ秋は遠い。西の空に、ひとつ、ふたつと星の輝きが見えた。その星々が浮かぶ赤い空を濃紺の夜が塗り替えていく。それによって、星は一層の輝きを得る。その瞬きは、何を示すのだろうか?運命はよく星にたとえられる。「星の下に生まれる」とはよく言われる言葉だ。すぐれた星の下に生まれた者だけしか、すぐれた人生を歩むことはできないのか?そんなことはないはずだ。そう自分にきっといいきかせて、ウィザードは自室の中に消えていった。
夜の帳がますます降りてくる。生暖かい風が、寮棟の前の芝生を揺らしてていた。大会の日にまた一つ近づいていく。
第2節『銀髪の天才ソーサラー』
やれやれ、毎日毎日飽きないものだ。
今日もウィザード科のあの子は私に喧嘩を売ってきた。私ってそんなに嫌な女かしら?あの子に恨まれる心当たりなんてとんとないんだけど…。
更衣室の鏡を覗き込みながら、銀髪のソーサラーはひとりそんなことを考えていた。

だいたい、喧嘩するにしてもああもワンパターンだとやりようがないのよね。基本術式の『火の玉:Fire Ball』は確かに初等術式である『氷礫:Ice Balls』より上位の術式だけど、模擬戦で重要なのはスピードと手数、威力は二の次なのよね。輻輳して繰り出される彼女の火の玉のひとつひとつは重いけれど、生成速度の遅さと手数の少なさは致命的だわ。その間に私はいくつも氷礫を彼女に向かって繰り出すことができる。そのうち彼女は詠唱もままならなくなるわ。要するにやりようなのよ。それさえ分かれば、結構いい線行ってるのに、残念だわ。
でも、こう毎日だとさすがに困るわね。特にハンナたちがイライラしているのが気になる。あの子たちもひとりひとりはそんなに悪い子じゃないんだけど、集団になると嵌めを外しがちになるから正直ちょっと心配だ。ウィザード科のあの子が、私たちの練習に水を差しているのは事実だけど、それくらいのことで揺らぐようなら、それはむしろ私たちの方の実力が足りないというだけのことだ。少々の雑音はものともしないで、臨機応変に対応できるチームワークと集中力がなければ中等部の上級生は相手にできない。ハンナたちにもそれがわかるといいんだけど、まぁ、彼女たちには彼女たちの考えがあるだろうから、言っても仕方がないわね。一度あの子とはゆっくり話してみたい気もするけど、相手があの剣幕じゃ無理かしらね…。
そんなことを考えているところにハンナとその取り巻きたちが連れ立って更衣室に入ってきた。室内は一気ににぎやかになる。
「さすがお嬢ね、今朝もあの金髪バカはコテンパンよ!」
ハンナがあけすけに言う。まぁ、喧嘩に勝ったのは事実だ。
「私たちには、劣等種のウィザードを相手にしている暇はないって、昨日もあいつに言ってやったのに全然懲りてないんだから、こっちが参っちゃうわ。まったくバカの相手は疲れるわね。」
そんなことがあったのか…。あまりエスカレートしなければいいが。一抹の不安が脳裏をよぎる。私とあの子の喧嘩くらいは大したことではない。喧嘩といっても公式のルールにのっとった模擬戦をやっているだけだし、第一お互いに選手権を持つのだから、練習試合を申し込む権利も受ける権利もある。私はただ、彼女の挑戦を受けているだけで他意はない。
でも、ハンナたちの敵愾心には、時々、私でもちょっと怖くなるものがある。特にハンナたちが、あのウィザードの親友なのだろうか、いつも一緒にいる女の子に執拗に手を出しているのは前々から気がかりで仕方がなかった。今のところはただの言葉の応酬だけで、大事には至っていないし、相手も差して気にしていないようだけど、この大事な時期にエスカレートされると、私としては正直そっちの方が困る。
「ねぇ、お嬢。いい加減あいつらいっぺん分からせてやった方がいいかもね。」ハンナが言う。
「馬鹿なことはやめてよね。厄介事はごめんよ。第一、同学年のウィザード科なんて相手にもならないわ。今朝も見たでしょ?目標はもっと上に置かないと。同じウィザード相手なら中等部の上級生を相手にするくらいじゃないといけないわ。そうでしょ?」
「やっぱりお嬢ね!考えてることが違う。大丈夫、お嬢の快進撃の邪魔は誰にもさせないわ。今年こそ、ソーサラー科初等部の選手権チームは、その実力をギルドに見せつけてスカウト獲得よ!」
「おー!」だの「やー!」だのいう威勢のいい声が更衣室中にこだまする。私は正直そんなことには興味はない。まあそう言いきってしまうと嘘になるが、ハンナたちが考えているような壮大な野心は私にはないし、他人を見下して軽んじるというのも本当は好きじゃない。誰しもにそれぞれの事情があり、みな自分が置かれた場所で一生懸命にやっている。私だってそう。『貴族のご令嬢』なんてもてはやされてはいるけれど、現実はそんなにいいものではない。血統、伝統、格式、戒律、あれはだめ、これはだめ、あれをしろ、これをしろ、正直うんざりだ。本当のことをいうと、貴族の『お嬢』じゃなくて、ひとりの人間として向き合ってくれる友人が私は欲しい。もし今、我が家が没落して、名声を失えば、私がどんなにソーサラーとして優れていたって、ここにいるみんなは一人残らず私を見限るだろう。それは分かっているんだ。はぁ…。
「どうしたのお嬢?浮かない顔して。」
「別に、どうということはないのよ。気にしないで。」
「やっぱりあいつね。あいつのしつこさにうんざりしてるんでしょ。わかるわ。私たちに任せておいてよ。お嬢の邪魔は金輪際させないわよ。」
「大丈夫、そんなんじゃないわ。」
午前の講義の予鈴が聞こえてくる。
「急がなきゃ遅刻よ。」
チームリーダーとして、みなを急かす。
「遅刻者は特別訓練メニューをこなしてもらうからそのつもりでね。」
「お嬢にはかなわないわね。」
そんなことを口々に言いながら蜘蛛の子を散らすようにみな更衣室をあとにした。さあ、私も急ごう。
* * *
その日のお昼のことだった。食堂わきの少し開けた場所に私たちの選手権チームの面々とハンナの取り巻きが一堂に会しているのを見た。彼女たちは何事かを計画しているような様子だったが、私に声がかかっていないということは、私が気にすることではないということなのだろう。しかし、10人余りも集めていったい何をしようというのだろうか?今朝、去り際にハンナがいった言葉が急に思い出される。「金輪際邪魔はさせない」とは、いったいどうするつもりなのだろうか?本人には昨日直接伝えたが効果がなかったと言っていた。まさか…。いや、いくらなんでも彼女たちだってそんなに短慮ではない。ましてや大会を一か月後に控えたこの時期に集団で問題なんて起こせば、選手権それ自体に影響することは分かっているはずだ。そう自分に言い聞かせるようにして私はその場を去った。まさか、その判断が致命的な後悔をもたらすことになるとは、その時はまだ知る由もなかった…。
* * *
「おら、てめぇ、なめてんじゃねえぞ!」
ただごととは思えぬ怒号が、普段から人影のない研究棟の裏に響く。時刻は夕方5時を回ったころだ。陽は傾斜を強め、オレンジ色の光がぐるりと何かを取り囲む10人余りの人だかりを照らしていた。
「わかってんのか?あいつのせいで、お嬢も私らもずいぶん迷惑してんだよ。」
その一団に取り囲まれて、ひとりの少女がうずくまっている。ひどい暴力を受けたようだ、顔は痛みに歪み目からは涙がこぼれている。
「そのくらいでいいんじゃない。劣等種だけど、死なれても困るし。」そう言ったのはハンナだった。彼女は一団から少し距離をおいたところで一部始終を見物していた。どうやら彼女たちは放課後にリズをここに呼び出し、集団で暴行を働いたようだ。ついに一線を越えてしまった。
ハンナはリズに近づくと、片手で彼女の髪の毛の生え際を雑に握り、ぐいとその顔を持ち上げた。
「あの金髪もとんだバカよね。まあ、そんなの最初からわかってたけど。これだから劣等種は嫌いなのよ。」心底からの嫌悪を向ける。
「昨日のこの私の忠告をちゃんと聞いてれば、かわいそうなあんたはこんな目に合わずに済んだのにね。恨むならあいつを恨んでね。私を無視する方が悪いのよ。」
そう言うとハンナは手荒にリズの身体を振り払った。
「劣等種の分際で貴族にたてつくなんて、反吐が出るわ。悔しかったら何かやってみなさいよ、この劣等種!」
ハンナの言葉はどんどんエスカレートする。周りの取り巻きの中にも、その態度に動揺を見せる者が出るほどだ。
「なにもできないでしょ?劣等種だものね。それがあなたたちの運命なのよ。才能も素質もないくせに、私たちと同じ魔法使いですって!冗談じゃないわ。乞食と一緒にされちゃ迷惑なのよ。」
ハンナの心はどうしてこうまで歪んでいるのか?その見下し方には憎しみというより一種の狂気が宿っているようにすら思えた。
「悔しいでしょ?悔しいなんて高尚な感情が劣等種にあるのか知らないけど、あはは。」
ハンナは高らかに笑う。その瞳の色は尋常でない色と輝きをたたえていた。
「ねぇ、いつまでもはいつくばっているのってどんな気持ち?私たち貴族には永遠に分からないのよ。教えてくれないかしら。あははははは。」
その罵倒と侮辱は留まるところを知らない。
「そんなかわいそうなあなたにね。いいものをあげるわ。このハンナがあなたに力というものを教えてあげる。」
そう言うとハンナはリズの前にしゃがみこんだ。
「これはクリスタル・スカルという禁忌の魔法具よ。冥府の力を直接取り込むことができる代物でね。あなた方劣等種はもともとが空っぽだから、きっとたくさん取り込めるわよ。そしたらちょっとは強くなれるんじゃないかしら。どう?試してみる?」
ハンナはリズにその魔法具を見せつける。
「どう、これが力よ。私たちとあんたら劣等種を隔てる絶対の壁。でもこれがあればあなたも私たちに近づくことができるかもよ?」
不気味な表情でリズに迫る。全身に走る痛みでリズは答えることができない。
「ふん、やっぱり劣等種ね。何も言えないなんて全くの屑だわ。いいわ。ここに置いておいてあげる。使う使わないはあんたの勝手だけど、私たちにも我慢の限度ってのがあるのは覚えておいてね。もし、あの金髪バカがまたお嬢を煩わせたら、今度あいつの番だからね。次は半殺しでは済まないかもよ。」リズがキッとハンナの顔を見据える。
「なによ、まだ足りないの?まあ、あんたをこれ以上痛めつけてもしょうがないから、自分に何かできると少しでも思うんなら、それを使って私たちを止めてみることね。」そういうとハンナは立ち上がって一団を見た。
「帰るわよ。」
その言葉につき従って一団はその場を去っていった。
すっかり陽が落ちていた。その陰りの中に、リズと魔法具だけが残されている。初秋を思わせる少し乾いた風がその場を吹き抜けた。リズは倒れ込んだまま、唇を固く噛み締め、目から大粒の涙をこぼして泣いていた。唇には痛々しく血が滲む。
更にあたりは暗くなる。やがてリズは痛みに耐えながら、その魔法具を右手に握りしめて立ち上がった。その姿はハンナたちの仕打ちの凄惨さをありありと物語っていた。
彼女は寮棟の方へ向かって痛む足をゆっくりと引きずり始めた。
幾分か、夜空が高くなっているように見える。涙のしずくのように、星々と星座の瞬きが宵闇の虚空を彩っていた。
* * *
翌朝のウィザード科の更衣室である。
今日も朝の練習がこれから始まろうとしていた。そこに一人の少女が駆け込んでくる。
「ねぇ、聞いた!?」
「朝からうるせぇな、なんだよ?」
「あいつら、ついにやりやがったわ!」
「やったって何を?」
「あんた本物のバカなの?この時間にリズがいないのを何とも思わないわけ?」
「それって…、まさか!!」
「そう、そのまさかよ。あいつら昨日、研究棟の裏でリズをリンチしやがった。」
「なんだと!?ちくしょう、許せねぇ!」
そういうが早いか、ウィザードは更衣室を飛び出て、ウィザード科の練習フィールドに向かって一目散に駆けて行った。あたしが気に入らねえなら、あたしに言えばいい、なんでリズを。ゆるせねぇ!怒りがこみあげてくる。前後の見境など、もはや考えられる状態ではなかった。
階段を駆け上がると、ソーサラー科のフィールドが視界に開けてきた。
「くそ銀髪、出てきやがれ!」
そのソーサラーは、フィールドの一角で、朝の教練に備えて準備運動をしていた。
「また、あなたなの?今日はまたずいぶんな剣幕ね。」
「すかしてんじゃねえぞ、この野郎!てめぇ、よくもやりやがったな!あのクソ舎弟を使ってリズに手を出すなんて、きたねぇんだよ!」
それを聞いてソーサラーはハッとする。俄かに昨日の昼の光景が脳裏によみがえった。
「まさか…。」
「まさかも、さかさもあるか!リズの仇だ、覚悟しやがれ。」
「お願いよ、ちょっとまって。少し落ち着いてちょうだい。」
「おちつけだぁ?てめぇ、ふざけてんのか!?」
「とにかくお願いよ。」
その騒動を聞きつけてソーサラー科の選手権メンバーたちが集まってくる。もちろんそこには首謀者のハンナもいた。
「なによ、コイツ。あれだけやってもまだ懲りてないの?」
その声の方向をウィザードはにらみつける。
「てめぇ、よくもリズをやりやがったな!ぶっ殺してやる!」
「なによ、劣等種の分際でまたしても私の忠告を無視するつもりなのね。許せないわ。そっちこそ覚悟しなさい!」
「しゃしゃあと、冗談抜きで容赦しねぇ!」
いよいよふたりがやりあおうかというところで、大きな声がこだました。
「お願いよ、やめなさい!!」
声の主はソーサラーだった。その美しい姿のどこからそんな声が出るのか、その場に居合わせた者がみな一様に同じ驚きを隠せないでいる。
「ハンナ、どういうこと?」
「だから、こいつが毎日毎日お嬢の邪魔をしないように…。」
パァン!!!
乾いた音が辺り一面に響いた。
「お嬢、何を!?」身体を横たえ、左の頬に手を置いて、ハンナは目に涙をにじませている。ソーサラーが思い切りその頬をはったのだ。
「誰がそんなことを頼んだの?」
「だから、こいつが…」
「誰が一体そんなことを頼んだのよ!」
先ほどと同じ大きな声が響き渡る。
「ご、ごめん。」ハンナがしおらしい声を絞り出す。
「謝ってすむことじゃないわ。ハンナ、あなたは自分のしたことがわかってるの?」
「っつ!」それ以降、ハンナは口を利かなかった。
ソーサラーはウィザードの方に向きを変えると、静かに膝まづいた。
「謝って済むことでないことはよくわかっています。」その声が震える。
「でも今の私にはこうすることしかできません。実は、私にはハンナたちの非道に気付く機会がありました。でも、それを見過ごしてしまったのは私の落ち度です。結果的には全部私の責任です。ほんとうにごめんなさい。」
学年一とも言われる高貴な純血のソーサラーは、ウィザードの前に手をついて深々とその銀髪の頭を下げた。周りも、その光景が俄かには信じられないという面持ちで様子を見守っている。さすがのウィザードもすぐには言葉が出なかった。
「何だってんだよ、ちくしょう。」そうつぶやくのが精いっぱいだった。
「頭をあげてくれ。そこのクソ野郎の独断で、あんたが煽ったわけじゃないことだけはわかったよ。だからと言って、そのくそ野郎とはきっちり落とし前を付けるが、あんたにそうされたんじゃあきまりが悪すぎる。頼むよ、頭をあげてくれ。意地を張ったあたしも多分に悪かったんだ。謝るよ。」
そういうとウィザードはソーサラーのもとに膝まづきその手を取った。ソーサラーはそれに応じてゆっくりと頭を挙げる。
「本当に、ごめんなさい。あなたのお友達にはどうお詫びしていいか…。」
「それはいずれきっちりやってもらう。でも今はとりあえずわかった。」
そういうとウィザードはソーサラーの手を引いて立ち上がった。居住まいを正し、ソーサラーは威厳のある声で言った。
「本当にごめんなさい。ソーサラー科を代表して、正式にウィザード科のみなさんに謝罪します。お怒りはわかりますが、ソーサラー科の中の問題として、まずは私たち自身で今回の件を清算する機会を与えてください。お願いします。」
清水が岩にしみいるような、静かでいて威厳のある説得力を称えた物言いだった。だれもそれに異論をさしはさむ者はなかった。むしろ昨日の件に加担したであろう面々は、身の置き所がないという表情で、バツが悪そうにしている。
予鈴が遠くで鳴り響く。
「お前たちそこで何をしている!予鈴は鳴ったぞ。さっさと教室に行かんか!」見回りに来た指導教授が声を張り上げる。
ソーサラー科の面々は、それぞれの午前の教室に、ウィザードも自分の教室に向かわざるを得なかった。その日の朝の騒動はそうしていったん幕が切れたのであった。それから…。
* * *
放課後、教練用の教室に向かうとそこにはリズがいた。他の仲間も彼女を囲っている。
「遅刻よ。」リズがいつものいたずらっぽさで言った。
「大丈夫なのかよ?」
「あたりまえでしょ。あれくらいなんてことないわ。」
そうはいうものの、あちこちにばんそうこうをはり、あざをたくさん作っているその姿はあまりにも痛々しかった。
「リズ、すまねぇ。ほんとうにごめんよ。」
「なんであんたが謝るのよ。」
「だって、あたしがつまらない意地さえはらなきゃ、こんなことにはならなかったわけで。本当にすまなかった。」
「そんなのいいわよ。」リズはいつもの優しい笑顔を向けてくれた。
「ところで、あんたこれ要る?」
リズがクリスタル・スカルを片手に持ってウィザードに見せる。
「なんだよそれ?」
「なんでもね、理性と慈しみと引き換えにものすごく強力な魔法の力を冥府から授かることができる禁忌法具なんだって。『神秘の雲』で調べたらそう書いてあったわ。これがあればくそ銀髪にも勝てるんじゃない?」
「そんなのいらねぇよ。」
「そうよね。あんた、慈しみは最初からないからいいとして、その雀の涙ほどの理性をひきかえちゃったら、さしずめ火の魔法を使う猿だもんね!」
「うっせぇ。あたしが火だけじゃないってとこを今度みせてやるぜ。」
「へぇ、大した自身ね。」
「あたりまえだろ。あたしだってやるときゃやるぜ!」
「期待してるわ。」
理性と慈しみを奪うか…。この魔法世界には恐ろしい禁忌があるものだ。耐えがたい苦痛と屈辱に負けてあのときリズがそれを使わなくてよかったと、ウィザードは心底からそう思った。刹那、彼女はリズのその痛々しい身体を抱きしめていた。
「ちょっとやめてよ。私にそんな趣味ないんだから。」リズが笑う。
「あたしにだってねぇよ。なんていうか、チームワーク確認のスキンシップってやつさ。」
「そうね、ありがとう。」
そこにいあわせた仲間たちからあたたかい拍手が自然的に巻き起こる。
「おい、みんな。今度の大会はリズの弔い合戦だ!派手にやろうぜ!」
「ちょっと、勝手に殺さないでよね。」
教室全体があたたかい笑いにつつまれた。
時刻にすると、昨日の事件と丁度同じころだった。沈みゆく太陽も、涙のしずくのような輝きをたたえていた星々や星座も、同じ姿をていしている。しかし今日はその温かさがはっきりと違っていた。固定された環境、出自、運命、そうしたものに捕らわれていたとしても、人は自分の意思と可能性を自ら選び取ることができる。自然や運命はそれを入れるための器でしかない。器で中身が決まるわけではない。中身が器を彩るのだ。
教室のその談笑のあたたかさは、その夜遅くまでその熱を保っていた。
第3節『アーカムへ至る邂逅、そして』
私はなんて馬鹿なんだろう。気付く機会はいくらもあったというのに、そのすべてをことごとく見落としてしまった。ちがう、見落としたんじゃない。故意に見ようとしなかったんだ。今回のことの責任は全部私にある。ハンナが更衣室で不穏なことを口走った時、簡単に流すんじゃなくて、せめてもう少し彼女と言葉を重ねておくべきだった。あの小さな誤解さえ解いておけばこの事態は避けられたはずだ。また、あのお昼にしてもそうだ。ひとこと私が声をかけてさえいれば、彼女を傷つけることはなかっただろう。
そのことを考えると酷い心痛に襲われた。でも、チームのリーダーとして、この問題は私の手で決着をつけなければならない。少なくとも、ソーサラーの科の内側の問題だけでも、私自身が解決を導く必要がある。それが私の責任だ。
そう決意してソーサラー科の練習フィールドへと歩みを進めていた。そこに向かう階段に差し掛かった時、見知った人物が立っていた。
「よう。昨日は…。」ウィザードのあの子だ。
「こちらこそ。昨日は本当に…。」
「いや、それはもういいんだ。それよりあんたに見て欲しいものがある。」
何だろう?不思議に思っていると彼女はポケットから透明なガラスのようなものでできた、頭骨のオブジェクトを取り出した。
「あんた、これが何だかわかるか?」
「いえ、初めて見るものよ。何なの?」
「これは、あんたの舎弟が『力が欲しいなら使え』と言ってリズによこした、クリスタル・スカルっていう禁忌魔法具だそうだ。」

ソーサラーの顔に緊張が走る。
「で、こいつについて調べてみると、慈愛と理性と引き換えに冥府の魔法知識を使用者に授けるというトンデモない代物だった。」
まさか、ハンナがそんなことまで…。
「もしリズがこいつを使ってたらと思うと、あたしは怖くてたまらねえんだ。リズから力と引き換えにあのやさしさと理性を奪うなんて、考えたくもねえんだよ。それは人殺しと同じだぜ。」
全くその通りだ。胸が激しく痛む。
「だからあんたに頼みがある。今回のことは、あたしが勝手にムキになってあんたに挑戦したことがそもそもの原因だ。そのことについては本当にすまなかった。もう二度としねえよ。そのかわり、あんたたちも金輪際、こんな危ない真似はやめてくれ。」あの勝気がしおらしく首を垂れる。
「まったくあなたの言う通りよ。こちらこそ本当にごめんなさい。この問題はソーサラー科の側できちんと決着をつけるわ。」
「ありがてえ。で、もう一つ頼みがあるんだ。」
彼女はいよいよ深刻な面持ちになる。
「こんな危ねえもんを、なんであの女が持っていたのか気になって仕方がねえんだ。第一にこんなもんを持ってるなんてあいつ自身にも危険があるにちがいない。だから、コイツの出所と、あいつが持ってた理由をあんたに調べて欲しいんだ。」
「もっともね。でも、ごめんなさい。私はそうした禁忌や神秘についてはうといのよ。再発防止は私の責任で確実にやるけれど、その調査についてはどうしていいかわからないわ。」
「まあ、そうだよな。あたしにも見当もつかねぇ。」
ウィザードは言葉を続ける。
「それでだ。実はあたしらと同級にこういうめんどうな品物や厄介ごとについてやたらに詳しいウォーロックがいるって聞いたことがあるんだよ。」
その噂は私も知っている。
「で、今日の昼、そのウォーロックのところに行こうと思うんだが、あんたに一緒についてきてもらいてぇんだ。知っての通りあたしはこんな性格だろ?初めて話す相手に小難しいことをちゃんと説明できる自信がねぇんだ。だから、あんたに同行を頼みてぇ。」
「わかったわ。もとはと言えば私たちの側が引き起こしたことだし、ハンナの行動には私にも責任が大きいの。あなただけの問題じゃないわ。一緒に行きましょう。」
「ありがてぇ。ウォーロック科の教室は幸いあたしらウィザード科の隣だ。午前の講義が終わってからすぐに向かえば首尾よく捕まえられるだろう。そんなわけで、悪いけど、午前の講義がはけたらすぐウィザード科にきてくれねぇか?」
「もちろんよ。そのあと一緒に行きましょう。」
「すまねぇな。」
「そんな、誤るのはこちらの方よ。」
「よろしく頼むぜ。」
ウィザードの顔から緊張が解け、安堵の表情が広がる。
「じゃあ、私は行くわ。これからソーサラー科のメンバーと今回のことについてきちんと話して、それなりに責任のある結論を出すつもりよ。そのことについてはまた別の機会に話すわね。」
「わかったよ。よろしく頼む。」
そう言うと、ウィザードは踵を返し、自分たちの練習フィールドの方に向かっていった。私もしっかりしなければ、決意を新たにして、ソーサラーは階段を昇って行く。
まだ随分と暑いが、それでも幾分か吹き抜ける風の中に秋の装いを感じられるようになった、そんな日の朝だった。窓の外では、木々が青々と茂ったその枝をゆっくりと踊らせている。葉と枝の間をきらきらと光が揺蕩っていた。
* * *
午前の講義が終わった。さすがに今日ばかりは努力家を絵に描いたようなウィザードも、講義中気もそぞろであった。教室を出るとすでにソーサラーが彼女を待っていた。
「待たせてすまねぇ。」
「大丈夫、ウォーロック科の教室はすぐそこよ。さぁ、行きましょう。」
昼休憩の時間、あたりは騒然としていた。
ふたりがウォーロック科の教室にいままさに入ろうとしてしたとき、偶然にも件のウォーロックがそこから姿を現した。
「あの、すまねぇ。」ウィザードが声をかけると、ウォーロックは屈託なく言葉を返した。
「なにかしら?」
「突然ですまねぇんだが…。ああ、あたしはウィザード科の6年で、こいつはソーサラー科の同級なんだけど、あんたにこれを見て欲しいんだよ。」
そう言うとウィザードはポケットから例の禁忌具を取り出した。それを見たウォーロックは驚きを隠さなかった。
「まあ、クリスタル・スカルじゃない。そんな危ないものどこで手に入れたの?」
あたりだ!彼女ならきっとこれについて何かわかるにちがいない!
「実は…。」ふたりはここ数日の出来事について詳細な事情を彼女に伝えた。ウォーロックは難しそうな、心配そうな表情を浮かべている。
「事情は分かったわ。私にはそれがクリスタル・スカルであることはわかるけれど、その出所まではわからないわ。ただひとつ言えることは、アーカムから出たものではないということね。」
『アーカム』!!!ウィザードとソーサラーは顔を見合わせた。彼女はあのアーカムを知っているんだ。好奇と期待の色がふたりの特徴的な瞳に浮かんでいた。
「あんた、あのアーカムを知ってるのか?」ウィザードは驚きを隠さない。
「ええ、常連よ。」ウォーロックは冗談ぽく笑顔でそういった。
「これについて手掛かりを得る、何かいい方法はないかしら?」
ソーサラーが彼女に質問を振り向ける。
「そうね、さっきも言ったように、私自身が禁忌法具のことを全部把握している訳じゃないから、専門家に相談する必要があるわね。」
「そんな人がいるの?」
「もちろん!ただ、会うためにはアーカムに行く必要があるけどね。」
「頼むよ、あたしらをアーカムに連れて行ってくれねぇか?どうしてもコイツの出所を突き止めていろいろなんとかしてぇんだよ。」
「『いろいろなんとか』って、それじゃどうしたいのか全然わからないじゃない。」ウォーロックはころころと笑った。
「いや、すまねぇ。とにかく頼むよ、あたしらをそこに連れて行ってくれ!」
「おねがいよ。」ソーサラーも一緒に頭を下げた。
「あなたたちの話だと、事は急を要するみたいだから、早速、今日の放課後というのはどう?」
「ありがたい!頼むよ。」
「それじゃあ、ゲート前で待ち合わせしましょう!」
「わかったわ。」
「おうともよ。」
ふたりの顔に期待の色が輝く。これで前進を得られるかもしれない。
「ああ、そうそう。」その場を去ろうとするふたりを、ウォーロックがが呼び止めた。
「あそこの常連はもう一人いてね。その子も連れて行っていいかしら?」
「ぜんぜん構わねえぜ。」
「人数が多い方が心強いわ。」
「じゃあ後ほど。」
そう言ってふたりはウォーロックと別れた。
その後、ウィザードとソーサラーは一緒に食堂に向かい、昼食をともにした。つい数日前まで、毎朝、毎朝、ソーサラー科の練習フィールドで模擬戦をやり合っていたことが嘘みたいである。
太陽は真昼の位置にあった。その光はあかるくアカデミー全体を照らしている。にぎやかで活気ある学徒たちの声があちこちであがっている。穏やかなひと時であった。
* * *
約束の時間が来た。ウィザードとソーサラーは期待と若干の不安を共有しつつ、アカデミーゲートにウォーロックが現れるのを待っていた。秋が近づいてきたためであろう、心なしか陽の傾くのが早いような気がする。とはいえ、陽が沈むまでには、まだまだ時間は残されている。
「おまたせ!」今朝聞き覚えたばかりの声に続いてもう一つ声が聞こえた。
「おまたせしました。」
その声の主が、ウォーロックの言っていたもうひとり連れていきたいという人物なのだろう。それは黒髪と黒い瞳が美しいネクロマンサーだった。
「面倒かけてすまねぇな。」今来たふたりにウィザードが言った。
「よろしく。」ソーサラーがそれに続く。
「いいのよ。さぁ、行きましょう!でも、ちょっと遠いわよ。すぐ近くだけどね。」
不思議なことをいう子だ。遠いけど近い、どういうことだろう?彼女の天真爛漫に翻弄されながら、4人は例のマークスを辿って行った。
例のごとくクリーパー橋の高架下に差し掛かったあたりから、周囲が霧に覆われていく。そしてその霧は、南大通りを南下するに従って、一層濃くなり、アカデミー前との交差点に戻ってきたときには、あたりはもうほとんど何も見えなくなった。
「すげぇ霧だな。」ウィザードがつぶやく。
「そうね。こんなに濃い霧は初めて見るわ。」ソーサラーも驚いている。
「アーカムはここにあるわ。」
そういってウォーロックが指さした先に『アーカム』の看板があった。
「すごいわね。」ソーサラーの黄金の瞳が輝く。
「まじですげえ。」
「でもよ、ここってもしかして『キュリオス骨董堂』があるとこじゃねえか?」
「うふふ、そうね。私たちが知っている日常ではね。でも、ここはちょっと特別なのよ。」ウォーロックがいたずらっぽく言った。
「ほら、本当ならここは全部石畳で覆われているはずでしょ。でも土と草、そして水のかおりがしない?」
言われてみると、いつもの場所とは匂いが明らかに違って感じられた。匂いだけでなく、霧の切れ目からかすかに見える周囲の様子や地形も、本来そこにあるべきものとは微妙に違っていた。ふたりが不思議にとらわれているところで、ネクロマンサーが扉に手をかけた。押しても引いてもその扉は開かない。得心のいった顔で彼女は言った。
「今日は彼女ですね。」
そうしておもむろにドアを横に引いて見せた。そのドアは静かに横開きに開く。
「ちょうどいいわね。」ウォーロックがそんなことを言った。
アーカムの店内はいつもの通りだった。狭い一本通路の両脇に、埃をかぶった未知の魔術具や魔法具が乱雑に積み上げられている。
「広え。いや、この通路は狭えけど。」ウィザードが驚く。
確かに、彼女が指摘する通り、アーカムの店内はそのあるべき敷地より奥側に随分と広い。それはここが単に物理的に建設された場所ではなく、魔法的に構成された空間であることを意味していた。魔法は、これはラファエルの領域のものだが、空間や時空に対しても影響力を行使することができる。たとえば、時間を早めたり、止めたり、遅らせたり、空間を広げたり狭めたりといったことができる。本当に奇跡的な術式には、時空や空間をまるごと消し去るようなものまであると言われている。真偽のほどは定かではないが…。新参のふたりはその店内の禁忌と神秘の空間にすっかり心をうばわれ、夢ごこちの中にいるかのように、古参のふたりに誘われて奥のカウンターへと歩みを進めていった。
「いらっしゃい。」
ふたりには聞き覚えのある、もうふたりにははじめての声がカウンターから聞こえてきた。アッキーナである。
「まぁ、あなたたちでしたか。」
ふたりの姿を見とがめてそう言う。
「あら、今日はお友達もご一緒なのですね。」
「お久しぶりです、アッキーナさん。」
先頭を歩いていたネクロマンサーが彼女と真っ先に挨拶を交わした。それにウォーロックも続く。今ではすっかり常連となったふたりも、ここに来るのは久しぶりのようであった。
「どうも。」
「こんにちは。」
新客の二人もまた彼女と言葉をかわした。
「あらあら、今日は賑やかでうれしいわ。禁断の法具屋『アーカム』へようこそ。ご来店を歓迎いたします。私は店主のアッキーナ、アッキーナ・スプリンクル。」
その名前を聞いてふたりの顔に俄かに緊張が走る。
「アッキーナって!?」
「あの一級指名手配犯のか!?」
「違うわよ。まあ、そうでもあるけど。」ウォーロックが笑って言う。
「心配しないで、彼女は信頼のおける人よ。大丈夫。」
「はい、それは私たちが保証します。」ネクロマンサーも言葉を添えた。
ふたりはわかったようなわからないような顔をしながらも、当初の緊張は解けたようである。
「それで、今日はいかがいたしました?」

「見て欲しいものがあるのよ、アッキーナ。」ウォーロックが口火を切った。
「さあ、あれを見せて。」
ウォーロックに促されて、ウィザードがポケットから例の魔法具を取り出す。それはこの神秘の空間にあって禍々しい光を放っていた。
「アッキーナ、これの出所が分かるかしら?」ウォーロックが訊ねた。
「クリスタル・スカルのように見えますが…。」
それをウィザードから受け取ったアッキーナはひとしきり眺めまわす。
「大丈夫です。よくできてはいますが、これはまがい物です。ここにある本物のクリスタル・スカルではありません。おそらく最近あちこちに姿を現している『裏路地の法具屋』のどこかから流れ出たものでしょう。幸い、麻薬的な魔法がいくつかかかってはいますが、大したことはありません。本物にあるような破滅的な副作用はありませんね。これが、どうしましたか?」
「それじゃあ、これを使っても!」ウィザードの声が上ずる。
「はい、特段のことは起こりません。副作用もない代わりにこれといった作用もありませんが。使用すると幾分か魔力量と魔法威力が上がるくらいです。」
場の緊張が一気に解けた。特に、件のふたりにとってはその重荷からいくぶんか解放されたような、ある種腰の抜けるような心持ちとなったようである。
「実は…。」
ソーサラーがこの度の出来事を説明し始めた。さすが、学年1の天才と言われるだけのことはあり、その語り口は理路整然として的確かつ精緻であって、今回の事情を余すところなくアッキーナに伝えた。ウィザードはその姿にあっけにとられていた。
ソーサラーの話の中に、アッキーナがところどころ怪訝な表情を浮かべる個所があった。
「ところで…」アッキーナが口を開く。
「その、ハンナさんという方は昔からそのような感じの方なのですか?」
それを聞いてソーサラーがハッとする。確かに彼女は昔から、高飛車で他人に対して高圧的なところはあったが、今回ほど極端に他人を見下して罵倒したり、まして暴力沙汰を起こすような子ではなかった。むしろどこかにさびしさをかかえ、甘えられる先を探しているようなところすら持っていた。そういえば、彼女は貴族の令嬢ではあるが、いわゆる妾腹で、家族とは微妙な関係にあると別のチームメンバーから聞いたことがある。彼女には彼女なりの苦悩があったのかもしれない…。
そう思い返すと、ここ数日のハンナの様子が明らかに尋常でないことは確かであった。ソーサラーはその旨をアッキーナに話した。
「やはり、そうでしたか…。実はそのハンナさんについて気になっていたのですが、今の話を聞いて確信が持てました。彼女は『ケレンドゥスの毒』におかされている可能性があります。

俄かに騒然となる。
「その、なんとかの毒ってなんだよ!?」ウィザードがまくす。
「『ケレンドゥスの毒』は低レベルな錬金術といくばくかの魔法を使って錬成される薬です。程度の悪い『裏路地の法具屋』で最近盛んに扱われています。それは、不快感の軽減と緊張の緩和に効果があり、簡単に言えば『手軽に嫌なことを忘れられる一種の麻薬』です。ただ、少々副作用が深刻で、長期間連用すると服用者の精神は徐々に蝕まれ、その人格を極めて攻撃的かつ破滅的に変容させるのです。そのハンナさんの瞳に、呪印のようなものが浮かんでいるのを見たことはありませんか?」
「それはまだありません。」ソーサラーがすぐに応える。心なしか震えているようだ。
「そう、それはよかった。末期の症状になると、瞳に呪印が浮かび、正気を失います。思い込みが激しくなり、狙い定めた相手に見境なく襲いかかるようになります。」
「彼女を救うことはできないのですか?」ソーサラーの声が涙ぐむ。
「できなくはありません。ただ少々難しいものになります。」
「どうすりゃいいんだよ!?」
「『ケレンドゥスの毒』を解毒するためには、まずその毒を手に入れなければなりません。それを基にして解毒薬を魔法的に錬成します。ただそれは特効薬という訳ではありません。治療にはまず長期間にわたる治療薬の服用が必要になります。服用を止めると場合によって再発することがあります。また、全く完全に症状を治療することはできません。本人がある程度いまの自分を受け容れて、前向きに生きていこうとする気持ちを持たなければなりません。実はそれが一番難しいところです。変わった性格は完全には元通りになりませんが、本人の意思さえ強ければ、新しい人生を前向きに紡いでいくことは可能です。」アッキーナは静かに語った。
「完全には治らねぇのかよ。つまらねぇな。」
「そうですね。お気持ちは分かりますが、彼女自身の生きようとする力が試されると思ってください。」
「わかりました。」ソーサラーは涙をこらえる。
「ところで。」アッキーナが再び話し始める。
「実は最近、あちこちの『裏路地の法具屋』でその『ケレンドゥスの毒』が出回っていて、あの方も私もずいぶん心配しています。どうも何者かが資金を荒稼ぎするためにばら撒いているようなのです。先ほどの『クリスタル・スカル』もおそらく同じような事情で出回ったものでしょう。それで、あなた方にひとつお願いがあります。それらの出所について調べてもらえませんか?なにせ私は…」
「この店を離れることはできないし、あの方もこことの関係を公にできない、でしょ?」
「このお店の性質上、警察には届けられない。そうでしたね?」
ウォーロックとネクロマンサーが茶化して言う。
「まぁ、おふたりはもう本当にここの常連さんですね。」アッキーナも笑った。
「とにかく、そんなわけで調べて欲しいのです。お願いできますか?」
「もちろんよ!あなたたちも手を貸してくれるわね。」
ウィザードとソーサラーは互いに顔を見合わせる。
「いいぜ。」
「もちろんよ。」
どうやら話はまとまったようだ。なにより、ハンナを救うためには、いずれにしたってその『ケレンドゥスの毒』を手に入れなければならない。アッキーナの依頼はそのついでといえばついでである。
「じゃあ、また来るわね。」
「はい、お待ちしています。お帰りは分かりますか?」
「コイルを逆順に!」ウォーロックとネクロマンサーが声をそろえた。
4人がマークスを逆順にたどって再びアカデミー前に戻ってきたときには、もうすっかり日が落ちていた。確かに秋は近づいている。やらなければならないことができた。明日からは忙しくなりそうだ。
ゲートをくぐると、めいめい別れを告げてそれぞれの寮棟に向かって歩いていった。空はいよいよ高くなり、星々と星座がその天空のキャンバスを思いのままに彩っている。心なしか、秋虫の声が聞こえてくるような気がする。夜はしずかに更けていった。
第4節『決戦の朝』
ああ、いらいらする。腹が立って仕方がない。どうして私だけがこんなに惨めな思いをしなくちゃいけないの!お嬢もお嬢よ、なにも皆の前であんなふうにぶつことないじゃない!おかげで大恥よ。あの女、許せないわ。お父様にだって未だかつてぶたれたことないのに!…ふふ、お父様が私をぶつことなんてないわね…。お父様はなんでも与えてくださるけど、私にもお母さまにも本当の意味での関心も愛情もお持ちじゃないわ。私たちを手元においているのはご自分の対面のためだけですもの…。それは最初から分かっていたわ。私はお姉さま方とはちがう。奥様の娘であるお姉さま方は、お父様から本当の愛情を注がれている。それに対して私は…。いいえ、そんなことはどうでもいのよ。頭にくるのは、あの金髪の劣等ウィザードと、私に恥をかかせたあの女よ。ふたりとも絶対に許せないわ。そうね、まずは全ての種をまいたあの劣等金髪ウィザードを何とかしなくちゃいけないわ。そもそも、あいつがあの女につきまとったりしなければ、私たちは順調に練習を積んで、大会に臨み、上級生のチームにも勝利して、ギルドからのスカウトを受けることができたのよ!そうすれば、あのお父様だって、きっと私のことを見直してくださったはずだわ。そしてそうすれば、お母さまをもっと大切にしてくれたはずだもの。そのはずだったのに、あの劣等種のバカな金髪のせいで全てが台無しになってしまった。
あの女も、何が贖罪で責任だか知らないけれど、勝手に今年の大会エントリーを取り下げたりして。いったい何様のつもりよ!学年一の天才なんてもてはやされているけれど、私たちが助けてやらなければあんな金髪のバカひとり、対処しきれないくせに。いつでも自分は一格違うというふうにすかしていて、気に入らないったらないわ。いつかあの女とも決着をつけてやる!
でもまずはあのバカの劣等金髪よ。あいつだけは本当にただでは済まさないわ。私のこの手でずたずたに引き裂いてやる!そうよあの金髪を生かしておいたのでは、私の今後の人生はどんどん悪くなる一方よ。自分の身は自分で守らなければいけないわ。そのためにも、邪魔者は徹底的に排除しなければいけない!そう、あの劣等金髪に引導を渡す時よ!!
そう言い募ったハンナは、自室の机の上に置かれたカップから何かを一気に飲み干した。見てなさい、劣等種どもめ。この私がこれから皆殺しにしてやる!!
カップを置いた彼女の顔を映す鏡には、光の反射とは違う何か別の輝きが見て取れた。
* * *
朝の練習フィールドでは、ウィザードとそのチームメイトたちが教練のためのフィールド整備を行っていた。まだまだ暑いが、少し乾いた心地よい風が吹いている。その時だった。
「劣等金髪、出てきなさい!」
ハンナの声だ。しかしそれは何か不気味に揺れている。何事か?
「なんだてめぇ、やろうってのか!?」
「そうよ、まずはあんたから。そして次にはここにいる全員血祭りにあげやる!」もはや普通の女学徒の言葉ではなくなっている。リズは明らかにおびえていた。
喚き散らすハンナの顔を見て、ウィザードはハッと気づく。
「呪印だ!」
そう、ハンナの瞳には、アッキーナが『ケレンドゥスの毒』の末期症状だとして教えてくれた魔法の呪印が不気味に浮かんでいる。その時が来てしまった。とにかくソーサラーたちにこの状況を知らせるためにも、まずは正気を失っているハンナを止めなければならない。
「いいぜ、返り討ちにしてやる!」
ウィザードは彼女を止める覚悟を決めてそう言い放った。
ふたりはフィールドの真ん中にじりじりと進み出る。
「劣等種の分際で、よくも何度も私を無視してくれたわね!絶対許さない。」
その表情は怒りと狂気で大きく歪んでいる。なにより瞳の呪印が禍々しい。
「へっ、上等だ。かかってきやがれ。」
「ふん、あなたの弱点なんてお見通しなのよ。すぐに終わらせてやるわ。」
『水と氷を司るものよ。この手に氷の礫を繰り出す力を与えたまえ。氷礫:Ice Balls!』
ハンナの手から4、5個の大きな氷礫といくつかの小さな破片がウィザードに向かって繰り出された。
「へ、ずいぶんしけた数じゃねぇか!」ウィザードはさっと身をかわす。
「くっ、バカにして!」
続けざまにハンナは氷礫を繰り出す。その数についてはあの天才を相手にする場合とは比べるまでもなく問題にならない(あの天才は、一度の詠唱で15から20個近い氷礫を繰り出してくる)。しかし、ハンナの詠唱スピードは速い。うかうかしていればいつかは捉えられる。
「うってきなさいよ。あんたのへなちょこ火の玉を!」
ハンナが氷礫を立て続けに繰り出しながら挑発する。さすがに初等術式だ。詠唱が短い分反覆速度が半端ではない。しかもこの氷礫の魔法は魔力消費量が小さいため、連続で使用してもソーサラーのもつ魔力があれば、そう簡単には魔力枯渇は起こさない。氷礫をかわしながら、ウィザードはフィールド全体を所狭しと走り回る。「これならやれるぜ!」そう自分に言い聞かせた。しかし、しょせん火の玉:Fire Ball の術式では、詠唱速度の遅さと、命中精度の問題で、ハンナ相手と言えども話にならない。しかも魔力消費量はこちらの方が大きいときている。チャンスはそう何度もある訳じゃない。とにかく相手を疲れさせて詠唱のリズムが乱れた時を狙わなければ!あのしけた氷礫ごとぶっとばしてやる!
「どうしたのよ!そんなのであの女に勝てるつもりでいたの!?笑わさないで。最初からあんたなんてこの私で十分だったのよ!」
ハンナはなおも執拗に氷礫を絶え間なく一定のリズムで繰り出してくる。しかし、数が知れているのでかわすのは難しくない。なおもウィザードはフィールドを駆けまわる。
「炎しか能のない劣等ウィザードが、私たち優れた血統のソーサラーに勝てるはずなんてないのよ!」
その声が揺れる。疲れが見え始めた。
次第に氷礫を繰り出すリズムに乱れが生じ始める。
「はぁ、はぁ、ちょこまかと!くらえ、『Ice Balls!』、ちっ、もう一度、『Ice Balls!』」
明らかにリズムが悪くなった。リズムが整っていた内は、フィールドに常に合計10個前後の氷礫と欠片でウィザードを追うことができていたが、今では、5、6個に落ち込んでいる。そろそだな。
「炎しか知らない、一つ覚えのバカが!逃げ回ってばかりいないでかかって来なさいよ。」その声はいよいよヒステリックになってきた。よし!
「へっ、なめんじゃねぇ。ウィザードが火と光だけじゃないところを見せてやるぜ!」そういうと彼女は詠唱を始めた。
『天候を司るものよ。水と氷を司るものとともにしてわが手に雲を成せ。空気を振動させ、風を巻き起こせよ。周囲を飲み込め!竜巻:Tornado!』
そこに居合わせた誰もがその詠唱を聞いて息をのんだ。ミカエルの術式じゃない!
ウィザードの手からは雷が天地逆方向にほとばしり、その稲妻の周りに重苦しい積乱雲が瞬く間に形成される。刹那、積乱雲と大地の間に大きな竜巻が形作られ、それはやみくも一直線にウィザードを追うだけだったハンナの単純な軌道を的確にとらえた!繰り出されていた氷礫ごと彼女の身体をそれは飲み込んでいく。

「きゃあぁぁぁぁぁぁぁ!」
ハンナは、竜巻にぐわっと高く持ち上げられた後、激しく地面にたたきつけられた。それきり、彼女の動きは止まった。その身体はうずくまったまま痙攣している。
「おいだれか!」ウィザードの声がその場の緊張をやぶった!
「すぐにあのくそ銀髪…、じゃねぇ、今すぐあいつを呼んできてくれ!」
そういうと彼女は倒れ込んだハンナのもとに駆け寄った。
「大丈夫か?」
ハンナの顔は恐怖と狂気に引きつり、痙攣はますますひどくなるばかりでとても尋常な様子ではない。その瞳には陽炎のようにゆらゆらと怪しく『ケレンドゥスの毒』による呪印が揺れている。
「こりゃいけねぇ、あいつはまだか!?」
その場に人手はあるのだから、適当に助けを請うことはできた。しかし今のこの異常極まるハンナの姿についてどう説明すればよいか見当もつかない。ソーサラーと二人であれば、ハンナを安全な場所に移してやることもできる。そう思って、ウィザードはその到着を待っていた。
ほどなくして、ソーサラーが駆けてきた。リズが彼女を呼んでくれたようだ。
「何があったの?あ…!」
「あたしがぶっとばしたら、ハンナがこんなんなっちまった。こいつの目を見てくれ、末期の症状が始まってやがる。」
その呪印はうらめしくハンナの瞳に留まり続けていた。
「とにかく、どこかに運ぼう!」
「じゃあ、私の部屋へ!ここからなら角部屋の私の部屋が一番近いわ!」
そう言ったのはリズだった。
「わかった!」
どのみちリズにゃあ説明してやらなきゃいけねぇし。三人はハンナを助け起こし、ウィザードとソーサラーがその痙攣の続く身体の両脇を支え、リズが先導して進んでいった。
リズが部屋の戸を開け、ふたりがハンナを運び入れて、ベッドに寝かせる。その時には、いくぶんか痙攣は収まっていたが、瞳の呪印は消えず、ハンナの顔は苦悶に引きつっていた。
「すまねぇが、あいつらを呼んできてくれ。」それは、ウォーロックとネクロマンサーのことだろう。
「わかったわ。すぐに戻る。」そう言ってソーサラーはリズの部屋を後にして駆けて行った。
それから4、5分のうちに、その戸は再び開いた。
「どうしたの?」
「大丈夫ですか?」
ウォーロックとネクロマンサーが駆け込んでくる。ハンナを見るや、
「これは不味いわね。何とかできる?」
「はい、おそらく回復術式と治癒術式で、いくらか改善は見込めると思います。」そう言うとネクロマンサーは詠唱を始めた。
『慈愛に満ちた我らが加護天使よ。その慈愛の憐憫を垂れたまえ。その傷を癒さん。癒しの光:Healing Light!』
ハンナの痙攣が幾分弱まる。
「治癒も頼むぜ。」
「わかってますが、私たちの学年ではまだ治癒術式は使えません。代わりにこれを使いましょう。」
そういうとネクロマンサーはカバンから『万能薬』の薬瓶とシリンジを取り出した。シリンジの先の針をその薬瓶に立てて、手早く薬液をシリンジに移す。別の小瓶を取り出し、その中の液体でハンナの腕を消毒して、そこに万能薬を注射した。さすがは看護科併科のネクロマンサーだ。そこにいるだれもがその手際の良さに感心した。
注射をしてから、しばらくして、ようやくハンナの痙攣は収まり、瞳の呪印も消えて、普通の色を取り戻した。
「ハンナ、私よ。わかる?」ソーサラーが声をかける。
「お、お嬢…?」
よかった、意識が戻った。
「あの、私…。」
「いいのよ、大丈夫?」
「ええ、もう痛みは引いたわ。気分もいくらかよくなったように思う。」
そういうとハンナはゆっくりベッドの上で上体を起こした。一同の顔に、安堵の色が見える。
* * *
「ねぇ、ハンナ。」ソーサラーが本題を切り出す。
「『ケレンドゥスの毒』って知ってる?」
ハンナは、なぜそれを知っているのか、という驚きの表情をした。
「やっぱりお嬢にはかなわないわね。なんでもお見通しなんだから。私はいつでも空っぽの道化ね。」
「自分をそんな風に言わないで、お願いよ。」ソーサラーが声を震わせる。
「私は『ケレンドゥスの毒』の、そうね、いわゆる常習者よ。」
ハンナは静かに、自虐的な笑みを浮かべてそう言った。
一同が固唾をのむ。
「いったい、どうしてそんな?」
ソーサラーがハンナの手を取った。
「お嬢、私の出自については知ってるでしょ?」
「ええ。」
「私ね、いつも寂しかったの。家では誰も私を本気で相手にしてくれる人がいなかったわ。お母さまでさえ、お父様のお心をつなぎとめることに必死で、私を相手にする暇はないの。お姉さまたちが、そんなお母様と私を見下しているのは明らかだった。だからきっと悔しかったのね。」
ハンナの手を握るソーサラーの手に力がこもる。
「アカデミーでもね。私は本当はお嬢に嫉妬してたんだ。バカみたいでしょ。私なんかがお嬢に追いつけるはずないのにね。名門ソーサラー貴族の嫡出令嬢で稀代の天才ソーサラー、もし私がそんなだったら、きっと家族の見る目もかわるのになって、いつもそう思ってたわ。私はお嬢に憧れていたし、同時に憎らしいほどに嫉妬していたの。ごめんね。だから、純粋無垢にお嬢に向かっていけるあなたがうらやましかった…。」
そう言って、ハンナはウィザードの顔を見た。
「だからいっぱい意地悪しちゃった。」
「あれは意地悪ってレベルじゃねえけどな。」
憮然としてウィザードが言う。
「リズになんか言うことがあるんじゃねえのか?」
「そうね。その通りだわ。」
ハンナは申し訳なさそうに上目遣いでリズをみる。リズはいつもの慈愛に満ちた笑顔を保っていた。
「リズさん、本当にごめんなさい。謝って済むことじゃないけど…」
「いいわよ。よくわかんないけど、薬のせいなんでしょ。しょうがないじゃん?」
「本当にごめんなさい。」ハンナは激しく嗚咽して泣き崩れた。
「本当に…」そういうハンナの肩にリズはそっと手を置いた。
「で、私だけいまいちこの状況が呑み込めないんだけど、要するにそのなんとかの毒をこれから抜かなきゃいけないんでしょ?」とリズが言う。
「そのとおり。ハンナ、あなたはこれから『ケレンドゥスの毒』の解毒治療を受けなければいけないわ。今は、薬によって一時的に回復してるけど、時間が立てば、また毒が回ってくるわ。」ソーサラーが続ける。
「その治療は時間のかかる困難なものなの。それに…」
一瞬言い淀んだ後、意を決して告げる。
「完全に治ることは残念ながらないわ。でも、あなたに今の自分を受け容れて、新しい人生を自主的に紡いでいく強い意思があれば、きっとうまくいく。だから治療をしましょう!」
「ありがとうお嬢。」涙をしゃくりながらハンナは頭を下げた。
「それで、そのためには、その毒が要るんだ。」ウィザードが切り出した。
「あの毒と、あとクリスタル・スカルをどこで手に入れたのか、あたしらに教えてくれねぇか?」
「そうよね。わかったわ。」ハンナは頷く。
「あれは、昨年の秋、ちょうど大会が終わった日のことよ。私たちは残念ながら準決勝でウィザード科の中等部に負けてギルドのスカウトを逃したわ。私はそれに賭けてたから、どうしようもなくむしゃくしゃしてたの。そのときよ。憂さ晴らしに『スカッチェ通り』を歩いていたら、なんとも怪しい風体の男に声をかけられたわ。『ずいぶんお腹立ちですね。これを飲めば楽になりますぜ』って。それが『ケレンドゥスの毒』との最初の出会い。初めは禁忌法具だとは知らなかったわ。でもそれは実によく効いたの。それを飲んでしばらくすると、大会のことも、アカデミーのことも、家族のことも全部忘れられて、それはそれはよい心地だったのよ。気がついたら、私は自ら『スカッチェ通り』をうろついてその男を探すようになっていたわ…。」
一同が静かにその告白に聞き入る。
「あるとき、そんなにこれが気に入ったのなら、いつでも好きな時に買えるようにと『裏路地の法具屋』の場所…、正確にはそこに行く方法を教わったわ。教わったというか買ったのね。」
「で、その方法というのは?」ソーサラーが尋ねる。
「『スカッチェ通り』の小道に35段の階段がある場所があるわ。その階段の左端を登って左端を降り、もう一度左端を上って今度は右端を降りるの。そしてさらに左端を上ると、左手にその店は現れるわ。『P.A.C.ストア』というのがそこの名前よ。右端を降りるときに階段の数を数えてみて。35段の階段が36段になっていれば成功よ。その後でもう一度左端を登れば店の入り口が現れる仕組みになってるわ。クリスタル・スカルもそこで買ったのよ。」
そう言うとハンナは再び申し訳なさそうにリズの顔を見て、それから目を閉じた。

「少し眠らせた方がいいと思います。」
ネクロマンサーがそう言った。ソーサラーは静かにハンナの身体をベッドに横たえる。
「ハンナさんの治療のためには、その店に行って、同じ毒を手に入れる必要があります。私たち4人はすぐにそこに向かわなければなりません。そこでリズさんにお願いがあります。3時間おきに、夜中も含めてです。3時間ごとにハンナさんにこの万能薬を飲ませてください。」
ハンナのためにリズがそんなことを引き受けるだろうか?事態の詳細をつぶさに知るウィザードとソーサラーのふたりは気が気でなかった。
「まかせといてよ。それで彼女は助かるんでしょ?」
いつもの笑顔でそう答えるリズの表情には一片の躊躇いもなかった。
「大丈夫です。私たちに任せてください。」ネクロマンサーは答えた。
「それじゃあ、みんな。行くわよ!」
ウォーロックが号令をかける。
残る三人は深く頷いた。
『スカッチェ通り』はここから歩いて30分ほどのところにある比較的閑散とした地区だ。その上にかかる『スカッチェ大橋』は観光名所となっているが、通り自体はどちらかというとさびれている。だから『裏路地の法具屋』に目をつけられたのだろう。
4人は、アカデミーのゲートを抜け出ると一目散にそこに向けて駆けて行った。午前の講義はサボタージュである。だが今はそんなことを言っているときではない。急がなければ!
第5節『努力と才能、可能性とその外延』
「ここね。」
今4人は、ハンナが教えてくれた『スカッチェ通り』の脇に入り組むいくつかの裏路地のうち、35段の石段のある場所にいた。彼女の言う通り、狭い階段が下の路地から上の路地へと続いており、その段数は下から数えると確かに35段あった。上の路地には古びた集合住宅のような建物がひしめいているが、いまのところ商店らしいたたずまいは確認できない。
彼女が教えてくれた、そこに至る魔法を実践する必要があるようだ。
「とにかく、ハンナが教えてくれた通りにやってみましょう!」
ウォーロックの言葉に続いて、4人は石段を登り始めた。その石段は、狭い横幅に似合わず、その中央を不自然な亀裂が貫いており、各段は確かに左右に分離しているように見えた。最初は確か左端をのぼるのだ。
慎重に数を数えながら登っていくと、それは確かに35段あった。次はそのまま左端を降りる。段数を数えてみるとのぼったときと同じ35段ある。ある意味当然だ。ハンナはもう一度、左側をのぼれといった。
石段の中ほどに差し掛かったあたりから、こころなしか晩夏のこの時期とは思えない肌寒さを4人は覚えた。ほどなくして上の通りに到着する。問題は次だ。ハンナは、次にその石段の右端を降りろと言っていた。その際、慎重に数を数える様にと言い添えて。
その通りに実践してみる。1、2、3…、慎重に足元の階段を数えながら下まで降りた時に、一同は顔を見合わせた。
「36段ある!」
さきほど感じた肌寒さが一層強くなった。あたりがほんのりと霧に覆われてきたように思える。
「次でたどり着けるはずね。」ウォーロックはそう言った。
4人の顔に緊張が走る。
「最近、こんなのばっかりだな。」とウィザード。
ソーサラーは興味深そうにその黄金色の瞳を美しく輝かせている。
「さぁ、行きましょう!」ネクロマンサーが先導した。
石段を登るにしたがって、肌寒さは一層ひどくなってきた。もう肌寒いというより明らかに寒い。
「くそ、えらく寒いじゃねぇか。」ウィザードがこぼした。
いよいよあたりの霧も濃さを増してくる。足元も白く覆われ、階段の段差を目視するのが難しくなってきた。上の路地は真っ白で、そこに何があるのか、石段の途中からでは認識できなくなった。
それでも4人は進んでいく。ついに上の路地に出た。あたりは濃霧に覆われて満足に状況が分からない。『スカッチェ通り』はさびれた地区だが、倉庫街などがあるためそれなりに人の往来やその声が絶えることのない場所だ。ところが気が付いてみると周囲は不気味な静寂に包まれていた。
あたりを慎重に見まわす4人。
「あったわ。」とソーサラーが言う。
「ここのドアの上の小さな表札に『P.A.C.ストア』とあるわね。」
「どうやら、ここで間違いないようですね。」ネクロマンサーが確認した。
「みんな、心の準備はいい?行くわよ。」
ウォーロックがみなを促して、そのドアノブに手をかけた。
「いつでも、いいぜ!」ウィザードは強気だ。
押すのか?引くのか?
そんなことを考えながら、ウォーロックは試しにドアを引いてみた。はじめてアーカムを訪れた時と同じように…。
ドアノブがかちゃりと音を立て、思いの外新しいその木戸は静かに開いた。
* * *
店内は青白くぼんやりとした間接的な明かりに照らされていた。外観よりも店内はずっと広い。ちょっとした競技用フィールドくらいの広さはあるかもしれない。そのだだっ広い感じが独特の不気味さを演出していた。おそらくここも内部の空間を魔法的に拡張しているのだろう。
店内には、その内周を取り囲むように商品棚が整然と並んでおり、各棚には怪しげな物品がところせましと陳列されていた。4人は2人ずつ二手に分かれて、店の中を見て回り始めた。干からびた黒い人骨のようなもの、なんとも不気味な色の光をほんのり放つ液体を詰め込んだ薬瓶、衣類や装具、その他には、きっと偽物であろうが法石のようなものも扱っているようだった。神秘というよりは不気味な感じで、どの物品も『アーカム』のものとは少し違っている。それは、いわゆる品物の級の違いであるように思えた。

特筆すべきは、その店の一角に、最近誕生したばかりの『錬金銃砲』とその弾丸にあたる『法弾』の専用コーナーがあったことだ。それは非常に充実していて、それらがこの店の目玉商品であることに間違いなかった。特に法弾の種類が豊富で、一般の錬金法弾はもとより、『魔法銀の法弾』から、貴重な『炎鉄の法弾』まで各種が取り揃えられていた。さながら違法銃砲店といった装いである。
「あったぜ!」ウィザードが小声でそう言った。
三人は、その声のもとに集まった。彼女が指さす先には、あのまがいものの『クリスタル・スカル』とまったく同じものがショーケースに収められていた。
「ここで、間違いなようだな。」
「そうね。あとは『ケレンドゥスの毒』を探し出さないと。」
ウィザードとソーサラーがそんなことを話しているときだった。青白く不気味に薄暗かった店内がぱっと一気に明るくなった。
「いらっしゃいませ。お買い物ですか?」
聞き覚えのない、何か軽薄でいやらしい感じの声がそのやたらだだっ広い店内の奥から聞こえた。まもなくして、その声が姿を現した。それは、やせこけた30前後の比較的若い男で、薄気味の悪い真っ黒なローブを身に付け、酒にでも酔っているかのような足取りで4人に近づいてきた。

「P.A.C.ストアへようこそ、今日は何をお探しで?」
男は言った。
刹那、ウィザードがとびかかりそうになるのをソーサラーが静止して、4人はその男と対峙する。
「『ケレンドゥスの毒』を探しに来ました。取り扱いはありますか?」
ネクロマンサーが男にそう語り掛けた。
「それはそれは、ございますとも。そういえば、みなさんお若いのにずいぶんとこわばった表情をしておいでで。特にそちらのブロンドのお嬢さんは、どうにも怒りっぽくていらっしゃる。お疲れが溜まっているのでしょう。そんなみな様にあれはうってつけの商品でございます。」
そう言って男はにやにやと笑った。
「こちらでございます。」
男についていくと、そのだだっ広い店内の中央に配置された大きな陳列台の真ん中に、いかにも目玉商品でございという体でそれは陳列されていた。
「おいくらほど、ご入用で?」そのにやにや声が問うてくる。
「全部よ。」ウォーロックが毅然と言い放った。
「おやまぁ、それは何とも景気のいいお話しで。よいですとも、この棚の上のすべてをお譲り申し上げます。」
「そういう意味じゃないわ。」ウォーロックが声を厳しくする。
「そう、おっしゃいますと?」
「金輪際、それが市場に出回らないように、原料の残りかすまで、全部いただくわ!」
「なるほど、なるほど。そういう御用で…。」男の声の調子が変わった。
「みなさまは、治安警察かなにかのお方ですか?それにしてはずいぶんとお若くいらっしゃるようですが。」
「違うわよ。そんなんじゃないわ。」ウォーロックは続けた。
「へぇ?それじゃあまたどうしてそのようなご注文を?」
「友達のためよ。あと、そうね。あなたのそのイライラする口を黙らせるためかしら?」ウォーロックが挑発して見せる。
「左様でございましたか。私どもも商売でございますので。その邪魔しようという方々にはそれなりのおもてなしをしなければなりません。」
そう言うと、男は店の奥を振り返って、指笛を鳴らした。
それを聞いて、奥から7人の用心棒らしきのが姿を現した。
「おい、こいつらを始末しろ!」今までとは全く異なる攻撃的な声色で、男は命じた。
連中が襲い掛かってくるが、そうなることは織り込み済みだ。互いに少しずつ距離をとって、4人はさっと身構えた。
男たちは手に光るものを抜いた。
「どうやら、魔法使いではないようね!それなら!」
そういうが早いか、ソーサラーは詠唱を始める。
『水と氷を司るものよ。この手に氷の礫を繰り出す力を与えたまえ。氷礫:Ice Balls!』
さすが天才と言われるだけのことはある。1回の詠唱でその手が繰り出す氷礫の数はハンナの魔法の比ではなかった。20個近い氷礫が、2人の男をに襲い掛かり、その身体や頭を矢継ぎ早に強打する。氷礫に急襲された2人は、その場に伸びた。
「やるじゃねえか!じゃあ次は私の番だ。どうせこんな店、ぶっ壊しちまっていいだろ!」そう言うとウィザードは詠唱を始める。
『天候を司るものよ。水と氷を司るものとともにしてわが手に雲を成せ。空気を振動させ、風を巻き起こせよ。周囲を飲み込め!竜巻:Tornado!』
店内を大きな竜巻が駆け巡る。陳列棚はひっくり返り、商品は舞い上がる。その後、ガラガラと耳の裂けるようなけたたましい音を立ててそこら中に散らばった。その竜巻は、更に2人の悪党を捉える。彼らは竜巻に飲み込まれ、そのなかでもみくちゃにされながら、左右の壁に激しく打ち付けられて、そのまま動かなくなった。あと3人だ。用心棒をけしかけたその男は、最奥のカウンターに身を潜めている。
「私たちも負けてはいられないわね!一気に片付けてやるわ!」
『水と氷を司るものよ。その水を穢して毒を成さん。霧に変えて我が敵を蝕め。毒の霧:Poison Cloud!』
ウォーロックはその両手から濃緑の毒々しい霧を発生させ、残る三人の悪党どもを包み込んだ。男たちは、初めはその霧を払おうと手にした剣やらその他の武具を懸命に振り回していたが、次第にその動きは緩慢にになり、やがてもがき苦しみ始めた。毒が効いたようだ!なすすべなくその場に倒れ込んでいく。
「ざっとこんなものね。」ウォーロックがそういうが早いか、別の詠唱が始まる。
『現世に漂う哀れな霊の残滓よ。我と契約せよ。我が呼び声に応えるならばその彷徨える魂に仮初の影を与えん!魂魄召喚:Summon of Ghost(s)!』
詠唱を終えるとネクロマンサーは5,6体の霊魂を召喚し、店の最奥に身を潜めていたあのにやにや男にけしかけて取り囲み、ついに追い詰めた。
「くそう、役に立たねぇ野郎どもだ。」男は悔しそうに舌打ちしている。
4人は男に詰め寄った。
「さぁ、ありったけの『ケレンドゥスの毒』を出してもらうわよ。
「さっさとしやがれ、さもねぇと…。」
ウォーロックとウィザードが距離を詰める。
「なめやがって。これで終わりだと思うなよ。」
「なによ?これ以上、どうするっていうの?」
「へへ、こうするのさ!」
そういうと男は詠唱を始めた。
『呪われた者どもよ、わがもとに集え。その穢れた力を用いて我が敵を滅ぼせ!Summon of P.A.C.!』
大小様々の魔法陣が床に幾重にも描き出され、そのひとつひとつから全身黒づくめのおぞましい存在が姿を現した。

ウォーロックとネクロマンサーには、その異形の姿に見覚えがあった。信じられないのはその数で、ざっと30は下らないだろう。
4人は素早くそれらとの間に距離をとった。相手はいまやちょっとした軍団という様相を呈している。やられた!
「へへ、お嬢さん方。いかがなさいました?先ほどの威勢はどちらへ?」
男と異形がじりじりと近づいてくる。
「形勢逆転だな!」
確かにその通りだ、先の戦いでそれほどの魔力を消費したわけではないが、更にこれだけを一度に相手にするというのはどう考えても無理だ。しかも店内が無駄に広いため、効率よく逃げ出すということも難しい。そうこうにらみ合っているうちに4人はじわじわと店内の一角に追い詰められ、退路を断たれてしまった。万事休す。だれもがそう思って覚悟を決めた。
その時だった!
『水と氷を司る者よ。我は汝の敬虔な庇護者也。わが手に数多の剣を成せ。氷刃を中空に巡らせよ。汝にあだなす者に天誅を加えん!滅せよ。氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swords!』
まばゆい光に包まれ両手を掲げるソーサラーの周囲にはおびただしい数の氷の剣が形成されていた。その瞬間、それらの氷刃は雨のようにして異形の集団に降り注ぎ、瞬く間にそれらをすっかり切り刻んでしまった。そのただなかで、あのへらへらした店主と思しき男もまた、全身を切り裂かれて息絶えていた。

その場に、静けさが戻った。
「すげぇ…。」ウィザードはその茜色の瞳をこれ以上ないくらい大きく、丸くしている。ウォーロックとネクロマンサーも驚きを隠さない。
銀髪の天才はその身に発散魔力の残滓をまといながら静かにたたずんでいた。
「今のって、高等術式ですよね!」
「しかも、大規模集団攻撃魔法だわ。」
ウォーロックとネクロマンサーは顔を見合わせる。ウィザードはただポカンとしているだけだ。若干、初等科6年にして高等術式の大規模集団攻撃魔法を使いこなすとは、ソーサラーは評判以上の本物の天才であった。
「勘弁してくれ。」ウィザードがそうつぶやいた。
「あんたいったい何者なんだ。なんであんなのができんだよ!?」
「私のとっておきよ。今度あなたにも使ってあげるわ。」
すずしい顔で、しかし親しみのこもった声でソーサラーはそう笑った。
「いや、勘弁してくれ…。まじですげぇ天才だ…。」あの勝気がすっかり黙り込んでしまう。
いずれにしても、4人は危機を脱することができた。あまりの衝撃にしばらくぎこちない空気がその場に流れたが、しかしやがて4人は当初の目的を思い出す。
「『ケレンドゥスの毒』を持ち帰りましょう。」ウォーロックがみなを促した。
「そうですね。」ネクロマンサーも続く。
ウィザードの竜巻とソーサラーの氷刃によって店内はすっかりめちゃくちゃだったが、幸いにして『ケレンドゥスの毒』はすぐに見つかった。
「とりあえず、在るだけ全部持って帰りましょう。」
「そうですね。」
4人はあちこちに散らばったその毒の小包をあるだけ全部拾い集めて、一つの大きな荷物にまとめた。
「それじゃあ、とりあえずこのまま『アーカム』に向かいましょう。」
ウォーロックの提案にみな賛同し、その狂乱の法具屋を後にした。帰り方がよくわからなかったが、1度石段の左側をそのまま降りるだけで、気温は元に戻り、霧はすっかりはれていった。どうやら、完全に同じ逆順を辿る必要はなかったようである。
そのまま4人はマーチン通りまで移動して、そこからいつものようにマークスをたどって『アーカム』を目指した。
* * *
今日の扉は押し開けだった。そんなわけで、4人を少年アッキーナが出迎えてくれる。いつものアーカムのカウンター。

「おかえりなさい。首尾よく『ケレンドゥスの毒』は手に入ったようですね。」
その姿を初めて目にするウィザードとソーサラーのふたりは大いに混乱している。お決まりの場面だ。どういうことかをネクロマンサーがかいつまんでふたりに説明している。
「ええ、手に入ったわ。これよ。」
ウォーロックが荷物を開いて、その中の『ケレンドゥスの毒』をアッキーナに渡して見せた。
「確かにこれです。これがあれば治療薬を作れますよ。ちょっと待っててくださいね。とりあえずの分だけこれから作ってきます。あとは在庫を置いておきますから定期的にここに買いに来てください。」
そういうといつもの調子でカウンター裏の台所らしきところへいそいそと姿を消しっていった。しばらく時間がかかりそうなので、めいめい店内を散策することにした。ウィザードとソーサラーは興味津々である。ウォーロックは以前の経験を踏まえて、商品に触れるくらいはよいが、絶対に身に付けたり手に取ったりしないようにふたりにきつく忠告した。ここの商品はどれもそれくらい危険なのである。
30分もしたであろうか、それぞれがそれぞれの興味に任せて店内を見て回っていたところに、アッキーナがカウンターに姿を現した。
「お待たせですよ、っと。」
その声を聞いて4人もカウンターに集まる。
「これが治療薬です。朝昼晩、日に三回、欠かすことなく服用してください。最初は治療薬の方に副作用があって、不安が強くなったり、気分が悪くなったりすることがありますが、その症状は慣れればすぐにやみます。ですから、絶対に勝手に服用を中止しないでください。」
「ええ、わかったわ。」ソーサラーがその薬瓶を彼から受け取る。

「とにかく大事なのは、現在の自分を否定しないこと、将来の希望をもって治療に当たることです。実はこれが本当に難しくて、薬に限界があるというよりこれが出来なくて治療がうまくいかない場合が多いんです。きっとみなさんの助けが必要になると思いますよ。」
「わかってるよ。任せとけってんだ。」ウィザードが返事する。
ソーサラーも何か意を決したような表情をしている。
「ところで…。」ネクロマンサーが口を開いた。
「アッキーナ、P.A.C.という召喚魔法について聞いたことがありますか?」
「P.A.C.ですか。なるほど。みなさんがこれを手に入れたのは P.A.C.ストアだったわけですね?」
アッキーナはその店を知っているようだ。
「そこはある組織が裏金を稼ぎ出すために営業している『裏路地の法具屋』のチェーン店だということが最近分かりました。詳細は今調べてるところなんですが、どうやらそこそこ面倒な連中みたいです。まぁ、それでもお話を伺うに、どうやら今日その本店をみなさんが潰してくれたようなので、しばらくは静かにしているでしょう。僕もあの方も目を光らせておきます。それで、P.A.C.の召喚術についてですが、その術式で召喚されたモノを間近でみましたか?」
「それが…」
「こいつがすげえ魔法で跡形もなくずたずたにしちまったんで、ろくすっぽ見てねぇよ。」
「そうですか。ひとまず、ちょっと特殊なアンデッドの集団を召喚する術式ぐらいに思っていてください。これからもそれを使う連中がきっと現れるでしょう。」
「まじか!あんなのとしょっちゅう顔を合わすなんてごめんだぜ。」
ウィザードが今の自分ではどうにもできないというような面持ちで言う。
「私が召喚するアンデッドとは違うのですか?」
「そうですね…。」アッキーナが言葉を濁す。
「ちょっと訳あって今はお話しできないんですが、普通のアンデットとは違います。その証拠に水と氷の術式でも十分な効果があったでしょ?」
確かにそうだ。肉体を残している、残していないに関わらず、アンデッドは水と氷には強い。殲滅魔法でも殲滅しきれずに犠牲者がでることがあるくらいだ。しかし、今日の相手に、ソーサラーの水と氷の魔法は極めてよく効いた。
「とにかく、その術式で召喚される存在は、アンデッドではあるけれど、もう少し人間に近い異形の存在。そんな風に思っていてください。説明できる時がきたら話します。ところでみなさん、お茶でもいかがですか?」
「じゃあ、今日は『アインストンの血涙』がいいな。」ウォーロックが言う。
「私もそれで。」ネクロマンサーもリクエストする。
「よくわかんねぇから、あたしらにもおんなじ物を頼むぜ。」
「おねがいします。」
新参の二人もそれに決めたようだ。
「『アインストンの血涙』ですね。では少々お待ちください。」

「よっこらしょっ、と。」
お茶を載せたお盆を携えてアッキーナが奥から戻ってきた。
「お待たせしました。『アインストンの血涙』です。」
「へぇ~、きれいなお茶ね。見たことないわ。」
ソーサラーはじっとそのポットを見入っている。
4人とアッキーナは、しばしの時間、アーカムのカウンターを囲んで楽しく談笑した。時の流れを忘れるようなひと時であった。
その後、いつものようにコイルを逆順にたどってアカデミー前に戻った4人は、すぐにリズの部屋を訪れ、ハンナに薬を与えて、その夜はみなで彼女を見守った。
夜空は一層高く、天球上になって美しい星々をその身にまとっている。ときおり吹き抜ける風には初秋の色が明らかに濃くなってきた。暑さはまだまだ残るが、それでも秋は着実に近づいている。
いつまでも絶えない談笑の声が、晩夏と初秋を隔てる夜を彩っていた。
* * *
その後、ハンナは持病の悪化という名目でアカデミーの保健施設に入院することになった。その面倒はネクロマンサーと、何と驚くことにリズが見ている。リズはその役を自ら申し出た。ハンナは日々真面目に治療薬の飲用を続け、ずいぶん落ち着きを取り戻してきたようである。
* * *
さて、ところかわって今日は『全学魔法模擬戦大会』の当日である。
結局今年の6年生は、ソーサラー科もウィザード科もどちらも選手権を辞退した。そのため、目の前で繰り広げられるダイナミックな模擬戦の様子にスタンドから大きな声援を送っている。初等部や、中等部低学年の模擬戦は、フィールド上を歩いたり走ったりするだけだけだが、中等部高学年や高等部になるとそれはそれは派手な空中戦も展開され、ちょっとしたスペクタクルとなっている。特に高等部の高学年同士の空中戦は人気の見ものとなっており、それが繰り広げられるとスタンド全体がどっとどよめく。繰り出される術式も洗練され、その繰り出し方もより戦術的になり、見る者を飽きさせない戦いが繰り広げられていく。
そんな試合の行方を、ウィザードとソーサラーが、そしてリズとハンナが並んで熱く見守っている。
「まさか、あんたとこうして席を並べてこの大会を観戦することになるとは、思ってもみなかったぜ。」
「確かに、そうね。私たち、ずっと喧嘩ばっかりだったもの。」
「もうそれを言うなよ。悪かったよ。」
「ふふ、冗談よ。」
「それにしても、才能ってすげえな。初等部6年で、高等術式の大規模集団攻撃魔法とは恐れ入ったぜ。あんたにはかなわねぇ。」
「そんなこともないわよ。ウィザードのあなたがラファエルの術式を繰り出したときにはびっくりしたわ。自分の専攻科以外の領域を勉強するのなんて面倒だし、難しいし、普通はしないもんね。あなたが『努力の人』とみんなから呼ばれている意味がよくわかったわ。努力は可能性の外延を広げるのね!」
ウィザードとソーサラーが談笑している。その横ではリズとハンナが隣りあって、迫力ある高等部の模擬戦に熱い視線を注いでいた。ハンナの座っている脇には治療薬の薬瓶が置かれていた。今もきちんと服用を続けているようだ。その薬瓶は、治療を終えて新しい人生をしっかり歩みたいというハンナの強い決意を象徴するかのように、秋の陽の光の中で繊細な美しい輝きを、静かに、しかし確かに放っていた。
歓声と熱気は止むことがない。しかし、吹き抜ける風はすでに秋の色に染め上げられている。夏が終わりを告げる。新しい季節が始まっていく。
第3章
第1節『決戦!ウィーザード対ソーサラー』
あれからちょうど1年が過ぎた。
ハンナの回復は目覚ましく、かつてのような異常性を見せることはなくなって、すっかり落ち着きをとりもどした。むしろ、以前よりも素直になり、克己心を強めて他者への配慮を見せられる強さを獲得したようですらある。思わぬことに、今ではリズと親交をあたためるようになった。もちろんそこに、リズの献身と慈愛があることは言うまでもないが、ハンナもまた、自己の弱さと欠点、寂しさと劣等感を受け容れながら、しかし懸命に明日に向かっていこうとする強い決意を見せているのだろう。服薬はまだ続いているが、いつか彼女が、彼女らしい生き方を獲得する日は、決して遠くない。

幸いにも、みな、初等部の修了試験『魔術と魔法に関する一般教養試験』に合格し、中等部へと駒を進めることができた。学内では、ソーサラーが修了試験で1位を獲るであろうとの専らの評判であったが、主席を獲得したのは、ウィザードであった。彼女の懸命な努力は、徐々に、しかし確実に形を成してきているようである。ネクロマンサーもまた優秀な成績を収めて両科の過程を終えた。唯一、勉強嫌いのウォーロックだけは、教授の温情による追試によってかろうじて進級を得たが、彼女の名誉のためにも、その詳細は伏せておくべきなのかもしれない。
今日は、中等部として初めての『全学魔法模擬戦大会』の当日である。『学年別トーナメント』の準決勝において、ウィザードとソーサラーが、今あいまみえている。彼女たちは中等部1年にして、すでに空中戦を演じるようだ。両者ともに、反重力作用をもつ『虚空のローブ』をしっかりと着こなし、競技フィールドで試合開始の合図を待っていた。

* * *
「よう、ついにこの日が来たな!あたしらが当たるにゃ、カードが1枚早いけどよ。」ウィザードが不敵に笑う。
「そうね。まずはここで試験の借りを返させてもらうことにするわ。」
「さて、それはどうかな?今のあたしは一味違うぜ!」
「あらそう?私のとっておきを皆に披露する絶好の機会になるのかもね。」
「あれはもう見飽きて済んだ。」ウィザードが強気を見せる。
「言ってくれるわね。その続きは私に勝ってからよ。」負けないソーサラー。
ふたりの間に健全な緊張感が高まる。この1年でふたりは本当の意味での好敵手となった。特にウィザードの成長には目を見張るものがある。
「競技者準備!位置に付け!」
審判の声がこだまする。いよいよだ!
「学年別トーナメント、中等部1年、準決勝!1本勝負…。」
「はじめ!!!」
ついに火蓋が切って落とされた。
高度を変えながら、速度に巧みな緩急をつけてフィールドを旋回するウィーザード。ソーサラーは空中の1点で体を回転させながら彼女の動きを追っていく。
この競技大会の出場選手は、本当に魔法をぶつけ合うが、あくまで模擬戦であるため『競技採点の制服』をローブの下に身に付けている。それは、被弾した魔法を身体的ダメージから点数へと変換する魔法媒体で、それにより高等術式が直撃したような場合でも、選手自身が身体的損傷を負うことがないよう工夫されている(なお、『競技採点の制服』は双方が着用していなければ効果はない)。そのため、各出場選手たちは、互いに手加減をすることなく、全力でぶつかりあうことができる、文字通りの『模擬戦』なのだ。そして、先に相手に100ポイント分の損傷を与えた方が勝利を得る。
「どうくる?」
ソーサラーは身構える。ウィザードの力はほんの1年前とは比べ物にならないものだ。あらゆる領域の術式を身に付け、最近では錬金術もこなすようになったと聞く。旋回しながらなにかぶつぶつやっているようだが、そんなことは関係ない。模擬戦はスピードと手数、仕掛けてみるか!?
『水と氷を司る者よ。我が呼び声に応えよ。水流を圧して力と成せ。いまそれを解き放たん!加重水圧:Hydro Pressure!』
ソーサラーは高圧の水砲を、ちょうどその頭上に差し掛かったウィザードを待ち構えるようにして撃ち放った!
その軌道は見事で、狙い通りにウィザードに命中する!
やった!?…いや…違う!点が入らない、シールドだ!
ウィザードはただむやみに旋回運動を続けていただけではなく、的を小さくしながら、実に巧みに魔法障壁を周囲に展開してた。

ずいぶんやるようになったものね!
「へへ。」ウィザードが笑って見せる。
それを見守る場内がらひときわ大きな歓声を上がった。
それならば!
『火と光を司るものよ。水と氷を司るものとともになして、わが手に力を授けん。火と光に球体を成さしめて我が敵を撃ち落とさん!砲弾火球:Flaming Cannon Balls!』
詠唱と共にソーサラーは矢継ぎ早に複数個の大型の火球をウィザードに向かって繰り出した。その速度は非常に速い。さすが天才と言われるソーサラーだ。相反する属性の術式でもその力を十分に引き出している。
ウィザードは飛ぶ軌道を鋭く変えて回避行動をとるが、多角的に動く火球の方が巧みで速く、回避が間に合わない。そのうちの幾つかが命中した!今度こそ!…、!?、どういうことだ?やはり点が入らない!
ウィザードはなんと氷壁(火と光から身を守る障壁)をも同時に展開していた。すなわち、彼女の空中旋回には、対戦相手と距離をとりながら、属性の異なる障壁を二重に展開するという戦術的意味があったわけだ。

この魔法世界における魔法障壁は、どれもその障壁の属性と相反する属性の攻撃(及び物理的な干渉)は防ぐが、同じ属性の攻撃は貫通してしまう特性をもっている。ウィザードはソーサラーが火と光の領域の魔法を行使するであろうことを予め計算に入れていたのだ。
この私を読んでいたというの?あの子が!?ふふっ、見事ね!
さしものソーサラーも、そう何度もむやみに大技を繰り出したのでは、魔力が続かない。競技中の魔力枯渇は相手に100ポイントが入る。すなわち負けだ。
冷静なソーサラーは、ウィザードが空中を移動するその軌道を慎重に観察した。ふと、あることに気づく。
おかしい…。男子学徒側の観覧席の間近を通るときにだけウィザードは何かに気をとられているように見える。空中移動の制御に不自然さがあるのだ。なんだろう?さらに注意深く観察すると、そのタイミングでウィザードはスカートの裾をしきりに気にしていた。なるほど!そこでは例の名物教授が、光学魔術記録装置を手にうろうろしている。取り巻きたちも同様だ。そういうことか!相手の隙を突いて攻めることはもちろん考えたが、それでは面白くない。そう思って声をかける。
「ねぇ、そんなことを気にしながらじゃ、私には勝てないわよ!」
ウィザードを挑発する。
バレたか、という顔をするウィザード。
「うっせぇ、別にそんなんじゃねぇよ。」
スカートの裾をしっかり押さえて高速移動しながた、ウィザードが強がって見せた。
「大丈夫よ。誰もあんたのなんか見えたって喜びはしないから!いつまでもそんなことをしてるのなら、そろそろとどめを刺すわよ!」
このソーサラーには『氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swords 』という切り札がある。これは数多の氷の剣を一気に相手に向かって繰り出すという高等術式で、その数と威力が桁違いであるために、少々の障壁ではとても防ぎきれない。お互いにそのことは織り込み済みだ。
「うっせぇ、やれるものならやってみやがれ!」
どうやら雑念から解放されたようだ。それでいい。ここからが本番だ!ウィザードが下から上までまっすぐ、矢のような速さで移動してくる。しかし加速が単調で動きがまるわかりだ。今よ!
『閃光と雷を司りし者よ。我に力を!厚い雲を幾重にも積み上げよ。そこから光と稲妻を放ち我が敵を蹴散らさん。招雷:Lightning Volts!』
上空から無数の閃光と稲妻の束が、ウィザードを網にかけるように降り注ぐ。ウィザードは錐もみ状に旋回して回避を図るが、閃光と稲妻の数が多すぎる。そのうちのかなりの数がウィザードの身体をとらえて打った。ウィザードはひるみながら防御行動をとっている。決まった!
電光掲示板が青字(ソーサラー側)で40と表示する。
「ちきしょう、さすがだ!やりやがる。しかし!!」
そういうが早いか、ウィザードは間髪入れず隼のごとく一気に加速してソーサラーのすぐ側面に迫った。うそ!しまった!
「いただき!『衝撃波:Shock Wave!』」
衝撃波がソーサラーの脇腹に直撃する。彼女はようよう防御行動をとりながら、それでも体勢を立て直した。電光掲示板に30という字赤(ウィザード側)が灯る。接戦だ。
「やってくれるわね!」
「だから言ったろ。今のあたしは一味違うって。」
そう言いつつ、ウィザードの高速旋回が続く。今度はどこから来るの?ソーサラーにも若干の焦りが見える。ほんの一瞬その姿が視界から外れたその時だった。男子学徒側の観覧席の直上から、ウィザードが『竜巻:Tornado』の術式を放つ。ちょうどそのときの位置関係から、ソーサラーにとっては死角になっていた。なによ!?まずい!!
不意を突かれて回避行動がとれなかった彼女の身体は竜巻にもろにのまれ、帯電した激しい渦の中で、空気の荒波にもまれた。どうにか振りほどいて、再び体制を立て直すが、ダメージは大きい。奇襲を二度も成功させるとは、やるわね!
電光掲示板が赤字で80を灯す。
大歓声とともに、魔術記録装置の照明の瞳が矢継ぎ早に光を放った。
「へへ、あんたらしくないじゃないか。どうやら次で決まりだな。」
余裕を見せるウィザード。
肩で息をしながらもソーサラーは言う。
「どうかしらね?でも、ここで私にこれを使わせたことだけは褒めてあげるわ。終わりよ!」
『水と氷を司る者よ。我は汝の敬虔な庇護者也。わが手に数多の剣を成せ。氷刃を中空に巡らせよ。汝にあだなす者に天誅を加えん!滅せよ。氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swords!』
詠唱が終わるや否や、数えきれない数の氷の刃がウィザードめがけて降り注ぐ。急旋回と急加速を繰り返し、緩急をつけて飛ぶことで必死の回避行動を見せるが、あらゆる角度から矢継ぎ早に撃ち出されるその刃のすべてをかわすことは到底不可能であった。
「ちきしょう、やっぱかなわねぇ…。」
そのうちのいくつかは展開していた障壁が阻んだが、多勢に無勢、立て続けにふりかかる後続の無数の氷刃に障壁は打ち破られ、直撃を受けたウィザードはそのままフィールドに落下した。電光掲示板が青字で100を灯す。
「わあぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!!」
観客席からは大歓声が巻き起こり、魔術記録装置の照明の目が波のようなまばゆさを放って輝き煌めく。ソーサラーの逆転勝利だった。
「あの子が私にこれを使わせるなんてね…。」
少し悔しそうな、しかし、どこか満足そうな調子でソーサラーは呟いた。ウィザードはフィールド上で大の字になっている。
「やっぱ、天才はすげぇや。」その胸と肩は大きく上下していた。
「試合終了!100対80、勝者、ソーサラー科中等部1年代表!」
再び大歓声と光の目の輝きの波が訪れた後、スタジアムには進行を告げるアナウンスが鳴り響いた。
* * *
決勝戦までに、中等部2,3年生の準決勝その他の試合が入るため、少し時間があった。競技フィールドから引き揚げてきたふたりは、観覧席に手近な空席を見つけて、並んで腰を下ろした。
「やっぱ、あんたすげえよ。でも、あれは反則だぜ。」
「あらそう?でも言ったでしょ。褒めてあげるって。あなたは十分強いわ。」
「よせやい。」ウィザードは照れくさそうに鼻の下をぬぐった。
「急接近しての『衝撃波:Shock Wave』とは考えたわね。まんまとやられたわ。」
「だろ?自分でもいい線行ってたと思うぜ。初等術式は詠唱がほとんどいらねぇからな。いけると思ったんだ!あんたの『招雷:Lightning Volts』だってすげえぜ。水と氷以外のソーサラーなんてそうそういねぇ。」
「でしょ?」そういってふたりは笑った。
「そういえば、あなたでもあんなこと気にするのね?おっぴろげでも全然無頓着なのかと思ってたわ。」
「ばかいえ、あたしだって乙女だぞ。気にするさ。あんな馬鹿でけぇ『魔術記録装置』なんか持ってきやがって。気が気じゃねぇんだよ。なんだってんだ。」
「乙女!?乙女って言ったの!?だれ、だれのこと?」
ソーサラーがいたずらっぽく詰め寄る。
「あたしに決まってるだろ。こんな乙女そうそういねぇよ。」
「確かに。」思わず吹き出すソーサラー。
「なっ!?どういう意味だよ、それ?」
「あなたが言ったんじゃない。」

こうしてふたりは決勝戦の始まる少し前まで、眼前で繰り広げられる他学年の準決勝の行方などを見守りながら、しばし談笑した。
ほんの1年と少し前までは、このような光景を目にする時がくるとは思われなかった。例の出来事は苛烈をきわめたが、しかしそれは結果的には様々な人の縁を取り持つ契機ともなったのだった。
ウォーロック科のユリアという少女と対峙した決勝戦は、全く無難にソーサラーが勝利して、中等部1年の優勝を飾った。試験と大会、これで引き分けである。中等部の団体戦では、ハンナもチームに復帰し、それはそれは見ごたえのある戦いを披露した。しかしその準々決勝で、ソーサラー科のチームのメンバーのひとりが相手の術数にはまり、むやみに中等術式を連発したことで競技中に魔力枯渇を起こし、残念ながらそこで敗退となった。しかし、試合後、ハンナがその選手を責めることなどはなく、むしろ健やかな笑顔でチームメートの健闘をたたえていた。競技場から観覧席に移動してきたとき、そこには、例の解毒剤を持って彼女を迎えるリズがいて、昨年のことがまるで嘘のようであった。
* * *
ネクロマンサーは、看護科の救護班の方で大活躍しており、一日中忙しく救護・看護に奔走していた。熱中症や魔力枯渇はあとを絶たず、彼女たちもまた、この競技大会の裏方の主役としてその役割を存分に果たしていた。実のところ彼女が、看護科専攻の僧侶や聖女たちよりも、周囲の密かな人気を集めていることは公然の秘密となっていた。
余談であるが、初等部4年生の時、彼女が死霊科の制服を着て看護学部の講義に出たときは、それが闇市の翌日であったこともあって、様々な憶測を呼んだ。制服の再支給申請はしてみたそうであるが、結局、汚損品との引き換えでなければだめだというアカデミー側の主張は曲げられず、初等部卒業まで彼女はずっと死霊科の制服で看護科の授業に出る羽目になったそうだ。それゆえ彼女には『黒衣の天使』という二つ名がある。しかし、それもまた、今となっては懐かしい日々の思い出である。
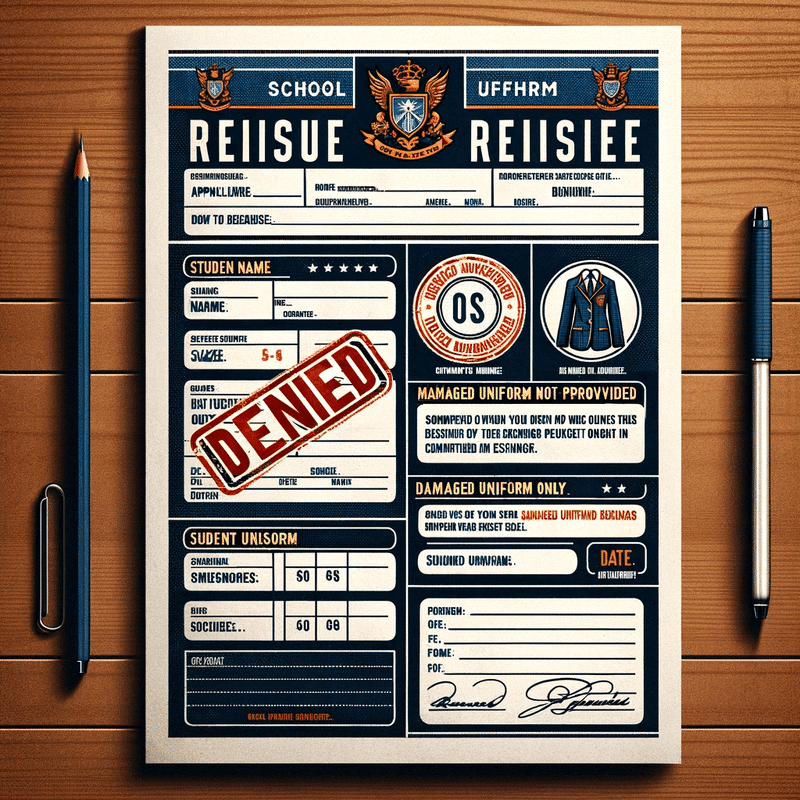
ただ、ここにウォーロックの姿はなかった。どうやら今年は大会参加をサボタージュしたらしい。もしかすると、今日も『アーカム』を訪ねているのかもしれない。このところ彼女は、かなりの時間を『アーカム』で過ごすようになっていた。
なお、彼女の進級試験について、少し詳細を明かしておくべきかもしれない。彼女は当初全くの無準備で試験に臨んでおり、知識を問う類の問題の出来は目を覆わんばかりであった。しかし、魔法学の理論と神秘の倫理に関する記述式問題の解答が、年齢不相応に極めて優れたものであったため、担当教授は彼女に追試の機会を与えたのであった。温情によって追試機会が与えれたというのは、実はレトリックにすぎない。追試についてはきちんと準備をして臨んだようで、その出来は実に満点に近く(一説には主席のウィザードより得点は高かったとも漏れ聞く)、彼女の進級会議では、その出来の良さに驚きを隠さないばかりか、絶賛する教授さえいたという。それほどの実力を秘めている彼女が、なぜ勉学とは違う方向に多くの関心を寄せるのか、果たして何がそれほどまでにその若い好奇心を捉えているのか、その時点ではまだ誰にもわからなかった。
9月の風がさわやかにアカデミーに吹き付ける。
少しずつ秋が深まっていく。
第2節『闇に蠢く影』
昨年の一件以来、4人は、休日などに誰かの部屋に集まって団らんの時を過ごすということをよく行うようになった。異国でいうところの女子会である。その集まりにはアカデミー嫌いのウォーロックも必ず参加し、他の3人と豊かに親交を温めていた。
今日は、ウィザードの部屋に集合して、さながらパジャマパーティの趣である。
「なぁ、よう。みんなはパンツについてどう思うよ?」
あまりに突飛な会話の振り出しに、3人は互いに顔を見合わせたが、すぐに年頃の少女らしく会話に花を咲かせた。
「やっぱり、かわいいのがいいんじゃない?」とウォーロック。
「私は、ロコット・アフュームのがいいと思います。」
「えー、ラヴィ・ムーンの方がかわいくない?」
「あそこのは、そのなんていうか、ちょっとデザインが美麗すぎて…。」
「それがいいんじゃん!」
ネクロマンサーとソーサラーが互いの好みを主張する。
知り合ったばかりのころのソーサラーはいかにも貴族のご令嬢という物言いであったし、今も必要な時にはその威厳を見せるが、気の置けないこの4人の集まりの中では年齢相応の率直さと愛らしさを見せるようになっていた。

「ちげぇよ。それじゃなくてパンツをどう思うか、って聞いてるんだ?」
3人はよくわからない顔をする。
「だから、パンツでしょ?」
「いや、それじゃなくて。ほら、あのいけ好かない学則を作った教授がいるじゃんか。そのパンツって野郎についてあたしは聞いてるんだよ!」
「ああ!」一同得心のいった顔をする。
「パンツェ・ロッティ教授のことね?」とソーサラー。
「そうだよ、だから最初からそう言ってるじゃねぇか!」
「あのね、教授の名前はパンツ・エロッティじゃなくて、パンツェ・ロッティよ。」諭すようにソーサラーがいう。
「そうなのか?」
「あなたって、あんなに勉強できるのに、とんだ天然よね。」
ウォーロックがころころと笑う。
「なんだよ、ちょっと間違っただけじゃねぇか…。」
「いずれにしてもだ、あいつちょっと異常じゃねえか?なんであんな絵にかいたような変態がアカデミーで教授やってんだよ。信じらんねぇ。」
3人は、それはもっとも、という顔をして見せた。
パンツェ・ロッティというのは魔法学の教授で、学内では知らぬもののない名物教授であり、迷物教授の二つ名をとるほどの有名人である。しかし、その地位は思う以上にずっと高く、政治力のあるハイ・マスターでありながら政府の高官でもあり、アカデミーではずいぶんと幅を利かせる実力者である。学内で彼に正面から苦言を呈することのできる者は限られていた。彼は、女学徒たちから極めて評判の悪い『学則8条6節』を策定した人物で、その条項とは「スカート丈はできるだけ短くあるべし。」というものである。それは、件の教授が前々回の『制服検討委員会』で強硬に主張したものがそのまま通ってしまったという代物で、男子学徒の評判こそ上々であるが、おかげで女学徒たちは身を守るのに気をつかわねばならず、常にスカートの裾の動向を心配する必要に迫られていた。その学則は、それくらいの丈の長さ、もとい短さをを要求してくるもので、一部ではその語呂に合わせて『エロ条項』とも揶揄されていた。

普段はともかくとして、大会で空中戦を披露する時などには、ひらひらちらちらとなにやかにやが見えてしまうため、男子学徒どもの好奇の目を前に、どうにも集中力をそがれて、気が気でなくなるのだ。先月の大会の折のウィザードとちょうど同じようにである。これは年頃の女学徒にとっては深刻な問題で、異性の目を引くのにせわしない向きはともかく、そうでない者にとっては実に胃の痛い問題であった。ウィザードもまたその一人である。特に最近では携帯式光学魔術記録装置が一般に普及したため、破廉恥な盗撮が後を絶たず、そうした魔術記録が神秘の雲などで不正に売買され、女学徒たちを大いに悩ませていた。ウィザードはそのことを言っていたのである。

「あの、なんだっけ、パンツェだったか?なんであんなスケベ野郎が魔法学の主任教授なんかやってんだよ。ありえねぇだろ。完全なセクハラだぜ。しかも大会の時なんて、取り巻きの男どもと一緒になってくそ大げさな光学魔術記録装置を持ち出してきたりしてよ。頭おかしいんじゃねぇかと思うんだ。あんなのを重用するアカデミーもアカデミーだぜ。」
ウィザードはずいぶんトサカにきているようだった。
「乙女だもんね。」
ソーサラーがこれ見よがしに茶化す。
「うっせぇよ!」
ウィザードはすっかりふくれて憮然としてしまった。
「まぁ、言ってることはよくわかるわね。」とウォーロック。
「これだけ多くの女学徒の要望と不満を無視するというのは確かに横暴だわ。いくら学則でも、学徒の安全と安心、そして女性の尊厳を尊重するべきよ。」
ウォーロックのその言葉は真剣みをおびていた。
「確かに、盗撮魔術記録の売買などもあるように聞きます。そんなのはちょっと許せないですよね。」
ネクロマンサーも同意した。
「なぁ、みんな!」
ウィザードが声を上げる。
「ここらでいっちょ、あのパンツ野郎に天誅を加えてやろうぜ!」
「といっても、どうするのよ?」ソーサラーがたずねた。
「あれだけ、盗撮魔術記録が出回ってるんだから、あいつはきっとそれをたくさん隠し持っているはずだ。だから、あいつの執務室に忍び込んで、証拠をばっちりつかみ、一発ぎゃふんといわせてやるんだよ!」
「威勢がいいのは結構だけど、バレたら退学ものよ!」
そんなことは到底無理という調子でソーサラーが言う。
「私もそれはちょっと無謀が過ぎると思います。別の手を考えては。例えば、署名を集めるとか…。」ネクロマンサーも慎重を示す。
「そんなかったりぃことやってたら、そのうちにあたしらのスカートの丈がなくなっちまうぜ。」ウィザードはエスカレートする。
「まぁ、ちょっと落ち着きなさいよ。」
そういってソーサラーが彼女をなだめていると、ウォーロックがすっくと立ちあがってこう言い放った。
「いえ、絶対やるべきよ!私は賛成だわ。こんな横暴を許していたんじゃ私たち学徒は委縮するばかりよ。理不尽な要求には断固抵抗すべきだわ!」
「わかってんじゃん!」ウィザードは手をたたく。
「でも…。」
ソーサラーとネクロマンサーは互いに顔を見合わせる。
「これは私たちの使命だわ!」
ウォーロックは悦に入り、それに向かってウィザードが声援を送っている。どうにも奇妙な構図だ。
「でも、やるといっても具体的な計画が必要よ。」
ソーサラーは慎重な姿勢を崩さない。
「第一、見張りをきっちりやる必要があるけど、たった4人じゃできることが知れているわ。」
「それなら大丈夫よ!」
ウォーロックはがぜん火がついてしまったようだ。自信に満ちた正義感ともつかないなにかを呈しはじめた。
「あなたが、魂魄召喚でゴースト召喚して、それに見張らせればいいわ。」
「私がやるんですか?」珍しくその黒い瞳が丸くなる。
「そうよ。あなた以外にいないもの。」
まるでそれが当然であるかのようにウォーロックはいう。ネクロマンサーはあっけにとられていた。
「話が早えじゃねえか。やつの部屋の場所はわかってるんだ。証拠さえつかめばあいつはぐうの音も出ねぇよ。やろうぜ。これはいわゆる人権問題、正義の戦いだ!」
どこかで聞いたようなもっともらしいことをウィザードがまくしたてる。
普段なら「はいはい」で終わるところだが、今回はウォーロックが妙に熱を帯びてしまっているのが始末が悪い。その後本当に計画を決行することが決まってしまい、『パンツェ・ロッティ天誅計画』なるお題目までできあがってしまった。
ネクロマンサーとソーサラーのふたりは、つきあいきれないという顔をしながらもふたりに調子を合わせている。結局にして、次の水曜日の深夜、すなわち件の教授が『アカデミー法石学会』に出席して留守をしているときを狙おうという手はずが整ってしまった。目的は彼が隠し持っているはずの破廉恥な魔術記録を回収すること、そう決まったのである。
その後は、具体的にどうする、ああするとまるでゲームでも楽しむような感覚でやり取りがずっと続いっていった。冗談半分、本気半分の奇妙なハーモニーはその夜、深夜遅くまで続いた。
時は全学魔法模擬戦大会からかれこれ1か月。この時間帯には秋虫が歌声をさかんに奏でる10月の半ばに差し掛かっていた。
秋の空は一層高く、天空にはこの季節ならではの星座が美しく輝いていた。空の輝きと地上のメロディーが秋の宵をそれはそれは美しく演出している。
人権と尊厳、自由と選択、幼かった彼女たちもそういうことを考える年齢に差し掛かっていた。はたしてその無謀とも思える計画はどのような顛末を迎えるのか。夜は静かに一層更けていく。
* * *
さて、今宵がその水曜深夜である。アカデミー全体がすっかり寝静まり、耳に届くのは秋虫の声だけとなった。その静寂の月明かりの下をこそこそと駆け回る一団がいた。
「本当にやるの?やっぱりやめない?」
ソーサラーが言う。
「ばっきゃろう。もう作戦は始まってんだ。ったく、貴族令嬢ってのは根性なしでいけねぇ。」
「まぁ!」
「静かにしてください!」ネクロマンサーがふたりを諫める。
パンツェ・ロッティ教授の私的執務室は教員棟の東側3階の角部屋にある。外から忍び込むには絶好の場所だ。見張り役はネクロマンサーとそのおともに駆り出されたかわいそうな数体の幽霊たち、連絡役はソーサラー、忍び込みを決行するのはウォーロックにウィザードと役割は決まっている。時は深夜をゆうに過ぎていた。

月明かりがその目的地たる角部屋をあかあかと照らしている。絶好のチャンスだ!
ネクロマンサーは召喚した幽霊たちに命じてあたりの警戒を怠りなく行っている。ソーサラーは連絡用の携帯式光学魔術記録装置を手になんとも落ち着かない様子だ。
「じゃあ、行ってくる!」
「お願いだから、へましないでよ。」
「任せとけって。」
「じゃあ、行きましょう。周囲のことは頼んだわよ。」
ウォーロックの号令で、ウィザードとふたり、3階のその部屋の窓まですっと上昇していった。大会の時と同じ虚空のローブを身にまとっている。案の定すべての窓は固く施錠されていたが、ウォーロックは余裕のようだ。
『錬金の力を司る者よ。我にその技巧を授けよ。閉ざされたものを開き、開かれたものを閉ざせ!不触の鍵:Invisible Keys!』。聞いたこともない術式を彼女は行使した。ウィザードはすっかり感心している。
窓の一つがカチャリと小さな音を立てた。ウォーロックがそれに手をかけると、窓がすっと開いた。
「やった!」ふたりは顔を見合わせる。下を見ると、厄介ごとに付き合わされたかわいそうな幽霊たちが、あちこちをふらふらを行きかっていた。携帯式光学魔術記録装置に着信を告げる明かりが点滅する。
「なんだよ?」
「どう、うまくいってるの?忍び込めそう?」
「あたしたちを誰だと思ってるんだ!ばっちりだぜ!」そう言ってウィザードは一方的に通信を切ってしまった。
「さぁ、ここからが本番よ!」
ふたりはその窓からそっと室内に入り込んだ。月明かりが十分にさしているとはいえ、さすがに室内は暗い。しかし明かりをつけるわけにもいかないため、ふたりは目を凝らしながら、室内を見て回る。次第に目が慣れてくる。ウォーロックは壁づたいに書棚やクローゼットを物色し、ウィザードはその執務机に近づいて行った。
「あったぜ!」ウォーロックを呼び寄せる。
「見つけたの?」
「ああ、こいつ隠してさえいねぇ。」

その目的物たる破廉恥な魔術記録はその執務机の上に乱雑に散らばっていた。その数は想像よりはるかに多く、100枚はゆうに下らないようだ。よくもまぁこれだけ集めたものだ。そこにはいろいろと映っていたが、明らかに盗撮の類だった。
「とりあえず、この状況を魔術記録に残して、あとは10枚くらい持っていきましょう。」
「そうだな。」
ウィザードは手持ちの携帯式光学魔術記録装置の照明の瞳の出力をぎりぎりに調整して執務机の現状をありありと魔術記録に収めた。
「これでいいだろう。」
「じゃあとは現物ね。できるだけ破廉恥なのを持っていくのよ。」
「うへぇ、いやな役回りだぜ。」
そういってふたりは十分な証拠能力があると思われる魔術記録を10枚ほど選定し、それをローブの内ポケットにしまった。
「それにしても、ここはあいつの執務室だろう?仕事中に何やってんだよ!」
「そりゃ、いろいろじゃない?」ウォーロックがいたずらっぽく言う。
月明かりの中でウィザードの顔が真っ赤になった。
「さぁ、行きましょう。」
そう言うとふたりは先ほどの窓からその部屋を抜け出た。魔術記録を失敬したので、侵入は遠からず露見するかもしれないが、足がつくようなへまはしていないはずだ。犯人の特定は無理だろう。そう思って、ウォーロックは先ほどと同じ魔法でその窓に鍵をした。ふたりがゆっくりと下に降りたその時だった。
「隠れてください!」
ネクロマンサーの小声が聞こえる。
「はやく、その茂みにでも。」
見ると2本向こうの通りを、『アカデミー治安維持部隊』に所属する学徒の一団が夜回りをしているのが見えた。とっさにふたりは茂みに身体を隠した。

「危なかったぜ。」
「そうね。」そういうウォーロックの表情は、これまで見たことのない嫌悪感をたたえていた。ウィザードは彼女がなぜそんな顔をしているのか気になったがあえて何も言わなかった。ただ、「犬め…。」彼女がそう呟くのが聞こえたような気がしていた。
しばしの間、一同の間には極度の緊張が走ったが、幸いにも夜回りの学徒達はそのままその2本向こうの通りを行き過ぎていった。やれやれ。めいめい胸をなでおろす。
「さあ、早くいきましょう!」ネクロマンサーの促しでその4人の女盗賊たちは秋の宵闇に溶け込むようにして消えていった。
秋の月はいよいよ明るさを増し、周囲の石畳を白く照らし出していた。ある10月中旬の深夜、彼女たちはちょっとした冒険を経験した。夜はなおも続いていく。朝まではまだまだ長い。
* * *
4人は今、『アーカム』にいる。
入り口は引き開きであった。また、めずらしく例の貴婦人が来店しており、幼いアッキーナがなにかと彼女の世話を焼いていた。
4人がアーカムを訪れたのは、これからどうするかについて、にわかに意見がまとまらなかったからである。ウィザードは、手にした証拠を突き付けて直談判すべきと強硬に主張したが、それは「盗人は我々でござい」とルビふって教えるようなもので、退学まっしぐらの無謀であった。
事ほどの次第を記した書面を添えて、アカデミーの掲示板に張り出してはどうかというのはソーサラーの提案であったが、その魔術記録には公共の掲示に耐えられる倫理性の欠片がもはや残されていなかった。魔法雑誌に事情を添えて送ってみたらどうかとネクロマンサーは提案したが、取り上げられなかった時には貴重な証拠をみすみす捨てることになるとして反対論が出た。
なにより肝心のウォーロックが、ウィザードの提案を強硬に支持するという有様で、議論噴出、議場騒然、どうにも意見がまとまらなかったため、今後どうすべきかを相談するためにここを訪れたのである。そこに例の貴婦人が居合わせたことは僥倖であった。
「お久しぶりです、マダム。」ウォーロックが話を切り出す。
「見ていただきたいものがありまして。」
「まぁ、何かしら?」
貴婦人の誘いを受けて、ウォーロックは例の魔術記録を取り出し、それらをカウンターにならべてみせた。
「まぁ!またずいぶんと面白い魔術記録ね。これはどうしたの?」
「はい、アカデミーのある教授の執務室から取ってきました。」
「あらあら、それは大胆ね。で、どうしようというのかしら?ここで売ればいいお金にはなるわよ。」貴婦人は目元を細めた。
「それが問題なんです!」少し語気を荒げてウォーロックが言う。
「こんなことが今、アカデミー内では横行しています。盗撮なのは明白で、この破廉恥さは明らかに女学徒に対する侮辱です。なによりこれを可能にしている学則が許せません。」
「そうね。あなたの気持ちはわかっているわ。ごめんなさいね。ちょっとした冗談よ。落ち着きなさいな。」そう言うと貴婦人はそのうちの1枚を手に取った。
「たしかに、ずいぶんとひどいわね。十分に立派な人権侵害だわ。」
「そうですよね!」
貴婦人の賛同を得られてウォーロックの声が上ずる。
「これらの証拠を使って事態を改善する方法はないでしょうか?」
「そうね…。」
手元のお茶のカップを一口傾けてから、貴婦人が続けた。
「私の友人に、『魔法社会における人権向上委員会』の理事を務めている方がいます。」
『魔法社会における人権向上委員会』とはおよそ魔法社会全般の人権問題、とりわけ子どもや女性、社会的弱者の権利向上を訴える、政府に対しても影響力のある有力な任意団体だ。確か、『キュリオス骨董堂』の店主である、キューラリオン・エバンデス女史がその座長を務めていたはずである。彼女のパンツェ・ロッティ嫌いは魔法社会でも広く知られており、魔法雑誌の対談などを通じて、公然と彼を非難する数少ない人物のひとりだ。もしかしたら…、そんな期待が4人の胸中をめぐった。
「とにかく、これを私に預けませんか?委員会経由で告発をしてもらえないか働きかけてみましょう。」
「はい、ぜひお願いします!」ウォーロックが力強く言った。
ほかの三人も貴婦人の提案に異論はないようだ。
「それでは、お預かりするわね。アッキーナ、これを大切にしまってちょうだい。」
「はい、マダム。」
そう言うと幼いアッキーナは小さな手でカウンター上の魔術記録を拾い集めた。とんとんとみみをそろえ、封筒に入れてからカウンター裏に置かれた皮のカバンの中にしまった。
「少し待ってて頂戴ね。きっと朗報を届けるわ。」
貴婦人の目元が優しく緩む。
「ありがとうございます。」
4人の盗人の顔に安堵の色が浮かんだ。
「さて、それじゃあお茶にしましょう。アッキーナ、『ルクスの緑』をいれてちょうだいな。」
「はい、マダム。」いつものようにいそいそと奥の台所に消えていく。
「あなたたちも大変ね。でも、これはきっといいことだわ。時には禁を破ってでも悪をただすということは必要になるものよ。」貴婦人はそう言って視線を手元のカップに移した。
しばらくして、両手にお盆を抱えたアッキーナが戻ってきた。
「お待たせしました。『ルクスの緑』です。マダム、こちらはおさげします。」
そういって、その幼い少女はヒスイ色の美しいお茶をめいめいにふるまってくれた。マダムが先ほどまで口にしていたカップをお盆に乗せて、その小さな影はふたたび台所へと姿を消した。
「さぁ、召し上がれ。」
「頂戴します。」
4人はめいめいにカップを手にし、その神秘的なお茶を口に含んだ。

「このお茶には飲む人の精神に魔法的に作用して、その冒険心を喚起し、正義感を強める作用があるのよ。また、何が正しく、何が間違いであるか、それを見極める感性を研ぎ澄ませるわ。今では忘れられたそんな古いお茶…。」
貴婦人はお茶の薬効を説明した。
ひとくちふたくちそのお茶を口に含んだ後、彼女は立ち上がって、4人に告げた。
「ごめんなさいね。あなた方とゆっくりお茶を楽しみたいところだけれど、今日はこれから行かないといけないところがあるの。お先に失礼するわね。」
そういうと先ほどアッキーナが例の魔術記録をしまった皮のカバンを手に取って、奥の闇に消えていった。4人はそれを静かに見送った。
その後しばし談笑していると、そこにアッキーナが戻ってきた。
「ごめんなさい。そろそろ閉店の時間なんです。」
「まぁ、ごめんなさい。」ウォーロックがアッキーナを気遣う。
「アッキーナ、いつもいろいろありがとう。」
それを聞いて幼子はちょっと照れくさそうにその小さな頭をふるふると横に振った。
「お帰りはお分かりですか?」
「コイルを逆順に!」今やその声は四重奏をかなでていた。
マークスを反対にたどり、4人が日常のアカデミー前に戻った時には、秋の日はもうすっかり落ちて、ひんやりとした夜の闇が彼女たちを取り囲んでいた。
「とにかく、彼女を信じて待ちましょう。」
ウォーロックのその声に、3人は大きくうなづく。
「きっとうまくいくさ。」
そういうウィザードの手をソーサラーがとった。
「では、みなさん。また明日。」
ネクロマンサーが別れの挨拶をする。
「また明日。」
そういって4人はめいめいの寮棟へと戻っていった。
深まる秋の装いを告げるひんやりとした乾いた風が心地よい。きっとうまくいくはずだ。秋の空は一層高く、星々と星座の色どりは日々美しさを増していた。かすかに、冬の気配も感じられる。少しずつ11月が近づいていた。
第3節『告発と弁明』
4人がアーカムを訪れ、貴婦人に例の件を依頼してからおよそ2週間を経た11月初旬のある日のことである。アカデミー内は俄かに騒然としていた。『魔法社会における人権向上委員会』の主席理事、キューラリオン・エバンデス女史から、パンツェ・ロッティ教授の行状に対する告発文が直々かつ正式にアカデミーに届けられたのである。もちろんその事実を一般の教職員や学徒が直ちに把握できるわけではなかったが、魔法社会一般において大衆にもっとも強い影響力を持つ週刊誌のひとつ『ウィークリー・ソーサリー・スプリングス』が11月第1週号のカバーストーリーとして、その告発文の全文と、問題の破廉恥な魔術記録をつぶさにスクープ掲載したことから、学内は上へ下への大騒ぎとなった。
「あの教授、前々から胡散臭いと思ってたけど、こんなことやってたのね!」
「許せないわ、こんな魔術記録を盗撮して販売するなんて!」
「最高評議員のお父様に言いつけて解任してやるんだから!」
女学徒たちが口々に怒りをあらわにする一方で、
「いや、これにはきっと何か理由があるんだよ。」
「教授は高等術式使用後の残留魔力の発散について研究しておられたから、きっとその一環だと思うな。」
「とにかく、週刊誌の記事をいちいち真に受けちゃだめだよ。」
男子学徒の反応は実に対照的で、パンツェ・ロッティに同情的だった。それは、自分たちの楽しみがこれで潰えてしまうかもしれないことを内心おそれているかのようですらあった。
「なによ、あんたたち!私たち女学徒の人権を軽んじるつもりなの!?」
「これだから男ってやぁよ。どいつもこいつもいやらしいんだから。もぅ、ちょっとどこ見てるのよ!?」
「いや、別に僕たちにそんなつもりはないんだよ。ただ、あくまでも一週刊誌の報道であって、事実確認はできていないんだから、不必要に騒いじゃいけないと、ただそう言っているだけなんだ。女性の人権を尊重するのは、当然のことだろ?」
「ふん、どうだか。あんたがこれに一切関与がない証拠なんてどこにもないんだから。」
「そんな、いくら何でもそれは飛躍だよ。」
女性と男性の、とりわけ男という生き物の悲しい性がつぶさに現れていた。4人は、そんな男子学徒の見苦しさに辟易しながらも、貴婦人が手際よくこの事態を手引きしてくれたことにひそかに感謝してた。
この告発と衝撃的な魔術記録のスクープをめぐるさまざまなやりとりが、ゲート、エントランス、ホール、教室に始まり、教務員室の中に至るまで、アカデミー全体をすっかり覆ってしまっていた。キューラリオン女史のその告発は実に厳しく、また添えられた魔術記録は非常に生々しいもので、その説得力は十分すぎるほどであった。これほど学内が騒然とすることは、めったにない。それくらいに、この告発文に関する雑誌スクープは大きな影響力を行使したのであった。以下がその全文である。
* * *

パンツェ・ロッティ教授に対する告発文
創世年紀2315年10月28日
魔法アカデミー総務部倫理科綱紀委員会 御中
拝啓
私たち魔法社会における人権向上委員会はその独自の調査の結果、貴魔法アカデミーの魔法学部長であるパンツェ・ロッティ教授の不適切かつ破廉恥極まる人権軽視行為を発見し、それに深刻な懸念を抱いております。教授の行動は、アカデミーの倫理規定、さらにはこの神聖なる魔法社会全体の倫理規範に著しく反しており、即刻の調査を要するものです。
私たちの懸念は、以下の証拠に基づいています:
第一号証:
教授の執務室の執務机の机上の状態を示す魔術記録。これは教授の職務上の不適切かつ非倫理的な行為をつぶさに証明するものです。第二号証の1~13:
極秘に入手したパンツェ・ロッティ教授自身によって撮影された魔術記録群の一部。これらは、当該教授が破廉恥極まる盗撮行為に直接関与していたことを明らかにするものであり、同時に、同教授がその密売に関与していたことを示唆する証拠であって、同教授の行為の悪質性および非倫理性を明確に示しています。
これらの証拠は、パンツェ・ロッティ教授が、女学徒の、下着を着用した下腹部及び臀部を不正かつ破廉恥な個人的目的において観察し、剰え、それを不道徳極まる魔術記録に収めた事実を総合的に明らかにするもので、同教授が、学内規定および一般的な魔法社会の崇高なる倫理観に違背する行動を取ったことを明示しています。また、それを学内において制度的かつ合法的に可能ならしめるために、貴学学則第8条第6節を不正に創設したことを強く推認させるものです。このような行為は、アカデミーの信頼と尊厳を著しく損なうものであり、学徒及び職員の安全と福祉に対する重大な脅威となっています。なにより、女学徒について最大限尊重されるべき人権への重大な挑戦であります。
したがって、私たちは貴アカデミーの綱紀委員会および関連各部局に対し、パンツェ・ロッティ教授の当該行為に関する即時の調査を求めます。また、適切な対応と処置を講じるよう強く要請いたします。
教授の当該行為がアカデミーの価値観と規範に反するものであることを踏まえ、この問題に対する迅速かつ公正な、そして賢明なご判断と対応がなされることを期待しております。
敬具
魔法社会における人権向上委員会
代表理事 キューラリオン・エバンデス
* * *
こうした話題が社会を駆け巡るスピードというは、えてして光よりも早いものである。各魔法誌の出版社や魔法報道局の記者・特派員がアカデミー・ゲートを取り囲むまでいくばくも時間はかからなかった。
ゲートでは広報担当者が顔中にあふれんばかりの汗をふきふき、しどろもどろに対応に当たっている。アカデミー最高評議会への出席も許される高位の学術位階の持ち主の、しかも世間の耳目がいかにも好みそうな類の一大スキャンダルである。さらに彼はアカデミーと政府を架橋する政府高官でもあり、おおあわを食ったのは最高評議会を頂点とするアカデミーの管理層で、彼らは直ちにパンツェ・ロッティ教授を召喚して、2日のうちに公式の弁明書を作成の上綱紀委員会に提出することを厳命したのであった。
一体全体何が起こっているのか把握しきれない当の教授には、ただ唯々諾々とその命に従う以外に選択肢はなかった。綱紀委員会の姿勢は、口頭での弁明の機会賦与は、書面での弁明を経てからでなければ一切許さないという異例の厳しさであり、退路を断たれたパンツェ・ロッティ教授が急遽したためたのが、以下の弁明書である。全文を紹介しよう。

パンツェ・ロッティ教授の弁明書
創世年紀2315年11月3日
魔法アカデミー総務部倫理科綱紀委員会 御中
謹啓
この度行われた魔法社会における人権向上委員会の代表理事、キューラリオン・エバンデス女史による小職の不正を糾弾せんとする趣旨の告発文について、小職は怒りと悲しみをもってそのすべてが事実無根であることを以下の通り弁明いたします。
キューラリオン女史は、小職の執務室の執務机上に破廉恥極まる魔術記録が存在したとして、それが、小職の私的な嗜好と私欲によるものであると、大天使をも恐れぬ悪辣な筆致をもって指摘しております。すなわち、小職が、女学徒の、下着を着用した下腹部ないし臀部を私的に観察し、剰えそれらを捉えた魔術記録を金銭目的で売買するために作成・所持しておること、また学内においてそれを可能ならしめるために当アカデミーの学則第8条第6節を不正の目的をもって制定したのであることがその告発の要旨でありますが、それは全くの事実誤認・事実無根であると宣言いたします。
綱紀委員会の一部にもご存じの方がいらっしゃるように、小職は中等術式および高等術式行使後の残留魔力の発散について真摯な研究を重ねているところでございます。周知のとおり、一度期の魔力消費量の多い術式を行使した後には残留魔力が詠唱者の身体から発散されますが、それは極めて強い魔法的作用と魔法的熱量をもつため、詠唱者の身体の安全を保護するために、その発散を速やかに促す魔法実践学的必要があるのであります。
残留魔力が胸部、下腹部、臀部といった体幹部に留まりやすいことは、魔法実践学におけるいわば学術的常識でありまして、確かに、女史が証拠として指摘するような魔術記録が、小職の執務机上に存在するのは事実ですが、小職はいかにすれば、例えば制服およびローブをいかなるデザインのものに変更すれば、残留魔力の発散と鬱熱の解消を迅速にできるかを、純粋に学術的に研究するための資料としてそれらを蒐集していたのに過ぎず、女史の指摘する「不正かつ破廉恥な個人的目的において観察」するという指摘は全く当たらぬものであると、宣誓する次第であります。高度な術式を日常的に行使する女学徒たちの身体の健康に配慮し、そのために研究成果を応用することは我ら聖職たる教員の尊い責務でございますから、本学学則8条6節には、魔法実践学的根拠が厳然と存在するのであります。
また、続いて指摘されております、それら魔術記録を金銭目的で転売するなどということは、およそ小職の良識の埒外のことでありまして、いうなれば何をおっしゃっておられるのか直ちには了知できないというのが正直なところでございます。
繰り返しになりますが、小職による当該魔術記録の所持と保管は、純粋な学術的目的によるものでありまして、そのひとつの証左として、小職はその魔術記録を隠蔽・秘匿などせず、現在もなお机上に資料として設置・陳列しておるところでございます。
加えて申し上げれば、女史はアカデミー在籍の折から小職を何かと目の敵にしており、その事実をご存じの委員の方もいらっしゃると存じますが、今回のことも、女史による小職へのいわれなき糾弾と、小職の神聖な研究に対する妨害であると指摘せざるをえません。
従いまして、これらの事情と小職の弁明をよくご斟酌の上、適切至当なご判断をいただけますよう、伏してお願い申し上げる次第でございます。
敬白頓首
魔法アカデミー魔法学部長兼最高評議会非常任評議員
教授 パンツェ・ロッティ
* * *
これらの告発文と弁明書の内容は、アカデミーの公平公正な情報公開の取り組みの一環として学内の掲示板各所に掲示された。さすがに、証拠となる魔術記録は破廉恥の具合が度を越しているために、ともに掲示されることはなかったが、大部分の者が『ウィークリー・ソーサリー・スプリングス』の記事によってその内容を了知していた。
学内および魔法社会では、あまりにも明々白々な証拠がそろっている以上、綱紀委員会は当然にキューラリオン・エバンデスの告発を認容して、パンツェ・ロッティ教授の弁明書を棄却し、近いうちに同教授は失脚するであろうというのが大方の見通しであった。次期魔法学部長や魔法学部教授の地位をねらう者らが、その空席を獲得するための準備に水面下で実際に着手しことは、言うに及ばぬであろう。
ところがである。
11月5日に開かれた総務部倫理科の綱紀委員会の結論はそれと真逆のものであった。すなわち、キューラリオン・エバンデスの告発文こそが客観的直接証拠能力を欠くものとして棄却され、パンツェ・ロッティ教授の弁明書が認容されたのである。これは魔法社会全体と学内にひっくり返るような驚きをもたらしたが、しかし冷静に思い返してみれば、パンツェ・ロッティ教授がその若さで、しかもアーク・マスターでなくハイ・マスターでありながら、非常任評議員としてアカデミー最高評議会への出席を許されているのは、実は最高評議会議長の個人的な特別の取り計らいがあったからというのはもっぱらの噂であって、それが事実であるならば、今回の意外極まるこの裁決もまた、急に生臭い納得感を帯び始めるのであった。権力というものが、常に正しく使われるの保障はないということを多くの者たちに再認識させたという点では、この一件には一定の意味があったのかもしれないが、天誅を下せると期待に胸を膨らませていた4人は、すっかり臍を噛む格好となったのであった。
アカデミーの火消しは思う以上に迅速かつ適切で、この一件はあっという間に世間の関心の外に置かれるようになった。あの魔術記録を持っているだけでも不潔で破廉恥だと粘り強く声を上げ続ける女学徒たちもいるにはいたが、新しい社会的関心の前に、その声はいよいよかき消されていった。
* * *
それから10日ほどが過ぎ、11月の中ほどに差し掛かった秋雨の日に、突然にして、パンツェ・ロッティ教授から例の4人に対して公式な呼び出しがかかったのである。
それは、教員執務棟東側3階の角にある例の場所であった。
「諸君がここに来るのは何度目かね?」
「ドアから入るのは初めてです。」ウォーロックが皮肉をきかせる。
あの月夜の一件が露見しているのは明らかだった。しかし、どうやってたどり着いたのか?もしかして寮の各部屋に盗聴用の魔術記録装置でも仕掛けているのではあるまいか?その可能性が皆無ではないだけに一列に並ばされた4人は俄かに背中に寒いものを感じていた。
「今の回答には英知の煌めきを感じないではないが、しかし、どうも最近の学生は、短慮かつ目上を侮りがちでいかん。」
パンツェ・ロッティ教授は続ける。
「しかしだ、私という人間は極めて聡明かつ寛容であるからして、単に諸君らを罰してここから追い出す以上のよい解決策を心得ている。幸いにして諸君らの行状を知るのは現時点では私だけである。すなわち、私の提案と指導に従い、その罪の禊をすることこそが、最も賢明かつ最良の選択であるということは、今年の中等部1年を代表する天才と秀才からなる諸君らであればよくわかるところであろう。」
なんとも嫌味な言い方である。
「したがって、私は諸君らに一つの使命を託したい。名目上全く別の理由により、諸君ら4人はこれから2週間謹慎処分とする。」
どういうことだ?4人は顔を見合わせる。
「その間に諸君たちには、ある調査にあたってもらいたい。私がこれから課す任務を2週間きちんとやりおおしたならば、特別の温情をもって、今回の諸君らの華麗なる女盗賊の行状は不問に付そう。もちろん、名目上の謹慎処分についても、私からの特命を受けた公的なものであったとして、諸君らの高等部進級に影響が出るどころか、むしろプラスになるように取り計らうことを約束する。どうだね?私のこの申し出を受けるか、退学するか、今ここで選びたまえ!」
「お話、よくわかりました教授。」
ウォーロックが口を開く。
「それで、おっしゃるその特命とは具体的にどのようなことかお聞かせください。」
「うむ、極めて聡明かつ適切な判断でよろしい。他の者も異論はないかね?」
残る三人もうなづいた。
「私としても君のお父様を悲しませるようなことはしたくないのだよ。わかってくれて安堵した。」
ソーサラーに流し目を送ったあとで、さらに教授は続けた。
「それではこれから任務の内容を説明する。」
「実は昨今、諸君らも聞いたことがあるだろう、『裏路地の法具屋』がこの魔法社会では深刻な問題となっている。そこで販売される違法品、特に違法薬物の学内持ち込みが近時深刻化しており、我々聖職者としては見過ごすわけにはいかん事態となっている。」
「だれが聖職者だよ…。」ウィザードが小声でつぶやく。
「何かね!」それを糺す教授。
「いえ、なんでもありません。」ウィザードは姿勢を正して見せた。
「よろしい、私からの特命というのはその『裏路地の法具屋』への潜入捜査である。そこに向かい、通い、交流して二週間のうちにできるだけ多くの情報を集めてきてもらいたい。そして手に入った情報はどんな些細なことでもあますことなくつぶさにこの私に報告せよ。それが諸君らへの特命である。」
「それで、その『裏路地の法具屋』にはどのようにしていけばよいのですか?」
ソーサラーが問うた。
「賢明な質問だ。いいかね。しっかり記憶にとどめたまえ。」
そういうと教授は例の執務室の机の上にこの街の地図を広げた。相変わらずその執務机の上には破廉恥な魔術記録が散乱していた。
「『サンフレッチェ大橋』を『マーチン通り』側から、次に示す順で渡りたまえ。すなわち、欄干のガーゴイル像までは右端を、そこから鳳凰像までは左端を、そしてその先は渡りきるまで橋の真ん中をまっすぐ進むのだ。よいかね?ガーゴイルまで右、鳳凰まで左、そこから中央をまっすぐだ。難しい暗号ではない。よろしいか?」
「わかりました。」
4人は返事をする。
「結構。報告は3日に一度、書面で提出することとする。報告書の提出が遅れるたびにペナルティを課すからそのつもりで真剣に任務にあたりたまえ。見たこと、聞いたこと、知ったこと、なんでもよい。つぶさに報告するのだ。なお、これは第一級の極秘事項とする。他言はすなわち懲罰の対象となる。わかったかね?」
「はい、わかりました。教授。」4人は声をそろえる。
「よろしい、では本日は以上だ。仮初の謹慎処分についてはすでに寮母に伝えてあるから、これから各々の寮に直帰して必要な準備を進めたまえ。遅くとも明日朝にはその店と何らかの接触をしてもらわねばならない。そのためにも本日午後の講義から謹慎扱いとする。以上だ。解散!」
そういうと教授はさっさと出て行けというふうにして4人を私室から追い出した。
寮に向かう道すがら4人はしきりに言葉を交わした。
「本当にやるのかよ。パンツの命令なんてまっぴらだぜ。」
「私たちに選択権はないわよ。それとも野良魔術師にでもなる?」
ソーサラーの言葉に、つまらないという表情を返すウィザード。
「『裏路地の法具屋』を探れなんて、パンツェ・ロッティ教授ってどんな方のかしら…?よくわかりません。」ネクロマンサーは怪訝そうな表情を浮かべている。
「こういうやり方って好きじゃないけど、自ら破滅を選ぶことは選択ではないわ。とにかく彼の言うとおりにやりましょう。」
ウォーロックは意を決したようだ。
「そうですね、どのみち私たちに選ぶことはできませんから。」
ネクロマンサーも同調する。
「なんにせよ、準備だけはしっかりしていきましょうね。」とソーサラー。
「でもよう、2週間にわたって接触って、具体的にはどうするんだ?4人連れ立って毎日お客でござい、って顔で通うのか?不自然だぜ。」
ウィザードのその指摘はもっともだった。
「アルバイトね。」ウォーロックが言う。
「それはいいかも!」賛同するソーサラー。
「とりあえず、これから私たちはアカデミーを追われた『野良魔術師』ということにして、当座の生活に困っているから働きたいと頼み込んでみることにしましょう。」ウォーロックが具体的に提案する。
「でもよう、一気に4人だぜ。難しいんじゃねぇか?」
「その時は乙女の色仕掛けに期待するしかないわね。」
「勘弁してくれよ…。」
ウィザードとソーサラーがそんな掛け合いをする。
「とにかくやる以外にないもの。最善を尽くしましょう。」
そのウォーロックの言葉に、みなの意思は固まったようである。
「それじゃあ明日の朝7時にゲート前で落ち合いましょう。くれぐれも準備を怠らないように。少々大荷物になっても、その方がむしろ『野良魔術師』感が出ていいわ。」
「そうですね。」ネクロマンサーがウォーロックに応じる。
「じゃあ、明日朝ね。」
ソーサラーのその一言をきっかけに4人はめいめいの寮室へと帰っていた。
外には冷たい秋雨がしとしとと降り続いている。11月もこの時期になるとずいぶん冷たい。晩秋を超えて冬の足音が静かに聞こえてくる、そんな昼時のひと時であった。
* * *
ところかわって、『アーカム』。
カウンターに腰かけ、未知のお茶のカップを傾ける例の貴婦人の世話を幼いアッキーナが焼いていた。ふたりが言葉を交わす。
「パンツェ・ロッティ、思ったより手ごわいですね。」
「そうね、彼はああ見えて馬鹿じゃないから…。」
貴婦人と件の教授は旧知なのだろうか?
「その実優れている面は多いのよ。見かけとは裏腹にね。賢くもあり、狡猾でもある…。でもあの性格、昔からどうにも好きになれないわ。まぁ、今回は私の負けということにしておきましょう。」
「よろしいのですか?」
「時にはこういうこともあるわ、アッキーナ。人生なんてそんなものよ。」
「はい。」
貴婦人は静かにまたカップを傾ける。
「それにしても、彼女たちを彼の指定する『裏路地の法具屋』に行かせて本当に大丈夫でしょうか?」
「そうね。確かに彼の目的は気がかりだけど、彼女たち自身で今起こっていることを見知るいい機会になるかもしれないわ。」
そういうと、貴婦人は少し遠い目でアーカム店内の神秘の中空を眺めた。
「危険はありませんか?」
「あの子たちですもの。きっと乗り越えてくれると信じているわ。」
「はい。」
「ところで、アッキーナ。」
台所へ行こうとする幼子を優しく呼び止める。
「はい、マダム。」
「戸棚にしまった例のものはまだ持っているの?」
「お小遣いにしました…。」
「まぁ、悪い子ね。その歳からそんなことを覚えてはだめよ。」
「はい。」
神秘の光に包まれたアーカムの店内を不思議な優しさが覆っていた。まもなく夜明けを迎える、そんな時刻のことであった。
彼女たちの朝は早い。
第4節『奮闘!裏路地の魔法具店』
翌朝7時少し前。
昨日の雨とはうってかわって、美しい秋晴れの一日となった。明け方までは雨が降り続いていたのだろう、あちこにできた水たまりには、高く抜けるような青空が映っている。石畳から蒸発する水の香りが感じられる。
昨日の約束通り、教授からの密命を実行すべく、仮初の謹慎処分を迎えることになった4人の魔法使いは、ゲート前に集合していた。めいめいそれなりの荷物を抱えており、さながら学園を追われる『野良魔術師』の小集団といったいでたちである。
野良魔術師とは、アカデミーの過程を途中でドロップアウトした者のことで、特に低学年時に他科の学徒との実力差を見せつけられるウィザードにそうなる者が多いことから、魔法社会では一般に、野良魔法使いではなく、野良魔術師と呼ばれている。しかし、野良になるのはなにもウィザードに限ったことではなく、様々な事情を抱えてそこに身を落とすものは存外多い。魔法の勉学と教練を途中で放棄しているため、実力が十分でない場合が多く、就ける職が限られるため、魔術・魔法を使う大道芸の一座に属したり(といってもたいていはその一座の下手間くらいしかできない)、見世物小屋で働いたりすることが多いようだ。その収入は一般に不安定で、生活は決して楽なものではない。また、場合によっては、盗賊や、それこそ『裏路地の法具屋』の店員など、非合法な世界に身を沈めざるをえない者たちもいる。
一方で、同じアカデミーの落伍者でも、本物の実力を身に着け、自らの意思でアカデミーを抜け、魔法社会で暗躍することを選ぶ者もいる。そうした者たちの多くは、在学中、不正にアカデミーの禁忌にアクセスしており、不相応な位階において禁忌術式や究極術式を巧みに操ることができるようになっており、こうした優れた力を持つ落伍者は『裏口の魔法使い』と呼ばれ、野良魔術師とは区別されていた。
いずれにせよ、正規の職に就くことが甚だ難しいこうした落伍者たちはその日の必要を賄うために職を転々とすることが多いのだ。今まさに、彼女たちはそうした事情を抱える野良魔術師の一団として、例の路地裏の法具屋を目指していくのである。
教授が指示した通り、マーチン通りを北に向けて『サンフレッチェ大橋』を目指している。
「おい、これほんとにうまくいくのかよ?」
「あら、もう作戦は始まっているのよ。乙女は根性なしでいけないわね。」
「うっせぇよ。」
ウィザードとソーサラーがいつぞやの月下のやりとりをあべこべに再現していた。
やがてサンフレッチェ大橋に差し掛かった。
「ここからね。」そういうとウォーロックはみなを橋の右側の欄干側に寄せた。
「ガーゴイルの像があるところまで、右側通行よ。」
そういって4人は歩き始める。晩秋の日差しが心地よく彼女たちを照らしていた。あたりは明るく、橋の下から川の流水の音が聞こえる。
「ここだな。」ウィザードがガーゴイルの像を見つける。
「それでは、ここからは左側通行ですね。」
ネクロマンサーが昨日教えられた手順を確認する。
石造りの大きな橋は、全面石畳が整備されており、昨日の雨でまだ湿気っていた。ところどころには水たまりが残されている。両脇の欄干には等間隔に実にさまざまの動物や魔法生物、架空の生物に至るまでが石造として立ち並んでいた。
「これが鳳凰像ね。」そう言ってウォーロックは鳳凰の頭を撫でる。
「あとはど真ん中一直線だぜ。」
ウィザードのそんな声が聞こえたあたりから、つい先ほどまで美しい秋の晴天に包まれていた周囲が俄かに霧に覆われ始めた。どうやらここまで、正しい暗号を実施できたようである。
「いきましょう。」ネクロマンサーが促し、3人はその大きな橋の通路のちょうど中央部分をまっすぐに歩き始めた。橋の向こう端までは、ちょうど全長の半分くらいの距離がある。進むほどにあたりに霧が立ち込め、朝の街の喧騒が遠ざかり、やがて白い静寂に包まれていった。橋の終わりにいよいよ差し掛かると、ちょうど橋の欄干の末端の左手側に、それは姿を現した。
アーカムや P.A.C. 商店とは異なり、その『裏路地の法具屋』は瀟洒な人気カフェのようなたたずまいを深い霧の中に沈めていた。箒を持った痩身で背のひょろ高い男が店先を掃除している。

「おはようございます。」ウォーロックはその男に声をかけた。
「こちらは…。」彼女がそう言いかけると、それを遮るように男が挨拶を返した。
「あら、おはよう。これはまたずいぶんかわいらしいお客様ね。うちのお店に御用かしら?」
「はい、こちらを訪ねてきました。」
「それはそれは。神秘の魔法具店『スターリー・フラワー』へようこそ。」
その男は独特の語り口で自己紹介を行った。
「あたくしは、ここの店長のリリー・デューです。今朝はどんな御用で?」
「突然にすみません。御覧の通り、私たちはアカデミーを追われてその日暮らしをしている者です。働くところを探しているのですが、アルバイトとして使ってもらうことはできませんか?」
「まぁ、そうなの?若いのに大変なことね。」
そういうとリリーは4人の足の先から頭のてっぺんまでなめるように眺めまわして値踏みした。
「なかなか使えそうじゃない?それで、あなたたちはどこまで進んだの?」
「『熟練:Adept の第1学年』です。」
熟練:Adept というのは、中等部の正式な位階名で、魔法社会の公式な場面で身分を紹介するときにはそのように言うのがならわしであった。
「そうなの。じゃあ魔法も中等くらいはいけるわね?」
「はい、何かとお役に立てると思います。」
リリーとウォーロックは交渉を続ける。
「そうねぇ、このお店はあたくし一人で十分といえば十分なのだけど、あなたたちがいてくれれば、朝っぱらからこうして箒を持つ必要もなくなるわけよね。それも悪くない話だわね。」
「雇ってくれよ。」
そう身を乗り出しそうになるウィザードをソーサラーが慌てて静止した。ここはウォーロックに交渉を一任した方が確かに思えたからだ。
「はい、掃除、洗濯、食事の準備から、品出し、接客、会計、帳簿の記帳に至るまでなんでもできます。」
いや、自分たちには、そのうちの半分くらいしかできない…他の3人はそんな顔をしている。ウォーロックはいったいどこでそんなことを覚えたのか?
「そうなの。まぁ、お嬢ちゃんたちかわいいし、男性客に受けそうだわね。賃金はそんなに出せないけど、それでもいいかしら?」
「はい、全くかまいません。雇っていただけるだけで感謝です。」
ふたりの交渉は続く。
「それで、厚かましいお願いなのはわかってますが…。」
「4人全員雇って欲しいって言うんでしょ?」
「はい。」
「いいわよ。そのかわり支払う賃金は4人で2人分、週払い、休憩はお昼に1時間、3時に15分。ただしお客様がいらっしゃるときは休憩は返上してもらうわ。朝は8時から、夕方6時まで。残業代はなし。あと、あたくしのことはリリーお姉さまと呼ぶこと。この条件を飲めるなら雇ってあげるわ。」
「もちろんです。それで…。」
「今日から働きたいのよね?まあ野良魔術師は日銭仕事だから、その事情はわかるわ。いいわよ。ただし…。」
リリーが俄かに語気を強める。
4人に緊張が走る。
「このあたくしを『社長』だの『店長』だの色気のない呼び方したら即刻クビにするからね。おぼえといてちょうだい!」
なんだ、そんなことか…。4人は内心胸をなでおろした。
「それじゃあ、店内に入ってちょうだい。」
リリーに促されて、4人は入店した。
神秘の魔法具店『スターリー・フラワー』と紹介されたその店内は、アーカムの神秘性とも P.A.C.ストアの不気味さとも異なり、明るい照明に彩られた華やかで活気のある、清潔で美しい内装だった。やはり店内は魔法で空間的に拡張されているらしく、外観よりもずっと広い。店の中央には、舞踏会でも開けそうな、200人くらいは収納可能と思われる広いホールがあった。陳列台は、そのホールの手前の小部屋に整然と並べられており、その内装はプロフェッショナルな感じのする洗練されたものであった。やはり様々の術具や魔法具が並んでいるが、若い女性が好みそうな占いアイテムや開運グッズといった類の商品をことさら多く取り揃えていた。

また、ホールの向こう側に見える別室には『Jewelry Division』という標識がかかっており、法石類の取り扱いもあるようだ。その場所をホールの向こう側に配置しているということは、おそらく VIP ルームのような性質を持たせているのであろう。
リリーの後に続いて、ホールを抜け、その VIP ルームに入っていく。そこには案の定、魔法的な光を放つ法石群が、所狭しとショーケースに収められていた。その陳列センスは見事で、各法石の美しさを殺さないように、実によく考えた配置がとられていた。その VIP ルームの横手には、「乙女のひ・み・つ」と書かれた暖簾で遮られた一角があった。
「あそこは何を取り扱うところですか?」ソーサラーが尋ねると、
「あらやだ、あれよ。ア・レ。あと、ソレとかね。その歳ならわかるでしょ?」リリーは意味深な表情をして見せた。
なぜかそこでネクロマンサーが顔を赤らめている。
VIP ルームを抜けた先には従業員用と思われる小部屋があり、その奥が店長、もといリリーの私室につながっていた。
「かけてちょうだい。」
リリーは4人を従業員室の長椅子に並んで座らせた。
「面倒くさいけど、これをよく読んでサインして頂戴ね。」
そういってめいめいに1枚ずつ用紙を渡した。それには連絡先と簡単な学歴・職歴の記入欄があり、まあ簡単に言えば身上書の類であった。用紙の下欄には就業条件が小さな字で細かく書き連ねられていて、一番最後はその就業規則等への同意を示す署名欄となっていた。4人は荷物から筆記具をとりだし、それぞれの情報を記入していった。
「最近はね、ここみたいな違法店でもいろいろ事情があって、書類をそろえておかないといけないのよ。世知辛い世の中になったものよね。」
そういうと、リリーは魔法タバコに火をつけてそれをくゆらせた。赤紫の怪しい煙がふっとあたりに充満する。
書類を書き終えた4人は、順にそれをリリーに手渡した。
リリーはそれらの書類にしばらく目を通してから、4人の役割を指示した。このリリーという男、仕事の仕方はきちんとわきまえているようである。
「それじゃあ…。」
そう言って、各々の役割を伝えていった。ウォーロックは品出しと在庫の補充、ウィザードは店内及び店先の清掃・掃除、ソーサラーは接客、ネクロマンサーは会計係と決まった。その従業員用小部屋には戸棚があり、そこにある制服に着替えたら、ホールを戻って、最初の展示台のある部屋に集合するよう命じて、リリーは先にそちらに向かった。
4人はいそいそと着替えを始める。
「うまくいったな。」上着を脱ぎながらウィザードが言う。
「そうですね。でもびっくりしました。あんなに交渉がうまいなんて。」
スカートのホックを外しながらネクロマンサーが続けた。
「こういう経験があるの?」
用意された制服の上着を身に着けながら、ソーサラーも訊く。
「まぁね。人生いろいろよ。」
そう言ってウォーロックはエプロンのひもを後ろ手に結んだ。
「さぁ、なんにしてもこれから2週間、私たちはここ『スターリー・フラワー』の店員となるわけよ。一生懸命働きましょう。もちろん例のこともしっかりやりながらね。」
ウォーロックが檄を飛ばす。
それから4人はリリーが指示した売り場へと戻っていった。
「なぁ、あの『乙女のひ・み・つ』ってとこ、何売ってるんだろうな?」
「たぶん、知らない方がいいと思います。」
ウィザードとネクロマンサーの間にそんなやりとりがあった。
売り場に4人が到着するとリリーは彼女たちを1列に整列させ、朝礼らしきものを始めた。それは「乙女とは何たるか」という内容に重きが置かれたもので、事務連絡というよりはリリーの矜持と信念を表示する一種の演説のようなものであった。女性の言葉を話すその男声は、なにやら不思議な魅力をたたえていた。
「それでは、今日も一日、ご安全に!」
4人が呼応するように頷くと、リリーが言った。
「ここで、『リリー・オー!』でしょ!当店の従業員の結束を確かめるおまじないよ。さぁ、やって!」4人は気恥ずかしそうにしながらも声をそろえた。
「リ、リリー・オー!」
こうして初日の勤務が始まった。

* * *
早くも一週間が過ぎ、今日までに提出した報告書は2本にのぼる。報告書の執筆はウォーロックが行っており、それに目を通したパンツェ・ロッティはいちいち満足という面持ちであった。教授の執務室を定期的に訪れながら毎日スターリー・フラワーに通う、奇妙な生活が続いていた。
4人はそれぞれ仕事にも慣れてきたようで、その手際は最初に比べるとずいぶんよくなってきた。リリーとも良好な関係を続いている。3日目にうっかりリリーを店長と呼んだウィザードをクビにするしないのすったもんだがあった以外は、平穏な日々が続いていた。
ここは、違法店といっても、クリスタル・スカルやケレンドゥスの毒のような危険な魔法具を扱うというよりは、法石と、それからいわゆるパンツェ・ロッティやその取り巻きが嗜好しそうな、そしてかつてネクロマンサーが人為のロードクロサイト欲しさに果敢に冒険を犯した類の、そういう商品を主に取り扱う異色の法具屋であった。怪しいといえば大いに怪しく、非倫理的といえば確かにそうであったが、禁忌魔法具のおぞましさとはおよそ無縁の、少々変わり種の『裏路地の法具屋』だった。このようなニーズも市場にはあるということなのだろう。
ただ一つ、Jewelry Division の中央に位置するひときわ大きなショーケースに展示されている、他とは別格の神秘的な輝きを放つ法石だけは特別で、清掃係のウィーザードもそこだけは掃除をするなと厳命されており、そのショーケース周辺は、常にリリー本人が細心の注意を払って管理していた。
客受けがよかったのは接客担当のソーサラーで、高貴な貴族令嬢である彼女の態度・仕草はいちいち洗練されており、接客を受けた客はその応対にすこぶる満足して帰るようであった。彼女のその適性を、あの短い面接だけで見抜いたリリーの経営手腕は確かなようである。

仕事において手際の良さを見せたのはウォーロックで、手慣れた様子で倉庫からの品出しと在庫補充をこなしていた。彼女もまた、リリーから、例の法石周辺のことだけはしなくてよいと言われている。

ネクロマンサーはここでも客の心をとらえたようで、さながら看板娘となっていた。彼女と話し込む客が多くて会計が滞って仕方がないという苦情がリリーによせられたりもしたそうだ。まじめで実直な彼女の仕事ぶりは確実で、リリーは安心して仕事を任せているようである。

ウィザードもまた、持ち前の向上心と真面目さで丁寧な仕事をしていた。広い店内を、例の法石の展示場所を除いて、隅から隅まで、徹底的に清掃してまわっている。ときどき彼女の苦手な破廉恥な品物を見つけては、顔をしかめつつ、それでもやはり丁寧に埃を取り除いていく。ただ、彼女にとって『乙女のひ・み・つ』の内部の掃除だけは苦手なようで、いつもげっそりした顔でその暖簾の奥から出てくるのが日常となっていた。

忙しくも、アカデミーで講義をうけ、魔法の教練を行うのとはまた違った充実感に満たされていた。密命の方も順調に進んでおり、その日の夜には3通目の報告書を書き上げようという、そんなある日のことであった。
* * *
その日は少々怖さを感じるような土砂降りで、晩秋の寒さが際立っていた。4人は肌寒さを仕事の熱気で上書きしながら、いつものように手を動かしている。そのとき、開店間もない店の戸が開いた。雨音が一気に大きくなって、冷たい風が店内に吹き込んでくる。ソーサラーが接客に向かうと、何とも形容しがたい、おそらくは人物というべきなのであろう不気味な存在が店内に立ち入ってきた。
それは一見すると若い女性の魔法使いのように見えたが、その関節や節々はあきらかに人間のそれと違う様相を呈しており、例えるならば球体関節人形のそれのようであった。しかし、各関節や節々の詳細はそこに身につけられた様々の装具や呪印によってカモフラージュされており、本当のところそれらが実際にどうなっているのかを視覚的に確かめることは難しかった。

「店長はいるか?」
不気味に震えるような乾いた声で、それはソーサラーに尋ねた。
「はい、おります。」
「呼べ。」
「かしこまりました。」
そういうとソーサラーはリリーの執務室に彼を呼びに行った。
ほかの3人も来客に気づいたようで、戸口に視線を送っている。その不気味な存在はあたりを見回すでもなく、ただ静かに立ち尽くしてた。ネクロマンサーが入り口を閉める。雨音が小さくなり、冷たい風はやんだ。しかし、そうした人間的な営みについて、それは全くの無関心を貫いていた。
「リリーお姉さま。」
そう呼ぶソーサラーの声が遠くに聞こえる。しばらくしてリリーとソーサラーがホールの向こうからやってきた。
「いらっしゃいませ。あたくしに御用で?」
その声を聴いて、それはリリーの方に向きを変え、口を開いた。
揺れ乾く不気味な声が言葉を紡ぐ。
「『ガラドリエルの恵み』を出せ。」
「せっかくでございますが、あれは非売品ですのよ。悪しからず。」
リリーがそういうと、それはずんと一歩リリーに迫り、その胸ぐらを乱暴につかんだ。
「なによ、あんた。いきなり…。」
「もう一度言う。『ガラドリエルの恵み』を出せ。」
「わかんない人ね、あんたも。あたくしそういうの嫌いよ。あれは非売品なの。おととい来て頂戴!」
リリーがそういい終わるが早いか、ソレはリリーをつかんでいるのとは反対の手に短刀を握りってリリーに振り向けた。
「あぶねぇ。」
近くで掃除をしていたウィーザードが、さっと飛びかかり、その手から彼を救出した。ネクロマンサーもその場に駆けつけて、声をかける。
「リリーお姉さま、大丈夫ですか?」
「あんまり大丈夫ともいえないけど、おかげで助かったわ。」
リリーは苦しそうに咳いている。
「おい、てめぇ!いきなりめちゃくちゃじゃねぇか!何しやがる!」
その声を聴いたソレは揺れるように体を動かして店内の一角に集まる格好となった3人の方に向きを変えた。この動きには見覚えがある!ネクロマンサーの脳裏にいくつかの記憶がよみがえっていた。
ちょうどその時、そいつの背後を鋭い電撃が襲う。ウォーロックだ!
電撃は大ぶりのローブを着込んだその背中に直撃し、その異形は大きく前のめりになった後、およそ人間のものとは思えないぎこちない動きで、ホール入り口そばの展示台近くに立つウォーロックを見据えた。
「『ガラドリエルの恵み』を出せ。」壊れたレコードのようにそれは同じ言葉をおぞましい音調で繰り返す。
「あなたが問答無用なら、こちらも容赦しないわよ!」身構えるウォーロック。
リリーをひとまず会計台の裏に避難させてから、3人もそれと対峙した。やるしかない!4人は意を決した。
リリーはカウンターの裏から顔の上半分だけを出して震えながら成り行きを見守っている。
『火と光を司るものよ。水と氷を司るものとともになして、わが手に力を授けん。火と光に球体を成さしめて我が敵を撃ち落とさん!砲弾火球:Flaming Cannon Balls!』
詠唱とともにウィザードの手から、複数の火球が異形をめがけて繰り出される。ソレは火球の方に向きこそ変えるが避けるそぶりをするわけではない。全弾が命中した。
「いっちょ上がりだ!」そう声を上げるウィザード。
その異形は一度大きく上体をのけぞらせた後、その反動で前方につんのめり、そしてまた壊れた操り人形のような動作を連続させて、元の姿勢に戻った。
「なっ!?効いてねえのかよ!?」
火球は確かに全弾命中した。ソレは特段障壁を展開していたというわけでもない。全くの無傷というわけではないが、しかし損傷らしい損傷はほとんどなかった。
「へっ、やるじゃねぇか。ならこれでどうだ!ずたずたにしてやるぜ!」
『天候を司るものよ。水と氷を司るものとともにしてわが手に雲を成せ。空気を振動させ、風を巻き起こせよ。周囲を飲み込め!竜巻:Tornad0!』
今度は『竜巻:Tornado』の術式を繰り出すウィザード。店内に巨大な竜巻が発生し、周囲の陳列棚もろともその異形を中空に巻き上げ、帯電する気流と空気圧で圧倒する。そして、その体を中央の商品棚に思い切りたたきつけた。轟音ともに商品棚は壊れ、その響きを後から増し加えるように竜巻で巻き上げられた様々の品々が、けたたましい音を立てて石造りの床に打ち付けられた。
「いやぁぁぁぁぁあぁぁぁぁあ!あたくしのお店がぁぁぁあぁぁあぁぁ!」
会計台の裏でリリーが狂乱の声を上げている。さもありなん。それほどにウィザードの竜巻は強烈であった。そのままリリーは失神したようだ。今度こそやったであろう。そう思った時だった。
壊れた陳列棚のガラスがバキバキと音を立てる。金属のフレームをゆがめる音を奏でながら、その異形はなおも立ち上がった。
「が、が、が、ららら、どりえるの、の、の、恵みを出せ。」
ウィザードが慄いている。
ウォーロックはさっとその異形の前に踊り出て、間髪入れずに高出力の『衝撃波:Shock Wave』の術式を繰り出した。
異形の体は大きく吹き飛び、ホールの奥の方に滑り込む。
「ここではだめよ。お店が壊れてしまう!」
そう言ってウォーロックは3人にホールに移動するよう促した。その異形はなおも不自然な動作の奇妙な連携を駆使して、よろよろと立ち上がった。
4人はホールに駆け込むや、それとあいまみえる。ここからどうする?ソーサラーの氷刃の豪雨は切り札に残しておかなければならない。この場面で彼女が魔力枯渇を起こすことは、すなわち全員の死を意味していた。
その時である。その異形の周囲に不気味な色の光が満ち、床に大小さまざまの魔法陣があらわれた。
「冗談じゃねぇ!」あのウィーザードが声に恐怖の情を載せている。
『呪われた者どもよ、わがもとに集え。その穢れた力を用いて我が敵を滅ぼせ!Summon of Enhanced P.A.C. Type-Blue!』
詠唱とともに床の多数の魔法陣から、青白い光をはなつ人型の異形の集団が姿を現した。その数は40前後におよぶ。

「あいつ一人でも手を焼くというのに!」ウォーロックが焦りを見せた。
その時だった!
『水と氷を司る者よ。我は汝の敬虔な庇護者也。わが手に数多の剣を成せ。氷刃を中空に巡らせよ。汝にあだなす者に天誅を加えん!滅せよ。氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swords!』
ソーサラーがおそらく最大出力と思われる『氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swords 』の高等術式を繰り出した。数えきれない数多の氷刃が敵の集団に襲い掛かる。
氷刃は目にもとまらぬ速さでその青白い人型を幾重にも切りつけていった。しかし、おかしい…。その人型は氷刃を浴びるたびに怯みはするが一向に効いている気配がないのだ。一通りの騒乱の後で、人型の群れははゆっくりと歩みを進め始めた。
ソーサラーの体からぼぅっと残留魔力が押し出される。まずい、魔力枯渇だ!高等術式を最大出力で繰り出したことで、ソーサラーは体内の魔力を一時的に使い切り、よわよわしくその場に座り込んでしまった。ウィザードがその体をとっさに支える。見ればあの天才の黄金の瞳に驚きと恐怖の色がにじんでいた。

どうすればいいのか?人型と異形がゆっくりと迫ってくる。もう駄目だ。そう思った時だった。
『慈悲深き加護者よ。我が祈りに応えよ。その英知と力をその庇護者に授けん。我が頭上に冥府の門を開き、暗黒の魂を現世に誘わん。開門せよ!暗黒召喚:Summon Drakness!』
これは死霊術の高等術式だ。繰り出したのはもちろんネクロマンサーである。彼女もまた高等術式を修得していた。その頭上には青白い冥府の門が描き出され、そこから夥しい数の悪霊の類が呼び出されている。彼女もまた、死力を尽くして高等召喚魔法を行使したのだ。その場に片膝をつきながらも、声を絞って悪霊に命じる。
「契約のもとに、我が敵を滅ぼせ!」やがて両ひざをつき、肩で息をするその体から残留魔力が押し出されていった。彼女も魔力を使い果たしたのだ。
しかし、召喚されたその死霊の軍団の効果はてきめんだった。数で互角かそれ以上、広いホールで死霊の群れと人型の群れが戦場さながらにもみ合う。耳をつんざくような死霊の声が響くたびに、その人型は引き裂かれ食いちぎられ、その場に死屍累々となっていった。死霊はついにあの異形の魔法使いもどきをも取り囲んだが、一瞬まばゆい閃光が走ったかと思うと、たちまち胡散霧消してしまった。敵は対アンデッド術式もこなすようだ。強い!
これまでの相手とは完全に別格だ。こちらはすでに2人が魔力枯渇を起こしている。ウィザードに残る魔力も少ない。
3人をかばうようにしてウォーロックが前に出て、その恐るべき異形と対峙した。ウィザードが心配そうにそれを見守る。
「しくじっても恨まないでよ。」ウォーロックは笑って見せた。
「さぁ、私が相手よ!」そういうとウォーロックは聞いたことのない術式の詠唱を始めた。
『閃光と雷を司る者よ。その胸中を開き、神秘に通じる秘術を授けたまえ。我は汝の敬虔な庇護者なり。天空の意思を我に知らせよ。閃光と雷を裁きの剣となさん!』
なんなんだ、この術式は!?ウィザードはそれを見たこともなかった。詠唱するウォーロックの全身を閃光を伴う焔のような魔力の渦が取り巻いていた。まさか!?いや、そんなことできるはずがない。

『今、天界の裁きをこの手でなそう。秘術!(制限付)裁きの雷光:Ristricted Lighting Laser of Divine Judgement!』
ウォーロックの両手の周辺に形作られた巨大な魔法陣の中に浮かぶ一塊の雲から、まるでそれ自体が光の剣であるかのように、閃光と稲妻がかの異形に向かってほとばしる。刹那あたりは目を開けていられないほどのまばゆさに包まれる。雷の轟音とともにその光の剣の群れは各々一直線にその異形の体を貫き、薙ぎ払う。先ほどまで、彼女たちの放つあらゆる魔法を受け付けなかったその体は光の剣によって引き裂かれ、その裂け目から閃光とともに真っ赤な炎を上げている。やがてその炎が異形の全身を包んで焼き尽くした。後には墨とも灰ともつかない燃え滓しか残されていなかった。
彼女の体からも残留魔力が押し出される。そのまま前のめりに倒れて動かなくなった。
「あたしは今、一体何ををみたんだ!?」
初めてソーサラーの氷刃の豪雨を見た時以上の衝撃が彼女を捉えて離さなかった。
* * *
その後ろから、気がついたのであろうリリーが、打撲して痛めた頭をさすりながらホールに入ってきた。
「まぁ、ずいぶん派手にやってくれたわね。」
「すまねぇ。」ウィザードがうなだれる。
「いいのよ。あんたたちがいてくれなきゃ、とっくにあたくしは彼岸の彼方、感謝してるわ。」
そういうと、ウィザードと手分けをして、魔力枯渇した3人をホールの客席に運んで、そこに座らせてやった。
「ねぇ、この子達大丈夫なの?」リリーが心配そうに訊ねる。
「ああ、どうということはねぇ。ただの魔力枯渇だ。」
「あいつにやられたわけじゃあないのね。」
そいうとリリーは立ち上がり、派手に壊れた陳列棚を何やらごそごそやっている。
「これを飲ませてやんなさい。」
「いや、でも…。」
「心配ご無用。禁忌の魔法具屋のどこもかしこもが、毒や呪いばかり扱っているわけじゃないのよ。人に夢を与える乙女チックなお店だって中にはあるわ。一週間以上も働いてそれに気づかないなんて、ずいぶんと不真面目な従業員もいたもんだわね。」
ウィザードの懸念は見事リリーに見透かされていた。彼の手には急速魔力補給用の秘薬があった。それはかなり高価なものだ。
「いいのか?」
「命の恩人から金をとるほど落ちぶれちゃないわ。」
そういって、リリーは半ば押し付けるようにその薬瓶をよこした。
ウィザードは3人に順にそれを飲ませていく。ほどなくして3人の体は魔力が戻ったことを知らせる薄明かりをともした。
「大丈夫か?」
「ええ、不覚だったわ。まさか水と氷に耐性を持っていたなんてね。」
「でも、なんとか撃退できたみたいでよかったです。」ネクロマンサーも体を起こした。最後にウォーロックがウィザードの腕の中で目を覚ます。
「おい…。」ウィザードが何か言いたそうにする。
「あれは絶対に秘密よ。報告書にも書いたらだめだからね。バレたらほんとに退学だから。」
「じゃあ、やっぱり。」
「な・い・しょ、ね?とどめはあなたが火と光の魔法で刺した、そういことにしてちょうだい。お願い。」
ウォーロックは愛らしくウィンクして見せた。
「お、おう、わかったぜ。」そう言うとウィザードはウォーロックをきちんと椅子に座りなおさせてやった。
4人がどうにかこうにかひとごちを取り戻したところへ、いつのまにか姿を消していたリリーが戻ってきた。
「あなたたちのおかげで命拾いしたわ。ありがとうね。お礼にこれをあげるわ。あたくしよりもあなたたちの方がきっとこれをうまく使えると思うから。」
それは、Jewerly Division の特別の展示台に鎮座して、リリー以外の干渉を許さなかったあの法石だった。
「それは…?」ウォーロックが問う。
「これが『ガラドリエルの恵み』よ。生命と霊性に関する神秘の力を高濃度で秘めた真石のね。」

真石とは法石のなかでも、天然の魔が凝縮することによってできた、極めて魔法特性の高い法石のことであり、恐ろしく貴重で高価な代物である。かつて幼いネクロマンサーが一風変わった自己犠牲によって入手した人為のロードクロサイトなどは錬金術と魔法による一種の人工的な法石で、ある程度の量産が可能な代物である。一方で、こちらは下手をすると生涯にわたって本物を見る機会を得られないかもしれないという、希少貴重な正真正銘本物の法石であった。
「そんな高価なものいただけません。」ウォーロックが拒む。
「あたくし、こうみえても人を見る目はあるの。あなたには間違いなく大きな運命的可能性を感じるわ。だから…、そうね。こうしましょう!これは贈与ではなく、投資。あなたの将来に対するあたくしの投資よ。そういうことなら文句はないでしょ?」
そういってリリーはその真石をウォーロックに両手で握らせ、その上から、自分の手を覆って固く握手した。
「本当に感謝しているわ。命の恩人の小さな魔女さん。」
その目は涙ぐんでいるようであった。
「では、きっとご期待に添えられるように、しばらくお預かりします。」
「あなたたちの成長と活躍を祈っているわ。」
「しかし、これどうしたもんかな。」
陳列部屋の方を見てウィザードが頭をかく。
「すまねぇ、ええと、リリーお姉さま。」
「あら、いいのよ。ここにあるのは金にはなるけど値打ちはないがらくたがほとんどだからね。あんたたちが、このホールであいつらとやりあってくれたおかげで、肝心の Jewelry Division と乙女のひ・み・つは手付かずですんだから。あれさえ無事に残っていてくれれば、あたくしの商売はいつでもどこでもなんとでもなるわ。」
4人の表情からいくばくかの緊張が解けた。
「さてと。そうはいってもしばらくは休店せざるをえないわね。したがって、あなたたちとの雇用契約は今日、この時までよ。全員クビね。ご苦労様でした。」
そういって5人は大いに笑った。それは実にすがすがしい笑顔であった。
「リリー・オー!」そう言って彼女たちはスターリー・フラワーを後にした。
わずかな期間であったが、4人はこの店と、そしてその風変わりな店長、もといリリーお姉さまにこの上ない愛着を感じるようになっていた。リリーに見送られて店を後にしたとき、すでに時刻は正午を回っていた。あれだけひどかった豪雨はいくぶんましな小降りになっていたが、この季節の雨が冷たいことに変わりはなかった。彼女たちは荷物からローブを取り出し、それを雨合羽がわりに頭からひっかぶってアカデミーへの帰路につく。思えば気が重いが、アカデミーに戻り次第、例の場所に出頭して3通目の報告書よりも1日早いイレギュラーの口頭報告をしなければならないことになる。不可抗力とはいえ、それは任務失敗の報告であり、パンツェ・ロッティ教授の叱責と懲罰が待っていることは想像に難くなかった。4人はアカデミーまで雨の中を駆けていく。
* * *
そしていま4人は、例の場所でパンツェ・ロッティ教授の前に一列に整列していた。ウォーロックから一通りの説明を聞いた後で、怒号が飛ぶ!
「誰が、そんな危険な真似をしろといった!殺されていたかもしれんのだぞ!!」
「しかし、あの場でそれを選択しないのは愚かであったかと。」
ウォーロックは毅然と応じる。彼女には相応の覚悟があるようだ。
「ほほう。つまり浅慮による軽挙妄動ではなく、熟慮の末の勇気ある断行であったと、そう言うのだな?」
「はい。」その瞳はまっすぐに教授を見据えている。
「よかろう。それについては君たちの無事に免じて不問に付す。本当に無事でよかった。とにかく、今日の出来事を中心にして詳細に内容をまとめ、3日のうちに最終報告書を提出したまえ。よろしいか?」
「わかりました。」4人は声をそろえて返事をする。
「その最終報告書の提出をもってこの度の特命は完了したものとみなす。よくやった!」
教授の机の上には相変わらずあの破廉恥な魔術記録が散乱していた。その数は一層増しているようだ。懲りない性格の御仁のようである。
4人はその後、いったんめいめいの部屋に戻って重苦しい荷物を置いたあと、着替えを済ませてから、報告書作成のために、ソーサラーの寮室に集合した。久々のパジャマパーティーである。若く張りのある楽しそうな声が、部屋の外まで漏れ聞こえている。
最後までまともに意識があったのはウィザードだけであったため、最終報告書はウィザードが執筆を担当することになった。また、リリーがくれた『ガラドリエルの恵み』については、「店内のその他の箇所は損傷軽微」とだけ記して、あえて事実を伏せることにした。
ソーサラーとネクロマンサーが用意してくれた夕飯を囲みながら、ウィザードの筆は進んでいく。3日あれば十分に仕上げられそうだ。
「約束だからね。」
ふたたびウォーロックがウィザードに向けて愛らしいウィンクを送る。
それに対して、ウィザードは両目が動くぎこちないウィンクらしき動作で応えた。
寒さはいっそう増してくる。冬がもうすぐそこまで来ているようだ。来週には暖房器具を出さなねばならないであろう。短くも充実したここしばらくの思い出話に花を咲かせながら、乙女たちの軽やかな声は冷たく空気の張りつめる晩秋の夜空にリズムとうるおいを与えていた。
夜が静かに更けていく。
* * *
「『ガラドリエルの瞳』の回収に失敗したようだな。」
「申し訳ありません…。」
「可愛い娘のために、私は大きなリスクを冒して君の研究への協力を続けている。厚生労働省もアカデミーの衛生部門も、いつまでも情報を遮断しておけるほど手ぬるい組織ではない。もう一度自分の本分を思い出し、成果を急ぎたまえ。大口をたたいていた拡張型も結局はこの様だ。本当にできるのかね?」
「P.A.C. の強化と制御はもうすぐ完成します。しかしそれには…。」
「そうも時間がかかるものなのか?手ぬるいのではないか。今回のことにしても、なぜそのような魔法使いが4人もそこにいたのだ!リリーだけだと言っていたではないか!」
「どうやら、アカデミー最高評議会に動きがあったようでして…。」
ふぅ、と大きなため息。
「君は、この私を失望させる才能だけは存分に持ち合わせているようだ。いいかね?娘のためでさえなければ、私はもうとっくに君のことを見限っている。そのことをくれぐれも忘れぬことだ。」
「心得ています。」
そうして頭を下げた男の手は、血がにじむほどに固く握りしめられていた。
第4章
第1節『アカデミーによる葬送』
時が経つのは早いもので、『スターリー・フラワー』の一件からすでに4年の歳月が流れていた。みな『魔術と魔法に関する高度専門論文試験と口頭試問』の関門をくぐり抜け、無事に高等部への進級を果たして、それから早くも2回目の冬を迎えようとしている。
『アカデミーによる葬送』の儀式を告げる重苦しい鐘の音が、冬特有の鉛色に煙る空に向かって、式場から学内全体へと響き渡っていた。
『アカデミーによる葬送』とは、アカデミーの課す任務によって不幸にも命を落とした学徒および教職員を、丁重に荼毘に付すための荘厳な葬儀である。その名の通り、式典自体はアカデミー内の聖堂で執り行われるが、厚生労働省のアカデミー管理部門がその挙式の全てを一手に担っており、アカデミー側としては、厚労省の指揮監督のもとで、衛生部門が具体的な司式を遂行をするにすぎなかった。その二重構造のため、情報の錯綜もしばしばみられるようである。
このところ、月に数度という異様な頻度で葬送の儀式が執り行われており、アカデミーはもとより魔法社会全体に大きな不安をもたらしていた。その原因は、『リッチー・クイーン』という名の強大な『裏口の魔法使い』が率いるアンデッドの大群『奇死団』による辺境集落への頻繁な襲撃にあった。裏口の魔法使いとは、アカデミーの禁に触れて分不相応に秘術を身に着け、あるいは禁忌とされる魔法具の力を不正に解放して、アカデミーから追われるようになった者をいう。この魔法社会の警察と軍事は政府とアカデミーとの二重構造になっており、一般的な事件や外敵の進行については政府警察と正規軍が対応するが、裏口の魔法使いなど、アカデミーが直接関与する事柄については、最高評議会のもとに組織されたアカデミーの私設警察および私設軍隊が対処にあたることとされていた。両者の関係はいわゆる縦割りで、よほどの重大事件や大規模紛争の場合においてこそ、協力をしないというわけでもなかったが、基本的には事件の性質に応じていずれの担当であるかが厳然と決まっており、相互に干渉を嫌ったのである。
今日もまた、『オッテン・ドット地区』の辺境地域警備中に偶発した『奇死団』との遭遇戦において犠牲となった『白銀の銃砲部隊』の隊員を悼み、その亡骸を丁重に葬るべく、葬送の儀式がしめやかに執り行われようとしていた。この儀式には、犠牲者の関係者、葬送の実務を取り仕切るアカデミーの衛生部門と厚生労働省の関係各署の職員、そして高等部在籍の学徒、および全教員が出席することとされていた。

「またかよ。」
「ここのところ、多いですね。」
「アカデミーはこの事態をいったいどう見ているのかしら?」
見知った3人の姿がそこにあった。3人?
そう、そこにウォーロックの姿はなかった。彼女は、高等部に進級して間もないころ、アカデミーが厳に接触を禁じる禁忌術式と究極術式、およびその行使に必要な大天使の神秘に関する情報に不正にアクセスしたことで、『裏口の魔法使い』としてアカデミーから追われる身となっていたのである。今となってはその生死を確かめる術すらなくなっていた。
会式の始まりを告げる鐘が荘厳な音を立てる。参列者は決められた位置につき、司祭の言葉に静かに耳を傾けていた。
「見ろよ、あいつ今日も来てやがるぜ。」
ウィザードが小声でささやく。
「本当ですね。」とネクロマンサー。
「厚労省の高官といったって、彼は確か技官のはず。どうしてそんな立場の人間が毎回参列しているのかしらね?」
ソーサラーはそう訝しがって見せた。

聖堂の内側を讃美歌と聖歌の合唱がつつみ、その式典は粛々と進行する。天井にも達するパイプオルガンが神聖な音律を奏でていた。今回の犠牲者は12人。看過できる数ではないが、アカデミーはそれでもなお、対『奇死団』作戦においては、近頃結成されたばかりの、対アンデッドに特化した錬金銃砲で武装する『錬金銃砲部隊』を用いた集団戦術で対応する方針を堅持しており、犠牲者の数は増える一方であった。アンデッドの専門家集団であるネクロマンサーのギルド『死霊術士・屍術士共済組合』は、召喚したアンデッドの大軍を奇死団にぶつけるのがもっとも犠牲の少ない方法であると度重ねて具申しているが、最高評議会を中心として、その提案を採用する意思は今のところないようである。
事態を重く見た政府軍事部門では、最高評議会と異なる見解も主張されはじめたようでもあるが、目下のところ、厚生労働省はアカデミーの姿勢に追従し、衛生部門を通じて粛々と葬送の儀式を執り行うばかりであった。
司祭による頌栄のあと、荼毘に付すべく棺がうやうやしく式場から運び出され、厚労省と衛生部門が管理する一時安置所に運ばれていく。葬送の儀式の最後の場面である。
アカデミーの任務によって命を落とし場合、一般にその遺体の損傷が激しいため、残された遺族の悲しみと心情に配慮して、アカデミーは遺体の開示および引き渡しを行っていない。この慣行はある時期から例外なく守られるようになった。一部の遺族からは、自分たちの手で葬ってやりたいという要望も強く寄せられが、公共の福祉への配慮であるとして、アカデミーはそれに応じることをしないでいた。犠牲者の遺族には政府およびアカデミーから手厚い補償がなされるため、多くの者がそれ以上の要求を思い留まるようであり、それでもなお、という声も皆無ではなかったが、アカデミーの姿勢は頑なであった。
荘厳な雰囲気を始終保ったまま、本日の葬儀が終わった。関係者および参列者は解散となる。
「『奇死団』問題、深刻ですね。私は『死霊術士・屍術士共済組合』の提言が的を射ているように思うのですが…。」
ネクロマンサーが言う。
「最近の、襲撃事件の頻度は少々異常だぜ。」
「そうね、『リッチー・クイーン』の目的は一体何なのかしら?」
3人は最近の世情について語りながら、それぞれの寮室に戻っていった。
* * *
『リッチー・クイーン』は『リッチ(最高死霊)』という呪われた位階をもつ裏口の魔法使いで、彷徨える屍となって各地を徘徊するアンデッドの群れを糾合して、強大な軍隊組織をしつらえた存在である。その目的は全くの不明であるが、被害は凄惨かつ苛烈で、襲われた村落の住人はみな惨殺されるか、アンデッドとして奇死団に組み入れられるかという、いずれにしろ救いようのない最期を迎えることになっていた。
奇死団は、集団として恐ろしいのみならず、リッチー・クイーンその人の卓抜した呪いの魔法力によってその脅威を幾重にも増し加えていた。まず、彼女は、常に『苦痛と苦悩を分かつ石』という神秘の法石をあしらった軽鎧付ローブを身に着けており、その部分に対する攻撃は、それがもたらす苦痛を攻撃者にそのまま反射した。つまり、彼女に対する致死性の攻撃は、攻撃者にも同様に致死的な効果をもたらすことから、迂闊に彼女に手を出すことができないという深刻な問題を惹起していた。

また、彼女が行使する呪われた禁忌の死霊術『死を呼ぶ赤い霧:Crimson Fog Calling Death 』は、その場に存在するすべての生者を無差別にアンデッドに変えて奇死団に組み入れるという実におぞましいものであったが、これらの事柄への対応は、政府とアカデミーで大きく異なっていた。
事態を重く見た政府軍事部門は、アカデミー管轄の私設軍事部門に直接働きかけ、最高評議会の決定とは違う方向からの局面打開を模索していた。しかし、その取り組みは、組織間連携の難しさが際立つばかりで遅々として前進していなかった。
それに対して、最高評議会を頂点とするアカデミー側は、アンデッドに効果があるとされる『魔法銀の法弾』で武装した『白銀の銃砲部隊』には、いまもってなお奇死団に対する十分な抑止効果があり、現状それ以上の対策は必ずしも要しないとする消極的な姿勢を一貫していた。
不思議なのは、たとえば『魔法銀の法弾』よりも更に対アンデッド効果の高い『炎鉄の法弾』の量産や、『炎鋼の法弾』の新規開発に関する予算の拠出をアカデミーが渋っていることである。彼らのこうした消極的姿勢については、魔法社会における人権向上委員会などをはじめとして、学徒の生命と尊厳を著しく軽んじる残酷な方針の維持であるという鋭い糾弾がなされているが、遺族に対する補償が十分であることから、そうした批判がさほどには世論の後押しを得られていないのもまた事実であった。
いずれにせよ、いま魔法社会全体が、アンデッドの襲撃による絶望と恐怖に打ち震えていたのである。
* * *
数日後、アッキーナからの呼び出しを受けて、3人は『アーカム』に集まっていた。そこには例の貴婦人も同席している。
「急に呼び出してごめんなさいね。」
貴婦人が3人を気遣った。
「構いません。それで今日はどうなさったのですか?」
ソーサラーがそう応じた。
高等部に進級したころからであろうか。これまでは、彼女たちの方からアーカムを訪問するばかりの一方通行であったが、それが双方向に連絡をとる形へと変わっていた。といっても、なにか特別の神秘的な手続きを経るというようなわけではなく、すっかり魔法社会に普及・定着した通信機能付きの携帯式光学魔術記録装置に、アッキーナからの着信がある、というだけのことである。もちろん、その日によってどの姿をしているかはわからないわけであるが、そのマジック・スクリプト(発信者を識別する番号のようなもの)は1つであったので、アッキーナからの着信であることを識別することは容易であった。ちなみに今日は、少女アッキーナからソーサラーへの着信であったようだ。
「『奇死団』のことはもちろん知っているわよね?」
「はい、最近アカデミーでは犠牲者が後を絶たず、葬送の儀式が頻回に執り行われています。」
ネクロマンサーが深刻な声で言った。
「あいつらはもう彷徨える屍の集団ってレベルじゃねえよ。ちょっとした軍隊だぜ。」
ウィザーも話に加わる。
「今日お呼びしたのはまさにそのことなの。アカデミーのあの不十分な対応をこれ以上黙認しておくのは忍びなくなってきました。あなたにはこの意味がわかるわよね?」
貴婦人は、その目を細めてネクロマンサーの顔を見た。
「はい。相手がアンデッドの場合、最良の策はこちらもアンデッドの大軍を繰り出すことです。そうすれば少なくとも生者の犠牲は出ませんし、リッチー・クイーンの『死を呼ぶ赤い霧:Crimson Fog Calling Death 』の脅威を事実上無効化できます。手前味噌ではないですが、私は『死霊術士・屍術士共済組合』の主張が正当だと考えています。」
「さすがね。」貴婦人は一層目を細めた。
「とにかくも、このままアカデミーに任せたのでは、事態が悪化する一方なのは目に見えています。それであなたたちにお願いというわけなのです。」
3人は顔を見合わせる。
「調べたところによると、次に奇死団が出没する可能性が高いのは、アカデミーから南西の方角にある『シーネイ村』という名の小さな農村部だということがわかりました。どうやら奇死団は先日遭遇戦のあったオッテン・ドット地区から西部国境を沿岸沿いに北上しているようなのです。そこで、あなたたちにはその村の護衛をお願いしたいの。護衛といっても、一番大切な目的は、奇死団と戦うことではなく、村の人々を無事に避難させて、その被害を最小限に食い止めること。ちょうど、その少し南のところに『アカデミー特務班』」がキャンプを張っていますから、そこまで彼らを安全に誘導していただきたいのです。」
そう言うと貴婦人は、手元のカップを一口傾けた。
『アカデミー特務班』というのは、アカデミーの衛生部門に所属して厚生労働省の直々の指揮で動く、遺体回収のための特別チームである。有力な魔法使いと高度な回復・治癒術式を身に着けた僧侶および聖女からなる文字通りの特別編成で、被災地や紛争地の近くにキャンプを張って、そうした現場で被害者が出た場合に、後日『アカデミーによる葬送』を完遂するため、犠牲者の遺体または瀕死体を速やかに回収するという特別任務を負っていた。彼女たちの実力は折り紙付きで、どのような過酷な現場からであっても、確実に犠牲者の遺体を回収していた。その任務が失敗したのは、ここ10年程の期間でたった1度だけだと伝えられている。
もちろん、それほど速やかな遺体回収が可能なのであれば、彼女たち自身を増援として差し向け、犠牲の回避をまず図るべきではないか、とか、犠牲が出る前に彼女たちに退路を確保させればよいのではないか、などというもっともな批判はあるわけであるが、とにかくも、アカデミーによる手厚い補償という事柄が、まるで麻薬のように人々の批判的思考を麻痺させていたのであった。
「人命救助だな、任せとけってんだ。ついでにあたしが奇死団を壊滅させてやるぜ。」
そう息巻くウィザードを貴婦人が諫めた。
「それはいけません。護身・護衛のために最小限度の交戦をすることは、やむかたないところでしょう。しかし、深追いや全面衝突は絶対にお避けなさい。特に、もしその場にもしリッチー・クイーンが臨場していたら、ほかのことは一切考えないで、村人と一緒に特務班のキャンプまで一目散に逃げるのです。それが約束できないのであれば、今の話は忘れなさい。」
「すまねぇ。」
ウィザードがしょげる。その顔を見て貴婦人が言った。
「大丈夫です。あなたの心根はよく知っています。その正義感と向上心はいつかきっとあなたを大きく成長させるでしょう。ただ、何事も直情に任せてはいけない場合がある、ただそれだけのことです。」
それから、彼女は奥に向かって声をかけた。
「お茶を淹れかえてくださるかしら?」
いつもなら、エメラルドの瞳の少女がよちよちと奥の台所に姿を消していくところである。しかし、件の少女は樽に腰かけてクラッカーをポリポリとかじるばかりで一向に動く気配がない。
そうなのだ。3人が高等部に進級したころ、ちょうどアーカムとの相互連絡が始まった時と期を一にして、ここアーカムに新顔の店員が現れたのだ。
その彼女はいつも、正体を隠すかのようにローブを目深に着込み、魔法の呪印が複雑に施された仮面を顔に身に着けていた。3人はすでに彼女とも馴染みであるが、その仮面の下の素顔を見たことはただの一度もなかった。
アッキーナの話では、北方騎士団との領土境界線にあって小競り合いの絶えない『ノーデン平原』で発生した紛争に不運にも巻き込まれ、その際、顔に大やけどを負い、剰え、その喉は火の熱さによってつぶれてしまったのだったということである。

奥からその女性が、お盆を持って姿を現した。3人と貴婦人に軽く会釈をしたあと、めいめいにお茶をふるまっていく。今日のそれは『マリンガの黒ゴマ茶』という一風変わった風味のもので、強めの薬効とごま油の風味が独特なエスニックなものであった。貴婦人の説明では、飲む者の生命力を高め、次の行動に向かう活力を促進する代物だそうだ。
少女アッキーナとウィザードはこれが少々苦手なようであったが、ソーサラーとネクロマンサーは美味しそうにカップを傾けていた。

* * *
「どうでしょう?引き受けていただけるかしら?」
ウィザードは合点承知という顔をし、人助けならと、ネクロマンサーもまんざらでもない。そのなかでひとり、ソーサラーだけが複雑な表情を浮かべていた。
「相手は、アンデッドの集団なんですよね。」
そういう彼女の瞳には明らかな翳りが見えた。
「私の術式は…。」
そう言いかけたところで、貴婦人が目を細めて言った。
「あなたの心配はわかるわ。あなたは水と氷のソーサラーとしてとても優秀だけれど、対アンデッドということになると、その効果はどうしても限定的になるものね。」
そうなのである。水と氷の術式は、押し流すか凍らせるか、あるいは氷刃のようなもので切り裂くかであるが、それらの特性はことごとく対アンデッドという点では不利に働いた。スケルトンやゾンビのような、腐肉を残すアンデッドが相手の場合には、それでも高水圧で粉砕したり、氷刃で切り裂いたりすることに一定の効果が期待できたが、ゴーストやスペクターなど、すでに腐肉を失った霊的存在に対しては、それらのアプローチはほとんど意味をなさなかった。また、霊的存在を低温によって凍りつかせるということも不可能であるため、ソーサラーは一般に耐アンデッド戦において大きな弱点を抱えていたのである。
これほどの天才でも自分の能力に限界を感じる場面というのがあるのか?ウィザードにとってソーサラーのその反応は意外だった。その場に俄かに重苦しい雰囲気が漂う。
その時だった。『マリンガの黒ゴマ茶』と交換に、その前に飲んでいたお茶のカップを下げるため台所に行っていた仮面の女性が、両手に一振りの剣を携えてその場に姿を現した。
「ありがとう。」
そういうと貴婦人はその剣を女性から受け取り、ソーサラーの前に示したた。
「これは『ソウル・セイバー』という呪われた剣です。しかし、随所にあしらわれた真石パールによって、極めて優れた耐アンデッド性能を有しています。これをあなたに貸し出しましょう。」
そういって、貴婦人はそのまがまがしく青白い光を放つ剣をソーサラーに差し出した。

「ただし、この剣を決して武具としては振るってはいけません。これを剣として振るうたびに、それを握るあなたの手指からは血が奪われ、長く使っているとあなたがアンデッドになってしまします。」
では、どうすればよいのか?そんな面持ちでソーサラーは貴婦人の瞳に見入った。
「この剣は、武具としてだけではなく、術式を引き出す媒体としてもとても優れています。そして、今話したように優れた対アンデッド性能をもっているわけです。つまり…。」
それを聞いてソーサラーがハッとした表情を浮かべる。
貴婦人はその美しい目を一層細めた。
「できると思います。」
ソーサラーは頷いて見せた。
「では、これをあなたに。」
そういうと、貴婦人はソーサラーにその柄を握らせた。
「くどいようですけれど。」
貴婦人は声のトーンを落とす。
「これを剣として振るってはいけません。それだけはくれぐれもお忘れないように。お化けになったあなたになんて会いたくないですから。」
そういって貴婦人は冷めかけたお茶を一口傾けた。
「できるだけのことをやってみます。」
そう言うとソーサラーは身に着けていたローブを脱ぎ、そのむき身の剣を包んで、膝に抱いた。
「それでは、お引き受けいただけるということでよろしいわね?」
3人は頷いた。
「これは、ギルド『アーカム』から、あなた方への初めての正式な依頼です。もちろん報酬はお支払いします。また、万一の時には保険契約に基づいて十分な補償をいたします。」
貴婦人が目配せすると、仮面の女性が保険契約に関する書面をめいめいに渡した。
「それにご署名くださいな。」

その促しを受けて3人は書面にサインをし、用紙を仮面の女性に渡した。その書面には、どのような場合にどのような条件で保険金の支払いが行われ、またその他の補償内容の対象になるか、蟻のような小さな文字で約款がしたためられていた。
「これで契約完了です。みなさんの検討に期待しておりますわ。」
* * *
ここ魔法社会では、アカデミーは教育機関であるだけでなく、実務機関として、また慈善団体としての性格を併せ持っている。
実務機関であるとは、そこに在籍する高等部および一部の中等部の学徒による労働力の提供が、魔法社会に対して実際にされるという意味である。実務の依頼は、各々が所属するギルド、例えばネクロマンサーであれば通常は『死霊術士・屍術士共済組合』からなされ、それを受けて職務に当たるのが一般的な仕組みになっていた。この社会では、彼女たちは10代前半の実に早い時期から経済的自立を迫られており、親元に貴族が多い裕福なソーサラーを別にして、みな何かしらの社会的機能を担わなければ生活を維持できない事情があった。
今回の場合、有力貴族の嫡出令嬢であるソーサラーにとっては、依頼の諾否によって金銭的に窮するということはなかったであろうが、身寄りに乏しいウィザードやネクロマンサーにとっては、ある種の死活問題であったともいえるのである。
いずれにせよ、事程左様にして、3人はシーネイ村の人々の護送任務に着手することになった。
シーネイ村は、アカデミーを中心に据えて地図を見ると、そこから南西に2日ばかり行ったところにある村落で、アカデミー特務班のキャンプはさらにそこから半日ほど南に下ったところに展開されていた。
3人は念のため、衛生部門に連絡を取り、そのキャンプの展開状況を確認したが、貴婦人の説明は当該部門による説明と精緻に一致しており、信頼のおける情報であることが確認された。
『全学職務・時短就労斡旋局の事務所』に寄って、公務遂行のための休暇取得願いを提出する。依頼元を『アーカム』とすることはもちろんできないわけだが、虚偽の情報を記載しても、アカデミーからの照合によって、すぐに露見してしまう。貴婦人が言うには、『南5番街22-3番地ギルド』と書けば大丈夫ということであったので、3人はその言葉を信じてそのとおりに記載した。
ほどなくして公務のための休暇取得は許可され、3人はシーネイ村へと向かう準備に奔走した。水、食料、水薬、回復薬、魔力回復薬、着替え、ローブ、その他の装具に武具、持参すべきものは非常に多い。アーカムで依頼を引き受けた日の2日後、大荷物で達磨のようになった3人がゲート前に集合していた。
「シーネイ村までは、ここから約2日の行程ね。」
そういうソーサラーに、ネクロマンサーが続いた。
「マダムの話では、その北上速度から逆算し、てシーネイ村付近に奇死団が姿を現すと見込まれるのが、約10日後。つまり、現地についてから約1週間、住民の方々の避難誘導に割ける時間があることになります。」
「特務班のキャンプまでは普通に行って半日ほどだから、大人数・大荷物で移動しても1、2日あればたどり着けるだろうぜ。キャンプには十分な物資があるはずだし、特務班の精鋭がそろっているから、そこまでの移動にさえ成功すれば、安全は確保できるはずだ。」
ウィザードが任務の見通しを確認した。
「それじゃあ、行きましょう。」
ネクロマンサーを先頭に置いて、3人は任務への旅路についた。
時はすでに12月の初旬を過ぎて中ごろに差し掛かってる。日々寒さは増すばかりだ。灰色に煙った空から粉雪がちらついている。
人影とも荷物の塊ともつかないその姿は、かすむ冬の気配の中に静かに消えていった。道のりは長い。
第2節『シーネイ村にて』
アカデミーを出発してから、もうずいぶんと歩いた。冬の陽は早々に西に傾き、夜の帳がおり始めている。シーネイ村まで約2日の行程のうち、そろそろ半分を消化したことになる。この道のりにおいては『ケトル・セラー』の街が最後の大きな市街区で、そこを過ぎると一気にひと気はなくなる。手付かずの自然が旅人を歓迎する様相となり、3人は街道を取り囲む森に差し掛かっていた。シーネイ村まで、道はかろうじて整備されてはいるが、それは舗装されておらず、獣道と大差ないものであった。夜間にそこを行くのには大きな危険が伴うことが予想される。特に、この少し南方まで『奇死団』が来ているのだとすれば、その分隊、もしくは『リッチー・クイーン』に引き寄せられた別の『彷徨える屍』と偶発的に遭遇しない保証はない。したがって、森が深まる前に、野営をしようということになった。
「今日はこのあたりにキャンプを張りましょう。」
ソーサラーは荷物を降ろし、あたりを確認しながらそう言った。幸いにして近くに清水をたたえた小川が流れており、水の補給ができそうである。
「さすがこの季節だな、陽が落ちるのが早えぜ。」
荷を下ろし、薪を集めを始めながらがらウィザードがこぼす。
ネクロマンサーはさっそく数体のゴーストを召喚し、テントの設営を手伝わせていた。薪集めを終えたウィザードがそれに魔法で火を起こす。すっかり陽の落ちていた周囲に暖かい明かりが戻った。
「食事にしましょう。」
そういうとソーサラーは焚火に鍋をかけ、持ってきた携帯用の食材をその中に入れる。しばし炒めた後でそこに水といくばくかの食材を追加し、鍋料理を作り始めた。メインの食材は鶏肉で、その他にいくらかの野菜と魚介の干物が添えられていた。それらが鍋の中でぐつぐつと音を立てる。ネクロマンサーは夜中に焚火を絶やさないために、テントの設営を終えたゴーストたちに薪拾いをさせていた。
ソーサラーは鍋に調味料を加えて味を調えながら、鼻歌を奏でている。ウィザードは、3人分の水筒と、何本かの空の薬瓶をもって近くの清水まで水の補給に行った。
冬の空は透明感があり、そのガラスのドームのような天球に、美しい星座がその軌跡を描き始めていた。星々の瞬きは麗しく、月あかりが静かに3人のいるあたりを照らしていた。
「そろそろいいわよ。」
ソーサラーが2人を呼んだ。
彼女は貴族の嫡出令嬢ではあるが、使用人をよく使うためには自らがまず様々なことを知り、経験しておかなければならないという両親の教育方針を受けて、幼少のころから調理・裁縫・掃除といった家事の一通りをわきまえていた。特に料理はよほど腕のよい料理人に仕込まれたのであろう、その手際と味付けは見事なものであった。
3人は、各々の荷物から小ぶりの椀と匙を取り出し、その焚火を囲んでソーサラー自慢の料理を賞味し始めた。用意できる食材は、干物か魔法瓶詰しかないため、それほど凝った調理はできないはずであるが、彼女の手が織りなすその鍋料理は実に美味で、まる1日歩き続けてきた空腹を満たすに充分であった。

3人は、葡萄酒を開けた。ここ魔法社会でも、齢20に満たない者の飲酒は原則として禁じられているが、満16歳を迎えた後は、葡萄酒とビールの飲用についてだけは、適量に限り認められていた。
ウィザードが先ほど汲んできてくれた清水で食事を終えた後の椀を軽くすすぎ、そこに葡萄酒をついで乾杯した。その葡萄酒は例の貴婦人が餞別にと持たせてくれたもので、なんでも体力と魔力の回復に効果があるのだそうである。
「旅の成功に!」

そうして、椀を傾ける。その酸味とアルコールが1日の疲れを癒してくれた。3人は、もう一杯ずつ葡萄酒を椀に入れ、ゆっくりと酔いしれていく。出た話といえば、年相応の少女のものであったが、この3人は特段異性には興味がないらしく、恋の話には花が咲かなかった。
その一方で、おしゃれや衣類、好みのお店から食べ物については大いに話が盛り上がった。アーカムで供されるそこでしか飲めない不思議なお茶のこと、貴婦人がたまにおみやげに持たせてくれる古のお菓子のこと、話はつきることがなかった。ほろ酔いになった3人は、ネクロマンサーを中央にして肩を寄せ合い、互いの身体を温めあいながら、古い童謡を一緒に歌ったりして親交を温めた。その傍らで、ゴーストが集めてきた薪をせっせと火にくべている。
夜もすっかり更けてきた。ネクロマンサーは数体のゴーストを見張りに立て、また護衛用に何体かの力の強い死霊を召還して、テントの周囲に配置した。
この魔法社会では、アンデッドは人間の生活と密接に関係しており、いわば隣人のような関係にあった。それは制御を失うと『彷徨える屍』となって人に害をなすようになるが、召喚者または作成者による制御が効いている間は、実によい労働力であり、時に兵力であって、魔法社会における不可欠の一翼を担っていた。だからこそ、奇死団のように、アンデッドが結託して人を襲うというのはごく身近の差し迫った脅威だったのである。
3人はテントの中で身を横たえ、しばし明日の行程などを確認した後で早々に眠りについた。まだまだ旅の道のりは長い。
月が星々と星座の間を縫うようにして空をゆっくりとかけていく。あたりは一層静けさを増し、ときおり聞こえる獣の遠吠えがその静寂を一層際立たせていた。
* * *
翌朝は美しい晴天であった。清水から霧が立ち上っており、冬の朝日の光を受けてそれはきらきらと輝くヴェールのようであった。まだ時間的には早かったが、不測の事態に備え一刻も早くシーネイに到着しようと、3人は出発の準備を始めていた。テントや寝袋といった大きな荷物はゴーストたちに片付けさせ、その間に3人は清水で顔を洗い、手拭いで簡単に身体を拭いてから焚火の場所に戻った。けなげのゴーストが一晩中火の番をしてくれており、火を絶やすことなく守ってくれていた。
3人はその火で湯を沸かし、簡単に淹れることのできるコーヒーを準備して、昨日と同じ椀に注いで朝食をとった。朝食は乾パンと干し肉、いくばくかの野菜の魔法漬けで、簡単なものではあったが、その日はじめの滋養の摂取としては十分であった。

ゆっくりとコーヒーで身体をあたためながら、その日の行程を確認していく。途中特段のことがなければ、夕方にはシーネイ村落に入れるはずで、今晩はそこで宿をとるか野営するかし、その翌日に村人に事情を説明して、避難活動を開始することで段取りが決まった。今日もほぼ一日歩き詰めになる。コーヒーを飲みほした後、椀をしまい、火の始末を確実にしてから、各々大きな荷物をしょって再び歩き始めた。
荷物をゴーストに運ばせれば楽はできるわけであるが、ゴーストは日中の日差しを極端に嫌う。あまり長時間日光に当て続けると灰になってしまうため、原則として彼らを使役できるのは陽が落ちてからか室内に限られていた。腐肉を残すアンデッドについては日光による灰化の心配こそないが、その肉体は文字通り腐敗が進んでいるためあちこちもろくなっており、荷の重さに耐えられずに気が付いたらどこかで潰れていたというようなことがよくある。そうした厄介を回避する意味で、面倒ではあるが、荷物については自分たちで運搬しようと決めていた。
太陽が東から南に、そして西に、まるで彼女たちの歩みがその原動力になっているかのように、天上を駆けて行く。せっかちな冬の陽がいよいよ地平線に差し掛かろうかというころ、3人の目前に、天然のままではなく人の手で管理された原風景が広がり始めた。シーネイの集落に到着したのだ。とはいえ、まだ街道の脇は田や畑ばかりで人家はまばらであったが、そこから1時間も歩かないうちに、人里にたどり着いた。藁ぶき屋根の小屋が連なる小さな村ではあったが、生活感がありありと感じられ、そこに息づく人々の活気と活力が伝わるようであった。
3人は街道で出会った村人に村長の家を教わり、ひとまずそこを訪ねることにした。陽はすっかり西に傾き、青紫色の空に一番星が瞬いていた。
「ごめんください。」
ソーサラーが先ほど教えらえた家の戸をたたく。村長というからには、それなりに高齢の人物を想像していたが、中から出てきたのは、齢40そこそこの、短い栗毛の髪に碧眼の、美しい顔立ちの女性であった。

「いらっしゃい。旅のお方かしら?」
女性が問うた。
「はい、ギルドの依頼を受けて、現在西方国境を沿岸沿いに北上中の奇死団からみなさんの安全を確保するために派遣されたものです。」
ソーサラーがかいつまんで事情を説明する。
「そうなの。わかったわ。ここじゃなんだからとりあえず入って。」
そういって女性は3人を家に招き入れた。藁ぶき屋根の小さな小屋であったが、その室内は綺麗に整理整頓されており、清潔感に満たされていた。ちょうど食事の準備の最中であったのか、竈にかかった鍋からは空腹を刺激するなんともいえないあたたかいかおりが漂っていた。室内はあたたかく、3人の凍えた身体をやさしく癒してくれた。
女性は3人を食卓につくように促し、自分も席についた。テーブルには6人分の座席があったが、彼女が普段使っているのであろうその椅子以外は、ずいぶん厚い埃に覆われていた。3人はローブの袖で軽くその埃をはたいてから、ゆっくりと椅子に腰を下ろした。
「いま、食事の準備をしているから、ちょっとお待ちね。」
台所から女性の声が聞こえてくる。
「お気遣いなく。」ソーサラーはそう答えた。
「こんなものしかないけれど…。」
そういって女性は寸胴鍋いっぱいにこしらえたシチューをテーブルに運んできてくれた。
「いけません。私たちはご用件をお伝えしたらすぐに失礼しますから。」
そういうソーサラーの横でウィザードはその鍋の中身にくぎ付けになっている。
「遠慮なんてすることないよ。あたしはここで一人暮らしだら、時々こうして何日か分の食事を作り置きするのさ。あんたたちが訪ねて来てくれたのが今日でちょうどよかったよ。ひとりで摂る食事ほど味気ないものはないからね。私に付き合うと思って、一緒に召し上がりなさいな。」
そういうと女性はお椀を用意して、そこにシチューをついでくれた。ウィザードの茜色の瞳がきらきらと輝いている。
「それでは、せめてものお礼に…。」
そういうとネクロマンサーは、自分の荷物からまだ封を切っていない新しい葡萄酒の瓶を取り出した。
「いいのがあるじゃないか。ご相伴にあずかるよ。」
そういうと女性は台所に戻って、木製のコップを4つテーブルに運んできた。
そこにネクロマンサーがゆっくりと葡萄酒をついでいく。
女性が作ったシチューの香りと葡萄酒の香りがあいまって、3人と、そしておそらく今知り合ったばかりのもう一人の女性の空腹と食欲を強く刺激していた。
食事を始める前に4人は自己紹介を交わした。その女性は、ネリーという名で、一昨年までは彼女の父親がここの村長をしていたが、狩りの途中で運悪く彷徨える屍に遭遇し、村の仲間数名とともに帰らぬ人となったのだとのことであった。その後は、公選を経て、村長の仕事を彼女が引き継いでいた。
ネリー村長の用意してくれた食事と、ネクロマンサーが供した葡萄酒は食卓を華々しく彩った。そのシチューは兎の肉を煮込んだもので、その肉は口の中でほどけるほど柔らかく、旅の疲れを癒すには十分すぎるほどの美味であった。香辛料を少し強めに効かせたその味付けは、3人の舌をすっかりとらえていた。

「それで。」
酔いが回ってしまう前にと、ソーサラーが切り出した。
「奇死団のことはご存じですね。」
「ああ、もちろん知ってるさ。ついこの間もここからしばらく行った先にある南の集落がやられたと聞いているよ。」
葡萄酒を傾けながら、リリーはため息交じりにそう言った。彼女が言っているのは、おそらく、白銀の銃砲団の12人の隊員が犠牲になった、オッテン・ドットの遭遇戦についてであろう。隔地の情報が辺境の地域でも共有されているということは、やはりその脅威が着々と間近に迫っていることを物語っていた。
「実は現在、奇死団は西方国境を沿岸沿いに北上していまして、その進行速度から逆算すると、これから約8日後にここシーネイの村落付近に出没することが見込まれています。それで私たちは『南5番街22-3番地ギルド』の依頼により、皆さんの安全を確保するためにここにやってきました。」
相変わらず、理路整然とソーサラーが事情を説明する。
「『南5番街22-3番地』って、聞いたことのないギルドだね?」
ネリー村長はコップを片手に小首をかしげた。それもそのはずである。当の3人も実はそれがどのようなギルドなのか、そもそも実在するのかさえ知らないのだ。しかし、『アーカム』から派遣されてきたというわけにはもちろんいかない。
「これをご覧ください。」
ネクロマンサーが自分の荷から、1巻の書状を取り出して、それを広げて見せた。それは件の『南5番街22-3番地ギルド』による、ギルドの職務と任務についてしたためた一種の辞令ないしはその証明書で、もし身分を証明する必要があるときにはこれを相手に見せるようにと、貴婦人から言われてネクロマンサーが預かっていたものであった。
「この辞令は確かに本物みたいだね。まぁ、この魔法社会にギルドはいろいろあるからね。変なのでなければ、特段気にはしないよ。それで、私たちにどうしろっていうんだい。」
ネリー村長が問う。
「はい、残念ながらこのところ奇死団の勢力は増す一方で、情報通りここに姿を現した場合、対抗する術はありません。」
「もっともだね。」ネリー村長は一口葡萄酒を含む。
「ただ、幸いにして、現在『アカデミー特務班』がここから半日ほど南の地域で大規模なキャンプを展開しています。ですから、まずは村の方全員、ここからそこに移動していただき、その後はアカデミーの指示で市街地に設営された被災地救援所へ移動していただきたいのです。」
「私たちにこの村を捨てろっていうんだね?」
「残念ながら。」
ソーサラーの声が曇る。
「政府軍隊がアカデミーとは別の組織を結成して近々運用を始めるような話も耳にしたけど、そういう応援が得られる可能性はないのかい?」
「はい、現在のところ、政府とアカデミー間の調整が難航しており、あと8日のうちにこの村落全体を護衛するのに十分な増援の到着を期待できる見込みはありません。」
「そうかい…。」ネリー村長が視線を下に移す。
「私たちも最大限の支援と協力をいたします。ですから、どうかご理解ください。」
「そうだね、あんたのいうことがもっともだ。わかったよ、明日さっそく集会を開いてみんなにそのことを伝えるよ。ただね…。」
ネリー村長が言葉をつまらせる。
「あたしゃこの若さだろ。まぁ、あんた達に比べればずいぶん老け込んではいるが、正直村長というには少しばかり威厳が足りなくてね。だから、あたしのいうことを素直に聞いてくれない村民もきっといると思うんだ。彼らをどう説得したものか、少々難しいかもしれないね。」
そう言って、更に葡萄酒を口に含んだ。
「その点については、私たちからも説明と説得を行います。」
ソーサラーがそう言い、ネクロマンサーとウィザードは力強くうなづいた。
「そうだね。あんたらのいうことであれば、耳を傾けるかもしれないね。なにせこんな辺境まで命がけで来てくれたあんた達の言うことだ、邪険にする道理もしなさ。」
そういって、ネリー村長はコップをあけた。
そのとき、夜はずいぶん更けていた。おそらく21時をまわったくらいであっただろう。
「今夜はどうするんだい?」
ネリー村長が訊ねる。
「手ごろな場所を見つけて野営するつもりです。」
ソーサラーはそう答えた。
「この寒い中でかい?」
「はい、昨日も森の中で過ごしました。必要な準備は整えているので、ご心配には及びません。」
「でもね、わざわざ遠くから足を運んできてくれたあんたたちを寒空の下に放り出すというも、こちらの気が引けるね。」
そういってネリー村長は首をかしげる。
「祖父と父が使っていたベッドは処分してしまったから、床で雑魚寝にはなるけど、外よりはましだろうよ。よかったら泊っていきな。」
「しかし…。」
言いよどむソーサラー。
ギルドの職務執行中は可能な限り、現地住民に面倒をかけてはいけないことになっており、救急救命に関する場合を除いて、自立行動をとることが義務付けられていた。
「ギルドの掟は知ってるけど…、母も魔法使いだったからね。そんなこと言わなきゃバレはしないよ。それに何よりこのあたしがあんたたちをちっとも面倒とは思っていないんだ。年上のいうことは聞いとくもんだよ。」
そういって奥の戸棚から何枚かの毛布をとりだし、それを手渡してくれた。
「ありがとうございます。それではお言葉に甘えます。」
ソーサラーは丁寧に頭を下げた。
「この家に風呂はないけど、水場はこの奥にあるから、顔と手を洗うくらいはできるよ。それじゃあ、あたしはもう休むから。また明日。」
そういうと、ネリー村長はベッドのある自室の暗がりへと姿を消していった。3人は教えられた水場で手と顔を洗い、手拭いで簡単に身体をふいてから毛布をかぶって眠りについた。
若くして村を率いなければならない重圧。ソーサラーはネリーのことを考えていた。彼女もまた、有名貴族の嫡出令嬢として常に周囲の期待を背負わされ、息の詰まる思いをすることが多かった。また期待というのは、それに応えられたときはよいが、それを裏切ると思わぬ事態を引き起こすこともある。瞼の裏の美しい黄金色の瞳の上に舞う銀の砂を眺めながら、遠い昔のハンナとの一件を思い出していた。
静かに意識が眠りの中に吸い込まれていく。やがて、銀の砂も見えなくなった。
* * *
翌朝、ネリー村長は早朝から起きだして、各家々を回り、正午に緊急の集会を開くことを知らせて回った。小さな村落であるとはいえ、そこそこの人家があるため、すべての家を回るのに要した時間は2時間を下らなかった。
ソーサラーとネクロマンサーは、出かけるネリー村長から、朝食準備の許可を得ており、せっせと台所を動き回っている。ふたりが朝食の準備をしている間、ウィザードは一人、村に出かけてその集落の状況をつぶさに確認していた。万一遭遇戦となった時の退路の確保などについて考えをめぐらせているようである。
時刻が9時に差し掛かろうとしていたところに遅めの朝食である。パン、ベーコン、鶏卵、サラダ、それにコーヒーとさまざまな料理が食卓を彩っていた。あらかたの準備が終わったところに、ネリー村長とウィザードが戻ってきた。

「こりゃあ、ありがたい。こんなにきちんとした朝食をとるのは何年かぶりだよ。」
ネリー村長の声が弾んでいた。
「おかえり。どうだった?」
ソーサラーがウィザードに訊く。
「とりあえず、正面門を閉めて、裏から村人を順次移動させていけば大丈夫なはずだぜ。あとは時間だけの問題だ。見通しではあと7日。3,4日で移動準備が完了すれば、安全にキャンプまでたどりつけるだろう。」
ウィザードは先ほどの見分の結果を伝えている。
「さあさあ、みなさん。朝食にしましょう。」
そういって、ネクロマンサーが淹れたてのお茶のポットをもって台所から食卓へとやってきた。めいめい席について、朝食のひと時が始まる。
「それで、集会の首尾はどうですか?」
ソーサラーがそう尋ねると、
「正午に開催する予定に決まったよ。一応全部の家が参加するそうだ。あとは、うまく話をまとめられるか、だね。」
そういいながら、パンをコーヒーでのどに送った。
朝食を済ませて、その後片付けをしていたら、正午はどんどんと近づいてくる。4人は、村人に告げる内容、その順番、提案の仕方といった事柄を詳細に打ち合わせ、11時30分に村の集会場へと向かった。
その集会場は古いラファエルの教会を改装したもので、40から50名が一堂に会することのできる広さの場所だった。
4人が到着したとき、すでに何組かの村人が、集会場の中で待っていた。
「今日はありがとう。」
ネリー村長が挨拶をして回るが、その中に一人、彼女の挨拶に対して首を背ける中年の男がいた。村長は気にするでもなく集会場の奥の、かつては説教台であったのだろうところに行って、居住まいをただした。
そうこうしているうちに時刻は正午となり、集会場には村人が一堂に会した。会場内は静かにざわついている。
「みんな、聞いてちょうだい。」
ネリー村長が話し始めた。
「ギルドから派遣された魔法使いのお嬢さんたちの話では、今日から1週間のうちに奇死団がこの村の近くに現れるそうだ。その規模と数からして、あたしたちだけじゃあとても対抗できないから、南に展開されているアカデミーのキャンプまで、みんなで移動することにしたい。」
会場のざわめきが一気に大きくなる。村人は心配そうな面持ちで互いに顔を見合わせていた。
「みんなの心配はよくわかるよ。あたしとしてもなんとかこの村を守りたい。しかし、相手はあの奇死団だ。ついこの間も、ここから南の集落が襲撃されて、偶然居合わせたアカデミーの特殊部隊もろとも全滅したことはみんなも知ってるだろう。村を離れることには生活の心配が付きまとうが、殺されちゃあ元も子もない。だから、あたしは、村長としてみんなに頼むよ。ここを離れて南に移動しよう!」
彼女がそう言い終わるのを待たずして声が聞こえた。
「俺たちにこの村を捨てろというのか?」
さきほどネリー村長の挨拶から顔をそむけた男だ。
「奇死団が来るというが、誰かがそれを見たわけじゃねぇ。第一、ここ数か月この界隈に彷徨える屍は出ていねぇんだ。自分の親父がそいつらに殺されたからって神経質になりすぎてるだけのことだろうよ。」
男は続ける。
「なぁ、みんな。ここは先祖代々守り続けてきた村だ。ここにいようぜ!」
集まった村民の一部からその言葉に対して賛辞が送られた。拍手をしてい者もいる。その一方で、命あっての物種、村長の言う通り逃げるが賢明と言い出す者ももちろんいて、その場は一気に騒然となった。がやがやと議論ともつかない言葉の応酬が繰り広げられた。
どうにも収集がつきそうにないので、ネリー村長は多数決をとることにした。ネリー村長の提案に対して、賛成が21,反対が18が、保留が7という非常に難しい結果となった。
ソーサラーとネクロマンサーのふたりで、現有の戦力では実力による対抗は不可能であること、政府もしくはアカデミーからの増援は期待できないこと、残り日数に限りがあって一刻も早く移動を開始する必要があること、さらには、アカデミーが災害救助施設を用意しているので、そこまで行ってしまえば、当座の生活の心配はないことなどを具体的に説明して見せた。その後に再度多数決をとると、結果は、賛成が30,反対が11,保留が5というように変わった。
しかしながら反対派の一部は実に強硬で、何があってもここを離れることはしないの一点張り。議論は完全に膠着してしまった。ネリー村長が「これは既定の村長決定だ!」としてかまをかけたりもしたが、反対派は聞く耳を持たなかった。幸いなのは保留派が、多数派への恭順の意思を示したことくらいだった。結局その日はそれ以上の説得は難しかったため、ウィザードとネクロマンサーが、賛成派の誘導準備を翌日から開始し、ネリー村長とソーサラーで村の防備にとりかかる、ということでとりあえずの落着を得た。
冬の陽はすでに大きく西に傾いており、濃いオレンジ色の光がその古いラファエルの教会を染め上げている。3人はそこに懐かしい人の瞳の色を垣間見ていた。
ネリー村長が、3人に物見やぐら付きの、今はもう使われていない粉ひき小屋をあてがってくれた。おかげで3人は、当面の準備が整うまでの作戦遂行拠点を得ることができた。そこは古い石造りの小屋で、中は粉と埃と蜘蛛の巣でいっぱいだったが、ネクロマンサーの召喚した幽霊たちはそれをせっせと掃除して、どうにか人が居住できる状態に整った。ウィザードは持参した羊皮紙にこの村の見取り図を描いて、防衛のための計画を練り始めた。
3人にこの場所を提供してくれたとき、その去り際にネリー村長の言った「面倒かけてすまないね。」という言葉が彼女たちの心にとげのように刺さっていた。
冬の陽はすっかり沈み、片付けや掃除を終えた3人が夕飯にありついたのは22時を回ってからのことだった。その日は、乾パンと干し肉、少々の魔法漬けだけを口にして早々に床に就いた。といっても、固い石畳の床の上で、村長が貸してくれた毛布をかぶるだけの簡易な床であった。冬の寒さは厳しくなる一方であったが、幸いにもこの粉ひき小屋には煙突付きの暖炉があり、ウィザードがそこに火を準備してくれたため、寒さをしのぐことはできた。
月が夜空高く青白い光を放ち、その周囲を冬の星座たちが彩っていた。明日からはただでさえ少ない人員を二手に割いて作戦に当たらなければならない。3人は緊張をかかえながら、静かに眠りに落ちていった。
第3節『共闘』
一夜が明けた。冬の張りつめた早朝の空気の中で太陽が光を放っている。
あと6日。急がなければならない。『奇死団』の到着予定と進路はあくまで見込みであって、完全な予測は不可能だからだ。幸い、南に展開する『アカデミー特務班』とは現在も通信機能付携帯式魔術記録装置を介して連絡が取れており、受け入れ態勢は順次整っているとのことであった。速やかに移動されたし、それが彼らからの応答だった。
断固としてこの村落を自ら守るという避難移動反対派が11世帯と無視できない数に上ることから、賛成派をキャンプまで護衛しつつ、反対派とともに村の防衛にあたる二方面の分割作戦を実施することに決まった。
村人の誘導と護衛をネクロマンサーとウィザードが、村の防衛をソーサラーとネリー村長が担当する。本来であれば、対峙すべき敵がアンデッドであることを考えると、対アンデッド効果に優れた魔法特性のウィザードを防衛に残す方が合理的であるが、しかし、護送こそがこの作戦の要であり、その最中に万一襲撃があったことを考えると、やはりそちらにウィザードを回さざるを得なかった。また、護送するキャラバンに怪我人や病人が出た時、回復治療ができるのはネクロマンサーしかいない。したがって、彼女を護送役に回すのは自然な判断であった。
事程左様に、対アンデッド防衛戦において、それを最も苦手とするソーサラーが残ることになったわけである。ソーサラーは、本当にやりきれるのか不安であったが、例の貴婦人が貸してくれた対アンデッド効果を極めたという、呪いの剣もある。また、腐肉を残すアンデッド相手であれば、水と氷の術式も効かないいわけではない。作戦全体の成功を考えれば、この選択が最良である、そう自分に言い聞かせて準備にあたった。
ネクロマンサーは力の強い霊体を数体召喚して、そのうちのひとつを物見やぐらに配置し、残りを周囲の警戒にあたらせた。極度に不足する防衛側の戦力をアンデッドで補強する手段もないではないが、召喚されたアンデッドと召喚者の間の距離があまりに開くと、制御が不安定になる危険があることから、その案は見送られた。見張りの霊体についても、ネクロマンサーと一定以上距離が離れた時には自然に冥府の門に戻るようにあらかじめ設定された。結局、ソーサラーと、ネリー村長率いる村人だけで防衛戦を展開しなければならないことになるわけだが、それはあきらかに無謀であった。今日もまた、その事実を告げて反対派の説得を試みたが、彼らは「先祖の眠るこの地で死す」の一点張りで、3人の説明にも、ネリー村長の言葉にも一切耳を傾けなかった。
なにゆえに彼らがそうまでしてネリー村長に非協力的なのか、その理由をソーサラーが訊ねてみたところ、なんでも、昨日ネリー村長を露骨に無視した反対派の頭目であるハインダスという男は、かつてネリー村長の父親と村長の座を争った経験の持ち主で、その公選に負けて以来、ネリー村長を家族ごと敵視しているのだとのことであった。特に、村長の父親が不慮の事故で亡くなってからは、その敵愾心を強め、ことあるごとに村長の決定や意見に対して敵意をあらわして露骨に反対するのだとのことである(なお、ネリー村長の父親の死後の公選でも彼は得票でネリーに負けている)。「あんな小娘より、俺の方が村長にずっとふさわしい」というのがハインダス氏の言い分であるそうだ。彼に付き従った反対派の残る10世帯は、いわゆる彼の取り巻きで、村長選のときにもハインダス氏を支持した人々なのだという。
いずれにせよ、反対派の人々が避難移動に賛成しない以上、彼らを見捨てて賛成者だけで避難するということはできない。無謀な分割作戦なのは明らかであり、あとできることは奇死団がここを避けて移動してくれることを祈るのみ、もはやそんな状況に追い込まれていた。
* * *
それから2日が経った。奇死団の到着予定まであと4日。避難準備はおおよそ整い、翌日から南下開始となった。見張りの霊体の報告によると、差し迫った危険はまだないようである。少なくとも、避難誘導は無事に完遂できそうだ。問題は村落の防衛作戦の方で、今日までに集落を囲む柵の補強と、正面入り口へのバリケードの設置は終わった。今は反対派世帯に対する護身術等の教練をおこなっている。中には、かつて魔法使いや術士だった者もいるにはいるが、戦力というにはあまりにも乏しかった。ハインダスは『錬金銃砲』を使えるらしく、『魔法銀の法弾』を所持しているとのことで、「アンデッドは俺が全部始末してやる」と息巻いていたが、それは不安解消の材料にはならなかった。
こちらの戦力は、11世帯およそ40名弱。そのうち、女性と子どもだけでも避難させるようにどうにかこうにか説得に成功したため、実際には20名前後、それにソーサラーとネリー村長を加えたのが現有戦力となる。強力な霊体であるレイスが5体いるにはいるが、ネクロマンサーとの距離が一定以上離れた時点で召喚は解消されるので、数のうちに入れておくことはできなかった。
避難準備はいよいよ整い、ネクロマンサーとウィザードは出発の準備を
着々と進めていた。こちらは100名近い大所帯となるため、その誘導は大ごとである。しかし、賛成派の村民が協力的な姿勢を示してくれたため、その翌日には出立できる見通しとなった。
ネクロマンサーが戦力不足を懸念して、召喚者の距離と関係なく使役できるメダリオンによる屍を生成しようと提案したが、残念なことにこの村の風習は火葬であり、土葬ではなかった。メダリオンによる屍の生成には、形をとどめる遺体が必要なのだ。非常に心もとないが、奇死団に襲われた時には、玉砕戦を覚悟するしかない。
その翌日。冬の朝露が明るい陽の中でまばゆい光を放っている。霜が降り、寒さが一段と際立つ朝になった。奇死団の到着見通しまであと3日。
ネクロマンサーとウィザードは避難賛成派の住民とその家族、および反対派に属する女性と子どもたちを集会場に集めて、移動準備の最終段階に入っていた。
「みなさん、準備はよろしいですね。これから、村の裏戸を出て、南に向かいます。本来は歩いて半日から1日の行程ですが、この人数ですからおそらく倍はかかるでしょう。順調にいけば明日の昼頃から夕方にかけて、アカデミーのキャンプに到着できる見通しです。そこまでいけば安全は確保されますから、とにかく慎重に、それでも急いで南下しましょう。」
ネクロマンサーが住民にこれからの説明を行っている。ウィザードは周囲の警戒に余念がない。
朝10時を迎えた。
「それではみなさん、出発します。」
ネクロマンサーの誘導で避難移動が始まった。一行は村の裏戸をぬけ、そのまま道沿いに南下を始めた。死霊たちからは特段の報告はない。どうやら避難は間に合いそうだ。
100名を超える集団の移動は容易ではない。そのすべてがようよう裏戸を抜けて南に向かった後、ソーサラーたち防衛組はそこにもバリケードを設置し、いよいよ籠城戦の構えとなった。幸い、村落の中に川が流れ込んでおり、また井戸もあるため、水に困ることはなさそうだ。ほとんどが穀物ばかりだが、食料も当面の分はある。どのみち、奇死団と邂逅してしまえば、飲食の心配など必要なくなるわけではあるが。
避難組の移動が終わったその日、各村民の配置が決定された。物見やぐらにソーサラー、入り口のバリケードにハインダス氏ほか錬金銃砲を取り扱える者数名を置き、その他は鋤や桑で武装して、ハインダス氏らの背後を護衛するという段取りに決まった。実際、なんとも心もとない布陣であるが、これで対抗するしかない。その日の夕刻にも、「今ならまだ間に合うから」とネリー村長とともに反対派に再度の説得を試みたが、結局徒労に終わった。
冬の陽が暮れるのは早い。寒さに張り詰めた透明の空気がちりちりと肌を刺す。空には、夏のそれとはことなる色とりどりの星座が、思うままに美麗な軌跡を描いてた。運命の日はそう遠くない。ソーサラーは静かに覚悟を新たにしていた。
* * *
その翌日の昼前のことだった。予定通りならば奇死団到達までにまだ3日を残しているはずであったが、周辺警戒にあたっていた死霊の1つがけたたましい声を上げて戻ってきた。幸いにして死霊はまだ残っていた。しかしそれは、避難誘導が難航している可能性を意味するものでもあった。
死霊の言うところでは(腐肉を残す低次元のアンデッドには口を利く能力をすでに喪失しているものも多いが、召喚された死霊や幽霊などの霊体アンデッドとは意思疎通が可能である)、50体前後のアンデッドの一団が、こちらに向かっているそうなのだ。幸いにして、奇死団本体の姿はまだ確認できなかったと、死霊はそう告げて、再び周辺警戒のために飛び立っていった。

「アンデッドの集団がこちらに来ます!その数はおよそ50。みなさん位置についてください。」
ソーサラーが集会場付近でおのおの準備と訓練に勤しんでいた村人たちに声をかけた。そして自身は、物見やぐらへと駆け上がっていく。そこから見通すと、死霊の告げた通り、一塊の黒く蠢く集団がこちらの方に向かってきているのがわかった。おそらくは奇死団の先遣隊か、もしくはリッチー・クイーンの存在に誘われて合流を図る『生ける屍』の群れのどちらかだろう。いずれにしても、このままやつらが進路を変えなければ、この村に侵入してくるのは明らかだ。
村人たちもまた手に武具を携え、打ち合わせた通りに配置についた。アンデッドはゆっくりと近づいてくる。会敵まではおよそ20分というところだろう。村中に緊張が走る。
アンデッドの低い呻き声が耳に届くようになってきた。まもなくだ!ただ幸いにしてこの群れに、飛行可能なものはいないように見える。またそのほとんどが腐肉を残していた。これならやれるかもしれない、ソーサラーは一抹の希望を込めて、貴婦人が預けてくれた呪いの剣の柄を強く握りしめた。
その低く不気味に響く声がいよいよ間近に迫ってくる。バリケードからでももう十分にその姿は見えていることだろう。
刹那、バリケードから何発もの銃声が響き渡る。そのいくつかはアンデッドの群れの数体に命中した。しかし急所を外したのであろう、それらはまたよろよろとこちらに向かってくる。やはり、20名ばかりの現有戦力でこれにあたるのはほぼほぼ絶望的であった。アカデミーが対アンデッド効果に優れるとしてその主張を譲らない錬金銃砲は、事程左様にほとんど役に立ちそうもなかった。
ついに数体のアンデッドが正面入り口に設置したバリケードにとりついた。銃声は続いているが、芳しい効果は得られないようだ。このままではまずい…。しかし、相手が腐肉を残すアンデッドならば!意を決して詠唱を始める。
『水と氷を司る者よ。我は汝の敬虔な庇護者也。わが手に数多の剣を成せ。氷刃を中空に巡らせよ。汝にあだなす者に天誅を加えん!滅せよ。氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swords!』
魔力枯渇を起こさないように慎重に出力を調整して、『氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swards 』の術式を繰り出す。
形成された氷刃は文字通り豪雨となって、迫りくるアンデッドの群れを引き裂かんと飛来していく。やはり、相手が腐肉さえ残していれば十分に効果はあるようだ。50体前後の生ける屍のうちのそのほとんどを蹴散らすことができた。バリケードの付近ではなにやら歓声が上がっている。
やった!そう思った時だった。
霊体と思しき黒い影が、物見やぐらに立つソーサラーの横をかすめる。飛べるアンデッドもいるのか!?反射的に右手に持った呪いの剣を振るってそれを薙ぎ払うが、その瞬間、右手に激痛が走る。みると、右手のひら全体から指の先まで血が色濃くにじんでいた。
「なるほど、マダムはこれを言っていたのね。確かにこれでは命がいくつあっても足りないわ。」そう言ってソーサラーは構えを新たにする。
「飛んでくるものもいます。気を付けて!」
物見やぐらの上から、声をかける。バリケードの付近では、氷刃で倒しきれなかったアンデッドがいよいよそこにとりつき、乾いた木をたたき、それを裂く、けたたましい音を奏でていた。
銃砲の音の位置が変わった。どうやらハインダスたちはバリケードから、村の中ほどに移動したようだ。いよいよ乱戦になる。木戸を打ち、裂く音がいよいよ大きくなり、ついに轟音とともにバリケードが破られた。数はそれほど多くないが、数体のアンデッドが、村落に侵入してきた。ここからではだめだ!そう思い定めて、ソーサラーは一目散にやぐらを駆け下り、村人たちと合流した。相手の数は空飛ぶ霊体を含めて十前後。霊体の数が多い。それさえなんかすれば組せない相手ではなさそうだ。厳しいことに変わりはないが…。
「みなさんは、裏戸の方に移動して!そこに新しいバリケードを築いてください。早く!」
その声に従って、村人たちは後退する。
意を決してソーサラーは呪いの剣を構えて詠唱を始めた。
『生命と霊性の均衡を司る者よ。この法具を通じて汝の加護を求む。彷徨える魂に永遠の安らぎを与えたまえ。冥府の者を冥府に返せ。悪霊への危害:Harm Non Material!』
呪いの剣から虹色の光が潮流のようにほとばしり、不浄の者たちを飲み込んでいく。それに飲まれたアンデッドたちは、まるでその光と一体化するように消えていった。しかし、この術式は腐肉を残すものには効果がないようで、5体ほどの生ける屍を残してしまった。ソーサラーにとって手詰まりとなりつつあったその時、背後でかぼちゃの潰れるような音がした。振り返ると、ハインダスが狙撃銃型の錬金銃砲の柄でソーサラーの背後に間近に迫っていた生ける屍の頭部を叩き潰していた。
「嬢ちゃん、目はあちこちに着けとくもんだぜ。」
そういって彼は不敵な笑顔をして見せた。
「あの、ありがとうございます。」
そう言いかけた時、地を這うような亡者の呻きが聞こえ、なにかがな崩れ落ちるように倒れこむ音がした。
「そういうあんたは、どこに目をつけてんだい?」
声の方を振り向くとネリー村長が手にした鋤で、ハインダスをその右後方から襲おうとしていた生ける屍の胴体を見事に貫き倒していた。
「こりゃあどうも、結構なことで。」
ハインダスは目を丸くしながら、そうおどけて言った。
残る敵はあと数えるほどだ。
「さあ、みんなあと少しだよ。こいつらをあたしらの村から追い出そうじゃないか!」
「へっ、いちいち格好をつけやがる。」
そういうハインダスの顔にはもう反抗心は見えなかった。
「いくぜ、野郎ども!この村は俺たちのものだ。」
そういうと、ハインダスとその取り巻きたちは手にした錬金銃砲を構えて正面から迫りくる残りの敵に照準を合わせた。
「あの世でまた会おうぜ。」
そういうと、何丁かの錬金銃砲が一斉に火を噴いた。
それらはことごとく頭や心臓といった急所に命中し、法弾を受けた生ける屍はほとんどバラバラに飛び散った。周囲に歓声がわきあがる。
「やったぜ!」
「それ見たことか!」
「俺たちの街を襲おうなんざ、100年早え。しっかり熟成して100年後にもう一度来やがれ。」
そんな声があちこちで上がった。
「あんたのおかげだよ、ありがとう。」
ネリー村長がそう言いかけたその時だった。
轟音とともに裏戸側のバリケード脇の柵が破られ、そこから大量のアンデッドがなだれ込んできた。
「なんだい、別口かい?」
ネリー村長が強がって見せる。
「どれだけ来たって同じだ。」
村長をかばうようにしてハインダスが身を乗り出した。
しかし、どう見ても多勢に無勢、おぞましく緩慢に地を這うその腐敗した黒い波に、ここにいる全員が飲まれる運命はもはや確定しているかのように思えた。終わりはいつか来る。早いか遅いか、それだけだ!そう思い定めて体内の魔力を振り絞り『氷刃:Squall of Ice-Swords 』を今まさに全力で放とうとした。
その時だった!
腐った黒い波の背後から、業火の波が覆いかぶさり、一気にその群れを焼き尽くしていった。その巻き上がる炎の先に、見知った顔があった。

「あぶねぇ、あぶねぇ、ギリギリ間に合ったってところだな。」
ウィザードだ!
ふたたび村落の中にどっと歓声が沸き起こる。
「なんでここにいるの?みんなと一緒にいったんじゃあ。」
あの天才の声が上ずっている。
「いやな、避難中もずっと死霊で監視をしてたんだけどよ、奇死団とは全然違う方向に『彷徨える屍』を見つけてな。どうやらそいつらもリッチー・クイーンに呼び寄せられているみてぇでさ。で、あとの事はあいつにまかせて、あたしはとんぼ返りしてきたってわけよ。村に迫るこいつらの群れが視界に入った時には正直もう駄目かと思ったが、どうにか間に合った!」
そういってウィザードは肩を大きく上下させている。
九死に一生とはまさにこのことだ。
ソーサラーはその黄金色の瞳を潤ませて、おもわずその身体をだきしめた。
「ありがとう。」
「おいおい、よしてくれ。あたしにそんな趣味はねぇよ。」
照れくさそうにウィザードが言う。ふと見ると自身を抱きしめるソーサラーの右手が血にまみれているのに気付いた。
「どうしたんだよ、それ。痛くねぇのか?」
「ああ、これね。」
涙をぬぐいながらソーサラーが言う。
「あのソウル・セイバーっていう剣、本当に呪われているのよ。ちょっとうっかり一振りしただけでこんなになるんだから。」
「えげつねぇな、アーカムも。」
そういって、ふたたびふたりは固く抱擁した。
「青春だねぇ。」
ネリー村長がハインダスの方を見て言う。
「ちげぇねぇ。」
ハインダスは片目を閉じて返した。
時刻は夕刻に差し掛かっていた。長く伸びた冬の陽が赤くシーネイ村を照らしている。ひとまず危機は去った。しかし、先ほどこの村を襲ったのは奇死団の本体ではない。その到着は目前に迫っていた。いずれにせよ覚悟を決める必要がある。誰もがそう思った時だった。
おもむろに、ウィザードの通信機能付光学魔術記録装置に着信が入った。マジック・スクリプトはアッキーナのものだ。
* * *
「みなさん、ご無事ですか?」
その声はアッキーナ婦人だ。
「おぅ、なんとか、まだ生きてるぜ。といっても、奇死団本体が来たら終わりだけどな。もう手の打ちようがねぇぜ。」
「そのことなんですが、奇死団は当初の北上ルートをはずれて『ミレイの森』を抜け『アナンダ氷原』に集結しつつあるようです。」
「そりゃまたずいぶん東じゃねぇか!どうなってんだよ。」
「わかりません。ただ、どうやらそこが奇死団の最終目的地のようで、各地から彷徨える屍の集団が呼び寄せられるように集結しています。」
『アナンダ氷原』とは、北方騎士団と国境を接する『ノーデン平原』にも連なる場所で、アカデミーなどが存在する中央市街区からみると北西方向、シーネイ村から見ると北東方向に位置する万年の氷原である。そこはかつてアカデミーの命により作戦に赴いた若いソーサラーが、それに失敗して命を落とした場所でもあった。その魔法使いは、齢17歳にしてその短い生涯を閉じたが、その事件が他の悲劇と大きく違ったのは、アカデミー特務班が彼女の遺体の回収に行ったとき、それがすでに失われていて、ただ、彼女がいたであろうと思しき場所に、禍々しい残留魔力を放つ、魔法陣の跡が刻まれていたことであった。結局、その真相は伏せられ、その人物は作戦の犠牲になったものとして、しめやかに『アカデミーの葬送』が執り行われた。もちろん、その棺は空っぽであった。
* * *
その夜は宴会だった。奇死団がその進行ルートを大きく変えたことで、シーネイ村への脅威は去ったのである。奇死団の目的が明らかでない以上、この村が再び襲われる危険は皆無ではないが、アッキーナ婦人の連絡によれば、当面の危機が去ったことは間違いない。ネクロマンサーとも連絡が取れ、結局、避難を継続する人々はそのままキャンプ経由でアカデミーの災害救助施設に移動し、村に戻る選択をした人々は、明日ネクロマンサーとともに移動してくる手はずに決まった。
宴会の場では、あれだけ険悪な空気を醸し出していたネリー村長とハインダス氏が串焼きとビールの入ったコップをもって談笑している。きっと、完全に、とまではいかないのであろうが、しかし、互いに協力して助け合い、命を救いあったことで両者の間に連帯感のような情が芽生えたことだけは間違いないようである。きっと、今後この村をよくまとめていってくれるだろう。
そんなことを考えながら、ソーサラーはひとり葡萄酒の入ったコップを傾けていた。
「おい、食わねぇのか?」
両手に乗せた皿の上にこれでもかと料理を盛ったウィザードが声をかける。
「あなたはおなかペコペコみたいね?」
「そりゃそうよ。もう半分も行った先から、全力で走って戻ってきたんだぜ。腹も減るさ。」
「そうね。本当にありがとう。」
そういうと、ソーサラーはウィザードの頭に手を回して、自分の額を彼女の額にそっとくっつけた。」
「よせやい。」
そういうウィザードの顔は真っ赤だった。
「さぁ、食おうぜ!」
ふたりは風車小屋の入り口に置かれていた古い木のベンチに腰かけて、料理をほおばった。そのあとにのどに送るビールが格別である。ふたりの談笑はいつまでも絶えることがなかった。
夜空はその透明感を一層増し、数多の星々が白く瞬いている。張り詰めた空気の冷たさを、村落のあちこちで行われている焚火の熱が和らげていた。ふと冷たいものを感じる。雪だ。美しい空に、ちらちらと粉雪が舞っていた。いよいよ冬が深まっていく。
翌々日の朝方、村に残る選択をした避難民を連れてネクロマンサーが戻ってきた。
「大変だったみたいですね。大丈夫ですか?」
「ええ、この通りよ。」
そういってソーサラーは村全体を見せるように腕を振った。
「防衛作戦、成功ですね。」
「おうともよ。」
そういう彼女たちに、ネリー村長が声をかけた。
「あんたたちのおかげで、この村を守ることができたよ。本当にありがとう。」
「嬢ちゃんたち、大したもんだ。見直したぜ。」
ハインダス氏がいたずらっぽく笑う。
「それでは、私たちはこれからギルドに帰還します。」
ソーサラーが別れを告げる。
「大変お世話になりました。」
続くネクロマンサー。
「しばらくは、警戒を怠らないでくれよ。」とウィザードが言った。
「こちらこそ。あんたたちも道中気を付けるんだよ。」
「この村のことは、俺たちに任せてくれ。何度だって守って見せるぜ。」
それから3人は帰路についた。アーカムまではここから約2日かかる。
「気長に行こうぜ!」
そういって笑うウィザードとともに、3人の姿は街道を取り囲む森の中に消えていった。
昨晩からの雪がしんしんと降り続いている。
第4節『愛と喜びを分かつ約束』
リッチー・クイーン率いる『奇死団』の脅威はいよいよ高まりを見せていた。アナンダ氷原に駐留するその本体に、各地から『彷徨える屍』が合流してきており、辺境集落のいくつもが、奇死団の本体および合流を図る彷徨える屍によって蹂躙され壊滅させられていた。その規模はすでに一個師団にも及ぶという試算さえあるほどで、アナンダ氷原には夥しい数のアンデッドの群れが結集していた。
そこは、アカデミーや政府庁舎の集中する中央市街区から見て北西方向に位置しているが、その距離はさほど遠くなく、彼らの最終目的は、この魔法社会の中枢機能の破壊であろうというのがもっぱらの噂となっていた。いまだ氷原から動く気配を見せないものの、魔法社会全体においてその脅威は最高潮に達しようとしていたのである。
政府は、アカデミーの対応を手ぬるいとして、有力な魔法企業である『ハルトマン・マギックス』社に対し、対アンデッド用の特殊法弾『人為のルビーの法弾』の開発を特別に要請した。同社はそれをうけ、法弾のみならず、その機能を最大限に引き出すことのできる『専用の錬金銃砲』を完成させることで応えてみせた。政府軍事部門は、アカデミーの最高評議会を飛び越えてその私設軍事部門と独自の取り極めを交わし、アカデミーの優秀な学徒を選抜して対奇死団専門の『ルビーの特殊銃砲団』を結成、その脅威への準備を進めていた。ただ、ハルトマン・マギックス社製の、新錬金素材『炎鋼』をベースとするこれらの銃砲と法弾は、対アンデッド性能という点でこそ従来の装備の性能を大きく凌駕していたが、リッチー・クイーンの行使する、死霊術の奥義『死を呼ぶ赤い霧:Crimson Fog Calling Death 』、および彼女の能力を際立たせる『苦痛と苦悩を分かつ石』に対する対策は甚だ不十分なものであった。しかし、ただ座して死を待つわけにもいかぬ政府は、その特殊部隊を今まさにアナンダ平原へと派遣しようとしていたのである。
* * *
― 8年前 ―
これは今につながる過去の物語
「マリーお姉さま。」

魔法学部純潔魔導士科 高等部2年 専攻ソーサラー
かわいらしい声が聞こえる。あれはグランデね。そう思って振り返ると、高等部の学徒にはおよそ似つかわしくない『制御の魔帽』をかぶった少女が駆けてきた。
この子の名は、グランデ・トワイライト。飛び級を何度も重ね、若干12歳にしてソーサラー科の高等部に進級してきた稀代の天才ソーサラーである。それゆえ、安定した魔力制御のために着用が義務付けられる『制御の魔帽』をいまだに身に着けていた(遺伝的に特別に大きな魔力特性をもつソーサラー科の学徒は、満13歳に至るまで、学則によってその着用が義務付けられている)。
「どうしたの、グランデ?」
そう言うと少女はひとつの法石らしきものを取り出して言った。
「あの、これを作ったんです。」
その石は、シルクに覆われたようななめらかな部分と、カットにより美しい光沢を放つ部分とが巧みに入り混じった青白い魔法光を放つ、見事な人為の法石であった。
「驚いた!あなたがこれを錬成したの?」
「はい、この間、マリーお姉さまが教えてくださった錬金術と魔法の応用を試してみたんです。」
「へぇ~、あなたって、本当に天才なのね。あの基礎理論だけで、本当に法石を錬成するなんて。」
そういうと、少女はその小さな顔を恥ずかしそうにうつむけた。
「そんなことないです…。」
「ほんとうに見事だわ。これにはどんな効果があるの?」
「それは『愛と喜びを分かつ石』といって、それを与えた者と、持っている者との間で愛と喜びを分かちあい、それらを倍増することができるのです。それで…。」

少し言いよどんでから、少女は続けた。
「私は、それをお姉さまに持っていてほしいのです。お姉さまと私の、ふたりの間の愛と喜びを増し加えるために。」
「まぁ、とても素敵ね。じゃあ、これはもらってもいいのかしら?」
そう聞くと、少女は小さな頭をこくこくと頷けて見せた。その上で大ぶりの制御の魔帽がゆさゆさとゆれている。
「ありがとう、グランデ。」
そう言って、私は自分のローブに嵌められていた法石を外し、グランデのくれたその『愛と喜びを分かつ石』を取り付けた。
「どう、グランデ。似合う?」
「はい、お姉さま。」
そういうグランデの笑顔は真夏の太陽を一身に受けて咲き誇るひまわりのようであった。
「大切にするわね。」
「はい。」
高等部在籍者の平均年齢はおよそ17から18歳といったところである。そのため、この幼いグランデがその環境に馴染むことは容易でなかったであろう。ただ不思議なことに、編入の初日からこの子は妙に私に懐いてくれた。末娘の私にとって、妹のようなその存在はものすごく新鮮で、私たちはそれほどの間をおくことなく親交を温めるようになっていった。お互いにソーサラーだからということもあるが、街に買い物に出かけた時などは、本当の姉妹に見間違えられることもしばしばであった。
このかわいらしい妹をずっとそばに置いておきたい、グランデにはそんな気持ちにさせる魅力があった。
* * *
そう考えていると、グランデが私の履いている『増魔の魔靴』を不思議そうに眺めているのに気が付いた。
「どうしたの?」
そう訊くと、グランデは小さな首を少しかしげてこう聞いた。
「お姉さまの履いていらっしゃる増魔の魔靴はみなさんのものとはずいぶん違うのですね。それはどちらのブランドのどのような商品なのですか?」
教えようかどうしようか少し躊躇ったが、彼女には伝えることにした。
「いい、グランデ、ここだけの秘密よ。」
そういうと、彼女はまたこくこくと頷く。魔帽が優しく前後する。
「これはね、『古代屍術の魔靴』といって、実は禁忌法具なの。」
グランデの目が大きく丸くなる。
「危なくないのですか?」
「もちろん大丈夫よ。これは身に着けているだけで呪われるということはなくてね。力を引き出すには自分の意志でそれを解き放つ必要があるの。だから、普段は全然平気よ。でもね、とても強い力を持っているから、私は愛用してるわ。」
「そうなのですか。でも、絶対にその力を使わないでくださいね!」
グランデの声が大きくなる。
「大丈夫よ。そんなことしたらグランデに会えなくなるもの。」
「信じてますから!」
そんな話をしているうちに、午前の講義開始を告げる予鈴が聞こえてきた。
「それじゃあグランデ。またお昼にでも会いましょう。」
「はい、マリーお姉さま。」
そうして私たちはそれぞれの教室へと向かった。
季節は12月の中旬を迎え、あたりはどんどん寒くなる一方だ。北方の平原や氷原はすでに雪と氷に覆われていることだろう。そう思って窓の外を眺めると、粉雪が舞っていた。23日はグランデの誕生日だ。24日の生誕祭とあわせて盛大にお祝いをしよう。そういえば、グランデのほしいものをまだ聞いていたかった。あとで確かめておかなければ。そんなことを考えながら、午前の講義に集中していった。
こんな穏やかな日々がいつまでもつづけばいいのに…。
* * *
そんなある日のことだった。アカデミーの学徒に様々な職を斡旋する『全学職務・時短就労斡旋局』を経由して、私は、アカデミー最高評議会から呼び出しを受けた。当局を経由したということは、何らかの任務が与えられるのは間違いなかったが、呼び出し元が最高評議会というのは驚きだった。なんだろう?初めてのことで一抹の不安を抱えながら、アカデミーの中央尖塔に位置する最高評議会の議場へと向かった。ここに来るのは高等部進級のための口頭試問の時以来だ。
ドアをノックすると「入れ!」という声が中から聞こえた。
「失礼いたします。」
そういって静かにドアを開け入室すると、そこは何かの儀式を執り行うような荘厳な構えを見せていた。」
いよいよ不思議になって、戸口であたりを見回していると。
「進み出よ。特別の辞令を交付する。」
そいう言われたので、辞令書を持っているらしい評議員の前おずおずとに進み出た。
「マリアンヌ・イゾルデ。汝に『禁忌術式』の使用命令付き使用許可を下す。」
それを聞いて耳を疑った。禁忌術式へのアクセスは上等位階に進んでからでなければ原則として許可されない。高等部の段階で不正アクセスすれば、最悪退学にもなる、そんな代物だ。評議会はそれを私に「使え」と命じている。全身に緊張が走った。
「よく聞け。これから、汝はアナンダ氷原に赴き、ノーデン平原の本体から分かれた北方騎士団の分遣隊、その数およそ300を許可された禁忌術式の使用により撃滅せよ。これが今回の、最高評議会からの汝への特別辞令である。」
そういうと前に立つ評議員がうやうやしくその辞令書を私に手渡した。
「質問はあるか?」
この問いは儀礼であって、最高評議会の命令に質問したり意見を述べたりすることは許されていない。
「ございません。マリアンヌ・イゾルデ、謹んで辞令を拝領いたします。」
「よろしい、それでは直ちにソーサラー科の研究棟に向かい、禁忌術式へのアクセス手続きを済ませたまえ。必要な準備はこちらで済ませてある。以上だ。」
「かしこまりました。」
「なお、報酬・保険その他の事務手続きについては、全学職務・時短就労斡旋局から別途連絡する。行きたまえ。」
「はい。」
そういって私は評議会の議場を後にした。
まさか、私に評議会直々に禁忌術式の使用命令付き使用許可が下されるとは思ってもみなかった。それは、私の実力が評議会に認められたということでもあり、名誉なことなのは確かである。しかし、禁忌術式とは、その効果において敵味方を識別しない全領域無差別殲滅魔法であって、その行使が前提となる作戦には、犠牲を避けるために味方を伴うことはできず、たったひとりで臨まなければならない。今回の場合、私ひとりだけで、実に300騎の兵力を相手にしなければならないことを意味していた。故に、この辞令は学内では『死刑宣告』として恐れられてもいた。
極度の緊張が身体に走るのがわかる。しかし、アカデミーの、とりわけ最高評議会の命令は絶対だ。覚悟を決めるしかない。ソーサラーの禁忌術式の殲滅性は群を抜いていると聞く。幸いにして相手は組みしやすい北方騎士団の兵員だ。油断さえしなければやりおおすことはできるだろう。胸元の愛と喜びを分かつ石を固く握りしめて、自分にきつくそう言い聞かせた。
* * *
辞令を受け取ってから研究棟に向かう前に、荷物を取りに教室に戻ると、偶然そこにグランデの姿があった。
「マリーお姉さま。」
小さなグランデが駆けよってくる。
「まぁ、グランデ。午後の予定はもう全部終わったの?」
「はい。お姉さまはこれからどちらかへお出かけですか?」
「ちょっとソーサラー科の研究棟まで行ってくるわ。」
「そうなのですか。私もお供してかまいませんか。」
いつもならば、一緒に連れて行くところだが、今日はそうもいかなかった。
「ごめんなさいね。グランデ。実はね…。」
そういって私はグランデに事の次第を説明した。
「お姉さま、それって!」
グランデが目を潤ませ、いまにも泣き出しそうな顔をする。
「大丈夫よ、グランデ。どうしてそんな顔をしているの?」
「だって、だって…。みんながそれは死刑宣告だって…。」
その美しい青い瞳から、いよいよ涙が零れ落ちそうだ。
「確かに危険な任務には違いないけれど、相手は北方騎士団の分隊よ。特別強力な魔法使いを相手にするというわけでもないわ。だから、何も心配しないで待っていてちょうだい。24日にはあなたの誕生日会を兼ねて楽しい生誕祭を一緒に過ごしましょう。」
そういうと、その顔にわずかだが安堵の表情が戻ってきた。
「そういえば、まだ聞いていなかったわね。グランデは、今年のお誕生日には何が欲しいの?生誕祭の分も合わせて奮発するわよ。」
グランデは少しうつむいてから、照れくさそうに言った。
「あの、お姉さまに、マリーお姉さまに『増魔のリボン』を結んでほしいです。」
「そうか、もうすぐ13歳だものね。」
増魔のリボンとは、13歳以上の中等部の学徒、および高等部の学徒が制御の魔帽の代わりに身に着ける魔法具のことで、学内ではちょっとした大人の証、というような性質をもっていた。グランデは、ようやく制御の魔帽をかぶらなくてよい歳になるので、私に、そのリボンを自分の頭に結んでほしいと、そう言っている。
「いいわよ。とってもかわいいリボンをあなたに結んであげるわ。」
「本当ですか!?きっと、きっと、約束ですよ。」
その瞳はまだ涙で潤んでいたが、しかし、喜びと期待の光を同時に灯していた。胸元の愛と喜びを分かつ石がほんのりと魔法光を浮かべている。なるほど、これが愛と喜びを分かち合うということか。グランデの喜びが自分自身の喜びであるように感じられた。
「きっと、約束。だから、なにも心配しないで、待っていてね。」
「はい!」
天真爛漫なその笑顔は私の心をとらえて離さなかった。
冬の陽は短い。あたりはすでに明るさを失っている。
「さあ、もう暗くなるわ。ほんとうに陽が短くなったわね。送っていくわ。」
そういって私はグランデのまだ小さな手を引いて寮棟まで連れていき、それから研究棟へと向かった。雪がしんしんと降り続き、足元に積もった雪が静かにきしんでいる。いよいよ冬本番だ。アナンダ氷原か…。きっと雪と氷に深く閉ざされた場所なのだろう。辞令のことを思い出しながら、私の足は研究棟に向かう上り坂に、雪の足跡を刻んでいった。
* * *
12月20日。グランデとの約束の日まであと4日。
ついに、辞令が命じるその作戦を決行する日が来た。アナンダ氷原の南に展開されたアカデミー特務班のキャンプを出発したの夕方のことだ。十分な防寒装備をととのえ、その上から魔法特性の極めて高い『金縁のローブ』を着込んでいるが、それでも身体を裂くような寒さが襲ってくる。陽が完全に沈み切る少し前に作戦遂行地点に到達した。まだ北方騎士団の姿は見えない。作戦概要では、その分隊の全容を捉えた時点で、こちらに気づかれる前に禁忌術式によって殲滅することとされていた。
いよいよ陽は沈み、これまでに周辺の雪と氷を照らしていた陽の光が、月と星によるものに次第に変わっていく。太陽は地平線のぎりぎりのところでゆらゆらと揺れていた。不気味に寒さが増してくる。しばらく目を凝らしていると遠くに移動する物陰が見えた。
来た!確実に殲滅するには、十分に引き付ける必要がある。身構えてその動向を見守る。その影が次第に近づいてくる。
おかしい…。北方騎士団は基本的に騎馬兵だ。たとえ常歩で進んでいるのだとしても、進軍速度がこんなに遅いはずがない。俄かに緊張が高まってくる。そうこうしているうちに、一団の上空を飛び回る、明らかに鳥とは違う影が視界に入るようになってきた。
まさか!息をのんで警戒にあたる。アカデミーが、まして最高評議会が間違った情報をよこすはずがない。しかし、あれはどう見ても人間の姿ではないように見える。いよいよその影が近づいてきた。そして、夕日の残光の中にその姿がはっきりと照らし出された。
あれは北方騎士団なんかじゃない。アンデッドの群れだ!

まだ十分な距離がある。今なら特務班のキャンプまで撤退して、対処法を考えることもできる。しかし、そんなことをしたのではグランデの期待を裏切り、彼女に恥をかかすことにもなりかねない。
アカデミーの任務では、事情にかかわらず、撤退は作戦の一次的な失敗を意味する。まして、最高評議会の命令をしくじるというのは、大きな失態以外のなにものでもなかった。
きっとやれる!胸元の愛と喜びを分かつ石をぐっと握りしめて私は立ち上がった。いよいよ太陽がその姿を地平線の裏に隠そうとしている。アンデッドとの距離はもう十分だ。これ以上は危険ですらある。私は詠唱を始めた。
『水と氷を司る者よ。その胸中を開き、汝の敬虔なる庇護者に神秘の秘術を授けたまえ。禁じられた知性への道筋を示し、我に奇跡をなさしめたまえ。いま、大気と大地を絶対の低温で覆わん。すべての生きとし生けるものから生命の炎を奪おう。殲滅せよ!絶対零度:Absolute Zero!』
詠唱が終わるや、自然界では絶対にありえない低温があたりを覆いつくす。迫りくるアンデッドの群れは、瞬く間に凍り付いて動かなくなった。

あたりは静寂につつまれ、風の音以外には何も聞こえなくなった。目の前のアンデッドたちは氷と寒さによって完全に動きが止まっている。
やった!
そう思った時だった。氷が裂け、雪がきしむような音が聞こえて、あたりの動かないはずのものが、再びその活動を再開した。
「そんな馬鹿な!!」
最大級の禁忌術式をまともに受けて、アンデッドといえども活動を継続できるはずがない!しかし目の前の現実は、私の知っていることとは厳然と異なる様相を示していた。重苦しい影が再び私に迫ってくる。逃げるしかない!そう思い定めた時、足元からも無数のアンデッドが姿を現し、すっかり取り囲まれてしまった。残った魔力を使って『氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swords 』を繰り出し、退路を確保しようとするが、多勢に無勢、それは無数にわき続けるかのように私の周りを囲んでくる。そうこうしているうちに、迫りくる本体にも追いつかれてしまった。
「どうしてこんなことに…。」
その場から駆けだそうとした瞬間、雪の中から手を伸ばしたアンデッドに足首をつかまれ、私はそこにひざまずいてしまう。
私はここで死ぬのか?差し迫る死の恐怖がいよいよ現実となりつつあった。嫌だ。もういちどグランデに会いたい。彼女が贈ってくれた石を強く握りしめる。あの光り輝くような笑顔をもう一度見るまでは、彼女の頭に増魔のリボンを結んでやるその約束を果たすまでは絶対に死ねない!!
そして私は足首を掴むその穢れた手を振り払い、祈るような姿勢で詠唱を始めた。
『古代の魔を司る者よ。我が願いを聞き入れたまえ。我が肉体をささげよう。引き換えに屍術の奥義をなさしめん。我が名はマリアンヌ・イゾルデ!我と契約し、我に永遠の命を授けよ!古代屍術:Ancient Necromancy!』

履いていた古代屍術の魔靴からおぞましい色の魔力が漂い、私の周囲に禍々しい色の魔法陣が展開した。周囲のアンデッドたちもその魔力に圧倒されたのか、明らかに怯んでいる。
「待っていて、グランデ。約束はきっと果たすわ。」
その後、私の自我は暗い渦に飲み込まれていった。あぁ、グランデ…。
* * *
アカデミーの遺体回収特務班が、マリアンヌの作戦執行予定場所に到達したのは、それから数時間後のことであった。彼女たちが現場に到着したとき、アンデッドの群れはすでにその姿を消しており、同時に、そこにあるべきマリアンヌの遺体もまた忽然と姿を消していた。
特務班は何組かの捜索隊を結成して、周囲の相当範囲を捜索したが、結局彼女の遺体を発見することはできなかった。このようなことは、特務班にとっては初めての経験であった。
やむなく、捜索隊を撤収してキャンプに帰還した。事態をありのままに報告すると、特務班の指揮官であろう男が言った。
「おそらく、彼女の遺体はアンデッドに捕食され、跡形もなくなったのだろう。これ以上の捜索は必要ない。ご苦労だった。」
回収特務班の面々は責任を追及されず安堵したという面持ちであったが、その傍で、その指揮官らしき男はなにかほくそ笑むような不気味な表情を浮かべていた。
その後、アカデミーでは、犠牲者マリアンヌ・イゾルデを悼んで荘厳なる葬送の儀式が挙行された。参列したグランデはもはや涙におぼれていた。その小さな心は喪失という大きな穴にひどく苛まれており、その空虚はいまなお彼女の心の中で満たされていない。
― それから8年の月日が流れた ―
グランデは齢21となり、母のユリア・トワイライトが経営する一大魔法具チェーン『グランデ・トワイライト』の主任デザイナーを務めている。マリアンヌのことはずっとその心に留まり続け、彼女は会社の研究室にこもって商品の研究開発に没頭していた。そのあまりの集中と情熱(というより悲しみを忘れるための没頭)の姿に、両親は深く心を痛めていた。
特に娘を愛してやまない父のアルフレッド・トワイライト卿の心痛にはただならぬものがあった。娘に対する父のその愛情はどう報われるのか?グランデのその顔に、再びあのひまわりのような燦然と輝く笑顔が戻ることはあるのか?マリアンヌの死の真相は?
時の歯車はそれぞれを噛み合わせて、新たな時を静かに刻み始めていた。
第5章
第1節『思いがけない依頼』
リッチー・クイーンと奇死団の脅威は魔法社会においていよいよ高まりを見せていた。いまだアナンダ氷原から動く気配を見せないものの、一団に属する死霊たちが南東方向、すなわちアカデミーや政府庁舎のある中央市街区の近縁にまで頻繁に出没するようになり、侵攻の前触れではないかとして、人々を大いに震撼させた。
アカデミーが差し向けた『ルビーの特殊銃砲団』は、リッチー・クイーンの存在しない場でこそ目覚ましい戦果を上げたが、アナンダ氷原にごく近い場所で彼女が臨場した遭遇戦において、その全員が『死を呼ぶ赤い霧:Crimson Fog Calling Death 』の犠牲となってしまった。彼女の身に着ける『苦痛と苦悩を分かつ石』の効果もまた脅威であり、彼女を迂闊に攻撃することはできず、政府およびアカデミーには、ただただその動向を探るよりほかに、できることはほとんどなかった。
事態が長い膠着状態に陥っていたあるとき、『全学職務・時短就労斡旋局』経由で例の3人に呼び出しがかかった。
彼女たちは今その事務所に集まっている。
「君たちに集まってもらったのは他でもない。例の奇死団について相談したいという御仁が来られている。厚生労働省のマークス・バレンティウヌ氏だ。」
当局の担当官はそういって一人の男を紹介した。
その顔を見た3人は驚く。そう、その人物こそ、分不相応に『アカデミーによる葬送』に毎回参列していたあの男であった。

「ご紹介にあずかりました、マークス・バレンティウヌです。厚生労働省の技官を務めています。はじめまして。」
そういって、その男は手を差し出した。
ネクロマンサーは握手を交わし、こう言った。
「はじめまして、『南5番街22-3番地ギルド』の者です。」
「存じ上げております。さあどうぞ。まずはおかけください。」
そう言うと彼は3人に席を進め、そして自分はその対面に腰を掛けた。
「シーネイ村でのあなた方の活躍は聞いています。」
男はそう切り出した。
「それで、対アンデッド戦において実績のあるあなた方にお願いがあって本日は参りました。」
「それはどのようなことでしょうか?」
ネクロマンサーが訊ねる。
用意されたコーヒーを一口含んでから男は続けた。
「奇死団とリッチー・クイーンのことはもはや言うまでもありませんね?」
3人は頷く。
「実は、リッチー・クイーンは、かつてこのアカデミーの学徒だったのです。」
男は驚くような事実を告白した。3人は思わずその男の顔に見入る。
「今から8年前、不慮の事故によって絶体絶命に陥ったマリアンヌ・イゾルデという女学徒が、死の間際に禁忌の屍術の力を解放してリッチー・クイーンに姿を変えたのです。」
なぜ男はそんなことを知っているのか?そんなことが3人の胸中を駆け巡ったが、そんな彼女たちの動揺を慮るでもなく男は続けた。
「私は、彼女、そうマリアンヌ・イゾルデを呪われた屍術から解放したいと考え、そのための力を借りるべくこうしてあなた方を訪ねたのです。」
「しかし、すでにアンデッドの魔法使いになった人物を救い出す方法などあるのですか?」
訝しそうにネクロマンサーが訊ねる。
「ご懸念はごもっともです。ただ、私の研究によるとその方法は確かにあります。」
男は意味深に語り続けた。
「『古代屍術の魔靴』の力を解放して最高死霊(リッチ)となった者は、その体内に『魂魄の結晶』という秘宝を内包します。それを彼女の体内から摘出することで、彼女に人間の意識を戻させることができるはずなのです。」
「しかし、どうやってその秘宝を取り出すのですか?彼女の周りは師団規模のアンデッドが取り巻いていますし、なにより彼女自身の力が強大すぎて、私たちだけではどうにもなりません。」
ネクロマンサーは隠すことなく懸念を伝えた。
「あなた方が言っておられるのは『死を呼ぶ赤い霧:Crimson Fog Callign Death』と『苦痛と苦悩を分かつ石』のことですね?ご心配はよくわかります。事実私たちもその点に手を焼いています。」
ふたたびコーヒーカップを傾けながら男はそう言った。
「しかし、ひとつだけ方法があるのです。周囲のアンデッドはすべてリッチー・クイーンに呼応し、彼女の命令で動いています。つまり、彼女の動きを封じれば、活路を開くことができるのでる。ただ、そのためには彼女が持つ『苦痛と苦悩を分かつ石』を何とかしなければなりません。
「それは、その通りだと思います。」
ネクロマンサーは冷静に対応する。
「その石について、分かったことがあります。それはグランデ・トワイライトという人物が、アカデミー在学時に彼女に送った人為の法石がもとになっている可能性がありまして。それで、製作者のグランデ・トワイライト氏ならば、その石の効果を止めるための方法になにか心当たりがあるのではないかと、我々はそう考えているわけなのです。」
そう言うと男は、「失礼」とひとこと断ってから煙草をくゆらせた。
「それで、私たちにどうしろとおっしゃるのですか?」
ネクロマンサーが訊ねた。
「はい、あなた方にはグランデ氏を訪ねていただいて、その石の魔法効果を停止する方法を聞き出して欲しいのです。」
男はそう答えた。
「なぜ、私たちなのですか?厚生労働省において直々にお尋ねになればよろしいかと思いますが?」
「ごもっともなご指摘です。実は、それはすでに何度か試みたのですが、彼女は心を開いてくれません。そこで、年齢の近いあなた方であれば、もしやと思ってのですが…。お願いできませんか?」
男は妙に神妙な顔を見せる。
3人は互いに顔を見合わせた。
「そのグランデさんと、リッチー・クイーンはどのような関係だったのですが?」
「特別な姉妹のような関係です。」
そういって男は手に持った煙草を消した。
「アカデミー在学時代、彼女たちは特別な親交をあたためました。それでグランデ氏が例の石をリッチー・クイーン、すなわちマリアンヌに送ったのです。」
男は上目遣いにネクロマンサーの顔を見た。
「それで、そのグランデさんは、リッチー・クイーンがマリアンヌさんであることを知っているのですか?」
そう聞くと、
「はい。我々が彼女にその事実を伝えましたが、どうやら、それがまずかったようで。」
「と、おっしゃいますと?」
「グランデ氏はその事実を受け入れることができず、一層心を閉ざしてしまいました。それで、もはや私たちではもはや手の打ちようがなくなってしまったのです。」
「それは、そうでしょうね。」
ネクロマンサーは視線を下に落とした。
「ですから、シーネイ村で様々な困難を克服して同村を守ったあなた方にぜひとも彼女と接触を図り、例の石のことを聞き出してほしいのです。」
「かいかぶられても困ります。」
いつも物静かなネクロマンサーが語気を強めた。
「そういわずに、ぜひ頼まれていただけませんか?彼女を説得する材料は皆無ではありません。先ほど申し上げた通り、私の研究では、リッチー・クイーンが内包している秘宝『魂魄の結晶』をその体内から取り出すことができれば、マリアンヌに意識を回復させることができるはずなのです。それはきっとグランデ氏の心を動かすきっかけになるでしょう。いかがですか?せめて彼女に会ってみるだけでも。」
そういうと男はカップをあけてテーブルに置いた。
3人はしばらく顔を合わせてから頷いた。
「わかりました。結果は保証できませんが、試みてみましょう。」
「そうですか、それはよかった。これは厚生労働省からの正式の依頼です。事務的なことは、全学職務・時短就労斡旋局を通して、必要な手続きはこちらの方で済ませておきます。首尾については、当局に報告書としてあげてください。その結果によって改めてご連絡します。本日はご足労頂きありがとうございました。何か質問はありますか?」
いくばくか緊張の解けた面持ちで男は訊ねた。
「そのグランデさんにはどのようにしたら会えますか?」
「おっと、そうでした。これは大変な失礼を。グランデ氏はあの有名ブランド『グランデ・トワイライト』の末の娘さんで、同社の主任デザイナーを務めておいでです。ですから、同社をお尋ねいただければ会うことは可能です。もしよろしければ、アポイントメントだけは厚労省でおとりしますが…。」
「いえ、大丈夫です。私たちから一度出向いてみます。」
「そうですか。それではお願いいたします。」
「わかりました。」
男は立ち上がり、そう答えたネクロマンサーたち3人を戸口へ案内した。
「失礼します。」
そういって3人は面談室を後にした。
「でもよう、実際どうするんだよ。」
各々の教室に向かいながら、ウィザードが訊ねる。
「そうね、まるで雲をつかむような話だもんね。」
ソーサラーも確信が持てずにいるようだ。
「とにかく、一度そのグランデさんに会ってみましょう。リッチー・クイーンをこのままにしておけないのは確かだから。」
ネクロマンサーがそう言うと、あとの2人も頷いた。
「ひとまず今度の休日に、グランデ・トワイライトの本店を訪ねてみましょう。」
ネクロマンサーがそう提案した。
「そうだな。」
「でも、グランデ・トワイライトは大きな会社よ。アポイントメントなしで大丈夫かしら。」
ソーサラーは心配そうな顔をしている。
「そのときは、出直しましょう。今回の場合あまり形式ばらない方がいいように思うんです。」
「確かにそうだな。」
ネクロマンサーとウィザードが言葉を交わし、ソーサラーも頷いて同意した。
次の土曜日の午前8時にゲート前で待ち合わせることにして、それから3人はそれぞれの教室に向かっていった。
冬の陽は一層低く、斜めに明るい光を発しながら、降る雪と積もる雪を照らし出している。もうじき12月の半ばを過ぎる。いよいよ年末が近づいてきた。
* * *
約束の土曜日、約束の時間に3人はアカデミーのゲート前に集合した。『グランデ・トワイライト』社は、瀟洒で都会的な街としてしられる『インディゴ・モース』の大通りに本店を構える大会社で、魔法社会を代表する一大ブランドのとして著名であった。同社は、人為の法石『グランデ・アクオス』の開発に成功したことで急成長し、同法石を搭載した優秀な魔法具を手広く販売している。
いま3人はその本社前にいる。

「でけぇ。」
ウィザードがその茜色の瞳を見開いている。
「本当ですね。」
ネクロマンサーも怖気ているようだ。
「大丈夫よ。私ここの常連だもの。」
さすがは貴族令嬢である。ソーサラーは手慣れた所作でその店に入っていった。
「あいつ、本当にお嬢様なんだな。こんなところの常連なんて。」
「そうですね。さすがです。」
そういって2人も彼女について店に入った。
カウンターから接客の女性が姿を現す。
「まぁ、お嬢様でしたか。いらっしゃいませ。今日は何をお求めで?」
「グランデ主任デザイナーにお会いしたいのですが…。」
ソーサラーが用件を伝えると、受付の女性は困った顔をした。
「そうですか。デザイナーのグランデはどなたともお会いになりません。アポイントメントはお持ちですか?」
「いいえ、ないわ。でも、できればお取次ぎいただきたいのだけれど。」
ソーサラーが踏み込む。
「困りましたね…。お嬢様のご要望ですからなんとかいたしたいのはやまやまなのですが。」
そういって彼女は首をかしげる。本当に困っているようだ。
「マリアンヌ・イゾルデに関する話だと伝えてみてくれ。」
ウィザードが切り出した。
「それはどちら様ですか?」
あれから8年も経つ。マリアンヌとグランデ氏のアカデミー時代の関係を知らない従業員もいるようだ。
「そう伝えてもらえば、話を聞いてもらえるかもしれないんだ。頼むよ。」
ウィザードが懇願する。
「わかりました。連絡だけはしてみましょう。」
そういうと彼女はカウンターに備え付けられた通信魔法具を使って内線連絡を取り始めた。
「はい、わかりました。それでは…。」
3人の元に戻ってきた彼女は、
「お会いになるそうです。」とそう伝えて、3人を奥に案内した。
一流ブランドとして名高いその店の店内は実に洗練されていて、見事な内装であった。その洗練された様子は、3人にかつてのリリーの店を思い出させていた。
「こちらです。」
そういうと彼女はドアをノックした。
「どうぞ。」中から声がする。声の主がグランデ氏か?
返答を受けて受付の女性はそのドアを開き、3人を中に案内した。その部屋はありとあらゆる錬金具と魔法具に満たされており、まさに研究室といった様相であった。ちょうど、美しい青い瞳のブロンドの女性が法石らしきものを錬成しているところであった。高度な魔法を使っているであろうに、その女性は、なぜか増魔のリボンを身に着けていない。

「他人の思い出に土足で踏み込むとは、ずいぶんな方たちね。」
思いがけない切り出しに3人は当惑する。
「私が、グランデ・トワイライトよ。それで、なんの御用かしら?見ての通り、私は山積した仕事に追われているの。手短にお願いしたいわね。」
どうにも、あまり協力的とは言えない様子だ。
「それでは単刀直入にお話しします。」
ネクロマンサーが切り出した。
「マリアンヌさんを救える可能性があります。そのために『愛と喜びを分かつ石』について教えていただけませんか?」
そういうと、グランデ氏はため息をついてから言った。
「そう。あなたたちは厚生労働省の回し者なのね。マリーお姉さま、いえ、マリアンヌさんを助けることができるですって?あなたたちはリッチー・クイーンに対処するために愛と喜びを分かつ石のことが知りたいだけでしょう?」
なかなか手厳しい答えが返ってくる。
「そうではありません。」
しかしネクロマンサーもひるまない。毅然として続ける。
「『魂魄の結晶』という秘宝についてご存じですか?」
そういうとグランデ氏の顔色が俄かに変わった。
「知らないわ。それがどう関係しているというの?」
どうやら、厚生労働省の役人は、リッチー・クイーンがマリアンヌさんの転身であることは伝えたが、魂魄の結晶のことを話していなかったようである。その点に若干の違和感を覚えつつもネクロマンサーは続けた。
「リッチー・クイーン、いえ、マリアンヌさんの体内には、魂魄の結晶という秘宝が内包されています。私たちが調べたところでは、それを彼女の体内から分離することによって、彼女を人間に戻すことができる可能性があるのです。」
それを訊いたグランデ女史の態度は明らかに変わった。
「それは、本当なの!?お姉さまを、お姉さまを人間に戻せるというのね!?」
「はい、その可能性があります。しかし、彼女の身体からそれを取り出すためには、周囲のアンデッドを処理した上で、彼女に接近する必要があります。そのためには、どうしても愛と喜びを分かつ石について知る必要があるのです。」
ネクロマンサーは事情を説明を続けた。
「そう。」
そういって少し視線をそらしてから、グランデ氏はゆっくりと言葉を紡いだ。
「おそらく、リッチー・クイーンの身に着けている『苦痛と苦悩を分かつ石』は、お姉さまが『古代屍術』の力を解放したときに一緒に呪われてしまった愛と喜びを分かつ石のなれの果てなのでしょう。」
彼女は目元をぬぐう仕草をして言った。
「愛と喜びを分かつ石は、本来、それを与えた者と受けた者の間で、愛と喜びを分かち合い、それらを増し加える作用をもっていた魔法の石です。しかし、ご存じの通り、今では苦痛と苦悩を与えた者と受けた者の間で分かち合う、呪いの品となっています。」
彼女は目を閉じ、震える声で話す。
「その石の作用を止めることはできないのですか?」
ネクロマンサーが訊いた。
「どうでしょうね。あれを作ったとき私はまだ13歳でした。ですから、あの石には不完全なところが多々あり、まあ、だから禁忌具の影響を受けて呪われてしまったのだと思いますが、私自身もその魔法作用を止める方法を用意していなかったのです。」
「そうですか…。」
それを訊いて3人は落胆する。
「なぁよぅ。その何とかの石があんたの声に応えるってことはないのかい?だって、それはもともとあんたの心を相手と分かち合うものだったんだろう?」
そう訊いたのはウィザードだった。
「さぁ、わかりません。古代屍術の魔靴については、私も調べてみましたが、それは人間を超えた力を授ける代わりに、使用者の精神を含む肉体を代償として求めると聞きます。おそらくお姉さまはもう私のことを覚えていらっしゃらないでしょう。私の声がわかるかどうか…。」
彼女はすっかり消沈してしまった。
「それは、やってみないとわからないんじゃない?」
ソーサラーがそう切り出した。
「あなたとマリアンヌさんの間には特別な関係があったと聞いているわ。文字通りそれは愛と喜びで結ばれたものだったと私は思う。」
「知ったようなことを!」
グランデ氏は語気を荒げたが、その言葉を遮って、ソーサラーは続けた。
「あなたは、マリアンヌさんにもう一度会いたくはないの?もし、あなたにその気持ちがあるならば、彼女に会いに行きましょう。護衛は私たちが責任をもって行います。必ずあなたをマリアンヌさんのもとに連れていきますから。そこで彼女と話してみませんか?」
その黄金色の瞳が、グランデ氏の美しい青い瞳を見つめる。
「…、厚生労働省の方から、リッチー・クイーンがマリーお姉さまだと聞いたとき、激しく狼狽したわ。正直信じられなかった。お姉さまが呪いをうけてしまったなんて。でも同時にお姉さまが生きていらっしゃる、…生きているという表現が適切であるかはわからないけれど…、とにかくこの世界にまだ存在していらっしゃることを知った時には、嬉しくもあったわ。もしかするとお姉さまを救う方法があるのではないかと。それで、古代屍術の魔靴を始めとしてありとあらゆることを調べてみたのよ。私なりにね。でも調べれば調べるほど絶望に襲われたわ。あらゆる情報が、お姉さまの呪いを解くことはできないことを示していたから…。」
そういって、彼女は錬成の手を止めた。
「その情報の中に『魂魄の結晶』についてのものはありましたか?」
グランデ氏は静かに首を横に振った。
「それならば、私たちに賭けてみませんか?彼女の体内から『魂魄の結晶』を取り出し、マリアンヌさんを取り戻しましょう!」
熱を込めてネクロマンサーが提案する。
「あなたたちに賭けるか…。そうね。確かにあなたたちの提案は、マリーお姉さまを救う可能性を秘めている。賭ける、か…。」
そういうと彼女はしばらくの間押し黙り、それからやがて口を開いた。
「しかし、実際にどうするつもりなの?周囲のアンデッドは、魔法でどうにかできるとしても、『死を呼ぶ赤い霧:Crimson Fog Calling Death』を防ぐ術を考えないことには、私たち全員がアンデッドにされて終わりよ。私はお姉さまの傍にいられるなら構わないけれど、あなたたちはそれだと困るでしょう?」
その指摘はもっともだった。
「それについては考えがあるわ。」
そう言ったのはソーサラーだった。
「私たちには、そうした問題に詳しい助け手がいます。その人たちに具体的な対処方法を相談してみますから、その術が確立したら、私たちと一緒にリッチー・クイーン、いえ、マリアンヌさんとの接触を図ってみる、というのはどうかしら?」
「なるほどね。あなたたちが突然ここを訪ねてきて、マリーお姉さまを救うという提案をもってきたのも何かの運命かもしれないわね。いいわ、その賭けに乗りましょう。」
グランデ氏は意を決したようだった。
「ただし、私にも要求があるわ。」
グランデ氏は続けた。
「たとえ、マリーお姉さまを人間に戻すことができなかったとしても、せめて、…、せめて、お姉さまを呪いから解放して安らぎを与えて差し上げて欲しいの。それを約束してもらえるかしら?」
「できる限りのことをします。」
3人はそう答えるのが精いっぱいだった。
「そうよね、そうとしか言えないわね。」
グランデ氏はため息をついた。
「申し訳ありません。でも、最善を尽くします。」
「そう。少なくともあなたたちの真摯な姿勢はわかったわ。」
「ありがとうございます。それでは、改めてご連絡します。」
「ええ、吉報を待っています。」
そうして、3人は彼女の部屋を後にした。先ほどの受付の女性に促されて店外へと向かっていく。
「またあそこに行かないとな。」
「そうね、なんとかの1つ覚えみたいだけど、今はそれしか手がないもの。」
「それでは急いで向かいましょう。」
そういって3人は、雪の上に足跡を刻みながら、例のマークスをたどっていった。
* * *
今、3人は『アーカム』にいる。
アッキーナ婦人が出迎えてくれた。また、貴婦人も来店していた。
「いらっしゃいませ。今日はどうしましたか?」
アッキーナ婦人が話を振り向ける。3人は、現状をつぶさに伝えた。
「『死を招く赤い霧』を防ぐ方法ですか?」
そう言ってアッキーナ婦人は顔をしかめる。どうやらなにか心当たりはありそうだ。3人がそう思って彼女の顔を見入っていた時、貴婦人が傾けていたお茶のカップをソーサーに置いて言った。
「アッキーナ、あれをもってきて頂戴。」
「よろしいのですか?」
「ええ、この際よ。」
「かしこまりました。」
アッキーナ婦人はそう言うと、店の商品棚の方へと姿を消していった。
「ところで、あなたたち。」
貴婦人が声をかける。
「その依頼は、厚生労働省の何という人物から持ち掛けられたの?」
「技官のマークス・バレンティウヌという人物です。」
ネクロマンサーが答えた。
「そうなの…。」
そう言うと貴婦人は少し眉をひそめた。
「『魂魄の結晶』については、その人物があなたたちに伝えたのね?」
「はい。」
「そう…。」
そういうと、彼女はお茶を一口傾けた。
アッキーナ婦人が手に1着のローブをもってこちらにやってきたのはその時だった。
「マダム、お待たせしました。」
「ありがとう、アッキーナ。」
そういうと貴婦人は3人の方に向き直って、そのローブの説明を始めた。
「これは『死霊のローブ』という禁忌法具です。死を呼ぶ赤い霧を無効にする効果を持ちますが、同時に着用者を冥府の門に誘う機能を持っています。」
「それじゃあ、死んじまうじゃねぇか。」
ウィーザードが口をはさんだ。
「いえ、死にはしません。死ぬというより、生きたまま霊体になります。つまり、リッチー・クイーンと同じような状態になるわけですね。」
「しかし、それは事実上、使うことができないというのと同義ですよね?」
ネクロマンサーも懸念を表明した。
「そうね、心配はわかるわ。でも、このローブが着用者を冥府の門に誘うのは、これを身に着けた者が死の恐怖にとらわれた時だけ。ですから、このローブを身に着けているときに死のことを考えさえしなければ、危険はありません。」
貴婦人は目を細めて続けた。
「つまり、このローブを身に着ける者には、万難を排して生に向かう強靭な精神力が求められるわけです。それさえあれば、死を呼ぶ赤い霧から身を守りつつ、リッチー・クイーンに近づくことができるでしょう。」
しかし、それは実際には非常に難しい課題であった。夥しい数のアンデッドを相手に、死をまったく意識せずにいるというのは容易なことではない。3人の顔は緊張にこわばっていた。
「ほかに方法はねぇのかよ。」
ウィザードが訊ねてみる。
「そうね。ほかにはあなたたちがアンデッドになるくらいしかないわね。」
重苦しい空気がその場を覆った。沈黙が続く。
それを破ったのはネクロマンサーだった。
「わかりました。やってみます。確かに死は喪失ですが、それは生の半面でもあります。死を知らずして生を語ることはできません。そして死をよく知れば、それを恐れることはなくなります。なぜなら、死は生の前提であり、その帰結だからです。私たちが死を恐れるのはそれを喪失だと考えるからです。そうではなくて、死と生を人生の両面であり、自然の循環のひとつだと認識すれば、少なくとも恐れる対象ではなくなります。できると思います!」
「さすがね。」
そういって貴婦人は一層目を細めた。
「ほかのおふたりはどうかしら?」
そうしてウィザードとソーサラーの方に流し目を送る。
「私も差し迫る死を経験したことがあります。しかし同時にこの子が、常に希望はあることを教えてくれました。希望ある限り、死を恐れる必要はありません。私もできると思います。」
ソーサラーはそう答えた。
「とにかく、びびらなきゃいいってことだろ。あたしたちは生きるために生まれてきたんだ。死ぬためじゃねぇ。確かに死は誰にも訪れるが、それは人生の当然であって、びびることじゃあねえんだ。やってやるぜ。」
ウィザードも覚悟ができたようだ。
「そう。その心意気なら、きっとこのローブに飲まれることはないでしょうね。」
そういう貴婦人の目には満足の色が浮かんでいた。
「『死霊のローブ』をあと3着用意してちょうだい。」
貴婦人が店の奥に向かって声をかけた。アッキーナ婦人は、すでにある1着をたたんでいる。
しばらくして、店の奥から例の仮面の店員が姿を現した。彼女は綺麗に折りたたまれた3着のローブを3人の前に差し出した。
「くれぐれもこれを身に着けて死のことを考えてはいけません。いいですね。あなたたちに会えなくなるのはさびしいですから。」
貴婦人は念を押した。
「わかりました。ありがとうございます。」
ネクロマンサーが感謝を告げる。
「ここの品物が本当に呪われているということは、彼女がよく知っているはずです。」
ソーサラーが頷く。
「くれぐれも用心して。」
そういうと、貴婦人はカウンターの上で3人の前に置かれているそのローブを袋にしまって、ネクロマンサーに渡した。
「幸運と成功を祈っています。」
「ありがとうございます。」
そうして、4人はアーカムを後にした。
冬の色が一層濃くなる。あたりは白色と寒さに染まっていた。3人の後ろ姿がその景色の中に消えていく。
* * *
3人が去ったアーカムの中を冬の静けさが覆っていた。
「本当によろしいのですか?」
「そうね。止めるべきかもしれないけれど…。」
「このままでは、『魂魄の結晶』をみすみす彼の手に渡すことになりませんか?」
「その通りよ、アッキーナ。おそらく、まんまとせしめるでしょうね。」
「しかも、彼女を救うことはできないわけです。彼女たちには衝撃が大きすぎませんか?」
「あなたの言うことはよくわかるわ。」
貴婦人は一口お茶を傾ける。
「でもね、私は、その事実に彼女たちが、そしてグランデ・トワイライトがどう向き合うのか、それを見守りたく思うの。どんな絶望の中にも、必ず希望の光はあるものよ。救いのない人生はないわ。そう思わない、アッキーナ?」
「確かにそうですが…。」
「いずれにしても、このままでは誰も救われなもの。私はね、彼女たちの約束がきっと果たされてほしいと、心からそう願っているわ。」
「そうですね。その約束の実現が彼女の魂の救済となることだけは確かです。」
「できれば、もっと完全な救済を与えてあげたいけれど…。」
そういうと貴婦人は静かに目を閉じて、ひとつ大きなため息をついた。
アーカムの店内を一層の静寂が包む。その中で、アッキーナ婦人と仮面の店員が日常の用を務めていた。
冬の陽が静かに暮れていく。
第2節『果たされた約束』
アーカムで貴婦人から『死霊のローブ』を託された日の翌日、3人は改めてインディゴ・モースのグランデ・トワイライト本社を訪ねた。今回の取次はスムーズで、3人はいまグランデの研究室にいる。
「お待たせしました。マリアンヌさんを救うための具体的な準備が整いました。」
そういうとネクロマンサーはグランデに死霊のローブを差し出した。
「これは?」
グランデが問う。
「死霊のローブという禁忌法具です。身に着けることでリッチー・クイーンの『死を呼ぶ赤い霧:Crimson Fog Calling Death』を無効化することができます。これでマリアンヌさんに近づけます。」
グランデはそのローブをまじまじと見つめている。
「しかし、このローブは呪われているので、これを身に着けているときに死の恐怖を感じると、冥府の門に誘われてしまいます。」
ネクロマンサーはその半面についても説明した。
「死の恐怖か…。」
こぼすように、グランデが言った。
「マリーお姉さまを亡くしてから、もはや私にとって死は恐怖の対象ではないわ。マリーお姉さまがアンデッドの女王として君臨していることが分かった今、ある意味で死は私にとってお姉さまとの絆を回復してくれる可能性を秘めた概念でもあるの。とても皮肉なことだけどね。だから、私が死を恐れることはありません。お姉さまを救うために、あなた方に同行しましょう。」
グランデは思いを定めたようだった。また、マリーお姉さまに会える、その事実が彼女の心の虚空に新しい希望の火を灯していた。
ここ中央市街区からアナンダ氷原までは、約3日の行程である。すぐに出発すれば、奇死団と会敵するのはちょうど生誕祭の日ということになろう。奇しくも、それは、あの約束の日と重なっていた。
その後、4人はそれぞれ準備に奔走した。ウィザードは薬の買い出しに、ソーサラーは武具と防具を整え、グランデは効果のありそうな魔法具を集めていた。また、ネクロマンサーは厚生労働省に打診して、マークスと連絡を取っている。
「リッチー・クイーンと対峙する準備が整いました。これからマリアンヌさんの救出作戦に向かいます。」
「わかりました。政府からの応援は必要ですか?必要があれば、人員を回します。」
「いえ、死を呼ぶ赤い霧を無効にできるのは我々4人だけです。厳しい戦いになりますが、我々だけで作戦を決行します。」
「そうですか、わかりました。それではアカデミー特務班をあなた方の南方に配置して退路を確保します。」
「助かります。お願いします。」
「それで、首尾よく『魂魄の結晶』を入手出来たら、『隔地運搬:Magic Gate』の術式を使ってすぐにそれを私のところに届けてください。こちらで必要な処置を行います。」
「わかりました。入手次第、そちらに届けます。」
「きっと、お願いします。それで、ほかに必要なものはありますか?」
「いいえ、大丈夫です。なお、本作戦にはグランデ氏が同行します。それについて何か問題はありますか?」
「問題ありません。『苦痛と苦悩を分かつ石』の呪いを何とかするためには彼女の協力が必要なのは間違いないところです。事務的な手続きはすべてこちらで済ませておきます。みなさんのご無事と作戦の成功を祈っています。」
「ありがとうございます。最善を尽くします。」
こうして、4人は必要な準備をことごとく済ませた。魔法社会を覆う雪は一層深くなり、比較的南部に位置する中央市街地も、すっかり一面の銀世界となっていた。これから、師団規模のアンデッドの大軍勢に、たった4人で挑むことになる。どうにも無謀が過ぎるが、対奇死団戦は数による解決が非常に難しいのも事実であった。準備が完了したその翌日、いよいよ4人はアナンダ氷原への旅路についた。
* * *
行軍を開始して、はや3日目。明日にはアナンダ氷原に到着するだろうというとき、3人は目的地にほど近い『セルノニア平原』でキャンプを張った。平原といってもこの季節は深い雪に覆われており、雪原と呼ぶ方が適切かもしれない。雪以外に何もないその地で、彼女たちは最後の野営を行った。この作戦の無謀さを考えれば、文字通り最後の晩餐といった趣だった。
ネクロマンサーは力の強い霊体をかなりの数呼び出して、周囲の警戒に余念がない。ウィザードは、雪深い中、薪もろくにない中で火おこしに格闘している。ソーサラーは食事の準備をし、グランデがそれを手伝っていた。
どうにかこうにか火おこしに成功したウィザードが、そのことをソーサラーとグランデに告げる。
「これが作戦までの最後の食事よ。しっかり食べて明日に備えましょう。」
そういって、ソーサラーは鍋を火にかけた。
「それに、今日、23日はグランデさんのお誕生日でしょ。あまり盛大にはできなけれどお祝いしましょう。」
ネクロマンサーがそう提案する。
「あら、そんなのいいのよ。それより、明日に備えなければ。」
グランデが遠慮して見せた。
「気にするなよ。ここまで来たら、なるようになるさ。」
ウィザードが気遣って見せる。
「ありがとう。それにしてもあなたたちって面白い人よね。見ず知らずの私とお姉さまのために命を賭けようっていうんですから。」
そういって、グランデは少し微笑んで見せた。
「まぁそれもあるけどよ。どっちにしたって奇死団を放っておくことはできねぇしな。なりゆきってもんだぜ。」
ウィザードが少し照れくさそうに返答した。
「本当にありがとう。まさか、ここにきてお姉さまを救い出せる希望が持てるとは正直思ってもみなかったわ。」
グランデは神妙な面持ちをしていた。
「お気持ち、わかります。あなたのマリアンヌさんへのその思いは、きっと通じると思います。ですから、希望をもって明日を迎えましょう。」
ネクロマンサーが励ますように言った。
「そうね。」
そういうと、グランデは満点の星空を見上げた。明日お姉さまに再び会える。そう思うとこの8年間の心の虚空がなにかあたたかいものに俄かに満たされるような感覚を覚えた。
その目の前で、鍋が煮え時を知らせるぐつぐという音を立て始めた。
「もうすぐよ。今夜はちょっと奮発して、冷凍運搬してきた牛肉を使ったの。おいしいわよ。」
ソーサラーがいたずらっぽくそう言った。
鍋の中をのぞくと、それはいい色合いで、とっておきの牛肉と野菜が旨そうに踊っていた。

「さあ、そろそろ頃合いよ。食べて頂戴。」
そういって、ソーサラーはめいめいの椀に料理をつぎ分けた。空腹を誘う香りがあたりにただよっている。
「いただきます。」
そういって4人は晩餐を始めた。
「こりゃうめぇ。」
ウィザードが感嘆の声を上げる。
「こんなにおいしいものをいただけるなんて思ってもみませんでした。」
ネクロマンサーも喜んでいる。
「まさに、最後の晩餐にふさわしいメニューね。」
グランデが冗談交じりに言った。
ひとしきり食事を終えた後で、ネクロマンサーが荷物から葡萄酒を取り出した。
「これもとっておきです。乾杯しましょう。」
そういって、各々の椀に葡萄酒をついでいく。
「この間、『ラ・ノワール』から取り寄せたんです。おいしいですよ。」

彼女は、この日のために特別な一本を用意してくれていた。やはりみな、心中には決死の覚悟があるようであった。
「グランデさんのお誕生日に!おめでとうございます。乾杯!」
そういって4人は杯をあわせた。
極上の渋味とアルコールがその疲れたのどを癒していく。
「ありがとう。あなたたちのおかげていい誕生日になったわ。」
グランデがそういう傍らで、
「こりゃ、うまい!」
ウィザードが舌鼓をうっている。
「あなたったら、さっきからそればっかりね。」
とソーサラーがそれをからかい、しばしの笑いが巻き起こった。
「マリアンヌさんて、どんな方だったのですか?」
ネクロマンサーがグランデに問いかけた。
「とてもやさしいお姉さまだったわ。わずか12歳にして高等部に飛び級し、右も左もわからない私をとてもかわいがってくださった。それだけでなく、陰ひなたになって、助けてくださったのよ。だから、今度は私がお姉さまを助けるの。」
その瞳には確固たる決意が感じられた。
「お力添えします。きっと、マリアアンヌさんを救い出しましょう。」
「ありがとう。期待しているわ。」
ネクロマンサーとグランデは互いをまっすぐ見据えて、握手を交わした。その傍らで、ウィザードとソーサラーが肩を寄せ合ってうたたねしている。穏やかな時間であった。
冬の空はいよいよ美しく、まばゆい星々が星座の軌跡を描き出していた。その星々の間を縫うようにして、白い雪が舞っている。いよいよ明日だ。ネクロマンサーは火の番を霊体にまかせ、船を漕いでいるふたりを起こしてテントに誘い、周囲を再度確認してから、グランデとともにテントに入っていった。
雪は一層深くなり、テントに重く覆いかぶさっている。ウィザードの配慮によってテントの中は寒くはないが、外はずいぶんと冷えるようだ。さきほどからせっせと、霊体が焚火に薪をくべている。夜が静かに更けていった。
* * *
いよいよその時が来た。奇死団との決戦である。アナンダ氷原を前にして、すでにその大軍を目視することは容易であった。夥しい数のアンデッドが氷原に蠢いている。その数はゆうに10000を下らない。4人に俄かに緊張が走る。

その群れの最奥に、リッチー・クイーンの姿はあった。

「マリーお姉さま!」
思わず駆けだそうとするグランデをネクロマンサーが静止して、彼らとの距離を慎重に図る。
「で、どうする。正面衝突じゃあ勝ち目はないぜ。」
そういうウィザードに、ネクロマンサーが作戦を伝える。
「正面の大隊は私の召喚魔法で蹴散らします。あなたは奥の部隊に打撃を与えてください。」
「わかった。任せとけ。」
「その後に、中央に突破口を開きます。それは『氷刃の豪雨』で。」
ネクロマンサーがそう言うと、
「任せておいて。私にも秘策があるの。楽しみにしておいて。」
ソーサラーが不敵に笑う。
「わかりました、方法はお任せします。それで、グランデさんは私たちの後ろについて、絶対にそばを離れないでください。私たちがきっとあなたをマリアンヌさんのもとへ連れていきます。」
グランデは、力強くうなづいた。
奇死団に属する死霊がけたたましい声を上げている。どうやらこちらに気づいたようだ。
「いよいよです。みなさん覚悟はいいですね!」
「もとより、死は恐怖にあらず!」
そういって4人は位置についた。
「すぐに回復はしますが、このあと私はしばらく魔法を使えません。迅速に連携してください。」
そういうとネクロマンサーは詠唱を始めた。
『慈悲深き加護者よ。我が祈りに応えよ。その英知と力をその庇護者に授けん。我が頭上に冥府の門を開き、暗黒の魂を現世に誘わん。開門せよ!暗黒召喚:Summon Drakness!』
おそらく全魔力を一気に振り絞ったのであろう、彼女の頭上に描き出された冥府の門から夥しい数の死霊が一気に召喚された。奇死団全部と同数というわけにはいかなかったが、数千から5000程度の強力な死霊があたりを取り巻いている。
「契約のもとに、我が敵を滅ぼせ!」
ネクロマンサーの命を受けて、その死霊の群れは奇死団の前衛に向かって果敢な特攻を仕掛けて行った。耳を裂くようなその声とともに敵の前衛と大乱闘が巻き起こす。

相手は有象無象の『彷徨える屍』、それに対してこちらは魔法によって強化された強力な霊体、勝負は明らかで、その前線を押し込むことに成功した。
「後衛をたたいてください。」
ネクロマンサーのその声に続いて、ウィザードが詠唱を始める。
『水と氷を司る者よ。天候を司る者とともになして、わが手に雲を集めん。その雨の性質を変じ、あらゆるものを溶解せよ。酸の雨:Acid Rain!』

天空を俄かに毒々しい色の雲が多い、そこから敵の大軍勢の後衛めがけて、強酸の雨が降り注いだ。その効果はとりわけ腐肉を残すアンデッドに効果的で、瞬く間にその大半を溶かしつくしてしまった。前衛と後衛に大打撃を与えることに成功した。あとはリッチー・クイーンまでの活路を開くだけだ!。
ソーサラーがさっと前に踊りでる。
『水と氷を司る者よ。我は汝の敬虔な庇護者なり。今、わが手をもって氷の牢獄をなさしめよ。とらわれた者に永遠の死を与えん。滅せよ!鎮魂の牢獄:Prison of Requiem!』
詠唱を終えると、猛烈な冷気があたりを覆い、リッチー・クイーンを守護している一団を瞬く間に凍り付かせた。

「けどよ、アンデッドを凍り付かせたって…。」
そういうウィザードをしり目に、ソーサラーは不敵に笑って詠唱を続けた。
『破壊:Brake!』

そう言うと、さきほど凍り付いたアンデッドの群れは、こなごなの氷の屑に砕け散り、跡形もなく消え去った。こうしてリッチー・クイーンに至る道筋がついに開けたのである。その道を確保するかのように、ネクロマンサーが召喚した強力な霊体たちが、左右に敵陣を抑えこんでいる。
「いまよ!」
ソーサラーのその掛け声で、みな一目散にリッチー・クイーンのもとに駆け出した。文字通り、決死の行軍だった。一つ間違えれば、周囲でまだ蠢くアンデッドの群れに飲まれて終わりである。だが、だれもその危険を顧みるものはなかった。死霊のローブを身に着けた時点で、各々の覚悟は決まっていたのである。
こうして、ついに4人はリッチー・クイーンとその面前で相対することとなった。
* * *
馬上から冷たい視線が4人に注がれるる。
「マリーお姉さま!」
グランデは、声の限りに彼女に呼び掛けた。だが、反応はない。やがてそれは呪わしい詠唱を始めた。
『冥府を支配する者よ、わが声を聞き入れよ。我が前にあだ名すものに安らぎと使命を与えん。その肉を喰らい、魂を我がものとしよう。死を呼ぶ赤い霧:Crimson Fog Calling Death!』
来た!そう思って身構える4人。血をまき散らしたような真っ赤な霧があたりを覆うが、4人の身体と精神を死霊のローブが保護している。どうやらその防御効果は本物のようだ。
「お姉さま。マリーお姉さま。私です。グランデです。どうか、どうか目を覚ましてください。」
グランデの悲痛な声が聞こえる。
「グラ…ンデ…。」
そう言うとリッチー・クイーンは彼女の方を見つめた。リッチー・クイーンに対して致死性の魔法を繰り出そうとするウィザードを、ソーサラーは必死に止める。
「馬鹿ね!死ぬつもりなの。まずはあの石をどうにかしないと。」
「そりゃそうだけど。このままじゃ手詰まりだぜ。」
敵の前衛を左右に押しとどめている死霊が幾分か押し戻されているようにも見える。あの波にのまれれば後はない。4人に緊張が走る。
「今日は、12月24日。生誕祭の日です。お姉さまとの約束を果たすために私はここに来ました!目を覚ましてくださいお姉さま!!」
その声を聴いて、リッチー・クイーンの胸元に光る法石が、色を明滅させる。はじめは赤白く明らかに呪われた色を放っていたその石が、今は青白い光を放っていた。
「あれは、あれは『愛と喜びを分かつ石』の色!」
そう言ってグランデが叫ぶ。
「いまよ、いまこそ、お姉さまを、マリーお姉さまを止めてください。」
その声を聴くやウィザードが詠唱を開始する。
『火と光を司る者よ。我が手に炎の波をなせ。我が敵を薙ぎ払い、燃えつくさん。殲滅!炎の潮流:Flaming Stream!』
彼女の手から、猛烈な勢いの炎の潮流がほとばしり、それはリッチー・クイーンの身体をもろにとらえて、それを馬上から吹き飛ばした。その反動がウィザードに返ってくることはない。彼女は落馬して、その体を雪と氷に強く打ち付けた。
4人はすぐさまその傍に駆け寄った。起き上がろうとするリッチー・クイーンを、ソーサラーが『束縛:Bind』の術式で拘束し、ネクロマンサーが彼女の前に歩み出る。
「もうすぐです、マリアンヌさん。もう心配しないで。」
そういって彼女は、リッチー・クイーンの上体に手をかざし、呪文を詠唱した。その詠唱が終わると彼女の体内から乳白色の美しい結晶が浮かび上がってくる。これが『魂魄の結晶』に違いない!

ネクロマンサーはそれを手に取ると、すぐに転送用のゲートを開いてマークスに送り届けた。
「これで大丈夫のはずです。マリアンヌさんに呼び掛けてください。」
ネクロマンサーにそう促され、グランデが語り掛ける。魂魄の結晶を抽出されたリッチー・クイーンはその場でぐったりとしていた。周りのアンデッドの集団も動きを停止したようだ。
「マリーお姉さま、わかりますか。私です。グランデです。」
グランデは瞳にいっぱいの涙を浮かべてリッチー・クイーンの肩にしがみつく。
「グラ…ンデ。」
そいういうと、リッチー・クイーンは上体を起こした。
片手を彼女の方に伸ばして、言う。
「グランデ、あぁ、あなたなのね。」
「お姉さま、私がわかるのですね。」
「もちろんよ、私のかわいいグランデ。ずいぶん長く眠っていた気がするわ。今日は何日かしら?」
「今日は生誕祭の日、約束の24日です。お姉さまが眠っていらっしゃる間に私はもう22にもなりました。」
「まぁ、グランデ。いつのまにか私はあなたに追い抜かれてしまったのね。美しくなったわね。」
そいういうと、リッチー・クイーン、いやマリアンヌは暖かい微笑みを見せた。
「それじゃあ、大人になったあなたに、あのときの約束を果たさないとね。」
「あの約束を覚えていらっしゃるのですか?」
「もちろんじゃない。それを果たすために、私はここに帰ってきたのよ。」
「マリーお姉さま、そう言うとグランデはマリーに抱き着いた。」
「まあまあ、どんなに大きくなっても、あなたはあの甘えん坊のグランデね。」
そういってマリアンヌは優しい微笑みを浮かべた。
「ほら、頭を出してごらんなさい。」
そういうマリアンヌの手には、ひとひらの増魔のリボンが握られていた。
「約束よ。これをあなたに結んであげる。」
そう言って、マリアンヌは手にした増魔のリボンをグランデの頭に優しく結んでやった。
「よく似合うわ、グランデ。」
そういって彼女はグランデの頬を優しくなでた。グランデはその手をとって涙してる。
「泣いては駄目よ、グランデ。やっと約束を果たせたんじゃない。長かったわ…。」
「今日まで、増魔のリボンをせずに、ずっと待っていてくれたのね。ありがとう。」
「マリーお姉さま。」
ふたりがそう言って固い抱擁を交わした時だった。
マリアンヌの、リッチー・クイーンとしての身体が静かに灰になり始めた。
「お姉さま!?」
グランデが狼狽する。3人も何が起こっているのか俄かにわからない顔をしていた。
「いいのよ、グランデ。これで私はやっとあの呪われた身体から解放される。今とても幸せな気分よ。大人になったあなたにも会えた。」
彼女の胸元の石が、青白く美しい光を奏でている。
「これが愛と喜びなのね。あなたが私にそれを教えてくれたのよ。だから泣かないでね、グランデ。」
彼女の身体はどんどんと灰化していく。
「お姉さま、せっかく会えたのに。行かないで。私の傍にいてください。」
泣きじゃくるグランデの頭にそっと手を置いてマリアンヌが言う。
「まぁまぁ、いつまでも甘えん坊さんね。あなたはもうこの増魔のリボンを身に着ける立派な大人よ。私がいなくてもしっかり歩んでいけるわ。」
そういってマリアンヌは目を閉じた。
「もう一度あなたに会えてよかった。約束を果たせてよかった。強く生きてね、グランデ。幸せになるのよ。」
そうして、彼女の身体は完全に灰になって消えていった。その刹那、周囲のアンデッドたちは力なく崩れ落ち、それきり物音ひとつ立てなくなった。あたりの静寂をグランデの鳴き声が際立たせていた。そこには、ひとつ、青白い光を放つ、愛と喜びを分かつ石だけが残されていた。
「マリーお姉さま!」その声があたりにこだました。そのあとには深い深いしじまがその場を支配していた。
「ありがとう。」
その静寂を破ったのはグランデだった。
「いえ、でも…。」
ネクロマンサーが言いよどむ。
「いいのよ。最後にお姉さまと話ができた。そしてお姉さまは呪われた体から解放されたわ。今はそれで、それだけでいいのよ…。」
そう言って、グランデは頭上の増魔のリボンを優しくなでた。
「お姉さまは約束を守ってくれたもの。」
そう言うと、グランデは立ち上がった。
「ごめんなさい。こんなつもりじゃなかったんです。」
ネクロマンサーが謝罪する。グランデはそれに対し、首を横に振ってこたえた。
「あなた方が悪いのじゃないわ。それに、最後のお姉さまは幸せそうでいらした。愛と喜びを分かつ石を通じてそれは私にも伝わるもの。だから気にしないで。ほんとうにありがとう。」
そういうと、グランデは手にした愛と喜びを分かつ石を懐にしまい、それからネクロマンサーの手を取った。ネクロマンサーはその手を握り返し、ウィザードとソーサラーがその上に手を添える。
「ごめんなさい。」
「ありがとう。」
その言葉が、地平線に輝く1番星にこだましていた。
こうして、リッチー・クイーンと奇死団の一件は静かに幕を下ろした。許せぬのは、虚偽の情報をよこしてマリアンヌを2度目の死に追いやった、かのマークス・バレンティウヌである。
もちろん、ネクロマンサーは話が違うと彼に談判を持ち掛けたが、「マリアンヌに人間の心を取り戻させることができると言っただけで、彼女を完全に救うをことができるなどとは言っていない。結果的に彼女の魂をその呪われた身体らから解放できたのだから、感謝こそされ、恨まれる筋合いはない。」そう言ってマークスはそれ以後の連絡を一切絶ってしまった。たしかに、彼の言葉に嘘はなかったが、その巧みなレトリックは、3人の怒りに大きな火を灯した。3人は静かに打倒マークスの決意を固めていく。
12月24日、魔法社会の全体で、生誕祭が盛大に祝われていた。この辺境の氷原で、このような結末が訪れていてたとは露知らずに…。
降り続く雪はあたり一面を白く深く覆っていた。春までは長い。3人の魔法使いとグランデは胸中にそれぞれの思いを抱えながら、中央市街地へと向かって歩みを進めていた。
その姿が静かに雪景色に溶けていく。
* * *
「マークスが『魂魄の結晶』を手に入れたようです。」
「これで彼の計画は最終段階に向かうわね。」
そういうと貴婦人はいつものように、お茶のカップを一口傾けた。
「こちらも、すこし急いだほうがいいのかもしれないわね。」
そういうと彼女は誰かを呼んだ。
「あなたに、折り入ってお願いがあるの。」
そういう貴婦人の言葉に、その人物は頷いて答えた。
「アッキーナ、あれを用意してちょうだい。」
「よろしいのですか、マダム。」
少女アッキーナはその意向を確認する。
「今こそ、これを使うべき時だわ。これ以上の好き勝手は困るもの。」
「わかりました。」
そいういうと、いつものように少女アッキーナはよちよちと店の奥に姿を消していった。
「あなたにはこれから、アカデミーに出向いて行って、あるものをとってきてほしいの。」
アーカムのカウンターをはさんで、貴婦人ともう一人、ふたりの女性が言葉を重ねている。外では冬の寒さが一層際立っていた。
第3節『それぞれの年末、それぞれの事情』
マークスの巧みな欺瞞に踊らされる形でリッチー・クイーンと奇死団の事件は一応の解決を見た。迫りくるアンデッドの大軍の恐怖から解放された魔法社会は、新年を迎える準備で活気づいていた。奇死団によって壊滅させられた辺境の農村部にも少しずつ人が戻り始め、ゆるやかに平常が回復されようとしている。
その後、マークスは『アカデミーによる葬送』に姿を現すことはなくなり、厚生労働省からも忽然と姿を消した。問い合わせを行っても、厚労省は「セキュリティ上の理由でお答えできない」と繰り返すばかりで、その足取りを追うことはもはやできなくなってしまっていた。しかし奇死団壊滅後、それまで異様な回数で行われていた葬送の儀式は、一挙にその数を減じ、その裏で行われていた悪辣を知ることのないままに、人々は呪われた存在からの解放をただ純粋に祝い、歓迎していた。そんなある年末の深夜のことである。
アカデミーのゲート前にひとりの人影があった。
ずいぶんと懐かしいものだ。その人影はそう思っていた。ここから、中央図書館の展示室に侵入し、あるものを奪取するのがその目的である。中央図書館は、ゲートを入ってからまっすぐに進み、教室棟を超えて丘を登った左手にある。そこに至る道のりは比較的開けていて、身を隠す場所が少ない。その人影は慎重にあたりを警戒しながら進んで行った。
中央路を進んでいると、奥から夜回りをしている『アカデミー所属治安維持部隊』が見えた。とっさに物陰に身を隠す。危ない、犬に見つかれば作戦が台無しになる。そう思って、治安部隊の一団が行き過ぎるまで息をひそめていた。ここから中央図書館の入り口まではまだずいぶんと距離がある。夜回りの治安部隊と再度遭遇する可能性は高い。とにかく慎重に行かなければ!自らに言い聞かせるようにして緊張感を高めた。
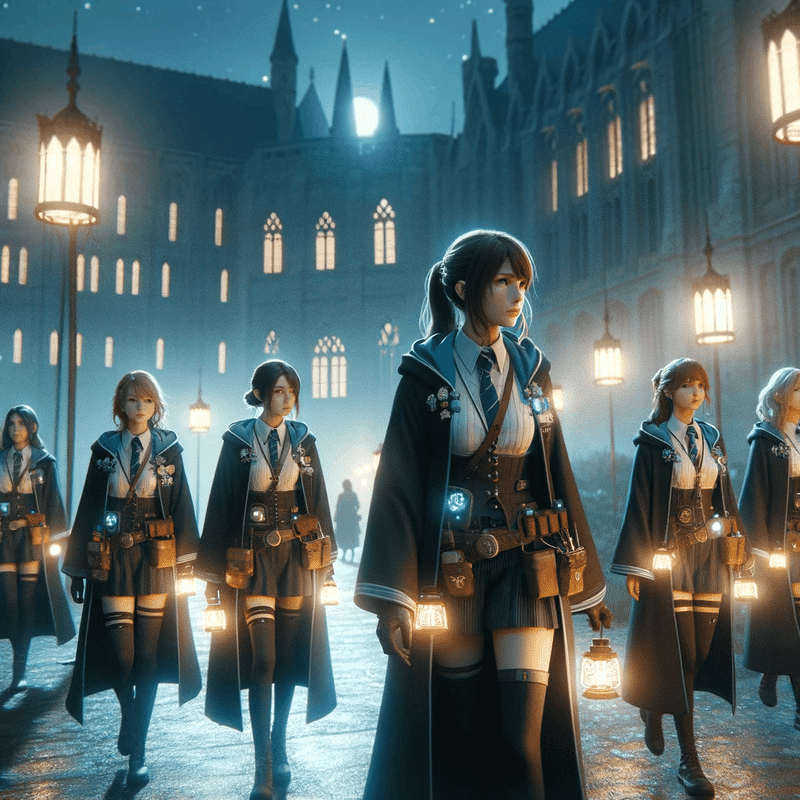
ここから、教室棟を抜けて丘をのぼりきるまでは身を隠す場所がほとんどない場所が続く。意を決して丘を駆け上っていった。冬の風がずいぶんと冷たく、それは肌を切りつけるかのようであった。月明かりがあたりを照らし出している。急いで丘を登りきらなければ!そう思って駆けていく。そういえば、昔にもこんなことがあったな。そんなことを考えながら、丘の上の通りにたどり着くと、そこに立ち並ぶ柱に身を隠してあたりを見回した。
夜回りの明かりがあちこちに見える。今夜はまたずいぶんと犬が多い。中央図書館の入り口の方を見やる。もう少しだ。雪に足跡を残さないように『浮遊:Float』の術式を行使しているが、これを使って走ると思うように速度が出ないのが難点だ。建物の屋根の下に潜り込み、そこから中央図書館の入り口に向かって一気に移動した。よし、ここまでは上々だ。
その人影は『不触の鍵:Invisible Keys』の術式を行使してその入り口を開け、中に侵入した。月明かりの届かない図書館の中は一層暗い。入り口のカウンター脇に姿を隠し、しばし目が慣れるのを待つ。ようよういくばくかあたりの状況を確認できるようになってきた。
3階の展示室までは、階段を上っていく必要がある。幸い夜回りの足音は丘の上にはないようだ。

階段を上り始めれば、もはや姿を隠す場所はない。一気に3階まで行く必要がある。空を飛べる虚空のローブを身に着けてこなかったことを少しばかり後悔した。意を決して、一目散に階段を駆け上がる。浮遊の術式が効いているので足音はしないが、やはり思うように足を繰り出すことができない。2階を通りすぎ、そのまま3階まで移動した、その時だった。
「中央図書館の鍵が開いている!侵入者かもしれん。見回るぞ!」
そういう声とともに数名の治安部隊の隊員が図書館内に入ってきた。彼女たちが手にする明かりで、館内が一気に明るくなる。急がなければ!そう思って階段を登り切り、3階の入り口に取り付く。書棚の影に身を隠し、下をうろついている治安部隊の動向を見守った。何名かが階段を上り始めた。急ごう!
浮遊の術式の効果を切って、足音を殺しながら絨毯の上を3階奥の展示室に向かって駆けていく。そこは3階の本当に最奥に配置されているため、かなりの距離を走らなければならなかった。ちらちらと明かりが近づいてくる。後ろをたびたび振り返りながら、なんとか展示室までたどり着いた。

そこは、アカデミーが所蔵する貴重な魔法具や本物の法石が展示されているスペースで、さながら博物館といった面持ちの場所である。この広いスペースから『天使の卵の化石』なるものを探し出さなければならない。そのためには何より暗いのが困る。魔法光を放つ法石などがあるため、書庫に比べれば夜目が効くが、それでも展示品のラベルを読み取るのは容易ではなかった。もっと勤勉にここに通っておくべきだった。そうすれば、展示品の位置くらいは把握できていたのに。そんな思いが脳裏をよぎる。息と足音に細心の注意を払って、展示台を見て回る。なかなか見つからない。
そうこうしているうちに展示室に明かりが灯った。犬どもだ!展示台の影に身をかがめて、行き過ぎるのを待つ。なかなか去っていかない。いらいらしながら、あたりを見回していると、そこからはす向かいに設置された展示台に、それらしいものを見つけた。あった!おもわず漏れ出そうになる声を胸の中に押し戻して、治安部隊が展示室から出ていくのをじっと待つ。彼女たちが持つ明かりが、静かに隣のスペースへと移動していった。いまだ!
彼女は展示ブースを『不触の鍵:Invisible Keys』で開錠し、その中の展示物を手に取った。目的物はとても不思議なもので、その形状はまさに卵であったが、質感は白い化石のように乾き干からびていた。ただ、中央付近に刻まれた呪印のようなものは、ごくかすかに白い光を放っているようにも見えた。

これはいったい何に使う者なのだろう?そう考えながら、ローブの内ポケットにしまい、展示室からの脱出をはかる。物陰から、階段周辺を見回すと、そこに治安部隊の姿はない。しめた!フロアと階段ががら空きだ!
その影は一気に階段を駆け下り、1階のフロアに至る。ここまでは順調だ。そう思った時、階上で警報が鳴る。
「展示物が盗まれている!総員、周辺警戒を怠るな!」
そう叫ぶ声が聞こえてきた。
どうやら見つかったようだ。ここからは追いかけっこになる。そう思い定めて、中央図書館の出口を一気に外に向かって駆け出ていた。ここから、裏門まではそれほど遠くない。入り口を出たところで、後方から声が聞こえた。
「いたぞ!追え!!」
ここにきて見つかってしまったか。まあいい、裏門を抜ければ夜の闇に紛れることは容易だ。裏門まで懸命に駆けていく。この丘上の通りを行き切って、石段を駆け下り、左手に曲がれば裏門はすぐだ。あと少し!大急ぎで石段を駆け下りて、丘下の通りとの交差点に出たその時、丘下にいた一団と鉢合わせてしまった。
「止まりなさい!」
そういわれて止まる馬鹿はいない。咄嗟に『衝撃波:Shock Wave』の術式を繰り出して右手から迫る一団を牽制する。
「貴様!抵抗する気か!構わん、発砲を許可する。」
そういうと治安維持部隊は錬金銃砲を腰から抜き取り、警告射撃なしでいきなり撃ってきた。身体をかすめる弾丸をかろうじてかわしながら、一気に裏門に向かっていく。
「待て!待たんか!」
そう言って治安部隊は銃声とともに追いかけてくる。しかし、警告射撃もなしで発砲してくるとは、これはそれほどにも価値があるものなのだろうか?いや、今はそんなことを考えている暇はない。走りながら法弾よけの障壁を展開し、どうにかこうにか裏門にたどり着く。あと少し!一気に裏門を駆け抜け、その先にある高架下の真っ暗なトンネルに駆け込んで、そのまままっすぐに夜の闇に溶け込んだ。
「まだ、近くにいるはずだ!探せ!」
裏門近くで声が聞こえる。
どうやらうまくまいたらしい。そっと胸をなでおろす。ローブから例のものを取り出してみると、真っ暗な宵闇の中で、それは確かにかすかながら白い光を放っていた。とても不思議なものだ。卵といえば卵だし、石の塊といえば石の塊だ。これは一体何なのか?そんなことを考えながら、再度それをローブにしまい、闇の中を駆けて行った。
* * *
その人影は今、『アーカム』にあった。
「これで間違いないですか?」
そう問うと、
「ええ、これよ。ありがとう。」
貴婦人はいつものように目を細めて言った。
「それは一体何なのですか?」
「私にとって、とても大切なもの。そして近い将来、あなたにとっても大切なものになるわ。」
「私にとっても、ですか?」
「そう。それはもう少し先のことだけれどね。」
貴婦人は一層目を細めてからこう言った。
「アッキーナ、お茶を淹れてちょうだい。」
「なににしますか?」
その声は少年アッキーナだ。
「そうねぇ、『ブレンダの秘密』をお願いするわ。」
「『ブレンダの秘密』ですね。少々お待ちください。」
奥の台所らしきところから、声がした。
「あなたには、重荷を負わせて申し訳ないわね。」
「いえ、自分で選択したことですから。」
「あなたは強いのね。」
「マークスの狂気を誰かが止めなければなりません。彼のしていることは到底許されるものではありません。」
「そうね。それだけですめばよいのだけれど…。」
貴婦人は少し言いよどむ。
「それは、どういう…?」
「そのうちにわかるわ。その時はきっとこれがあなたと縁(よすが)を結ぶでしょう。」
そういって貴婦人は、例の卵のようなものを片手に持ち、まじまじと眺めた。
「お待たせしました。」
奥から少年アッキーナが、お盆にお茶を載せて姿を現した。

「どうぞ。」
そういってアッキーナがお茶をふるまってくれる。
「そう言えば今日はこれも一緒にいかがですか?『ハインリヒのショコラケーキ』が手に入ったんです。」
そういうとアッキーナは再びに奥に行き、そこからケーキを持って戻ってきた。
「これはおすすめですよ。」

「まぁ、それはいいわね。ぜひいただきましょう。」
そういう貴婦人の前で、アッキーナがケーキを切り分けてくれる。
「それでは、いただきましょう。」
そう言って、3人はお茶を楽しんだ。『ブレンダの秘密』というお茶は、蜂蜜のような甘みと、ほんの少しいぐみのある独特の風味のお茶であった。貴婦人の説明では、飲む者の好奇心を高め、勇敢さを増し加える効能があるのだそうだ。また、『ハインリヒのショコラケーキ』は、その見た目に反して甘さはごく控えられており、むしろチョコレートの苦みが際立つ大人の風味であった。その苦みとブレンダの秘密の甘みが何とも言えない味のハーモニーを奏でていた。
「しかし、なぜマークスはあんなことをしているのでしょう?」
その影が貴婦人と話す。
「そうね。おそらく生命の創造に興じているのでしょう。」
「でも、彼がやっているのは、実際は…。」
「ええ、あれは間違いなく生命への冒涜ね。」
「葬送によって荼毘に付されるはずのご遺体をアカデミーから簒奪して、それを異形の生命体に変えるなんて、よくもそんな恐ろしいことを考えたものです。許せません。」
「そうね。彼は明らかに狂気にとらわれているわね。」
そう言って貴婦人はカップを一口傾ける。
「あの、P.A.C.という術式で召喚されるのは、マークスの手によって操作されたご遺体のなれの果てだったのですね。」
「そう。死という人間の最期にして最大の尊厳を弄ぶ彼は確かに許されざる存在だわ。しかし、『魂魄の結晶』を手に入れて、彼の研究はいよいよ完成段階を迎える。しかも、彼は新しい後ろ盾を手に入れたようですから、その狂気は一層加速するでしょうね。」
「アカデミーですか?」
「そうね。アカデミーの一部が彼と手を結んだのは間違いないわ。」
「最高評議会ですか?」
「どうかしら。まずは調べてみないと。」
「この事実を魔法社会に公表して、世論でマークスを追い込むことはできませんか?」
「そうね。その手もないわけではないけれど…。」
貴婦人はケーキをひとかけ口に運ぶ。
「厚生労働省の高級技官とアカデミーが結託して、遺体から人為の生命体を錬成していたという事実は、社会全体に与える衝撃が大きすぎるわ。できれば、秘密裏に解決したいわね。」
「そうですか…。わかりました。私もその点に十分に配慮します。」
「そうね。ありがとう。今晩のことで、おそらくアカデミーのあなたに対する追跡は一層苛烈になるでしょう。ここにいるときは安全だけれど。外にいるときにはくれぐれも用心してね。」
「心得ています。」
「頼りにしているわ。」
アーカムの店内を、お茶とケーキの甘い香りが芳醇に彩っている。貴婦人ともう一人は一体何を話しているのか?マークスが人為の生命体を遺体から錬成しているとはどういうことか?膨大な犠牲を生んだ奇死団事件そのものが何者かに仕組まれていたというのであろうか?ただ、その背後にマークス・バレンティウヌという人物の存在があることだけは明らかだった。
冬の夜が白んでくる。明けの明星がまばゆく輝いていた。夜明けとともに、アーカムの戸は静かに施錠された。まもなく年が明ける。
* * *
ところかわって、こちらは例の3人とグランデである。マリアンヌと再会を果たし、約束が成就された一件を経て、彼女たちにもまた新たな親交の輪が芽生えていた。
今日は4人で、歳末セールに繰り出している。奇死団の脅威から解放された魔法社会の街々は、彩りと活気を取り戻していた。買い物ならば、グランデの店である『グランデ・トワイライト』でもできるが、おしゃれな服飾を見に行こうということで、若者の街『フィールド・イン』にある有名ブランド『ラヴィ・ムーン』を訪れていた。
「あなたたちの歳なら、フィールド・インが似合うのだろうけれど、私にはもうそろそろ無理かもね。」
グランデが笑って言う。
「そんなことないですよ。まだまだ、若いんですから。」
そう応じるソーサラー。
その傍らでは、こうした若者の街に繰り出すのに慣れていないのであろうウィザードが、おのぼりさんのようにきょろきょろしている。
「ちょっと、落ち着きなさいよ。」
「お、おぅ。こういうところはどうも慣れなくていけねぇ。」
「何言ってるのよ、こここそ乙女の街よ。」
ソーサラーが軽やかに笑う。ネクロマンサーも微笑んでいた。
4人が店内で談笑していると、店の奥からひとりの人物が現れた。
「いらっしゃいませ。本日は『ラヴィ・ムーン』フィールド・イン本店にようこそ。」
そう言って出迎えてくれたのは、同ブランドの設立者であるラヴィ・ムーンその人だった。思いがけず有名人に出会えて、3人は俄かに色めきだっている。
「あなたは、『グランデ・トワイライト』主任デザイナー、グランデさんですね。実は私、あなたの大ファンなんです。あなたの錬成した『グランデ・アクオス』は当店でも重用させていただいているんですよ。お会いできて光栄です。」
ラヴィはグランデに手を差し出した。
「こちらこそ。ご高名は存じ上げています。グランデ・アクオスを使ってくださり、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。」
グランデは握手に応じた。魔法社会における有名人ふたりの思いがけない邂逅に店内がざわめいている。
「今日は何をお探しで?」
そう問うラヴィに、
「この子達に無理やり引っ張ってこられたのよ。私のようなおばさんは、こんなおしゃれなお店にはとても似合わないわ。」
グランデは謙遜がちに答えた。
「あら、あなたと私は同年代でしょ?。あなたがおばさんなら、私もおばさんです。ということは、ここにある商品は全部おばさんの手によるものということになりますから、遠慮なく見て言ってくださいな。」
そいういてラヴィはころころと笑った。
ブランド『ラヴィ・ムーン』は主に十代の少女たちに絶大な人気を誇るブランドで、フェミニンなかわいらしいパステルカラーのアイテムが特に耳目を集めていた。若者に人気のブランドとしては他に『ロコット・アフューム』があるが、こことそことで、まさに2大勢力を形成している。店内にはありとあらゆるおしゃれアイテム、服飾、下着にいたるまで、若者向けの商品が所狭しと並んでいた。
「まさか、あなたに会えるとは思っていませんでしたよ。」
「こちらこそ、お会いできて嬉しいですわ。」
ラヴィとグランデが楽しそうに談笑している。その後ろを3人がついてまわっていた。同じ魔法具のデザイナー同士、通じるものがあるのであろう。ふたりはすぐに意気投合して、大いに盛り上がった。その店内の華やかさに圧倒されているウィザードと実に対照的であった。
「あなたも、こんなのを着てみたらいいんじゃない?」
ソーサラーがウィザードに下着を勧めている。

「勘弁してくれ。あたしがこんなの着てどこにいくんだよ。」
「デートとか?」
「相手がいねぇ。」
「まぁ、そうよね。」
そのふたりのやりとりをネクロマンサーがあたたかいまなざしで見守っていた。先を行くラヴィとグランデのふたりはいよいよ話に花が咲いたようで、さまざまな商品をみてまわりながら、両ブランドでどのようなコラボレーションが可能かといったビジネスの話にまでその話題の枠を広げていた。そんなふたりの背中を見つめながら、3人は、マリアンヌを失ったグランデの心の喪失をラヴィが埋めてくれればよいのに、そんなことを考えていた。
「今日のお話の続きは、ぜひまた次の機会に。」
そういうグランデに、
「こちらこそ。これからもいろいろ一緒にやっていきましょう。」
ラヴィはそう応じた。
ふたりは再度固く握手を交わしてから、その日は分かれた。帰り道、グランデは心なしか弾んでいるように見えた。
喪失と充足、出会いと別れ、人生には様々な岐路がある。その都度その都度の選択が運命を決定づけていく。運命は決して所与のものではない。人生は与えられるものではなく、自ら紡ぐものだ。
雪の降る街に、将来の希望に満ちた若人の明るい声がいつまでも行きかっていた。
第4節『スカッチェ通り南市街区の惨劇』
厚い雲に覆われた月明かりのない、真っ暗な年末の深夜だった。ひとりの人物を蠢く影のような集団が追っている。激しい息遣いと雪を刻む複数の足音がせわしなく響きわたっていた。追っ手は40から50人はいるだろうか、ちょっとした小隊規模である。
よくもまあ私一人にこれだけ差し向けてきたものだ。逃げる人物はそんなことを考えながら、足を繰り出していた。追っての速度は思いのほか早い。どうやら P.A.C. も完成段階にあるようだ。走りながら後ろを見やると、甲冑の上にローブを着込んだ黒づくめの集団が、その目元だけを不気味に光らせている。やはりあれはもう人間ではない。人の死を弄ぶなんて!そう思うと俄かに怒りがわいた。こんな非道なことがよくもできたものだ。追っ手の数は犠牲者の数でもある。キッと唇をかむ。追っ手にはその手を緩める気配はない。
「追え!」
「逃がすな。」
乾いて震えるような不気味な声が背後から聞こえる。
姿を隠すための仮住まいにしている借家の郵便受けに放り込まれていた、マークスの居場所を教えるという匿名の情報に従って深夜の繁華街まで出向いたが、まんまと一杯食わされた。その情報は実のところ罠であって、指定された場所に行く途中のひと気のない路地で、この連中に囲まれてしまったのだ。それからこの追送劇は始まったわけである。
アカデミー前からマーチン通りを北に抜け、今はサンフレッチェ大橋を駆けている。
禁忌術式や究極術式を使えば、この程度の追っ手を退けることは容易だ。しかし、遺体に手を加えて作られた人為の生命体なるおぞましいものがその魔法社会に存在することを、しかもそれらの製造に当該社会の統治の中核を担う政府厚生労働省とアカデミーが関与しているという事実を一般の人々に知らせるにはまだ時期尚早だ。片づけるにしても、跡形も残らないように、完全に殲滅する必要がある。追っ手をかわしながら、そんなことを脳裏に巡らせていた。
深夜といえども年末のこの時期は、いたるところにひと気がある。まずは可能な限り閑散とした地域におびき出さなければならない!それにしても、偽情報に引っかかって『漆黒の渡烏』に追われる羽目になるとは、へまをしたものだ。口元に自虐的な笑みを浮かべながらもなお、逃走を続ける。

『漆黒の渡烏』とは、アカデミーが編成する対特殊犯罪の特務班で、アカデミー所属治安部隊では手に負えない重要犯罪や、強力な『裏口の魔法使い』に対処するために特別に派遣される部隊である。しかし、その実は、マークスが手を染めている人為の生命体開発計画 P.A.C.:Production of Artificial Creatures の犠牲者の成れの果てであった。その性能と機能は日を追うごとに完成度を高め、今では人間の魔法使いよりも強力であるかもしれない。だが、その生産材料は人間の遺体なのだ。なんという許しがたい非道であることか!内心に一層の怒りが込み上げてくる。いつか必ずその非道を止めてみせる!その決意を新たに死ながら、サンフレッチェ大橋を北に駆けて行った。
底冷えのする真冬の寒さの中、まるで身を切られるようだ。走りながら、どこで追っ手を処理するかをずっと考えていた。最適な場所はひと気がなく、民家が少なくて、人的・物的被害を最小限にできるところ。どこだ?思案しながらもひたすらに走る。
ここから先で、その条件を満たすところと言えば、スカッチェ通りがある。そこは市街区が南北に分かたれており、北市街区には現住建造物が多く人家が密集しているが、他方の南市街区は商業地で大規模な倉庫街だ。すでに物流が止まっているこの時節ならば、大きな損害を出さないで、殲滅性の高い術式を行使することができる。まぁ、いくつかの倉庫が巻き添えになるかもしれないが、この際そんなことは言っていられない。マークスの薄汚れた野心が露見することで、ようやく奇死団の脅威から解放されたばかりの人々を再び不安と恐怖のどん底に陥れるよりははるかにましだろう。スカッチェ通りに行こう!そう思い定めて足を速めた。
後ろの追っ手は、さすがすでに人間ではないだけあって疲れることを知らない。いつまでも機械仕掛けの人形のように同じペースで追いかけてくる。こちらはどんどん息が上がる。さすがに苦しくなってきた。口を開け荒く大きな息をしながらスカッチェ大橋に差し掛かった。

ここは、スカッチェ通りの上にかかる高架で、市街地を一望できる観光名所となっている場所だ。恋人たちがここで愛を誓うと、その縁は成就するとのもっぱらの噂である。そこを渡るからには、この追送劇を市民に目撃されるリスクがあったが、幸いにしてこの丑三つ時には、もう人々の姿はそこにはなかった。橋を渡り切り、道なりに大きくぐるりと回って、石段を駆け下りればスカッチェ通りに出る。もう少しだ!乾いた空気がのどにしみて咳を誘う。咳きこむと息切れが激しくなって一層苦しさが増すが、ここで止まることもできない。懸命に足をかい繰って、ようようスカッチェ通りに差し掛かった。スカッチェ通りの市街区は、その上にかかるスカッチェ大橋を基準にして南北に分かれている。スカッチェ大橋の真下まで移動し、それから追っ手の方を振り返れば、追っ手を南市街区に捉えたことになる。スカッチェ大橋のたもとはもうすぐだ。そろそろいいだろう。
逃げ続けていた人物は、その場で足を止め、南市街区の方を向いた。すると追っ手もまた、走るのをやめ、じわじわと詰め寄ってくる。

案の定、南市街区はひと気がなく、無人の倉庫だけが立ち並んでいる。ここならいいだろう。しかし、追っ手は相当の数だ。確実に命中させ、殲滅するためには、ちょろちょろと動かれたのではやりにくい。「威力は一級、精度は三流」そんな思い出が一瞬頭をよぎった。とにかくも、まずは動きを止めなければ!幸いにして今の私にはこれがある!できない相談ではない。そう、その人物の頭上には、普通の人間にはあるはずのないもの、天使の輪が浮かんでいた。もっともそれは本物ではない。アカデミーが、天使への信仰で成り立つ魔法社会の秩序と倫理に反するとして絶対の禁忌とする法具『人為による天使の輪』である。それは、着装者に神秘の力を授け、秘術への直接アクセスを可能ならしめるという破格の魔法具だった。
その人物は詠唱を始めた。
『我は今、禁を破って時の秘術に接触せん。時を司る者よ、その胸中を開き、わが手にその神秘の力を委ねたまえ。星々の理に介入し、現在、過去、未来、流れる時の法則を今操らん!星天よ、その動きを止めよ!星天運航停止:Stop Movement of Planets!』
禁忌魔法の術式だ!それは時を操り、星々の運航を止めてその場のあらゆるものの時間を停止するという時空の秘術であった。これまでカチャカチャと甲冑の音を響かせ、足元の雪をきしませていたその音が一斉にやんだ。空気の振動や風の揺らめきさえ感じられない。時が完全に止まったのだ。
よし!そう言って人物はさらに詠唱を重ねる。
『閃光と雷を司る者よ。その胸中を開き、神秘に通じる秘術を授けたまえ。我は汝の敬虔な庇護者なり。天空の意思を我に知らせよ。閃光と雷を裁きの剣となさん!今、天界の裁きをこの手でなそう。秘術!裁きの雷光:Lighting Laser of Divine Judgement!』
かつてリリーの店で異形の魔法使いを貫き焼き尽くしたのと同じ術式であるが、今度は人為による天使の輪の力もあって、無制約にその魔法力を引き出せているのだろう。あの時とは全く規模の異なる稲妻が、さながら光線のようにして天空から降り注ぐ!

ひとしきりの閃光の点滅と轟音の後、あたりに静寂が返ってきた。追っ手はその究極術式の前にことごとく焼き尽くされ、墨か灰のような跡形をわずかに残すばかりのとなった。その様子はまことに凄惨で、破壊の限りが尽くされた後には、その術式の詠唱者だけがただ一人、南市街区の方を向いてたたずんでいた。

これで、魔法社会の市民に人為の生命体というおぞましい存在について知られる心配はない。周囲に焼け残った遺体がないことを慎重に確認してから、その人物は宵闇の中へと姿を消していった。
* * *
この事件は、『スカッチェ通り南市街区の惨劇』として、魔法社会に大々的に報じられた。どの報道も、極悪非道で無慈悲極まる『裏口の魔法使い』が市民の犠牲も顧みずに真夜中の市街地でアカデミーのエリート特務班である『漆黒の渡烏』を惨殺したと書き立てており、魔法社会の市民たちは、その脅威の『裏口の魔法使い』を大いに恐怖した。せっかく、リッチー・クイーンと奇死団の問題が解決した矢先にこれかと嘆く向きも多かった。しかし、その真相は闇の中に隠されていた。アカデミーは、偶然現場で記録された魔術記録を公表して犯人を第一級の指名手配とした。
この事件ではアカデミーでも話題となり、さまざまな憶測が飛び交った。魔法新聞の記事をみて、このようなやり取りをする3人の人物の姿がある。
「おい、見ろよ。」
「なに?スカッチェ通りの事件のこと?」
ウィザードとソーサラーが魔法新聞の記事に見入っている。
「これって…!?」
指名手配の魔術記録を見てネクロマンサーが息をのむ。
「あんたも気づいたかい。これ、あいつだよな。」
「はっきり顔が映ってないから断言はできないけど、確かに似てるわ。」
「生きていらしたんですね。」
3人は口々に感想を述べる。
「でも、なんでこんなことを。これじゃあまるで…。」
「本物の『裏口の魔法使い』ね。」
「どうしてあの人が、アカデミーや魔法社会に弓を引くのかしら?」
「勉強嫌いで不真面目だったけど、こんなことをするやつじゃなかったぜ…。」
「信じられないわね…。」
「これからマークスを追わなきゃならないって時に、もしあいつに会ったら、あたしらどんな顔すりゃいいんだよ…。」
「そうね。」
ソーサラーが言いよどむ。
「彼女は、マークスたちと手を組んだのでしょうか?」
「わからねぇ。なにもかもわからねぇよ。」
ネクロマンサーの問いにウィザードがあからさまないらだちを見せた。
「とにかく、事情が分かるまでこの犯人が彼女に似ているということは伏せておきましょう。」
そう提案するソーサラーに、ふたりは深くうなづいて答えた。
アカデミーは本件について公式の声明を出し、この史上最悪ともいえる虐殺事件について全学を上げて復讐することを誓った。その声明を受け、治安維持部隊及び漆黒の渡烏への志願者が急増したことは言うまでもない(漆黒の渡烏は P.A.C. による影の部隊だけでなく、表向きにはアカデミーのエリートで構成される特殊部隊としての体面をも一応は保っていた。もちろん、普通の隊員たちには、その背後で暗躍する P.A.C. の部隊が存在することは巧みに隠蔽されていたことは言うまでもない)。
いよいよ年の瀬が迫った時に、アカデミーでは『スカッチェ通り南市街区の惨劇』で犠牲となった『漆黒の渡烏』の隊員を悼む『アカデミーによる葬送』がしめやかに執り行われた。漆黒の渡烏の犠牲者は総勢20名とされたが、そこにアカデミーによる情報操作があったことは明らかである。しかし、アカデミーの側にいる者で、その事実を知る者はごくわずかであった。
いよいよ、その年も暮れようとしていた。雪は一層重くなり、魔法社会全体が白く覆われていく。奇死団事件に続いて世間を大いに騒がせたこの裏口の魔法使いの身柄を、追跡確保の上その場で処刑したとアカデミーが報じたのはそれから2日後の、その年最後の日であった。その一報に多くの市民が胸をなでおろす中で、3人は、深い悲しみの入り混じった複雑な感情をもってそれを受け止めていた。
* * *
アーカムにて。
「先日は大変だったみたいですね。」
少年アッキーナが語り掛ける。
「そうね、さすがに緊張したわ。」
「でも無事でいらして何よりでした。」
「ありがとう。本当はこんな大事にするつもりはなかったのだけれど。」
そういってお茶のカップを一口傾けた。
「でも、中途半端なことをして、P.A.C. のことが魔法社会に公になることは避けたかったのよ。」
人物はそう語る。
「その判断は賢明だったと思いますよ。」
「そう言ってくれると救われるわ。」
「ところで、あれは、なかなかすごかったでしょう?」
「ええ、神秘にアクセスして秘術の術式を直接引き出せるというはすごい魔法具ね。アカデミーが禁忌とする理由が分かるわ。」
「そうですね。彼らは自分たちの権威の象徴である『神秘のティアラ』を遥かに凌駕するこの魔法具が広く出回るのを極度に恐れていますから。」
「表向きは、天使の信仰に違背するってことにされてるけどね。」
「そうですね。実のところは、自分たちの既得権益を確保しておきたいという、ただそれだけなのですが、建前でうまく言いつくろったものです。」
「ほんとうね。うんざりだわ。」
「まあまあ、お怒りはわかりますが。それよりこんなのはいかがですか?」
そういうと少年アッキーナは奥に引っ込んでから、しばらくしてお盆を手に戻ってきた。
「デュームのプディングです。おいしいですよ。」

そういって、少年アッキーナはそのプディングの乗った皿と匙をよこしてくれた。
その人物は、一口くちに入れる。
「おいしい!」
「でしょ?」
「ブルーベリーの酸味とプディングの甘さのバランスが絶妙ね!いくらでも食べられちゃうわ。」
「あの晩はたくさん走ったでしょうから、その分を補ってください。」
そういってアッキーナは笑顔を見せた。
「そうえば…。」
食べながら人物がいう。
「私たちってもうずいぶん長い付き合いになるけれど、あなたのことをほとんど知らないままだわ。今もこうしてあなたと普通に話しているけれど、本当はとても不思議なことなのよね。この前会ったあなたはご婦人だったし。」
「そうですね…。」
洗ったばかりのグラスの水分をふき取りながらアッキーナが言った。
「お話ししないといけないことはたくさんあるんですが。なかなか事情が複雑でして。でも、お話しできる時がきたらきっとお話ししますよ。僕の秘密のことも、マダムのことも。」
「ええ、気長に待ってるわ。」
そういって、ひと匙、またひと匙と口に運んでいく。
「これは本当に絶品だわ。」
そういう顔はしばし緊張から解放された、年頃らしい愛らしい表情を浮かべていた。
外には、年の移り変わりを知らせる鐘の音が鳴り響いている。
「新しい年が来るわね。」
「そうですね。」
こうして、様々なことがあったその1年が静かに暮れ、新しい年を迎えようとしてた。
雪はなおも深々と降り続いている。冬はまだ厳しくなる一方である。
第6章
第1節『動き出した歯車』
「どういうことかわかるように説明したまえ。」
詰問する声が聞こえる。
「これで、ついに P.A.C. 計画が完成するのです。」
「そういうことを聞いているのではない。なぜ『魂魄の結晶』を抽出したマリアンヌが消滅するのだ。話が違うではないか!!」
「ですから、『魂魄の結晶』の抽出によってマリアンヌに人間の理性を取り戻させることはできると言いましたが、彼女を永続的に救うことができるとは最初から申し上げていません。」
「貴様は、この私をたばかったのか!?そもそも、なぜマリアンヌが『魂魄の結晶』を内包することを知っていた!そう言えば貴様はかつてアカデミー特務班の指揮官として本省から出向していたことがあったな。まさか!」
「ふふ、ようやくお気づきになりましたか。」
男は不敵に笑って見せた。
「そのまさかですよ、次席事務次官殿。マリアンヌが『古代屍術の魔靴』を愛用しているのを知って、アンデッドが群れなすアナンダ氷原に彼女を差し向けたのはこの私です。私にもアカデミーの最高評議会には何人か知り合いがいましてな。」
「何を言っているのだ、貴様は!ということはこの一連の奇死団騒動はすべて最初から貴様が仕組んだことだというのか!?」
「ようやくお分かりになりましたか?その通りですよ。私が、マリアンヌをリッチー・クイーンに転身するように仕向け、そして P.A.C. 計画遂行に必要な遺体、特に貴重な瀕死体を集めるために、いわばあなたを利用したのです。」
「では、私は、娘の、グランデの真の仇のために手を貸していたというのか!?」
「まぁ、そういうことになりますかな?おかげで、P.A.C. 計画はまもなく最終段階を迎えます。いや、もうすでに完成に至っております。」
「貴様、恩をあだで返そうというのか!!」
声の主があいての胸ぐらをつかみ上げる。
「恩をあだで返す?滅相もない。あなた様にはずいぶんとお世話になりましたから、私になりに最大限の謝意をお示しするつもりでおります。」
「ふざけたことを!!」
「そういえば、私の研究成果をご覧になりたいとおっしゃっておられましたな。よいでしょう。私の最大限の謝意として、あなたを私の最高傑作の最初の犠牲者にして差し上げます。」
そういうと、その声の主は実験室らしい部屋の横手にある重い扉を魔法で開錠した。
「さあ、ごらんなさい。素晴らしい出来でしょう!あなたが欲しがっておられた研究成果です。その実力をその身でたっぷりと味わうがよろしい。それでは失礼いたします。次席事務次官殿。」
そういってその声の主がその部屋を出ると、外から鍵のかかる音が聞こえた。そして、先ほど開いた扉の中から、おぞましいものが姿を現す。ひとしきりの残虐の後、その部屋に静けさが戻った。外では、男の高笑いが響いていた。
* * *
厚生労働省の庁舎の脇にある公園の植え込みで、同省の次席事務次官であり、グランデの父であるアルフレッド・トワイライト卿の惨殺死体が発見されたのは、新年が明けて間もない雪の激しい日のことであった。その遺体は、何か大型の獣とでも争ったかのような無残な姿で、見る者は目を覆わずにはいられなかった。その事件は、すぐに魔法社会の人々の耳目に届くことになる。
「奇死団の一件以降、物騒なことが続くね。」
「年末にやっとあの残酷な『裏口の魔法使い』が処刑されたばかりだというのに。」
「新年早々これとは、やりきれないよ。」
そんな声が辻々のあちこちから聞こえてきた。市民たちの動揺を抑えるために、街には政府警察が、アカデミー内には治安維持部隊が常時厳重な警邏体制を敷き、俄かに物々しい雰囲気を醸し出していた。
この事件の後、3人はアッキーナ婦人からの連絡を受けて、『アーカム』を訪れていた。
「事件についてはもうお聞き及びですね。」
アッキーナ婦人が3人に確認する。それに3人は頷いて答えた。
「アルフレッド・トワイライト卿は、ご存じの通り、グランデさんの御父上です。あのひどい殺されようは尋常ではありません。きっと大きな闇がその背後に蠢いていることは明らかです。」
「で、あたらしらにどうしろというんだよ。」
ウィザードが訊ねた。
「この事件の真相を調べてほしいのです。」
「しかし、あまりに手がかりが少なすぎませんか?」と言うネクロマンサー。
「しかも相手は厚生労働省でしょ?私たちに取り合うかしら?」
ソーサラーも心配そうだ。
「政府警察の公式見解では、トワイライト卿は魔獣に食い殺されたことになっています。しかし、あの傷は魔獣によるものとは考えにくく、それよりもっと力の強いものの仕業のように思えます。また、周辺に魔獣の目撃情報が一切ないのも気がかりです。」
アッキーナが状況についての見解を述べた。
「でもよぅ、トワイライト卿がどこかでその強大な力とやらにやられて、その遺体が発見場所に運ばれたのだとしたら、それこそ調べようがねぇぜ。目撃者が皆無てことだろ?」
ウィザードの指摘は正鵠を射ていた。
「グランデさんなら、最近の御父上の行動についてなにか思い当たることがあるのではないでしょうか?」
ネクロマンサーが切り出した。
「しかし、いま、彼女に聞き込みをするのは気が引けるぜ。マリアンヌのことがあってから半月かそこらで、今度は親父だからな。」
「そうね。彼女の心情を思うと、難しいかもしれないわね。」
「いずれにしてもこの事件を放っておくことはできません。」
アッキーナが毅然と言い放つ。
「とにかく、なんでもいいのでまずは情報を集めてください。」
「わかりました。とにかくできるだけのことはやってみましょう。」
ネクロマンサーはそう言って、ふたりに目配せした。
ふたりもそれに呼応して頷く。
「これは、ギルド『アーカム』からの正式の依頼です。きっとお願いしましたよ。」
それから、3人はアーカムを後にした。しかし、引き受けてはみたもののあまりにも雲をつかむような話過ぎる。みな正直途方に暮れていた。ひとまず事件の接点と言えば、グランデしかいない。3人は大きなためらいを抱えながらも、インディゴ・モースのグランデを訪ねることにした。
街ではまだ新年の賑わいが続いている。多くの市民にとって惨殺事件は他人事だった。魔法誌や魔法報道局は事件を面白おかしく書き立て、騒ぎ立てはするが、それは人々の関心を引こうとするばかりのことで、肝心のことは何も捉えていなかった。
* * *
インディゴ・モースにある『グランデ・トワイライト』本店は、喪に服し、新年のセールをすべてキャンセルしていた。本来であればひっきりなしであるはずの客足がすっかり途絶えていたのが印象的である。幸い、従業員は店に出てはいるようで、グランデとの取次を頼むことはできた。グランデも、それに応じてくれて、3人は今、グランデの私室にいる。
「グランデさん、この度は本当に…。」
ネクロマンサーが弔意を告げる。
「ありがとう。まさかお父様があんなことになるとは思わなかったわ。」
グランデはやはり消沈していた。
「でもね。くよくよ泣いてばかりはいられない。」
そういって、グランデは涙をぬぐう。
「私はこれからここの主任デザイナーとして、経営者であるお母さまを支えていかなければいけない。お姉さまたちのこともある。私がしっかりしないといけないのよ。それで、今日は?」
「お父様のことで、何かお心当たりはありませんか?」
ソーサラーが問うてみた。
「そうね。あまりにも突然のことで正直、私にも状況がよくわからないわ。」
グランデも困惑している。
「例えばよ。最近どこかに頻繁に出かけていたとか、そういうことはないか?」
ウィザードが訊いた。
「そういえば…。」
グランデには思い当たることがあるようだ。
「お父様はお仕事熱心な方だから基本的には家と庁舎を行ったり来たりするばかりだったけれど、一昨年あたりから、『ラウンド・オーソル』街にある料亭によくお出かけになられていたわね。そのころ、私はマリーお姉さまのことでふさぎ込んでいたのだけれど、お父様が言うにはそこに私の悲しみを癒せるかもしれない情報があるのだということだったわ。それが何かヒントにならないかしら?」
ラウンド・オーソルは中央市街地の中でも特に政府庁舎や議事堂が集中する政治の一大拠点である。
「その料亭の名前はわかりますか?」
ネクロマンサーが訊ねる。
「確か、お父様がそこの会員証をもって言いらしたわ。ちょっと待ってて。」
そういうとグランデは自室を出て、2階に上がっていった。
「どう思う?」とウィザード。
「そこで、誰かと会っていたことは間違いないわね。」
「でも、厚生労働省の次席事務次官が庁舎外で会う人物っていったい誰なのでしょう?」
ネクロマンサーは首をかしげた。
「いや、省外の人間であるとは限らないぜ。重要な話だからこそ、省内ではできないということだってあるはずだ。」
その指摘は確かだった。
「グランデさんからその場所を教わったら、一度訪ねてみましょう。」
そんな話をしているところにグランデが戻ってきた。
「あったわ。これよ。」
それは『カロン・ラクザス』という誰もが知る高級料亭だった。政治家や官僚、アカデミー高官御用達の店で、そこでは様々な政治密談が行われることで有名な場所だった。こうした店の従業員の口は堅い。聞き込みは困難が予想された。
「ありがとうございます。ひとまず、そこに行って事情を聴いてみます。」
そう言ってネクロマンサーはその会員証を魔術記録に収めた。
「気を落とさないでね。」
「無理をするなよ。仇はあたしたちがとってやる。」
ソーサラーとウィザードがグランデを気遣う。
「ありがとう。あなたたちも無茶をしないで。」
そういって3人はグランデのもとを後にした。
* * *
それから2日後、3人は『カロン・ラクザス』を訪問した。
「いらっしゃいませ。」
瀟洒なたたずまいの受付嬢が3人を迎える。こんなときは、ソーサラーの出番だ。
「今日は、お伺いしたいことがあってきました。」
「どのようなことでしょう?」
「先ごろお亡くなりになられたアルフレッド・トワイライト卿が、一昨年ほど前からこちらのお店を頻繁にご利用になられていたと伺ったのですが、どなたとご面会になられていたかわかりますか?」
受付嬢は、困ったという顔をして返答した。
「まことに恐れ入りますが、お客様のことをお話しすることは出来かねます。」
「そこをなんとかお願いできませんか。私たちは、亡くなられたトワイライト卿のご息女の友人なのです。卿の死の真相について知りたいのです。」
ソーサラーが負けじと食い下がるが、
「そう、おっしゃられましても。私共は口が堅いことが身上でございますので。どのような事情があれ、お客様の情報をお話しすることはできません。」
そう言ってゆずならない。しばらく押し問答を続けたがどうにも埒が明かないので、仕方なく引き上げようということになった。それで、店の出口を出て、前庭から門へと向かおうとした時であった。
「もし。」
3人を呼び止める声がした。振り返ると下働きの従業員なのであろう、3人より2つ3つ年下の少女がそこにいた。
「あの、アルフレッド様の死の真相をお調べになっておられるというのは本当ですか?」
その少女は話始めた。
「ええ、そうです。あなたは?」
そう問うソーサラーに、
「私はここで働いているラマンダと言います。実は私はアルフレッド様には大恩がありまして。それで、さきほどお話が聞こえたものですから、お声がけした次第です。」

少女は恐る恐る語った。聞くところによると、その少女はこの料亭の前で身売りに出されようとしていたところを、偶然そこに居合わせたトワイライト卿に救われ、卿が彼女の身代金を支払ってくれたのみならず、その身元引受人となって、この料亭で下働きできるように世話してくれたのだとのことだった。卿に恩義を感じるこの少女は、その不幸な死の真相を暴くために役立つならと協力を申し出てくれたのであった。
「ラマンダ。ここでは、なんだから。お部屋を1室お借りできる?」
ソーサラーが少女に尋ねた。
「はい、ご案内いたします。」
少女はそう言うと、2階の1室に3人を案内した。そこは手狭ながらも非常に洗練された内装の見事な部屋で、まさに高級料亭の一室というたたずまいであった。
「なぁ、おい。こんなところ、大丈夫なのかよ?あたし、金はないぜ。」
ウィザードが慌てている。
「大丈夫よ。任せておいて。」
ソーサラーはそう言って笑って見せた。

「とりあえず、簡単なお料理と飲み物をお願いね、ラマンダ。」
それから、これからしばらくあなたは私たちの客人だから、その旨、お店の方に伝えてちょうだい。
「かしこまりました。」
そういってラマンダは部屋を後にした。しばらくして料理と飲み物が運ばれてくる。それは見事な海鮮と美しい白ワインであった。

「ラマンダ、あなたも召し上がれ。」
ソーサラーがもじもじしているラマンダに料理を進める。
「あの、あの、本当によろしいのですか?」
「もちろんよ。あなたは私たちの大切な協力者だもの。」
「心配しないでください。あなたから聞いたことは絶対に秘密にします。ですから、知っていることをすべて話してもらえませんか?」
そう促すネクロマンサーの顔を見つめて、ラマンダは話し始めた。
「アルフレッド様がここにおいでになられるようになったのは、一昨年くらい前からです。それからは、週に一、二度定期的においでになられるようになりました。その時はかならず同じお相手と面会しておられました。」
「その相手の名前はわかる?」
ソーサラーが問うと少女は首を横に振った。
「お名前はわかりません。しかし、お話が漏れ聞こえる限りでは、同じご職場の方のように感じられました。そのお相手の方の研究に関することがいつも主な話題であったように思います。」
「その相手の顔を見ると、わかりますか?」
そう言ってネクロマンサーは、ローブの内ポケットから1枚の魔術記録を取り出して見せた。
「この方ではなかったですか?」
それはマークス・バレンティウヌの魔術記録であった。
「そうです。こちらの方です。この方のご研究に資金を繰り出すかどうかというお話をいつもしておいででした。この方がアルフレッド様のお嬢様のご心痛を和らげることのできる可能性をお持ちでいらっしゃると、そのように聞こえました。」
3人は我が意を得たりという顔をする。グランデのことだ!
「なんでも、アルフレッド様の末のお嬢様のご心痛を和らげるにはあるものを手に入れることが必要なのだけれど、それについてはお役所とアカデミーの衛生部門に緘口令を敷く必要があると、そして、そのためにはアルフレッド様の協力が必要なのだと、そのようにもお話になられておられました。」
どういうことだろう?その「手に入れる必要があるもの」というのが『魂魄の結晶』を指しているのは明らかだったが、マークスの研究とはいったい何のことか?また、そのために卿が協力していたとはどういうことか?緘口令ということは、卿が立場を利用して情報操作をしていたということなのだろうか?様々な可能性が脳裏をめぐるが、確たることはただ一つ、卿の死に、かのマークスが関与している可能性が極めて高い、ということである。
「最近、この魔術記録の人物はお店を訪ねてきますか?」
ネクロマンサーが訊くと少女は首を横に振った。
「アルフレッド様がお亡くなりになられた時期を境にして、まったくお姿をお見掛けしなくなりました。」
「この人物のしていた研究というのが何かわかる?」
ソーサラーが訊ねる。
「いいえ、わかりません。ただ、P.A.C. という言葉がおふたりの間によく上っていました。それが何を指すのかは私にはとんと見当が付きませんが。」
P.A.C. !!!
ここにきて、点が線をなしつつある。おそらく、P.A.C. というのがマークスの研究のことであり、具体的にそれが何であるかはわからないが、その研究をトワイライト卿が支援していたこと、そしてそれが『魂魄の結晶』となんらかの関係がある、ということだけは明らかになった。あとは、マークスが、3人に欺瞞を弄してまで『魂魄の結晶』を手に入れたがった理由がわかれば全容を解明できるかもしれない。ラマンダの証言によって、歯車が静かに噛み合い始めたような気がしていた。
「ありがとう、ラマンダ。とても参考になったわ。」
ソーサラーが声をかける。
「お役に立てましたか?」
「もちろん、大いに役立ったわ!」
「どうか、アルフレッド様の無念を晴らして差し上げてください。あの方がいらっしゃらなかったら、私は今頃色街に売られていました。あの方は私の恩人なのです。」
そういうラマンダの瞳は涙に潤んで輝いていた。
「約束するわ。きっと卿の敵は私たちでとるわね。」
「ありがとうございます。きっとお願いします。」
それからしばらく料理を楽しんだ後で、3人は料亭を後にした。会計は目玉が飛び出るような金額だったが、ソーサラーは涼しい顔でその支払いを済ませた。ウィザードとネクロマンサーは目を丸くしていた。
* * *
さて、トワイライト卿殺害事件の背後に、かのマークス・バレンティウヌの存在があることは明らかとなった。しかし問題は、マークスに至る糸が切れてしまっていることである。厚生労働省に問い合わせても、マークスに連絡をとることはできなくなってしまっていた。厚労省は、セキュリティ上の理由を主張するだけで全く埒が明かない。
3人は、マークスが技官でありながらアカデミーによる葬送に必ず出席していたことを思い出し、アカデミーの衛生部門に接触を図ることにした。ネクロマンサーの話では、遺体の搬出と一時保管に関する職務は、その仕事内容の性質上担い手が少なく、そこにおける人的なセキュリティ・レベルを維持するのが存外難しいということであった。そこで、やりようによっては担当者をうまく篭絡して情報を引き出せるのではないかということになり、その人物に接触を図ることになった。
遺体の安置所を現在管理しているのはシモネンという男で、酒やけした赤ら顔の小男だった。周囲の話では、酒と金にだらしなく、それらのためであれば親でも売るというもっぱらの評判であった。それで、3人は十分な手土産を携えて、そのシモネンを訪ねたのである。

「初めまして、シモネンさん。」
ソーサラーが挨拶を交わす。
「あっしに何用で?」酒の匂いがそこら中から漂ってきた。
「厚生労働省の元技官で、アカデミーによる葬送に毎回参列していたマークス・バレンティウヌ氏をご存じですね?」
「旦那がどうしたというんで?」
「アカデミーによる葬送とマークス氏の関係について、何か知ってることがあれば話してほしいのです。」
ソーサラーが切り込んでいく。その刹那男の目がきらりと光った。
「お嬢さん方が知りたいというのは、旦那のご商売のことで?」
「ご商売?」
「ええ、旦那は葬送の儀式を使ってちょっとしたご商売をしておいででしてね。」
「詳しく話していただけますか?」
「そりゃあ、構いませんがね。ただ、あっしは少々のどが渇いておりまして。」
そう言って男はほくそ笑んだ。
「そうですか。こちらなどいかがですか?」
ネクロマンサーがブランデーのボトルを取り出して見せた。
「これをあっしにいただけるんで?」
「もちろんです。お納めください。」
「こりゃあどうも。」
そういうと男はネクロマンサーの手からボトルを奪うようにして、自分の傍らにそれを置いた。
「それで、マークス氏の商売というのは?」
「どうやら、旦那はご自分の研究に葬送の儀式をご活用なさっておいででだったようで。」
「というと?」
「へへ、あっしもアカデミーの従業員ですから、守秘義務というやつがありまして。なかなか簡単にお立場ある方のことをお話しするわけにはまいりませんので。」
そう言いながら男はにやにやしている。
「そうなの。じゃあ、これでいかがかしら?」
ソーサラーはかなりの数の金貨が入っているのであろう革袋を男の手に握らせた。男は早速その革袋をあけて値踏みをした後、上目遣いで話し始めた。

「実のところですね。あっしらにとってはけったいな話ですが、旦那は死体、とりわけ瀕死体を非常に欲しがっておいでだったんです。それで、特務班が移送してきた瀕死体はアカデミーではなく、厚労省の医療班に極秘裏に移送し、遺体についてもこっそりどこかに運び込んでおいででした。」
「そんなことを!?」
3人の顔に緊張が走る。
「あっしらは旦那から金をつかまされてそれを黙認していたんで。そんなわけでここ最近頻回に行われていたアカデミーによる葬送に用いられた棺は大方というか正直その全部が空っぽだったと、そういうことでさあ。なんでも旦那が取り組んでおられる研究には、いっぺえの死体が必要だとかで、だからあっしらはせっせとその手伝いをしておりましたんで。」
「なんてこと!でも、そんな不正はすぐに厚労省が把握するでしょうに!」
ソーサラーが怒りをにじませる。
「それなんでさ。その厚労省のかなり上の方に旦那の協力者がいらしたらしく、旦那の行状はことごとく伏せられていたんでさぁ。あっしらが口を割らない限りまずバレることはないってくらいに情報統制は完璧だったようですぜ。」
「その協力者というのは誰?」
「ほら、先ごろ殺された。なんて言ったか?でかい魔法具屋の奥さんを持つおひとでさぁ。」
トワイライト卿のことだ!
「なぜその方が、マークス氏に協力していたかわかりますか?」
そう問うネクロマンサーにまたしても男はいやらしい笑顔を向けた。
「いやあ、何と言いますか、守秘義務がですね。」
「もちろんよ。」
そう言って、ソーサラーはもう1袋革袋を渡した。男はまたもや袋を開いて値踏みしながら続けた。
「なんでも、その御仁のお嬢さんを助けるためだそうで。そのお嬢さんはなにやら悲しみに暮れておいでだったそうなんですが、旦那の研究がその解決策になるかもしれないと。それと引き換えに旦那の研究について目をつぶれというか、まあ協力しろということだったみたいでさぁ。」
つながった!グランデの心の傷をいやすため、つまりマリアンヌを救済するために卿はマークスの研究を黙認する形で彼に手を貸していたのだ。そして自分たちがマークスに欺かれたように、卿もきっと騙された。それでトラブルとなって殺された可能性が高い!!!犯人は間違いなくマークスだ!
「で、マークス氏が今どこにいるかわかる?」
「それが、とんと見当もつかねえんで。あっしらとしてもいい金づるがいなくなって商売あがったりですよ。へへ。」
なんとも下卑た笑いをその男は浮かべた。しかし、マークスの行方を知らないというその言葉に嘘はなさそうだ。
「ありがとう。これもとっておいて。」
そう言ってソーサラーはもう1袋、革袋を男に手渡した。
「こりゃあどうも。」
男は慇懃無礼なお辞儀を繰り返しながら、仕事場へと戻っていった。
トワイライト卿の死にマークスが直接関与しているのはほぼ確実となった。しかし、マークスの目的がいまいちよくわからない。葬送の儀式から遺体や瀕死体を奪っていったい何をしようというのか?3人は頭を抱えていた。真相を究明するにはやはりマークスのしっぽを掴むしかないのかもしれない。
年が明け、1月も半ばに差し掛かるが、冬はまだ厳しく、魔法社会全体が深い雪に覆われている。マークスはどこに消えたのか?またその目的とは何か?3人の探求は続いていく。
第2節『敗北』
3人がアルフレッド・トワイライト卿の死の真相にたどり着き始めたころ、それは1月も半ばに差し掛かろうという時であった。またしても、魔法社会を震撼させる出来事が起こり始めていた。さまざまな辻々で、通り魔事件が頻発するようになったのである。犠牲者はみな、トワイライト卿と同じような惨たらしい姿で発見された。あるものは獣に裂かれたようであり、またある者は魔法の火で焼き尽くされ、中には、雷で撃たれたような者もあった。奇死団の一件以降、裏口の魔法使い、変死事件、そして今回の通り魔事件と、魔法社会の人々は息つく暇もないほどに続く災難に見舞われていた。3人は、またしても『アーカム』の依頼により、この通り魔事件についても調べることになったのである。
「しかし、こうも次々だとさすがに参るぜ。」
そうこぼすのはウィザードだ。
「そうね。でも、あの犠牲者の殺害された様子からして今回の通り魔事件がトワイライト卿の一件と何らかの関係があるのは確かよ。」
ソーサラーはそう分析した。
「はやく解決して、人々の不安を取り除かないといけませんね。」
ネクロマンサーも焦りをにじませる。
この通り魔事件については、アカデミーの治安維持部隊や漆黒の渡烏の他、各ギルドも一斉に調査に乗り出しており、特にウィザードのギルドである『全国魔術師生活協同組合』は精力的にその調査にあたっていた。しかし、その全容はようとして明らかにならなかった。増え続ける犠牲者に政府もアカデミーも業を煮やしていたが、その惨劇が、文字通り常にいずれかの「通り」で起こることだけは、明らかになりつつあった。
そのため、深夜の辻々では物々しい警邏体制が敷かれるようになっており、3人も、ルートを決めて、毎夜警戒にあたっていた。
1月中旬の極寒の時期である。深夜の警邏は困難を極めるものであった。雪深い中を、今夜も3人は、サンフレッチェ大橋から、マーチン通りを南に抜け、アカデミー前を通って、リック通りへと差し掛かっていた。
「それにしても寒いな。こうも冷えると体に堪えるぜ。」
「そうね。このところマークスについての新しい手掛かりも得られないし…。」
「確かに、手詰まり感が強いですね。」
そんなことを話しながら周辺の警戒にあたっていた。
雪はどんどんと降り積もり、魔法社会全体を真っ白に覆って、その一面の銀世界を月明かりが怪しく照らし出していた。遠くで犬の遠吠えが聞こえる。そのほかに耳に入るものといえば、雪を刻む足音だけであった。時間の経過とともに一層冷え込みが厳しくなる。
「それにしても、いくら『通り魔』だからって、こうも毎回どこかの通りでおこるもんかよ?」
ウィザードが不思議そうに言う。
「まぁ、『通り』で起こるから『通り魔』って言うんじゃない?」
「でも、その指摘には一理あります。何かを探しているんでしょうか?」
3人がそんな会話をしながら、リック通りを抜けて東に進路を取ろうとしていた時だった。
漆黒の闇夜に大きな悲鳴がこだました。
「通り魔だ!」
声のする方に駆けつけてみると、そこには何とも惨たらしい犠牲者の姿があった。礫を繰り出すような魔法で、何度も身体を打ち付けられたようで、全身に打ち身と傷があり、ところどころ骨は砕かれ、街路樹にもたれかかるようにしてその哀れな人物は息絶えていた。
3人はすぐさまあたりを見回った。
ネクロマンサーは、死霊まで繰り出して一帯を捜索したが、残念ながら犯人の足取りを追うことはできなかった。
「どうやら、これは魔法使いの仕業ですね。」
ネクロマンサーが見解を述べた。
「そうね。どうやら『転移:Magic Transport』の術式で移動しているようだわ。」
ソーサラーも同意見のようだ。
「しかし、そうだとすると厄介だぜ。文字通り神出鬼没の通り魔ってことになりやがる。」
「とにかく、この件について当局に通報しましょう。」
そういって3人は、アカデミーの治安維持部隊と連絡を取り、臨場した部隊員に今起こったことをわかる範囲で報告した。

「悲鳴が聞こえて駆けつけると、このご遺体があったということですね?」
「ああ、あたしたちが駆けつけた時にはもう犯人の姿はなかったぜ。」
「見た範囲では、魔法による危害のように感じられます。また、犯人のその素早い移動の状況から考えて魔法使いによる犯行ではないでしょうか?」
「しかし、『スカッチェ通り』で事件を起こした裏口の魔法使いはすでに処刑されているはずです。新手が現れたという情報は今のところないのですが…。」
しばらく隊員と情報を交換した後、3人はアカデミーへと帰寮した。その夜はそれ以上のことは何もつかむことができなかった。
翌日も、そのまた翌日もこれといった手がかりは得られないままに、犠牲者の数だけが増えていった。犯罪は次第に大胆になり、深夜帯のみならず、明け方や夕刻など陽がある時間帯にも起こるようになってきた。被害者に共通点はなく、完全な無差別犯罪で、魔法社会全体が大きく戦慄していた。政府およびアカデミーは一層の人員を繰り出してより厳重な警邏体制を敷いていたが、犯人にたどり着くことは容易でなかった。
それから一週間ほどが過ぎた、雪が降りしきる特に寒い夜のことである。3人はその日も独自に調査と警戒にあたっていた。その日は、アカデミー前から西に進路をとって、マーチン通りを北に進み、サンフレッチェ大橋を抜けてスカッチェ通りへと向かっていた。北風が強く、上空でひょうひょうと空気が鳴いている。
「寒いぜ。」
ウィザードがこぼす。
「本当ですね。この寒さはちょっと異常です。」
ネクロマンサーも耐えかねているようだ。
「ねぇ、あれを見て!」
そう言ったのはソーサラーだった。
彼女が指し示す方向をみると、ちょうどスカッチェ大橋に差し掛かろうというところに、怪しげな魔法光を放つローブの人物の、何かを探すような姿たがあった。
3人は、その人物に声をかけた。
「こんばんは。どうかなさいましたか?」
ネクロマンサーがさりげなく切り出す。
「ご存じかと思いますが、通り魔が頻発していますから、安全な屋内へ移動してください。」
ソーサラーがそう勧めた。
「おい、聞いているのか?」
ウィザードがその意思を確かめるも、その人物は、何かぶつぶつと呪文のようなものを唱えながら、しきりにあたりを見回している。明らかに様子がおかしい。

「私たちは『南5番街22-3番地ギルド』の者です。お話を聞かせていただいてもよろしいですか?」
ネクロマンサーがそう話しかけた時だった。
その怪しいローブの人影は、さっと姿勢を変えて3人の方を振り向くと詠唱を始めた。攻撃術式だ!
その手から炎が3人に向かってほとばしる。咄嗟にその場を離れて身をかわす3人。
「おい、てめぇ、何をしやがる!」
「暗号を…。」
その人影はしきりになにかを呟いている。
「抵抗はやめなさい。あなたの身柄を当局に引き渡します。おとなしくしてください!」
ネクロマンサーが警告をするが、聞く耳を持たない。その影は『転移:Magic Transport』の術式を繰り返して小刻みに瞬間移動しながら、3人に向かって襲い掛かってきた。
「おい、どうするよ!?」
「どうするって、やるしかないんじゃない?」
ウィザードの問いかけにソーサラーが答えた時だった。今度はその手から稲妻がほとばしる。
「あぶない!」
そういって、ウィザードがソーサラーの身体を横倒しに押しのけた。間一髪である。どうやらこいつが通り魔の犯人に違いない。警告に応じないのならば、撃退するまでだ。そう思い定めて3人はその人物と正面から対峙する。相変わらず、北風が上空でか細い鳴き声を上げていた。
* * *
「しょうがねぇ、やってやるぜ!」
『火と光を司る者よ。我が手に炎の波をなせ。我が敵を薙ぎ払い、燃えつくさん。殲滅!炎の潮流:Flaming Stream!』
ウィザードが火と光の高等術式を繰り出す。その手からは炎の潮流がほとばしり、その人影を包み燃やし尽くそうとする。
直撃であった。しかし、その人影はその炎をものともせず、反対に『氷刃の豪雨』を繰り出してきた。
「障壁を!早く!」
ソーサラーの声に呼応してウィザードが『炎壁展開:Fire Walls』の術式を行使して3人の周囲に障壁を展開する。しかし、襲い掛かってくる氷刃のいくらかは防ぐことができたが、障壁は瞬く間に破られ、3人はその刃に組み伏せられた。致命傷でこそないが、相当の傷を負っている。
直撃を避けられたのは、ネクロマンサーが咄嗟に数体の霊体を召喚し、それらが身代わりになってくれたからで、非常に危ない局面であった。
「強い。」
ソーサラーが呟く。
「もう一度!」
『慈悲深き加護者よ。我が祈りに応えよ。その英知と力をその庇護者に授けん。我が頭上に冥府の門を開き、暗黒の魂を現世に誘わん。開門せよ!暗黒召喚:Summon Drakness!』
ネクロマンサーが霊体を召喚する。今度は数も多い。
「契約のもとに、我が敵を滅ぼせ!」
彼女の命令で召喚された霊体は一斉に通り魔に襲い掛かる。その刹那!その手から虹色の光がほとばしったかと思うと、霊体はことごとく胡散霧消してしまった。相手は、耐アンデッド術式も心得ているようだ。
それならばと、ソーサラーが『加重水圧:Hydro Pressure』の術式を繰り出す。通り魔はよけるそぶりも見せずにそれは直撃するが、やはり全く効果がない。
「そんなばかな!」
ソーサラーも驚きを隠せない。
またしてもそのローブの人影は詠唱を始める。今度は『衝撃波:Shock Wave』だ!とっさに防御行動をとるが、ほぼ直撃で、3人は後方に大きく吹き飛ばされ、橋の欄干に身体を強打した。衝撃で息ができない。痛みをこらえて相手を見据えるが、それはお構いなしに、次の詠唱を始めた。
「やられる!」
3人は、目を固く閉じて、顔をそむけた。
その時だった。
あたりがまばゆい昼光の明滅に照らされ、通り魔に向けて稲妻がほとばしった。その稲妻には相当の威力があるようで、その影も身をひるがえして回避行動をとっている。あきらかに直撃を嫌っているようだ。その稲妻の出所を探すようにあたりを見回している。
続けざまに、稲妻がほとばしる。その影は一歩、二歩と後ずさり、それを避けていく。なおも稲妻の襲来は続き、ついにあきらめたのかその人影は『転移:Magic Transport』の術式を行使してその場を去っていった。
ようやくその場に静けさが戻る。雪は相変わらず降り続け、上空では風が鳴っている。
「助かったのか…?」
ウィザードはあたりを見渡すが、雷撃で援護してくれた者の姿はもうあたりにはなかった。
「いったい何なの?」
ソーサラーも慄いている。
「誰かわかりませんが、命を救われましたね。」
ネクロマンサーがゆっくりと立ち上がった。橋の欄干に強打した身体が激しく痛む。氷刃による傷もあって、立っているのがやっとだった。
「なんてやつだ…。」
「あんなの相手じゃ、命がいくつあっても足りないわね。」
「そうですね。とにかくこちらの魔法が通用しないのが難点です。」
3人は顔を見合わせて落胆する。
ひとまずその場はネクロマンサーの回復術式でいくばくか傷を癒し、警邏中の治安維持部隊隊員に状況を説明して犯人の風体を伝えてから帰寮した。完全な敗北であった。
雪はなおも降り続き、さながら吹雪の様相を呈してきた。風の鳴き声は一層するどくなり、耳の奥が痛いようにさえ感じる。相手は相当に強力だ。果たして対抗できるのか?3人の胸中には恐怖と不安が渦巻いていた。
* * *
翌日3人は『アーカム』にいた。昨晩の報告と、通り魔への対策を相談するためである。相手が高等術式をものともしないという事実は驚愕であった。
今日のドアは引き開きで、少女アッキーナが3人を出迎えてくれた。
「いらっしゃい。」
そういうとアッキーナは3人にお茶を勧めてくれた。今日は『ベルガモント』だった。

「アッキーナ、今日はマダムはいらっしゃらないの?」
ソーサラーが訊ねると、少女はふるふると顔を横に振った。
「そう…。困ったわね。」
そういうソーサラーに、アッキーナが言った。
「何があったのか話してください。できるだけ力になります。」
実は…、そういって3人は昨晩の事情を彼女に説明した。それを訊いた彼女は小首をかしげてからこういった。
「基礎魔法威力の不足です。」
「それはわかってるけどよ。あたしたちじゃ高等術式までしか使えないんだ。それがああも効かねぇとなると手の打ちようがないぜ。」
ウィザードが焦りをのぞかせた。
「どんな下着を着てる?」
アッキーナがひょんなことを訊いた?
3人はよくわからないという風に顔を見合わせる。
「あたしは、そこらの店で売ってる普通のやつだよ。」
ウィザードがそう答えた。
「私は、ロコット・アフュームのです。」
「私は、今日はラヴィ・ムーンよ。」
ネクロマンサーとソーサラーもその日の一着を報告した。
「それではだめです。」
少女は、真剣なまなざしで言った。
「魔法使いたるもの、準備は重要です。特に着衣は魔法力の強化に重要な意味を持っています。」
「それは知ってるけどよ。だから、こうして『輻輳の手指』に『増魔のリボン』、『増魔の魔靴』にローブまで、最適なものを選んでるぜ。」
「基本がなっていません。」
アッキーナは毅然と言い放った。
「基本っつてもよ。」
ウィザードは動揺する。
「おしゃれの基本は下着です。魔法力強化の基本もまたしかりです。」
普段口数の少ない少女アッキーナが今日は妙に雄弁だ。
「ちょっと待っててください。」
そういって、彼女は店の奥へと姿を消した。
「どう思う?」
「さぁ?」
そんなことを言っていると、奥からアッキーナが戻ってきた。両手いっぱいに下着らしきものを携えている。
「よっこらしょ、っと。」
そう言って彼女はカウンターにそれらを並べて見せた。
「まずはこれ、『炎熱のビキニ』。これは火と光の領域の魔法特性を著しく高めます。これを着ていれば、相手に魔法が届きます。」

「といってもこれ燃えてねぇか?こんなの着られるのかよ?」
「着られる。熱いけど。」
「熱いのかよ!」
少女がこくこくと頷く。
続いてソーサラーの方を向いて別の下着を示した。
「これは『氷結のビキニ』。水と氷の力を大きく引き出す。ただ、冷たい。」

「もうひとつは、これ。『死霊のランジェリーセット』。冥府の門に直接アクセスできる力を得られる。対霊術式に耐性のある霊体を召喚できる。」

「これらを着て戦えば、きっと勝てる。」
アッキーナはそう言った。
「でもよ、アッキーナ。この店の商品ってことは呪われているんだろ?」
少女は当然という面持ちでこくこくと頷く。
「そこは否定してほしかったぜ。」
ウィザードがうなった。
「それで、アッキーナ。これは実際にどう呪われてるの?」
ソーサラーが訊ねる。
「『炎熱のビキニ』と『氷結のビキニ』は着ている者の体力を徐々に奪う。そして、『死霊のランジェリーセット』は長く着ているとレイスになってしまう。だから、どれも着ていられる時間は短時間。どんなに長くても3時間以内には脱がないといけない。」
アッキーナはそう説明した。
「反対に言うと、3時間以内であれば、十分な魔法威力の向上を得られるってことだな?」
「そう。」
少女はやはりこくこくと頷く。
「相手はたぶん人間じゃない。だから、相当に魔法威力を底上げしないと通用しない。準備が大事。肝心な時には勝負下着。」
「わかったわ。アッキーナ。試してみる。」
ソーサラーが意を決したようにそう言った。
「ほかに何か気を付けることがありますか?」
「ない。とにかく3時間。時間だけ守って。」
幼いアッキーナはそう言って、お茶を飲んだ。
「でもよ、そんなに魔法威力を底上げしたら、魔力枯渇を起こさないか?」
もっともな懸念だった。
「大丈夫。呪われているかわりにその心配はない。とにかく時間。時間だけが重要。」
「わかったわ、アッキーナありがとう。」
「大丈夫。」
そういって少女はふるふると首を横に振った。
しばらく今後のことについて相談したのち、3人はアーカムを後にした。身を切るような寒さがあたり一面を覆っている。しかし、下着を変えたくらいで本当にあの強大な力に対抗できるのか?しかし、今はアッキーナの提案に乗るよりほかに手がないのも事実であった。
3時間というのは思いのほか厳しい。というのも相手とすぐに遭遇できる保証はないからだ。警邏中にも時間は経過していくわけで、そのあたりをいかに調整するか、3人は思案した。そして、毎夜22時から翌1時まで捜索をすることに決め、万一の時にはその呪われた着衣をすぐにでも脱ぐことができるように、着替えを持参するということで話が決まった。
雪と風は一層激しくなり、今夜は吹雪そうな気配だ。マークスを逆順にたどる3人をその雪と風が容赦なく襲った。今夜もう一度!3人は静かに逆襲を誓う。
第3節『再戦と逆襲』
年端も行かない少女アッキーナに乙女のおしゃれの基本は何たるかを教授された3人は、その翌日、託されたあの勝負下着を身に着けて、通りの警邏にあたっていた。その日は、アカデミー前から進路を東にとってリック通りを北上し、クリーパー橋の高架下を移動していた。ちょうど『アーカム』に至るために M.A.R.C.S. を辿るのに似た道筋だった。今日も雪は深く風が強い。吹雪くとまではいかないが、天候は荒れ、月は厚い雲の中に隠れていてた。星はちらちらとその瞬きを見せるが、冬の悪天候が3人を容赦なく襲っていた。そんな中、ひとりそわそわしているのはウィザードだった。
「どうしたのよ?」
ソーサラーが訊ねる。
「いや、あっちーんだよ。おまえらなんともねーのかよ?」
そういってウィザードが毒づく。
「私は寒いわよ。外がこれだけ寒いってのに中まで寒くて芯にいるわ。」
「私はなんだか身体が消えていきそうです。」
ソーサラーとネクロマンサーがそう応じた。
この服飾を身に着けていられるのは3時間。それ以上は危険が及ぶ。3人は慎重に時間を計りながら、警邏を続けていた。クリーパー橋の高架を抜けて南大通りを南下するころにはちょうど時間になる。今日はひとまずそこまでになりそうだ。
「着替えてからもう少し警邏する?」
そう訊くソーサラーに、
「おいおい、こんな真夜中に通りのど真ん中で素っ裸になんのかよ。勘弁だぜ。」
そう言ってウィザードは首を横に振った。
雪はどんどん深くなり、風もひっきりなしに鳴いている。熱かったり寒かったり、消えそうだったり、三者三様の事情を抱えながら、クリーパー橋の高架下を過ぎて南大通りを南下していた。その日はマーチン通りを通っていないので、あたりが霧に覆われることはない。アーカムへ至る暗号は極めて精緻に機能していて、わずかでもその所定の道筋を外れると目印となる霧を生じることはなかった。
南大通りを南下している途中で、喧騒な事態に出くわした。
「あそこだ!」
「追え!」
そんな声が聞こえる。
その声のする方に駆けてみると、先日煮え湯を飲まされたローブの人影がアカデミーの治安維持部隊と交戦していた。
治安維持部隊も必死に対抗しているが、実力の差は明らかで、どんどんと追い詰められていく。
「こいつ、抵抗するな!」
そういって所持している錬金銃砲を発砲する。弾丸は命中するが、一向に効いている様子がない。そうこうしているうちにその影が繰り出す強力な魔法によってたちまち窮地に追い込まれていった。
3人はそこに駆けて行って、声を上げた。
「ここは『南5番街22-3番地ギルド』が引き継ぎます。怪我人を連れてすぐに退去してください。」
その声を聞くや、治安維持部隊は撤退を始めた。
「すまない、よろしく頼む。我々の手には負えない。」
そう言って引き上げを開始する治安維持部隊の面々。
「ここは任せてください!」
こうして、再びそのローブの異形と対峙することとなった。相手は禍々しい殺意に満ちている。果たしてこの勝負下着とやらがどこまで効果を発揮してくれるのかはわからないが、残された時間はそれほど長いわけではない。3人は各々その異形と距離をとって対決姿勢を鮮明にした。
* * *
「このやろう。前回の借りは返してやるぜ。アッキーナ様直伝の勝負下着の威力を見せてやる!」
それもどうなのよ、と言いたげなソーサラーを尻目にウィザードが詠唱を始める。
『火と光を司るものよ。水と氷を司るものとともになして、わが手に力を授けん。火と光に球体を成さしめて我が敵を撃ち落とさん!砲弾火球:Flaming Cannon Balls!』
中等術式だが、根限り輻輳を効かせて、これでもかという数の火球を繰り出す。先日とは違い、今日は相手も回避行動をとってきた。明らかに直撃を嫌っているようだ。繰り出した火球の何発かが命中する。
相手は大きく上半身をのけぞらせ、火球が命中した個所から火を噴きだし、その箇所が赤く燃え上がっている。
「効果があるぞ!」
ウィザードが声を上げた!
「どうやら、アッキーナのアドバイスは間違いないようね!」
そう言って、ソーサラーが『氷刃の豪雨』の術式を詠唱する。
『水と氷を司る者よ。我は汝の敬虔な庇護者也。わが手に数多の剣を成せ。氷刃を中空に巡らせよ。汝にあだなす者に天誅を加えん!滅せよ。氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swords!』
数多の氷刃がその影を襲撃する。それは障壁を展開し、防御を図ったが、いくつかの氷刃がその体を捉え、確実にそれを切り裂いた。
低くおぞましく唸る声が聞こえる。勝負下着には確かな効果がある。基礎魔法威力を高めることで、相手の耐性能力を上回ることができているようだ。そのローブの人影は見覚えのあるぎこちない動きを連続させながら、居住まいをただしてこちらに向き直る。
その手に魔力が込められるのがわかる。
「来るわよ!」
ウィザードはそのソーサラーの声に呼応して『光の盾:Lighte Shield』の術式を展開した。相手は凄まじい勢いの雷撃を展開したが、どうにかそのすべてを遮蔽することができた。勝負下着の効果は攻撃術式だけではなく防御術式にも及ぶようだ。
その傍らでネクロマンサーが詠唱をしている。
『慈悲深き加護者よ。我が祈りに応えよ。その英知と力をその庇護者に授けん。我が頭上に冥府の門を開き、暗黒の魂を現世に誘わん。開門せよ!暗黒召喚:Summon Drakness!』
彼女の頭上に冥府の門が開き、そこから多数の死霊が飛来する。ローブの人影は、前回と同じように対霊術式を行使した。一部の死霊はそれに飲まれて消滅するが、今回はそれに耐えるものも少なくない。やがて3、4体の強力なレイスがその人影にとりつき、ひとしきり格闘する。耳を裂くような声のたびにその人影を食いちぎり、引き裂く。人影はとても人間の者とは思えない、どす黒い血を噴き上げながら、手にした術具であろう剣で悪霊を薙ぎ払っていた。
もう一息。そう思ってネクロマンサーは詠唱を重ねる。
『天候を司る者よ。我が手に暗雲をなせ。大気を帯電し、その力を解き放たん。我が敵を撃て!Thunder Cloud!』

詠唱が終わるやあたりに一層の暗雲が垂れ込め、そこから幾筋もの稲妻が、そのローブの人影をめがけてほとばしった。それは『転移:Magic Transport』を駆使した巧みな回避行動でそのほとんどを交わしたが、それでも幾筋かは確実にその身体を捉える。稲妻の命中したところからは閃光と炎がほとばしり、その影は明らかに怯み狼狽している。その身体からは、いよいよ炎が吹き出、燃え盛らんばかりとなったが、その瞬間、それは『転移:Magic Transport』の術式を行使してそこから逃げ去ってしまった。
「ちきしょう。あと少しだったのに!」
ウィザードが悔しがる。
「まぁ、撃退できただけでよかったわよ。」
ソーサラーはそう言いながらも肩で息をしていた。
「それにしても、強いですね。今日はたまたまタイミングが良かったですが…。」
そういって、ネクロマンサーもその場に片膝をついている。
「こちらにタイムリミットがある以上、そう何度もやりあえるわけじゃねぇ。早めにケリを付けねぇといけねぇな。」
ウィザードは言い聞かせるようにそう言った。
「時間と言えば、今は何時?」
ソーサラーが慌てて聞く。
「大変、もう1時20分を回っています。急いで着替えないと!」
「って、こんなところで真っ裸になるのか!勘弁してくれよ。」
ウィザードが嘆く。
「死ぬよりましよ。」
そういって、ソーサラーが服を脱ぎ始めた。
「まて、まて、いくらなんでもやばすぎる。おい、死霊召喚してくれよ。そいつらを目隠しにしてくれ。」
「こんな夜中に誰も見ちゃいないわよ。とにかく寒くてたまらないわ。」
そういってどんどん服を脱ぎ始めるソーサラーの周りを、ネクロマンサーが召喚した死霊が覆い隠すようにその周囲に集まってくる。3人は、着替えを済ませて、なんとか人心地ついた。
「この方法はリスクがありすぎるぜ。」
「確かにね。もうすこし抜本的な解決策を考えないと、今後やっていけないわね。」
ウィザードの懸念にソーサラーもそう答えた。
「とにかくも、ひとつ前進ではあります。」
ネクロマンサーが静かにそう言った。
「まったく対抗できないということはなくなりました。あとはもっと効果的な方法を探すだけです。」
3人は深くうなづいてから、リック通りまで撤退していた治安維持部隊に追いつき、状況を説明して帰寮した。
天候は荒れる一方で、改善の気配を見せない。冬の厳しさはまだまだ続いている。空はうなるように風の音をしきりに響かせていた。春はまだ遠い。
* * *
その翌日、3人の姿は『アーカム』にあった。
今日の扉は押し開きで、3人を迎えてくれたのは少年アッキーナである。
「いらっしゃい。昨晩はご活躍だったみたいですね。」
お茶を淹れながらアッキーナが言う。
「あなたが勧めてくれたあのアンダーウェアの効果は確かに間違いがなかったけれど、今後あいつとやりあうにはもう少し抜本的な対策が必要になるわ。」
ソーサラーはそう告げた。
「そうですか。まぁ、確かに、3時間というのは便利が悪すぎますよね。あれをいつも着ているというわけにいかないわけですから。」
アッキーナもそれは承知していたという調子で言う。
「なにかいい方法はないものかしら?」
そう問うソーサラーに、
「とにかくも、魔法下着は皆さんが思っているよりも重要です。呪われたものを身に着ける必要はありませんが、魔法力の拡張に優れたものを常に身に着けておくことは大切です。」
とアッキーナは答えた。
「それは今回のことでよくわかったわ。でも、今の私たちにはもう少し現実的な対策が必要なのも事実よ。」
ソーサラーははっきりと現在の懸念を伝えた。
「確かにそうですね。まあ、とりあえずはお茶を。今日は『ガリーニーデン』です。」
そういって、彼は3人にお茶をふるまった。

そのお茶は、にんにくのような辛みとショウガのような薬味の効いた独特のもので、ウィザードはとても飲めたものじゃないというような顔をしている。
「遠からず、あれとは再戦しなければならないわ。アッキーナ、何かいい対策法はないかしら?」
ソーサラーが問う。
「皆さんが、禁忌術式や究極術式を身に着けてくだされば解決なんですが…。」
そういうアッキーナに、
「でも、そんなことをしたらあたしら、そろって退学だぜ!」
ウィザードが食い下がった。
「ごめんなさい。わかっていますよ。困りましたね。」
そう言いながら、アッキーナはポットをゆっくりとゆすっている。
「いらっしゃっているの?」
奥から声が聞こえた。
「はい、おいでになられています。」
その声にアッキーナが答える。
「すぐに行くわね。」
そう言うと足音が近づき、奥から貴婦人が姿を現した。
「いらっしゃい。」
「お邪魔していています。」
3人は貴婦人と挨拶を交わした。
「通り魔に手を焼いているようね。」
アッキーナが淹れたお茶のカップを傾けながら貴婦人が言う。
「そうなんです。呪いの下着は確かに効果がありますが、いつでも使えるわけではありません。」
ソーサラーは状況を説明した。
貴婦人はいつものように目を細めてから、
「いっそ、あなたがたも、裏口の魔法使いになる?」
そう問うてきた。
「いや、それは…。」
言いよどむ3人を前にして、
「ごめんなさい。ちょっと意地悪を言っただけよ。あなたたちにそんな無理を強いるつもりはないわ。」
そういって、貴婦人はさらにカップを傾けた。彼女の言う、あなたたち「も」というのが少し気になった。
「実は、あなた方に立ちはだかっている相手は、とても強力なの。」
貴婦人は続ける。
「本当は、政府やアカデミーが中心となって対処すべき問題なのだけれど…。」
言いよどむようにして貴婦人は続けた。
「残念ながら、今は彼らの協力を請うことは難しいわ。事態は深刻な局面を迎えつつあるの。そういえば、P.A.C. についてはまだお話ししていなかったわね?」
3人はその言葉に、食い入るように聞き入った。
「P.A.C. とは、Production of Artificial Creatures の略、つまり、人工生命体の製造ね。」
驚くべきことを貴婦人はさらりと言った。
「マークスは、アカデミーから簒奪した遺体を錬金術と魔法により冒涜することで、そこから人為の生命体、いうなれば『人為の魔法使い』を錬成しているのよ。」
貴婦人はお茶を一口含んで続けた。
「あなたたちが、これまで対峙してきた敵、ポンド・ザックの闇市や、P.A.C. 商店、リリーさんのお店で戦ってきた相手はみんなその犠牲者の成れの果て…。」
そういうと貴婦人は大きくため息をついた。
「そして、奇死団の一件を経て『魂魄の結晶』を手に入れたマークスは、ついに究極の P.A.C. を開発することに成功したわ。先日来あなた方が交戦したのはその究極の P.A.C. の一つよ。」
3人は息を飲む。
「それはもう人間をあらゆる点で凌駕しているわ。いまや、正直呪いにでも頼らなければ、傷一つつけることはできない存在となっている…。」
そう言って彼女は再び深いため息をついた。その美しい瞳は静かに虚空を見つめている。
「マークスの狙いは一体何なのですか?無差別殺人が目的とも思えないのですが…?」
ネクロマンサーが貴婦人に問うた。
「おそらく…。」
貴婦人は静かに語り始めた。
「彼は、創造主になったつもりなのでしょうね。」
それに続く言葉を3人は固唾をのんで見守った。
「おそらく、何か明確な目的があるというより、自分の力で生命を思うままにできるということ、それ自体が、いま彼の心を深く捉えてているのだと思うわ。自分の生み出した究極の生命が他の生命を蝕んでいく。そのこと自体を純粋に楽しみ喜んでいるのだと思うわ。」
貴婦人は驚くべきことを口にした。
「そんな、それって…。」
ソーサラーが驚嘆の面持ちでこぼす。
「そう、狂気ね。彼、マークスは今完全な狂気にとらわれているわ。自分は万能の創造主になったという幻想にね。」
そう言うと、貴婦人はカップを空けた。
「あなたたちと、それから、この魔法社会それ自体がとんでもない狂気との対峙を迫られているのよ。」
貴婦人はそう言った。
「私たちに、私たちにできることはありませんか?」
ネクロマンサーが声を震わせて貴婦人に問うた。
「そうね、あなたたちにできることは、マークスを止めることだけ。でも、その力はあまりにも強大だわ。」
3人は言葉を失った。
しばしの沈黙がその場を覆う。
「アッキーナ、あれをもってきて頂戴。」
貴婦人が静かにその静寂を破った。
「かしこまりました、マダム。」
そういって少年アッキーナは奥に姿を消した。
「あなた方は正義をどのように考える?」
貴婦人は難しいことを聞いた。
「正義ってのは、あれだろ。悪を挫いて弱きを助ける。悪辣を退けて、善を敢行するってやつだ!」
ウィザードが自信満々に答えて見せた。
貴婦人は、いつものように一層目元を細めてから、
「若いっていいわね。でも、その純粋さは嫌いじゃないわ。いいでしょう。あなたに力を授けます。呪われたものではなく、本物の力を。ただし、それを決して私欲のために濫用しないとここで約束できるかしら?」
貴婦人は不敵な笑みを浮かべて、そう言った。
みな、突然の申し出に当惑を隠せない。
「正直であることはいいことよ。」
そう言って、貴婦人はポットから自分のカップにお茶をついだ。
その時、店の奥からアッキーナが戻ってきた。その手には、いくつかの美しいティアラが携えられている。
「これがなんだかわかる?」
貴婦人が訊ねる。
「『神秘のティアラ』ですよね?」ネクロマンサーがそう答えた。
「あなた方に、本当に善を探求する意思があるなら…。」
そういって、貴婦人はアッキーナの手からそのうちの一つを手にした。
「でもそれは、『終学:マスター』の位階を得るまでは身に着けてはならないのでは?」
アカデミーの規律についてネクロマンサーが懸念を表明した。貴婦人はその言葉を受けて話始める。
「力の資格って、いったい、なんなのかしらね?」
3人は顔を見合わせた。
「私はね。思うの。それは形式ではないのだと。力を授かる資格とは、それにふさわしい意思を宿した時、そうではないかしら?」
そういうと、その瞳に微笑みをたたえた。
「あなたがたは、この魔法社会のために、というより、あなた方の心にある善のために力を尽くしたいとは思わないかしら?」
突然の問いに狼狽する3人。
「その善っていうのは、こうありたいとか、こうあるべきではないとか、そう思う心のことか?」
ウィザードが問うた。
「そうね、それは近いわね。あなたは『どうあるべき』だと思うの?」
貴婦人はそう訊く。
「あたしは、よくわかんねぇけど、自分が嫌なことを相手にするのはなしだと思うぜ。だれもがそれを守っていれば、きっと苦痛は減るはずだ。」
いいわね。そういって貴婦人が目配せすると、アッキーナはウィザードにティアラを差し出した。
「これをあなたに。」
そういって、うやうやしく手渡す。それは見事な真石ルビーのティアラだった。
「あなたはそれにふさわしいわ。」
貴婦人は一言そう言った。

「あなたたちはどう?正義をどのように考える?」
貴婦人がソーサラーとネクロマンサーに視線を送る。
「正義とは…。」
ソーサラーが口を開いた。
「きっと人それぞれにあるもので、画一的に決まるものではないと、そう思います。でも、きっと、喜びや愛を増し加え、苦痛や悲しみを退けること、それが正義なのだと思います。喜びはひとに活力を与え、生に導きます。その一方で、苦痛は活力を削ぎ、希望を損なうからです。人は、みな生に向かって生きる希望と責務を負っているのだと思うのです。その道筋に連なるものが正義ではないでしょうか?」
貴婦人はその答えに満足したようだった。アッキーナに流し目を送る。それを受けてアッキーナが差し出した。
「これはあなたにふさわしいものです。」
それは、真石エメラルドで彩られた、極上のティアラであった。
「遠慮はいらないわ。それを手に取って身に着けなさいな。」
貴婦人はそう言って促した。

ソーサラーは恐る恐るそれを受け取って、そっと頭上に据えた。彼女の美しい銀髪の上で、それは見事な輝きを放っていた。
「最後はあなたよ?あなたにとって正義とはなに?」
貴婦人はネクロマンサーに優しいまなざしを向けた。
しばしうつむいてから、こぼすように答えた。
「ごめんなさい。正直私にはわかりません。でも、生きること、生き続けることは人間にとって大切なことだと思います。私たちは生まれたその瞬間から死を運命づけられ、いわば有限の時の中である意味では無為な人生を紡ぐことを強いられています。しかし、その歩みは決して無意味なものではなく、喜び、悲しみ、怒り、愛情、そういったかけがえのない感情に彩られています。そのひとつひとつの経験、瞬間が人生の意味を形作るのだと、そしてそれらがその人なりの正しさを紡ぐのだと、私はそう思っています。」
そういう彼女に、貴婦人はあたたかい視線を送った。
「正直なことはよいことです。迷いもまた人生の重要な要素。でも、その中で、あなたは確実に大切なことを掴みつつあるわ。」
そう言って、アッキーナに促した。
「これをどうぞ。」
彼は真石パールに輝くティアラをネクロマンサーの前に差し出した。
「これは、あなたにふさわしい。」
そういって、それを手に取るように促した。
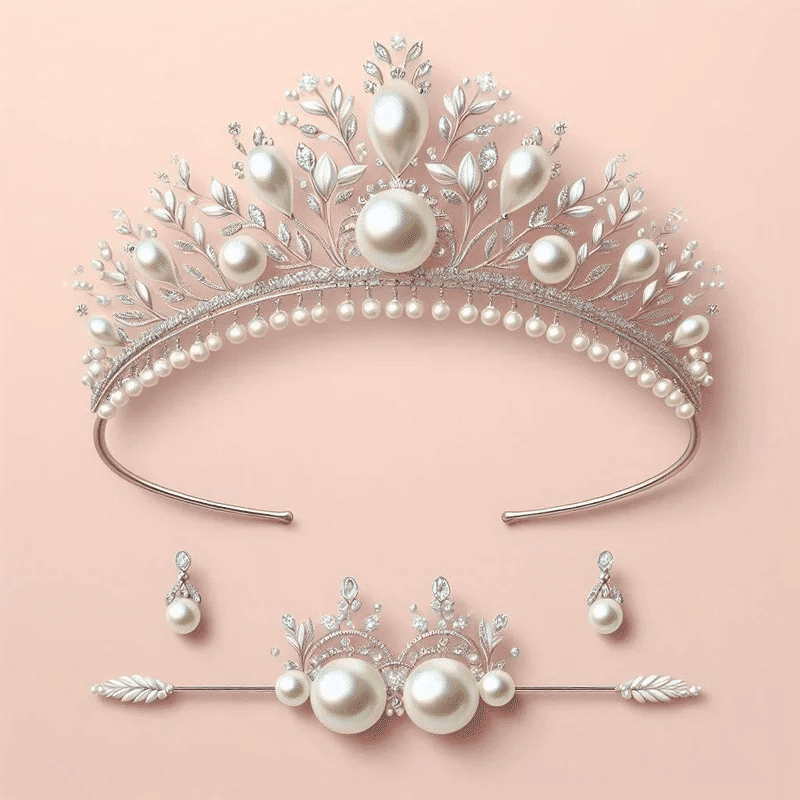
彼女はそれを手に取ると、静かに頭上にいただいた。つややかな黒髪の上に、乳白色のティアラの放つまきとてりが、優雅に鎮座していた。
「少し早いけれど、あなた方の新しい第一歩よ。」
そういって貴婦人は、3人の顔を眺めた。
「このティアラは呪いの品などではなく、本物の『神秘のティアラ』です。あなた方の魔法特性を大きく拡張してくれるでしょう。これからあなた方の前には力の強い巨悪が立ちはだかります。いざという時は、これを身に着けてそれらと対峙しなさい。」
その言葉を聞きながら、3人は、頭上に輝く『神秘のティアラ』を静かになでていた。
『神秘のティアラ』とは、上等位階、すなわち高等部を卒業して『終学:Master』の位階に進んだものだけが身に着けることを許される、いわば修行の修了の証であった。実際は、各々が魔法具店で、めいめいの懐事情にあうティアラを購入するのが魔法社会のならわしであったが、その場合、真石を配したティアラはあまりに高価すぎて、まず手にすることはできなかった。しかし、貴婦人は、3人にその成長の証として、真石をあしらった本物のティアラを用意してくれたのである。これで、下着の着用時間に煩わされることなく、その力を存分に引き出すことができるようになるだろう。
「それは、あなたたちがこれまでに様々な困難を乗り越えて、立派に力を獲得した証です。アカデミーでそれを身に着けるのは、学則上いろいろと問題があるでしょうけれど、必要な時にはそれを頭上にいただいて、信じる道をお進みなさい。」
そう言って、貴婦人は3人に優しい視線を送った。
* * *
「さあさあ、せっかくですから、鏡をごらんなさいな、っと。」
そういって、少年アッキーナが鏡を持ってきた。3人は『神秘のティアラ』を頭上にいただくそれぞれの顔を見て、照れくさそうにしていた。
その時だった。
普段は滅多に訪れる者のないはずのアーカムの入り口を乱暴に打ち破るような轟音が響いた!
「やっと見つけたぞ!」
聞き覚えのある声がする。
「こんなところに隠れていたのか。面倒な暗号を張り巡らしおって。」
その声はマークスのものだった。
3人と、そしてアッキーナ、貴婦人が入り口を見やると、そこに異形の存在を伴ったマークスの姿があった。
彼は、彼女たちを見据えて言った。
「これはこれは。これまで私の崇高なる研究をたびたび邪魔してくれた面々が勢ぞろいではありませんか。好機とは実にこのことですな。」
そう言ってなんとも嫌な笑顔を浮かべた。
「おや、かの失敗作もご同席とは。これはいい!」
それを聞いてアッキーナが渋い顔をした。
「君たちのおかげで、私の研究は思いがけない時間を要したが、しかし同時に君たちが道化を演じてくれたことで、奇しくも完成にこぎつけることができたのだ。その例をたんとさせていただかなければなるまい。どうか心ゆくまで私のこの素晴らしい研究の成果をその身で堪能してくれたまえ!」
そう言うと、彼の背後から甲冑とローブに身を包んだおぞましい存在がゆっくりと姿を現した。

「ある意味、君たちのおかげで完成した究極の P.A.C.:人為の魔法使いだよ。その成果を確かめるための被検体には、君たち以上の存在はないとそう思ってね。ずいぶんかかったがようやくここを突き止めることができた。さあ、歓迎してくれたまえ!」
その究極体なるものがゆっくりと前に歩み出てくる。
3人は、椅子の背に駆けてあったローブをさっと身にまとい、それと正面から対峙した。通り魔は、ここアーカムに至る道筋を夜な夜な探していたのだ。そしてついに、彼はあのコイル巻きの暗号を解読して今ここに立ちはだかっている!マークスとの直接対決時がついに到来した!
両者の間の空気が鋭く張り詰めていく。
第4節『新しい一歩』
魔法使いたちは今、突如轟音とともにあらわれた来訪者と対峙している。その招かれざる客は、異形の存在を伴って『アーカム』の神秘の静寂を脅かしていた。それは、静かに彼女たちの方に歩み寄って来る。その両手には禍々しい魔力がたぎっていた。
刹那、狭い店内を稲妻が幾重にもほとばしる。

両脇にうずたかく積み上げられた魔法具が音を立てて崩れ、あたり一面に埃が巻き上がる。
「相変わらず、問答無用だな!」
ウィザードが相手を見やった。
「マダム、急いで表へ。」
アッキーナは貴婦人を安全な場所へ連れて行こうとしている。
「待ってちょうだい。」
そう言って貴婦人は詠唱を始めた。
『小さな神の名を持つ者よ。我が呼び声に応えよ。果敢なるものに助けと恵みを与えん。憐憫をたれよ!祝福:Blessing!』
貴婦人が全く聞いたことのない術式を詠唱すると、3人の足元に、白く輝く魔法陣が展開し、彼女たちを暖かい魔法光で包んだ。その身体に力があふれてくる。
「ここはお任せします。」
そういって、アッキーナが奥に押し込むようにして貴婦人を連れていった。目の前の異形の存在はただならぬ殺気を漂わせている。
またしても、その両の手に魔力がみなぎった。
「くるわよ!」
ソーサラーの声に呼応するように、ウィザードが『光の盾:Light Shield』の障壁を展開した。
異形の手から再び稲妻がほとばしり、その障壁を脅かしていく。閃光と雷を受けてそれはびりびりと震えるが、どうにかその衝撃の全てを受け止めることができた。
「今度はこっちの番よ!」
そういうと、ソーサラーは『氷刃の豪雨:Squall of Ice-Swoards』の術式を繰り出した。『神秘のティアラ』によって引き出されるその効果はこれまでとは比較にならないもので、ひとつひとつの氷刃の鋭さが増しているのみならず、その降り注ぐ密度にもまた一層の磨きがかかっていた。

狭い室内で轟音を立てながら、数多の氷刃が異形めがけてうなる。マークスは、その背後に身を隠していた。氷刃は異形が身に着けているローブや魔法具を激しく切り裂いていく。それは怯んで体勢を崩した。
これまでに組してきた P.A.C. よりはいくぶんかなめらかな動きで、姿勢を立て直しながら、今度は火球を放ってきた。3人は前後左右にさっと身をかわしてそれをよけるが、火球は容赦なくアーカムの店内を破壊していった。カウンターは砕け散り、薬瓶の陳列棚が倒れて、ガラスがあたりに飛散する。
「ちきしょう、いいようにやりやがる!」
ウィザードはそう言って詠唱を始めた。
『火と光を司るものよ。水と氷を司るものとともになして、わが手に力を授けん。火と光に球体を成さしめて我が敵を撃ち落とさん!砲弾火球:Flaming Cannon Balls!』
放たれた複数の火球が、異形めがけて飛んでいった。それは身を守るような姿勢をとりながらも、ひるむことなく、それらを受け止める。どうやら、マークスを守ることを最優先に行動しているようだ。火球を受けたところは赤く熱され、火がくすぶっている。こちらの繰り出す魔法が効いていることは間違いなかった。
『慈悲深き加護者よ。我が祈りに応えよ。その英知と力をその庇護者に授けん。我が頭上に冥府の門を開き、暗黒の魂を現世に誘わん。開門せよ!暗黒召喚:Summon Drakness!』

間髪入れずに、ネクロマンサーが力の強い死霊を複数召喚し、相手にけしかけた。異形が行使する対霊術式にそのいくつかは飲まれるが、残りは振り死霊の群れを振りほどこうとするその身体にとりついた。恐ろしい叫び声とともに、異形のローブは引き裂かれ、甲冑は噛み砕かれる。しかし、それでもなお、それは術式を繰り出してきた。『衝撃波:Shock Wave』の術式を正面から受けたウィザードは、思い切り後方に吹き飛ばされ、カウンター奥のドアを破って、その奥に倒れこむ。その身体にはあちこちに血がにじんでいた。異形は左右に揺れるようにしながらなお迫ってくる。
「強い!しかし!」
『閃光と雷を司りし者よ。我に力を!厚い雲を幾重にも積み上げよ。そこから光と稲妻を放ち我が敵を蹴散らさん。招雷:Lightning Volts!』
詠唱とともにソーサラーが雷撃を放つ。それは『転移:Magic Transport』を小刻みに使用して巧みにその閃光と稲妻をかわすが、それでも、幾筋かの雷が確実にその呪われた身体を捉えた。
大木が裂けるような音がして、甲冑と装具が砕け散り、傷口が閃光と火花を発した。しかし、その動きが止まる気配はない。居住まいをただすと今度は、ソーサラーに向けて、『竜巻:Tornado』の術式を繰り出した。防御行動こそ間に合ったものの、その空気の圧力を受けて彼女の小さな体は、書棚に強く叩きつけられた。全身に痛みが走り、その場にうずくまった、口元が血で濡れる。
異形はその身体にまとわりつく死霊を力任せにねじ伏せ、なおもゆっくりと迫ってきた。身に着けた装具はすでにずたずたで、破れて避けたローブの裾を引きずるその姿は文字通り生ける屍であった。しかし、なおもそのまま雷撃を繰り出す。不意を突かれたネクロマンサーは壊れたカウンターの裏に放り込まれて痛みに悶えた。
「冗談抜きで、強えなこいつ!なら、これでどうだ!とっておきだぜっ!」
『火と光を司る者よ。我が手に炎の波をなせ。我が敵を薙ぎ払い、燃えつくさん。殲滅!炎の潮流:Flaming Stream!』
ウィザードは火と光の高等術式を繰り出した。その両手から猛烈な業火の潮流が流れ出て、異形の身体を包み込んでいく。それに合わせるようにしてソーサラーが術式を重ねた。
『空気と圧力を司る者よ。圧縮と暴発によって我が敵を爆ぜよ。貫通衝撃:Strike Impact!』
大きな衝撃音とともに異形の身体を持ち上げた。それは勢いよく宙を舞って、石造りの壁に強烈にたたきつけられた!金属の砕ける音がして、甲冑がはげ落ちていく。
その場にうずくまって、ようやく動きを止めた。
「やった!」
そう思った瞬間だった。内側から殻を破るようなめきめきという異音とともに、これまで以上におぞましいものが、その砕かれ破られた甲冑とローブを脱ぎ捨てるようにしてその姿を現した。

「ははは。見たかね!これが完成した P.A.C. の力だよ。君たちがこれまで味わったのは恐怖のほんの入り口に過ぎない。メインディッシュはここからだ!」
こそこそと身を隠しながらマークスが高笑いしている。
「しょうがねぇ!本当のとっておきだ!」
そういうとウィザードは懐から炎の呪印が刻まれた短刀を取り出した。

「こいつで引き出される術式は一味違うぜ!」
そう言って詠唱を始めた。
『火と光を司る者よ。法具を介してその加護を請わん。業火を火球となして立ちはだかる者を粉砕せん!貫け!殲滅光弾:Strike Nova!』
赤というよりは紫色に光り輝いて周囲に稲妻をまとう高エネルギーの光弾が目にもとまらぬ速さで、そのおぞましい存在に向かって繰り出された。

ドンという爆発音とともに、その右腕をもぎ取る。それは後ろ手に大きくのけぞり、バランスを崩しながら、それでもよろよろと姿勢を戻した。その刹那、残った左手から閃光がほとばしる。3人は宙に持ち上げられ、壁や天井に激しく身体を打ち付けられた。ネクロマンサーは肩で大きく息をしている。ソーサラーも限界に近いようだ。
片腕がもがれたことで身体の均衡を大きく崩し、不自然極まる運動を繰り返しながら、その存在はなおも迫ってくる。
ネクロマンサーは死力を尽くして再度霊体を召喚し、その足元を狙って繰り出した。強力な霊体は異形の脚を噛み砕き、切り裂き、その場に組み伏せた。それは片膝をつきながらも上体を大きくそらしておぞましい咆哮を上げる。その声は心の奥底を凍り付かせるような恐怖の音を奏でていた。
異形が残った左腕でなお術式を繰り出そうとしたその時だった。
『水と氷を司る者よ。法具を介してその加護を請わん。清流を刃となし、高圧で切り裂け!噴出水剣:Water Jet Blade!』

詠唱とともにソーサラーの手から一陣の水流が刀の太刀筋のように弧を描き、残る左腕を切り飛ばした。彼女の手には一振りの美しい法具が握られている。

両腕を失い、片足をもがれて、それはその場で、大きなうめき声をあげた。しかしなおもその戦意は失われていない。
「これで終わりだ!」
そう言うと、ウィザードは、口元からエネルギー弾を放出しようとするその異形に向かって、再度『殲滅光弾:Strike Nova』の術式を繰り出した。光弾はそのおぞましい頭部に着弾するや激しい爆発を起こして、それを四散させた。両腕と頭部を失ったそれは、静かにその場に倒れこみ、それきり動かなくなった。あたりにはどす黒い血液のようなものがあふれ出ている。
ウィザードの身体から残留魔力が放出される。彼女はすべての魔力を使い切ったようだ。その身体を背後からソーサラーが支えた。
3人は、ようようにして、おそるべき相手を撃退した。咄嗟にマークスを追おうとするが、その姿は既にそこから失われていた。どうやら、『転移:Magic Transport』の術式でそそくさと逃げ出したようである。破壊の限りが尽くされたアーカムの店内に、ようやく静けさが戻ってきた。異形の身体に埋め込まれた様々の法石は、それが倒れてからしばらくの間は光を放っていたが、それは次第に弱々しくなり、やがて暗く沈黙した。
「よくもまぁ、しかしこんなものを作ったものだぜ。」
ネクロマンサーから魔力回復薬を受け取って力を取り戻したウィザードが言う。
「でも、この体の持ち主にもかつては人生があったのよね。」
ソーサラーが物憂げに言った。
「このような生命への冒涜を絶対に許すことはできません。」
打倒マークスの決意を新たにするネクロマンサーがそこにいた。
「それにしてもあなた、すごいじゃない!それ見せてよ。」
ソーサラーが言うと、ウィザードは照れくさそうに手にした短刀を彼女に見せた。
「これ、どうしたのよ?」
「へへ、このあいだ錬金したのさ。すげぇだろ。火と光の術式から力を引き出すための法具だぜ。」
「ふーん。実は私も作ったのよ。」
「ああ、さっき見たぜ。それ、まるで氷刃だよな?」
「そうね、氷刃を模して錬金した氷の剣よ。水と氷の術式を力を引き出す法具ね。」
「おふたりともすごいのですね。いつの間にそんな高度な錬金術を。」
ネクロマンサーが感心している。
「まぁな、いつか必要になる時がくると思ったんだよ。いつまでもアーカムを頼ってばかりってわけにもいかないしな。」
「ご同様。」
そういって3人は身体の痛みをこらえながら、それでも笑顔を交わした。
* * *
平穏を取り戻したアーカムに貴婦人とアッキーナが戻ってきた。
「大丈夫ですか?」
「ええ、なんとかね。」
「めちゃくちゃ強い相手だったぜ。」
「正直勝てる気がしませんでした。」
そう言ってめいめい言葉を交わす。
アッキーナは店内を見回している。
「これは、しばらく休店ですね。」
「それも悪くないわ。時にはあなたにもお休みが必要よ。」
そう言って、貴婦人はアッキーナの頭に手を置いた。
そういえば、マークスがアッキーナに向かって「失敗作」と言っていた。何のことだろう?訊ねるべきかどうか思い定まらなかった3人は、その問いを飲み込んだ。
「お茶にしたいところだけれど、これでは難しいかしら?」
貴婦人が冗談ぽくいう。
「床に座ってなら、なんとかなりますよ。」
そういって、アッキーナは壊れた台所へと向かっていった。
「ポットは無事、カップは何とか人数分ありそうですよ、っと。」
そんな声が聞こえた。
しばらくして奥からアッキーナが姿を現した。
「棚が壊れてしまって、お茶は大散乱。唯一『九頭竜茶』の葉っぱだけがなんとかとりあえず残ってました。」

そういって、いつものようにお茶をふるまってくれた。カウンターはすでにばらばらになってしまっているので、みんなで床に座った。
「あと、これもありました。一緒に食べましょう。『龍頭のお餅』です。」

「まあ、いいわね。いただきましょう。」
貴婦人のその声に合わせて、みなお茶を楽しみ始めた。
「でもよぅ、これからどうするよ。ここもこんなんなっちまったし。」
ウィザードがお菓子をほおばりながら心配そうに言う。
「そうね、再建までにはしばらく時間がかかるわね。」
貴婦人はアーカムの店内を眺めまわした。
「まぁ、なるようになりますよ。」
少年アッキーナは楽観的だ。
「それにしても、どうしてマークスの悪事は今日まで明るみに出ずに、ここまで進展することができたのでしょうか?」
ネクロマンサーが疑問を呈した。
「ひとつには、トワイライト卿の協力があったことが大きいですね。」
アッキーナが言う。
「彼は、厚生労働省の次席事務次官で、『アカデミーによる葬送』と『アカデミー特務班』を総括する立場にありました。ですから、彼の采配で情報を巧みに隠蔽することができていたんでしょうね。あなた方がシモネン氏から聴取したとおりですよ。権力というのは時に複雑なものです。」
「でも、アカデミーの目も節穴ではないでしょ?ご遺体の横流しなんて、すぐに露見してもよさそうなものだわ。」
ソーサラーがもっともな指摘をする。
「それについては…。」
貴婦人が口を開いた。
「アカデミーの内部、特に最高評議会に近いところにマークスの協力者、あるいはその行状を知っていて敢えて黙認する勢力がいたと考えて間違いないでしょうね。」
そう言って、茶碗を傾けた。
「アカデミーも無条件には信用できねぇってわけだな。」
「そうね。これからは何が正しくて、何が間違っているのか、自分の目と心で判断しなければいけない、そういうことになりそうね。」
ウィザードの言を受けて、ソーサラーが言う。
「でも、なんにしても、ひとまずマークスの野望を退けることができました。今後は彼も好き勝手はできないと思います。」
ネクロマンサーはそう見通しを語った。
2月を前にして、雪と寒さに閉ざされた冬の気配にごくわずか、春の到来が感じられるようになってきた。厳しい寒さは今後もなお続くだろうが、しかし、季節は雪解けへと静かに進んでいる。逃走を図ったマークスの去就、姿を消したあと処刑されたことにされたウォーロックのこと、そして、3人に迫る上等位階への進級試験、ひとつの決着を迎えながらも、新しい歯車は音を立てて時を刻み続けていた。
この後、彼女たちをどのような運命が待ち受けているのか、あるいは所与の宿命の頸木を超えて、彼女たちが自らどのような人生を紡いでいくのか、透き通る美しい水色の瞳で、貴婦人がその行く末を見つめていた。
その翌日から、なぜか突然に『キュリオス骨董堂』が改修による休店となった。それは何とも奇妙な不思議な一致であった。
― 後編に続く ―
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
