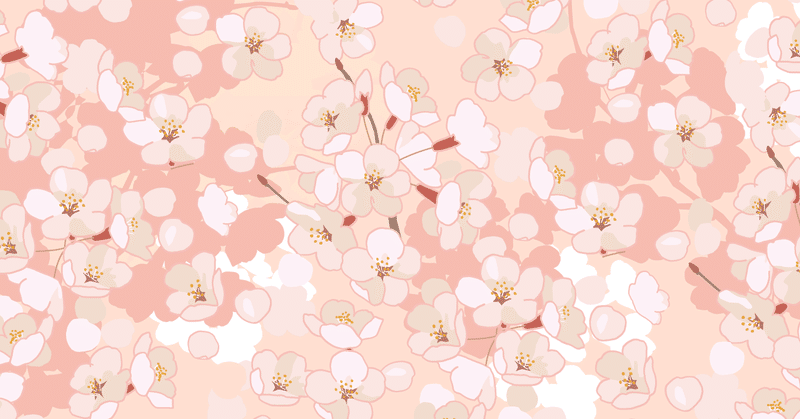
花と新風
京都鴨川の桜は散りぎわだった。
「はー、桜ももう終わりやんなあ」
川面に重なる白い花びらを見渡して、硝子は大きく伸びをする。若草が萌える河原には、青いビニールシートがあちらこちらに敷かれ、子どもから大人まで花見を楽しんでいる。鴨川の両岸には桜が植わっており、上流に向かってうすべにの花霞が続いていた。
「ええ時期に来れたなあ。はい、硝子ちゃん」
水筒からお茶を注いでいた春が、紙コップを硝子に渡してくれる。受け取ったコップからは、紅茶のよい香りがした。「おおきに、春さん」と微笑み、硝子はコップに口をつける。アールグレイだろうか、柑橘系の爽やかな香気がたちのぼった。
「おいしい。あっ、これ、ほどいてしまっていいですか?」
コップを一度ビニールシートのうえに置いて、重ねられた包みをほどく。
風呂敷の中から、パックに入った厚焼き玉子のサンドイッチが現れた。それと別のパックには、菜の花とベーコン、たまねぎをはさんだもの。おやつ代わりなのか、林檎のコンポートをはさんだものまで。「おお……」と風呂敷を畳む手を止め、思わず感動のため息を漏らす。
「めちゃめちゃおいしそう。さすが愛妻とみまごう弁当をつくる男」
「えぇ……? なんやて、愛妻?」
「そない勘違いされてはるらしいですよ、あのひと。職場で」
お手拭きを春に渡して、硝子は河原の斜面をくだってきた男に気付くと、手を振った。
「あき。こっち!」
声に気付いた男が、端末をチノパンのポケットに入れてこちらに向かってくる。ブルーシートを出したところで、職場からかかってきた電話がやっと片付いたらしい。
「あんた遅いから、サンドイッチ先に食べてしまうとこやったで」
「あー、べつに待ってへんでよかったんやけど。あ、ふたばの豆餅がある」
硝子が持参したパックには、ふくふくの豆大福が六つ詰められていた。
さすがに昼ごはんをすべて用意してもらうのは気が引けたので、行きがけに買ってきたものだ。しっとりしたあんこが詰まった豆大福は、あきや春の好物でもある。
「サンドイッチと紅茶にはあわへんかったかなあ」
「ええやん、和洋折衷で。ほな、いただきます」
ブルーシートにあぐらをかいたあきが手を合わせる。
三月最後の週にあたる日曜日。硝子はあきと春と前から約束していた花見に来ていた。
――ふたりで会う代わりに、春もまじえてごはんを食べよう。
もともとは硝子と彼氏の関係を慮ってされた提案であったので、フリーに戻った今はそうする必要がなくなってしまったのだが、意外にもあきは約束を守った。硝子に会いたいと春が言っていたというのは、もしかしたら嘘ではなかったのかもしれない。ちょうど鴨川の桜が満開だからと、近くの河原で花見をすることになった。
「そやけど、残念やねえ。しょこちゃん、四月から東京なんやて?」
あきから話を聞いていたらしい春が息をつく。
そうなんです、と硝子は苦笑した。
――東京にある警察庁の夢視捜査推進室。
それが四月からの硝子の職場となる。
通常、警察官は各都道府県単位で採用されるが、硝子は夢視捜査の専門職として警察庁の試験に合格して捜査官になった。この場合、勤務地は全国が対象となるから、転勤は十分ありうる。はじめの職場がそれまでの在所に近い京都だったのは運がよかっただけで、数年経てばどこかに異動することもあるかな、とは思っていたけれど、まさか二年で、しかも本庁勤務とは。
「本庁て、つまり栄転てことなん?」
尋ねた春に、「どうなんかなあ」と硝子は紅茶をのみつつ首を傾げた。
「単に捜査官が足りてへんって話なんかな、と思います。去年から新規採用再開しましたけど、まだ動ける捜査官は十人ちょっとしかいーひんし」
内示後に名簿を確認すると、推進室にはすでに「人」タイプの夢視者がいた。捜査室付けではないが、警察庁には「物」タイプの夢視者も二名勤めている。ここに硝子も加えて、四名の夢視者が首都に集まることになった。来年には、首都で四年に一度の国際大会がひらかれる。そのための治安維持を目的に、首都に人材を多く集めているという噂を聞くことがあったが、推進室の本格稼働も今の時流にのってのことなのだろうか。
「でも、しょこちゃんひとりで東京行くわけやろ。親御さんは心配せぇへんの?」
「ええと、うちは親元離れて久しいのであまり……。友だちかて、忙しくてひと月にいっぺん会えればええほうですし、そない変わらへんかなって」
春の口ぶりで、どうやらあきは硝子の出自をほとんど春に話していないらしいことに気付く。とすると、あきを刺した鳥彦が硝子の養父であることも知らないということになる。研究所や過去の硝子とあきの関係についてもたぶん。そもそも、春があきの過去についてどれくらい正確に把握しているのか、部外者の硝子にははかりかねた。
(十六歳の、素性もなんもわからへん男の子を育てるって、結構すごいことやと思うけど)
なんとなくあきのほうに目を向ける。
硝子と春がしゃべっているあいだ、あきは横から口を挟んだりせず、そば近くまで垂れた桜の花を眺めている。あきは今日はたいしてしゃべらない。春の陽気か、すこしぼんやりしているのかな、とも思う。でも、もともとそういう男なのかもしれない。これまではふたりでいることが多かったから、必然ふたりでしゃべっていたけれど、そういえば、あきは大勢が集まるとだいたい輪の外で静かにしている。そういう子どもだった気がする。
「ほいなら、しょこちゃん。あきをもらってやってよ」
春があきの腕を引っ張って、いきなりとんでもないことを言い出すので、硝子は瞬きをした。向かいであきが噎せている。
「何ゆうとんねん、かあさん」
うろんげな顔をしたあきに、「そやかて、あんたもう三十三になるのにふらふらしよって」と春が嘆息する。
「わたしが持ってきたお見合い、ひとつも実らへんし。しょこちゃん、うちの子ほんまモテへんの。昔はときどき、ごくまれに、なんやおった気ぃするけど、三月と続かん。そない逃げたくなるほど性格がわるいんかねえ。どう思う?」
「性格はまぁ……」
わるいような。
わるくもないような。
「なんやねんその間」
「さておいて、顔はわりといいと思いますよ」
「顔て」
いちおう褒めたのに、あきは微妙そうな表情をして視線をよそに逃がした。この話題を早く変えたいという空気がありありとたちのぼっている。でも普段のあきなら、さっと話を変えてしまうだろうに、春の会話は邪魔できないらしい。あきが完全に下手にまわってしまう人間はそう多くないので、春さんすごい、と硝子はあらためて思う。
それにしても、ときどき、ごくまれになんやおったひとたちって、具体的にいつといつ、何人だったんだろう。モテへん言ってたくせに、ごくまれにはいたのか。彼女いない歴イコール年齢じゃなかったのか。だまし討ちにあった気がして、胸のあたりがちくちくしてくる。
面倒になって、硝子は息をついた。
「やさしくて、あったかいひとだと思いますよ」
でも、つめたくて、無責任なときもある。
あきのことが硝子にはわからないし、このひとのこと今もまだずるずる好きなんだろうなって思いつつ、まちがったことをしているような気がいつもしている。どこが好きなのかもよくわからない。ときどき的確にやさしいことを言うから、よろめているだけかもしれない。結局顔が好きなだけかも。それくらい、あやふやだ。
「お見合いぎょーさん持ってきてあげたらええと思います」
春に向けてにっこり笑いかけると、あきが辟易とした顔で嘆息する姿が見えた。
「無責任にうちのおかあさん焚き付けんといてや」
帰り道、あきは不機嫌そうだった。
春は趣味の大正琴の教室があるとかで、途中で別れてしまった。しかたなく小春日和の鴨川の遊歩道を、紙袋をさげた男と並んで歩いている。花筏の川を子連れのカルガモが泳いでいく。泳ぎが下手な子ガモが少し遅れて必死に兄弟についていっている。
「息子の将来を心配してはる、ええおかあさんやん」
「硝子があないなこと言うから、数か月はお見合い地獄や。断る身にもなってみぃよ」
モテないくせに最初から自分が断る前提らしい。
嫌味な男やな、とつぶやきかけて、思い直した。
「あきは結婚せぇへんの?」
「しない」
きっぱりした返事だった。
そう言うてるのに聞いてくれへん、とここにはいない春に向けて嘆息する。
ふうん、とあいまいにうなずくことしか硝子にはできない。
でも少なくとも、ときどき、ごくまれになんやおったひとたちとは、付き合っていたわけだ。いくつのときだろう、と硝子はなんとなく考えた。短大生になって定食やまだで再会したとき、あきはなんというか、もう今のあきだった。
「なに」
黙ってしまった硝子に、あきは横目をやった。
「あんたが女の子とお付き合いする姿を想像して、想像力の限界を迎えてた」
「そないアクロバティックなお付き合いはせぇへんで。ふつうです、ふつう」
「ふつうに手ぇつないだり?」
「そやな」
「ふつうにキスをする」
「そうです」
話を打ち切りたそうな顔をして、あきは数歩前を歩き出した。
川のほうに伸びた枝の花影がその背に落ちている。ふうん、とつぶやいて、硝子は自分が知らない時間に想いを馳せる。まあ、三十三ならそういうこともあるのかもしれない。誰かを好きになったり、つきあってみたり、それでうまくいかなかったり。硝子だって、ほんの少しまえまで、似たようなことをしていた。
「どういうときに、付き合いたいっておもうの?」
そろそろ、本当に話を打ち切られそうな気がした。
こたえるのが面倒になると、あきは適当に話を流す。あきに言うことを聞かせる春さんはここにはいない。だから、答えがかえってきたのは少し意外だった。
「さみしいとき」
瞬きをした硝子を振り返り、あきは口の端を上げた。
「ふつうやろ」
「ぜったい嘘」
思わず硝子は言い切った。
「あんたがさみしいとかありえへんもん。地球上でひとりになっても、鼻歌うたって生きてそう」
「なんやねんそれ。ほいで、しょこちゃんは? 向こうの家は決まったん?」
緩やかにあきは話の矛先を変えた。
「うん。勤務地が霞が関やねん、荻窪にした」
やっと追いついた男の隣を歩く。春色の淡いピンクベージュのロングスカートがバレエシューズのまるい爪先で揺れている。あきのほうは無地のニットにモカブラウンのチノパンを合わせていた。革の腕時計をした手首がニットの袖からのぞいている。シンプルな装いのなかで唯一、年季の入ったごつい腕時計がいいなあ、と思う。
「荻窪?」とあきが尋ねた。
「丸の内線一本でいけるんよ。そこの1Kのマンション。家賃がめっちゃ高くてびびった」
「へえ。荷物はもう送ったんか」
「家具とか家電とか、おっきい荷物はな。わたしは手荷物もって新幹線で行く」
「いつ?」
「あさって。京都駅から朝ののぞみで――あぁ、見送りはおかまいなく」
冗談めかして言うと、「それは残念」と嘘か本当かわからない言葉が返ってきた。
あきの肩越しにひかりが波打つ水面が見える。花びらが敷き詰められたうすべにの川をあきはポケットに軽く手を入れて眺めている。
ふいに、やっぱり今日はのあきはあんまりしゃべらないな、と思った。あとやっぱりぼんやりしている。いつもより油断していて、いつもなら聞かない言葉がぽろっと返ってきたりする。それはとてもささいな、ほかのひとなら違いがわからなそうな、ささいな変化だったけれど。
さみしい、と言ったあきの言葉を思い出す。
まさかな、とすぐに思い直す。
「東京ってふつう何年くらい行くもんなん?」
「どうやろ。二年か……三年? けどわたし、もともと警察庁採用やねん、その次の勤務地が京都とはかぎらへんし。まあ春さんやないけど、同居の家族はおらんから身軽」
「そか」
目を伏せて、ふふっとあきは小さくわらった。
何故かやさしいわらい方だった。
「そういえば俺、今日しょこちゃんと東京のぺっかぺかのカフェでなんやどでかいパフェ食ってる夢みた」
「パフェ? ちゅうか、あんたの夢って洒落にならん……」
近い将来起こることを予知するのが夢視者としてのこの男の能力でもある。
頬を引きつらせた硝子に、「おいしそうな未来でええやん」とあきは適当なことを言った。ちょうど鴨川に架かる大橋のまえに行きつく。あきの実家と硝子の在所は、この橋で左右に分かれる。なんとはなしに足を止めた硝子に、「ほな」とあきは声をかけた。
「豆餅おおきに。余ったの、あとでおかあさんと食べるわ」
「うん。春さんにもよろしく」
「元気で、硝子。風邪ひかんようにな」
大きな手のひらが軽く硝子の頭を撫ぜた。
指先がこめかみのあたりの髪をいらう。ふつうのひとより低温で、きれいな指先が硝子はすきだ。本当は顔よりも。だけど、この手が穏やかな親愛以上の情動をのせて硝子に触れたことは一度だってなかったし、いくつになってもあきにとって硝子はこわい夢を見たって泣いていた七つの子どものままなのかな、とも思う。なんだかかなしい。でもそれと隣り合わせの、子どもの頃のままのすきだなあという親愛の情も硝子には確かに根を張っていて、いかんともしがたい。この男との関係はいかんともしがたい。昔も、今も、きっとこの先もだ。
「あんたも。元気でね」
大きく息をついてから笑い返すと、「はい」とあきはかしこまった返事をして髪をいらう手を離した。あとはもう言うことがなくなってしまう。お互いもう一度目を合わせ、「元気でね」「はいはい」と言い合った。くどい。もう一度目が合いそうになったが、お互いくどい……と思ったらしく、そこできびすを返した。こういうタイミングだけ妙に合う。
「あき、風邪ひかんといてな」
「はいはい。はい」
適当そうな返事を背で聞きつつ顔を上げると、晴れた春空が視界いっぱいにひろがっていた。遠ざかる足音がする。あぁ振り返りたいな、と思ったけれど、やめた。硝子は素直じゃない。でも、あきだってたぶん素直じゃない。お互いさまで、こういうところは似たもの同士だ。
そしてまたいつ会うかの約束もしないまま、橋の左と右に分かれた。
花と新風/了
++
この物語は、「ナイトメアはもう見ない」をもとにした短編になります。水守糸子個人の創作物になりますので、出版社へのお問い合わせはお控えください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
