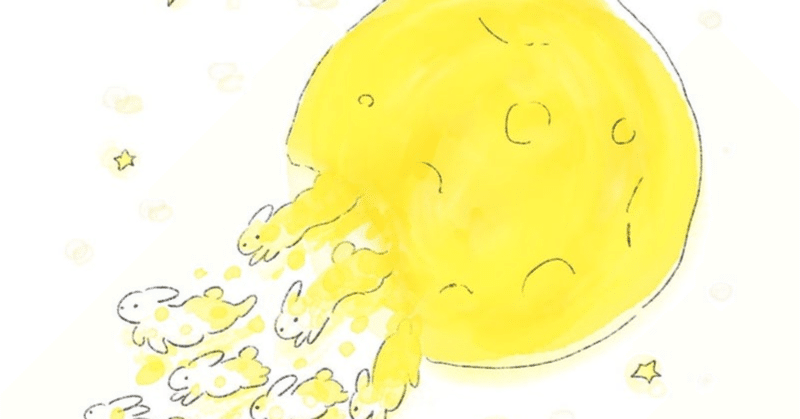
満ちる
トタンに蔦が絡んでいる。元は白色だったのだろうその壁は、古い釘から赤茶の錆が流れ出し、遠目にはベージュに見える。通勤時、目もくれず通り過ぎていた古い二階建て。
土曜日に休日出勤を終えた私は、真っ直ぐにその建物を目指した。
車を置く。少し歩く。遂に目的地に立つと私は見上げた。その全貌に、急な不安を覚える。いそいそとスマホを取り出した。先週から幾度と開いたページと、目の前の建物を交互に見た。ここで間違いないだろうか。怯んでドアを開けられそうにない私は、ほんの少しだけ、間違いを期待した。しかし、やはり確かに同一の建物のようだった。
一階は作業場のような造りになっている。木工製作所だろうか。ちらと見やってすぐに目を逸らした。無骨な職人と目が合いでもしたら気まずい。それか口の悪い職人。何見てんだお前、などと始まったら恐ろしい。
私は一瞬父を思い出した。頑固な大工の棟梁だって通りすがりの人に怒鳴ったりはしない。大丈夫、大丈夫、と自分に言い聞かせ、そそくさと建物の脇へ移動する。
そこには、人ひとり入れるくらいの小さな窪みがあった。私は洞窟の中に潜り込むかのように、恐る恐る足を踏み入れる。壁にはメニューや店内写真などがピンで止められていた。ほっと安堵する。やはり、この二階はカフェになっているのだ。
毎日通り過ぎてもうどれくらいになるだろう。この老いた建物が理想のカフェだと知ったのはついこの間だ。
私は心を落ち着けて、ドアの丸い取手を引いた。蝶番がキィ…と小さく鳴く。目の前に伸びる木の階段を見上げた。白い壁に掛かった絵、淡い色合いのステンドグラス。木目をコーティングする柔らかな陽の光。
思わずスマホを掲げて写真を撮ろうとして止めた。特に強い感情が湧いた訳でもなかったが止めた。もしかしたら、この空間、この瞬間に湧き上がった感情を大切にしたかったのかもしれない。切り取ることで薄れる気がしたからかもしれない。
昔読んだ本に載っていた言葉。バックパッカーの日本人男性は、旅先で出会った外国人女性からこんな言葉をもらったという。彼は素晴らしい景色に感動してシャッターを切り続けていた。彼だけでなく、周りの観光客も皆写真を撮っていた。彼女だけがカメラを持たず、景色を眺めていた。彼女は彼のほうを向くと、
「写真はココで撮るのよ」
と笑いながら自分の胸を指差した。
階段を一口一口味わうように登った。登り切って立ち止まる。ステンドグラスのドアを開けた。
木の温もりが出迎える。客は私一人だった。こんな贅沢あるだろうか。ぽっかりと開いた窓を見た。窓辺に四人がけのテーブルがあった。そちらへ向かおうとした爪先が迷い、やっぱりこっちでいいか、と諦めるように手前のテーブルに向いた。
「どうぞ。窓際へ」
爪先の微かな揺れを見ていたのだろうか、オーナーらしき男性が声をかけてくれた。私は振り返り会釈した。その声に背中を押されるように窓際の席へ向かった。
昼休憩を午後一時に取った私の腹は午後四時でもまだ満たされていたので、カフェオレだけを頼んだ。
カチャリ、と音がした。辺りを見回すと、その音はカーテンから聴こえてきていた。窓に掛かった薄いカーテンの先にはビーズが縫い合わされていて、吹き込む風に揺れていた。そして時たま窓の木枠をビーズが触れる。
ピアノのメロディと、春の風と、奔放なビーズ。揺れる観葉植物の緑色と、柔らかに佇む木目。夜は月光に濡れるのだろうか、窓際に置かれた青と紫のガラス瓶。
「はい、どうぞ。ごゆっくり」
アンティーク調のカップとソーサーが静かに置かれる。熱いコーヒーに冷たいクリームが乗っていた。一口含むと心臓がゆっくりと波打った。呼吸が深くなっていく。カップを置いて外を眺める。ペンダントライトの下で佇むと、このまま柔い光に溶けていけそうだった。
ピアノの旋律。マイナーコードが胸の奥を突いてくる。途端に映画『マディソン郡の橋』が浮かんだ。たった4日間過ごした人との永遠の恋。メリル・ストリープ。あの映画を観たのは大学生のときだったか。今の私はどんな風に観るのだろうか。マイナーコードが突いてくる。私は堪らずカフェオレをもう一口飲んだ。
カフェで小説を書きたいと思っていた。けれどこの空間では気が引けた。没頭してキーボードを叩く気になれなかった。
次は本を持って来ようと思った。カーテンや葉が揺れるこの空気の一部となってただ佇みたい。風が吹いて私の毛先が揺れている。深く深く呼吸する。
満ちて来ている。睫毛の先まで満ちて来ている。香りと音と光と風が充満している。爪の先まで。
自分自身を見つめた。思春期の頃思い描いた37歳にはなれていない。寧ろかけ離れている。欲しかった未来の何パーセントも手にしていない。見た目も中身も夢も現実も。足りない私のまま、足りない日々を生きている。 けれど今、この空間で確かに私は満ちていた。それは確かだった。足りないままの、未熟なままの、欠けているままの私。ただの私が確かに、満月のように満ちていた。
「ありがとうございました」と伝えたら、「また」と無口なオーナーは言った。
ステンドグラスのドアを開けると、一口一口味わうように階段を降りた。


と、つい話しかけてしまった花
グロリオサ
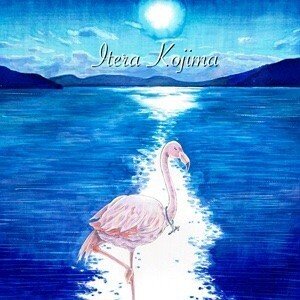
湖嶋家に届くサブスクの花束を眺めながら、
取り留めようもない独り言を垂れ流すだけの
エッセイです〜
ぇえ…! 最後まで読んでくれたんですか! あれまぁ! ありがとうございます!
