
娘を手放した日
「子供がほしい」
「何人ほしい」
「男の子がいい」
「女の子がいい」
昔からどれにも頷くことがなかった。
子供をもつということに対して、私には一切の願望も欲求も無かった。想像の中で私は独身だったし、既婚だったし、夫婦二人だったし、子持ちだった。どんな自分にもなれたし、どの自分でも良かった。一つのカタチに願望が強く傾くことが無かった。それが自然だったし心地よかった。
―――
旅先のインドネシアで現在の夫に出会い、4日で結婚を決めた。事故に巻き込まれるように唐突な出会いだった。有無を言わせぬ程に急激な渦に巻かれ、吸い込まれていくようだった。息を継ぐのに必死で、憧れを描いている暇などなかった。
結婚後、日本で暮らし始めた。夫の故郷では、私達の赤ちゃんが待ち望まれていた。結婚数ヶ月の私達に国際電話が「赤ちゃんは、赤ちゃんは」と繰り返す。重しが上に乗っかってなかなか水面まで浮き上がれずにいた。息継ぎが出来ない。そんな日々だった。
夫は、結婚前から女の子を欲しがっていた。
名前も考えていた。候補がいくつかあった。男の子の話は一切出なかったが、別にそれでよかった。私には特別願望が無いのだし、彼がそういうならそれがいい。私の脳がつぶやく。
「女の子がいい。女の子を産む」
私は妊娠した。
まだ胎動も感じられない妊娠五ヶ月。夫が、額に入った結婚写真を眺めて言った。
「この君を見て、俺の母さん泣いたんだよ。まるであの聖者の妻みたいだって泣いてたよ」
聖書に出てくる名前を聞きながら、額の中に収まっている自分を見つめる。彼の国の伝統衣装をまとい微笑んでいる。
その妻の名前が耳に残っていた。私の中に響き渡り充満していく。
「その名前にする。この子の名前」
夫が考えてきたいくつもの女児の名前をすっ飛ばして、私はお腹の子の名前をその時決めた。夫は嬉しそうに笑っていた。
私の母にその名前を明かした時、彼女は喜んだ。それは素敵な名前だと手を叩いてみせた。夫の家族に告げた時も皆が喜んだ。その名前を口にする度、私達夫婦は幸せだった。
その名前には、誰しもを笑顔にする不思議な力があるようだった。そしてその名前をもって産まれてくるこの子もそんな力を秘めているように思えた。
―――
「うん、男の子ですね」
腹の膨らみの上でエコーの機械がやや速度を落とした。まとわりつくようなジェルの生温かさを感じながら、トン、と静かに崖から突き落とされる。
「あ、そうですか」
ぎこちない笑顔だけは作るまいとなるべく柔らかく笑ってみせた。
「うん、ほぼ間違いないね。男の子ですよ」
福耳の菩薩のような医師が慈悲深い笑顔で、なんとか岩肌にしがみついていた私の指を優しくコンコン、と叩く。
あ、駄目だ。もう指に力が入らない。今度こそ、谷底へ落ちてゆく──。
―――
『女の子 産み分け法』
数年後、私のスマホに関連ワードの履歴が積もっていた。二人目の妊娠を考えていた私達の前に、子供の性別という神の領域が立ちはだかる。
いや、私の前に、だ。
産み分け法は一人では実行できないと知り、あれこれ必死で説明する私の肩に、夫が一言ポンと置いたのだった。
「女の子が良いとは言ったけど、それはおまけみたいなもんだよ。神が、この家庭にはこの子供って与えるんだから、その子が俺たちにとってベストなんだよ。もしもう授からなかったとしても、それは運命なんだよ」
右肩が緩んで左肩が凝固していく。ちぐはぐだった。
「神の決める運命だよ」という彼の顔が、「この名前どうかな」と楽しげに列挙していた明るい表情に覆われていく。
夫は諦められたのだろうか。私はなぜ諦めがつかずにいるのだろうか。性別は元より子供を持つことにさえこだわりなく生きていた私が、なぜここまで諦められずにいるのだろうか。
これまでの人生の中で諦めたことを思い返してみた。浮かび上がってきたのは、たった一つや二つの出来事だった。きっと諦めてきたことなんて数知れないはずなのに、思い出せるのはたったそれだけだった。しかもその数少ない「諦めたこと」は、とうの昔にさっぱりと割り切られているか、別の案に取って代わられていた。要は、すっかり完了していた。
いつかは『娘』も諦められるだろうか。これまでと同じように。
何度思い描いた『娘を抱く夫』の姿を想像する。胸が詰まって思わずその映像をぷつりと切った。
こんなにも諦めきれないのは、これが私の願いではないからだと気づいた。これが私のものだったなら、きっとどうにかやり過ごせる。これまでの『諦めたこと』のように、割り切って、代わりを見つけて。
しかしこれは夫の願いだった。私は叶えてあげたかったし、与えてあげたかった。
あの頃の笑顔を知っているからだ。諦めたあとの笑顔じゃなくて、希望の中で咲くあの笑顔を知っているからだった。
―――
次男が産まれ、三男が産まれていた。
夫の妹から、写真付きのメッセージが届いた。
エコー検査では男の子だと告げられ男の子の名前を用意していたのに、生まれたのは女の子だったという。
夫のスマホの画面に映ったその赤ちゃんは、薄いピンクのブランケットに包まれていた。とても美しかった。
「ねぇ、姪っ子に名前つけたい?」
夫が優しい目をして私に言う。とても穏やかだけれど、私をちゃんと見ていた。
「妹がそうしてほしいって言ってるんだ」
思いつくのは、あの名前しかなかった。
けれどどうにも唇が動かなかった。
この名前を出したら終わってしまう気がした。あの日の夫の笑顔が一気に褪せて、もう二度と元通りに戻らなくなる気がした。
夫は私の心の激しい揺れを包むような優しい目のままでそこにいた。
私は、恐る恐る強張った唇を動かした。
宝物のように大事にしまってきた、大切に大切にくるみ続けてきたその三文字は、この胸から唇を伝い音となり、そっと空気に触れた。
夫は柔らかく笑った。
パパー、パパーと、廊下の向こうから子供たちの呼ぶ声がする。彼は子供部屋へと足早に向かっていった。息子たちと夫の賑やかな声が響き始める。
「おわり」
私はつぶやいた。じんわりと瞳が濡れていく。
終わった。
終わってしまった。
手放してしまった。
そして、上半身をまたベッドに横たわらせると、静かにひとり泣いた。
「おわり」
私は繰り返した。
「おわり」
言い聞かせるように繰り返した。
こだまする賑やかな声を遠くに聞きながら、私は一人泣き続けた。私が手放したのは「娘」だろうか、それとも若き日の夫の夢だろうか。
この涙は今、ちゃんと流すべきだ。本能がそう言った。押し寄せる涙の狭間で思った。
もしかしたら夫は救いたかったのかも知れない。自分がとっくに運命だと受け入れたことに、まだ囚われ続けている私を。
彼の願いをどうしても叶えたかった私と同じで、彼の上にも私の願いが重く居座っていたのかも知れない。
彼は、私が「娘」を手放す瞬間をちゃんと見届けてくれた。
そして姪っ子が正式に命名された。送られてきた写真の中で、可愛らしい正装に包まれ小さな瞳を閉じていた。
あの名前をその身に纏い、彼女は今日も美しい。
インドネシアへ帰省したら、私はこの子を抱くのだろう。妹に「義姉さん、この子を抱いて」と言われ、両手を差し出すだろう。
その重みを、香りを感じながら、澄んだ瞳に呼びかけるだろう。
あの大切な三文字を。
その時私の瞳が少しだけ滲むのは、きっと夫だけが知るだろう。
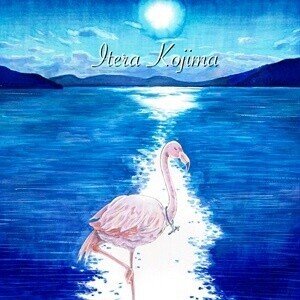
ぇえ…! 最後まで読んでくれたんですか! あれまぁ! ありがとうございます!
