
戻る日
固く重い何かが激しくドアにぶつかった。大きな破裂音に振り返る。なだれ込んで来たのは真っ赤な顔をした白人女性だった。甲高い叫び声が吹き出した。
「飛行機がハイジャックされたの!ニューヨークで!」
呆然としたのは、その日が私の留学初日で右も左も分かっていなかったからではなかった。
静まり返った美術室に、居場所を失った彼女の吐息だけが浮かんだ。あんなに真っ赤だった女性の顔の上で、熱がスー、と引いていくのが見えた。彼女が放心状態で教室をあとにすると、皆は何事もなかったかのようにまた絵を描き始めた。私も絵を描き始めた。
文化や人種は違えど、温度差は感じるもんなんだな、空気は読むもんなんだな、などとペンを滑らせながら思った。
ーーー
2時間目は化学だった。
教室に入ると、もう何人かが席についていた。まだ休み時間だというのにお喋りもせず、ただ一点を見つめている。視線の先には一台のテレビ。
不自然さから来る違和感を覚えながら、私は空いてる席にぎこちなく腰を下ろした。まだ友人など居ない私は、周りにならってそのテレビに目をやった。
青空とビルが映るだけの画面を、数十人が息を沈めて見つめるのは異様なものがあった。耐え切れなくなり、周りの表情をさっと盗み見する。
その瞬間、隣の席の女子が息を呑んだ。と同時に、斜め前に座っていた男子が口に手をやった。
日光を浴びてキラリと光る機体が、ビルにめり込んでいく。女性の真っ赤な顔と叫び声が蘇った。
校内アナウンスが流れ、生徒は次々と立ち上がり、リュックを担いだり教科書をまとめたりし始めた。私も訳が分からぬまま、担いでまとめて席を立った。授業は打ち切り、生徒は早退となったようだった。
「皆、気をつけて帰るんだよ!あ、この子今日からの留学生、仲良くねー」
遠く離れた位置からカメラ撮影されるビルはあまりに無機質で、機体はあまりにゆっくりと進んだ。器用に重ねた積み木をカシャァンと崩した程度に見えた。
バタバタと騒々しい教室の中で、教師のその言葉を一体何人が聞いたか分からない。私の存在を、一体何人が気に留めたか分からない。まるで取ってつけたような私の存在を。
あの瞬間どれだけの人の命が握りつぶされたかなど、あの瞬間世界がどんな色に塗りつぶされたかなど、想像すらしなかった。
夢にまで見たアメリカ留学初日に、なぜこんな紹介のされ方なんだと、そんなことの方が気になるほどに私は未熟だった。
その日は、9月11日だったのに。
ーーー
時が経つに連れて、その色は濃くなっていった。ありとあらゆる場所にアメリカ国旗が貼られた。家のドア、レストランやモール、車、そして私の部屋の壁にまで。ある日急にホストマザーが入ってきて、国旗のポスターを貼っていったのだ。
白い壁が気に入ってたのに、嫌だな…とぼんやり思った。
ボウルいっぱいのキャンディやチョコを抱えて待ったハロウィン。うちに来たのはたった2人だった。ずっと憧れていたアメリカ生活を楽しみたいと思う少女の気持ちなど、取るに値しなかった。
夜は静かだった。誰も街を歩かなかった。
誰も大声で笑わなかった。静かに沈む日々の中で、人々は何度も「神のご加護を…」と唱えた。
私が目の当たりにしたあの景色、私の周りに漂っていたあの色は、一体何色と呼ぶのだろうか。静けさの下に燃える炎のような、悲しみの下を這う怒りのような、涙の下に渦巻く意地のような、あの色は。
ーーー
数ヶ月後、私は誘われたクリスマスパーティーに居た。
カウントダウンや乾杯、賑やかな雰囲気に、私もよく笑い楽しんでいた。数ヶ月前、暗転した世界は、あの凍てついた暗い日々は、ゆっくりと溶け始めたかのように思えた。遠い過去のような9月10日以前にもう一度人々は還ろうとしているようだった。
「ねぇ見て!」
一際、明るい声に皆が振り向いた。
その瞬間、部屋全体の空気が一気に凍りついたのが見えた。
酔っていたのだろうか、彼は大判のバスタオルをグルグルと頭に巻きつけて笑っていた。その姿はニュースを騒がせたテロ主犯格の顔写真を連想させた。
パーティーは一瞬にして終わった。
皆で少しずつ温めてきたこの世界は、こんな投石でいとも簡単に割れるくらいに脆かった。
ーーー
放課後、ホストファザーの車を待っていて、課題に必要な教科書を忘れたことに気づいた。日本の学校の細い廊下とは比べ物にならないほどだだっ広い廊下を戻る。しかし、人気の無くなった薄暗い雰囲気は、ある程度の陰気さをもって、日本のそれと通じるものがあった。
自分のロッカーの前に立ち、慣れた手付きでダイヤルを回す。右に回し左に回し、もう一度右へ。だいぶ、こちらの生活にも慣れてきた。人見知りなりに英語を話し、友達も出来てきた。ままならないことは多々あれど、まあ何とかやっている。分厚い教科書を取り出してロッカーを閉める。
ホストファザーはそろそろ来るだろうか。もしかするともう到着しているかも知れない。足音の響く廊下を足早に戻る。
すると前方に一人の女子生徒が現れた。影は、近づくに連れ次第に色を帯びていく。そしてあの日の映像がフラッシュバックした。
なだれ込んできた女性の血走った目。思わず口をつぐんだ男子生徒の手。晴れやかな青空。キラリと光る機体。無音。崩壊ーー。
彼女は、ヒジャブを被っていた。
こんな生徒、居ただろうか。ヒジャブを被る生徒なんて、この学校に居ただろうか。私は初めて見るその女子生徒に困惑した。そんな私を気にも止めず、彼女は私の横を通り過ぎる。伏し目で足音も立てず、流れ去るように。
いや、きっと居たんだろう。私が来るよりずっと前から。ヒジャブを被って居たんだろう。もしかしたらもう何度かすれ違っていたのかも知れない。
あの事件が、彼女の存在を浮かび上がらせたのだった。ぐるぐる巻のタオルにパーティーが凍てついたように。
その日以降、私は彼女をよく見かけるようになった。廊下で、トイレで、カフェテリアで。そして彼女はいつも一人だった。
よく見かけたのに、彼女の顔をあまり思い出せないのは、ヒジャブで少し隠れていたからだろうか。話したことがなかったからだろうか。
答えはよく分かっている。
私が後ろ姿しか見ていなかったからだ。
こちらに歩いてくる彼女を、私は真正面から見ようとしなかった。いつも、彼女が横を通り過ぎるのを待ってから振り返るのだった。
私の記憶の中で、彼女はいつも後ろ姿だった。
ーーー
今でも考える。
私に友達は出来ていただろうか。隠し切れないこの髪とこの肌の色を私は認めてやれただろうか。無機質な床面だけを見て過ごしたんだろうか。皆が私を振り返って見たんだろうか。
ニュースを騒がせる顔写真が、もしアジア人だったら。
あの暗い世界を歩き続けられただろうか。あの色の中を泳ぎ切れただろうか。
毎年あの日が来ると、私は16歳に戻る。だだっ広く薄暗い廊下に戻る。ぎこちなく振り返るだけの私に、戻る。
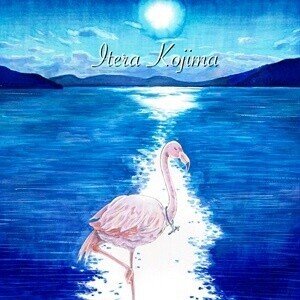
ぇえ…! 最後まで読んでくれたんですか! あれまぁ! ありがとうございます!
