
この星のもとを
誰かの土曜日を、食べ尽くす。
自分本位に、貪り尽くす。
無遠慮に、飲み干す。
誰かの大事な週末を。大事な土曜日を。
腹の底が満たされて、やっと焦点が定まったのは、夕方だった。せっかくの土曜日は、刻々と陰っていく。
その人は、私の前にふんわりと笑みを残して去っていった。
残ったのはたしかな安心感と、空の方まで広がった視界と、揺るぎようの無い一本の芯。
私はこの日を「転機」と呼ぶことにした。
スマホの画面にひたすらくっついて過ごしたこの日を。
丨
先日、フォローしている三上裕喜さんが、「占いのリハビリ」を始めようとしているのを知った。
付き合っていただける方、と呼びかけていた。
ぐわん、と持ち上げた手を、錆びた蝶番が鳴くように降ろしたのは、私が一対一の人間関係をもつことに臆病だからであった。
交わることで生まれ得る数々の素敵なことよりも真っ先に、未知の会話から生まれる緊張、勝手に傷つく可能性、気を遣わせてしまうもどかしさなどが次々と弾き出されていく。
私の脳のデフォルトはこうなっていた。
私の歩んできた人生が、一針一針編み上げてきた作品がこれだった。
どうしようもなく期待はずれなそれ、
それが私だった。
だから私は降ろした手をそのままにした。
丨
そんな日々の中に、こんな記事が滑り込んできた。
愕然とした。
その「愕然」こそが、しっかりと私に証明した。
降ろした手には、まだ諦めが引っかかっていたということ。絡まっていたということ。
たなかともこさんは、そのアイコンから眩い白と香るオレンジ色をきらきらと零しながら、颯爽と飛びゆく。まるで流星のように。
いつも私が足踏みしているその前を、すーっと飛び回っていくのだ。まるで夜空を斬るように。
そのバイタリティは、その笑顔と笑い声のスケールに表れている。
足踏みする私の、立ち尽くす私の、背中にじんわりと手を当てて「やってごらんよ」と笑いかけてくれたこともある。
私は、きらきらと零れる彼女のそれに向かって手を挙げた。
触れようとしたのだろうか。
掴もうとしたのだろうか。
変わろうとしたのだろうか。
丨
自分を知りたかった。
なぜ、自分がこうなのか、知りたかった。
なぜ、あの人のように生きられないのか、なぜこんな人生なのか。
そんなことをぐるぐる考えて雁字搦めに溺れた日々もあった。
ぱっ、とDMの白い画面に浮かんだ丸いホロスコープ。
その中には、私の、私だけの点が散らばっていて、私だけの線が結ばれていた。
三上さんは、その暗号を読み解き、流れるように、しかし丁寧に言葉を並べていった。
私が挙げた「書く」というテーマに沿って生まれてきたその言葉たちは、私の溝に傷に、ぽた、ぽた、と染み込んでいった。
その言葉は、書くしかなかった過去の私の涙を拭ったし、暗がりの中で報われずに書き続ける未来の私の肩を抱いたし、その先にともる温かな灯りを見せてくれた。
丨
「パートナーとの関係性」
その一言目が、ぐさりと私の胸を貫通した。
「一対一で向き合う人との関係が、人生において重要な役割を果たす」
続いて飛んできた二言目が、十分深かった傷を、さらに深くえぐって行った。
私が見てほしいと伝えたテーマは、「書くこと」のみだったのに、それを差し置いてまず最初に飛んできた「人間関係」という表現は、私に何十年もまとわりついてきた夜の暗い海のようなテーマだった。
私の人生のテーマだった。
結婚してからは、思い描いていた「平穏な日常」からだいぶかけ離れるような激しさと不安定さにぐるぐると巻かれていく息苦しさに、ただただ、後悔した。
一生のパートナー選びを、誤ってしまったのだろうか、私達は、互いに。
そんな後悔の波が、ささやかな日常を無情になぎ倒していった。
こんな日々の中で、私が私のことだけを、私の人生や私らしさだけを、考えて生きていけるはずがなかった。
私の人生は今や、彼との関係性の浮き沈みに上下左右され、彼と私の運命は一体化していた。肉も血管も一人の人間のようになって、切り離そうとメスを入れたりしたら、赤黒い血が滲む。
徐々に高度を下げつつ、ゆっくりと着地点を見極めつつあったチャットルームに、すがるような女の声は響く。
彼は、もう一人分のホロスコープを作成し、タロットカードも展開し、とことん付き合ってくれた。
とことん。
最後まで。
私のあのかすれ声が消えるまで。
強張りがほどけて、立ち上がれるほどになるまで。
丨
「そういう星のもとに生まれた」
とは誰が言ったことばだろう。
目に見えるものしか信じられない人がいる。
目の前に、証拠ばかりを並べてほしい人もいる。
けれどきっと、人間にとって重要なものはいつも、目に見えないように出来ている。
それを知りたいと、追い求めたいと思った女の話だ。
あらゆる角度を照らして見せてくれた人が存在したという話だ。
それはすべて事実で、現実だったという話だ。
昨日までよりだいぶ明るくなった足元を見ながら、私は歩を進めてみようと思えた。
私はこの星のもとで、生きていく。
目を逸らさずに、一歩一歩。
私だけの星のもとを、最期まで歩いてみせる。
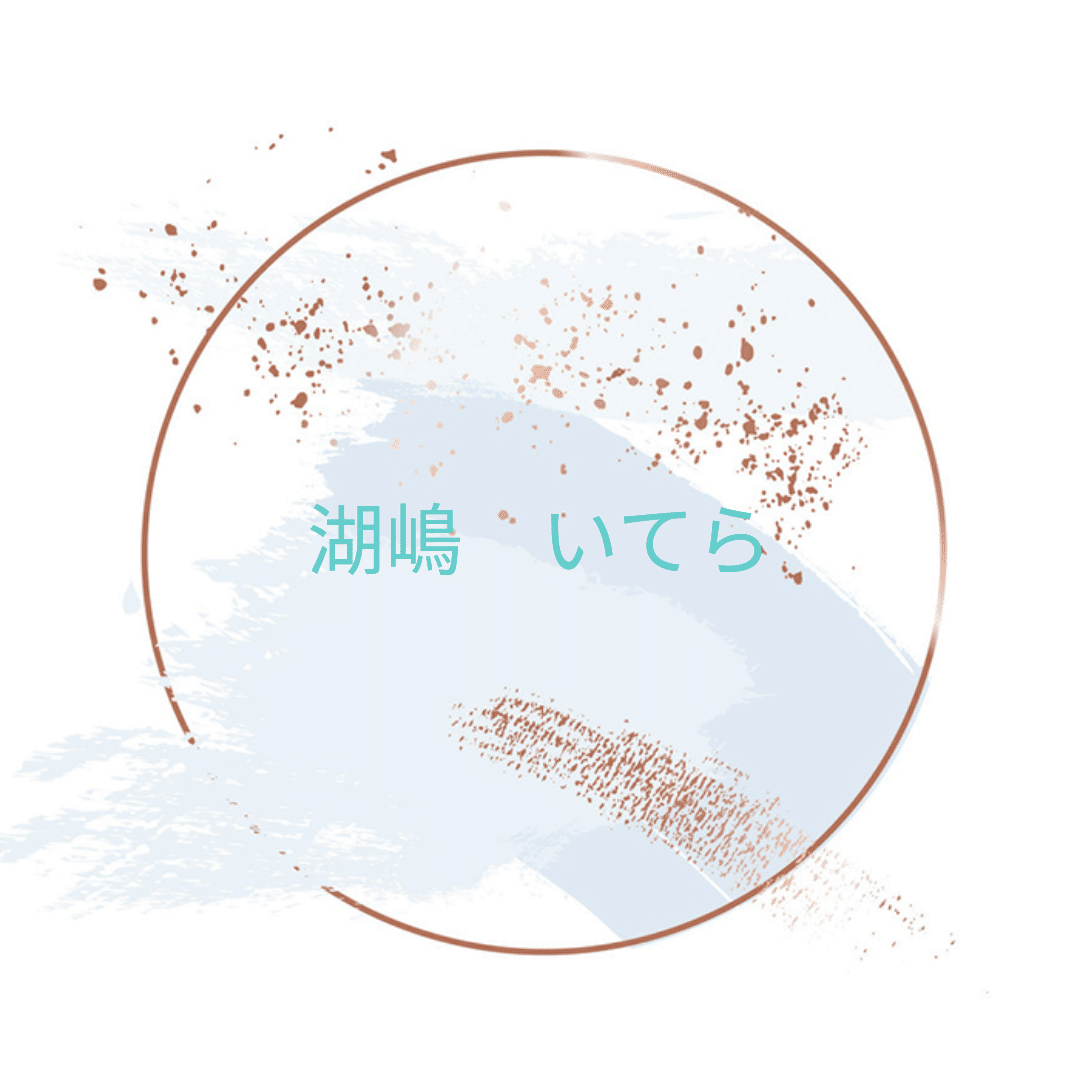
ぇえ…! 最後まで読んでくれたんですか! あれまぁ! ありがとうございます!
