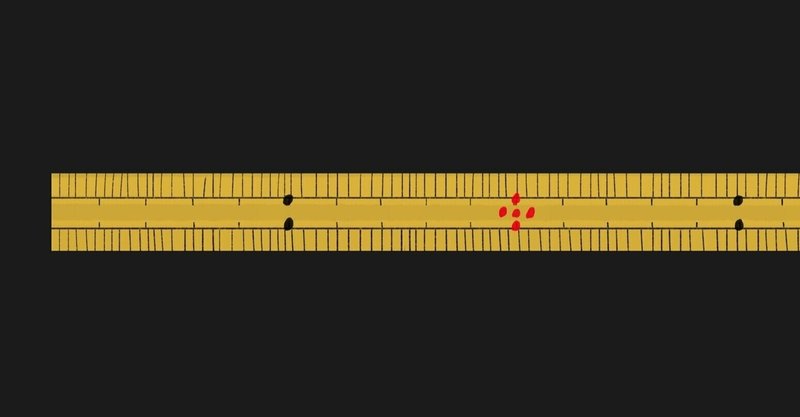
2割の怠け者は「評価軸」の問題
働きアリの法則というのがあります。
①働きアリのうち、よく働く2割のアリが8割の食料を集めてくる。
②よく働くアリ、普通に働くアリ、サボるアリの数の比は、2:6:2。
ウィキペディアで、「働きアリの法則」を調べてみると、次の通り出てきます。
-働きアリのうち、よく働く2割のアリが8割の食料を集めてくる。
-よく働いているアリと、普通に働いている(時々サボっている)アリと、ずっとサボっているアリの割合は、2:6:2になる。
-よく働いているアリ2割を間引くと、残りの8割の中の2割がよく働くアリになり、全体としてはまた2:6:2の分担になる。
-よく働いているアリだけを集めても、一部がサボりはじめ、やはり2:6:2に分かれる。
-サボっているアリだけを集めると、一部が働きだし、やはり2:6:2に分かれる。
※ウィキペディア「働きアリの法則」より引用
面白いのは、「よく働くアリ:普通に働くアリ:サボるアリ=2:6:2」のうち、どれかひとつの集団(例えば「よく働くアリ」だけ)を集めてみても、その集団の中で、また同じように「よく働くアリ:普通に働くアリ:サボるアリ=2:6:2」に分かれるという点です。
結局、1つの組織というのは、そういうふうに構成されるということです。そして、このことは人間の組織にも当てはまるといいます。
業績をあげたい経営者からすると、下位20%の怠け者(サボるアリ)を働かせることができれば、会社の生産性を向上させることができるということで、時々、これが話のネタとして取り上げられることもあります。
しかし、結局、どう切り取っても、この比率は変わらないのだから、どうしようもありません。そこで、ひとつの考え方として、こんなものがあります。
下位の20%を辞めさせると、残り80%の社員のモチベーションが低下するからです。
上位20%のリーダーも、60%の中堅社員も、常に「下に落ちるリスク」を抱えています。
「下位20%に落ちたら、クビ切りに遭うかもしれない」となると、会社のために身を粉にして頑張ろうとは思いません。むしろ転職すら考えるようになりかねません。
しかし、仕事の成果が挙がらなかったり、病気などのリスクに直面したときでも、「会社は必ず雇用を守ってくれる」とあらかじめ確約されていれば、「会社のために献身的に働こう」と思うはずです。
※ダイヤモンドオンライン「「2-6-2」の下位20%は宝!下の2割を切らないと、なぜ、10年以上離職率ほぼゼロになるのか?」2017年5月25日より引用
下位の20%、いわば怠け者を切らないことで、上位80%がやる気をもって仕事をしてくれるというのです。まぁ、そりゃそうだろと思います。
当たり前ですが、上の20%には意味があるし、真ん中の60%にも意味があって、さらに下の20%にだって意味があるのです。
これらは評価軸の問題です。私は、組織なるものはもっと3次元的に捉えるべきだと考えています。
3次元的に組織を捉えるということは、それを概念図で示せば、それも3次元になります。その3次元組織を評価するということは、そんなに単純ではありません。

イメージとしては、こんな感じです(絵が下手で、心の底からごめんなさい!)。ともあれ、人の評価というのは、多様な軸でみないと分からないということです。
アリの話も、人の組織の話もそうですが、それらの評価を「食料」だったり、「業績(売上?)」を元にして考えています。そう考えてしまったら、2:6:2のメンバーは自ずと固定化していきます。
上掲記事では、下位20%を切ってはならない、切ってしまうと上位80%のモチベーションが下がるといっています。これはこれで、その通りなのでしょう。
しかし、これをもっと別の表現で言うこともできます。
例えば、「他人のモチベーションを高める」という新しい軸を用意して、それを評価するとしたら、下位20%の怠け者たちは、たちまち上位20%に躍り出るかもしれません。新しい評価軸を設ければ、上位20%、中位60%、下位20%のメンバーはガラリと変わりうるということです。
組織には、いろんな要素が詰まっています。複数(あるいは多く)の人々が集まるわけですから、そこには人が集まれる環境がなければなりません。ただ、売上があればいい、業績が上がればいいというものではありません。
そこには、円滑な人間関係があるかとか、働き甲斐があるとか、心地よく仕事ができるとか、助けたくなる同僚がいるとか・・・なんでもいいですが、そういうものが合わさって組織なのです。
場合によっては、緊急事態が発生して、そうしたトラブルにも対応できる危機管理体制だって求められます。20%の下位は、怠け者という捉え方ではなく、組織にとってはゆとりです。怠け者という言い方に対して、敢えて「遊び」という表現をしてもいいと思います。
「遊び」もなく、全員がパッツンパッツンで働くような組織が、普段起こらないようなトラブルに見舞われたら、あっという間に崩壊するでしょう。組織にとって、20%の怠け者は「遊び」であっても、不要なわけではないのです。
問題は、それを「遊び」として、切り捨てるところにあります。
こんなことに悩んでいる組織の責任者がいるとしたら、たくさんの評価軸を持ってみろ、そうやって組織を多角的に評価してみろと言いたくなります。
もう少し踏み込んで言えば、一人の人を評価したときに、その一人が20%の評価軸で上位、60%の評価軸で中位、20%の評価軸で下位になるくらい、組織は多種多様な評価軸をもって然るべきではないかとすら考えます。
さて、ここまでは組織の話です。まぁ、世の中に経営者と呼ばれる人たちは一部でしょうし、こんな話は、もしかしたらほとんど役に立たないかもしれません。
ただ、私がここで言っておきたいのは、こうしたことは、人一人について考えるときも同じではないかということです。

上図は、私が3次元的組織を考えるときの概念図です。3次元的組織というのは、どこの点をとっても、そこを中心に展開できます。そして、この概念を「会社」とか、「学校」とか、「組合」とか、そういうことに当てはめる必要もないと思います。
例えば、今、自分の身の回りにいる人たちすべてが、それぞれ自分を中心にして、このように繋がっていると考えればいいわけです。つまり、上に示すような3次元的組織を、今、住んでいる社会と捉えてみるのです。
そう考えたら、既にあなたは、この世界の中心にいて、自分をリーダーとした組織のなかにいることになります。
そんななか、あなたの周りには、きっと「2:6:2」の法則で、振り分けられる多くの人たちがいることでしょう。そして、その評価軸が少なかったら、あなたの周りにいる人たちは、自ずと上位20%、中位60%、下位20%に振り分けられ、固定化されるのだと思います。
それは自動的に「好きな人、普通の人、嫌な人」になってしまうかもしれません。
仮にそうだとしたら、ちょっと待った!
少し離れてみてみましょう。いろんな評価軸があると思うのです。たくさんの評価軸をもってみましょう。そうしたらきっと、あなたの周りにいる人たちは、「上位20%、中位60%、下位20%」に固定しないのではないでしょうか。
すると、意外と嫌いな人はいなくなるかもしれません。
2割の怠け者は、きっと評価軸の問題ですから・・・。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
