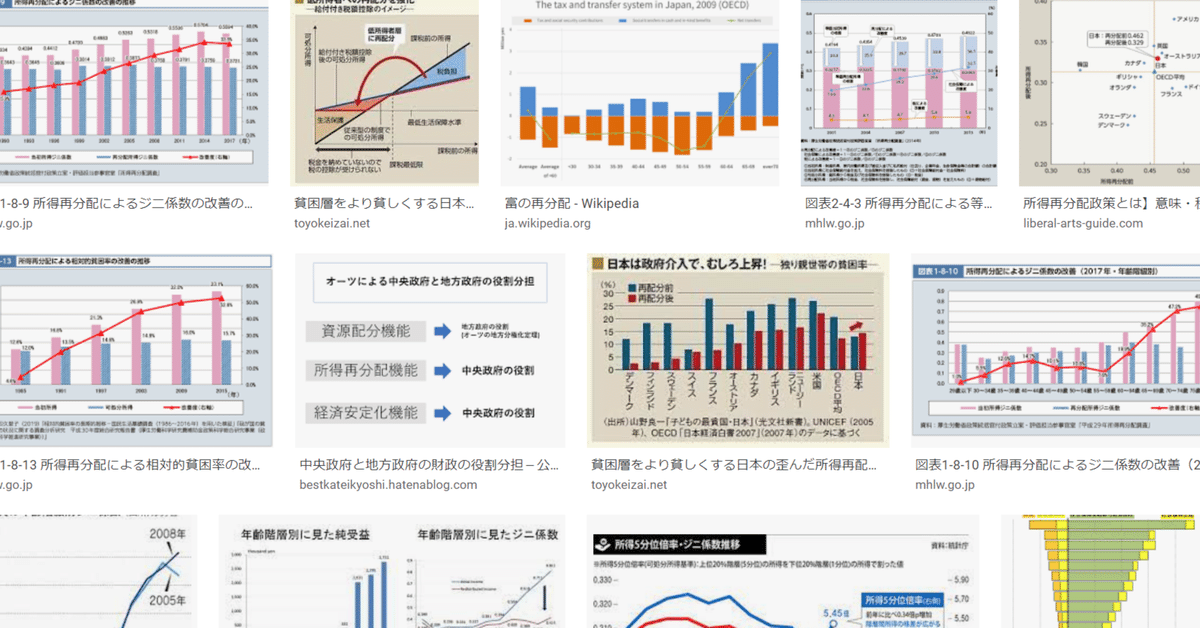
政府の所得再分配について 公共経済学
生活保護者の働くインセンティブを高める案として、受給期限を設定するということがあるようである。生活保護者としての生活レベルが高いため、働く意欲が低下するのは理解できる。一般の会社員は、会社が税金について源泉徴収する仕組みとなっている。これは、徴収側はかなり有利な仕組みである。本来であれば、納税感覚が高まるはずだが、これでは、納税している意識が少なく、さらに再配分している感覚も薄れているのではないか。転職などをして、住民税を自主納付となる場合、コンビニなどで地方税を払う際は、高い買い物をしていることを実感できることから、源泉徴収制度をやめることで、税負担の度合いと、再配分している実感を持てるようになるのではないか。政府側にとって我々納税者は「豚」のような存在であり、豚同士が支えあう仕組みの動物園の中で過ごしているようなものである。再分配に寄与している世帯・個人・企業は、政府の養分となって、経済活動を行っているようなものである。何をどのように再配分するかを定性的に分析・分類したものが本日の授業内容であるとおもうが、原理は理解しても、何かしらの不満が残る印象を受けた。
所得分配の視点 ②所得再分配と課税 政府による様々な所得再分配政策 給付と保険料や税制の支払いとの関連に基づく所得再分配 ①世代間所得再分配の例 第1世代・現役期→第2世代・幼年期・・・保育サービス、児童手当 第2世代・現役期→第1世代・老年期・・・年金保険、医療保険、介護保険 ②世代内所得再分配の例 老年期・・・年金保険、医療保険、介護保険 現役期・・・医療保険、失業保険 ③個人間所得再分配の例 累進税の所得課税、相続税、生活保護 国と地方との間で行われる財政移転に基づく所得再分配 ④地域間所得再分配の例 地方交付税交付金、国庫支出金 ・・・地域間所得再分配は、個人間所得再分配の効果も持つ。 第1世代 幼年期 現役期 老年期 第2世代 幼年期 現役期 老年期 ②世代内所得再分配 ①世代間所得再分配 中央政府 地方政府 地方政府 地方政府 高所得者 ④地域間所得再分配 低所得者 ③個人間所得再分配 - 21 - 所得再分配とターゲット効率性 横軸:当初所得の水準に応じて、家計を原点から右に並べる。 貧困線:貧困状態にあると考えられる所得水準 当初(再分配前)所得は OCEFG 線 ・・・貧困状態を救済するのに必要な社会保障給付は、面積①+③分 政府による社会保障給付後の再分配後所得は BDFG 線 ・・・社会保障給付総額は、面積①+②分 ②分は過剰な給付、③分は本当に必要な家計に給付が届いていない。 必要な家計に必要なだけの給付を行う必要(=ターゲット効率性) (参考)社会保障給付費総額の推移 所得 家計 貧困線 E O C B A D F G ① ② ③ 当初(再分配前)所得線 再分配後所得線 - 22 - 「負の所得税」構想(M.Friedman , J.Tobin) 所得税制と公的扶助(生活保護)制度を関連付けて考える。 所得税も生活保護給付もない場合、所得は OY 線上 生活保護制度:AB 線 課税最低限:OY2(OY2 を超える所得には所得税を課税) ①所得が OY1 までの家計に対して、OA 分の生活保護給付を実施 ・・・働くインセンティブを阻害する。 所得税と生活保護給付が行われる場合、所得は ABCDE 線 ②低所得層に対して、負の所得税を導入:AF 線 ・・・給付後所得が純増する。→働くインセンティブを刺激 負の所得税を導入し、適用所得を拡大したり、働くインセンティブ を考慮したりするほど、多額の給付費(公的財源)が必要となる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
