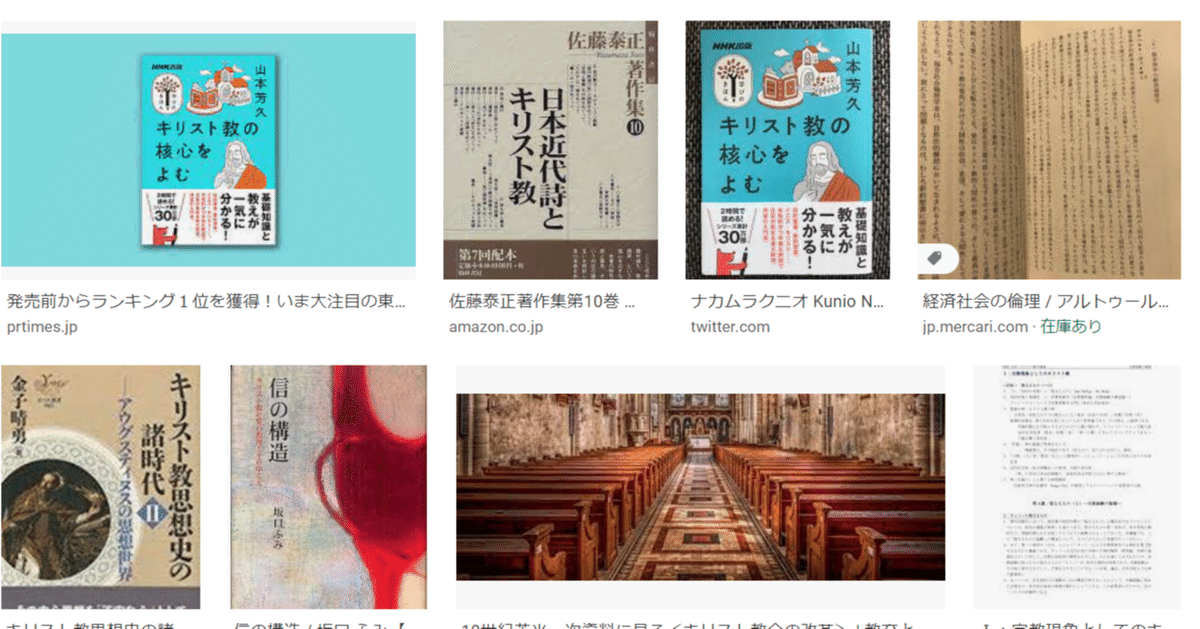
キリスト教の核心をなすもの
人間と哲学の知第6回講義課題(20211119)
*はじめに
皆さん、今日は。担当の〇〇〇です。昨日の講義ではキリスト教の核心をなすものと、キリスト教の人間観とその社会的影響について学びましたが、今回の課題は特に「キリスト教の核心をなすもの」を中心に纏めて頂き、それに対する自分の見解を書いて下さい。な
お、人間観・社会的影響を含んでも構いません
*締め切り
11月26日(金)PM8:00・締め切り
(1)文字数1000~1500字。
(2)講義で使用した資料か或はその資料と同等の信憑性のある資料に基づいて書くこと。
(3)出典は必ず挙げること。
(4)唯纏めるのではなく、最後に自分の見解も書くこと
(5)担当の指示する日時に提出すること。
***************
2021/11/19
「キリスト教の核心をなすもの」を中心に纏めて頂き、それに対する自分の見解
前期の西洋思想とインドの思想の授業(20210721)において、今回と同様の講義をなされたところ、参考に前回のレポートを付記いたします。前回と違う視点で、自分の見解をまとめます。
<まとめ>
イエス:ユダヤ人として生まれる。ユダヤ教を踏まえながらも独自の教えを説く。他方、正統ユダヤの反感を持たれ処刑された。人間の最も大切なものとして、神への愛と隣人への愛を説いた。
キリスト教の普遍性と超越性とは、「愛」ないし「人」の捉え方に基づく。
彼の死と復活の物語は、自ら死ぬことによって自分の支配圏全体を活性化する王のイメージと結びつく。
パウロ氏が、イエスの不名誉な死を、イエスが生前説いた愛の要請を実現する宇宙的・世界的なドラマへと構成しなおすものだった。すなわち、父なる正義と愛の神は、自分の子供(イエス)を世につかわし、罪なき彼を犠牲として死なしめ、それによって全人類の罪をあがなったという創作である。(贖罪の犠牲、壮大なドラマ化に成功)
ネオプラとニズムとの親近性
世界と超越者という二項対立の世界観の中を流動的に移動する存在を構築したことで、ヘレニズム世界との親和性が生まれた。パウロの物語/創作は、既存の世界観の融合が容易であった。他方、相違性もあり、旧約及びキリスト教思想が本質的に歴史的な思想だという点である。
パウロは「コリント前書」において、キリストを中心とする一つの体という教会論をうちたてており、この集団に属することによってのみ人は救われるという考えは、キリスト教の全歴史を通じて変わることが無かった。いわば、軍隊にも似た編成をもった。
<感想> 純粋な感想であり、それぞれの宗教を冒涜する意図はなく、個人の脳内で冷静に処理した感想です。悪意のある表現を避けていますが、限界もあります。ご了承ください。
この論述を読めば読むほど、「キリスト教」は、結局のところ、「愛」を利用した世紀を貫くねずみ講式ビジネスである。それらが分かっていながらも、もしくは、気づかせないふりをして、ヒトはなぜキリスト教へ寄り添うのだろうか。日曜日に協会に通う。それはそれでよい。イスラム教は、「金曜」、ユダヤ教は「土曜」、キリスト教は「日曜」それぞれが、お祈り等をする曜日を分けている。もはや、出勤表のようである。イスラム君、ユダヤ君、キリスト君の・・・。
キリスト教の核心をなすものは、軍隊にも似た編成をもつ教会組織の維持であるといえるだろう。その手段として、キリストという「ネタ」とそれにまつわる出来事(贖罪)を活用し、天才的なビジネスマンであったパウロ氏が考案した、ビジネスモデル特許のようなものである。
永遠に続く宗教は世の中に存在しないと定義することができるならば、この「キリスト教」なるある宗教は、消えていくだろうと予測する。なぜなら、AI(人工知能)やそれを超える合理性集合知が開発されることで、キリスト教等で観念的な存在である「愛」や「神」について、人々が冷静に容易にイメージすることが可能となり、絶対的なAIへの信仰が進むことで、宗教という概念が変化すると予測している。ある一つのメニューにすぎず、何を今夜食べましょうかというレベルになるような気がしている。少なくとも、教会組織の維持は困難になり、貨幣経済・資本主義の変化とともに、組織が変容・劣化していくだろうと予測している。逆に、さらにキリスト教の教会組織が拡大するきっかけや要素は、いったい何があるのだろうか。まったくもって、思いつかない。むしろ、イスラム教の拡大に押される格好になり、縮小していくだろう。
以上(1,387文字)
<まとめ>
2021/7/21前期の西洋思想とインドの思想
キリスト今日の核心をなすもの
ナザレのイエス・・・ 地中海東部 出身 ユダヤ人
ユダヤ教から独自の教え
ローマ宗教・ユダヤ教とも対立し、迫害受ける。
処刑後に弟子たちが、その教えを広めていった。
主の教義は、「愛」「人」のとらえ方
パウロが物語を創造した。いわばストーリーテラー。脚本家。ドラマ作家。それがキリスト教の普及の原動力となった。その結果として、古代哲学がキリスト教的にゆがめられた。
汎神論・・・神も人間が自然を支配しているということを認めている。人間の優越性あり。
人間が自然を探求することによって、神の顕現につながる。自然の本当の在り方、法則が求められる。自然を支配している法則にたどり着く。
ベーコン 先入的偏見
4つのイドラ(idola:幻想、偶像)
数学を軽視もしくは敵視
ガリレオ 汎神論的自然哲学から自然研究の方法論の哲学への展開へ
数学を重要視
<見解>
前提として、単純に哲学するということで、概念を文字化している。決して、神を冒涜するとか馬鹿にするとかそういう意図はありません。そこで、神という定義次第で、諸々の方向性が変化してしまうのが、愉快である。なぜなら、例えば、ガリレイさんもベーコンさんも、神の存在を疑うことをしたかもしれないが、在る前提で、自然研究をされた、もしくは神を探すために、自然研究に没頭してしまったといえるのではないか。彼ら二人が、現代にトランスポートしたら、原発問題やコロナ等の社会的な集合知の異変に対して、自然研究の力を存分に発揮して、高度な知能でAIをも凌ぐもしくは活用し、問題解決方法を編み出してくれるに違いない。一方で、日本は神頼み的な発想や精神論的に政治や行政運営がされているような状況もあり、日本の集合知がidola取りつかれたかのように、合理性のない意思決定や行動をするカオスな社会情勢が続いている。現実を正しく把握せよというベーコンのような一部合理的な集団に人間はすべてなるとはいえないが、時に人々は、イドラにまみれている状況を温泉にでも行って洗い流すことが大切なのではないか。古代ギリシャにも日本にも温泉は好まれた文化であった共通点があるのではないか。
さて、ベーコン氏は数学を否定的にとらえようとするセンセーショナルな行動で、注目を浴びようとしたかもしれないが、賢いが故に彼は自己矛盾に耐えきれなかったということが想像できる。一方、ガリレイ氏は、数学を重要視し、自然を数学で記述するということに試みた代表者である。彼は、もやもやとしていた、自然と神と人間の関係性が宗教的にゆがめられたものを整理したと理解したが、それはそれと天才過ぎて周りが追いつけず、持ち上げられただけだったのではないか。実際には、私が思うに、資本主義や貨幣経済の弊害から、かつてのあいまいさを上手に商売に結び付けて、人間のidolaに付け込みつつ、何か救われる可能性をお金で解決できます的な宗教が今でもはびこっている一面があるのではないか。このような宗教の歴史は一般教養として国民全体が正しく持つことで、上手に生き抜ける人が増える社会になるのではないかと夢想しているところである。
以上(1274文字)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
