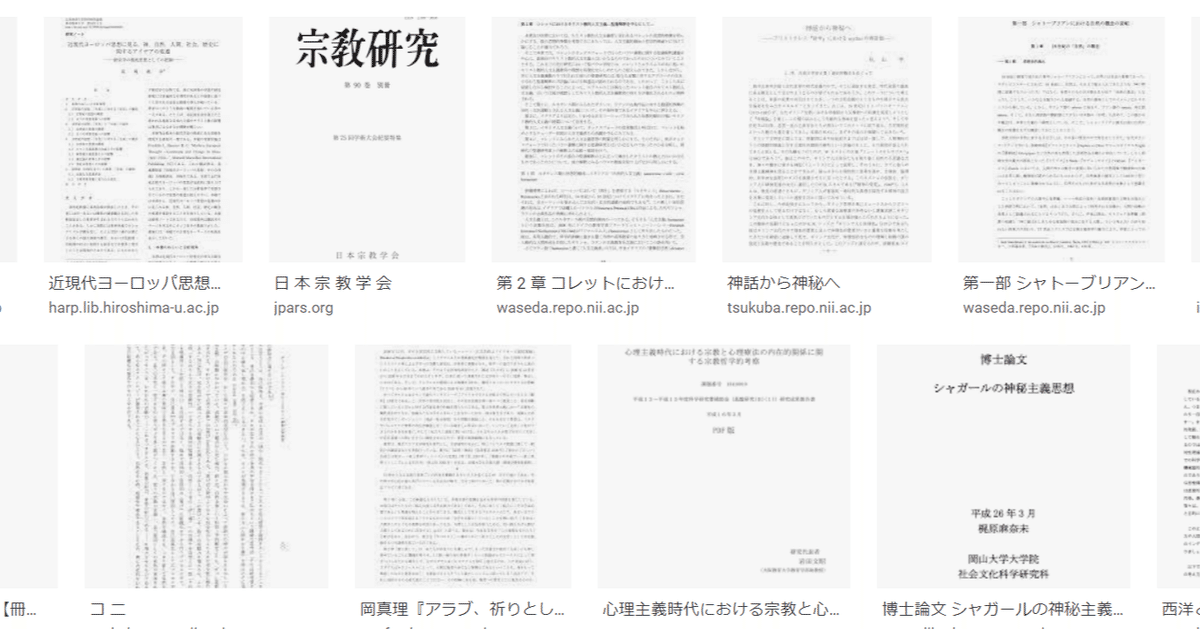
古代ギリシャの人間観について神秘主義的潮流のそれと自然学的潮流のそれを比較して、更に自然学的潮流の至った人間観に見られる問題点について】まとめ
【古代ギリシャの人間観について神秘主義的潮流のそれと自然学的潮流のそれを比較して、更に自然学的潮流の至った人間観に見られる問題点について】まとめ
それぞれの定義
1 神秘主義的潮流
(1) ディオニソス信仰 → 人間は神秘的な存在
・信仰の信者の中心は女性であった。特色がある。人間は不死の神になれるというもの。ギリシャ人の精神的願望に応じたもの。
(2) オルフェウス教 → 輪廻の思想 霊魂は不死
・禁欲を行い魂を強化 輪廻の業
(3) ピタゴラスの思想 →魂の輪廻
・生物は肉体という墓場の中に堕ちている状態。
魂の在り方の方が大切
2自然科学的潮流における人間間
ミレトス学派/エレア学派(ヘラクレイトス)/ピタゴラス/エンペドクレス/アナクサゴラス/デモクリトス
3ソクラテス・プラトン・アリストテレスにおける人間観
ソクラテス→合理的
プラトン→人間を外側から規定
アリストテレス→理性的・社会的動物
<感想>
哲学の授業を前期から受講しているが、基本的に、過去の哲学的歴史やその体系を学ぶことと、哲学することとは別物である。講義で哲学を学ぶということは、過去の哲学情報を身に付けることが第一義的であるものとされているだろう。ところが、私においては、実際に哲学してみたいのである。過去の哲学者がどうだったかなど、どうでもよく、とにかく哲学をしてみたいという、短絡的な理由で講義を拝聴しているところである。自分でも、過去の哲学者の基本的な考え方や、それぞれの差分・特徴などを把握することは、とても大切であり、それは、自分の中の哲学する能力を高める可能性があるということは、なんとなく理解しているつもりである。ところが、自分の哲学体系の方が、過去の偉人よりもすぐれている訳は、無いのに、もしかしたら、自分の方が優れてしまっているのではないかという、淡い期待をもっている。そこが、小人間の愚かなところである。反省と自覚の毎日である。
現在は、日本の四季は、秋であり、紅葉のさなかである。沖縄では、秋を感じることは、難しいかもしれないが、ここ日光の近くで生活していると、紅葉が美しく、そろそろ落葉してしまうという瞬間であり、山々が非常に美しく思える。ところが、デモクリトスは、自然はもはや全く機械論的に解されるとされ、その言葉をそのまま受け止めれば、落葉することと哲学は切り離すべきであり、落葉をもって哲学とすることは、哲学本来の探究をやめてしまっていることに等しいということを言っているのではないかと理解してしまっている。葉に色が付き、赤くなり、葉が落ちる、葉は人間とは違うが、人間と同じくアトムの集合体である。デモクリトスが、幸福とは決して感覚的快によって得られるものではなく、精神的快によって得られるものであり、その精神的快とは心の安静不動の状態を意味していたされているが、この定義は、現代の我々にも当てはまるのではないか。なぜなら、おいしいものは、おにぎりを食べてもおいしいと感じるときもあり、それを幸福と感じるときもある。遠足で食べるおにぎりの味は、その情景を思浮かべるだけでもおいしそうに思えるし、心の状態が良い時にこそ幸福が得られるということではないか。同じおにぎりでも状況が違えば、幸福感のあるものとなる。
以上(約1250文字)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
