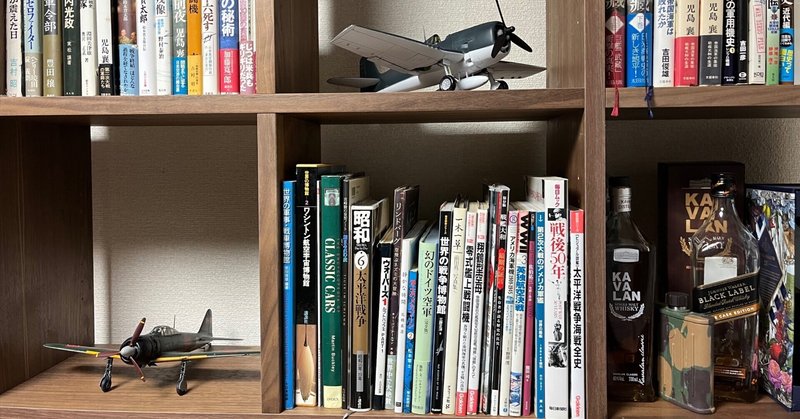
杉田庄一ノート93 「島川正明氏が語る杉田庄一」
島川正明氏は大正10年に徳島県に生まれ、昭和14年6月に佐世保海兵団入団、15年に第53期操縦練習生に採用され、戦闘機搭乗員となった。昭和16年台南空に配属され、太平洋戦争初期に坂井三郎氏の三番機となって活躍した。その後、ミッドウェイ島攻略後に進出する航空隊として予定されていた六空に転勤する。
杉田もそのとき新人搭乗員として六空に配属されていた。ミッドウェイ海戦時に空母加賀に便乗していたが沈没、からくも脱出生還している。その後、ソロモン空域の戦いに参加、1年実戦を積んでいる先輩として杉田ら若手を育てた。
当初、ブイン飛行場はジャングルを切り開いたばかりでこぼこの滑走路しかなく、離着陸も難しかった。島川は次のように書いている。
「ブイン飛行場には、幅十メートル、長さ八百メートルの鉄板を敷いた滑走路が一本あったのですが、若手のパイロットは、これに満足に着陸することもできなかったのです。
若手が十人いれば、九人までがおしゃかにしてしまった例もありました。
実は、この滑走路は、母艦航空隊のパイロットにも鬼門になっていたのです。母艦航空隊員は、基地航空部隊員よりも優れた技量を持っていましたが、フックを使えない着陸となると、さほど上手ではありませんでした。横に滑ってはみ出したり、つんのめって尾部を天に上げて止まっていました。
”母艦屋”も技量レベルの低いパイロットが多くなっていたのだろうと思います。
また、零戦そのものも、その当時のものは、ブレーキ装置がお粗末でした。少し強く引くと、前につんのめるし、引き方が少し甘いと、オーバーランするというぐあいでした。効き方が不安定なので、着地後のブレーキ操作には、神経を使ったものです」
そのような若手の中の一人に杉田がいたのだが、ある日、B-17対策の空戦練習中に杉田は本物にあってしまう。杉田は、訓練通りに、いや訓練以上にぎりぎりまで突っ込んでいきB-17にぶつかって撃墜?することになる。幸い、杉田の零戦は補助翼を失っただけだったのでよろよろしながら無事着陸している。 そのときのことを島田は次のように書いている。
「日付についてはほとんど記憶にないが、たしかこのころだったと思う。敵偵察機(B17またはB24)が毎日といってよいほど基地の上空に現れるようになった。しかも時刻は、いつも正午である。(われわれはこれを定期便と呼んだ)
わが戦闘機にたいし、よほどの自信があったものとみえ、きわめて正確に上空に現れるのである。まるで私たち二〇四空戦闘機隊を無視したかのように・・・・。彼らは過去にわが零戦と戦った経験があるのかも知れない。でなければ、このような定期便は出せないはずだ。
私たちは基地上空哨戒の任務を兼ね、この偵察機にたいする攻撃方法を訓練していた。敵の集中砲火を避けるため、斜め上方、同前下方、そして背面攻撃などがそれである。つまり、敵の視角外からの攻撃方法なのだ。
後上方攻撃など基本どおりの方法では、わが方の二十ミリ機銃にたいし、敵機十三ミリ(正確にいえば十二・七ミリ)機銃の弾道がすぐれているため、被害が多かったのである。そんなある日、訓練中の杉田上飛が飛来した敵機にたいし、斜め上方から攻撃をかけたが、きわめて接近の早い反航のため、退避が遅れ、垂直尾翼が敵機に接触し、敵機は空中分解して墜落していった。
彼は己れの空中ミスを恥じ、おそるおそる報告していたが、おとがめを受けるどころか、逆におほめにあずかり、照れていたようである。以後、しばらくの間、敵の定期便は姿を現さなかった。杉田の大手柄である。
彼はリンゴのような紅いほっペタをして大声で笑う好青年で、ラバウルに引き揚げた後、多数の敵機を撃墜したと聞いたが、攻撃精神の旺盛な好青年だった。」
島川は昭和18年マラリヤで内地帰還する。内地では大村空で教員となり、昭和19年に二二一空に転勤、最後は三四三空の四〇一飛行隊の先任搭乗員となる。四〇一飛行隊は、三四三空の練習部隊で若手搭乗員を養成して本隊に送り出す役目をおっていた。本隊の搭乗員が少なくなる中で、8月14日に本隊への転勤を命ぜられ移動中の15日に終戦となった。戦後は海上自衛隊のパイロットとなっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
