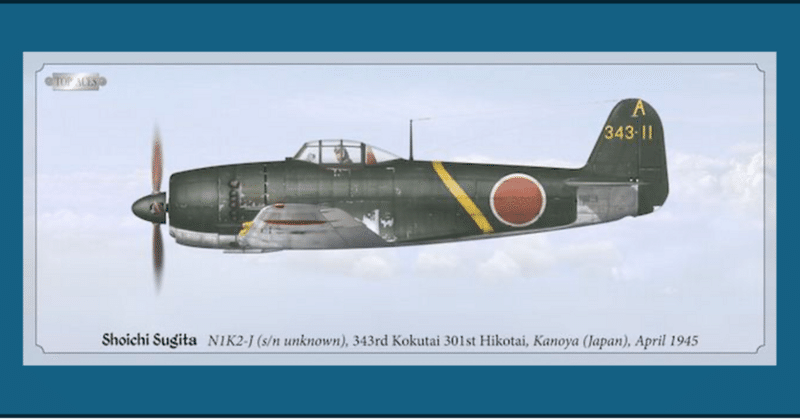
杉田庄一物語 その64(修正版) 第六部「護衛」 山本長官遭難
四月十八日六時、快晴。ラバウルの東飛行場の輸送機発着所に七〇五空の一式陸攻三機が機首を滑走路に向けて直角に並べられていた。待機所に一番近くに山本長官搭乗機、その次が宇垣参謀長搭乗機、そしてトラック島に戻る第二航空戦隊司令長官角田覚治中将の搭乗機という順である。角田長官は山本長官と同じ新潟県の出身で、先輩後輩の間柄である以上に個人的にも懇意であったため、山本長官出発を見送ってから出発する予定にしていた。
その日、山本長官はいつもの白い第二種軍装ではなく、めずらしくカーキ色の第三種軍装に身を包んでいた。その上に肩かけのついた革バンドに軍刀を帯びていた。前線に行くためであろうが、これまでの見送るための軍装とは違う覚悟がそこにあったのかもしれない。
六時五分。長官機が出発し、ついで参謀機が飛び立った。二〇四空の零戦も空中で合流した。
「伝承零戦空戦記2」(秋本実編、光人社)の中で柳谷は出発の様子を次のように語っている。
「明けて十八日はいい天候だった。未明に起床し、ただちに飛行場にむかった。 朝食は、麦飯と塩マスと塩からい味噌汁で、待機所ですませた。
待機所のまえには、すでに搭乗機六機と予備機二機が、整備分隊員の手で入念に試運転されている。
われわれも飛行帽、ジャケット、落下傘帯、拳銃などを着用し、点検をすばやくすませた。
まもなく『直掩搭乗員、指揮所まえ整列』の命があり、そこへ行くとすでに宮野飛行隊長が待っていた。直掩機指揮官森崎中尉以下われわれが整列すると、
『離陸して編隊を整えながら西飛行場へむかう。 飛行高度の注意。西飛行場上空を旋回しながら中攻機をむかえ合流する。 そのときの高度は斜め約五百メートル後上方を進行』
と、指示をうけた。
『カカレ!』 の号令で一斉に、われわれは挙手の礼をし、さっそく指定の零戦にむかって駆け足、 大きく朝の空気を吸ってゆっくりと操縦席におさまった。
操縦席で厳密にスロットル、全速スローなどの点検をすばやくすませた。すべて調子は上々で、計器も正確に作動している。
やがて風防より右手を外にだして発信の合図を待った。一番機、二番機以下すでに点検を終え、待機の状態である。 すると、指揮所から離陸の合図がでた。
指揮官森崎中尉の前輪チョークがはらわれ、発進。つぎつぎと東飛行場を離陸し、所定の編隊を組んで西飛行場へとむかった。
その間、何分を要したことか。 高度五百メートルで編隊を組み眼下の花吹山に目を転ずれば、 祝福するかのように硝煙を吹きあげている。やがて編隊が、西飛行場の上空にさしかかるころ、 司令長官以下幕僚を乗せた一式陸攻二機が下方から離陸してきた。 さっそくそれと合流した。」
陸攻一番機の操縦員は、小谷立男飛曹長、二番機の操縦員は林浩信二飛曹で二人とも経験豊かなベテランであった。一番機には、高田軍医長、樋端久利雄航空参謀と副官福崎昇が乗り込み、二番機には宇垣纏参謀長、北村主計長、海野気象長、今中薫通信参謀、室井捨治航空参謀が乗り込んだ。
行程約三百五十浬(約六百キロメートル)だが、ブーゲンビル島及びショートランド諸島の制空権はまだ日本にある。ブーゲンビル島でも敵機の空襲はあったが、それはいつも夜間か、単独または数機による高高度からの水平爆撃であり、戦闘機だけが現れることは「通常」考えられなかった。繰り返しになるが、米軍の陸上戦闘機が飛来するにはガダルカナル島基地から遠距離すぎる。かといって近海にいる米海軍空母の情報はなく、海軍機による飛来も考えられない。二時間弱の距離であるが、通常であれば敵に襲われる心配はほとんどない。しかも快晴である。午前中は太陽の方向に向かって飛ぶことになるのが一抹の不安をあたえた。敵を発見しにくくなる。
七時二十分、一行の前にブーゲンビル島が水平線上に姿をあらわした。六機は高度二千五百メートルを保ち、一式陸攻が上位に位置していた。計画では七時四十五分にバラレに到着する予定であった。ここまでくればあと数分で到着である。皆の心には安堵感がよぎったにちがいない。
七時二十五分、突然、二機の一式陸攻機は編隊を組んだままで高度を下げ始める。敵機だ。高度を下げたのは、低空で進むことにより敵機からの攻撃を受けにくくするためだ。下からの攻撃は防げるし、上空からはねらいにくくなる。はたして敵機が後方約千五百メートルの高度に現れる。四機のロッキードP38戦闘機である。さらに上空高度六千メートル付近にも多数のP38が直掩しているのが見えた。待ち伏せだった。
米軍はP38戦闘機隊を二つに分けていた。一つは、山本長官をねらう攻撃隊でランフィア大尉を小隊長とする四機編隊である。もう一隊は、ブイン基地から迎撃に来るであろう多数の零戦部隊を迎え撃ち攻撃隊の邪魔をさせない直掩隊だ。全体の指揮官でもあるミッチェル少佐が指揮をしていた。
米軍は暗号の解読で護衛機が六機であることを事前に知っており、ジャングルに紛れるように千五百メートルの高度で攻撃隊四機を待機させ、直掩隊十二機は高度六千メートルで待機していた。ブイン基地には多数の零戦がいることは確認済みでこれらに備えるためである。山本長官の出迎えに数十機の零戦が上空直掩をすると予想していた。直掩隊は、出迎える零戦を抑え、攻撃隊は零戦にかまわず陸攻を攻撃するという作戦だった。
しかし、ブイン基地からは零戦は上がってこない。実は、長官を出迎えるため地上では整列がかかっていた。敵が来ることを予想だにしていなかった。
敵機の出現に一式陸攻の一番機も気付き、直ぐに機首を下げて樹海の上空五十メートルまで降下した。ブイン基地まで五〜六十キロメートルの距離、わずか数分で着く。しかし、山本長官達の乗った陸攻が迎撃されるのには十分な時間であった。
七時三十四分、米軍が予定していた到達予定時間より一分早いだけだ。奇跡のような遭遇だった。一番機は右方向へ、二番機は左へと逃げた。すかさず銃撃を受け、一番機は火炎をあげて樹海に突っ込んだ。詳細は「柳谷証言」で後述する。
二番機も炎を弾きながらモイラ岬付近の海上に不時着水し転覆した。五分あまりのできごとであった。モイラ岬はブインの基地の近くにあり、見張り員がすぐに大発で二番機の救助に向かった。岸に向かって泳いでくる者を救いあげると林操縦員だった。林は
「もう二人海に放り出されて生きている者がいる。たのむ」
と、沖を指した。すぐさま大発は沖に向かい、宇垣参謀長と北村主計長を拾った。
P38戦闘機の行動半径は五百マイル(約八百キロメートル)である。ガダルカナル島からブーゲンビル島までは、直線距離で三百マイル以上あり、途中の島嶼郡には日本軍の緊急避難基地が置かれていて直線飛行は難しいことが予想された。迂回航路の半径は四百三十五マイルとなり、これに空戦を行うとなるとP38戦闘機といえども余裕はあまりない。ブーゲンビル上空で待ち伏せしている時間は三十分ほどに限られていた。山本長官が時間通りに行動することを考慮しての作戦で、分刻みで行動予定がたてられていた。日本軍の暗号電文にある時間通りに山本長官一行が動くことが作戦成功の鍵をにぎっていた。そして、山本長官は時間通りに行動した。その正確さがわずか数分のチャンスを米軍にもたらした。
米軍が暗号を解読していたことを日本軍は知らなかった。この作戦が実行されたあとも解読されたことに対して懐疑的であった。詳細は後で記すが、暗号を解読されたかどうかを試すためのニセ視察作戦を後日実施して、安心をしている。米軍はそのことも承知済みだったのに。それにしても、まさか暗号が解読されるはずはないという「作戦の緩み」は、ガダルカナル島をめぐる攻防戦でも繰り返されたことだった。組織的な緩みが蔓延していたとも考えられる。
<引用・参考>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
