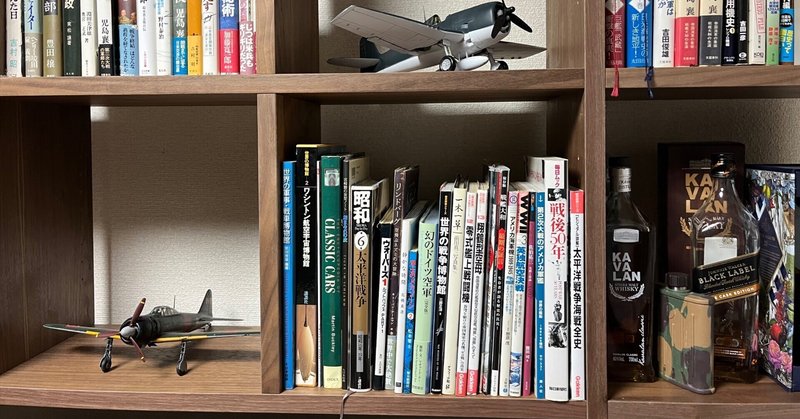
杉田庄一ノート94 「宮崎勇氏が語る杉田庄一」
宮崎勇氏は元三四三空戦闘機搭乗員。大正8年10月広島県呉市に生まれ、父は海軍工廠に勤めていた。丸亀中学校を中退して、昭和11年に6月に佐世保海兵団に入る。最初は水兵として軍艦「磐手」「長良」「熱海」に乗っていた。先輩の勧めもあって飛行機搭乗員の試験を受け、合格して昭和15年から土浦航空隊(戦闘機専修)に入った。内部試験を受けて入る丙種予科練(丙飛)二期生である。搭乗員になった時はすでに22歳だった。丙飛三期の杉田の一年先輩にあたる。同期は68人で、52人が戦死した。
昭和17年二五二空に配属、11月から空母「大鷹」でラバウルに進出し航空戦に参加。昭和18年5月に内地帰還し、二五二空際編成で再び所属して硫黄島作戦に参加する。昭和19年末の三四三空編成時、源田司令に分隊士を命ぜられる。以後、終戦時まで三四三空戦闘301隊で菅野大尉の腹心の部下として若い搭乗員のまとめ役を担う。戦闘301隊のエースである杉田の兄貴分のようなポジションにいた。
宮崎氏の著作「帰ってきた紫電改」の中に「杉田庄一上飛曹の死」という一節があり、杉田の戦死時の状況を知ることができる。
「特攻ルートを開く援護作戦をおこなっていた、この時期の四月十五日、三四三空は、優れたパイロットのなかでも、とくに惜しい人をなくした。
この日は、私たちS301・新撰組が出撃にそなえて鹿屋の飛行場に待機していた。
午後二時五十分ごろ、電探(レーダー)と監視哨からの情報で、
「敵艦載機編隊、佐多岬(鹿児島県)南東十浬、鹿屋へむかう」と入ってきた。
源田司令は、少し近いが放っておく手はないと、「即時発進」を命じ、われわれはエンジンを始動して滑走にかかった。
ところが、敵の動きは意外にすばやく、F6FとF4U二十機が飛行場の南東数浬に現れた。すでに突撃態勢をとっている。われわれの離陸直後に襲われれば、ひとたまりもない。やむなく、司令は、「発進をやめ、避退せよ」と命令した。源田司令としても非常に迷った一瞬だったと思う。
隊の大部分はこの発進中止命令を聞き、了解したのだが、なぜか二機だけ伝わらなかったのか滑走をはじめていた。これに気のついた連中が、祈るような気持ちで二機をみつめた。
先に発進した一機は、離陸直後五十メートルも空中に浮かないところで銃撃され、翼を裏返して滑走路のはずれに消えた。これが杉田庄一上飛曹だった。なんとか逃げようとする、もう一機も撃たれた。宮沢豊美一飛曹である。
海軍航空隊きってのエースパイロットといわれた杉田君は、知る人ぞ知る、十八年四月、ラバウルから前線視察に出た連合艦隊の山本長官機を六機の零戦で護衛していた、その一機である。護衛隊は、襲ってきた十数機の敵機を迎え撃ったがおよばず、山本長官は戦死した。
杉田君は昭和十三年、新潟県の生まれ、農学校を中退して昭和十五年、海軍に志願し、私の翌年(昭和十七年三月)に丙飛三期を卒業した。
杉田君の初戦果は、十七年十二月、ブイン(ラバウル基地があったニューブリテン島の東隣、ブーゲンビル島に設けた前線基地)迎撃戦である。強敵B17爆撃機に単身で突進し、体当たりで相手の右翼を切って撃墜したというから、猛烈な闘魂のパイロットだった。
「二〇四空」「二六三空」「二〇一空」といった前線の戦闘機隊で転戦して、「三四三空」に呼ばれ、その二年余りの空戦歴で個人撃墜をなんと七十機におよぶ、とある。
杉田君を兄のように敬愛していた隊員は多い。」
・・・・以下略。笠井氏と田村氏の思い出が語られる。
宮崎氏は、その日の基地の様子も「二人の遺体」として記している。
「この、杉田上飛曹戦死の際、私も待機線で搭乗して発進を待っていたのだが、『中止命令』をハッキリ聞いてとりやめた。
騒ぎが一段落した夕方、私は杉田、宮沢両隊員の遺体がどうなったか気になって、基地の中を探した。それが、なかなか見つからない。
そこで、通称「ハチコン」、正式には「第八根拠地隊」という鹿屋の地上部隊ーーーこの隊が、外から来た部隊の庶務的な世話などを一手に担当していたので行ってみた。
基地の中心部から少し離れた位置に、この部隊はあった。そこで何か分かるかもしれないと思って一人でいってみたのだが、この隊の裏山を切り抜いたような壕があって、そこに二つの木箱が置いてあるのを偶然みつけた。人の大きさだったのでソッとあけてみると、杉田、宮沢両君の遺体だった。胸にグッとくるものがあり、根拠地隊の隊員に、
『もっと何とかなりませんか。この搭乗員は、われわれにとって大変な人なんだ・・・・』
と、説明して軍医を呼んだ。
すると、代わりに少佐の人が出てきたので、三四三空側からは志賀飛行長(少佐)が来てくれた。
そうすると、今度は相手は中佐が出てきて話し合って、ようやく日が暮れた頃、根拠地隊の軍医課で遺体を安置してくれて、われわれも、ひと安心したのだ。
戦争に戦死はつきものだが、真っ昼間の地上の、私たちの目前で散った凄惨な被害だった。戦争とはいえ、二人が寂しく放っておかれた処置は哀れでならなかった。豪快な杉田君の笑顔と一緒に、この日のことを思い出す。」
宮崎氏は、終戦時には少尉となって帰郷。戦後、航空神経病となって一時は視力が落ちるが回復し、松山市で妻の実家の酒屋を継いだ。2012年、92歳で死去。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
