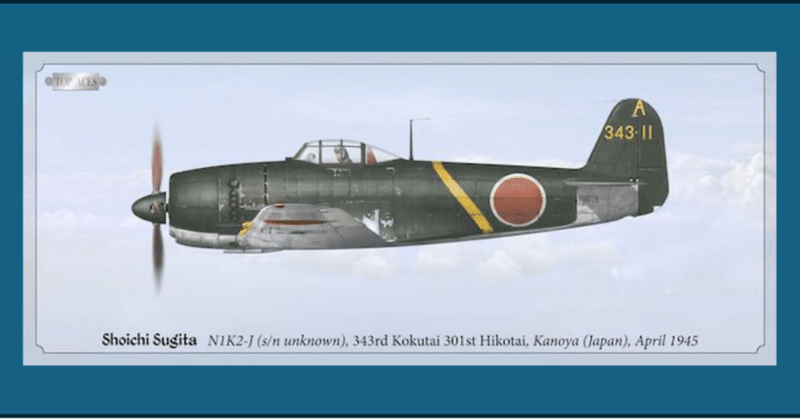
杉田庄一物語その8 第二部「開戦」海兵団入団
少し戻って同年(昭和十五年)六月一日、杉田は舞鶴海兵団に海軍志願兵として入団した。履歴書には「海軍四等航空兵ヲ命ズ」「舞志飛第一四九一号」(操練)「丙種予科練 整備兵ヲ命ズ」と書かれている。
昭和十五年は予科練制度が大きく変わった年で、杉田はおそらく海兵団にいる四ヶ月の在団中に丙種予科練に応募したものと思われる。履歴書をみると杉田は二等兵になるまで所属は整備兵となっている。ただし、一度も整備兵分隊に所属して訓練を受けていないので、もし不適格となったときのために原隊として整備兵に属していたと思われる。
海兵団というのは、拠点となる大きな海軍基地で、新兵教育をおこなう教育機関である。横須賀、呉、佐世保におかれていたが、昭和十四年に京都の舞鶴にもおかれた。舞鶴にはもともと海兵団があったのだが、軍縮条約のために閉団されていたのを復活したという経緯がある。舞鶴海兵団はおもに北陸方面出身者を対象とした。杉田は十月十五日までの約四ヶ月を舞鶴海兵団で過ごしている。
ところで同じく六月に、のちに六空および二〇四空とラバウルで共に戦う中村佳雄も横須賀海兵団に四等機関兵として入団している。中村は、北海道市別の農家の三男で大正十二年生まれ。高等小学校を出てから実家の仕事を手伝っていたが、自立するために海軍機関兵を志願した。海兵団を終えて、戦艦「比叡」の新三等兵になるが、旧三等兵による罰直(しごき)がすさまじく、抜け出したい一心で部内選抜の操縦練習生を受験する。数十倍の難関を潜り抜けて合格し、杉田と同じ丙種予科練三期生になる。ラバウル後は厚木空、そして三〇二空に配属され雷電に乗りB29を撃墜している。最後は、三四三空に異動し戦闘四〇一隊、そして同戦闘七〇一隊で終戦を迎えている。
甲乙丙の飛行教程に差はなかったが、丙飛には兵歴を持っているものがいて、下士官から三等兵までの混成になり、杉田の属した第三期丙種予科練生(丙飛三期)は二百人くらいいて、大部分が三等兵である。三等兵は、海兵団から直接予科練に入っている者たちだ。しかし、前述のようにこれまでの操練選抜者(現場からの選抜者)も中に混じっており年齢差も五歳くらいあった。三等兵曹が二名、数名の一等兵や二等兵もいた。
前年に海兵団入りした杉野計雄(呉海兵団)も機関兵として駆逐艦「黒潮」に配属されたあと、陰湿な制裁体制に嫌気がさし、部内選抜を経て二等兵として丙飛三期に入っている。
杉野計雄とは、この後予科練習生(予科練)、飛行操縦練習生(飛練)、六空と共に過ごすことになるが、詳細は後述する。ミッドウェイ海戦後、空母「大鷹」戦闘機隊、大村空、佐世保空、空母「翔鶴」戦闘機隊、二五三空、六三四空、台中戦闘機隊、最後は博多空教員兼務特攻隊飛行兵曹長として終戦を迎えている。
杉田は海兵団に入団した時に「四等航空兵」であったが、十月十五日に卒団した時には「三等航空兵」を命ぜられ同日予科練に入る。翌十六年四月二十八日に予科練を卒業して操縦練習生になったときに「昭和十六年勅令第六二五号ニ依ッテ海軍三等整備兵トナル」と履歴に書かれている。もし搭乗員不適格となって落とされた時に迎え入れる原隊として、整備科を原隊として所属していたのではないかと推測する。予科練では試験などで一回でも不合格になると原隊に戻されることになっていた。航空兵が不適格なら整備兵になる道を残しておくということだ。
杉田はこのあと十月一日の定期昇格で「二等整備兵」になり、十一月二十九日に大分航空隊の所属になるが、翌十七年三月三十一日に卒業して第六航空隊に所属するまで「二等整備兵」で、同日「配属変更」の命令を受けようやく「二等航空兵」となっている。

話を戻して、杉田は六月一日に海兵団に入団したわけだが、海兵団というのは拠点となる海軍基地で新兵教育をおこなう教育機関である。横須賀、呉、佐世保におかれていたが、戦備拡張政策により昭和十四年に舞鶴にもおかれた。舞鶴にはもともと海兵団があったのだが、軍縮条約のために閉団されていたのを再復活したという経緯がある。舞鶴海兵団はおもに北陸方面出身者を対象としていて、杉田もここに入団した。杉田は六月一日から十月十五日までの約四ヶ月を舞鶴海兵団で過ごしている。
海兵団では海軍水兵としての基礎訓練を受ける。入団するとまず、姓名申告から始まり、カッター訓練や軍歌行進などの新兵教育が行われ、軍隊での集団生活を徹底的に叩き込まれる。
起床ラッパで五時に起き、六時に朝食、八時から午前中の課業、十二時昼食休憩、十三時から十六時まで午後の課業、十六時四十五分から夕食、十九時から温習(自習)、二十一時三十分消灯。その間、分刻みで細かな日課があり、班長が細かく指導する。全ての作業は他の班と競争であり、負けると連帯責任となり全員が罰直をくらうことになる。
多くの海兵団経験者が思い出としてあげるのがカッター訓練と罰直である。カッターは軍艦に装備される木製の短艇で長さ九メートル、中央部の幅二・四五メートル、排水量一・五トンで十二人の漕ぎ手が固い板の上に座って太いオールで水をかく。尻の皮はさけてしまっているのに冷たい塩水をあびる。訓練期間中は治るひまがない。オールも太いだけでなく握りのところには鉛が埋められており、扱うのは大変だった。全体重をかけてぶら下がるようにして引き、引き終わるとすばやく突き出さねばならない。冬でもすぐに汗まみれになる厳しい訓練だった。
罰直はその場で殴り身体に覚えさせるということで海軍兵学校でも行われていたが、原則は拳固やビンタであった。殴った方も痛くなるため、そうそう殴るわけにはいかないのだが、下士官から兵への罰直はバッター(樫の木で作った特製バット)を用いることが多かった。打ちどころが悪くて死亡したり、恐怖のために自殺したりする者もいた。海兵団後に水兵として所属艦に赴任すると、罰直はさらにエスカレートしていくことが多く、「鬼の◯◯、地獄の◯◯」(◯には軍艦名が入る)など、凄惨さを競う言葉も生まれていて、海軍の悪しき伝統となっていた。
この理不尽な罰直から逃れるために操縦練習生をめざした者も多い。ただ、実際に練習生になるためにはかなりの倍率をくぐり抜けなければならず、受験に失敗して原隊に戻ると先輩からのさらに陰惨な罰直が待っていることになった。
ところで、私(石野)の父も杉田の二年遅れで海軍航空兵を志願し、直江津町から舞鶴海兵団に入っている。高等小学校を出てから頚城鉄道の浦川原営業所で機関車の整備をしていた前歴をもっていたため航空整備兵として採用された。私が幼い頃、いっしょに風呂に入るといつも海兵団の頃のトンデモ話を聞かせてくれた。もっとしっかり聞いておけばよかったと今になって思う次第。
<参考>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
