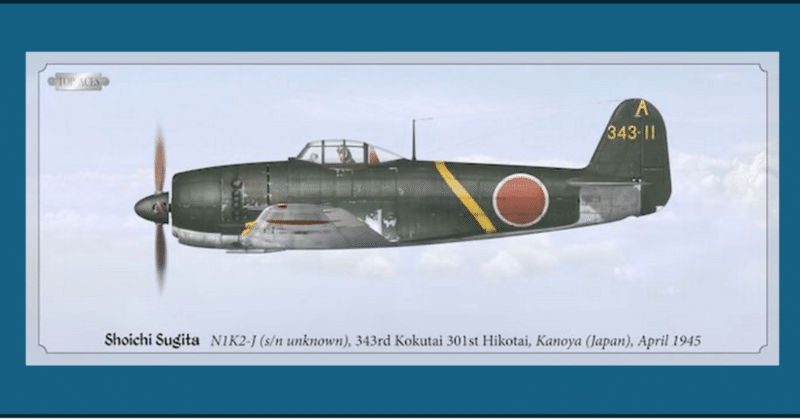
杉田庄一物語その9 第二部「開戦」予科練入隊
昭和十五年十月十五日、杉田は舞鶴海兵団を終え三等航空兵として霞ヶ浦の鹿島航空隊(土浦航空隊派遣)に着隊する。すぐに分隊編成があり、操縦、電信、偵察と分かれ、操縦分隊はそのまま丙種予科練生予定者となる。第三期丙種予科練生(丙飛三期)が新編成されたのだが、この時点ではあくまで「予定者」であり正式の訓練生とはなっていなかった。
入隊予定者が全員揃ったところで学科試験がなされ、不合格者数名はすぐに原隊に帰される。五十八人中七番という成績が履歴原票に残されている。その後、身体検査と適性検査が数日かけて行われ、ここでも不適格者は原隊に戻される。
連日の検査や試験をパスした者は正式に土浦航空隊に入隊となり、丙種予科練習生となる。杉田の履歴書には、「鹿島航空隊着隊」と記され「丙種飛行予科練修生(操縦専修)予定者」「土浦航空隊に派遣」と補足されている。履歴書では十六年二月二十八日に「土浦航空隊入隊」となっており、書類上のことと思うが所属などが後付けで動いたようだ。
同期入隊の杉野の『撃墜王の素顔』(杉野計雄、光人社)によると操練入隊予定者が数日かけて集まってきて分隊を編成したことが記されている。当時の様子を杉野は次のように書いている。
「数日が過ぎた頃、予定者がぞくぞくと入隊し、 二百人くらい集まって来た。その中に三等兵曹二名と数名の一等兵と二等兵がいたが、ほとんどは三等兵であった。一週間後には全員が入隊したので、分隊編成がはじまり、操縦、電信、偵察と分かれていった。
また、この時操縦練習生(操練)は丙飛、少年航空兵が乙飛、中学校卒業で募集したのが甲飛と呼称が変わったことを知った。
予定者全員が集まったところで学科試験があって、数名の不合格者が出て呼び出され、原隊に帰された。その後、身体検査と適性検査が精密検査と称して数日実施され、不適格となってまた何名かが帰されていった。聞きしに劣らぬ首切りであるのに戦々恐々とする日が続いた。せっかく親しくなった友が何人か不合格になり、退隊するのを見、無情さに明日は我が身ではなかろうかと、不安になることもあった。
不合格となり去り行くものが、ツェッペリン飛行船の船体格納庫を記念にみたいと言うので、いっしょに見に行くことにした。そのとき説明してくれた整備科の下士官が、親切な説明のなか、この格納庫の扉が、一反歩の大きさと言ったのを不思議といまも覚えている。あの首になって去った友もおそらく戦死したのではなかろうかとよく思った。しかし、二枚の扉か四枚の扉かは忘れている。
連日の検査や試験を運よくパスした私たちは、阿彌ヶ原台地を下りて、湖のほとりに新設された土浦航空隊に入隊した。隊門を入ると、湖にいたる大通りがある。右は練兵場で左に庁舎があって、その庁舎裏に鉄筋コンクリート二階の大きな隊舎があり、続いて木造二階建ての校舎が連立する大きな学校の姿であった。
私たち丙飛三期は初めての同時採用方式に変わり、隔月少数クラスから数ヶ月ごとの採用制に変更されて多人数クラスになった。三期丙飛は、飛練も四月と六月に分かれ十七期及び十八期飛練になった。私は十七期の早いクラスであった」
杉田も杉野と同じ飛行練習生(飛練)十七期になり、ペアとして訓練にはげむことになるのだが、詳細は後述する。
昭和十六年一月、東条陸相が『戦陣訓』を示達する。全陸軍の将兵に向けた戦場での心得であるが、その中に「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すことなかれ」という一文があった。「捕虜になるくらいなら、潔く自決せよ」という意味である。もともとは陸軍の兵に向けたものではあったが、そのスローガンは陸海軍のみならず全国民の精神的な拠り所になってしまう。
『戦陣訓』にしばられて、多くの優秀な搭乗員が、粘り強く生き抜くよりも潔く自死や自爆を選んでしまうことにつながった。その結果、ただでさえ少ない搭乗員がますます逼迫することになり、作戦遂行にも支障をきたし、戦略的な失敗につながってしまう。また、敵国捕虜に対しても、「捕虜なのに生きていて恥ずかしくないか」という思いから、ジュネーブ条約を無視した扱いがしばしば起きてしまい、人権問題として戦後裁かれることになったのだ。
法律でもないのに、法律以上に人間をしばる言葉に恐ろしさを感じてしまう。
<参考>
〜〜 ただいま、書籍化にむけてクラウドファンデイングを実施中! 〜〜
クラウドファンディングのページ
QRコードから支援のページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

