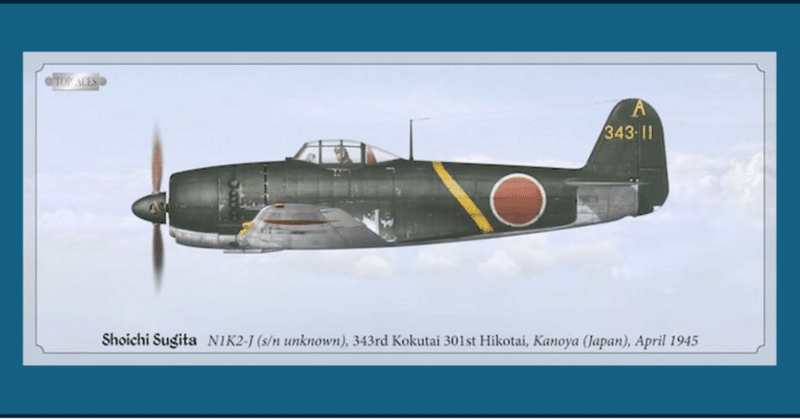
杉田庄一物語その35 第四部「ガダルカナル島攻防戦」補給戦になったガダルカナル島の戦い
ガダルカナル島の戦線では、日本軍米軍ともに激しい戦いをしていたが、両軍とも戦うための補給が間に合わなかった。前述のように、島には食料となる動物はトカゲやネズミくらいしかなく、短期で決着をつけるつもりであった一木支隊は上陸後すぐに食糧などの入った背嚢遺棄命令が出されていた。米軍海兵隊も補給が来ず、日本軍が退却時に残していった食糧・物資を確保し、一日一食で耐えていた。
連絡を受けた米軍の補給部隊は駆逐艦による輸送隊を編成し物資補給を行っていた。日本軍も補給船では安全に運行できず、駆逐艦によるドラム缶での補給を行うことにした。速度が劣り対空戦闘力のない輸送船では、航空機による攻撃に耐えられないためである。日本軍ではこれを「鼠輸送」とか「ドラム缶輸送」と呼んでいた。
このドラム缶による輸送は、空のドラム缶を苛性ソーダで洗浄したあと、中に半分ほど米麦を入れて封をし、ロープでつないで駆逐艦から海中に投げ入れ、陸上からはロープで引き寄せるという方法がとられた。予備実験は、トラック停泊中の戦艦「大和」で行われ、海面に浮かせるためには米麦はドラム缶半分くらい入れて浮かせればいいという結果を得ていた。
補給を確保するため、期せずして日米双方が駆逐艦を用いることになったが、補給の際、艦船は航空機による攻撃には弱いことが証明されることになった。制空権を得ることがこの戦いの優劣の決めてであることを日米双方ともに戦いの中で痛感する。
駆逐艦による輸送は明るいうちでは攻撃をうける可能性が大きいため、日が暮れてから着くような工夫をしなければならない。しかし、そのことが零戦による上空哨戒を日没まで引っ張ることになってしまう。零戦には夜間着陸する能力がなく、ブカ基地にも照明装置がなかった。そのため午後の遅い時間を担当する四直は、薄暗くなるギリギリまで護衛した後、駆逐艦の近くに着水する作戦が考え出された。無謀な計画と飛行隊長の宮野大尉は反対するが決行されることになった。
十月十一日、船団上空哨戒任務を四直に分けて行うことになった。編成は、一直第一小隊一番機田上健之進中尉(海兵六十八)、二番機杉田庄一二飛(丙三)、三番機渡辺清三郎二飛(丙三)、二直第一小隊一番機相根勇一飛曹長(乙五)、二番機川上繁登一飛(丙三)、三番機平野重夫二飛(丙三)、三直第一小隊一番機川真田勝敏中尉(海兵六十七)、二番機大正谷宗市三飛曹(乙九)、三番機加藤正男二飛(丙三)、第二小隊一番機森崎武少尉(予備七)、二番機島川正明一飛(操五十三)、三番機中野智弌一飛(丙三)。第三小隊一番機岡崎正喜一飛曹(操三十八)、二番機竹田彌一飛(丙二)、三番機加藤好一郎二飛(丙三)。四直第一小隊一番機宫野善次郎大尉(海兵六十五)、二番機岡本重造一飛曹(操三十一)、三番機尾関行治一飛曹(操三十二)、第二小隊一番機久芳一人中尉(海兵六十八)、二番機鈴木軍治一飛曹(乙七)、三番機倉内隆二飛曹(操四十五)。
この日の編成は宮野が決めている。( )内は出身種別と所属期を表しているが、三直や四直には敵機来襲の予想が大となるため実戦体験者を多く編成に加えたシフトであることがわかる。とくに四直の帰投はどうしても日没後になってしまい、基地到着三十分前ごろからは夜間飛行になってしまう。四直の搭乗員は経験豊かなベテランのみで編成された。宮野自身の名前も最も危険な四直小隊長に書いてあった。一直二番機には杉田の名前がある。
現地上空での哨戒は午前七時五十五分から午後四時五十分までとされた。一直が出発したのは五時前であった。ブカからラバウルまで三時間近くかけて飛び、現地上空を二時間哨戒したあと再び三時間かけて洋上飛行をおこなって帰ってくるという過酷な任務であった。
しかし、この計画は甘かった。ぎりぎりまで哨戒任務についた四直は、やはり夜間での帰投になった。上空四千メートルから真っ暗な闇の中を着水することは、さすがのベテランでも不可能であった。海面付近の高度判定ができず、うねりに対応できないで海面に激突したり、それを避けようと失速落下したりで、六名の搭乗員のうち二名が即死、二名が重傷の被害を出した。宮野も不時着水した時に照準器に額をぶつけて怪我を負っている。また、午前中の二直も悪天候の中の帰途で、相根飛曹長、川上一飛、平野二飛の三名が行方不明になっていた。
輸送隊の直衛任務初日でベテランを含めた操縦者を七名(戦死者五名、重傷者二名)と零戦九機が失われることになった。しかも、その日敵機は一機も現れずじまいであった。当然であるが、飛行兵たちは無謀な計画をたてた上層部に対して腹立たしさと抱き、士気が低下した。
『島川正明空戦記録』(島川正明、光人社)の中で、島川は次のように書いている。
「ガダルカナル島ちかくで日没まで哨戒し、ブカまで帰投することは、当時の単座機にとっては、かりに充分な夜設準備がなされていたとしても無理だった。たとえ三百マイル以上の夜間飛行を充分こなし得るパイロットがいたとしても、雲一つない月明ならともかく、戦闘後、しかも変わり身の早いソロモンの気象条件下にあっては、やはり不可能ではなかろうか。」
島川はさらに付け加えている。
「言うまでもなく、艦上機にはフロートはついていないのだ。このような作戦を立て命令を出したのは、いったいだれだったのか。私はこれらの先輩上官の死を考えるとき、この人たちはさぞ口惜しかったであろうと、断腸の思いを禁じ得なかった。この時期、もっとも貴重なパイロットをむざむざ戦死させるとは・・・・」
また、『指揮官空戦記』(小福田皓文、光人社)の中で小福田も次のように記している。
「戦争というものの無駄と空しさを考えさせられる一日であった。とくに、この日戦死した五名のパイロットたちは、内地から有力な増強戦力としてやってきて、まだ数日しかたっていない、大事な戦力であり、頼りとした部下たちである。数少ない士官パイロットの久保中尉や、至宝的な歴戦の勇士相良兵曹長、また下士官パイロット最古参のべテラン岡本一等飛行兵曹などがふくまれていた。
私は、その悲報を耳にしたとき、彼らのこの悲運を悲しむとともに、前途に横たわる戦況のきびしさと、わが部隊の運命を予告されたような暗い気持に沈んだ。」小福田自身はデング熱でこの時寝込んでいた。
ラバウル進出時の事故と無理な船団護衛任務での事故とで、ラバウルに進出してから一週間あまりで十二機と八人の搭乗員が失われることになった。幕舎の指揮所では森田司令が椅子に身を沈めて泣いていた。無理を承知で困難な任務を命じた自分を許せないようであった。ラバウルに来てすぐにこのような顛末で、今後の戦闘の厳しさと不吉な予感を隊の皆が感ずることになった。
十月十二日、深夜でのガダルカナル島への揚陸任務を終えた水上機母艦「日進」と「千歳」の哨戒任務を六空で行った。上空に友軍機を認めた両艦の乗組員は帽子を振って感謝を伝えたと記録されている。五時三十分に一直六機がブカ基地を発進し、十機時三十五分帰着。二直六機は、七時三十分に発進し、午後一時四十五分に帰着。三直三機は十一時四十五分に発進、フアウロ島付近でおそらく天候不良により引き返している。四直は中止になった。杉田は編成に入っていない。
十二日以降三十一日まで戦闘行動調書に杉田の名前は出てこない。「履歴原表」に十月十二日デング熱と書かれている。小福田をはじめ六空搭乗員数名がこの頃、デング熱にやられて編成から外れている。『指揮官空戦記』(小福田皓文、光人社)に次のように記載されている。
「ブカ島に移ってまもなく、私はデング熱にかかった。南方の戦場にいる以上、いずれはマラリアか、デングにやられるとは思っていた。デング熱は、かねて軍医官や経験者に聞いていたとおり、毎日四十度近い高熱が、周期的に襲ってきて、うなされる。デングの特徴は、その高熱と、腰の痛みといわれていたが、私の場合も御多分にもれず、日夜ベッドの上でうなっていた。食欲がなく、毎日三食、パパイヤだけで生きていた。」
デング熱は蚊を媒介とするウィルス感染症で、七日間の潜伏期間の後、三十八度から四十度近い発熱と激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹が出る。発熱は二日から十日ほど続き、その後解熱する。
ソロモン海域の戦線では日本軍、米軍ともデング熱やマラリヤ、赤痢に悩まされた。マラリア蚊に刺されると内地の蚊と比較にならない痛痒さで、刺された場所がすぐ化膿し、三日熱性マラリアになる。熱帯地方なのに悪寒が酷く、毛布にくるまっていても寒さを訴えるほどになる。ピークのときは四十度近くの高熱が数時間続く。注射で一時的に抑えても、すぐにぶり返す。このような症状が一日おきに二週間ほど続くとようやく平熱にもどる。しかし、体力がおちるとすぐに再発した。
また、猛烈な暑さだけでなく連日雨が続くため湿気がひどく、おびただしい数の蠅がいた。話をしているときに口の中にまで入り込むほどで、食事のときは真っ黒に群がる蠅を追い払ってから食物を口にしなければならなかった。そのため感染症にかかる将兵が多く出て、医薬品の補給が重要になった。搭乗員には優先的に医薬品が補給されたが、ガダルカナル島戦線の兵達の多くは感染症と飢えで亡くなっている。米軍は殺虫剤DDTを使って駆除に努めていた。
ガダルカナル島への出動が日常的になり、六空のブイン基地への移転が急がれた。ラバウルで一週間過ごした六空本隊の整備員及び基地員は、搭乗員たちに先行して「りおん丸」でブインに向かった。相楽もその中にいた。
ブインに着いた日は雨で陸揚げができず、翌日も雨。基地員の木川、兵器員の相楽、酒井、坂村らが雨の空を眺めていたら小型機が飛んできた。「おや零戦がはやくも到着したか」と思っていたらグラマンだった。さらに翌々日には米軍のPBY飛行艇がやってきて魚雷を落としていった。ジャングルのどこかで敵の偵察員が見張っているらしく、今更ながら最前線であることを自覚させられた。
ブインは予想以上にひどいところだった。ジャングルの中の飛行場は建設中で、滑走路脇には大木の切り株がごろごろしており、すぐにぬかるむ滑走路には砕石を敷き詰めることになった。しかし、それも間に合わず、鉄板をならべた。日本製の鉄板もあれば米軍のものもあり、とりあえず敷き詰めたという具合だ。作業はもっぱらクワにシャベルにモッコだった。土木作業はなかなかはかどらず、ようやく完成したときに小福田飛行隊長が試験的に滑走路に降りて使用に耐えるかどうかを試した。テストパイロットだった小福田にとっても難しい滑走路だった。もちろん上手に機体を操って降りている。
<参考>
〜〜 ただいま、書籍化にむけてクラウドファンデイングを実施中! 〜〜
クラウドファンディングのページ
QRコードから支援のページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

