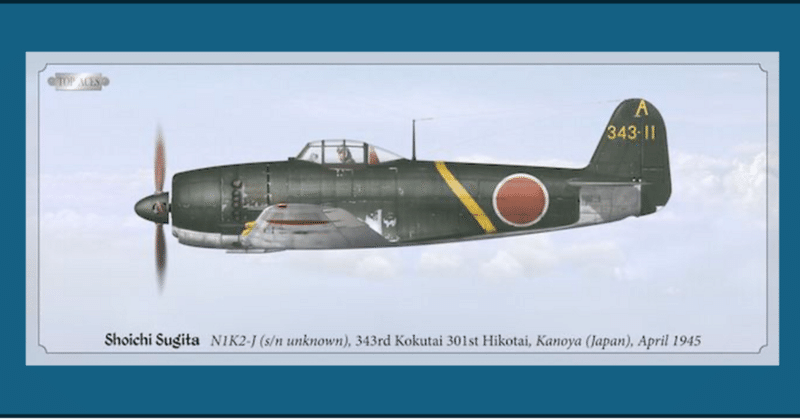
杉田庄一物語その5 第一部「小蒲生田」安塚農学校
昭和十四年(1939)四月、杉田は高等小学校を卒業し、安塚農学校(現新潟県立高田高等学校安塚分校)に入学する。当時の若者にとって無所属は許されなかった。青年学校令が出されていて、高等小学校を卒業すると実業学校もしくは青年学校に属さねばならなかったのだ。
自宅から十キロメートルほど離れた農学校まで毎日歩いて通った。この農学校は、明治四十四年に旧安塚高等小学校の校舎を使用し東頸城郡立農業学校として開校した郡内にある唯一の中等教育施設である。大正五年には郡制廃止に伴い新潟県立農学校となっている。
杉田は、安塚農学校在学中に海軍を、それも戦闘機搭乗員を目指し願書を出している。航空兵として搭乗員になるには中学校卒業程度で受験できる甲種予科練と高等小学校卒で受験できる乙種予科練があった。さらに少年志願兵になってからでも内部受験で航空兵になる道があった。なんとしてでも自立したかった杉田は海軍志願兵に応募した。
海軍航空兵として搭乗員になるには中学校を卒業して受験できる予科練と少年志願兵になってから航空兵になる道があった。高等小学校卒であれば、乙種予科練生になるか、いったん水兵になってから内部受験で操縦練習生になる手順を踏まねばならない。
たとえ航空兵になってからも搭乗員と整備員の二つのコースがあり、搭乗員になるのは難関だった。さらに搭乗員のコースから戦闘機、艦上爆撃機、艦上攻撃機、偵察機などに分かれて行く。そして希望よりも適性が優先された。あこがれの戦闘機搭乗員への道は果てしなく遠い。杉田は、まっしぐらに進むだけだと言い聞かせて勉学に励んだ。
同年五月、ノモンハン付近で満洲国とモンゴル人民共和国との国境をめぐる小競り合いが日本とソビエト連邦(ソ連)との軍事衝突にまで発展する(ノモンハン事変)。事変とはいいながらも実際はソ連軍との真っ向勝負の戦争だった。欧州では数年前から戦争の機運が高まっており、軍事的緊張はすぐに世界中に広まった。日本海軍でも航空隊の増強が急務になり、航空下士官兵の採用増加が図られることになる。
同年八月、ドイツとソ連がポーランド問題悪化を理由として不可侵条約を結ぶ。ソ連を敵国としてドイツと防共協定で手を結んでいた日本にとって、晴天の霹靂であった。平沼首相は、「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を生じた」と声明を発表し総辞職する。
九月一日、ドイツ軍がポーランド領内に侵攻した。英国とフランスが相互援助条約に基づいて九月三日にドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が始まった。続いて、九月十七日、ソ連軍がポーランドに侵攻する。米国も危機感を募らせており、空母の大量建艦と海軍機一万五千機の整備を含む海軍大増強スターク案が成立した。世界の緊張は一気に高まり、日中戦争も激化する。米国議会は、「国防強化促進法」を成立させ、あらゆる兵器・軍需品・部品・機械・原料などの輸出を制限する。日本のこれ以上の南進を食い止める意図だった。
日本の石油備蓄量は昭和十四年当時で六百七十二万キロリットル。全需要量の七割前後を米国からの輸入に頼っていた。これは平時で二年弱、戦時では一年半分と見込まれていた。米国が石油の輸出を止めれば、海軍は船も航空機も動かすことができなくなる。米国は、輸出制限で日本を封じ込める作戦に出た。
しかし、この輸出制限は逆に作用した。海軍部内の強硬論者(艦隊派)は、まだ石油備蓄があるうちに米国をたたいて、輸出禁止を緩和させねばと考えるようになっていく。石油がなくて困るのは軍隊だけではない。燃料の高騰は国民生活を圧迫した。米国憎しという心情が日本国民全体に広まっていく。
また、ヨーロッパでのドイツ軍の動きは日本国民にも強く影響を与えることになった。ドイツの勢いを借りるべしという世論が次第に強くなり、その声を味方につけて陸軍は「日独伊防共協定」を推し進めようとする。海軍部内でも「艦隊派」は同調し、これを押しとどめようとする米内光政、山本五十六、井上成美の「海軍穏健派トリオ」は右翼の壮士たちから命をねらわれる危険を感じながら過ごすことになる。日独伊の軍事同盟を求める輩が連日海軍省に押しかけて、米内や山本、井上に対して「国賊!腰抜け!イヌ!」と暴言を浴びせた。とりわけ山本は始終刺客に狙われていて、金庫に遺書を用意するまでになっていた。
少し前の八月下旬、阿部信行陸軍大将が平沼内閣の後継首班として信任された。阿部は首相になるにあたって、「英米と協調する外交方針をとること」という天皇からの直接の指示を受けている。阿部首相は、天皇の意を汲み、欧州大戦不介入、中立維持を明らかにする。英米友好の方に舵をとろうとしたのだ。
この動きを見て米内は軍事参議官に退き、山本を連合艦隊司令長官に転出させた。これ以上山本を中央に置くと生命の危機となることを案じての米内の人事であった。井上は、支那方面艦隊参謀長兼第三艦隊参謀長に転出した。
この年の秋、杉田は海軍志願兵の願書を出した。海軍志願兵の試験は十月に行われる。甲種予科練ほどではないが、高等小学校卒だけで受けられるため、志願者は多い。試験は三日間である。学科試験は、まず数学から実施されるが、次の国語の試験の間に採点され、未達のものは落とされそのまま帰らされる。学科の次は、身体検査、そして運動能力試験。懸垂や肺活量の検査などを経て、口頭試問が最後にある。
まだ、戦時のような切迫した状況ではなく、同郷から数十名受けて最後まで残るのはほんの数名であった。合格した後も身辺調査などをされて採用証書が渡されるのはさらに絞られる。徴兵されて陸軍へ行くよりも志願兵として十代で海軍へ行くのが当時の若者のあこがれだった。合格していても採用通知が来るまでは安心していられなかった。翌年三月初旬になってはじめて採用通知が来る。そして、出頭は三ヶ月後の指定日と通知される。内定通知をもらった杉田は、採用証書を眺めながら海兵団へ入団するまでの日々を待ち遠しく過ごしたに違いない。
安塚農学校(現新潟県立高田高校安塚分校)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
