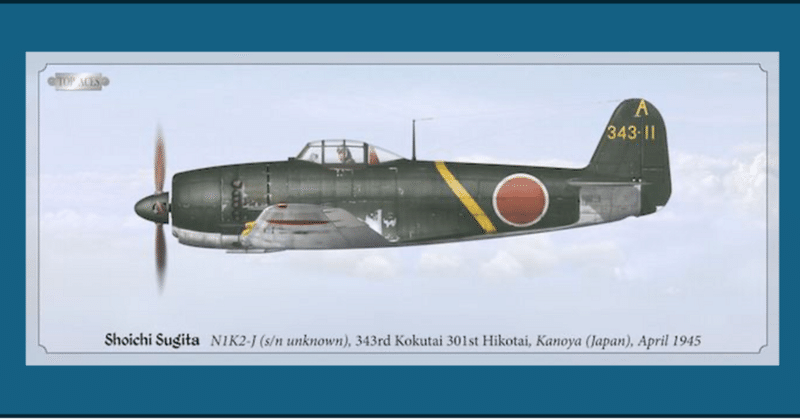
杉田庄一物語その10 第二部「開戦」予科練の一日
杉田は予科練でどのように過ごしたのだろうか。朝日新聞社が昭和十九年に刊行したガイドブック『海軍少年飛行兵』を参考にまとめてみる(海軍では陸上でも艦内を想定した生活用語が使われている)。この『海軍少年飛行兵』は、予科練を目指す者に対するガイドブックで、志願の方法から予科練生の生活まで詳しく丁寧に書かれている。
・朝六時起床(夏は五時半)。十五分前に伝令員が「総員起こし十五分前、吊床当番配置につけ!」と触れ回る。吊床当番は、戦友たちの眠りをさまさぬよう細心の注意をもって自分の吊床を手早くくくり、吊床格納所の位置について、皆の目覚めるのを待つ。五分前に「総員起こし五分前」の拡声器の放送が入る。このとき、吊床(ハンモック)の中ですでにみな寝たふりをして身構えている。
・六時、起床ラッパが鳴り、終わると同時に吊床をフックから外し、二十秒で丸太状にたたんで紐で結縛し、ネッチング(収納場所)に格納する。
・格納し終わると洗面と用便をすまし、着替えてから兵舎の横に整列する。順次、隊伍を組んで練兵場まで駆け足。どんな短い距離をゆくのでも隊内の動作はすべて駆け足でなければならない。分隊ごとに人員点呼のあとは朝礼と海軍体操、号令演習、冬ならば寒稽古。当直将校による訓話、宮城遥拝、五か条斉唱。朝礼のときは第一種軍装。そのあとは白い事業服に着替えて日中はそれで過ごし、夜の温習(兵舎内での自習時間)前にふたたび制服に着替えなおし、脱いだ事業服は「衣嚢」という大きな袋の中に畳んで収納する。
・起床三十分後に甲板掃除、七時十五分からは週番練習生による課業報告、食事五分前に食卓につく。食事ラッパが鳴ると気を付けの号令で礼を行ってから朝食。食事は班ごとに長テーブルに向かい合い、班付の教員が上座に座って一緒に食べる。
・八時、ラッパ「君が代」とともに軍艦旗掲揚、その後は講堂で温習、八時五十分に課業整列があって副長の訓示や分隊長からの報告。分隊毎に所定の教室に向かう。授業科目は普通学と軍事学に分かれていて、普通学は民間の教師が教える。乙種と丙種は、数学、物理、化学、国語、漢文、地理、歴史、作文となる。甲種は、中学三年時修了の基礎学力があるとされ数学と物理だけになる。軍事学では、砲術、航海術、水雷術、運用術、通信術、航空術で武官が教える。この他に、状況判断、部下統率の方法、陸戦教練が課せられている。モールス信号や手旗信号が一番苦しいとされた。
・午前は、三〜四時限の課業(学習)。十二時に昼食。昼食が一番ボリュームがあった。一日四千カロリー摂取が標準とされた。昼食には班長から戦争の状況や戦訓などの話がある。食後の休憩は銃器の手入れなどを行う。
・午後は、二時限の課業があり、十四時四十五分からは別科目として武技、相撲、水泳。籠球(バスケットボール)、排球(バレーボール)、闘球(ラグビー)などもあった。とくに闘球が奨励され、大学チームとの対外試合もよく行われた。体育の時間が終わると「課業止め」の号令がかかり夕食準備。
・十六時四十五分に夕食。食後は酒保(売店)、バス(風呂)、洗濯などの自由時間。
・十八時三十分に温習。温習終了後は練習生同士が向かい合って「五省」を唱える
「ひとつ、至誠に悖(もと)るなかりしか」
「ひとつ、言行に恥ずるなかりしか」
「ひとつ、気力に缺(かく)るなかりしか」
「ひとつ、努力に憾(うら)みなかりしか」
「ひとつ、無精に亘るなかりしか」
・二十時五十分に吊床降ろし。デッキの掃除をしてから二十一時には巡検、就寝。
甲種、乙種、丙種と多少の違いはあるが、概ね同じようなスケジュールだった。
丙種予科練習生となって半年くらいの速成教育で十六年四月二十八日に、杉田は卒業となった。それでもこれ以後の予科練生の超速成教育に比べればまだ余裕があったといえる。
三月、「土浦航空隊」を卒業し「筑波航空隊」に操縦練習生として入隊することになる。予科練ではまだ操縦訓練はなく、学科と身体訓練を詰め込んだだけである。いよいよ操縦訓練に入ることになる。
さて、2023年10月に茨城県稲敷郡阿見町にある予科練平和記念館を訪ねた。陸上自衛隊土浦駐屯地に面して建てられており、隣接している駐屯地内の遊就館(予科練記念館)にそのまま歩いていけるようになっている。途中に自衛隊の衛兵が立っていて敬礼してくれるのがうれしい。私が行った時は女子隊員だったが、その機敏な動きにおもわず「ご苦労様です」と声がけをしてしまった。



多くの写真を眺めてあるいていると厳粛な気持ちになりました。
〜〜 ただいま、書籍化にむけてクラウドファンデイングを実施中! 〜〜
クラウドファンディングのページ
QRコードから支援のページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

