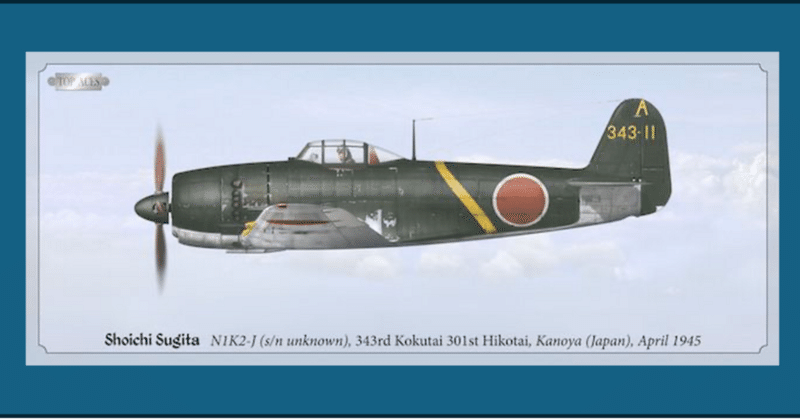
杉田庄一物語その13 第二部「開戦」延長教育(実用機操縦課程)
昭和十六年十一月二十九日、杉田は筑波海軍航空隊での操縦練習課程を修了し、延長教育(実用機操縦課程)に進級する。戦闘機専従の杉田は、杉野や谷水と共に大分海軍航空隊(大分空)に同日付で配属命令が下される。開戦へ向けて慌ただしい軍の動きの中で筑波基地から大分基地まで転勤する。
同日は重臣会議が開催され、米英との開戦について最終審議が行われている。もう引き返すことのできない逼迫した状況となっていた。しかしまだ、太平洋上にあって山本五十六は外交交渉に最後ののぞみをかけていた。
筑波から大分までは三日間の行程である。東京まで出て東海道線に乗り換え名古屋までで一日目の夜を迎える。そのまま列車の中で夜を過ごし、京都で朝を迎える。神戸を過ぎ、瀬戸内沿岸は連合艦隊を見せないため窓はヨロイ戸が下ろされる。広島では憲兵が乗り込んできて目を光らせる。下関で関門連絡船に乗り九州へ渡る。大分には翌々日の朝に到着する。その間、民間人と乗り合わせることになるが、操縦練習生のマークが誇らしく、疲れていても姿勢は崩す者はいなかった。
大分航空隊(大分空)は海軍唯一の戦闘機訓練専門の練習航空隊である。丙飛三期だけでなく、海兵六十七期、甲飛五期、乙飛十期の各戦闘機搭乗員と海兵六十七期艦上攻撃機搭乗員が同時期に大分空で訓練を行っていた。杉田はここで四ヶ月の延長教育を受けることになる。
『本田稔空戦記』(本田稔、光人社)の中に大分空での訓練の様子が次のように描かれている。本田は杉田の一年前に戦闘機専修訓練を受けている。
「すべての訓練は『総員起こし』から始まった。一日の始まりに気合いが入っていないと終日間が抜けたような気分になる。従って霞ヶ浦では一分三十秒以内、谷田部では一分で上げた釣り床を、ここではさらに記録を更新し二十秒以内で納めるように要求され、まさに神技に近い動作である。いざ出撃に際して一刻を争うことはわかるが、それにしても人間というものは訓練を重ねればどんなことでも可能だ、ということを身をもって経験させられ、『あらゆる行動に不可能はない』ということをこれほど身近に感じ会得できたことはなかった。 そしてこの自信がこれから。先展開されるあらゆる猛訓練に耐え得る精神的なバックボーンになるのである。
朝、総員起こしと同時に飛行場へ飛んで行き、まず格納庫の扉をあける。それから朝礼、海軍体操、再び格納庫へ舞い戻り飛行機を出し、列線に並べる。搭乗割りを見て自分に振り当てられた機体の点検を行なう。すべて早駆けであり、これまた競争である。 それから朝食。 朝食が終わると飛行服に着替え飛行場へ早駆け、そして飛行訓練が始まる。毎日これらの繰り返しであったが、その日、その日が充実した精神と緊張の連続であった。 これほど充実した日課、寸分の暇もない猛訓練はまさに一日が娑婆の十日にも一ヶ月にも相当するような感じさえした。」
この段階まで進むと、階級もあがり自信にみなぎっている様子がうかがえる。常に失敗=落第、原隊に復帰という恐怖からものがれら、あと一息という安心感もただよっていた。
「まずは九十戦による慣熟飛行である。 中練の赤とんぼに比べるとさすが実用機だけあってスピードも出る、加速も良い、だいいちエンジンの音が違う。運動性もよく上昇率もよい。 いかにも実用機らしく操縦桿をちょっと動かしただけで敏感に曲がり、中練のようにフワリ、フワリと浮いているという感じはなく動作が敏捷である。ただそれだけの違いで操作上ことにむずかしいこともなかった。違うといえば、速度が速いだけに着陸時の操作の勝手が違うくらいのことで、それもむしろ機体が重いだけに引き起こしが楽でありドンピシャリ定位置に接地でき痛快であった。」
「中練連時代のように上空で編隊を組むのと違って、ここでは初めから三機編隊で離着陸しなければならない。でこぼこの芝生の滑走路を翼をゆさぶりながら離陸していく様は、 まだ足のしっかりしていない雛鳥が一斉に走り出すようなものであった」
「この九十戦にはものの四、五時間も乗ったら次は九十五戦による慣熟飛行があり、続いて空対射撃の訓練に入った。飛行前に搭載弾数及び弾の色を確認する。(弾に色がつけてあり標的の吹流しに命中するとその色がつき、誰の弾が命中したのかがわかるようになっている。一番機は教官、二番機、三番機は我々練習生という三機編隊で離陸する。 南国特有の灼熱の太陽がギラギラと照りつける別府湾上空に出てそのまま南下し、佐賀関の製錬所の煙突を右にみて、別府方面から来る曳敵機を待つ。高度千五百メートル、一番機の展開の合図に従って単縦陣隊形をとり、九十度接敵法にて一、二、三の順に等間隔で曳敵機に向かう」(原文ママ)
本田は九十五戦での射撃訓練で近づき過ぎて吹き流しをかぶってしまい、あやうく墜落しかけ分隊長から鉄拳を喰らうが、「無事着陸させたことは大変立派である。沈着冷静な態度、大いによろしい」と褒められ、処罰は受けなかった。
当時訓練に使われていた飛行機は、中島三式艦上戦闘機、中島九〇式艦上戦闘機、中島九五式艦上戦闘機、三菱九六式艦上戦闘機である。九六戦が現役で前線配備されていた時代で、最新鋭の零戦はまだ練習航空隊には配置されていなかった。もっぱら九五艦戦で空戦や夜間飛行、特殊飛行などの訓練が行われ、仕上げとして九六戦が使われ、零戦はまだ配備されていなかった。
先に述べた十二試艦戦が皇紀二千六百年(1940)に制式採用されため零式艦上戦闘機となった。採用年末尾の0をとって零式(れいしき)とつけられた。「ゼロセン」と呼ばれるようになったのは戦後である。三千キロメートルの航続距離、時速五百三十キロメートルを越す速度、二十ミリ機関銃(陸軍は機関砲と呼んでいた)、極限まで軽くして得た格闘性能とどれをとっても当時の世界水準を超えていた。
特に「剛性低下方式」と名付けられた「たわみ」を利用した操縦索は零戦の運動性の良さを引き出す特徴となった。低速のときは大きく舵が動き、高速時はたわみによって舵の効きが小さくなるという優れたアイデアだった。
しかし、航続距離と格闘性能を高めるため徹底した重量削減をおこなったため、強度に弱点があり急降下速度に制限を行わなければならなかった。また、しぼりにしぼった空力デザインは完成された美しさをもつものの二千馬力エンジンへの換装する余地をもってなかった。さらに、性能を重視したため工作を難しくし生産性が劣ってしまった。米軍機が生産性を優先したのと対照的である。
実戦部隊への配備要求は強く、試作機段階から日中戦争の前線に配備され活躍した。三菱だけでなく中島でも生産にあたることになり、終戦の年に紫電改が登場するまで最優先で生産されることになるが、この時期の練習航空隊での配備はとうてい望めなかった。
さて、大分航空隊では開戦前のこの時期までは、実戦経験だけでなく技量優秀な教員を揃えることができていた。また、戦闘訓練についても日米開戦の気運が高まっており、かなり実戦を意識した激しいものになっていた。訓練期間はやや短縮されはしたが、開戦後に比べれば時間をかけて行う余裕もあった。射撃訓練もスイッチを同調させたカメラによって行っている。
『撃墜王の素顔』(杉野計雄、光人社)の中で射撃訓練について、次のように記述されている。
「射撃は機体に固定して取り付けた機関銃(砲)で、照準器にうまく敵機が入るように狙って発射すれば命中するわけである。だが、実際にはそう簡単ではない。銃口と目標の距離や彼我の飛行機の辷り、風、射角などに加えて気象条件などの要素も正確に合致しないと、飛行中の射弾は命中しない。だから、銃口を目標に近づけて射撃しない限り全弾命中はないのである。
射撃の名人は、いかに安全に敵に接近できるかで決まる。それはわかっていても、簡単にできるものではない。経験を積み重ねてこそ極意がつかめるのである。
練習航空隊の射撃標的は、長さ五メートルの麻布製の袋型の吹き流しを使用したが、実施部隊では三メールの長さの小型になる。しかし、練習生の場合は、長さも太さも大きい曳的でも、なかなか命中弾を得ることが困難であった。
射撃は最初、数回は実弾ではなく写真射撃が実施され、実弾射撃に進む。弾丸と同じ早さでシャッターが落ちて的が写るので、後でフィルムを現像し、スクリーンに映写すると、射距離、角度、軸線などが判定され、それによって教官が一人一人に注意指導を行なう。
注意されたからといって、技量未熟の練習生が、『はい、それでは』と簡単に修正できるものではない。少しでも進歩があれば、まあまあといえる。」
杉野は、温習の時間に教室に回ってきた当直の吉田教員に「吹き流しにぶつかる気持ちで接近し、撃ってみよ」とアドバイスを受ける。翌日の射撃訓練で、がまんにがまんをかさねて吹き流しに接近してカメラ銃の発射ボタンを押すが、五メートルの吹き流しをかわしきれずにプロペラでかんでしまう。前述の本田と同じケースである。これは叱られると思いながら分隊長に報告すると、「体当たりは自分も命がなくならないのでやらないことだよ」と諭される。杉野の経験では、このような失敗は通常は罰直対象になるのだが、笑いながら諭されたと語っている。教員にもまだ余裕があった。
二年後になると様相が変わる。昭和十八年に徳島航空隊で「延長教育」(実用機操縦課程)を受けた笠井智一は戦場帰りの教官から散々な目に遭う。『最後の紫電改パイロット』(笠井智一、光人社)に次のような記述がある。
「徳島航空隊に到着してすぐに総員整列がかかり、号令台に牧幸男飛行長(海兵六十五期)が駆け上がった。牧大尉はラバウルの空中戦で顔を火傷していて、手も足も不自由な様子だったが、歴戦の勇士らしく見るからに精悍な感じがした。
彼は、『ここでは貴様たちを叩いて、叩いて鍛え上げる。ここを出るまでに、一人残らず鷲の目のような戦闘機操縦員に仕上げる。そのつもりでこい』と訓示した。
戦後、牧大尉の海兵仲間が『ものすごくいい人』と彼を褒めていたが、われわれ練習生にとってこれほど怖い隊長は経験がなかった。怖いというのは見た目のことではない。徳島ではバッターのない日はなく、罰直では飛行場を何度も走らされた。(中略)火の出るような訓練、そして制裁ばかり・・・。」
(原文ママ、牧大尉はミッドウェイ海戦で負傷)
短い期間で厳しい戦場で生き抜ける精神力を身に付けさせようという親心から出たものと思われるが、まだ中学校を出たばかりの少年たちにとっては厳しさよりも恐怖が印象に残ったのだろう。笠井は、戦後になってもこのときのことは思い出すと怖いと述べている。
同じく笠井は戦闘機による練習過程を次のように書いている。
「最初に固定脚・プロペラ二枚の九六式戦闘機で離着陸訓練を二、三回行ない、その後すぐに零戦での訓練がはじまった。まずは複座の零戦『十七試練戦』で基本操作と操縦間隔を覚え、二、三回乗ったらいきなり『明日から単独で乗れ』と言われた。しかし、最初は零戦はなかなか一人で操縦するのは難しい。赤とんぼ(九三式中練)は簡単に離着陸できるが、零戦はスロットルを前に押して全開にし、スピードが上がって離陸したら風防を閉め、すぐに引込脚を収め、フラップを収めなくてはならない。着陸のときは脚を出し、フラップを出さないといけない。いろいろとやることがあって忙しい。この離着陸の操作をわずかな期間で覚えなくてはならなかった。
離着陸訓練では『誘導コース』という決まった航路(離陸、第一〜四旋回、着陸)を順番に飛行した。慣れるまでは操作にもたつく。もたつく間に高度はどんどん上がる。距離は余分に飛んでしまう。飛行機を降りたら教員に殴られる。重い飛行靴のまま、飛行場のまわりを全力疾走で走らされる。走っている途中で何人も落伍する。あまりにも厳しい連日の訓練に、そのまま海に突っ込んで死んだらどんなに楽か、と考えるまでに精神的に追い込まれた。しかし、いま思えば本来数ヶ月かけてやる延長教育を短期間で仕上げるためには教えるほうも隊長以下、みな命がけだったはずだ。」
杉田の時代とは異なり、笠井の時には延長教育はたった二十日間で終了することになる。そして、そのまま戦場に出されたのだ。その後の笠井の動静については後述する。
<引用・参考文献>
〜〜 ただいま、書籍化にむけてクラウドファンデイングを実施中! 〜〜
クラウドファンディングのページ
QRコードから支援のページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

