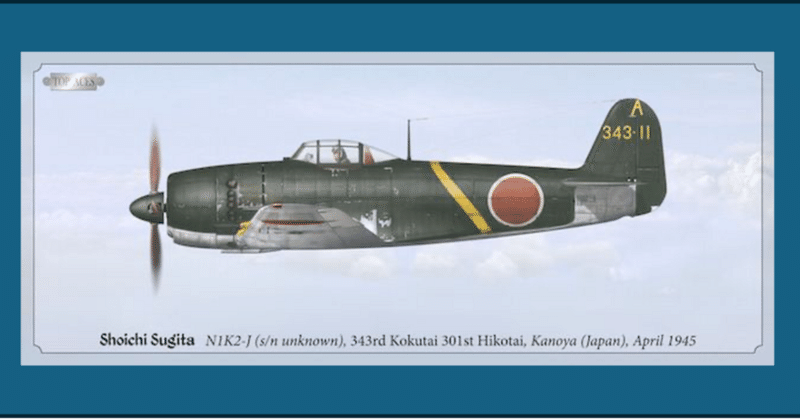
杉田庄一物語その11 第二部「開戦」飛行操縦専修練習生
昭和十六年があけた。ヨーロッパではドイツ軍が戦線を拡大し、その勢いは止まるところを知らなかった。そのニュースは全国の映画館で強制的に流され、知らず知らずに国民は戦争へ意識を高めていくことになる。四月になると「日ソ中立条約」が調印される。有効期間は五年間で、「①日ソ間の平和友好関係の維持と領土保全、②第三国からの軍事行動があった場合でも日ソ間は中立を維持すること」を目的とした。この条約によってソ連の脅威を取り除くことができ、南進政策に専念できると松岡洋右外相は主張した。しかし、ソ連にとってもドイツとの戦いに専念できる都合の良い条約でしかなかった。事実、ドイツの敗戦と共に一方的に破棄されてしまうことになる。
日米間の緊張も増してきていた。四月十六日、緊張を解決するために正式な日米交渉が開始する。米国は「日米国交打開策」を示してきた。ルーズベルト大統領と近衛首相のサミットにより日米間の懸案事項を調整するというものだ。米国側がこの案に好意的であることを得て、近衛首相と陸軍上層部もこの案を進めようと考えていた。最終決定は訪欧中の松岡外相が帰国するのを待って行うことになった。しかし、「独伊との三国同盟の締結」、さらに「日ソ中立条約」という大きな成果をもって帰国した松岡は、真逆の方向に向かうこの案に「愚劣にもほどがある」と激怒し、強硬な内容の代替案を作成する。松岡は交渉を進めていた野村大使にこの代替案をハル国務長官に渡すよう指示する。三十一日、「松岡代替案」を渡されたハル長官はこれまでの交渉を覆す強硬な内容に憤慨する。一時は雪解けに向かうかと思われた日米間の緊張は再び高まることになる。
この年の秋、第三次近衛内閣が東条内閣に変わったころに、山本五十六を連合艦隊司令長官から中央に戻そうという運動があった。しかし、東条内閣の海軍大臣嶋田繁太郎が承知しなかった。山本は通常であれば満期になって連合艦隊司令長官を退くはずだったが、戦争を見越してか、あるいはここにきて戦争反対を運動されては困ると思ってか、人事凍結となる。
十六年四月二十八日、杉田は予科練を卒業する。同日、第十七期飛行操縦専修練習生(飛練十七期)として筑波海軍航空隊に入隊する。六月一日に「昭和十六年勅令第六二五号ニ依ッテ海軍三等整備兵トナル」と履歴に書かれている。前述のように、落とされた時に迎え入れる原隊として整備科に所属していたのではないかと推測する。予科練、飛練を通して、練習生は試験などで一回でも不合格になると原隊に戻されることになっていた。
筑波海軍航空隊は、霞ヶ浦飛行場の予備飛行場を使っていた霞ヶ浦友部分遣隊が、大量の搭乗員養成が必要となったため昭和十五年に独立した練習航空隊である。飛練十七期には前述のように杉野計雄もいて、中島隆三等航空兵曹のもとで共に学ぶペアになる。日本海軍ではペアという言葉を、「複数の搭乗員仲間」というような意味で使っていた。
このとき中島教員に学んだペアの六名は、杉野計雄二等機関兵(戦闘機専修)、谷水竹雄三等水兵(戦闘機専修)、杉田庄一三等水兵(戦闘機専修)、加藤正男三等水兵(戦闘機専修)、篠原某三等機関兵(艦爆専修)、大内某三等水兵(中攻専修)である。半年間操縦訓練をみっちりと仕込まれたあと、それぞれ専修コースに向かうことになった。杉野だけは機関兵としての経験があったので二等兵であるが、あとの練習生はみな三等兵である。落伍すると原隊にもどされるため練習生のうちは、原隊所属がついてまわる。
この隊での教育は初級操縦士の養成であり、複葉の九十三式中間練習機を使って操縦訓練を行った。木製骨組みに一部金属の複葉機で、胴体も翼も布張りであった。目立つように赤黄色に塗り分けされていたので「赤トンボ」と呼称されていた。


前の席に練習生、後ろの席に教員が乗る。前後席に連動する操縦装置が付いており、練習生がミスをすると後席の教員から棒で頭を叩かれ、操縦をとられてしまう。杉野計雄(かずお)は初めて単独飛行をした時のことを著書「撃墜王の素顔」の中で次のように書いている。
「第一回目のソロの日、私は一番に出発することになった。南よりの微風で、絶好のソロ日和であった。
同乗飛行が終わり、列線に入ると、後席の教員が
『エンジン止めるな、単独飛行に出発』
と言って降りて行き、同僚が着けてくれる尾部の小さな識別の吹き流しを確認して地上滑走に入った。
何度も深呼吸し、心を落ち着けて飛び上がっていった。
『やったぞ!』
と思い切り叫んだら、ずいぶん落ち着いた。飛行を終わって教員に報告し、
『御注意、お願いします』
と言ったら、一言、
『上出来、言うことなし』
だった」
中島教員の指導は実戦に則した優れた指導であったようで、この六人のペアから杉田、杉野、谷水という三人のエース搭乗員を輩出している。
前述したように杉野はこの六人の中ではすでに兵歴もあり、階級も上であった。海軍では親しい間柄は、名前の一部をとって呼び合っていた。杉田と杉野は呼び名が二人とも「杉さん」であったが、年齢が三歳ちがうので二人の間では、「杉!」「杉さん」であった。杉野も自身が駆逐艦乗組員時代に厳しい制裁を受けたことから部下を決してなぐなかったことを誇りにしている。終戦時には飛行時間千九百九十四時間、撃墜数三十二機を記録している。(『日本海軍航空隊のエース』による)
谷水竹雄は、大正八年生まれで三重県の出身。昭和十八年、空母「翔鶴」飛行隊員となり、ラバウル航空戦に参加する。その後、台南空に転勤、教員兼務で迎撃と哨戒任務についた。昭和十九年十一月三日、P-51マスタングによって撃墜されるが落下傘降下で脱出生還している。昭和二十年、二〇三空に転勤し、終戦まで戦闘を続けた。谷水も終戦時飛行時間千四百二十五時間、撃墜三十二機と記録されている。(『日本海軍航空隊のエース』による、十八機という説もある)
基本的な操縦技術だけでなく、空戦を意識した特殊飛行などの訓練もこの「赤トンボ」で行っていた。「赤トンボ」は手を離せば自然に正しい空中姿勢をとってくれるという安定した飛行を行えるのだが、空中戦のような特殊飛行を行う技量を養うにはかえって安定性が邪魔になる。それでも練習生たちは、教員からの指導によってさまざまな特殊飛行の訓練を重ねていった。
その頃、隣の分隊に羽切松雄飛曹長が着任した。羽切は中国戦線での零戦による重慶攻撃などですでに有名になっていた戦闘機搭乗員である。前線から戻ったばかりの羽切は眼光鋭く、他の教員とは全く違っていたという。羽切にあこがれて杉野は戦闘機専修を希望した。杉田もあるいは影響されたかもしれない。のちにラバウルで、杉田は羽切編隊の二番機として数多く飛ぶことになる。
この時期に徹底的に飛行操縦を身に付けることができたのは幸いだった。翌年からは次第に訓練時間が少なくなり、操縦技術が未熟なまま戦場に出されるようになる。戦争末期にはとにかく離陸と着陸ができればという速成教育になり、その多くはそのまま特別攻撃隊(特攻隊)に編成されていくことになる。杉田はそれでも時間をかけての飛行訓練を受けられた最後の世代だった。
<参考>
〜〜 ただいま、書籍化にむけてクラウドファンデイングを実施中! 〜〜
クラウドファンディングのページ
QRコードから支援のページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

