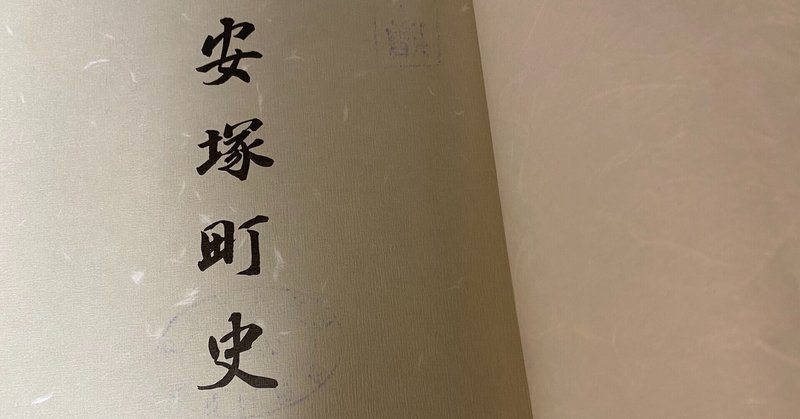
杉田庄一ノート2:昭和初期〜安塚町史から
杉田庄一は、旧安塚村の生まれである。昭和30年に安塚村は分村し、町制に移行した。杉田の生まれた中保倉地区は月影地区とともに浦川原村となる。その後、上越市に合併するわけだが、このような経緯で現在は上越市浦川原区になっているのだが、杉田のことを書いた資料の多くは(旧安塚村)と記されている。そのため、杉田に関する問い合わせは安塚区の総合事務所に行くことが多い。先日、安塚区の総合事務所に尋ねた折、毎年のように何人かから問い合わせがあるという。しかし、問い合わせに出た職員で杉田のことを知る人は少ない。隣村なのだから仕方がない。出身地で知らないのは不勉強だと怒られることもあるそうだ。
さて、安塚町史を調べて見た。この町史は、平成16年に編纂されており、浦川原村が分村で分離されたあとのものなので当然ながら杉田のことは記されていない。しかし、杉田が過ごした昭和初期から昭和10年代の生活を知ることができる。
昭和4年10月24日のアメリカ株式市況大暴落(いわゆる暗黒の木曜日)による世界大恐慌は、日本の山奥の旧安塚村にも押し寄せた。農産物の価格の暴落により、今と比較にならないほど農業収入に依存度が高かった純農村は大不況となる。前年の半値くらいになった米価のため、納税・肥料代・農機具の支払いで飯米まで売らねばならず、生活は困窮を極めたと記されている。電気事業会社あるけれど利用者が少なくラジオ普及に努めたと記されている。その後も不況は続き、昭和9年は凶作となる。また、昭和初期は大雪が続き、不況に追い討ちをかけるような苦難の連続であったと書かれている。杉田は、大雪のときも1日も休まず学校に通った。
満州事変から日中戦争が起こる過程で戦費がふくらみ、国民生活全体が逼迫していた中、戦争遂行のための非常事態体制が敷かれることになる。昭和12年「国民精神総動員中央連盟」が中央で結成され、新潟県でも「国民精神総動員実行委員会」が開催され、戦時体制が推進された。昭和13年4月1日には国家総動員法が制定される。各地の工場は兵器の増産につとめ、生活物資が不足し、自由販売から配給制になる。昭和14年には物価統制令によって、日曜雑貨の価格まで統制されるようになる。
杉田が子供時代を過ごした日本は暗雲が常に立ち込めていたといえよう。今、我々はコロナ禍で生活に窮屈さを感じているが、そんなもんではなかったと思われる。私の両親も同じ時期に子供時代を過ごしている。モノを大切に、質素でつつましい生活は子供時代に築かれたのだろうな。
昭和14年、杉田は高等小学校を卒業すると安塚農学校に入学する。この農学校は、東頸城郡全村長が請願書を出すなど、強い設置要請運動によって明治44年に旧安塚高等小学校の校舎を使用して東頸城郡立農業学校として開校した。郡内にある唯一の中等教育施設であった。大正5年に、郡制廃止に伴い新潟県立農学校となる。杉田は、昭和14年に入学し、その年に退学して海兵団に入る。他の資料などを読むと当時の海軍少年兵への志願は前年末頃に行われ、合格者はおって通知となり半年後の8月に招集されたようである。最終合格するまで選抜が繰り返されるため、原籍をもちながらテストを受けるのが通例だったと思われる。杉田は、海軍に入るのをいまかいまかと待ちながら農学校に通っていたではなかろうか。安塚農学校は戦後に新潟県立農業高等学校になる。昭和24年には松代、松之山、保倉、牧の各村に分校をもつ新潟県立安塚高等学校となる。
興味深い記録として、すこし時代が違うが大正期の体格の記述がある。徴兵検査にかかる検査だと思われるが、大正三年度から八年度にかけての壮丁の平均身長は5尺一寸六分六厘(156.6cm)、平均体重は一三貫七八四匁(51.7kg)とある。杉田は身長が170cmくらいだったという記録がある。兄と慕った菅野直隊長が160cmくらいだったので、当時としては身長が高かった方だろう。今年一月に亡くなった笠井智一氏(杉田の直属の部下だった)は身長180cm近くあったというから大男になる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
