
座談会:ゴール設定の違いが難しさ 「情報植物学」という新たな分野への挑戦
※情報処理 Vol.62 No.12 特集「植物と情報処理」より先行公開
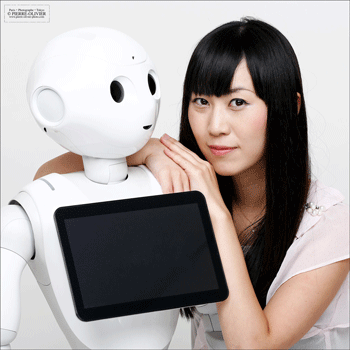
執筆:太田智美
参加:中島敬二(奈良先端科学技術大学院大学)・稲見昌彦(東京大学)・上田貴志(基礎生物学研究所)・植田美那子(東北大学)・近藤洋平(自然科学研究機構)・内海ゆづ子(大阪府立大学)・太田智美
植物学と情報学を融合した「新学術領域」をめぐる座談会が,7月15日にオンラインで開催された.この新学術領域は,植物学と情報学の融合を通じて新しい学術領域を創造し,両分野を発展させることを目指して2年前に発足.研究代表者に,奈良先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科の中島敬二教授,研究分担者には,東京大学・先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授,基礎生物学研究所・細胞動態研究部門上田貴志教授らが名を連ねており,文部科学省の科研費で研究活動を行っているという.
本座談会には,中島教授,稲見教授,上田教授のほか,同研究分担者である東北大学大学院・生命科学研究科の植田美那子教授と自然科学研究機構・生命創成探究センターの近藤洋平助教,大阪府立大学・大学院工学研究科の内海ゆづ子講師が参画した.

「植物計算機」や「指先が顕微鏡になる装置」
このプロジェクトでは,どのようなことを実現しようと考えているのか,具体的な研究成果を見るのが分かりやすいと思うので最初に触れておこうと思う.
同プロジェクトでは,これまでに多くのブレインストーミングを行い数多くのアイディアを出してきたという.その中から,「植物計算機」や「指先が顕微鏡になる装置」の話を聞いた.
「植物計算機」とは,同プロジェクトが主催する融合研究コンペティションで,大学院生のチームが発案したもの.詳細は非公開とのことだが,植物の情報システムをリアルな媒体に移した提案だという.「開発期間1年」というコンペティションの採択条件のため,残念ながら実現には至らなかったが,5年ほどあれば実現できるであろう興味深い提案だったと教授らは口々に話す.
「指先が顕微鏡になる装置」については,すでに複数のメディアでも取り上げられているが,指先に装着した顕微鏡カメラが拡大画像をディスプレイに映し出し,同時に触覚を提示する装置だ.開発は東京大学の研究チームによって行われたが,実はきっかけはこのプロジェクトの構想段階での雑談で,それをきっかけに稲見教授と檜山特任准教授がひらめいたのだという.「指先が顕微鏡になる装置」は筆者も実際に触れたことがあるが,ひとことで表すならば「触れる顕微鏡」といったところだろうか.植物をなぞると,映し出された葉脈などを見ながらポコポコと指で辿ることができる.
何をしようとしているのか
そもそもなぜ植物学者たちは情報学者と組み,情報学者たちは植物学者と組み「新学術領域」を創るのか.それは生物学者が感じる限界と,情報学の異分野への関心の高さに関係があるようだ.最終的なゴールとして両者が求めることは,それぞれ違う.
植物学者のゴールは「情報を使って植物を知る」ことだ.中島教授は「植物の成長のおおまかな原理は,ほぼ分かってしまった.しかし,1つ1つの細胞の変化がどのように統合されて植物の器官の形や向きが変わるのかまでを知るには,今の方法論では分からない.そのためには,ブレイクスルーが必要」と話す.
たとえば,最新の顕微鏡イメージングでは,超高解像度で4次元のデータを得ることができるという.しかし,その中から興味のある部分のデータだけを取り出して,定量的に解析するのは人間の能力だけではほぼ不可能.一昔前のデータ量なら自分のPCを使って手作業で解析できたが,生物の仕組みの真髄を探るにはより大きなデータを扱わなければ意味がないし,部分と全体の正確な対応付けが必要だという.
同じく植物学者である上田教授は,次のように話す.「顕微鏡データに捉えられてはいるけれど,研究者が認知できていないことがあるのではないか.(人間の)認知能力の範囲外にある現象を,技術を使って認知のダイナミックレンジの中に入れてあげるということをやると,今まで見逃していたようなことも分かるようになるのではないか.たとえば,基礎科学の画像や配列情報やそのゆらぎの情報,階層の違う複数の次元にまたがるようなデータを人間が理解できる形に変換してくれるのが情報学だと考えている」
生物学者は情報学者に,「データに潜む未知現象の発見を加速する仕組みの設計」を期待しているようだ.そして,生物学研究の方法論を「新しく」したいという.
植物学者と情報学者の「情報」の定義
そもそも,「情報」の定義に立ち戻りたい.植物学者が意味する「情報」と,情報学者が意味する「情報」で解釈は同じなのか,それとも異なるのか.
植物学者がイメージする「情報」
「植物が『情報処理をする』というと,たとえば外の情報(環境やストレス,虫に食べられるなど)や,細胞同士で『おまえはこの細胞になれ,おれはこっちの細胞になる』というように,細胞同士で情報のやりとりをするケースなどをイメージする.力学的な刺激や光などの刺激を受容体が受け取って,それを植物内で分子情報として伝え,最終的にはどの遺伝子を活性化させるか,どういうふうに成長を変えていくか,といった出力を行う.そういうときに「情報処理」「情報伝達」といった言葉を使う」(上田教授)
「生物にはホメオスタシス,つまり生体恒常性という基本的なシステムがある.情報のフィードバックが最も効いているシステム.それから,シグナルトランスダクションという生物学の少し懐かしい言葉がある.生体内のタンパク質や遺伝子が段階的に「情報」を伝えて最後に形や生理状態を変化させるという概念だが,ネットワーク状の膨大な経路を統合的に扱うシステム生物学が台頭している現代では,あまり使わなくなった」(中島教授)
情報学者がイメージする情報
「日本語の『情報』という言葉が,今のような意味で使われるようになったのは戦後のこと.そういうことを考えれば,情報という概念自体が新しい.それまでは軍事用語として使われていたという側面もある.昔は,陸軍中野学校などの『諜報』に近い意味も含まれており,『電信を使って情報を伝える』という意味とは限らなかった.戦後になり,アメリカ合衆国の数学者であるノーバート・ウィーナー(Norbert Wiener)がサイバネティックスを提唱したとき,フィードバックの信号の性質に興味を持ったのがその後クロード・シャノン(Claude Elwood Shannon)により提唱された情報理論と並ぶ源流の1つではないか.かつては,エネルギーと情報の区別が明確ではなかった」(稲見教授)
「情報を定義する上で『ものごとが起こせる』というのは大事なポイント.近年『情報熱力学』の生物への応用が注目を集めており,バクテリアの生化学的フィードバック系の性能や分子モータの制御の限界について,物理学の立場から議論できるようになってきた.しかし,植物のような複雑なシステムについてはまだまだこれから」(近藤助教)
なぜコンピュータは熱くなるのか
「コンピュータはどうしてこんなに熱くなるのか不思議だ」ーーこう話すのは,植物学者の中島教授だ.そしてその理由を次のように語る.「なぜ不思議なのかというと,コンピュータというのは基本的に,回路に電気を通しているだけだから.一方,ゆっくりだからという理由もあるかもしれないが,植物は熱を出さずにちゃんと情報処理をしている.水を吸い上げること1つとっても,自分自身のエネルギーを使わずに,体中に水を運ぶ.とても省エネルギーなシステムに感じる.そのあたり,コンピュータもできるだけ少ないエネルギーで情報処理をできないものか.たとえば,自由エネルギーの方向性に従って情報を処理する仕組みが実現できれば」(中島教授)
そんな中島教授に対し,稲見教授は答える.「たとえば,情報学の世界では量子コンピュータや,物理リザバーコンピューティングなどが注目されている.またDNAや粘菌を情報処理に用いる試みもあり,これらは自然計算というパラダイムとして認識されている.その中の1つの手段として,植物を使おうという話はたぶんあるのではないか?」(稲見教授)
「エネルギーについて一番考えている植物学者は,光合成研究者かもしれない」と,上田教授は話す.光合成というのは,太陽の光エネルギーを生物が使う化学エネルギーに変換する洗練されたシステム.今,光合成を作動させる基本的なタンパク質の構造はほぼ解かれていて,太陽光と水があればエネルギーが取り出せる,というような技術の研究も進んでいるようだ.
植物学×情報学,どうやって1つの学問として束ねていくか
この2つの分野を1つの学問にするには,いくつか大きなハードルがある.その中で,最も大きな課題が「ゴールが違うこと」であったように思う.
たとえば,工学系に近い情報学の分野では,「問題があって,それを解決する」というのがよくあるやり方だ.しかし,生物学では「新しい発見につなげるために,こういうツールが欲しい」という要請になることが多いという.言い方を変えれば,情報学では「どこまでできたら成功か」が明示されているが,生物学の学術研究との連携では,必ずしも明示されていないため,研究ツールの開発には,より密接なコミュニケーションが必要なのだそうだ.コンピュータビジョンを専門とする内海講師は,「画像から,病気の診断を自動的に行う医用画像処理分野が発展したのは,病気か病気ではないかを見分けるという,明確な目的があったからだ.問題がクリアになっているということが,情報学とコラボレーションするには大きな要素となる」と話す.
もう1つのハードルとして挙げられたのが,「生物学の情報を,情報系のパイプラインに乗せる難しさ」である.「元々定量化されていない(数値になっていない)データをいかに情報処理に乗せやすい形にもっていくかが重要だ」と中島教授は言う.たとえば,画像を見たときに,「いかに数値として表すか」ということが情報学の人からすれば当たり前のことかもしれないが,生物学者にとっては難しいという.「すぐに相談できる人がいるかどうかで,かなり敷居が下がると思う」と話した.
植田教授も,こう続ける.「変換できるものが情報だと考えると,まずパイプラインに乗せるまでが課題.結局,植物を画像解析するといっても,実際にやっているのは植物そのものではなく,顕微鏡で見た画像の解析に過ぎない.そのため,たとえば光合成をがんばっているタンパク質のリアルタイムでの立体構造の変化や電子伝達の様子などを,そのまま質を落とさずに取ってくることができないと,何をやっているかを情報学的に計算し,シミュレーションし,再現して……といった解析のスタートラインに立てない.私たちは,生体内で何が起こっているかを把握したいというのが目的なので,『まず何が起こっているかを把握して数値化する』というのが解析の出発点ということなら,何もできないのではないか,”よく分からないもの”をそのまま数値化してプラットフォームに乗せるには,どのようなブレイクスルーが必要なのか」(植田教授).
植物学と情報学の境界領域の難しさという点について,「農業におけるAI技術の応用などがすでに色々あるだろうと言われそうだが,植物学の基礎研究というのは問題設定がまた違う」と,近藤助教は言う.実際,近藤助教も互いに議論する前には「データさえあれば後は作物の計測などと同じ」と思っていたそうだ.しかし,植物学の基礎研究では植物の形を生み出す分子レベルのメカニズムやそれが進化してきたプロセスなど,思ってもみなかったようなことが問われていた.逆に植物学者も,近年の発展著しい情報学を細かくフォローできているわけではない.そこで植物学者と情報学者の問題意識の共有や情報交換を促進する体制がまずはあるとよい.近藤助教は「はじめから明確な共同研究のテーマがあることはむしろ稀.雑談を交えながらのデータや技術の共有から多くのプロジェクトが始まった」と話した.
情報学の稲見教授は「植物を模倣したロボットの研究例があるが,植物の個体内での情報処理メカニズムや群としての植物の生存戦略から学ぶ新たな情報学の研究領域も生まれるかもしれない.しかも生物の世界は量子的な振舞いまで織り込まれている.いかに互いの分野の面白さを共有するかが重要だ」と締めくくった.
生物学が「新しく」なる日は,新しい分野の誕生日なのかもしれない.
(2021年9月3日受付)
(2021年9月17日note公開)
■太田智美
国立音楽大学卒業.慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科修士課程修了.アイティメディア(株),(株)メルカリを経て,現在同研究科附属メディアデザイン研究所リサーチャー.同博士課程在学中.ロボット「Pepper」と生活をともにしている.ヒトとロボットの音楽ユニット「mirai capsule」結成.
※本特集記事(全体)を入手するには以下の方法がございます.ぜひご利用ください.(特集「植物と情報処理」が掲載される情報処理 Vol.62 No.12は2021年11月15日の発行になりますのでご注意ください)
1)情報処理学会会員になり(http://www.ipsj.or.jp/nyukai.html),電子図書館(https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/)に登録する.
2)fujisan(https://www.fujisan.co.jp/)で購入する.
3)amazon/Kindleで購入する.(https://www.amazon.co.jp/)
