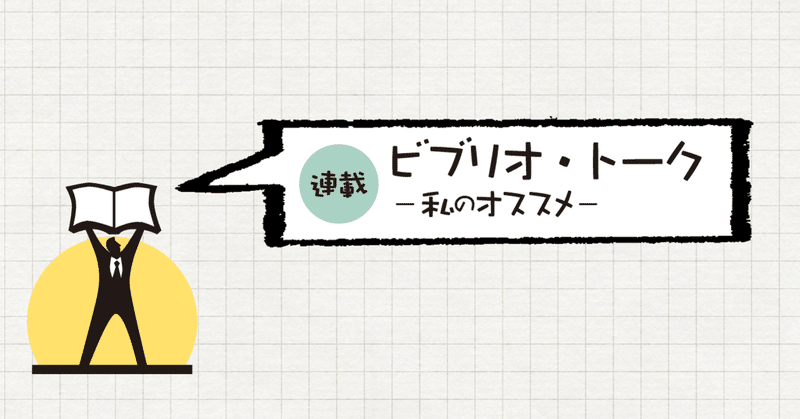
『アポロ13』に学ぶITサービスマネジメント ~映画を観るだけでITILの実践方法がわかる!~
田名部元成 (横浜国立大学)
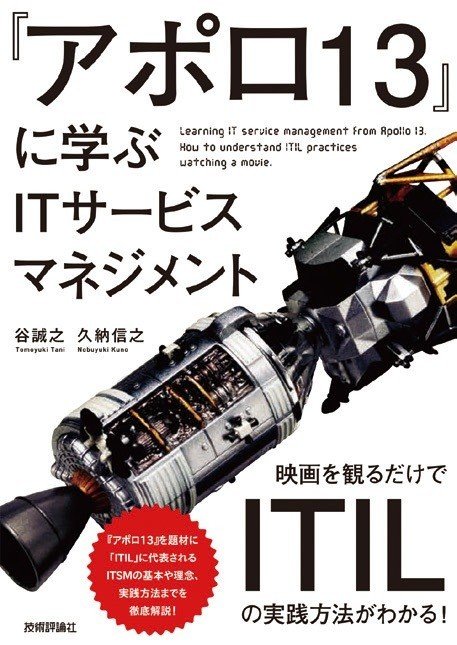
谷 誠之,久納信之 著
技術評論社(2016),256p., 1,980 円+ 税, ISBN:978-4-7741-8492-0
※本記事のPDFは情報処理学会電子図書館に掲載されています。(http://id.nii.ac.jp/1001/00182245/)
IT サービス
私たちの生活は,数多くの無形の助けによって支えられています.たとえば,公共交通機関は移動する際の手段を,また,医療機関は健康や心身機能を維持・回復・増進する手段を提供してくれます.私たちは,これらの手助けを借りて,期待する成果の実現を手にしていきます.顧客が,自力で目的を達成するために所有する材料,機械,道具などの有形のものは製品と呼ばれますが,顧客が,手助けを受けて目的を達成するために借りる手段は,サービスと呼ばれます.
従来,情報技術(IT)は,道具とみなされることが多く,私たちは,IT を所有し,それを活用することで目的を達成しようとしてきました.しかし,近年の流れは,クラウドサービスの考え方に代表されるように,IT をそれが提供するサービスとしてみなす方向へと向かっています.この,IT の「所有から利用へ」というトレンドは,IT ベンダやシステムインテグレータを含む情報サービス産業と情報システムを利用して事業を展開するユーザ企業の両者に対して大きな影響を与えています.その両者にとって,IT が提供するサービス(= IT サービス)によって,いかに顧客に価値を提供するかが重要な課題となっています.
このようなIT サービスを管理する手法は,IT サービスマネジメント(ITSM) と呼ばれます.ITSM の文脈でサービスとは,顧客が特定のコストやリスクを負うことなく,期待する成果を実現することを促進することによって,顧客に価値を提供する手段のことを言います.やや難しい言い方をしましたが,サービスを考える際に重要なことは,何らかの目的を達成したい顧客の存在を認識し,その顧客にとってそれが提供する価値を見極めることです.サービスの価値には,できなかったことをできるようにする,あるいは,従来よりも効果的・効率的にできるようにするという有用性の側面と,有用性を確実に提供するという保証の側面があります.ITSM は,これらの両側面から顧客に価値を提供しつづけられるように,IT サービスを効果的かつ効率的に管理するための体系的な手法のことです.本書は,このITSM をテーマにしています.
ITILをアポロ13で!?
ITSM に関する多くの書籍や文書では,管理手法に関する知識項目は,命題的表現やその事例提示によって説明されます.読んでもなかなか意味が分からなかったり,分かった気になっていてもあとから思い出せなかったりすることが多々あります.ところが本書は,『アポロ13』というストーリーを題材にして,ITSM に関する理念や考え方を豊富な文脈の物語的提示とともに具体的かつ網羅的に紹介していています.
ITSM に対して,広く利用されているアプローチに,ITIL( IT Infrastructure Library) があります.これは,1980 年代に英国政府がまとめた,IT 提供者に求められるサービス機能に関する成功事例集に端を発しています.本書は,ITIL の考え方を,大胆にもアポロ13 号に押し寄せる数々の出来事や事故を題材にして,アポロ計画で行われていたと推測される取り組みをも含めてITSM の視点から説明していきます.一見無謀にも見える斬新なアイディアですが,いざ読んでみると『アポロ13』が史実に基づいて作られたストーリーだということもあって,臨場感を保ちながら読み進めることができます.
現行のITIL では,サービスライフサイクルをサービスストラテジ,サービスデザイン,サービストランジッション,サービスオペレーション,継続的サービス改善のフェーズに分けていますが,これらは,(順序は前後しますが)アポロ13 のストーリーに沿って第2 部から第6 部にわたって無理なくカバーされていて,ITIL の全体像が容易に把握できるよう実にうまく設計されています.
本書は,ITIL の考え方は何となく知っているが,ITSM のツボがよく分からないと感じている人,ITILという言葉が気にはなっていたが,なかなか本格的に学ぶ機会がなかった人,ITSM をすでに導入している組織においてITIL の考え方をより深く学ぶ必要がある人にとって,良いガイドとなるでしょう.
ITSM における新たな気づき
かく言う私は,ITIL の専門家ではありません.勤務先大学の情報基盤センター(いわば,企業での情報システム部門に相当)でITIL プロセスをベースとした IT サービスマネジメントシステム( ITSMS) を運用する取り組みに着手してから,まだ2 年しか経験がない初心者です.本書で述べられている『アポロ13』における事象や事故に対するITSM 的な意味づけは,現場で起こるさまざまなことがらをITSMの視点から再検討する機会をもたらし,結果としてITSM に対する理解を深めることができました.
ITIL の最大の発明は,インシデント管理と問題管理を分離したことであると本書では紹介されていますが,それほど深く考えていなかった過去の事案が,まさに,これに該当するものでした.インシデント管理とは,ユーザや顧客がやりたい「事業」を,サービスを用いて実現することができない,または,できなくなるかもしれない状態(=インシデント)を,いち早く取り除いてサービス品質を通常の状態に戻し,ユーザや顧客の事業を再開させることを目的としたプロセスのことを言います.また,問題管理とは,インシデントの根本原因を究明し,再発を防止して,サービス品質とユーザ満足度を一定の水準に保つプロセスのことを言います.
実は,この「迅速な現状復帰」と「インシデントの原因究明と発生防止」という目的は,しばしば対立するのです.たとえば,原因究明のためにインシデント状態の保全が必要となる場合,あるいは,迅速な現状復帰方法が確立されているがインシデントが頻発する場合などがあります.しかし,インシデントに対応するための,目的が相反する異なるプロセスの存在が明示的になることによって,インシデントをサービス提供者のより上位のマネジメント上の問題として捉えることが可能となり,その視点からどちらのプロセスを優先させるかを決定できるようになります.
本書は,ITSM を実践する人にとっても,さまざまな出来事に対するサービスマネジメント的感受性を高めることに寄与することでしょう.ITSM に多少なりとも接点や関心がある方は,ぜひこの新しいスタイルの本を手に取って,ITSM の世界を覗いてみてください.
(「情報処理」2017年7月号掲載)
■田名部元成(正会員)
横浜国立大学国際社会科学研究院教授,情報基盤センター長.博士(工学).専門は情報システム学.横浜国立大学情報基盤センターにおけるISO/IEC 20000 に基づくITSMS の運用を主導.
連載「ビブリオ・トーク」が1冊の書籍になった『IT研究者のひらめき本棚 ビブリオ・トーク:私のオススメ』も発売中です(2017年2月号まで掲載)。https://www.kindaikagaku.co.jp/science/kd0548.htm
