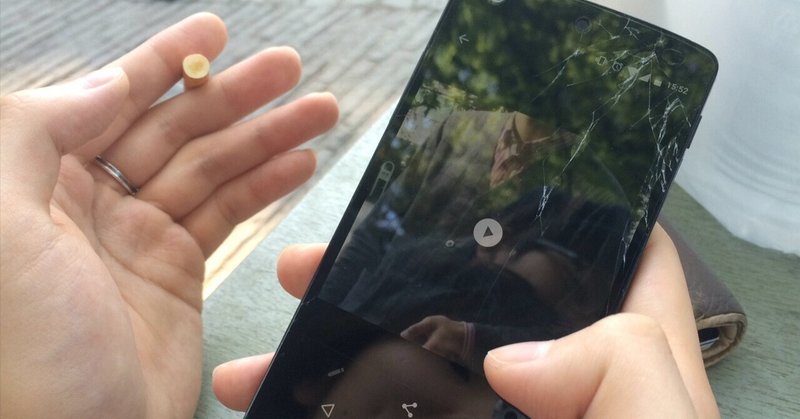
山本浩貴+h「共同性についてのノート、絵巻物」②
以下の文章は、『いぬのせなか座1号』(2015年、いぬのせなか座)に掲載された山本浩貴+h「共同性についてのノート、絵巻物」のなかの一部です。
前提に関しては①を御覧ください。
今回は、マドリン・ギンズの荒川修作論と、荒川修作+中村雄二郎「新しい創造を求めて」について。読みやすくするため、改行等を加えています。(山本)
マドリン・ギンズによるテキスト「アラカワ・図形からモデルへ」(以下、引用は、『アールヴィヴァン』一号、一九八〇年所収の瀧口修造・岡田隆彦・松岡和子訳を一部改変)。そこでギンズは、荒川修作の絵画を、《他の絵画のようには作用しない》ものだと言う。
《そこには、起りうる可能な配置がすべて明示されるように開放されてあるだけで、どんな特殊の手触りや命名の既成形式にも陥らない、ただ「そこに在る」という原型的な横断面がある》
別の言い方では、《あらゆる側面から注意深く観察することを要する》《彫刻的なもの》。そこでは、ひとつの思考に解消されない、複数の視角をどこまでも要求する事物としての絵画がほのめかされているが、それだけだと単に、ラッセルが例にあげるように〔※「感官与件の物理学に対する関係」のこと〕、道端に落ちている十円玉でも用が足せるようになってしまう。どこがどう違うのか。
《これらの絵画においてアラカワが意図したものは、〝思考する場 thinking world〟を想像の平面にもたらすこと》、《思考する場それ自体(その活動の群)のニュートラルな(?)表示である》。複数の視角がなるべくうまく出会えるひとつの場をつくるというよりは、それら視角らの群れそのものを、可能な限りたくさん提示してしまうこと。複数がひとつに出会うことは求められていない。彼らがたとえ矛盾し、お互いに両立しえない思考をなしていたとしても、それらをやはり群れとして提示できるかどうかが、悩まれている当の課題だ。
《事実上起こりえない紡ぎ(対立しあう二つの道を同時に進む)から長く引き出された仮説線が分散し、その仮説同士で、軸店のまさに「肉」を事実上分割している。もしこの仮説線が個人から送り出されるなら、空白部分を送り出しているのは誰か?
こうして、キャンヴァスは、個々別々の視点から分割される。個人の考えも同じように分割される。もっと厳密に言うなら、個人の考えは、キャンヴァスに示された仮説と傾向のすべての接合点(複数の点)になる。
実験にたずさわろうが瞑想しようが、見る者はこの研究の対象となる。そもそもの初めから、この個人にとっては、彼がひとつの集団であることがはっきりしていなくてはならない。実際、彼はその集団の構成分子の集合以上のものである。というのは、少なくともその瞬間には、彼は、空白をも送り出しているからだ》。
いくつもの思考のばらけた共生が、まさしくそのような言葉の並びによって、あらわされている。まずひとつに、キャンヴァスを見るわたしの思考は、キャンヴァスにおかれたひとつひとつの色やかたちや線によって散らばり複数に結びつく。つまり私からキャンヴァスへと思考の基点が移り、私はむしろキャンヴァスによる研究、試行錯誤の対象として捕獲される。次に、そのようなかたちで捕獲されること自体に、私の群性が認められる。キャンヴァスを介していく人もの私らの思考が隣りあうということが、いつのまにか私個人の組成のばらばらさへの指摘になる。
こうした、私の内部と外部に認められるふたつの複数性は、私という思考の集まりがその構成要素以上のものになるときにあわられるという、空白において、一致する。そしてその空白は、キャンヴァスの表面にもやはり、発見されている。
まさしくここで、ブランクへの検討がなされているのだった。キャンヴァスを朝十時に右から見つめた私の思考と、夜八時に下から見つめた私の思考が、それぞれには回収しえないような過剰さをもってひとつの私に統合されるとき、私はキャンヴァスないしは私自身にあるその過剰さ、ブランクでもってして、まったく別の肉体をもった私らとの、決してひとつにまとまりはしない複数の接合点を成す。
《共同制作というコンテクストにおいて、その共同制作者は、アラカワが部分的にしろ全体的にしろ、正しいか間違っているかを証明することによって、手を貸すのだ。〔…〕「われは他者なり」と言ったランボーは正しかった。だが、「他者はわれなり」とも言える。共同制作を学ぶことは、他者である私をさらに変調させることになろう。〔…〕「われわれは私」なのである》。
具体例として、ギンズは盲点について語る。ふつう盲点は視界のはじで、ひっそりと身を潜めているが、それを前面へ引き出すことはできないだろうか?
《スキャニングメカニズムは何であれ、いずれかの点で盲点の形成を伴う》。《盲点は、なまなましいありのままの変換可能性へのもうひとつの出発点とも考えられる。視神経が網膜の壁に押し入る点で、即ち、精神から目へと架かる橋のたもとで、巻き込まれた変換可能性がすっかり結び合わされるということが起るかもしれない》。
私という視角が常にもってしまう思考の中心性、私という枠組みを完全に脱ぎ捨てて思考することなどできないというどうしようもなさのあらわれとして、盲点を捉える。そして、私は盲点を媒介に、私というものを抜きにした思考そのものに触れうるかもしれない、と仮定する。ただしそこで盲点は、《われわれが見るのに失敗しているポイント》たちのなかから、実際に機能するものを、選別されなければならない。
《考える者が所有していないものについて、時に他者が考えるかもしれないということは、この領域のいくつかが盲点ではなくて、ブランクだということを示している。恐らく、ブランク・スポットとみなされるものから盲点かもしれないものへの変調がある。ちょうど、ブランクから知覚されるものへの変調があるように。》
私の思考のあふれかえりが、知覚と結びついてひとつに結びつく点を盲点とし、そこであらわれる思考の拡散と収縮の動きを、「別の私による思考ら」の生息地たるブランクと、区別する。むしろ、私とブランクの関係から、私の変換可能性としての盲点を、ふるいで選び取る。
かつて荒川が検討していたという、レオナルド・ダ・ヴィンチの問いを、ギンズは引用している。
《「作り手が絶えず死んでいくとすれば、それを新たに作りなおすのは誰か?」》。
それへの答え。
《「分解する速度が分解していく速度」(直観)によってこの変換に影響を及ぼしもたらすのは "Texture of mapping" そのものである。〔…〕"Point Blank: Distance of focus, how anonymous is this distance which is a texture"》。
どういう意味か?
荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』へ迂回しよう(以下、引用は、三浦雅士訳を一部改変)。
そこで荒川とギンズは、私という概念を「場所の虚構」と呼び変えた上で、次のように書きつけている。《この、それ自身の距離をもたない/場のつらなり、/そして、体がそれ自身に対してもっているのと同じほどの/わずかな遠近法しかもたない場のつらなり、/は《何かをするということが知覚されるところ》からできている》。
身体の内外で繰り返された出来事の、集中点としての群―先の、キャンヴァス上でなされる、私の内外の複数性とそこでのブランクの発生を、思い出しておく―は、周囲の点から自律していながら、しかし同時に大きく依存してもいる「切り閉じであるもの」として、お互いに距離をつくりあう。
それら無数の距離を、横切り織るものが、《かたちづくられる空間》ないしは《知覚》と呼ばれる。《繰り返し切り閉じることによって、それは距離という遊戯、たとえば腕や手足が見えてくるという遊戯をはじめるのである。》このような知覚が、場所の虚構という私を、出来事の群という場とは別に、しかしそれと紐づけながら、かたちづくっていく。
《切り閉じであるものを通して、感覚は、つまり先駆けるものは、ブランクの周辺を織ってゆく。場についての場が織られる。個人は、ブランクの場の網目(巣)として生きているのだ。個人それぞれにとって、場の網目は、つまりそれが個人にほかならないわけだが、ブランクにとどまる。ちょうど、場の網目が場所の虚構を予期させるように、またあるいはそれを育む土壌として働くように。》
ここに、私の内外にブランクをともなった複数性が見つかるゆえんがある。"Texture of mapping"の、おぼろげではあるがその内実だ。そして、荒川+ギンズが「死なないために」示そうとする転生(天命反転)もまた、距離の織物の組み立て直しを、場所の虚構とブランクという、互いに自らの持続をゆだねているものらの内部構造のほつれから行うことによって、なされるものと定義されるだろう。
《距離の織物、すなわち空間は、それ自身を、場所の虚構のうちに生じるさまざたな不均衡から組み立てあげる。場所の虚構と空虚がお互いを発生させるように。〔…〕以下の場合、場所の虚構はブランクになる。関係しそこなったとき、生起しそこなったとき、脱臼によって、分裂によって。それらによって妨害されたとき、場所の虚構は抹消され、隠される。/切り換えること、前へ、また後ろへと切り換えること。すなわち、きらめきとしての無次元。/これがつまり、永遠というものの本質、あるいは少なくとも、自らを「私」と呼ぶ世界を組み立て直すためのすべての要素である。》
ふたたびギンズの「アラカワ・図形からモデルへ」にもどる。
"Texture of mapping" 、キャンヴァスの上で成されていた複数の私の思考の、体を介してのちりぢりばらばらないくつもの接合が、すなわち作り手を私の死後にまで引き継ぐ。天命反転の実態である。すると重要なのは、いかにしてものづくりにおいて、場所の虚構とブランクを、互いにほつれあい、組み立て直しあうような状態に持ち込ませるのか、ということになる。
そのような関係性が成り立つためには、《非常なきちょう面さが必要になる。厳密に道案内をするモデルと同じくらい入り組んだ図面がなくては、この約束は守られないだろう。/これ〔荒川の作品〕は、思考する場によって地図として使用されるモデルである》、そういってギンズは、《蜂がどのようにダンスの情報を受け、処理し、あるいは使用するかを学ぶためデザイン》された、J・L・グルードによる装置を掲げている。
もはやキャンヴァスは二次元である必然性などどこにもない。こうして荒川+ギンズは平然と、建築に向かう――。でも、だからといってキャンヴァスの上に残された色やかたちや線が、身体の運動に完全に取って代わられるわけもない。荒川は、それらを、複数の作り手による共同の思考を培うメディウムとして、「言葉」と呼んでいるのだから。
《われわれの肉体とか物とかそれは全部言葉ですから。》
《ぼくは色も線も形も、普通の言葉のように使っているわけです。できるだけ言葉に近く。》
《他の言葉、線とか面とか形とか、そういうものを、何千年もかかってつくり上げてきた活字のグラマーのように使えないだろうか。もし使えるとしたら、まったく違うものをつくり上げることができるだろう。》
《モデルをここに一つ提出しようということ、それに代わる動く活字、それから呼吸する活字をモデルとして提供する。それからそれの使い方を考える……。》
《外側にまず作り上げなきゃいけない。それをぼくはモデルというのです。》(荒川修作+中村雄二郎「新しい創造を求めて」『アールヴィヴァン』前掲書、以下同様)。
さまざまな物や体や形態を言葉として提示すること、それが外側に作られるモデル……新たな「距離の織物」の道標となること。そうしたモデルは、やはり、複数人によって共通して使用可能でなければならない。
《二度、三度と使えないものは、ぼくは決して信じることができない。》
《他人が使えない限り、私そのものができるはずがないです。》
《部分部分は誰にでもわかる、それでいながら一つなのです。/ぼくが一つ情熱を持っているのは、フランケンシュタインの例じゃないけれど、あのようにできる人もいるんじゃないか、私はできなくても、あのようにこの主題をつくるやつがいるんじゃないか。》
フランケンシュタイン。そう、荒川は、モデルというものを、私を私の外側に作り出すものとして、考えている。
蜂の動きを、大きな機械が分析し再現するように……《私に近いもの。近いだけじゃなくて私そのものじゃなくちゃいけない、いずれは。顔形とかそういうものは変わってもいいから、マテリアルは。》
私らによって共通して使用されることのできる私、というかたちをとるものが、モデルと呼ばれる。
そしてそこに、荒川のいう「言葉」は、食いこむ。
《私が使う言葉というのは、言葉イコール肉体です。言葉イコールオブジェクトです。このイコーリティをどのようにつくり上げるかという言葉のための言葉の世界。》
《あるものからいろいろな自由を取ってしまった言葉、集約された言葉ですね。重さを失ったり、フロントを失ったり、バックを失った言葉です。それをぼくはある一定のところへ置いて、引き伸ばしたり私と同じような高さにしたり、いろいろしたわけです。ひょっとすると、その仕掛けから逆にこちら側、こちらの肉体が見えてくるんじゃないか。》
《あらゆる肉体とかあらゆるオブジェというのは、もうそこの中で四捨五入された不自由な言葉の世界。それは、変ないい方をすると、向こう側とこちら側をつくり出すためのもう一つの肉体です。それをぼくは不自由な言葉の世界というのです。》
このとき「言葉」という呼び名で指し示されているものは、盲点をともなった視角と似る。
言語表現に知覚運動が埋め込まれているという単純な話にとどまらず、そこで肉体や物が、常に私という、奇妙な複数性に開けた場を、その欠如と統一の不可避性において作り出しているということ自体が、「言葉」の内実となる。
それはつまり、複数の私らの共同を成すモデル、もうひとつの肉体、フランケンシュタインを、真の意味での「言葉」として扱おうとするということだ。場所の虚構がブランクへと脱落する瞬間をともなった道具。
《今までの線画や芸術は類似性というのですか、それに頼っていたわけです。けれども類似から受けるものというのは、われわれは一人ひとり違うものだから、いわゆる言葉のない世界といわれた。だからぼくは、その言葉のない世界を一度言葉にして外へ提出しているから、今度つくり上げられるものは、目の前に見ているようなものでしょう。今までそれでは言葉にならないというものを、ぼくは言葉にしたり絵にしたりするわけです。それを今度は向こうから自分で見ながら、その部分部分をもう一度総合して、頭の中で一つのものができ上がってくる。逆のプロセスですね。》
絵画に言葉を用いた重要な作家として、荒川がカンディンスキーをあげていることを、彼の、外的対象に依存しない絵画がもつとされる「内的必然性」という概念とともに、思い出しておくべきだろう。
ここで荒川がいう類似は、ある知覚対象を、それに似たもので置き換え、鑑賞者に再現させる、表象を基礎においた描写の仕組みだ。そこでは、絵画と外的対象が「似る」ことが目指されてしまうために、その基準において必ず生じるずれは、絵画と対象の間でおぼろげに宙吊りにされ、そのまま私とあなたの間の不一致の可能性へと、ずれこんでいってしまう。それでは共同制作は成り立たない。
そうではなく、あちらの私とこちらの私が、お互いのうちに生まれる総合=「私が私であること」を、思考の結果として、なぜかやり取りできてしまうように、色や線やかたちを使用する(荒川は、デリダによる差延を、ブランクと結んでいた)。
そのとき、線や色やかたちの言葉化、フランケンシュタイン化が成立し、同時にその判定基準に従って、言葉の使用方法が事後的に発見される……このことこそを、制作の最大の目的、関心事とする。魂の制作=言葉の制作。
《中村 実は人間の身体というのは在来考えられてきたように、単なる物体などではないんですね。むしろ最近では、活動する身体の中に一種の統合作用あるいは機能があって、その機能がこれまで心と呼ばれてきたものだというふうにみなされるようになってきた。〔…〕荒川 今あなたのいわれた心と肉体のことですけれども、それはまさに言葉の世界そのものですよ。》
そうしてつくられた制作物が、再び言葉の新たな制作基準・分析道具になるという、試行錯誤の循環のかたちづくりが、制作物の質の確かめとしても、目論まれていく。
では、なぜ活字だけではだめなのか。言葉の使用方法を、いくつも多重的に走らせる必要があるからか。それこそが、私の共同性を、私の、そして制作物の、外側につくるからか。
《ぼくは線が必要な時は線、色が必要な時は色、その色について書くことよりも、それを使って表現する。/だから、ある限られたところで部分が提出されて、総合は見る側に任せてあるわけです。だから結果的に新しいランゲージがつくられるところは、この本の中にはないんです。ぼくの絵の外側に、見る側のほうにある。》
メディウムに特定的であるがゆえに、メディウムを変えても持続する思考。私と物質的には異なるがしかし私であるフランケンシュタイン、私の分身。
《あの線は美しかった、あの色は美しくなかったといわれると、その間のグラマーが消えていっちゃうわけです。一番大切なのは、その間のグラマーなんです。そのグラマーがどのような重みをもってくるかによって、世界がコーディネートされるわけでしょう。そのように行かせる情熱とか行動をもたせるための仕掛けなのです。ぼくに対しても。》
《絵画には二つ以上のゲームがある。哲学とか詩とかは一つのゲーム。》
《たくさんのゲームが抽象的でなく、具合的に使われていかなきゃだめなのです。》
言葉はその使用方法の複数性において、言葉たりうるがゆえに、常に体を物を、言葉にしようと右往左往しなければならない。言葉はモデルであり私のフランケンシュタインであり、私の体は私の複数性のために、ひたすらな右往左往を、遠く離れた宇宙にいる私へ向けて、強いられている、ということ……「新たな距離」の手さぐり。
《われわれは意外に一つのランゲージ・ゲームで教育されてきたわけでしょう。となると、あの世界とこの世界というのは別のものだと思っているのです。「あの」と「この」の違いで。だけどあれは両方同じところにあって、同じ場所で起こっていることだということを、われわれは早くから、たとえば信仰をしていた人たちは何千年も前から知っているわけです。》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
