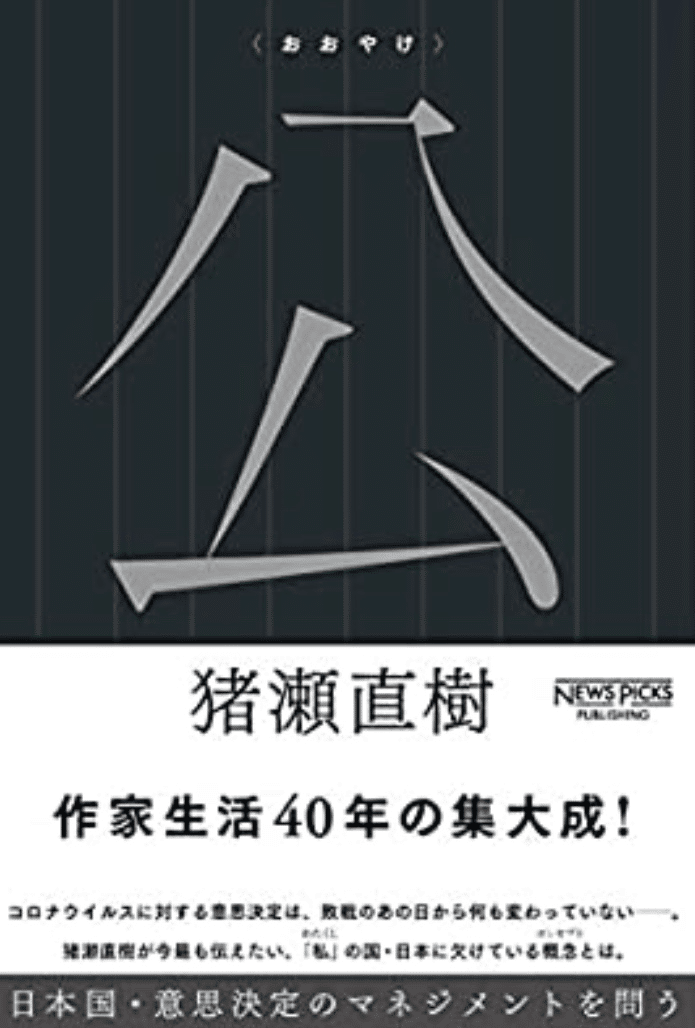たった一文字のタイトル、『公』という本を出します。
たった一文字のタイトル、『公』という本を出します。Amazon予約開始しました。
コロナ禍を経て、日本は表面的に変わることはできるだろう。満員電車による通勤からテレワークへ、教育施設のオンライン化、中央から地方への雇用シフトなど、おそらく見えやすいところの動きは始まる。
だがほんとうに変わるのか。変えられるのか。変わろうとするのなら、この国に本質的に欠けているものが何なのか理解しなければならない。それが本書のタイトルでもある「公」という概念だ。
「公」と耳にして、その意味が何だかわかったようでいてわからない、それが正直な実感ではないかと思う。
だから僕はいまここに、コロナ禍において、ドイツのグリュッタース文化大臣が、アーティストやクリエイターを「生命維持のための不可欠な存在」と言い切って、真っ先に給付金を支給したところに「公」の意味のヒントがあることを示しておきたい。
「ほんの少し前まで想像だにしなかったこの歴史的状況において、我われの民主主義社会は独自で多様な文化および(独自で多様な)メディア界を必要としている。クリエイティブな人々のクリエイティブな勇気が危機を乗り越える力になる」
いっぽう日本は官僚機構が肥大化した特殊な国家だ。官僚機構はシンクタンクと行政の執行機関を兼ねている。国家ビジョンを無感性の官僚機構がつくっている。
「独自で多様なメディア界」とは「官」の下僕であるような日本のサラリーマンメディアと同じではない。
アーティスト、作家、クリエイター、フリージャーナリストなど今後の社会を創造し、デザインする人たちの戦いに強い期待感を表明している。「クリエイティブな人々のクリエイティブな勇気」にこそ「公」が宿っているからである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?