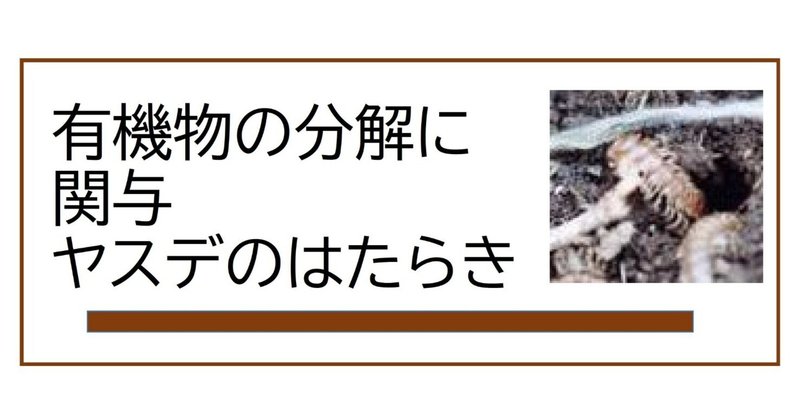
有機物の分解に関与するヤスデのはたらきとそれを活かす栽培
ヤスデ類は、ミミズ類と同様、有機物の分解に関与し、畑の土づくりに重要なはたらきをしています。
ヤスデの幼虫と成虫では餌が違う
ヤスデ類の分解者としての特徴は、食べ物が発育段階で異なることです。土壌中で生活する幼虫は、土壌中の腐植を餌として利用し、齢を重ねる(7回の脱皮)ごとに大きくなり、土壌中に穴を掘り通気性、排水性を良くするなど物理性の改善に寄与しています。脱皮時には、土壌を使って脱皮室をつくります。したがって、ヤスデ類が生活できるには、土壌構造が破壊されない安定した環境が必要です。
成虫は、落ち葉や枯れ草を大量に食べて、必要な栄養分を確保するとともに、糞として排泄された落ち葉や枯れ草をもう一度食べます。このことで、排泄された糞中で増殖した微生物が分解したものや微生物の酵素を利用し、落ち葉や枯れ草を直接食べることでは利用できなかった資源を無駄なく利用しています。
このように土壌動物が生活することで、糞中や土壌中の微生物のはたらきが促されて、動物の体外でも動物の腸内のようなはたらき(外部ルーメン)が活発に行われています。
これらのはたらきによって、有機物の生産者である植物の生育を促し、結果として、多くの有機物を土壌に還元することで、土壌動物の生活を豊かにしています。
ヤスデの生活を保障するライ麦の栽培
化学肥料や農薬を使用しないで、冬季間にライ麦を栽培し、春に青刈りしたライ麦を地表面に被覆した不耕起畑では、ヤケヤスデ科のなかまがみられます(図1)。

ヤケヤスデの生活と不耕起・冬季間のライ麦栽培・刈り敷きの条件が、適合しているためと思われます(図2)。このヤスデは秋に産卵し、冬季間を幼虫で過ごします。ライ麦の刈り敷き後の6月ごろから成虫がみられ、7~8月には高密度になります。もちろん、地表面に被覆された麦わらは成虫の餌になりますが、作物を加害することはありません。

ヤスデ類が生活できる管理は作物の生育・収量も良くなる
ヤスデ類は、畑に有機物を被覆することで、被覆物とともに持ち込まれたり、畑の周りから侵入したりして、畑のなかでみられることがあります。
畑のなかで一生を過ごせるような管理(たとえば、不耕起栽培)を続けることで、ヤスデ類は、土壌構造を改変したり、土壌中の微生物をはじめ他の動物の生活にも影響を与えたりして、その存在が直接的、間接的に作物の生育・収量を向上するようになります。
参考文献
藤田正雄(2006)土を育てる生きものたち(3)大食漢-ヤスデのはたらき.ながの「農業と生活」, 43(3):9.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
