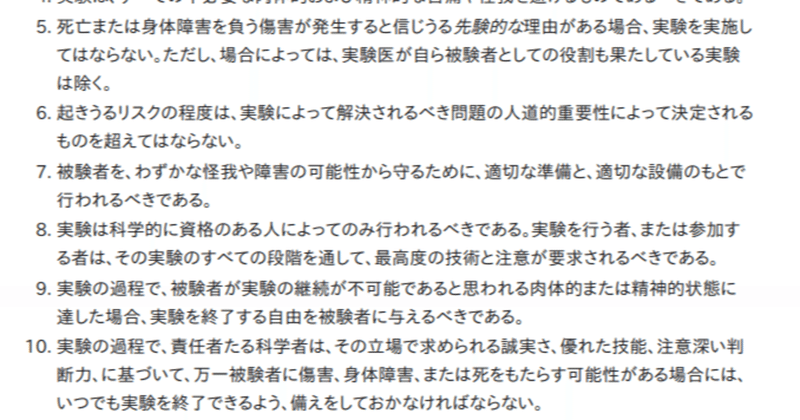
ニュルンベルク綱領と組織的犯罪処罰法と国際組織犯罪防止条約と多種異物混合液多臓器炎症劇薬接種教唆製薬企業等収益没収等と国際的傷害致傷致死組織犯罪取締り
多種異物混合液多臓器炎症劇薬(新型コロナワクチン)接種による、数十億人傷害致傷および致死等国際的組織犯罪と多国籍劇薬処方教唆製薬企業の重役等・ビルダーバーグ会議参加者等・WHO世界保健機関・Gavi(ワクチンと予防接種のための世界同盟)・イベント201参加者等・「ロック・ステップ」シナリオ作成慈善財団等の国際的組織犯罪取り締まりと傷害致傷致死ワクチン接種関連する収益没収が行われ、波動治療方法及び装置等が医療機関家庭等に普及による325種類の神経を含む身の病等からの完全解放等が進むか、人類社会国土国家が破壊され、人間の命が奪知恵奪健康奪命者教・悪魔教の植民地にされる続ける社会継続か歴史的岐路に立っている。
伝染病の治療に生物化合物多種異物混合液劇薬ワクチン接種は必要無い。薬草療法湯治等温熱療法食事療法等数千年の伝統医学もあり、波動治療方法及び装置に(Arbitrary Waveform Generator)AWG免疫と言う先進技術もある。
国際的組織犯罪シンジケートは金融マフィア立中央銀行の通貨発行量の数%搾取蓄財した財力で財力の魔性に弱い権力者権威者等を奴隷として、また報道権力や専門家権威に弱い代議士等権力者の善意を利用して、国際的組織犯罪に使用している。
金融マフィア立国際機関指導者等・各国各地域行政機関等・報道機関重役等・劇薬処方教唆多国籍製薬企業重役等・毒薬療法劇薬処方信仰医療機関責任者等・ワクチン接種教唆傷害致傷致死等でアフリカインド等の民衆から提訴等された国際的ワクチン接種教唆偽善団体等。
https://ja.wikipedia.org/wiki ニュルンベルク綱領 より
"ニュルンベルク綱領における10の要点
綱領の10の要点は、"許容されうる医学実験("Permissable Medical Experiments")"と題された評決のセクションで与えられたものである。
1:被験者の自発的な同意は絶対に不可欠なものである。
2:実験は、社会の利益のために実りある結果を生み出すようなものであるべきであり、他の方法や研究手段では実行不可能なものに限り、また無作為でも本質的に不要なものであってはならない。
3:実験は、動物実験の結果、及び病気の自然な過程についての知識、研究中の他の問題についての知識、に基づき設計され、予想される結果が実験を正当化させるものでなければならない。
4:実験は、すべての不必要な肉体的および精神的な苦痛や怪我を避けるものであるべきである。
5:死亡または身体障害を負う傷害が発生すると信じうる先験的な理由がある場合、実験を実施してはならない。ただし、場合によっては、実験医が自ら被験者としての役割も果たしている実験は除く。
6:起きうるリスクの程度は、実験によって解決されるべき問題の人道的重要性によって決定されるものを超えてはならない。
7:被験者を、わずかな怪我や障害の可能性から守るために、適切な準備と、適切な設備のもとで行われるべきである。
8:実験は科学的に資格のある人によってのみ行われるべきである。実験を行う者、または参加する者は、その実験のすべての段階を通して、最高度の技術と注意が要求されるべきである。
9:実験の過程で、被験者が実験の継続が不可能であると思われる肉体的または精神的状態に達した場合、実験を終了する自由を被験者に与えるべきである。
10:実験の過程で、責任者たる科学者は、その立場で求められる誠実さ、優れた技能、注意深い判断力、に基づいて、万一被験者に傷害、身体障害、または死をもたらす可能性がある場合には、いつでも実験を終了できるよう、備えをしておかなければならない。"
"組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第136号)は、暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益の資金洗浄(マネー・ローンダリング)行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定める日本の法律である。略称は組織的犯罪処罰法、組織犯罪処罰法など。
暴力団による薬物・銃器犯罪や、地下鉄サリン事件など、組織的犯罪の規模拡大・国際化が大きな治安悪化要因となっていることから、これに対処するため本法は制定された。"
"定義(2条)
・団体
共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの
・犯罪収益
財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により取得された財産、資金等提供罪により提供された資金、外国公務員等不正利益供与罪により供与された財産、公衆等脅迫目的資金提供罪に係る資金
・犯罪収益に由来する財産
犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産
・犯罪収益等
犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産
・薬物犯罪収益
薬物犯罪の犯罪行為により得た財産若しくは当該犯罪行為の報酬として得た財産又は前項第七号に掲げる罪に係る資金
・薬物犯罪収益に由来する財産
薬物犯罪収益の果実として得た財産、薬物犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産
・薬物犯罪収益等
薬物犯罪収益、薬物犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産
・組織的犯罪の加重処罰(3条以下)等
団体の活動として、下記の罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、通常の刑罰よりも重い刑罰が科される。また、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、下記の罪を犯した者も、同様に加重処罰される。
・「団体の活動」とは、団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。また、「不正権益」とは、団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。
・刑法199条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは6年以上の懲役(同、 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役。)
・刑法220条(逮捕及び監禁)の罪 3月以上7年以下の懲役(同、3月以上5年以下の懲役。)
・刑法223条1項又は2項(強要)の罪 5年以下の懲役(同、3年以下の懲役。)
・刑法246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役(同、10年以下の懲役。)
・刑法249条(恐喝)の罪 1年以上の有期懲役(同、10年以下の懲役。)
・刑法260条前段(建造物等損壊)の罪 7年以下の懲役(同、5年以下の懲役。)
なお、組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽、組織的な殺人等の予備の自首には刑の必要的減免がある。
犯罪収益等の没収・追徴(13条以下)
犯罪収益等の没収・追徴について、その範囲を拡大し、手続を整備した。”
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
”国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(こくさいてきなそしきはんざいのぼうしにかんするこくさいれんごうじょうやく、英: United Nations Convention against Transnational Organized Crime, TOC)は、組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)・司法妨害・腐敗(公務員による汚職)等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約である。略称は国際組織犯罪防止条約。TOC条約、パレルモ条約とも。
本体条約のほか、「人身取引」に関する議定書、「密入国」に関する議定書 、「銃器」に関する議定書の、三議定書がある(正式名称は下記。)。2000年11月15日、国際連合総会において採択された。
2020年5月現在、署名国は147、締約国は190(経済団体として加入している欧州連合を含む)。
主な内容: 国際的な組織犯罪を防止し、およびこれと戦うため、重大な犯罪を行うことを合意すること等一定の行為の犯罪化、裁判権の設定、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等につき規定する。
用語(2条)・適用範囲(3条)
本条約において「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、物質的利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
・本条約において「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。
・本条約において「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。
・本条約は、別段の定めがある場合を除くほか、第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪並びに重大な犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
・組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
・物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
・組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
・締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
・犯罪収益の洗浄の犯罪化(6条)
締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
・犯罪収益の不正な起源を隠匿すること等の目的で犯罪収益である財産を転換し又は移転すること及び犯罪収益である財産の真の性質等を隠匿し又は偽装すること。
・犯罪収益である財産を取得し、所持し又は使用すること。
この条の規定に従って定められる犯罪に参加し、これを共謀し、これに係る未遂の罪を犯し、これをほう助すること等
・締約国は、すべての重大な犯罪並びに第五条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪を前提犯罪に含める。自国の法律が特定の前提犯罪を列記している締約国の場合には、その列記には、少なくとも、組織的な犯罪集団が関連する犯罪を包括的に含める。
・腐敗行為の犯罪化(8条)
締約国は、次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
公務員に対し、当該公務員が公務の遂行に当たって行動し又は行動を差し控えることを目的として、当該公務員等のために不当な利益を約束し、申し出又は供与すること。
公務員が、自己の公務の遂行に当たって行動し又は行動を差し控えることを目的として、当該公務員等のために不当な利益を要求し又は受領すること。
・没収及び押収(12条)
締約国は、自国の国内法制において最大限度可能な範囲で、この条約の対象となる犯罪により生じた犯罪収益及びこの条約の対象となる犯罪において用い又は用いようとした財産等の没収を可能とするため、必要な措置をとる。
・裁判権(15条)
締約国は、犯罪が自国の領域内で行われる場合及び犯罪が自国の船舶内又は航空機内で行われる場合において、第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。締約国は、犯罪が自国の国民に対して行われる場合等にも、自国の裁判権を設定することができる。
・犯罪人引渡し(16条)
この条約の対象となる犯罪並びに第五条、第六条、第八条及び第二十三条に規定する犯罪並びに重大な犯罪であって、組織的な犯罪集団が関与し、かつ、引渡しの請求の対象となる者が請求を受けた締約国の領域内に所在するものについてこの条を適用する。ただし、請求に係る犯罪が請求を行った締約国及び請求を受けた締約国の双方の国内法に基づいて刑を科することができるものであることを条件とする。
この条の規定の適用を受ける犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。
請求を受けた締約国は、状況が正当かつ緊急であると認められる場合において、当該請求を行った締約国の請求があるときは、その引渡しが求められている自国の領域内に所在する者の抑留等を行うことができる。
・締約国は、この条の規定の適用を受ける犯罪につき容疑者が自国の国民であることのみを理由として引渡しを行わない場合には、犯罪人引渡しの請求を行った締約国からの要請により、不当に遅滞することなく、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負う。
・法律上の相互援助(18条)
締約国は、第3条に規定するこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、提訴及び司法手続において最大限の法律上の支援を相互に与える。
・特別な捜査方法(20条)
締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合には、監視付移転の適当な利用及び適当と認める場合には電子的監視等の特別な捜査方法の利用ができるように、可能な範囲内で、かつ、自国の国内法により定められる条件の下で、必要な措置をとる。
・司法妨害の犯罪化(23条)
締約国は、この条約の対象となる犯罪に関する手続において虚偽の証言をさせること等の目的のために暴行を加え又は不当な利益を約束すること等の行為及び裁判官又は法執行の職員によるこの条約の対象となる犯罪に関する公務の遂行を妨害するために暴行を加える等の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
・証人の保護(24条)
締約国は、この条約の対象となる犯罪に関する刑事手続において証言する証人等について、生じ得る報復等から保護するため、適当な措置をとる。
・被害者に対する援助及び保護の提供(25条)
締約国は、この条約の対象となる犯罪の被害者に対し、援助及び保護を与え、被害者が損害賠償等を受けられるよう適当な手続を定める。”
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
