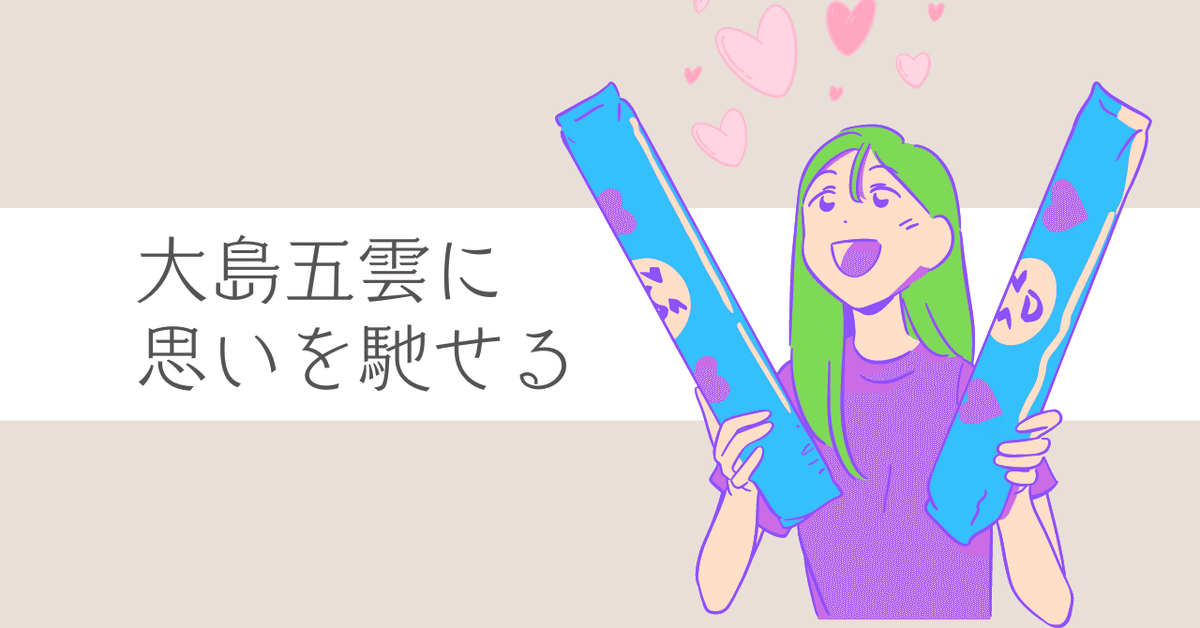
井波彫刻中興の祖・大島五雲に思いを馳せる
井波彫刻を一躍有名にしたのが『住宅欄間』であったことは、ご存じの方も多いと思います。
住宅欄間の需要があったからこそ、井波の彫刻師は専業で食べていくことができるようになり、弟子を取って技術を残すことにも繋がりました。
注:この記事は個人的な見解を含みます。情報の正確性には気をつけていますが、あくまで参考程度にご覧ください。もし訂正箇所などがあればコメントでお知らせいただけるとありがたいです。
井波欄間彫刻の父・大島五雲
その井波彫刻の『住宅欄間』は、井波彫刻の名工と言われる大島五作氏によって開発されたと言われています。五作氏は後に「五雲」に改名し、大島五雲の名はその後、4代まで受け継がれることになります(以降、初代・大島五雲氏のことを「初代」と表記します)。
初代が生まれたのは幕末。桜田門外の変が起きた翌年の1861(文久2)年。
初代の父は大工兼彫刻師だったそうです。
この時代だと、おそらく10歳過ぎくらいで修行に出たと思うので、第二次世界大戦が始まる直前の1937年(※1)に亡くなるまで約60年程の間、彫刻師として活動されたと考えられます。
そして年齢から考えると、明治後期から大正期くらいが、職人として一番脂が乗っていた時期なのではないでしょうか。
(※1)生没年は井波彫刻協同組合編の「井波彫刻師系譜」を参照
残念ながら、初代の作品と年代についてわかる資料は少ないため、いつどのようにして彼が住宅用の欄間を開発したのか、その経緯をたどることは容易ではありません。
ですが、1915(大正4)年サンフランシスコ万国博覧会に欄間「清梅春蘭」を出品していることから、この頃には既に住宅欄間を確立させていたと思われます。
※公開時、作品名を「清海春蘭(せいかいしゅんらん)」と記載していましたが、誤りだったため訂正しました(2023年10月2日)。
万博で名誉金賞を受賞したこの作品は現在、富山県立高岡工芸高等学校附属の青井記念館美術館に所蔵されています。
(↓所蔵作品パンフレット2ページ目中央下)。
https://www.kogei-h.tym.ed.jp/wp-content/uploads/2017/04/0b2a3f28befae32c9b7f814f1126f6c2.pdf
私の心を射抜いた大島五雲の欄間

引用元:時代家具のびるWebサイトより
恐らくこの写真の欄間は、二代目・大島五雲の作だと思うのですが(初代じゃないんかい!と思われた方、すみません)、この作品をWebで見たのがきっかけで「大島五雲」を知りました。
画像だけで見とれてしまいます。
ツタの細いところとか、いったいどうなっているのでしょうね…。
二対で完成するような配置がたまりません(語彙力の無さよ)。
残念ながら、上記画像の本物を拝見することは叶いませんが、生きている間に一度拝んでみたいものです。
初代の欄間も、動植物を写実的に表現する彫りの技術の高さと、余白を活かした構図が特徴です。
ちなみに、初代のコレクターさんは大勢いるようで、市場に出ることも稀な上に競争率も高いようです。
富山県や石川県であれば、まだ家に大島五雲の欄間が入ったお宅があるかもしれません。もし「大島五雲」銘が入った欄間をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただきたいです…。見たい…。
他に初代の欄間が見られるところ
個人宅はなかなかハードルが高いですが、
砺波市の浄光寺さんのお座敷にある欄間は見ることができます(要事前予約)。

下の写真は「梅に竹」のモチーフ。
超絶技巧はさることながら、住宅欄間の特徴である、
表と裏の見せ方がちゃんと計算されている点も感動を覚えます。
梅の木の幹に絡みつく小枝の表現たるや…!!

引用元:目で開く浄光寺~浄光寺の伽藍と彫刻~
真宗大谷派醫王山浄光寺発行
わずか数センチの一枚板を、平面図(下絵)と脳内だけで計算して彫っていったと想像すると頭がパンクしそうです。
制作年代をお伺いするのを失念してしまいましたが、
国会議員を務めた方が由緒あるお寺へ寄進されたもの、ということを考慮すると、すでに一定の評価を得ていた初代に依頼がいったと考えるのが自然かと思います。
とするとやはり明治の終わりから大正期にかけて制作されたものかと思います。
余談ですが、電話で「今日見れますか?」とぶしつけな問い合わせをしたにも関わらず、浄光寺のご住職と坊守の若奥様は大変丁寧に案内してくださいました。本当にありがたかったです。
初代の作品は、井波の瑞泉寺にももちろんあるのですが、
欄間ではないのと、高いところにあってよく見えないため、
「うーん、よくわからん」となってしまいます(汗)
瑞泉寺は名工たちの作品オンパレードで、建物自体が美術館そのものなのですが、見えにくいのが難点です。
ですが、これについては今後、デジタル技術の活用である程度解消されていくと思います。
彫刻師が技術を習得する過程については、昔も今もブラックボックスです。
初代も『技術は学ぶものではなく、自ら習得するもの』という職人気質の持ち主だったようですので、彼の考えを知ることは更に難しそうです。住宅欄間開発の経緯や思いなんてもってのほか……。
なので、次回は井波彫刻の『住宅欄間』が生まれた背景を、当時の情勢などを考慮しながら、もう一歩踏み込んで客観的に推察してみたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
