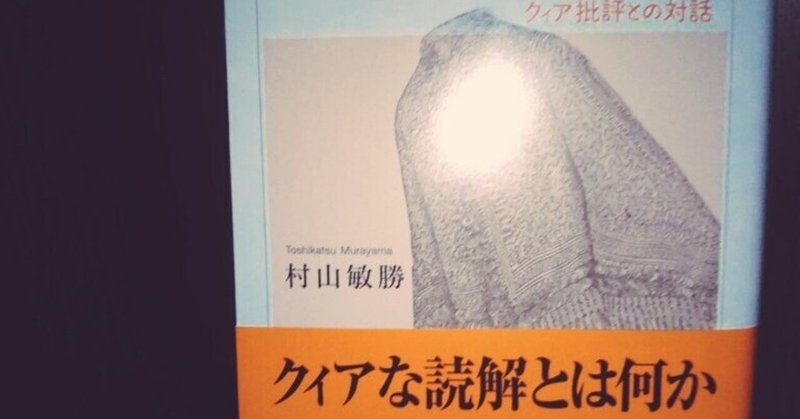
読んだ感想:村山敏勝『〈見えない〉欲望へ向けて――クィア批評との対話』(人文書院2005/ちくま学芸文庫2021)
※以下、『〈見えない〉欲望へ向けて――クィア批評との対話』の引用は(文庫版 頁)と表記する。
〈クィア〉の遍在。「クィアな人々は、奇妙であること、ずれていることによってのみ同じ集合に入るのであり、ゲイもレズビアンもS/M者も、それをいうならばヘテロセクシュアルも、歴然たる差異を生み出すような歴然たる同一性を持っていない」(文庫版15頁)。もし〈クィア〉なるものが、レズビアン〈だけ〉ではなく、ゲイ〈だけ〉ではなく、バイセクシャル〈だけ〉ではなく、トランスジェンダー〈だけ〉ではなく、インターセックス〈だけ〉ではないのだ、とすれば、あるいは、いま挙げたカテゴリーのすべてが〈クィア〉と混同されたり〈クィア〉に包摂されるべきではないのだとすれば、〈クィア〉は誰にとっても、つねにすでに、よそよそしさとともにある何かしらかであることになるだろう。そのように、誰もが〈クィア〉と無縁でいられず、しかしながら誰も〈クィア〉にはなりきれない、そんなものとして〈クィア〉を捉えることもできる。マイナー性のように遍く浸透する〈クィア〉な欲望あるいは〈クィア〉な美意識という想定がとりうる。もちろん、誰もが〈クィア〉に包摂されうるとの論が、〈クィア〉なる名指し/名乗りが抱えてきた歴史の重みを等閑視してしまった、現行社会への批判意識も骨抜きになったグロテスクなかたちの〈みんなちがって、みんないい〉宣言だとか〈みんなそれなりにいきづらい〉宣言だとかのようなものに陥ってしまうかもしれない、という危惧は、村山自身が、本書の導入部からはっきりと述べている。「実際、単婚的ヘテロセクシュアルを享受している表面的に「ノーマル」な人間があらゆるセクシュアリティの自由と平等を旗印にして「われこそはあらゆる人と同様にクィアなり」と宣言しても、たんに趣味の悪いジョークでしかないだろう」(文庫版17頁)。――これは念頭に置かれるべき一節であろう。
注:ただし舞踏家のクライド・スミスによる「いかにして私はクィア異性愛者になったのか」(1997)以来、英語圏ではクィアな異性愛というありかたがとりうるのかどうかさえも議論されてきた(とはいえ、それはシスジェンダー異性愛者らの手による〈クィア〉の濫用であり〈クィア〉が内容空疎なバズワード化するのを助長するに過ぎないとの批判も繰り返しあり、そうした批判が生ずるのも故無きことではない)。2018年には、例えば同性婚なる発想また語法が(シスジェンダーの男女ありきで考えられがちだった)結婚の内実を書き換えうるのと通じ合うような仕方でクィア異性愛もまた異性愛の内実を書き換えうるのかということを検討した論文が発表されている。
しかしながら、冒頭でそう書いた上で、あとがきで自身「現在世間的に見てごくごく規範的なヘテロセクシュアルとして、異性の配偶者と暮らしている(第三章で書いたように、性的なことが強調されない暮らし方だ)」(文庫版293頁)と告白し、苦心して「なぜクィアか?」(同)との声に答えようとする村山のどこか〈居心地の悪そうな〉振る舞いが、読者の眼からは何かしらかそれ自体〈クィア〉に映りもする、と述べることもできるだろう。ともすれば、こんな肖像すら脳裡に描かれる。――〈ノーマル〉を僭称するものらへの抵抗のよりどころとしてあるはずのQueerの世界へと(半ば)足を踏み入れ、そこで交わされる語や振る舞いをあたかも「身内のもの」のごとく用いて、いわば現地へと溶け込んでみせもする、「現在世間的に見てごくごく規範的なヘテロセクシュアル」。そして「たとえ自分勝手な愛しかたであっても、すべての人を愛したい」(文庫版294頁)と願い、読むことで「他人の気持ちを感じ取るという性的な歓び」(同)に憑かれた、「現在世間的に見てごくごく規範的なヘテロセクシュアル」。――そんな肖像が。
注:もちろん、先のように述べる村山敏勝が1993年に刊行の河出書房新社のムック『エイズなんてこわくない ゲイ/エイズ・アクティヴィズムとはなにか?』などにも参加していたことなども念頭に置かれるべきである。90年代でもゼロ年代でも10年代でもまた今日でも、「現在世間的に見てごくごく規範的なヘテロセクシュアル」が例えばダグラス・クリンプを学んできたとは、残念ながら考え難い。私のような半可通がこう評するのもおこがましいことではあるが、村山は際立った勉強家であったし、フロンティアの翻訳者であり紹介者だった。
一方では、セジウィックやバトラーやベルサーニ、コプチェクやジジェクといった書き手の議論(クィア理論ほか精神分析・政治・文化に関連する諸論)を整理しつつ、他方では、ディケンズ、ジェイン・オースティン、シャーロット・ブロンテ、フォースター、ウィラ・キャザーなど英文学の正典的地位にいるであろう諸作家の文章を(その研究史を踏まえつつ)読解しもして、さらには京極夏彦の探偵小説や英語圏の探偵小説論まで参照する。そうして理論と実作を横断し、アイデンティティ、プライヴァシー、公共性、共同性などの読み/書きによる創出と、それらが含み持つ境界のほつれや収まりの悪さを大胆に思考する村山は、しかし「クィア批評」の語り手に一致しきることなく、半ば外側に身を置きながら粘り強く「クィア批評」との「対話」を続けていく。「クィア批評」の紹介者でありながら、「クィア批評」のネイティブ・スピーカー(に準ずる者)として話をしないその態度は、本書の第三章で素描されるようなコミュニティ≒公共圏の感覚に裏打ちされているのだろう。「国家的、地域的、民族的な共同体の多くは、その構成員のかなりの部分が生まれたときからそこに属していることを想定しているのに対して、ゲイ・コミュニティはそうではないし、文学読者の、あるいはおたく=ポップカルチャー愛好者の共同体もそうではない。われわれにとってオースティンは、誰もそこに最初から帰属してはいない参加型コミュニティの構造を考えるための、正しい思考モデルなのである。実際にオースティンの世界では、階級によってあらかじめ選別の大部分がおこなわれているとしてもだ」(文庫版97-98頁)。オースティン作品自体の読解とオースティン読者のファンダムを題材にしたラドヤード・キプリングの短編との読解を合わせておこない、「公共性はすでに倒錯している」と題された節で結ばれる第三章の議論は、ポップカルチャーの愛好が一層にライフスタイル化し、様々なプラットフォームがファンの土着性をよりいっそう演出するようになり、ファンダム政治的なロジックが随所に浸透した今日、いっそう意義深く機能するように思われる。
注:また、本書での書下ろしであり、自己破砕的マゾヒズムから形たちのコミュニケーションへ、というベルサーニの思想上の力点の変化を論じた第八章は、異色にして出色のベルサーニ論である。村山が訳出を担当した以下の記事も併読すると理解が深まる。「インタヴュー:レオ第八章以外・ベルサーニとの対話」(聞き手:ティム・ディーン、ハル・フォスター、カジャ・シルヴァマン)『批評空間』2002年1月(第3期第2号) 所収。なお本書においてベルサーニは八章以外でも折々に参照されている。
村山の示す、ゲイ・コミュニティなどとの距離感、それは所詮自分などは「現在世間的に見てごくごく規範的なヘテロセクシュアル」という部外者に過ぎないのだ、といった腰の引けた(居直りの)所作なのではない。そうではなくて、自分が何者かを自分だけで決め切ると信ずる強権的な身振りとの決別こそが、そこに読み取られるべきものである。村山は、言ってみれば、いつでも自分が読んでいる相手に私淑するかのようにしながら読もうとしている。「そもそもものを読むとは、他人になること、同一になれるはずのないものに同一化することだ。そして本書でくりかえしてきたように、同一化と欲望とは区別がつかない以上、読むことは原理的に性的かつ無作法なものでしかありえない[……]めんどうな理論を学ぶのも、他者の思考を追体験したいという欲望のため以外、なにがあるというのか」(文庫版294頁)。だから、村山は、戯画的に描けば著者を召喚獣のように、理論をスキルのように装備して強くなる(強さを誇る)つもりのゲームのプレイヤーなのではなく、師の教えに感化される者のような読み手であり書き手なのである。ただし、師の欲望を己の欲望と取り違えることは避けようとする。「語る主体のアイデンティティが、語られている欲望と一致しないところに、クィアな批判の場が生まれるのだ」(文庫版63頁)。
注:これを書いている私はまた別の欲望に衝き動かされている面があるように、自身、感ずる。例えば私にとっての理論を学ぶ快のひとつは、ひとりではできない身体の(目や耳や脳の)動かしかたを体感するところにある。はじめて補助付きで逆上がりを成功させたときに覚えた、この身体にこんなこともできるのだというよろこばしい驚きにも似た感情が伴う。あるいは、ドゥルーズ『スピノザ 実践の哲学』で引かれるマラマッドの小説『修理屋』の一節が思い出される。「しばらくたってからぱらぱら読んでみているうちに、急につむじ風にでも吹かれたようになって、そのまま読みつづけてしまったのです。さっきも申しましたように、私には全部理解できたわけではありません。でも、あんな思想にぶつかったら、誰だって魔女のほうきに乗っかったような気になります。あれを読んでからの私は、もうそれまでの私とは同じ人間ではありませんでした……」。しかしながら私の欲望は「同一になれるはずのないものに同一化すること」よりも、ともすればもっと無作法かもしれない。あるとき与えられた図版を用いてコラージュをつくるように指示された私は、人間や家具の写真また矢印や英字の記号を切り刻んで貼り合わせ、別のヒトガタをつくっていた。私は原作破壊的な二次創作の制作に憑かれており私自身が破壊されて別の機械の部品になる瞬間を夢見ている。
村山とともに、この際どく誘惑的な、倫理的であるとともに最高度の快楽でもあるとされる「クィア批評」の語りに、身を委ねきらず身を浸すこと。逃れる/身を守る/戦うためのアジールへと、違法じみたそして/あるいは異邦じみた、よそよそしい心を抱えつつ、だが馴染みのごとき顔をつくり、出入りすること。特権的な余裕(例えば異性愛規範[Heteronormativity]を生き抜けるがゆえに得られたようなそれ)を持つ者のツーリズムへと落着してしまうおそれも、もちろんある。しかし、本書から学びうる事柄のひとつは、部外者/当事者の線引きへと居直らずに、いわば異郷で居心地の悪さを抱えつつもそこに溶け込もうと努める、そうした振る舞いなのではないか。潜伏者の名乗りがたさ語りがたさを抱えることでしか学べないものもあるだろう。例えば公共圏にやってくる他者、つまり新参者を、歓待しようとすること。また、公共圏からずり落ちそうな他者たちにも、寛容になろうとすること(ただし丸ごと目溢しするのではない仕方で)。これらがそうではないか。もはや自分が身を置く場が公共圏なのか否か判然としなくなる瞬間すら間々体感する者にとって、学ぶべきことがらは、安全な(自分のままでいられる)閉じた空間や集まりの紹介(売り出し)の情報よりは、自分を折らずに曲げたり、隠すことなく抑えたり、他に合わせつつ己に合わさせたりする折衝の技法であり、それを可能にする環境の構想であろう。避難民でも観光客でもないような旅人になるための手引きとして本書は読めるだろう。
注:他方で、公共圏への不安定な定住こそが旅と一致する可能性に本書は賭けているようにも映るのだが。村山自身のあとがきや田崎英明の解説を除けば最後の第八章のベルサーニ論は、以下のように結ばれている。「「他なる同じさ」、それはヨハネの脚と子羊の角のように、ただ似ているもの、欲望の弁証法を脱したつながりにもあてはまるはずだ。しかしこのことばが「ホモセクシュアル」ということばと結びつくとき、無限の同一化は、差異の分離戦の前で正気に引きずり戻される。クィア批評がもっとも解放的になるとき、それはゲイ・アイデンティティが無意味になるときであり、と同時に、われわれの知る世界におけるアイデンティティの束縛という地平の再任が迫られるときでもある。この地平に耐えつつ、そこから快楽を生み出す費用を、たえず「不正確に反覆」していくことが、われわれの作業である」(文庫版291頁)私は小さな〈不正確な反復〉を遂行できただろうか?
[了]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
