ヒトに意識は必要か? 稲葉振一郎『銀河帝国は必要か?』読書会【闇の自己啓発会】

闇の自己啓発会は2月8日、都内某所で稲葉振一郎『銀河帝国は必要か?』読書会を行いました(都合により、予定していた課題本を変更しました。楽しみにしていた方には申し訳ありません…)。調子の悪い人が多く、いつも以上に具合の悪い話が多くなった気もしますが、その模様をお伝えしていきます。
※これまでの活動についてはこちらをご覧ください。
https://note.com/imuziagane/m/mbd28cf65025b
※【闇の自己啓発会】は読書会記事を募集しています。
https://note.com/imuziagane/n/n9123acc09bec
◇参加者一覧
【ひで】シス 目黒から新宿に引っ越しました。今回の引っ越しで10回目です。無職になりました。
役所【暁】 今までに8回引っ越しています。転職に向けて動き始めました。好きな異世界召喚系ゲームは、Xuse『永遠のアセリア』。
【江永】泉 今までに7回引っ越しています。好きな異世界転生系小説は、めり夫『幸福な結末を求めて』(ヤマグチノボル『ゼロの使い魔』二次創作、未完)。
【木澤】佐登志 今までに3回重版してます。『ニック・ランドと新反動主義』と『ダークウェブ・アンダーグラウンド』をよろしくお願いします。
◇本記事の小見出し一覧
■はじめに
■本の感想を
■著者の他の本ってどんなもの?
■第1章 なぜロボットが問題になるのか?
■ヒトにオリジナリティはあるか?意識は必要か?
■まだ脳で消耗してるの?
■第3章 宇宙SFの歴史
■アシモフについて
■ギグエコノミーが社会構造を変える?
■参考文献について
■出生加速主義は宇宙進出を促す
■光速の限界が「外部」を産む
■終わりに
◇稲葉振一郎『銀河帝国は必要か?』(2019年 ちくまプリマー新書)目次
第1章 なぜロボットが問題になるのか?
第2章 SF作家アイザック・アシモフ
第3章 宇宙SFの歴史
第4章 ロボット物語−アシモフの世界から(1)
第5章 銀河帝国−アシモフの世界から(2)
第6章 アシモフと人類の未来
参考文献
あとがき
■はじめに
【江永】 しばらくポテチ食べててもいいですか。カロリーが足りなくて。
【ひで】 いいですよ。
【木澤】 僕もここ1ヶ月ぐらいシラフの状態がなくて、今日も少しクラクラしてます……。
【ひで】 シラフじゃなくてもWebの連載できるんですか……クリエイティビティには影響がなければいいのか。
【暁】 細かいとこは編集や校閲がチェックするので大丈夫なんじゃないですか。
【木澤】 そうですね。
【ひで】 ぼくもここ一週間ぐらい平均睡眠時間が4時間切ってるんですよね。
【暁】 僕も躁が続いてて脳がめちゃめちゃです。こんな社会で、シラフで健康に生きていられる人の方が異常者なんじゃないかって、最近結構思いますね。
■本の感想を
【ひで】 今回の本は、全体的にどうでしたか?
【暁】 非常に稚拙な感想なんですけど、SF作品がたくさん出てきて「これ読んだわ〜」「これ読んだことないな」っていうのが色々出てきて面白かったです。次の読書に繋げられそう。あと以前の読書会でやった同著者の『不平等との闘い ルソーからピケティまで』よりずっと読みやすかった(笑)。前にやった海猫沢めろんさんの『明日、機械がヒトになる』にも共通するような内容でしたね。
【ひで】 たしかに『不平等との闘い』は新書なのに読むのがかなり重かったですよね。今回のは読みやすかったです。
【江永】アイザック・アシモフに対してぼんやりとしたイメージしかなかったので、あとがきの「アシモフ自身が語る通り、アシモフは小説家としては決して一流ではなく」(p.216)と始まる一文しかり、いわゆるアシモフ像に付着した権威をバキバキ剥いでいく著者の評言が印象的でした(他には第2章、とりわけp.57-58の経歴まとめの記述など)。
もっともこの新書の大筋では、アシモフはその天才的な着想で「我々自身の欲望を水路づけし未来をつくった」(p.216)し、その点で言えば、従来から評価されていたロボットSFのみならず、一見地球上の政治や権力の発想や構図を引き写した寓意に過ぎなくも映る宇宙SF、とくに銀河帝国ものにも改めて評すべきところがあるのだ、と肯定的に評価されていたとも思います。〈自分の好きなものはいかなる点ですごいのか〉みたいなものとは異なる評価軸が導入された、丁寧で外在的なSF批評にもなっており、敬すべきスタイルだなと思いました。
【暁】 最初に「銀河帝国」と聞いて、「銀河英雄伝説かな?」と思いましたけど、アシモフの方かー!ってなりましたね。そういえば『銀河英雄伝説に学ぶ政治学』っていう本が出ていました。どういう感じかわからないので手を出していないですけど。銀英伝自体、田中芳樹が大学院生だった当時としてはよく頑張って書いてるけど政治体制の区別とかちょっとアレなので…。
【江永】大庭弘継と杉浦功一による本(2019)ですね。国際政治学などが専攻の方々の。他には、西田谷洋『政治小説の形成』(2010)で、『銀河英雄伝説』が話のまくらとして引用されていた記憶があります。私は同作の原作に触れたことがなく、n次創作しか読んでいないのですが、キャラや組織の立場や設定、主要な出来事の流れは何となく知り及んでいます。
【暁】 僕は好きなんですけど、宇宙空間が舞台なのに、戦いとかがすごく平面的なんですよね。元々中国史が好きな作家なので平原の戦いっぽい。行政機構なんかもキャラクター名に沿ったドイツ風ではなく中華風ですし。アニメではSF的な肉付けを頑張っていましたけども、そもそも宇宙空間について掘り下げるタイプの話ではなく…。脱線しました。本の内容に戻りましょう。
【木澤】 ロボットとか宇宙への探求とかを突き詰めていった結果、逆にロボットの方が第零原則とか言い出して人類の定義について思い悩んだり、アウタースペースへの問いがいつの間にかインナースペースへの問いに回帰していくという構造が面白かったですね。とはいえ、外への思考=志向が図らずも人間についての思考=志向を深めることになるという相関関係はある意味で普遍的でもあります。
たとえば、1968年に編集者のスチュワート・ブランドが『ホール・アース・カタログ』というヒッピー向けの情報カタログ雑誌を出しましたよね。その創刊号の表紙は、宇宙船アポロ4号が1967年に撮影した地球のカラー写真だったんですけど、実はそれまで(宇宙飛行士以外は)誰も地球の姿を眺めたことがなかったんです。60年代といえば冷戦における宇宙開発競争の時代で、アメリカもソ連も我先にと宇宙空間の開拓を推し進めていたわけですけど、そこで振り返って地球の写真を撮ろうとは誰も思わなかったわけです。
ブランドはこうした状況に苛立って、「なぜ我々はまだ地球全体を見たことがないのか?」と印字されたバッジやポスターを作ったりしてNASAに対して抗議活動を行った。そもそもブランドが『ホール・アース・カタログ』を立ち上げようと思ったきっかけは、『宇宙船地球号』で有名なバックミンスター・フラーの講演だったとされます。その講演でフラーは「地球を平らで無限な広がりとして認識すること、これこそがすべての過ちの始まりだ(people perceived the earth as flat and infinite, and how that was the root of all their misbehavior.)」という内容の主張をした。
地球平面説のような陰謀論が大手を振っている現在からすると隔世の感がありますが、それはともかくとして、ある日(1966年2月)、当時28歳のブランドがノースビーチの三階建てアパートの屋上で、LSDをキメながら毛布を巻いて縮こまっていると、眼下のサンフランシスコ市街地のビル群が完全な平行に並んでいないことに気づいて衝撃を受けた。フラーの講演の記憶もあり、それは地球が丸いので曲がって見えるのだとブランドは直感した。これが上述のNASAに対する抗議運動にも繋がり、最終的に人工衛星のカメラの向きを反転させるに至るわけです。
『ホール・アース・カタログ』の表紙は、人類が一つの星のもとに生きているという実感を読者に与え、カウンターカルチャーを牽引する意識革命を促すきっかけになった。70年代以降のエコロジー運動やガイア理論などのカウンタームーヴメントの高まりは、こういったヴィジョンから生まれきた、といっても過言ではないでしょう。
【暁】 概念が見えるようになって初めて人間に統合意識が生まれるのって、近代国民国家の形成過程と似てますね。明治時代の日本だって、それまでは諸藩がごちゃごちゃしていたのを「天皇は偉いんじゃ!」という風に国家神道というわかりやすい物語を創り、国民意識を形成していった。東欧などもわりとそんな感じで、民衆にもわかりやすい言語や文化を“発見”して啓発することで、国民国家を創っていきましたし。
【木澤】 「可視化」というプロセスはやはり重要だと気づかされますね。イメージ/表象の重要性。トマス・ホッブズの『リヴァイアサン』初版の口絵もそうですね。あれには武力を象徴する剣を右手に、統治を象徴する王笏を左手に屹立する王冠を被った巨人が描かれていますが、よくその身体を見ると、それが多数の人間=臣民の集合体であることがわかる。要するに有機的国家を表象する手段としてそうしたイメージが用いられている。
【ひで】 リバイアサンの絵を中学校の社会科の教科書で初めて見たとき、感動したんですよ。
【江永】 あの扉絵ですね。アブラハム・ボスの手になるという。田中純『政治の美学』(2008)の第Ⅱ部第2章やG・アガンベン『スタシス』(高桑和巳訳 2016)などが、あのイメージの読み方を提示していて面白かった記憶があります。「可視化」のプロセス、イメージの制作過程の検討は、近年、イコノロジー研究の中でも重視されているように思われます。既成の思考を引き写すのみが図像の役割なのではなく、図像を制作しようとする作業が思考を深めたり、図像を参照するなかで解釈が変わったり、制作に伴って新たなコンセプトが形成されたりする側面もある、と。
田中上掲でも紹介されている(シュミットのホッブズ論を評価する話の前座としてですが……)、ドイツの美術史学者H・ブレーデカンプは、いろいろな図像行為を思考形成の過程に編み込んだ美術史みたいな著作をいくつも書いていて、例えばライプニッツのスケッチ群を論じた『モナドの窓』(原研二訳 2010)とか、ガリレオの素描を論じた『芸術家ガリレオ・ガリレイ』(原研二訳 2012)とか、邦訳も多数あります(なおガリレイ論は、ガリレイ作と推定した、話のメインとなる書物が、刊行後に後世の偽書だったと判明してしまった件でも有名なのですが)。で、ブレーデカンプには『ダーウィンの珊瑚』(濱中春訳 2010)という著作があります。個人的にはこれが特に面白かった。
進化論と図像といえば、系統樹という、系統の分岐と各生物の類縁関係の分類を図示した樹木的表象が想起されると思うのですが、実は、C・ダーウィンの『種の起源』(邦訳多数 原著1859)には「ダイアグラム」、つまり簡素な図式ないし一覧図しか記載されていないのだそうです。進化論における、いわゆる系統樹のイメージの源流は、どちらかというと、E・ヘッケルの著作の挿絵などに求められるらしい(もちろん存在するものの分類体系を樹に擬する図像は、いわゆるポルピュリオスの樹など古来から確認されています)。
で、ブレーデカンプは、ダーウィンの珊瑚(のスケッチ)へのこだわりなどを通して、樹(の枝や幹)という表象が暗黙裡に持ち込みがちな階梯的な上下間系を批判しつつ系統分類を思考しようとする試行錯誤の痕跡として、ダイアグラム形成にまつわるダーウィンのスケッチ群などを辿っていくんです(なお、進化生物学の専門家が系統樹などを説いた著作として、三中信宏『進化思考の世界』(2010)と『系統樹曼陀羅』(2012)を挙げておきます。同著者には他にも多数の著作があります)。
【木澤】 ヘッケルの系統樹って要は進化における「存在の大いなる連鎖」の視覚化なんですよね。結局ヘッケルは優生学思想の方に行っちゃうんですけど。ここでもアナロジー的なイメージ/可視化が、翻って思想の方にフィードバックとして与える役割の無視し得ない大きさがよくわかりますね。ちなみにヘッケルはゲーテの形態学から影響を受けた一元論者で、生命と無機物との間に質的分断を設けず、むしろ生命は無機物から発生した、という連続説を唱えた。そして、その無機物と生命の懸隔を埋めるミッシング・リンク(原形質)を求めて世界中の海洋生物を調べていくんです。
【ひで】 無機物と生命のミッシングリンクといえば、最近東大が、「生命の発生はランダムネスから生まれた。ランダムから生命を生むぐらい宇宙は広大だった」って発表をしてました。それだけ宇宙は広大だから他の地球外生命体と会うことも難しいんでしょうけど。
【江永】 その発表も、空間的なモデルの更改、つまり宇宙の広大さに関する理解がインフレーション宇宙論によって変化したことが、ひとつのポイントですよね。人類が現状で観測しうる限りの広さにおいては、偶然生じるにしては確率があまりにも小さい(から説明として不十分)とされてきた事象(十分な長さのリボ核酸の誕生)が、従前よりもずっと広いと想定された宇宙の、そのどこかでなら、十分に生じうると言えることになった。イメージ、あるいはダイアグラムの制作と思考の生成には絡み合う側面がある。宇宙の理解が(特に光速や距離をめぐる知見が)SF制作とどう関わってきたのかは『銀河帝国は必要か?』の主要な論点のひとつでもあったと思います。
■著者の他の本ってどんなもの?

ここで江永さんが、著者の他の著作を取り出します。
【江永】著者の論述の特徴として、自著で以前展開した議論を圧縮して、今回展開する新たな議論の足場にする、という操作を明示的におこなっていることが挙げられると思います。ということで、少しずつ集めています。いまは収集途中で、まだほとんど読めてないですが、こうして見ると、私この著者がめちゃ好きな人みたいですね。
【暁】 著者、ジャンル横断的な知識があるから色々書けて凄いですよね。あ、『ナウシカ解読 増補版』めちゃ読みたい!帯に「どのようにしてハッピーエンドの試練を乗り越えるのか、バッドエンド依存症に陥る相応の根拠とは?」と書いてある。僕バッドエンドが大好きなので刺さりそうです。この本はどういう内容なんですか?
【江永】 まだ通読できてないので、拙いことしか言えませんが、えーと、ハッピーエンドの試練やバッドエンド依存症については明示的には冒頭とか第四部第1章のところで書かれていますね。……広江礼威『BLACK LAGOON』(2001-)が続きをなかなか書けないのは何故か? という話をしていますね。
【暁】 それは作者が同人誌書くのに忙しいかr…ゲフンゲフン。僕はアニメしか観てないのですが、『剣客商売』的な一話完結型なら無限に書けそうですけどね。
【江永】 そうですね。つまり、スピンオフとかn次創作なら権利上はいくらでも続けられるわけですよね。舞台や主要キャラや時系列が破綻しなければ。そこを問題にしてるっぽいんですよ。土地や時代の設定的に、『BLACK LAGOON』の舞台ロアナプラは、いずれ解消されてしまう自由都市みたいなんですね。時間的なイメージで言うとモラトリアムというか。で、モラトリアム終わったら人生おしまいだ、それがリアルだ、的な感性、どうもこういうものを「バッドエンド依存症」と読んでいるみたいに感じます。「ハッピーエンドの試練」とは、どうも、空疎なユートピアか、安直な破滅か、という二者択一を超えて続く世界、ないし社会を想像できるか、というような話に思えますが……。
ちょっと自分の関心に寄せて自分の言葉で話してみます。ジェイムソン「アメリカのユートピア」(同名論集に所収。田尻芳樹・小澤央訳 2018)を読んでから、フィクションとユートピアのことが気になっていました。(以下の私の記述は著者の思考に厳密に即してはいません。稲葉振一郎『ナウシカ解読【増補版】』の第一部第5章以降のユートピア論や、第三部の特に第4章の議論などの方が、はるかに洗練された枠組を提示しています……)。
例えば、現状というのは、たとえ無問題に見えても、常に既に隠蔽された搾取から成り立っているといった発想はありえますよね。少なくとも、現状のすべてを理想通りと理解するのでもない限りは。この現状をそれに似せていくべき理想っていうのが、ユートピアだとする。で、そもそものユートピアの設計(前提や推論の進め方)に問題があるという発想も、ありえますよね。物語はこういったユートピア構想の耐久テストとも考えられるわけですね。物語の展開とともに、登場人物たちを通して、その世界の不具合みたいなものが、可視化されたり把握されたりする。不具合の原因が登場人物レベルなら悪者を滅ぼして一件落着なわけですが、社会や世界のレベルなら?
不具合があるのはどうしようもない、とするならバッドエンドがくるわけですが、不具合をどうにかするために物語の設定をいじったり何かをなかったことにしたりすると、言うて物語だから作者が都合でいじれるだけやんけ、と物語に醒めてしまう。あるいは、ユートピア物語にリアルな世界を合わせるために「設定」をいじくる「作者」ポジションをこの世界に召喚しようとする羽目になる。つまり超人的な支配者が待望される。さもなくばユートピアなんかなくて単に殺伐としたサバイバルだけがあるという思考停止に至ってしまう。でも、ユートピアが内在的にサバイバルへと解体されてしまうのだとすれば、その裏返しに、サバイバルからユートピアを立ち上げる契機もあるのではないか?
SFジャンルをユートピア論的な問題意識で読むとこういう話が出てくると思うんです(この設定されたルールに従うモデルの耐久テスト的な享受に即した仕方で、SFやミステリ、ファンタジーなどとメタフィクション様式の交差するラインとして、セカイ系とデスゲーム、なろう系などを辿るのは面白そうです――ジャンルごとの固有性の整理をないがしろにしていると批判を受けそうですが)。「バッドエンド依存症」というのは、ユートピアを断念してしまうこと(ただし、ご都合主義に開きなおる拙いユートピア擁護よりはマシ、と捉えられているっぽい)。「ハッピーエンドの試練」は、たぶん、ユートピア案をテストするという、物語制作におとずれうる試練のことなのだ、とまとめられると思います。
すみません、つい自分の所感を述べ立ててしまいました。新書の話に戻りましょう。
■第1章 なぜロボットが問題になるのか?
【ひで】 「自律型宇宙探査ロボットは正当化できるか?」って出てきますけど、コレどういう意味なんですか? 稲葉さんの他の著書読んでいないからわからなくて。
【江永】 正当化というのは大別すると二側面で妥当か否かの話っぽくて、権利の水準での話と、功利的というか、宇宙探査に必要か否かという話ですね。稲葉振一郎『宇宙倫理学入門』の第5章だと、たしかに「本格的な系外宇宙探査のためには、人格を有する自律したロボットがあることが極めて望ましい」(p.116)のではある。けれども、人格があって権利があって判断力もあるが自然人ではない者たちを、どうやって不正ではない仕方で宇宙探査に従事してもらうか、という問題が論じられていました。
【ひで】 なるほど……。
【暁】 課題本の第1章では、基本的に人型ロボットはコスパ悪いので作られなさそうだけど、宇宙開発を進める場合については生身の人間では厳しいので、機械にやらせようって機運が生まれるかもね、って話が出てましたね。『ブレードランナー』のレプリカントが創られた理由がこれですが、仰るように倫理的問題があり、同作中で“彼ら”は反乱を起こした。以前、『三体』の作者・劉慈欣さんが日本に来て講演したときに、「環境汚染対策としての宇宙移住ってどうなると思います?」って聞かれて「言うて地球がどんなに汚染されても火星よりは住みやすいから実現しないだろう」って答えてましたし、宇宙開発のための人型ロボット開発は、そういう意味でもやはり厳しそうですね。
個人的には人間の形をしたロボットって宇宙探索以外にも、セクサロイドとかがありえるんじゃないかと思います。ちょっと前にひでシスさんがツイートしてた、セクサロイドが人類を支配するようになる『無限射精拷問』とか面白かったですし、そういう可能性もあるのかなって。ちなみに同作は『搾精病棟』の著者の前の作品です。
【ひで】 たしかに自動運転をするためのロボットは人間の形をしている必要ないですよね。一方でセクサロイドなら、セックス相手は人間の形をしていたほうが受け入れてくれる人は多そうですし、人間の形をしているのも合理性があります。
【江永】 人間の形、が何を指すのかにもよりますが、コスパを追求するんだったら、わざわざ無機物を組み合わせて人体の模造品をつくるより、人権のない人体(そんなものがありうるとして)を製造する(そんなことがゆるされるとして)方が容易そうに思えます。新書にも「むろんわれわれが知っている一番性能が高くて安上がりな自動機械は、人間、自然人そのものです」(p.47)ともあったし。
【ひで】 人権のない人間……大脳皮質のない人間を遺伝子改良で生み出す、とか。
【暁】 ヤバすぎる…。セクサロイドなら人間相手にできないことができるし、見た目の年齢を固定できていいと思うんですけど(虚淵玄『鬼哭街』などを念頭に置いて話しています)。まあでも今の意見は人間に近い存在に人権を認めない立場からの発言になるので、やはり問題はありますね…。バトーさんやミュウツーに怒られてしまう。
■ヒトにオリジナリティはあるか?意識は必要か?
【江永】 第1章の6節や7節の、人間などには心とか意識とかが何故あるか、ではロボットに同じような機能は必要か、といった面から物事を捉える語り方は、伊藤計劃『ハーモニー』(2008)を思い出させました、が、思えば著者自身が『ナウシカの解読【増補版】』で伊藤『ハーモニー』を論じていました。
【暁】「 ロボットが人間の役に立つにはネットワークに接続していないといけないよね」というのがp.19にあったんですけども、それと対になるように「人間は接続されてないからオリジナリティがある」みたいに書かれていた。でも僕なんかは意識が常にTwitterに接続されているんですよね。スタンドアローンと言えるのだろうか? とか、ネットに接続・依存しすぎると党派性に囚われてオリジナリティを失っていくんじゃないか? とか考えてしまいました。
【ひで】 暁さんは「人間もTwitterで常に繋がっている」っておっしゃってましたけど、本書では「人間は手でOutputして目や耳でInputするだけで脳が直接繋がっているわけではない」というように明確に区別されていたような気がします。
【江永】 例えばこんな風に出てきますね。「すでに示唆した通り、現在のネットワーク社会の延長線上にわれわれの未来を考えるならば、そこでの典型的なロボットは、常にネットワークにつながっているはずです。しかし人間の脳は、他人の脳とネットで直接つながったりはしていません。そしておそらくそのことは、人間の心の自律性と不可分なのです」(p.40)。ただ、論点がずれてしまうかもしれませんが、何がどう「つながって」いるのか、また「自律」しているのか。これらはそう自明でもないかもしれない。もっとも、今ではイーロン・マスクの立ち上げたNeurolinkとか、コンピューターと人間を端的に物理的に(?)つなげる試みもある、とも言えそうですけれども。
【木澤】 最近、Anya Bernstein『The Future of Immortality: Remaking Life and Death in Contemporary Russia』という、ロシアにおけるトランスヒューマニズムやロシア宇宙主義の最新動向を追いかけたルポルタージュを読んだんですけど、その中にNeuroNetというかなりぶっ飛んだプロジェクトが出てくるんです。そのプロジェクトは一言でいえば、『攻殻機動隊』における電脳化のもっとスピリチュアルなバージョンです。
要は、脳波によるブレイン・マシン・インタフェース(BMI)を用いて人々の脳を相互接続させることによってWEB4.0、すなわちモノのインターネット(IoT)ならぬヒトのインターネットを実装しようという壮大かつ誇大妄想的な計画です。脳波によるコミュニケーションは、言語だけでなく、イメージ、経験、記憶、主観性といった非言語的なコミュニーケーションも行えるとされています。BMIは現在でも医療やリハビリテーション、または娯楽の領域(たとえばNeuroSkyという企業はコンシューマー向けの脳波センサーなどを発売しています)で既に活用されてますが、NeuroNetはそれらとはまったく目的意識というか志の方向性が異なります。
NeuroNetの大義(!)、それは一言でいえば「集合意識」(a collective consciousness)の確立です。これはロシアにおける新ユーラシア主義的なナショナリズムの一変種であると同時に、19世紀後半から20世紀にかけてのロシア宇宙主義やボリシェヴィズムの伝統をも受け継いでいるプロジェクトであると言えます。ロシア宇宙主義のヴィジョン、それはたとえば、ソロヴィヨフが提唱した、神人性を獲得した全人類と全自然が団結して一つの霊的な有機体となったときに地上に立ち現れる、完全な調和と統一が完成した神的な王国「ソフィア」のヴィジョン。他にも、「協同の哲学」を唱えたボリシェヴィキのアレクサンドル・ボグダーノフは、輸血による血液交換を通じて、人々が類縁関係を結ぶことで一つの集団的人間を創造することができると考えていました(結果、ボグダ―ノフは血液交換の実験が原因で命を落としていますが……)。
NeuroNetの掲げる理想は、いわば人々の意識を一つに結集させることで、ある種の「共同作業」を通じて困難かつ巨大な仕事を成し遂げる、言い換えれば集団作業によって「未来」を構築することです。もちろん、ここにはソビエト時代における、あの宇宙開発という大いなる事業、すなわちスプートニクに対するノスタルジックな夢――失われた未来が仮託されていることは指摘するまでもありません。
ところで脱線しますが、ここ最近YouTubeなどでソビエトウェイヴなるジャンルの音楽をよく目にするようになりました。これはシンセウェイヴと呼ばれる1980年代の電子音楽やイメージをフィーチャーした音楽のサブジャンルのひとつで、要はそれのソビエト版ということになります。これは実際に一聴してみた方が早いと思いますが、やはりどこかノスタルジックで、また宇宙やロケットのヴィジョンが用いられることも多いです。訪れることがなかった「未来」に対するノスタルジー……。
話を戻しますと、NeuroNetには宗教的かつスピリチュアルな要素も濃厚に見受けられます。ソロヴィヨフは、霊的な「神の国」は歴史の終わりにのみ実現するという黙示録的なヴィジョンを抱いていたと言われますが、NeuroNetの共同設立者のPavel Lukshaも、人々の意識をNeuroNetを介して繋げば、破滅的なコンフリクトが発生することもありえる、といった発言をしてて、さらに彼はその混沌を「最後の審判」のプロセスとさえ比較しているのです。彼らにとって、NeuroNetの実現は、ある種の集団的浄化(カタルシス)のプロセス、すなわち「救済」でもあるということです。そして、もし我々がその「最後の審判」を乗り越えることができれば、集合的弥勒菩薩(collective Buddha Maitreya)(!)の状態に到達することができるだろう、というわけです。
【江永】 えらい大味にキリスト教や仏教などのコンセプトをつなげてきましたね、NeuroNetの方々。いや実は精緻なロジックの筋が通っているかもしれないですが。
【暁】 『キノの旅』のエピソードみたいな感じだと嫌だなぁ。脳内で考えてることが全部互いにわかるようにしちゃった人たちの村があって、「これ面白いねー」「は、つまらないんだが?」みたいな事案が頻発してヤバいので、結局みんな脳波が届かないように離れて孤独に暮らしている、という話があるんですよ。
【木澤】 おそらくその『キノの旅』のエピソードでは個々人のアイデンティティが未だに自律したものと捉えられてると思うんです。あるいは統合失調症のような状態ですよね。他者の思考や言葉が自分の脳に侵入してきてしまう。それに対してNeuroNetは、少なくともその最終局面においては、もはや自分と他者の区別すら意味をなさないというか、集合意識がそれ自体で一つの実体をもった意識のように立ち上がってくる。前々回の『幸福な監視国家・中国』の読書会で出てきた「ソラリスの海」の話とも近いかもしれません。
【暁】 なるほど。デカめの一般意思、エヴァの人類補完計画みたいな感じですかね。
【木澤】 もちろん、NeuroNetがエヴァの人類補完計画や一般意思云々と異なる点は、そこにはロシアにおける諸々の地政学的/精神史的な土壌や文脈が重く横たわっているという点です。先程も言ったように、意識の統合というヴィジョンは、ロシアにおいては往々にして宗教やナショナリズム、さらには共産主義の記憶などとも関わってくる。現に、NeuroNetは元は民間発のプロジェクトだったのですが、現在では国有プロジェクトのひとつにもなっています。
【ひで】 ヤバすぎでしょ。
【暁】 ひぇっ。
【江永】 相対的に見てロシアは領土が広い方だと思いますが、広い場に人が点在するようになっていくほど、ナショナリズムの醸成って意識の統合みたいな話に重点が置かれそうな印象があります。感性バラバラでもなんだかんだ一緒に暮らしてる、みたいな感じにはならないわけで。
【木澤】 前々回扱った『幸福な監視国家・中国』と併せて読むと、興味深いヴィジョンが見えてくる気がします。つまり、地球では意識の繋がった人々がソラリスの海を形成し、宇宙ではネットワークから切り離されたスタンドアロン型のロボットが働いている、といった……。
【ひで】 どこが興味深いんですか?
【木澤】 つまり、宇宙探査のためにロボットは自律性を備えて一種の自我を手に入れる一方、人間はネットワーク的な集合意識を形成することで個体としての自我は消失していく、という逆説的なプロセスですね。このことについては何もNeuroNetを持ち出すまでもなく、たとえば安藤馨は『統治と功利』の中で、統治功利主義の国家のもとでは近代的な個人、すなわち「人格」は無用のものとなる、と論じていますね。
安藤は、「人格」を近代の産物としての擬制的実体に過ぎないと喝破し、そして「我々の統治功利主義は……快苦を経験する意識主体としての人間を「人格」の圧政から――哲学的急進派が個人を家父長的圧政から解放しようとしたのと同様に――解放しようとする現代の急進派(ラディカルズ)という名誉ある地位を占めるだろう。」と宣言し、「人格亡きあとのリベラリズム」を掲げるに至るのです。
安藤はデレク・パーフィットの議論を援用しながら、「人格」は意識主体の予期によって成り立っていると述べています。たとえば、「労働をすればお金が入るから、今は労働という苦役を耐え忍ぶ」「犯罪を犯せば罰(=刑罰サンクション)を受けるからやめておく」等々。このように自律的な「個人」は比較的長期の予期スパンを前提とした制度の下に成り立っています。
逆に言えば、我々の未来への予期がなければ正負のサンクション予告による現在の意識主体への統治は成立しえないということです。ですが、統治能力や統治技術(アーキテクチャ)が今よりもさらに高度に発達して、統治の割当単位が「個人」よりもさらに精細なものに、言い換えれば、長期の予期を前提とした制度上のサンクションがなくとも統治が遂行できるようになったら果たしてどうなるか。
たとえば、そこでは被治者に対しても短期の予期スパンしか求められなくなり、未来に対する安定した予期を誰も行おうとしなくなるかもしれない。つまり、統治者が被治者の欲望をあらかじめ先回りして「配慮」してしまうような社会。先の例で言えば、たとえばベーシックインカムという形で、先回りしてお金を給付してしまう。言い換えれば、欲求主体に先んじた形で主体を「配慮」し欲求充足の効率的提供を行う(「配慮の論理」)。そこではもはや未来に対する予期は単に不必要なものとなり、ということは「自律」も「人格」ももはや不必要ということになる。
【江永】それこそ、この本で整理されているアシモフのビジョン、心理歴史学による文明の調整や、ガイア=ガラクシアやソラリアといった統合知性体の話を彷彿とさせますね。確かに、現在時点しか意識しない主体が、統治においても理想になるのももっともだな、と思いました。例えば、自粛ないし萎縮するときって、未来方向だと恐怖感とかが、過去方向だと罪悪感とかが原因になったりするじゃないですか。たいていは後が恐いか前が申し訳ないかで自重というか、身を慎むわけですよね。もしそれらが自己抑圧でよくないとなれば、そりゃあ、過去と未来とを思考する能力をなくしてしまう方向になるよな、と。
【木澤】 安藤はまた別の箇所で、「人格のインテグリティ」は意識主体の予期、それと過去の記憶と未来時点に対する一定の愛着=共感パタンとほぼ同一視できると述べていますね。ここで思い出したのは、アラン・ワッツが未邦訳のエッセイ「Psychedelics and the Religious Experience」の中で書いているLSDの効果についての記述です。ワッツはそこで、LSDを摂取した際の特徴的な意識作用として、「時間の引き伸ばされたような感覚」と「現在のこの瞬間への意識の集中」を挙げています。未来に対する執着心が消え失せ、たった今この瞬間に生起している出来事に対するとてつもない重大さと面白さに気づく、と。そうした境地においては、道を忙しげに歩いてゆくビジネスマンの姿があまりにも馬鹿らしく見え、涅槃のような安心感とともにグラスに満たされた水の煌めきに我を忘れて見入ってしまう……。こうしたLSD体験を先程までの文脈に置き換えれば、要するにここで起こっていることは「人格」の消失だと言ってみることができるでしょう。過去と未来に対する愛着=共感パタンが一時的に解除され、そこにあるのは瞬間の意識、つまり浮遊する意識の切片のみというわけです。
【江永】 なるほど。そういえば私は最近、自分に人格や意識がなくなりつつあるんじゃないかと感じることがあります。
【暁】 「おめでとう!」
【木澤】 エヴァの最終回じゃないですか。
【暁】 ふふふ。
■まだ脳で消耗してるの?
【木澤】 本筋とは外れるようですが、第1章(33頁)に出てくる、成熟して定着生活に入り移動する必要がなくなると自分の脳を食べてしまうホヤの話が「人格」亡き後の世界観っぽくて面白かったですね。「まだ脳で消耗してるの?」という。
【江永】 いずれ、脳が、親知らずとか盲腸みたいに、余計だったり〈病気〉の原因だったりするので、手術で切除されていく、みたいな世界が到来するかもしれませんね。進化論について哲学的な概念分析などを試みているエリオット・ソーバー『進化論の射程』(松本俊吉ほか訳 2009)を瞥見していると、こんな一節があり、記憶に残りました。脳の特徴がもたらす行動すべてが適応的だと考えるべきではない、という脈絡での記述です。「おそらく脳は[進化の途上で生じた]副次的な機能を多く持っているだろう。脳が生み出す思想や感情には、脳が進化した理由とはまったくかかわりのないものがあるのである」(ソーバーp.422)。言われればもっともだけれど、エグい指摘ですね。脳の「副次的な機能」がもたらす事象が適応的ではなく、現今の環境では病的になったり致命的になったりする可能性もある。
【木澤】 ホヤの例を見て感じたのは、脳って進化の過程で必ずしも必要なのだろうか、ということです。統治テクノロジーの発展を「進化」と捉えることができるかという問題はありますが、たとえば統治功利主義の究極段階に達した瞬間に、人類が一斉に自分の脳を食べだしたら面白そうだなと思いました。私はホヤになりたい。まあそこまでいかなくとも、現代でも脳の機能、たとえば記憶は少なくない部分が脳の外にあるアーカイブ(たとえばグーグル)によって外在化されつつあるし、ビッグデータアルゴリズムは主体の選好を先回りして提示することで選択にまつわる意思決定の「重荷」を人間から取り除こうとしつつあります。
【暁】 H.G.ウェルズの『タイムマシン』で、働かなくてよくなった人間たちがお馬鹿なぽよよん状態で生きてるのを、さらに加速させるとそうなりそうですよね。
【ひで】 Googleカレンダーを使うようになってから予定を覚えられなくなったとかですね。ただ、そうやって機能の外部化をしたときって人間に元ある能力が消え失せたのではなくて、もともとあった思考力を他のものに使えるようになっただけなんじゃないですか。
【暁】 確かに。コンサルの人に300円貸して、って言ったら、「オレは300円貸していることを覚えていたくないからあげる。脳の記憶容量を保持するのがもったいない」って返されたという話と同じですかね。僕も日本地図を記憶するコストを捨てて他の知識の獲得にリソースを割いてるので、わかる気がします。
【江永】さっきの「つながっている」か「自律」しているかの話とも関わりそうですね。例えば、アンディ・クラークは、『生まれながらのサイボーグ』(呉羽真ほか訳 2015)の中で、人が時間を知っているとはどういうことなのか、と問うています。「もしかするとあなたは、実際に自分の腕時計を見る前から時間を知っているのだ、と言って構わないかもしれない。これは、月面着陸の年号を実際に自分の生物的記憶から呼び出す前からその年号を知っている、と言ってよいのと、ちょうど同じことなのだ」(クラークp.67)。地図で言えば、地理が頭に入ってなくてもスマホでGoogleマップなどの地図アプリを呼び出してそれで済むなら無問題とも言えるし、私はこの辺の地理がわかります、とさえ言えてしまうのではないか、という話です。
私の自律性が、何らかのアーカイブにアクセスして要求されたデータを提示できる能力で立証される面があるとして、アクセス先が身体内の脳であれ外部の地図や時計であれ(速度差があるならば問題になるかもしれないが)、同じ速度で処理できるならば、体内か体外かという区分は重要ではないかもしれない(『生まれながらのサイボーグ』第2章「透明な道具」などを参照)。
また、手元の道具か身体の一部かという話だけでなく、自分の能力かインフラの恩恵かという話もできそうですね。A・V・バナジー&E・デュフロ『貧乏人の経済学』(山形浩生訳 2012)の第3章「ソファからの眺め」の節にあった印象的な記述を思い出します。「わたしたちは自分たちの限られた自制心と決断力をあてにする必要はほとんどないのです。でも貧乏な人々は、常にその能力をあてにしなくてはなりません」(p.102。なおここでの「わたしたち」と「貧乏な人々」の線引きには異議が生じるかとも思いますが、この本が主に、開発経済学的な観点から、いわゆる最貧国の人々がとる行動の合理性を理解することに関心を寄せている旨を申し添えておきます)。選択を委託する代わりに個人へと(選択に割くはずだった)リソースを提供するのがインフラであるとも言えそうだし、インフラが利用者の判断力をエンハンスメントしているとも言えるでしょう。おそらく二つの言は表裏一体です。
【暁】 選択は疲れるから少ない方がいいって発想も近いのかな。ジョブズやザッカーバーグが毎日同じ服を着てるのは不要な選択を減らすためとか。余談ですが、アメリカのスタートアップが1ヶ月洗濯しなくていい服を開発してるのも、そういう選択のコストと関係してるのか…?と思わなくもなかったり(駄洒落ではない)。
あと、仕事に加えてケアや家事労働を担わされがちな女性が、それ以外のことを考える余裕がなくて不利な立場に置かれやすいという問題にも繋がっている感じがあります。
■唸れ!光速の通信環境
【暁】 第1章で個人的に面白かったのは、『機動戦士ガンダム』のコロニーが太陽系の中に収まっている理由を「通信の都合」だとしている箇所ですね。それ以上遠くなると、新海誠の『ほしのこえ』みたいに通信の時差でエラいことになってしまうんでしょう。
【ひで】 光の速度は意外と遅いという話ですね。昨日Twitterで光の遅さを図示する動画がRTされてきました。
NASAの科学者が光速を可視化するためのアニメーションを作成。一連の動画↓は光の速度がどれほど速く、そしてまた恐ろしいほど遅いかを示している 笑。1秒に地球を7周半、地球から月までだと1.255秒、地球から火星までは3分2秒。毎秒約30万kmと書くより断然わかりやすい⚡️。pic.twitter.com/tC4escKqXC
— Sangmin @ChoimiraiSchool (@gijigae) February 7, 2020
【江永】 本書p.41からの話ですね。地球上でも、光の速度といっても通信ケーブルの長短などで差が生じることを利用して、金融情報を先んじて手に入れて荒稼ぎする話がありました。ジェ ームズ・ブライドル『ニュー・ダーク・エイジ』(久保田晃弘監訳・栗原百代訳 2018)の第5章では、「証券取引所でのやりとりは闇の売買と、闇の光ファイバーの問題となった」(p.127)などと表現されていました。ブライドルの記述の元ネタは、たしかマイケル・ルイスの本でしたね。
【ひで】 『フラッシュボーイズ』ですね。アメリカには金融市場がいくつかあるんですけども、微妙に値段の違いが出たときに誰よりも早く売り買いすることで儲けられる、みたいな。映画化されたんでしたっけ。
【江永】あー。おそらく、キム・グエン監督『ハミングバード・プロジェクト』(2018)ですね。ルイス『世紀の空売り』(東江一紀訳 2010)が原作の映画『マネー・ショート』(アダム・マッケイ監督 2015)ほどはバズらなかったみたいです。
■第3章 宇宙SFの歴史
【暁】 網羅的なSF史で、この章はかなり面白かったですね。ポストヒューマンかつアポカリプスものと言えば、本書で言及されてなかった中だと上田早百合『華竜の宮』をオススメしたいです。AIと人間という話だと、飛浩隆『グラン・ヴァカンス:廃園の天使』も。どちらもジェンダー意識高い&面白くて、自分がSFを少し読むようになるきっかけになった作品です。
【木澤】 イーガンを読みたくなりましたね。古書店で買った『ディアスポラ』を積んだまま、まだ読めてないので。
【ひで】 現実世界で「SETIがいくら探しても地球外生命体がなかなか見つからないな〜」ってなると、SFの主題がスペースオペラが廃れていった、みたいな現実の科学調査がSFの潮流に影響を及ぼしているって部分が面白かったです。
【暁】 いや、我々に見えてないだけでもう地球外生命体に監視されてるかもしれません。『幼年期の終り』みたいに、宇宙人が悪魔など別の概念として既に認知されている可能性もあります。余談ですがマクロスと幼年期の終りってかなり雰囲気近いな~と思っていたら、「超時空要塞マクロス」のサントラにそのものズバリ「幼年期の終り」というタイトルの楽曲を見つけて「やっぱり~!」と思いました。往年のファンからしたら常識なのかもですが。
【江永】 著者はいわゆる「実学」っぽい目線でフィクションを扱うだけでなく、文学史やジャンル論のような観点も交えてSF内の流行り廃りを丁寧に論じてますね。『宇宙倫理学』でも宇宙SFからポストヒューマンSFへが論じられていますし(第6章など参照)、SFなるものの(ファンタジー他とは区別される固有の)意義に関しても『ナウシカの解読【増補版】』などで論じています。
【木澤】 人類が宇宙に進出する動機には様々なものがありますが、わけてもロシア宇宙主義の始祖ヒョードロフの場合は事実は小説より奇なりと言いますか、「自分たちの祖先たちを復活させるのが自分たちのプロジェクトだ」と主張しているのですが、過去に死んでいった祖先の人たちの死体ってもはや風化してパーティクル状になって空気上のみならず宇宙にまで散開してしまっているわけですよね。なので、その分子を宇宙まで回収しに行くために我々人類は宇宙開拓を断行しなければならないのだ、と。
【江永】 いい人ですね。
【ひで】 パーティクル――分子って同じ分子式をしていたら同じものなのだから、同じものを集めれば復活できるはずなので、地球上で集めればいいのに。
【木澤】 死体の分子にはその先祖の系列の記憶が宿っているんだという一種の宗教観をヒョードロフは持っているんです。
【暁】 !!!それとまったく同じ話をしている物語があって、市川春子『宝石の国』という漫画なんです。主人公たちは人間のような意識と人間のような身体を持つ「宝石」なんですけど、(以下の発言はネタバレです)主人公のかけがえのない相手が砕かれちゃうんです。そのかけらを集めれば復活できるはずだってことで、主人公が敵地(月)に乗り込んでいく話なんですよ。
【木澤】 まさにロシア宇宙主義の世界観ですね。
【暁】 ちなみに著者は仏教校出身で作中にもかなり仏教のエッセンスが入っています。ロシア宇宙主義ともその辺で何か関係してるんですかねぇ。あるいは著者がロシア宇宙主義を意識していたのか、偶然なのか。僕はこういう話を聞くとすぐにアニメの具体例を思い浮かべるのですが、それが読書の際に理解の助けになるので、何か軸になるものがあると他のことするにも便利だな…と最近思います。
■アシモフについて
【江永】 新書の内容からは外れますが、アイザック・アシモフは、エイズの合併症で死亡したと伝えられています。アイザック死後にジャネット・アシモフ(妻)が自伝で記したところによると、1983年の心臓バイパス手術で使用された輸血血液を通してHIVに感染していたらしい。エイズ患者だったことは、アイザック死後もしばらく秘密にされていたようです(以下はSF誌宛てのジャネットによる抗議書簡に関するページ)。
【暁】 僕は体が弱いので肉体改造や機械化に惹かれますし、人によっては肉体的な事情が創作や思想に影響を与えるという可能性もなくはないのかもしれませんね。
■ギグエコノミーが社会構造を変える?
【ひで】 Uberとかって相手との継続的な取引もないし、即金でお金を引き出せるし、予期の期間が短いですよね。先程の「人格は予期から生まれる」という話に基づけば、それこそギグエコノミーに従事していると人格形成が薄くなってしまうということになりませんか。
【江永】 なるほど……。例えば稲葉振一郎『AI時代の労働の哲学』(2019)には「AI」よりもギグ・エコノミーの方が、社会のあり方の変容という観点から見て、重大なのではないかと示唆する記述があります。ギグ・エコノミーは、雇用というよりも請負で回す仕組みであり、指示にたいして結果を出す(出し方に巧拙の差が出る)のではなく、手段に従う(誰がやっても同じでなければならない)ことが求められる。これで構成される場では確かに人柄は問題にならない(極論ですが、指示ごとに別人が従っても支障が少なそう)。
「人格」という語は、やっかいですね。『銀河帝国は必要か?』のp.190のあたりなどを参照するに、まずカント主義による功利主義批判のポイントは、人格が、それ自体は分割できない、いわば数え上げの元になるものであり、人格同士では快苦の大小や上下を比較考量できないと指摘する点にあったらしい。けれども、デレク・パーフィットが、人格をより細かい意識の諸断片に分解可能なものとする理論的枠組みを再興した(逆に個々の身体を越えた集団身体水準の人格も想像可能になる)。で、安藤馨の議論にならって、予期による統合という限りで人格(予期した上で決定した選択の責任を担う主体)を想定するならば、時間の幅(あるいは予期に使用できる情報や記憶の量?)に応じて、人格には濃度(責任の濃度でもある?)が備わっていることになる、という感じでしょうか? 日常的な言葉遣いとして、〈人格の向上〉とか〈人間が薄っぺらい〉とかいう言い回しはあるわけで、そういう言葉遣いとはうまく馴染む発想かもしれません。
【木澤】 これは単なる思弁ですが、未来に対する予期スパンと愛着=共感パタンが限りなくゼロになれば、そのときこそ他者への配慮が容易になると思うんですよね。未来時点に対する一定の愛着=共感パタンが人格のインテグリティから解除されたとき、意識の切片としての意識主体は、現在という同じ瞬間を共有する別の意識の切片(=他者)に対して、まるで自分の未来に対するのと同じように愛着=共感パタンを形成することができるようになるのではないか。そして、もしLSDによるアシッド・コミュニズムがあり得るとすれば、それはこのようなものなのではないか、と夢想したりします。
【暁】 一般には人格を高める「徳」によって他者に配慮できるようになろう!という感じなのに、木澤さんの発想だと他者に配慮するためにむしろ人格が邪魔だ! という感じになっていて、とても面白いですね。
【江永】 「徳」や「良識」が、人体の行動を制御するものとして人体と切り離して考えうるならば、それらからの解放による人体の自由の増大とかも考えられそうですね。その人体は、有徳でもなければ良識的でもない挙動をするリスクがある、という扱いになりそうですが。
【ひで】 Japanese Big Traditional Companyって営業しないんですよ。昔からある取引先と仲良くやっていくことだけ求められる。だから日本の大企業の社員には「営業がうまい」とか「仕事ができる」とかそういうのじゃなくて、「昔からの取引先をビビらせないよう、異常者じゃないこと」が求められる。
【暁】 は~、マジでその発想許せね~!みんな同じじゃイノベーション起きないじゃん。
【ひで】 ギグエコノミーとかで予期の期間が短くなっていくと、「異常者じゃないこと」を求めるみたいな社会のあり方が根本的に変わってしまうというのは肌感覚としてわかる感じがする。
【木澤】 現代の社会では自分の未来に対する予期や愛着=共感パタンに固着せずに、他人に対してまるで自分の未来に対するように配慮しちゃったりする人のことを異常者って呼んでるような気がします。健常者というのは自分の未来に対して安定した予期ができる人、自分の未来に配慮できる人たちなんですよね。
【暁】 「安定は、希望です」ってことですかね。
【ひで】 トランプとかは本当に予期できないですし。
【江永】 でもそれは、周りからの空気を読めという強圧の遮断でもありうる。明文化された規則と暗黙の慣習を組み合わせた交渉術への、対抗策にも見えます。
【ひで】 アメリカ国家の決定者が、アメリカ国家としての意識というか人格を持っていないのはヤバいとは思いますけどね。
■参考文献について
【暁】 話は飛びますが、最後の参考文献も良かったですね。人工知能について川添愛さんの著作が紹介されてます。僕も以前川添さんの別の著作『自動人形の城』を読んだのですが、とても読みやすくて良かったです。言語学の観点から見ると、我々が思い描くようなAIの実現って前途多難よね…という感じでした。
なのにいま、日本維新の会が「AIが代替できるようになるから、司書なんか要らない」って予算増やさない理由にしてるので、狂ってるなと思いました(余談)。
【ひで】 維新の会の司書いらない理論はヤバいですよね。
【江永】 その理屈だと、間接民主制下の議員は建前上は人民の意思の中継点だろうから、集計アルゴリズムと意見調査インフラさえ整備できたら議員も撤廃できそうだ、といった主張も強弁できそうですね。議員を立法コンサルタントだと捉えるなら話は変わってきそうですが。司書も、(アーカイブ化=積ん読も含むような)読書のコンサルタント、ないし読書(のみならず独学)のインストラクターだと捉えれば、属人的なスキルを要するという話になりやすい気がします。図書館と政治の話だと以下の対談記事が面白かったです。
(読書猿×スゴ本 映画『ニューヨーク公共図書館』についての対談記事)
【暁】『ニューヨーク公共図書館』、江永さんと観に行きましたが、色々考えさせられるいい映画でしたね。
■出生加速主義は宇宙進出を促す
【江永】 そろそろ話の締めに向かいましょう。まずは手短に2章4章5章の内容をふりかえっておきます。2章では作家史に絡めてアシモフのロボットSFの意義を確認し、それと架橋されるべき宇宙SFへの着目や、宇宙SFを再検討する意義などが記されていました。また4章では主にアシモフのファウンデーション・サーガが(ロボットと人類の役割に焦点をあてつつ)取り上げられており、5章では一種の歴史法則的アイディア(心理歴史学)と望ましい社会のあり方を中心に同サーガが読み直されていました。
それと5章では、このサーガに即して、ありうべき未来社会の形態が著者により整理され、以下の4つの選択肢が挙げられていました。(a)人類全体の利益とともに、自由意志をも重んずる銀河帝国(第1ファウンデーション)、(b)人類全体の利益に即して個々の意志にも介入する銀河帝国(第2ファウンデーション)、(c)人類を超えた惑星規模の生態系そのものである統合知性(ガイア)の拡張による一切の包摂(ガラクシア)、 (d)選別的排他的だが楽園的でもある完全管理社会への引きこもり(ソラリア)。そして6章では、これらの比較検討を政治・経済・法・社会などの道徳的・思想的・哲学的な議論とさらに絡めて深めていっています。まず、銀河帝国の中での対立が、功利主義内での対立と重ねられます。総量功利主義と平均功利主義です。そこから、それぞれの未来のあり方や、人類などが宇宙に進出していく(人口は増えるものとする)ことの意義などが検討されていきます。
【ひで】 総量功利主義が人間を増やせば増やすほどいいっていうのは盲点でしたわ。もし人類みんなが地球にしか留まれないっていう仮定を置くのなら、地球のリソースは限られているから人口のキャップがあるはずです。平均功利主義的を採用すると、地球上で反出生主義を導入して人間の数を減らすことで、人間一人あたりの厚生を上げることはできますよね。あ、でも人間の数によって技術革新のスピードが決まるから、あまりにも減らすと技術革新が遅くなって未来の効用が下がっちゃうからダメなのか。
一方で人類は宇宙にドンドン出ていけるという仮定を置くのなら、総量功利主義を採用すればどんどん人間を生産してどんどん宇宙の果まで送り込んでいくことで人類の厚生を無限に上げることができる。
【木澤】 総量功利主義って反出生主義の逆バージョンですよね。出生加速主義というか。
【ひで】 出生加速主義ウケますね。産めよ増やせよ地だけではなく天まで満ちよ。
【暁】 僕は反出生主義なので出生加速主義にはNoを突きつけたい。それはそれとして、総量功利主義を採用するんだったら、通常の3000倍の快楽を甘受する人間を遺伝子改良で大量に作り出すのがいいんじゃないですか。対魔忍みたいに(あちらは厳密に言うと改造手術ですが)。
【ひで】 あと人間をたくさん生産して麻薬漬けにしてドラム缶に詰めて地面に埋めていくとかすればコスパよく人類の功利を上げれそう。
【江永】 その方向で、地球という制約を外すなら、宇宙に快楽漬けの知性体を可能な限り敷き詰めて、空間を埋めていくのが理想ということになりそうですね。ただ、この総量功利主義的(?)な出生加速主義は、人間も造り変えていかないと実現できなさそうですね。差し当り思い付くだけでも、まずは生殖を外部化しないとキャップが外せなさそうですね。
【ひで】 快の質の変遷について。鬱っぽい人間って結婚して子供を産んで残すことが難しいですし、陽気な人の方が子孫を残しやすいと言えます。そういう人間が多く生き残った結果、中世時代の人間と現代の人間って脳の器質的にドーパミンの出る量が違うんじゃないですか?
【江永】 なるほど。そうしたいわゆる「自己家畜化」的な話が起こっていたとすれば、そういう違いもあると言いうるのかもしれない。
【暁】 適者生存ってやつですよね。狩猟時代はADHDの方が健常者より有利だった、という話もあります。
【ひで】 鬱の人の方が現状を冷静に分析できるという話も一方であるし、結局のところ繁殖するのは現環境に適応的なヤツという話ですね。
【江永】 ただ、現今の環境では適応的な特徴が、そのまま未来でも適応的だとは保証されていないことに留意しておきたいです。快楽の量や質の感じ方にに関してさえ。
【暁】 いま我々が快と捉えているものが、未来もそうとは限らない。あと、環境が変わると強い個体も変わるって、カードゲームみたいですね。
■光速の限界が「外部」を産む
【江永】 距離にたいして光速度の限界があるから惑星規模のガイアならまだしも、宇宙というスケールだとガラクシアが成立しない。これを著者は第6章の結びでポジティブに捉え直しています。「宇宙文明は、緩やかな多元的低速ネットワーク社会としてしかありえない。[……]宇宙空間の「距離の暴虐」は決して克服しえない障壁であると同時に、一種の安全装置でさえあるのです」(p.202)。ここの表現は『銀河英雄伝説』の、グエン・キム・ホア(自由惑星同盟草創期の指導者の1人)による「距離の防壁」の言を踏まえているように映ります(なお、元ネタは、オーストラリアの歴史を地理学的に捉えて論じたジェフリー・ブレイニー『距離の暴虐』(長坂寿久 小林宏訳 1980年)かと思います)。ともあれ、恒星間や惑星間の距離でですら、地球上で実現されつつあると見られているグローバルなネットワーク社会の成立は困難であるらしい。共時的な単一性が保持できない。
【木澤】 結果的に多様性が生まれる、ということですね。
【江永】 そうですね。だからこそ、既存の社会に耐えられない人々にはフロンティアを目指す余地もあるわけです(p.202だとR.A.ハインラインのSFの宇宙植民モチーフに言及があります)。グローバル社会の統治、ガイアの統治、自称ガラクシアの統治が、行き渡らないところへと。言ってしまえば、宇宙はEXITの味方です。「距離の暴虐」は距離の恩恵に転じもする。
【木澤】 そこには<外部>が発生する契機もはらんでいる。
【ひで】 いいこといいますね〜。異常者――多様性はフロンティアに存在する余地がある。
【江永】 この意味で、宇宙論的な思考は資本主義リアリズムに対するある種のカウンターパートになっていますよね。まだざっと眺めただけですが、ニック・ランド「Disintegration」(2019)が、そういう論調に映ったので気になっています。もっとも、異世界ファンタジーなどと異なりせっかく宇宙を検討しているSFの話なのに、地球上の政治経済の寓意に落とし込んでいると批判を受けてもしまいそうでもあります。ただ、超高速取引みたいに、ある観点からみれば、やはり地球上ですら双方向通信ネットワークを介した完全に共時的なやり取りなど成立していないわけです。だから「Disintegration」みたいな語りの余地もある。グローバルな統一の閉塞感ではなく、バラバラに分化していくこと(ただし、どうもランドはバラバラになることこそが自然の摂理かつ資本主義なんだと強弁していて、話がねじれていくのですが……)。
【ひで】 資本主義で覆いきれない外部は宇宙感覚で見れば絶対に存在すると。
【江永】 そうですね。光速と距離の問題が、無時間的なシェアや同期を不可能にしている。おそらく、このあたりは両義的で、交換の必要も困難もこの環境に支えられていると言えそうです。
【木澤】 先程も少し話に出てきましたが、投機家も通信ケーブルにおける一瞬の時差からお金を儲けたりしているわけですよね。初期の商業資本主義ってそもそも空間間の利ざやによって剰余価値を発生させてたわけですし。
【ひで】 そりゃ交換が成り立たないほど遠くにいれば資本主義に覆われないのは当たり前か。
【暁】 なんか色々聞いていて納得しました。ガンダムで地球から一番遠いコロニーが独立を宣言したのって、この宇宙空間の外部化も関係してそうですし、同時に、宇宙には銀河帝国を脱出した人たちによる自由惑星同盟が生まれる余地もあると。最後に銀河英雄伝説に戻ってきて、ちょっと感動してしまいました。
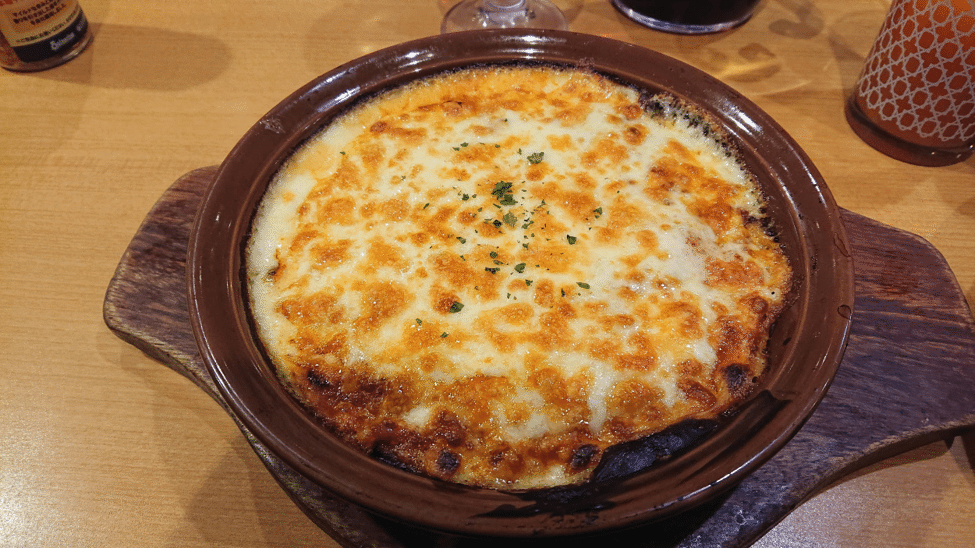
読書会後のご飯はサイゼリヤで。チーズたっぷりミラノ風ドリア、美味しくいただきました。
■終わりに
宇宙空間の多様性に希望を見出だした一同。読書会後にはサイゼリヤに行き、富沢ひとし『エイリアン9』、ブロトピア、チャイボーグなどのトピックについて話しました。木澤さんイチオシの『エイリアン9』は、可愛いキャラクターデザインに反して宇宙生命体に寄生された小学生たちが地球の存亡を賭けて戦うシリアスなお話だそうです。「ブロトピア」は、シリコンバレーで問題視されている男性優位主義の「ブラザーのユートピア」の略称。そこに入れない人からしたらディストピアだし、皮肉が効いてていいですね。「チャイボーグ」は、サイボーグのように美しい中国風メイクのこと。若い人の間では、こういうメイクが流行ってるんですね、などと盛り上がりました。
次回の課題本は「たまには新書以外を」という話に。パンデミックSFを読みたい役所暁が、小川一水『天冥の標』を提案。さらに木澤さんオススメのCRAFTWORK『さよならを教えて』なども挙がりました。最終的には、当読書会でも度々言及されており、ノベルス版もあるので手に取りやすいということで、大槻涼樹・虚淵玄(Nitroplus)『沙耶の唄』(ゲーム版でもOK)に決定しました。一体どんな読書会になるのか、お楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
